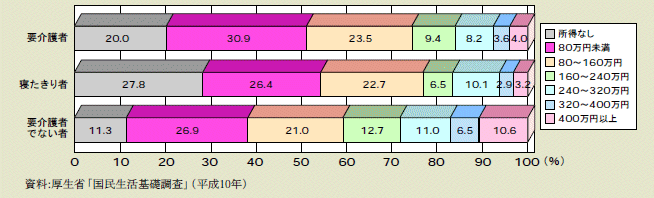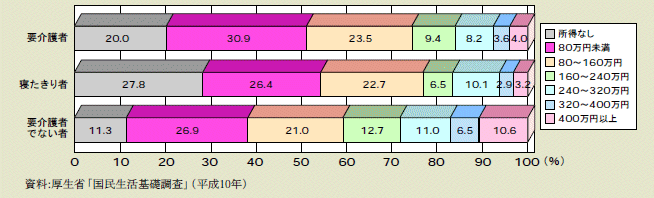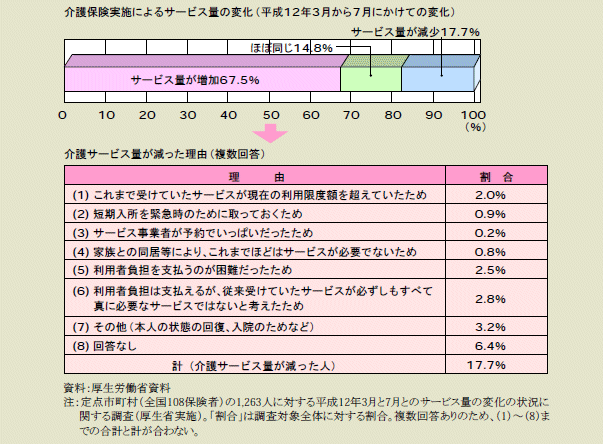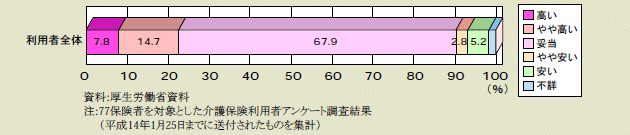2 経済状況と負担感
要介護者等の所得をみると、一世帯当たりでは、要介護者のいる世帯が709.2万円、寝たきり者のいる世帯では809.3万円となっており、全世帯の平均(657.7万円)と比較すると若干高くなっているが、一人当たりでは、要介護者のいる世帯が192.9万円、寝たきり者のいる世帯が203.1万円となっており、全世帯の平均(222.7万円)と比較すると若干低くなっている(表1−4−10)。
表1−4−10 要介護者のいる世帯の一世帯当たり・世帯人員一人当たり平均所得金額
<
CSVデータ>
平成9(1997)年
| 要介護者の状況 |
1世帯当たり |
世帯人員1人当たり平均所得金額(万円) |
有業人員1人当たり平均稼働所得金額(万円) |
平均世帯人員(人) |
平均有業人員(人) |
| 平均所得金額(万円) |
平均可処分所得金額(万円) |
| 全世帯 |
657.7 |
549.9 |
222.7 |
387.8 |
2.95 |
1.42 |
| 要介護者のいる世帯 |
709.2 |
593.1 |
192.9 |
381.9 |
3.68 |
1.34 |
| 寝たきり者のいる世帯 |
809.3 |
677.4 |
203.1 |
397.1 |
3.98 |
1.51 |
資料:厚生省「国民生活基礎調査」(平成10年)
また、要介護等の有無別に高齢者の所得分布をみると、要介護者で所得のない者は20.0%と要介護等でない者の11.3%を大きく上回っている。80万円未満、80〜160万円未満の階層についてみると、要介護者ではそれぞれ、30.9%、23.5%と要介護でない者(26.9%、21.O%)を若干上回っている。これらを合わせると、要介護の高齢者の約半数は所得が80万円未満となっていることが分かる。一方、要介護者で所得が400万円以上の者は4.0%であり、要介護でない者(10.6%)に比べて少ない(図1−4−11)。これは、要介護者はより高齢の者に多いこと、就労することが困難なことが背景にあるものと思われる。
図1−4−11 要介護・寝たきりの有無・高齢者個人の所得階級別にみた高齢者の割合(平成9(1997)年)
<
CSVデータ>
また、要介護者等の介護費用負担に関しては、要介護認定等を受けた者は、介護保険制度により、サービスの費用の1割負担でサービスが受けられる。また、同制度では、所得の状況に応じて施設入所時の食費や一か月当たりの負担限度額を設定し、低所得者への配慮を行っているほか、社会福祉法人による利用者負担軽減措置などが講じられている。こうした中、介護保険制度の施行により7割近くの者がサービス量を増やしており、利用者負担が重いためにサービスを減らした者は2.5%となっているほか、利用料の負担感についてみると、利用者の68%は妥当な水準と回答し、利用料が高いとする者は8%となっている(図1−4−12、図1−4−13)。
図1−4−12 介護保険実施によるサービス量の変化
<
CSVデータ>
このように、要介護等の高齢者は全世帯の平均に比べて世帯所得は若干高く、一人当たり世帯所得は若干低い。また、個人所得の分布はやや低所得に偏っているものの、介護保険の利用料の負担感については妥当な水準とみている者が多い。
(新大綱に基づく施策の方向)
介護サービスの費用を社会的に負担する仕組みである介護保険制度の普及定着を進める。また、社会福祉法人による利用者負担軽減措置を普及促進する。