第4章 日々の暮らしの基盤づくり 第1節 5
第1節 生活安定のための施策
5.スポーツ・文化芸術活動の推進
(1)スポーツの振興
ア 障害者スポーツの普及促進
2021年度「障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究」によると、障害のある人(成人)の週1回以上の運動・スポーツ実施率は31.0%(成人全般の実施率は56.4%(令和3年度「スポーツの実施状況に関する世論調査」))にとどまっており、上昇傾向にはあるものの、地域における障害者スポーツの一層の普及促進に取り組む必要がある。
2018年度から引き続き、地域における障害者スポーツの振興体制の強化、障害の有無を問わず身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備を図る取組等により障害者スポーツ団体の体制の強化を図り、他団体や地方公共団体等と連携した活動の充実につなげる取組を実施している。さらに、2019年度からは、様々なパラスポーツを試したい者に対して、スポーツ車椅子、スポーツ義足等の障害者スポーツ用具のレンタル等を実施するとともに、スポーツ用具の保守・調整や使い方の指導を行える人材等を備えた拠点(障害者スポーツの普及拠点)を整備することを目指し、関連の取組を順次実施している。
また、2018年度から2021年度まで、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)を契機に、全国の特別支援学校で地域を巻き込んだスポーツ・文化・教育の祭典を実施するとともに、特別支援学校を地域の障害者スポーツの拠点としていくことを目指す「Specialプロジェクト2020」を実施した。
イ 障害者スポーツの競技力向上
2021年9月、東京2020パラリンピック競技大会が開催され、日本代表選手団は金メダル13個を含む、51個のメダル獲得や入賞数の大幅増など優秀な成績を収めた。2022年3月に開催された北京2022パラリンピック競技大会においても、日本代表選手団は金メダル4個を含む、7個のメダルを獲得し、入賞数も前回大会から大きく増加した。また、東京2020パラリンピック競技大会、北京2022パラリンピック競技大会のいずれもメダル獲得の最年少・最年長記録の更新(※)など幅広い世代の活躍も目立った。スポーツ庁では、パラリンピックの競技特性や環境等に十分配慮しつつ、オリンピック競技とパラリンピック競技の支援内容に差を設けない一体的な競技力強化支援に取り組んできた。
具体的には、障害者スポーツの競技団体を含む各競技団体が行う強化活動に必要な経費等を支援する「競技力向上事業」を実施している。
また、「ハイパフォーマンス・サポート事業」により、パラリンピック競技大会でメダル獲得が期待される競技を対象に、スポーツ医・科学、情報による専門的かつ高度な支援を戦略的・包括的に実施するとともに、東京2020大会、2022年北京オリンピック・パラリンピック競技大会においてアスリート等が競技へ向けた最終準備を行うための医・科学・情報サポート拠点を設置した。
さらに、「ハイパフォーマンススポーツセンターの基盤整備」において、東京2020大会等に向けた我が国アスリートのメダル獲得の優位性を確実に向上させるため、競技用具の機能を向上させる技術等の開発を実施した。
加えて、オリンピック競技とパラリンピック競技を一体的に捉え、トップアスリートが集中的・継続的に強化活動を行う拠点としてナショナルトレーニングセンター(NTC)の拡充整備に取り組み、2019年6月末にユニバーサルデザインにも配慮したNTC屋内トレーニングセンター・イーストが完成した。
なお、東京2020大会等の結果を踏まえつつ、これまでの競技力向上施策の成果と課題を検証し、新たに「持続可能な国際競技力向上プラン」(2021年12月)を策定し、パラリンピック競技の国際競技力向上とオリンピック競技団体、パラリンピック競技団体間の連携の促進についても取組を進めていくこととしている。
※東京2020パラリンピック競技大会では、水泳女子背泳ぎ50m・100mでそれぞれ銀メダルを獲得した山田美幸選手(14歳・当時)、自転車競技女子タイムトライアル・ロードレースでそれぞれ金メダルを獲得した杉浦佳子選手(50歳・当時)が、我が国のパラリンピックメダリスト最年少記録、同金メダリスト最年長記録をそれぞれ更新した。また、北京2022パラリンピック競技大会では、クロスカントリースキー20kmクラシカル(立位)で金メダルを獲得した川除大輝選手(21歳・当時)が、我が国の冬季パラリンピックにおける男子金メダリスト最年少記録を更新した。

(2)文化活動の振興
我が国の障害のある人による文化芸術活動については、近年、障害福祉分野と文化芸術分野双方から機運が高まっており、広く文化芸術活動の振興につながる取組が行われている。
2018年6月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(平成30年法律第47号)が成立・施行されたことを受け、国は、2019年3月、同法に基づく基本計画を作成した。この計画に基づき、以下の取組を始め障害のある人による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しているところである。
厚生労働省では、2013年に開催された有識者による「障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」の中間とりまとめを受け、2014年度からは芸術活動を行う障害のある人やその家族、福祉事業所等で障害のある人の芸術活動の支援を行う者を支援するモデル事業を実施し、事業で培った支援ノウハウを全国展開すべく、2017年度からは障害者芸術文化活動普及支援事業を実施し、障害のある人の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)の更なる振興を図っている。
また、障害のある人の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として、2021年に「第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」(新型コロナウイルス感染症の影響により2020年から延期して開催)、「第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会」を国民文化祭と一体的に開催した。
さらに、文化庁では、障害のある人とアーティストが協働して行う創作活動・発表の実施や、助成採択した映画作品や劇場・音楽堂等において公演される実演芸術のバリアフリー字幕・音声ガイド制作への支援、特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場の提供等、障害者の文化芸術活動の充実に向けた支援に取り組んでいる。
◯全国障害者スポーツ大会
2001年度から、それまで別々に開催されていた身体に障害のある人と知的障害のある人の全国スポーツ大会が統合され、「全国障害者スポーツ大会」として開催されている。2008年度から、精神障害者のバレーボール競技が正式種目に加わり、全国の身体、知的、精神に障害のある方々が一堂に会して開催される大会となっている。本大会は、障害のある選手が、競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害のある人の社会参加の推進に寄与することを目的として、国民体育大会の直後に、当該開催都道府県で行われている。2021年度の第21回大会は、三重県において開催される予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点から中止となった。なお、2022年度の第22回大会については、栃木県で開催される予定である。
◯全国ろうあ者体育大会
本大会は、聴覚に障害のある人が、スポーツを通じて技を競い、健康な心と体を養い、自立と社会参加を促進することを目的として、1967年度から開催されている。2019年度は、第53回となる夏季大会が鳥取県・島根県で開催され、10競技に選手・役員合わせて約1,400人が参加した。
なお、2020年度夏季大会、2021年度夏季大会及び冬季大会については、新型コロナウイルス感染症の流行を受け中止となった。
◯デフリンピック
4年に一度行われる、聴覚に障害のある人の国際スポーツ大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。夏季大会は1924年にフランスのパリで第1回大会が開催され、2017年には、トルコのサムスンにおいて第23回大会が開催された。冬季大会については1949年にオーストリアのゼーフェクトで第1回大会が開催され、2019年12月にイタリアのヴァルテッリーナ、ヴァルキアヴェンナ地方で開催された第19回大会では、日本選手団として選手15名が参加し、6名が入賞した。
◯スペシャルオリンピックス世界大会
4年に一度行われる、知的障害のある人のスポーツの世界大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。順位は決定されるものの最後まで競技をやり遂げた選手全員が表彰される、といった特徴がある大会である。
夏季大会は1968年に米国・シカゴで第1回大会が開催され、2019年3月にアラブ首長国連邦のアブダビにおいて第15回大会が開催された。冬季大会は1977年を第1回(米国・コロラド州)としており、2017年にはオーストリアのシュラートミンクにおいて第11回大会が開催された。
また、スペシャルオリンピックスでは、知的障害のある人とない人が共にチームを組みスポーツを楽しむ取組も進めており、世界大会の種目にも採用されている。
◯パラリンピック競技大会
オリンピックの直後に当該開催地で行われる、障害者スポーツの最高峰の大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。夏季大会は、1960年にイタリアのローマで第1回大会が開催され、オリンピック同様4年に一度開催されている。2021年には、東京において第16回大会が開催された。次回は、2024年、フランスのパリにおいて開催が予定されている。
冬季大会は、1976年にスウェーデンのエンシェルツヴィークで第1回大会が開催されて以降、オリンピック冬季大会の開催年に開催されている。2022年3月には、中国の北京(ペキン)において第13回大会が開催された。次回は、2026年にイタリアのミラノ・コルティナダンペッツォで開催が予定されている。
スポーツ庁では、東京2020大会を契機として共生社会を実現するため、障害の有無にかかわらずスポーツに親しめる環境づくりを進めている。
夏季のパラリンピック競技大会が同一都市で2回開催されるのは東京2020大会が史上初であり、開催国として東京2020大会を契機に、2016年度からパラリンピック教育を推進する「オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業」を実施してきた。事業は主に2つあり、①学校現場でのパラリンピック教育の取組を促進するために、パラリンピアンやパラアスリートなどを学校に派遣し、自身の体験やエピソードに関する講演やパラ競技体験などを児童生徒と共に実践したり、②多くの児童生徒にパラ競技への興味関心を高めてもらうため、競技会場にてパラ競技を実際に観戦し事前事後に選手や競技に関する学習をしたりと、様々な活動を通じてパラリンピック教育を推進した。また、東京2020大会に出場したパラリンピアンが学校を訪れ、児童生徒と交流するなどの取組も展開されている。これらの活動によりパラ競技への興味関心を高め、共生社会への理解促進をより一層進めていく。
また、各地においても、県民パラスポーツ大会や、学校区、大学、企業対抗など様々なレベルでのパラスポーツの体験会・交流会が実施されるなど、これらの取組はさらに広がりを見せている。
このような動きが広がる中で、近年は、特に障害のある人と障害のない人が同じスポーツに参加する取組に注目が集まっている。知的障害のある人にスポーツの機会を提供するスペシャルオリンピックスでは、知的障害のある人とない人が同じチームで練習を積み試合を行う「Unified Sports®」の取組が進められているほか、一般社団法人日本障がい者サッカー連盟による、障害のある人と障害のない人が一緒にサッカーを楽しむ「JIFFインクルーシブフットボールフェスタ」など、互いの理解や心のバリアフリーを目指した多くの取組が行われている。また、従来のスポーツ大会に障害のある人の部門が併せて設けられる試みや、障害のある人のスポーツ大会に同一のルールで障害のない人が参加できる大会も広がってきている。
引き続き、これらの様々な取組の普及を通じて、多くの方に障害者スポーツの魅力を伝えていくとともに、スポーツを通じた共生社会の実現に向け取り組んでいく。
長野県民障害者スポーツプロジェクト
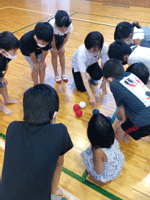

また、国立美術館、国立博物館は、障害者手帳を持つ人について展覧会の入場料を無料としているほか、全国各地の劇場、コンサートホール、美術館、博物館などにおいて、車椅子使用者も利用ができるトイレやエレベーターの設置等障害のある人に対する環境改善も進められている。
オリンピック・パラリンピックはスポーツの祭典のみならず文化の祭典でもあり、「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成27年11月27日閣議決定)において、日本文化の魅力を発信していくこととしている。2016年3月に、関係府省庁、東京都、大会組織委員会を構成員とする「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化を通じた機運醸成策に関する関係府省庁等連絡・連携会議」を開催した。その中で日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を活かし、障害のある人にとってのバリアを取り除く取組等成熟社会にふさわしい次世代に誇れるレガシー創出に資する文化プログラムを「beyond2020プログラム」として認証するとともに、日本全国へ展開することを決定した。2022年2月末時点で約19,700件の事業を認証した。
2018年6月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(平成30年法律第47号)が公布、施行された。
本法は、文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、「文化芸術基本法」(平成13年法律第148号)及び「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とするものである。
本法に基づき、2019年3月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」を策定、公表した。
計画は、法律に定める3つの基本理念を基本的な視点とし、2019年度~2022年度までを対象期間として、11項目の具体的な施策の方向性を記載したものである。計画に基づき、鑑賞や創造、発表の機会の拡大や、作品等の評価を向上する取組など、障害のある人による文化芸術活動の充実に向けた各種取組を実施しており、文化庁では2019年度から「障害者等による文化芸術活動推進事業」を実施し、鑑賞・創造・発表等について先導的・試行的な取組を支援している。
また、法律では地方公共団体による計画の策定が努力義務とされ、順次策定が進められているところであり、地方における計画策定及び取組の推進についても併せて支援している。
こうした計画に基づく取組の進捗状況等を踏まえ、2022年度中に計画を改定する予定としている。
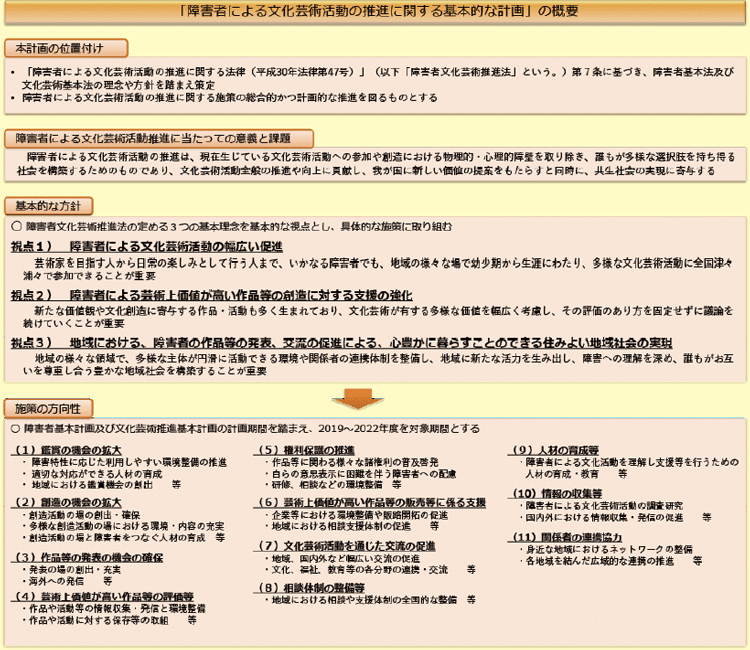
文化庁では、2020年度に引き続き、障害者週間にあわせて共生や障害に関わる展示やワークショップ等を行う「CONNECT![]() _」展を京都において開催した。
_」展を京都において開催した。
2020年度は、京都・岡崎公園に立地する美術館、劇場、図書館、動物園などの文化施設において実施した取組を、2021度は京都市内、さらに京都府域へと展開した。具体的には、身体感覚でアートを楽しむ展示・ワークショップや障害のある人の表現を多様な視点で紹介する展示会、障害のある人の「つくる」ことについてアーティストが様々な専門家にインタビューを行う映像展示、発達障害を扱ったドキュメンタリー映像視聴後のダンスワークショップなどの様々なプログラムを実施し、多様性や共生社会についてともに考える機会づくりとした。また、美術作家で舞台演出家のやなぎみわ氏、京都市立芸術大学学長で画家の赤松玉女氏、京都市京セラ美術館長で建築家の青木淳氏による鼎談を動画配信するなど、オンラインで参加できるプログラムも実施した。

インフォメーションボード
京都国立近代美術館

鼎談の動画配信
“生まれかわる美術館、大学、劇場から考える文化と共生”

展示風景 京都国立近代美術館
身体感覚で楽しむプログラム
「竹村京 Floating on the River」

展示風景 京都市京セラ美術館
「実はよく知らないんだよ。だから聞いてみようと思う。(中原)」の声と手話による映像の展示

