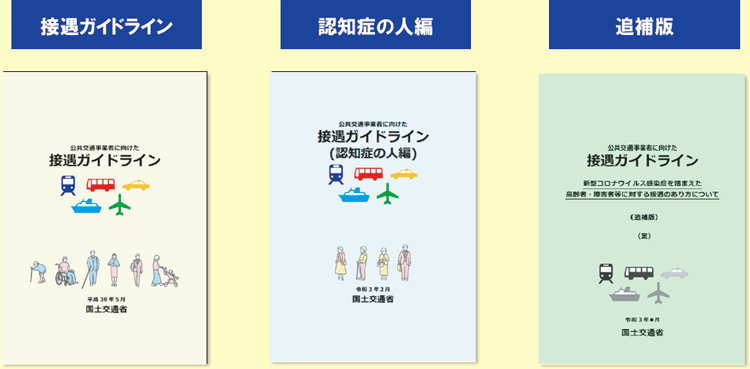第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 第2節 3
第2節 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組とレガシー
3.大会を契機とした共生社会の実現に向けた取組とレガシー
東京パラリンピック競技大会は、東京都による同大会後の都民意識調査(2022年1月28日公表)によれば、同大会を見た人は4割を超え、障害のある人への理解が進んだと回答した人が約3割、また、東京都内のバリアフリー化が進んだと回答した人が約6割となるなど、人々の意識を変化させる大会となった。
また、ユニバーサルデザイン2020行動計画をもとに、関係省庁等が共生社会の実現に向けた諸施策を推進する中、「ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議」を2020年度末までに4回開催し、レガシーとしての共生社会の実現に向け、施策の更なる進展を図ること、取組を加速化することの確認等を行った。また、障害のある人の視点を施策に反映させる枠組みとして、構成員の過半を障害当事者又はその支援団体が占める「ユニバーサルデザイン2020評価会議」(以下「評価会議」という。)を開催した。


評価会議は2021年末までに計5回実施され、2021年11月に開催された第5回評価会議において、大会を契機とした取組の主な成果の報告とともに、共生社会の実現に向け、大会のレガシーとして各主体が連携を図りつつ今後とも取組を継続していくことが期待されるとの総括が行われた。取組の主な成果及びレガシーは次のとおりである。
(1)共生社会の実現に向けた法制度の整備
・大会を契機とした共生社会の実現のため、バリアフリー法を2018年、2020年に改正。2018年の改正では、共生社会の実現の理念が法律に規定されるとともに、マスタープラン制度が創設。2020年の改正では、公立小中学校がバリアフリー基準適合義務の対象に追加されるとともに、自治体が作成するマスタープランや基本構想において、住民や関係者の理解の増進、協力の確保に関する事項等を追加する等、心のバリアフリーを強化。
・事業者による合理的配慮の提供について現行の努力義務から義務へと改めること等を内容とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が2021年通常国会において成立。
(2)心のバリアフリーの拡大・向上
・2020年度から小学校、2021年度から中学校で、新学習指導要領を踏まえた授業を全面実施。
・オンラインによるパラアスリート派遣やパラアスリートのメッセージ動画配信等による新しい生活様式に対応したオリンピック・パラリンピック教育を推進。
・国家公務員向け研修において、「障害の社会モデル」の理解を徹底するため、2018年度に有識者の講義を取り入れるとともに、地方公務員向け研修を2019年度から実施。
・2021年2月に公共交通事業者向け「知的・発達障害者等に対する公共交通機関の利用体験実施マニュアル(案)」を策定、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン(認知症の人編)」を公表し、2021年7月に新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」を公表。
・2020年12月、バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を開始し、2021年9月に66施設、2022年1月に49施設を追加認定。
・2020年6月、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和2年法律第53号)に基づき、電話リレーサービスを公共インフラ化する制度を導入。緊急通報対応や24時間対応も可能となり、2021年7月からサービス開始。
(3)ユニバーサルデザインの街づくり
・国立競技場において、車椅子席を約500席設けたほか、発達障害者等のためのカームダウン・クールダウンスペースや男女共用トイレ、補助犬用のトイレを設置するなど様々な障害者に配慮した設備を整備。
・2021年度からの5年間を目標期間とする新しいバリアフリー整備目標を策定。これにより、地方部を含めたハード・ソフト両面でのバリアフリー化をより一層推進。
・地方部を含めた更なる導入促進のため、2025年度までのバリアフリー法に基づく基本方針における目標において「各都道府県における総車両数の約25%について、UDタクシーとする」とした目標を新設。
・新幹線における車椅子用フリースペースの設置を2021年7月から義務化(東海道新幹線では6名の車椅子使用者が同時に利用可能に)。
・山手線内を中心に車椅子使用者が単独乗降しやすい駅を路線図上でわかりやすく示したバリアフリーマップを2019年12月に、最新版を2021年3月にそれぞれ公表。
・一定規模以上のホテル又は旅館の建築等を行う場合、2019年9月から、当該建築等を行う客室総数の1%以上のバリアフリー客室の整備を義務化。
・2021年3月、「高齢者、障害者等の円滑な移動に配慮した建築設計標準」を改正。小規模店舗内部において、入口の段差解消、扉幅の確保、可動席の設置等のバリアフリー整備を進めるための考え方等を追加。
・高齢者障害者等用便房(バリアフリートイレ)について、「多機能トイレ」、「多目的トイレ」等ではなく、機能分散を推進し、その効果が現れるような表記等による周知、広報啓発の充実等の取組方針をとりまとめ、適正な利用を推進。
・2020年12月、「学校施設バリアフリー化推進指針」を改訂するとともに、公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する2025年度末までの整備目標を設定。
・車椅子使用者用駐車施設等の適正利用の推進についてのポスター・チラシ等を作成し、2021年4月に広報啓発を実施。また、パーキング・パーミット制度を導入するため、2019年3月に事例集を作成。
(4)共生社会ホストタウン
・共生社会実現に向けた取組を実施する共生社会ホストタウンは、105件、その中でも他のモデルとなる先導的共生社会ホストタウンは、15件に拡大。(2021年8月末時点)
・パラリンピアンの受入れに向け、障害当事者参画によるまち歩き点検やバリアフリーマップの作成を実施したほか、パラアスリート等障害当事者による心のバリアフリー研修等を推進。
・コロナ禍においても、約50自治体がパラリンピアンの事前合宿・事後交流を実施したほか、直接受入れのなかった自治体においてもオンライン等で選手等と交流。
・2021年9月、「共生社会ホストタウンサミットin福島」をオンラインで開催し、パラリンピアンの受入れを契機とした共生社会の実現に向けた取組事例を共有するとともに、全国の共生社会ホストタウンにおいて、今後も取組を継続、発展させていくことを確認。
東京2020大会を契機に、共生社会を実現するため、政府レベルの取組としては、2017年2月に「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を策定し、障害のある人の視点を施策に反映させる枠組みとして「ユニバーサルデザイン2020評価会議」を開催して更なる施策の改善に取り組んできた。
この行動計画に基づく取組とあわせて、ユニバーサルデザインへの自立的なきめ細かい取組を促すため、パラリンピアンの受入れを契機に、全国各地における共生社会の実現に向けた取組を加速し、大会以降につなげていく「共生社会ホストタウン」制度を2017年11月に創設した。2021年8月末現在までに105件(109自治体)※が登録された。
※共生社会ホストタウン登録済み自治体(2021年8月末現在)
北海道札幌市、北海道釧路市、北海道滝川市、北海道登別市、北海道江差町、青森県弘前市、青森県三沢市、岩手県遠野市、岩手県陸前高田市、岩手県一戸町、宮城県仙台市、宮城県登米市、宮城県加美町、秋田県能代市、秋田県大館市、秋田県仙北市、山形県鶴岡市、山形県酒田市、山形県村山市、山形県東根市、福島県福島市、福島県猪苗代町、茨城県潮来市、栃木県那須塩原市、群馬県渋川市、群馬県富岡市、群馬県みどり市、群馬県邑楽町、埼玉県本庄市、埼玉県北本市、埼玉県富士見市、埼玉県三芳町、千葉県成田市、千葉県柏市、千葉県浦安市、東京都世田谷区、東京都練馬区、東京都足立区、東京都江戸川区、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都町田市、東京都国分寺市、東京都西東京市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、神奈川県平塚市・神奈川県、神奈川県藤沢市・神奈川県、神奈川県小田原市・神奈川県、神奈川県厚木市、神奈川県大磯町・神奈川県、神奈川県箱根町・神奈川県、新潟県長岡市、石川県金沢市、石川県小松市、石川県志賀町、福井県福井市、山梨県山梨市、山梨県富士河口湖町、岐阜県岐阜市・岐阜県、岐阜県岐阜市、静岡県静岡市、静岡県浜松市、静岡県焼津市、静岡県伊豆の国市、愛知県名古屋市、愛知県豊橋市、三重県伊勢市、三重県鈴鹿市、三重県志摩市、滋賀県守山市、滋賀県甲賀市、大阪府池田市、大阪府守口市、大阪府大東市、兵庫県神戸市、兵庫県明石市、兵庫県加古川市、兵庫県三木市、奈良県大和郡山市、奈良県田原本町、鳥取県鳥取市・鳥取県、島根県益田市、島根県邑南町、岡山県岡山市、岡山県真庭市、広島県広島市、広島県府中市、広島県廿日市市、山口県宇部市、徳島県鳴門市・徳島県、香川県高松市、愛媛県松山市・愛媛県、福岡県北九州市、福岡県飯塚市、福岡県田川市、福岡県大川市、福岡県築上町、長崎県島原市、大分県大分市、大分県別府市、大分県中津市、大分県佐伯市、宮崎県宮崎市、鹿児島県龍郷町(105件・109自治体)
共生社会ホストタウンの取組は、以下の二つの柱から構成される。
○共生社会の実現に向けた取組
障害のある海外の選手たちを迎えることをきっかけに、ユニバーサルデザインの街づくり及び心のバリアフリーに向けた、自治体ならではの特色ある総合的な取組を実施。大会のレガシーにもつなげていく。
○パラリンピアンとの交流
東京パラリンピック競技大会直後の交流も含め、幅広い形でのパラリンピアンとの交流を通じ、パラリンピックに向けた機運を醸成するとともに、住民がパラアスリートたちと直に接することで、住民の意識を変えていく。
また、共生社会ホストタウンのうち、他の共生社会ホストタウンのモデルとなる自治体を「先導的共生社会ホストタウン」として認定する制度を2019年5月に新たに創設し、パラリンピアンとの交流やホテル・公共交通機関のバリアフリー改修支援などについて国が重点的に支援することとした。
※先導的共生社会ホストタウン認定自治体(2021年8月末現在)
青森県三沢市、岩手県遠野市、秋田県大館市、福島県福島市、東京都世田谷区、東京都江戸川区、神奈川県川崎市、静岡県浜松市、三重県伊勢市、兵庫県神戸市、兵庫県明石市、山口県宇部市、福岡県飯塚市、福岡県田川市、大分県大分市(15件・15自治体)
<取組例>
〇当事者の視点に立った共生社会の考え方やパラスポーツへの理解を深めるため、中学校・特別支援学校合同のボッチャ体験会を実施。(岩手県遠野市)
〇共生社会ホストタウンの連携強化と取組の共有・発信のため、「共生社会ホストタウンサミットin 福島」をオンラインで開催。共生社会ホストタウンの取組に参加する市民等の発表や首長らによるパネルディスカッションを実施。(福島県福島市)
〇ブラジルパラリンピック14競技・選手団388名の事前合宿を21日間にわたり市内13会場、近隣の袋井市1会場で受入れ。パラカヌー選手団と市内チアリーディング団体とのオンライン交流では、子供たちが応援のダンスを披露。(静岡県浜松市)
〇総合体育館のトイレ、シャワー、観覧スペース、自動ドア等のバリアフリー化、またトレーラーハウスを活用した車椅子対応型の合宿所15棟(台)を整備し、ハード面のユニバーサルデザインの街づくりを推進。ドイツ及びベラルーシの車椅子フェンシング代表チームの事前合宿でも利用。(福岡県田川市)

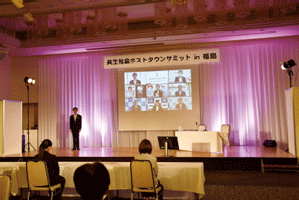


共生社会ホストタウンでは、コロナ禍により直接の交流が難しい中でも、オンライン等を活用した相手国・地域との交流や、共生社会の実現に向けた取組を継続してきた。
共生社会ホストタウンは、今後ともその取組を大会のレガシーとして継続していけるよう関係省庁等とも連携していくこととしている。
2017年2月に決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を踏まえ、公共交通事業者による一定水準の接遇を全国的に確保するため、2018年5月に交通モードごとの特性や様々な障害の特性等に対応した「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」を作成した。
また、上記「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」については、2019年6月に決定された「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症の方に対する公共交通事業者による研修の充実及び適切な接遇の実施を推進するため、2021年2月に「認知症の人編」を作成するとともに、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりを受け、感染症を踏まえた接遇のあり方について、公共交通事業者において提供する接遇の場面ごとに具体的な感染予防対策を実践するため、2021年7月に新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた「追補版」の作成を行った。
一方、交通モード別(鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、航空)に「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」の内容を業界単位で展開し、公共交通事業者による実施を促進するとともに、公共交通事業者の行う研修について、障害のある方が参加し、座学に加えて実習を行うカリキュラム・研修教材となるよう、2019年3月に作成した「接遇研修モデルプログラム」については、2022年3月に改訂を行い、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」の「認知症の人編」及び「追補版」の内容が反映されたものとなっている。
国土交通省としては、共生社会の実現に向け、ソフト面の施策として、引き続き、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」及び「接遇研修モデルプログラム」の周知・普及を図ることにより、公共交通事業者各社が実施する職員への接遇に関する教育訓練の向上に努めていく。