
 |
![]()
交通事故被害者の支援 第3章 交通事故が被害者に与える精神的影響
交通事故によって愛する家族を突然失うことは、遺族に多大な精神的苦痛を与える。いかなる形であっても、死はその身近な人にとって苦痛で耐えがたい思いを強いるものであるが、病気と異なって事故の場合は突然で予期しない形で現れ、また、加害者が存在しなければ起きなかったという気持ちから、死を受け入れにくくなり、複雑な葛藤を生み出すことになる。
平成10年に行われた交通事故被害実態調査研究委員会の「交通事故被害実態調査研究報告書」の中から、遺族の精神的負担について図-3に示した。
|
図-3 死亡事故遺族の精神的ストレス (交通事故被害実態調査研究委員会編「交通事故実態調査研究報告書 平成11年6月」より転載) |
事故後1ヵ月以内では、「事故のことについて考え込んでしまう(61%)」、「突然に事故のときの光景がよみがえる(56%)」、「気持ちが落ち込む(54%)」であり、いずれも被害者本人より高率であった。また、調査時点では「事故について思い出させるものにふれるとすごく辛い(60%)」、「事故に関わることは考えないようにしている(47%)」、「事故を思い出させるようなものや場所を避けてしまう(42%)」、「事故のことについて考え込んでしまう(42%)」であり、事故について考えたくないと思っている一方で、考えずにはいられないというアンビバレンツな状態が存在していることが分かる。
同調査におけるGHQ20の結果から、精神的健康状態が低いとされた遺族の割合は76.6%であり、被害者本人の58.0%を上回っていた。この結果から、遺族は被害者本人と同様、あるいはそれ以上に精神的苦痛に悩まされていることが分かる。
遺族において、精神的後遺症が大きいことは自助グループに参加している交通事故遺族の調査(佐藤、1998 ))によっても示されている。佐藤の調査でも、交通事故遺族では死別から調査時点まででPTSDと診断される状態を呈した人の割合は58.8%と高率であり、特に事故のことを思い出してしまうという侵入的想起の症状が多くみられることが示された。
このように遺族は、実際には事故を体験しておらず、事故現場を必ずしも目撃しているわけではないにもかかわらず、高いPTSDの発症率と精神健康度の低さを示したことから、事故による突然の死が家族にもたらす影響の大きさをうかがい知ることができる。
遺族の場合には、被害者本人と違って喪失体験に伴う「悲嘆反応」が見られ、これがPTSDやうつ病などと合併して複雑な病態を示す。以下に「悲嘆反応」についてまとめた。

(1) 急性期(数週間から数ヵ月)
最初は出来事の衝撃から、死の事実を受け入れられない「ショックと否認」の状態となる。死を現実のものと考えることができず、夢の中のようだった、他人事のようだったと話す遺族もいる。感情が麻痺してしまい、辛いとか悲しいという感情さえもわいてこないために涙さえ出てこない場合がある。
客観的には、非常に落ち着いてみえるため、周囲から「気丈な人だ」、「しっかりしているから大丈夫」、「冷たい」などと誤解を受けてしまう場合もある。この時期が過ぎると、次第に死を現実のものとして感じるようになるため、激しい悲しみに襲われる。
(2) 慢性期(数ヵ月後)
数ヵ月経つと死を受け入れて、遺族自身の生活を再建するということが行われるが、この過程で喪失に対する悲哀や抑うつ、怒り、不眠や身体的不調など、さまざまな症状が表れてくる。
ウォーデン(1991)は悲哀の課題として、1) 喪失の事実を受容する、2) 悲嘆の苦痛を乗り越える、3) 死者のいない環境に適応する、4) 死者を情緒的に再配置し、生活を続けるの4つをあげている。
亡くなった人は帰ってこないので、被害者と遺族の回復のゴールは異なるところにある。遺族にとっての回復は、悲しみは変わることがないが、死の事実を受け入れ、日常生活や社会生活を人生の希望や喜びをもって生きられるような状態になることであろう。
しかし、このような段階に至るためには、複雑な心理的葛藤が存在する。以下に遺族によくみられる心理状態をあげた 4)。
4) この部分は、「J.W.ウォーデン著/鳴澤實監訳 大学専任カウンセラー会 訳『グリーフカウンセリング 悲しみを癒すためのハンドブック』、川島書店、1993」を参考にまとめた。
1) 悲しみ
悲しみはあたりまえの感情ではあるが、表現の形は人によって異なっており、比べることはできない。必ずしも泣き叫ぶなど外にわかる形で表現される訳ではない。
2) 怒り
怒りは出来事そのものに対する理不尽さ、加害者への怒り、また自分を残していった故人に対する怒り(「どうして私を1人にしたのか」)など、さまざまなものがある。
事故や犯罪の場合では、加害者に対する激しい怒り(「殺してやりたい」)として、しばしば表現される。しかし、遺族自身も自分がこのような激しい怒りや憎しみの感情を持つことに困惑する場合もある。
また、加害者に直接怒りをぶつけられるわけではないので、家族や友人の無理解や支援の乏しさに対して、あるいは警察や司法関係者、保険業者などの対応の悪さに対して怒りが向けられることがある。罪悪感とともに遺族自身の内面に怒りが向けられてしまうと、自殺念慮や、自殺行動としてあらわれることがある。
3) 罪悪感と自責感
故人に対して、生前もっとこうしてあげればよかったとか、あのとき電話をしていれば助かったのにとか、外出をとめればよかったなど、自分が助けられなかったことに対して罪悪感や自責感が生じる。
ほとんどの場合、現実には不可能なことであり、非合理的ではあるが、遺族は自分を責めずにいられず「自分を責める必要はない」、「そういっても無理なことだった」などの周囲の慰めは受け入れがたい。
4) 不安感
不安はさまざまな理由で生ずる。故人が経済的あるいは心理的な支えであった場合、その人なしでこれからどうしたらいいか分からないという不安が生ずる。また、死を実感したことで、自分自身や他の家族に対して死の不安が出現する。子どもを亡くした遺族の場合、残された子どもが事故にあわないように過剰に心配し、外出させないなど必死で守ろうとしたり、少しでも姿が見えないとパニックになってしまうという場合もある。
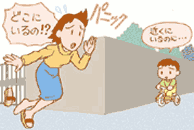
5) 孤独感
他の家族や友人がいても一人ぼっちだという感情が表れる。特に、配偶者を亡くした遺族では強い。
6) 疲労感
喪失のストレスからくる疲労だけでなく、実際に葬儀など疲れる出来事がたくさんある。また、特に犯罪や事故では裁判や保険の問題など、やらなくてはならないことがたくさん存在するために、物理的にも疲労が生ずる。
遺族はしばしば疲労を無視して活動をするため、うつ病の原因ともなる。疲労は無気力や無関心(家事ができない、他の家族に関心をもてない、仕事ができない)などの形で表現される。
7) 無力感
強い精神的ストレスから家事や仕事、育児などができなくなると、自分は何もできないという無力感が生じる。
8) 思慕
故人に対して、その存在を追い求めあいたいと願う気持ちであり、喪失体験では通常の反応である。
9) 解放感、安堵感
故人が家族に対してストレスを与えていたり、長期の病気を患い苦しんでいたような場合には、解放感や安堵感を感じることがあるが、それを感じたことに対して罪悪感が生じたりもする。
10) 身体的症状
身体の不調を感じることがある。以下のようなことが多いとされる。
腹部の空腹感、胸部の圧迫感、喉の緊張感、音への過敏さ、離人感、息切れ、筋力の衰え、体に力が入らない感じ、口の渇き、睡眠障害、食欲の障害。

11) 思考・認知の特徴
急性期では、混乱した思考がみられる。生き返らせたいとか、過去に戻って助けたい、あるいは故人の苦しむ姿などの故人についての考えにとらわれてしまう場合もある。故人がまだ生きているように感じたり、その姿が見えたり、声が聞こえるなどの幻覚が生じることもある。
このような幻覚は病的なものではなく、死後2〜3週間以内の遺族には一過性にみられることがある。
12) 行動の特徴
行動にも変化が表れる。ぼうっとしていて、自分がどうやって帰ってきたかよく分からないというような状態がみられる。また、人に会いたくない(周りにあわせるのが困難、孤立感、自分が暗いので周囲に不快な思いをさせるなどの考え)から、引きこもりがちになる。
故人を思いださせるものを回避する(一切部屋に入らない、写真を飾らない、持ち物を捨ててしまう)人もいれば、いつまでも納骨できない、故人のものを処分できない、部屋をそのままにしているなど、故人の存在をいつもそばに置こうとする人もいるなど、さまざまである。
前述の悲嘆反応は、病死など死に対して一般的に見られる反応である。しかし、交通事故死の場合は予期されない突然の死であり、かつ人為的なものである。このような場合には、通常の悲嘆反応より症状が複雑になったり、長期化することが見られる。
1) 非現実感が長期間続く
突然の予期しない死であるために非現実感が生じ、長く続く場合がある。感情の麻痺したような状態や呆然とした状態として表れる。
2) 罪悪感が激しい
実際には、遺族にはなんら責任はないわけであるが、「もし…していれば」という罪悪感が生じる。また、子どもの場合には死の前に親に怒られたり、兄弟とのけんかで「いなくなってしまえばいい」とか、「死んでしまえばよい」などと思ったことで、死んだのではないかという罪悪感が生じることがある。
3) 誰かを非難してしまう
罪悪感に伴って、家族の誰かを非難したいという欲求が生じやすくなる。特に親がついていて子どもを守れなかった場合には、その親への非難が生じたり、兄弟の一方が亡なった場合には、もう1人の兄弟に対して非難や欲求不満が向いたりする。
4) 裁判などが終わるまで悲しむことができない
交通事故で刑事裁判や民事裁判、補償の問題があるとそれに気をとられてしまい、十分に悲しむことができないという問題が出てくる。これらの手続きが終了した後に、悲嘆反応が表れることがある。
5) 強い無力感と怒り
突然の予期しない死は、自分たちにはどうすることもできないという感覚を生じさせ、強い無力感を生む。この無力感に対抗してコントロール感を取り戻そうという試みでもあるが、激しい怒りが生じる。しばしば「加害者を殺したい」というような発言として表れる。
6) 故人の遣り残したことの問題
故人が何かを遣り残している場合には、遺族がそれを痛ましく思い引き継いで行うことがある。これを行うことが回復につながる場合もあるが、残された兄弟が親の期待という圧力で兄弟の役割(進学、進路、親への関わり方)などを引き継がなくてはならないというようなことも起きてくる。
7) 死について理解したいという強い欲求
事故による死は理不尽なものであるが、どうしてそれが起きたかについて理解したいという欲求がある。それは事故の状況を確認したい、誰に責任があるか追求したい、加害者がどうして事故を起こしたか知りたいという欲求ともなる。そのために民事裁判を起こすこともある。
8) 精神疾患をきたす
PTSDやうつ病、不安神経症、アルコールや薬物依存症などの精神疾患をきたす率が高い。
佐藤(2001)は、死別の回復を妨げる要因として以下のことをあげている。
1) 死別状況
突然の予期しない死、事件など暴力的な死、遺族や死者に責任がある場合。
2) 遺族と死者の関係
死者との依存的な関係、愛憎半ばするアンビバレントな関係、子どもの死、配偶者の死、幼い子どもを残した母親の死。
3) 遺族の特性
繰り返し死別を体験すること、身体的・精神的な障害を有すること、依存的な性格、不安定な性格、低い自己評価。
4) 社会的要因
家族や親戚、友人が少ないなど孤立した状況、経済状態の悪さ、社会的地位の低さ、仕事にやりがいがない、幼い子どもがいる、家族内に被介護者がいること。
5) 二次被害
マスコミの取材、警察、司法関係者、医療関係者からの冷たいぞんざいな対応、未熟な治療者による悲嘆の軽視、近隣の風評など。
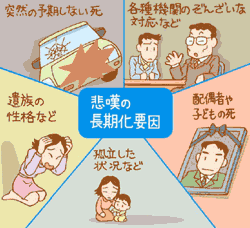
![]()