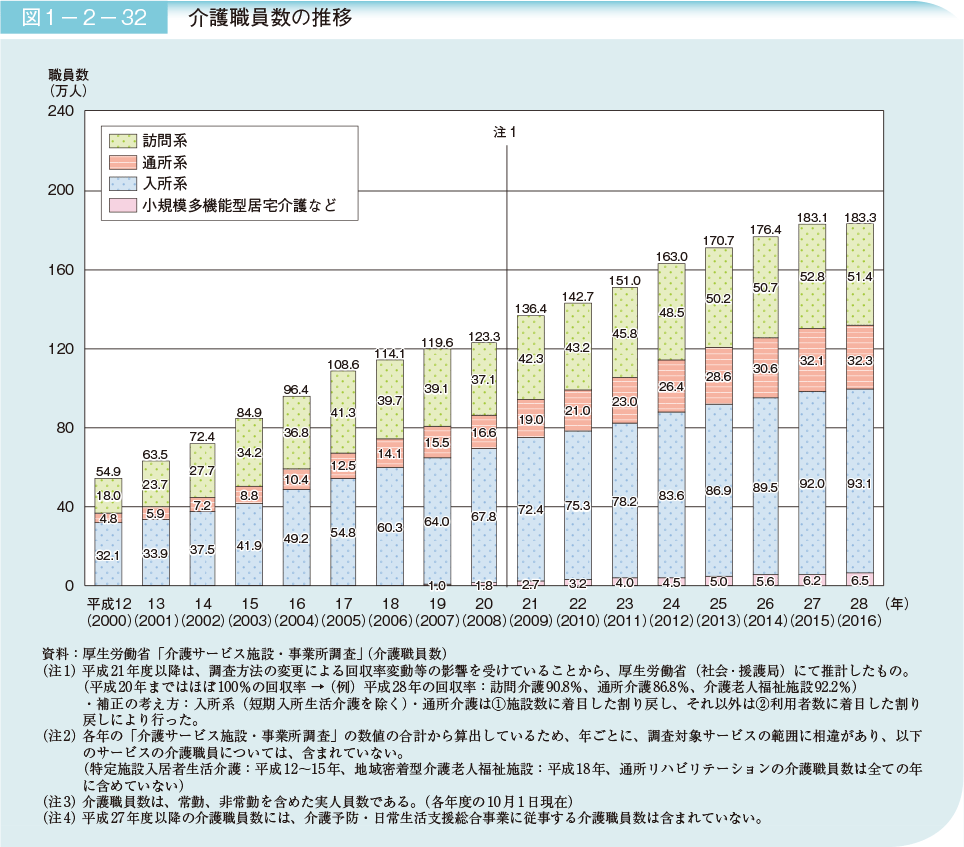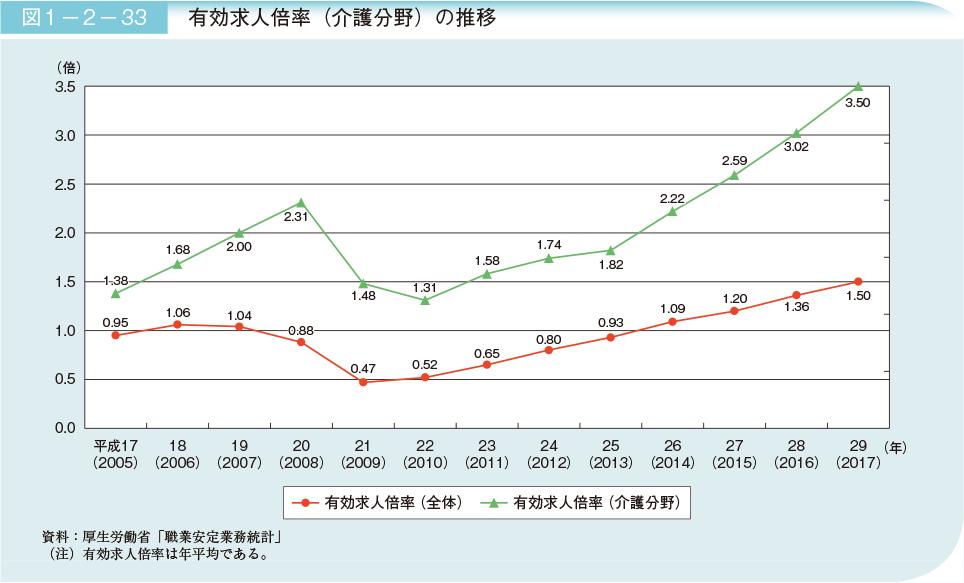第1章 高齢化の状況(第2節 2)
第2節 高齢期の暮らしの動向(2)
2 健康・福祉
○65歳以上の者の新体力テスト(握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行)の合計点は向上傾向
- 平成28(2016)年の70~74歳の男子・女子、75~79歳の男子・女子の新体力テストの合計点は、それぞれ平成10(1998)年の65~69歳男子・女子、70~74歳の男子・女子の新体力テストの合計点を上回っている(図1-2-18)。
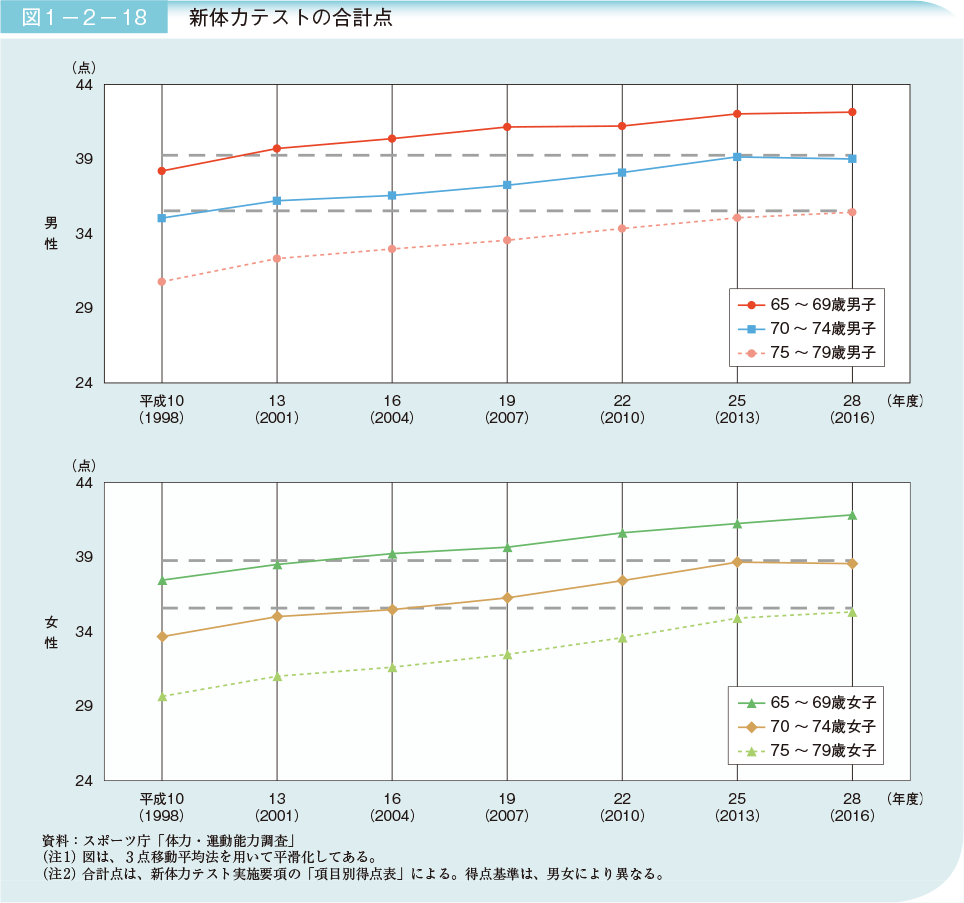
○60~65歳層の数的思考力と読解力は各国に比べて高い
- OECDの国際成人力調査(PIAAC)によると、60~65歳層の数的思考力、読解力は各国に比べて高い(図1-2-19、図1-2-20)。
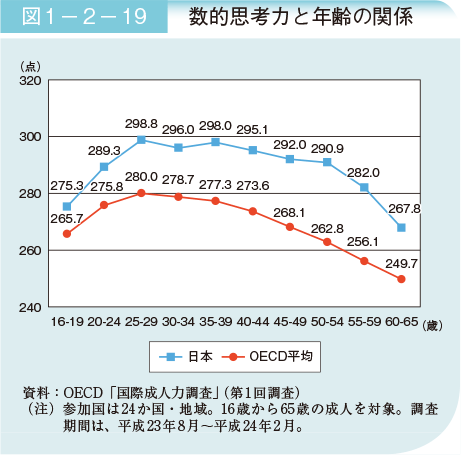
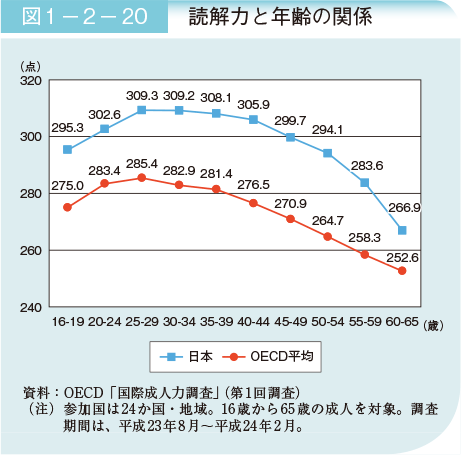
○健康寿命は延伸し、平均寿命と比較しても延びが大きい
- 日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成28(2016)年時点で男性が72.14年、女性が74.79年となっており、それぞれ平成22年(2010)年と比べて延びている(平成22年→平成28年:男性1.72年、女性1.17年)。さらに、同期間における健康寿命の延びは、平均寿命の延び(平成22年→平成28年:男性1.43年、女性0.84年)を上回っている。(図1-2-21)。
- 健康寿命と平均寿命の差を都道府県別にみると、男性では青森県(平均寿命:78.67年、健康寿命:71.64年)が最も差が短く、ついで山梨県(平均寿命:80.85年、健康寿命:73.21年)が短く、奈良県(平均寿命:81.36年、健康寿命:71.39年)が最も長く、ついで長野県(平均寿命:81.75年、健康寿命:72.11年)が長い。また、女性では栃木県(平均寿命:86.24年、健康寿命:75.73年)が最も差が短く、ついで愛知県(平均寿命:86.86年、健康寿命:76.32年)が短く、広島県(平均寿命:87.33年、健康寿命:73.62年)が最も長く、ついで滋賀県(平均寿命:87.57年、健康寿命:74.07年)が長い(図1-2-22)。
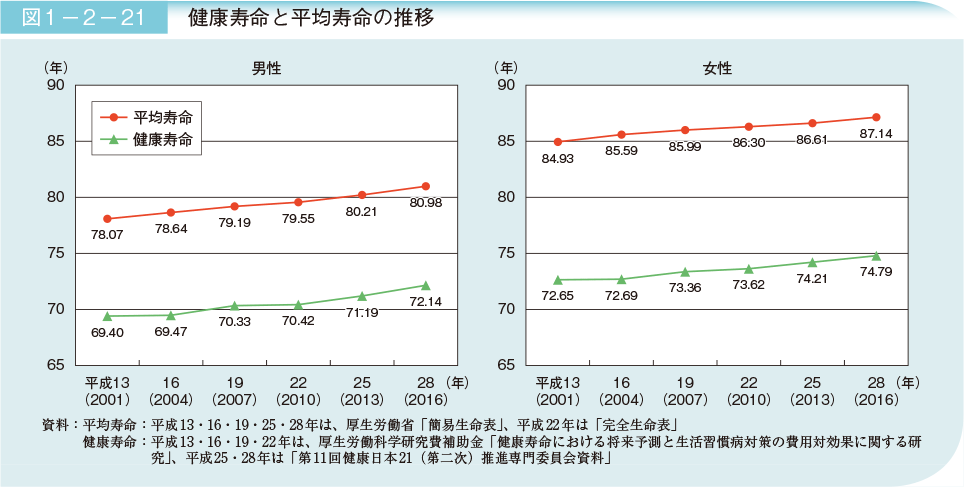
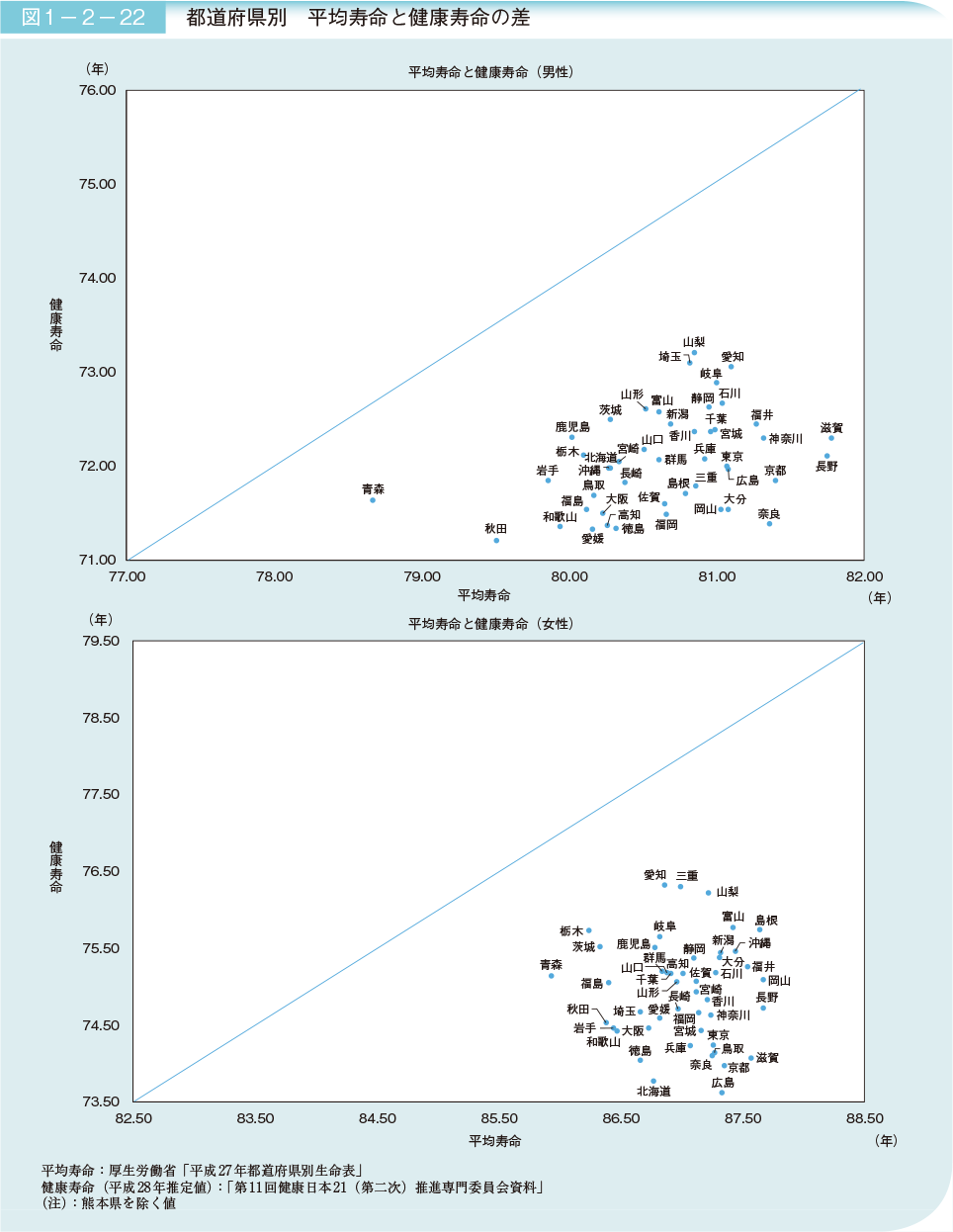
○65歳以上の者の死因は「悪性新生物(がん)」が最も高い
- 65歳以上の者の死因をみると、死亡率(65歳以上人口10万人当たりの死亡数)は、平成28(2016)年において、「悪性新生物(がん)」が926.2と最も高く、次いで「心疾患(高血圧性を除く)」528.6、「肺炎」336.9の順になっている(図1-2-23)。
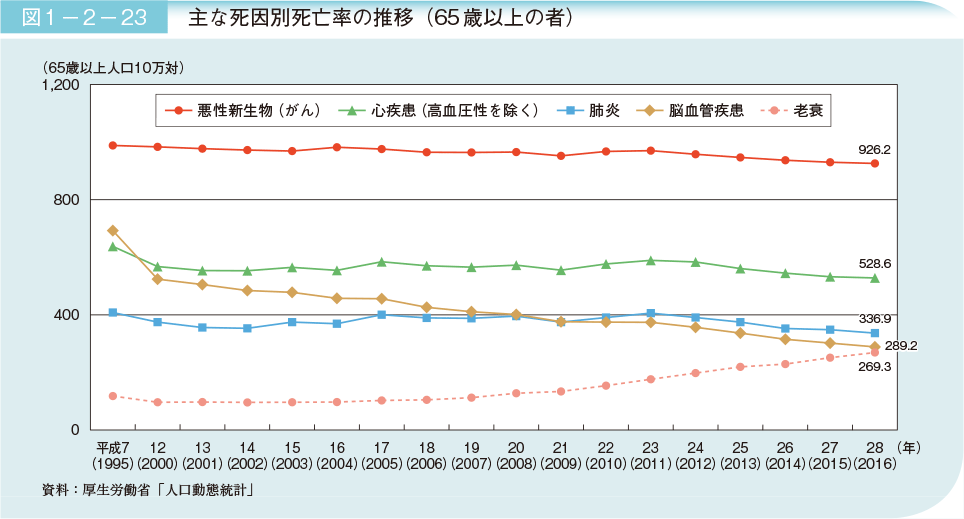
○65歳以上の者の要介護者等数は増加しており、特に75歳以上で割合が高い
- 介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けた人(以下「要介護者等」という。)は、平成27(2015)年度末で606.8万人となっており、平成15(2003)年度末(370.4万人)から236.4万人増加している。(図1-2-24)。
- 75歳以上で要介護の認定を受けた人は75歳以上の被保険者のうち23.5%を占める(表1-2-25)。
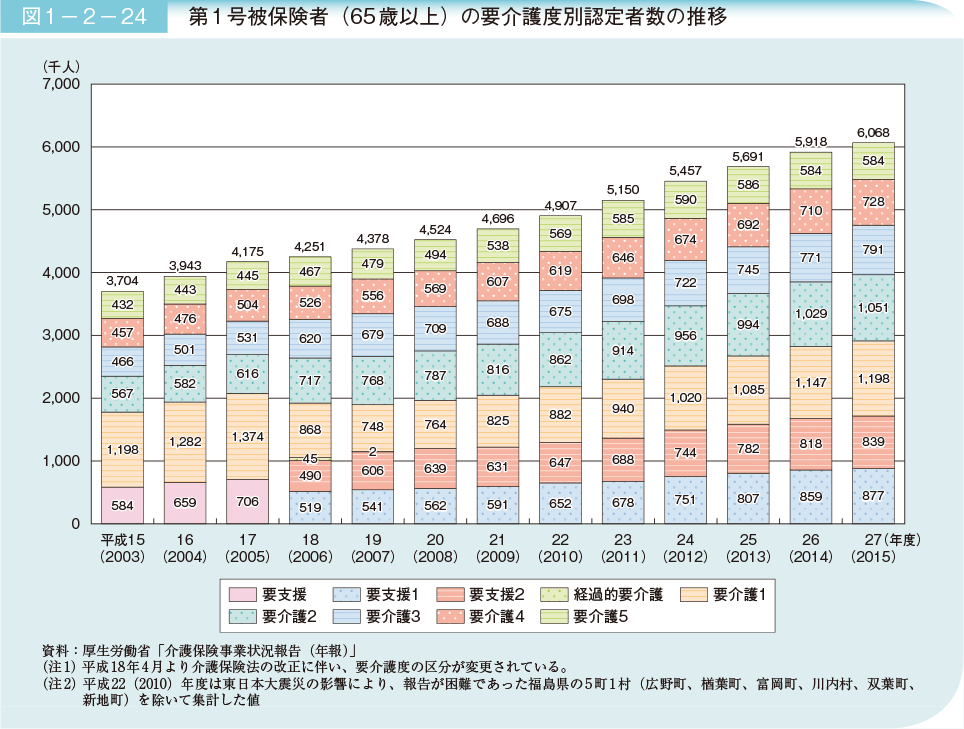
| 単位:千人、( )内は% | |||
| 65~74歳 | 75歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 要支援 | 要介護 | 要支援 | 要介護 |
| 246
(1.4) |
510
(2.9) |
1,470
(9.0) |
3,842
(23.5) |
| 資料:厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」(平成27年度)より算出 | |||
| (注1)経過的要介護の者を除く。 | |||
| (注2)( )内は、65~74歳、75歳以上それぞれの被保険者に占める割合 | |||
○自宅で介護を受けたい人の割合は73.5%、介護を頼みたい人は男性の場合配偶者、女性の場合ヘルパーなど介護サービスの人が最も多い
- 自分の介護が必要になった場合にどこでどのような介護を受けたいかの希望についてみると、自宅で介護を受けたいと回答した人の割合は全体で73.5%であった(図1-2-26)。
- 「介護を頼みたい人」についてみると、男性の場合は「配偶者」が56.9%、女性の場合は「ヘルパーなど介護サービスの人」が39.5%と最も多くなっている(図1-2-27)。
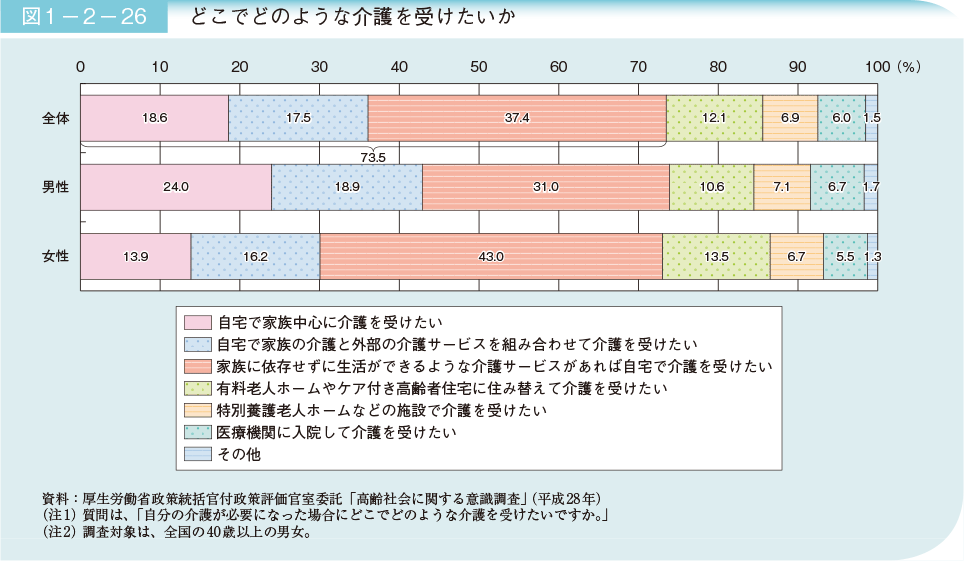
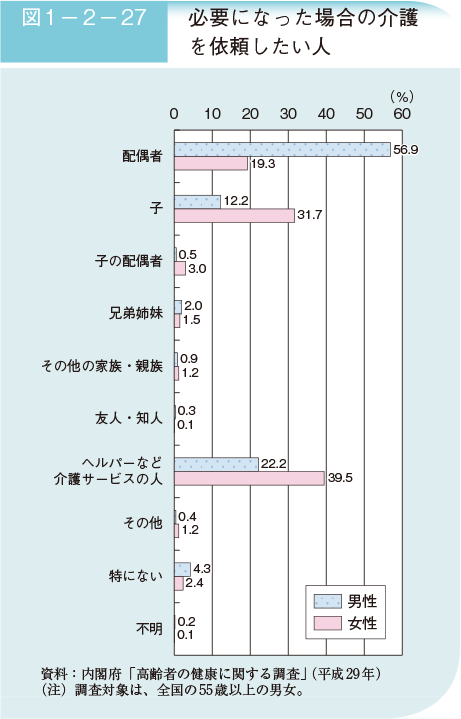
○主に家族(とりわけ女性)が介護者となっており、「老老介護」も相当数存在
- 要介護者等からみた主な介護者の続柄をみると、6割弱が同居している人が主な介護者となっている。
- その主な内訳は、配偶者が25.2%、子が21.8%、子の配偶者が9.7%となっている。また、性別については、男性が34.0%、女性が66.0%と女性が多い。
- 要介護者等と同居している主な介護者の年齢について、男性では70.1%、女性では69.9%が60歳以上であり、いわゆる「老老介護」のケースも相当数存在している(図1-2-28)。
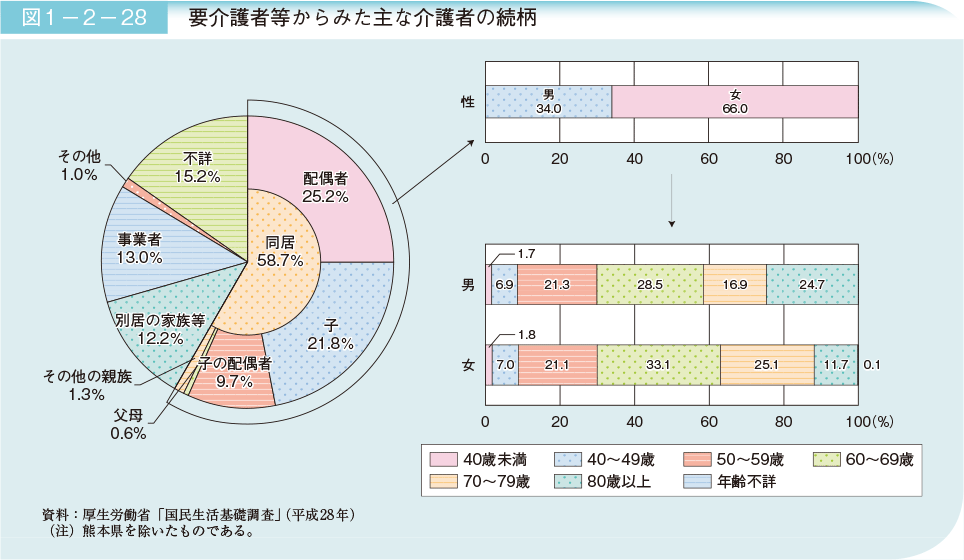
○介護や看護の理由により離職する人は女性が多い
- 家族の介護や看護を理由とした離職者数は平成23(2011)年10月から平成24(2012)年9月の1年間で101.1千人であった。とりわけ、女性の離職者数は81.2千人で、全体の80.3%を占めている(図1-2-29)。
- 介護・看護の理由による離職者数をみても、平成28(2016)年では女性の離職した雇用者数は62.6千人で、全体(85.8千人)の73.0%を女性が占めている(図1-2-30)。
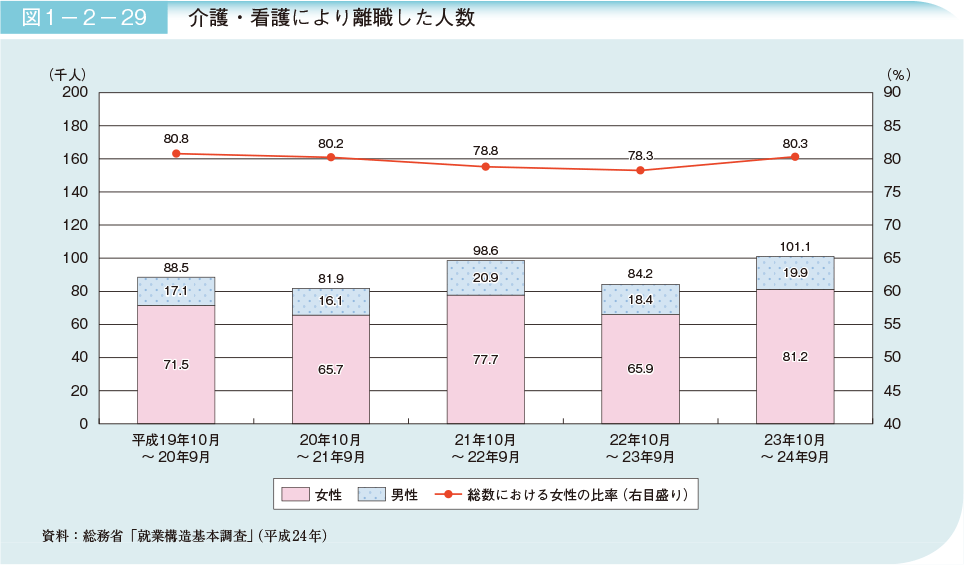
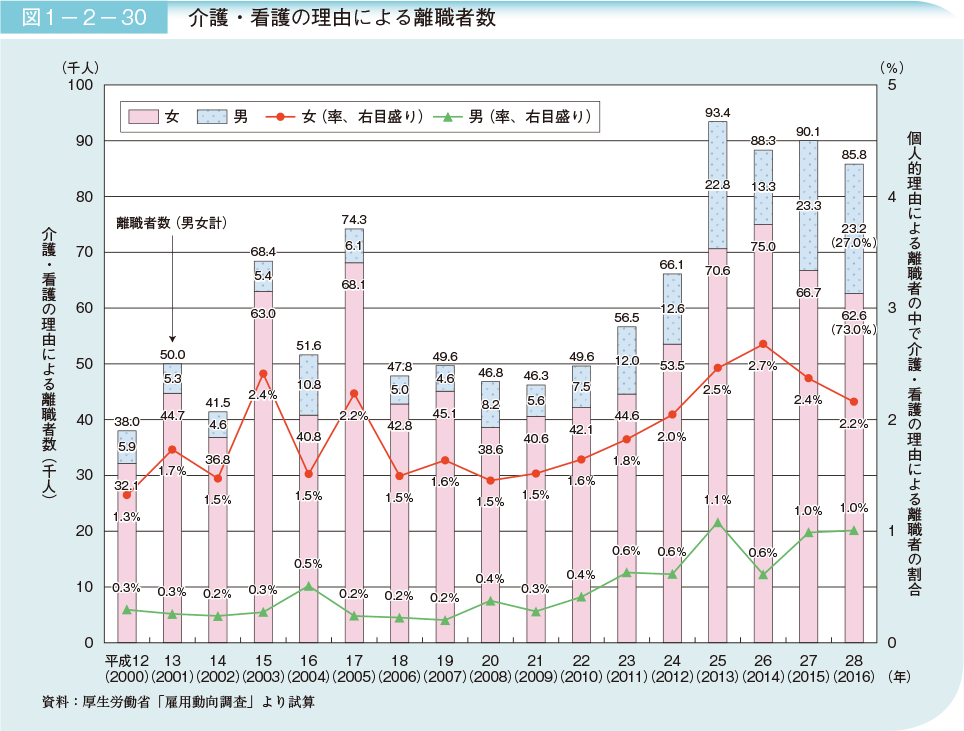
○介護施設等の定員数は増加傾向で、特に有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の定員が増加
- 介護施設等の定員数をみると、増加傾向にある。施設別にみると、平成28(2016)年では、介護老人福祉施設(特養)(530,280人)、有料老人ホーム(482,792人)、介護老人保健施設(老健)(370,366人)等の定員数が多い。また、近年は有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の定員数が特に増えている(図1-2-31)。
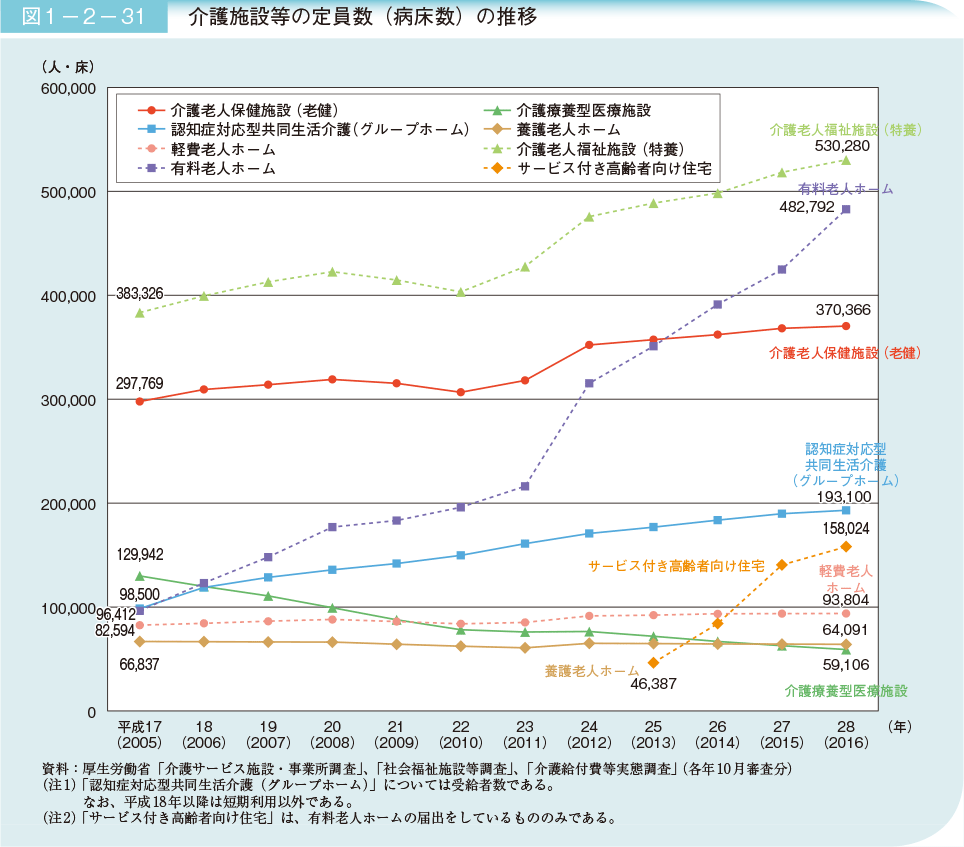
○介護に従事する職員数は増加しているものの、依然として不足している
- 要介護(要支援)認定者数の増加に伴い、介護に従事する職員数は大幅に増加している。平成28(2016)年度は、平成12(2000)年度(54.9万人)の約3.3倍の183.3万人となっている(図1-2-32)。
- 介護分野の有効求人倍率をみると、全産業の有効求人倍率に比べ、高い水準を維持し続けている。平成29(2017)年の介護分野の有効求人倍率は3.50倍となり、全産業の有効求人倍率(1.50倍)の約2.3倍となった(図1-2-33)