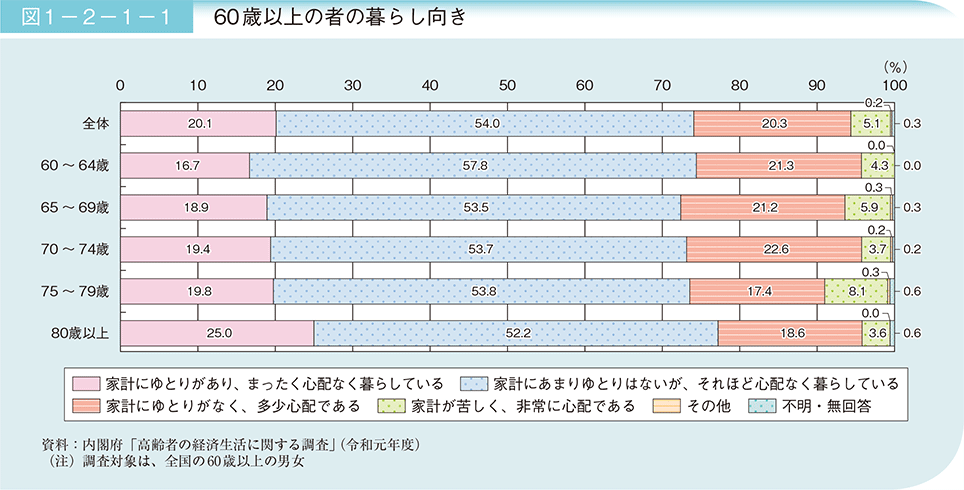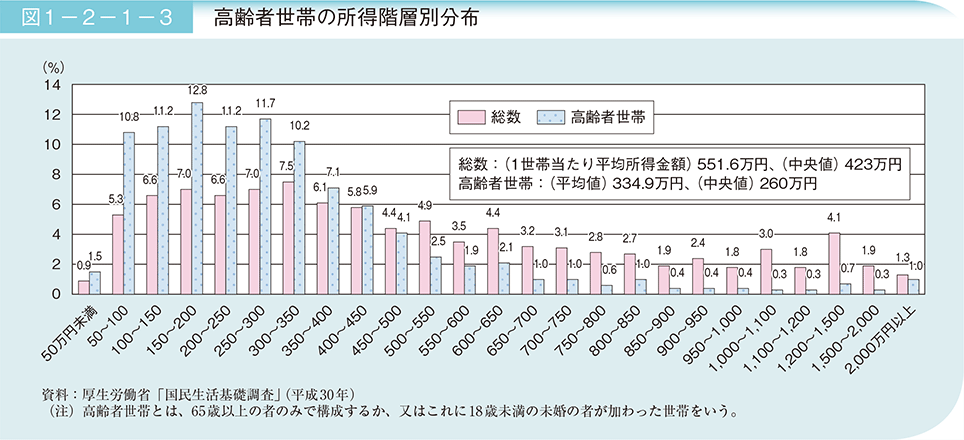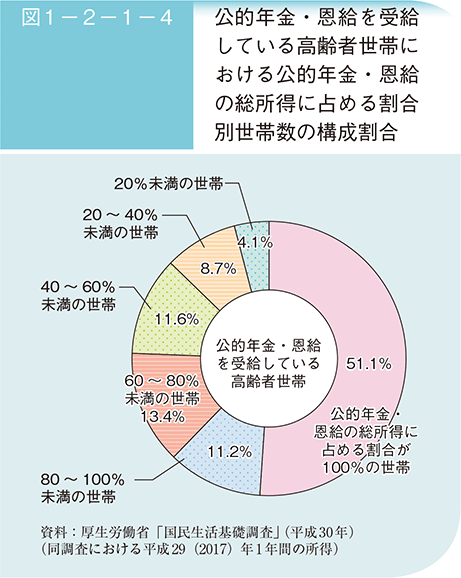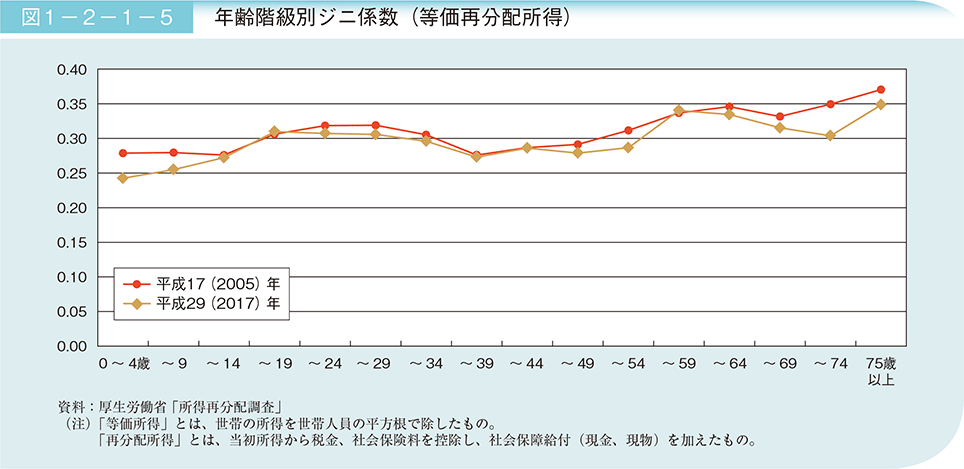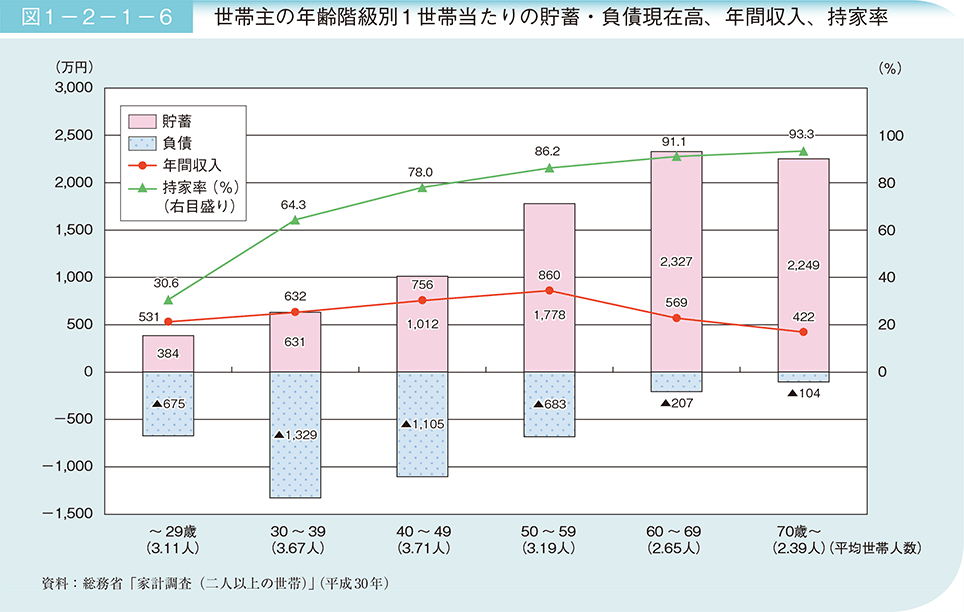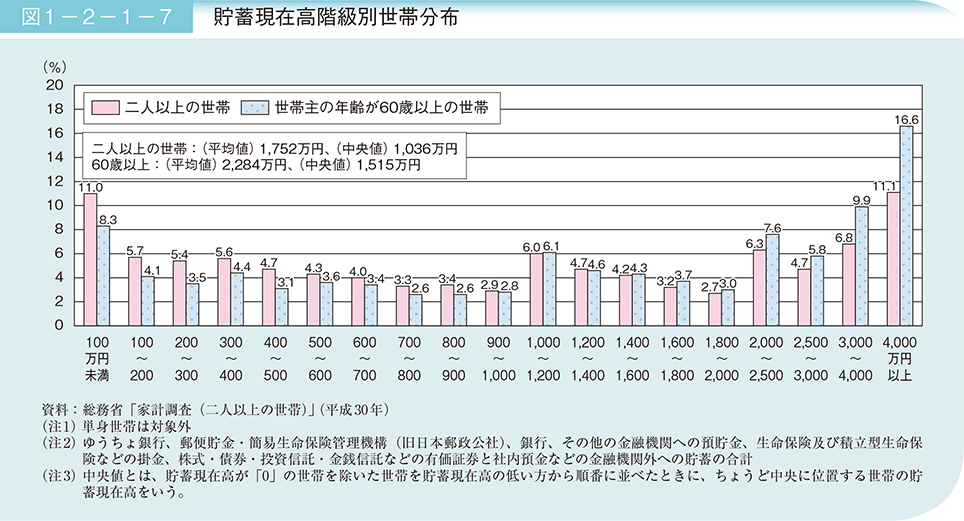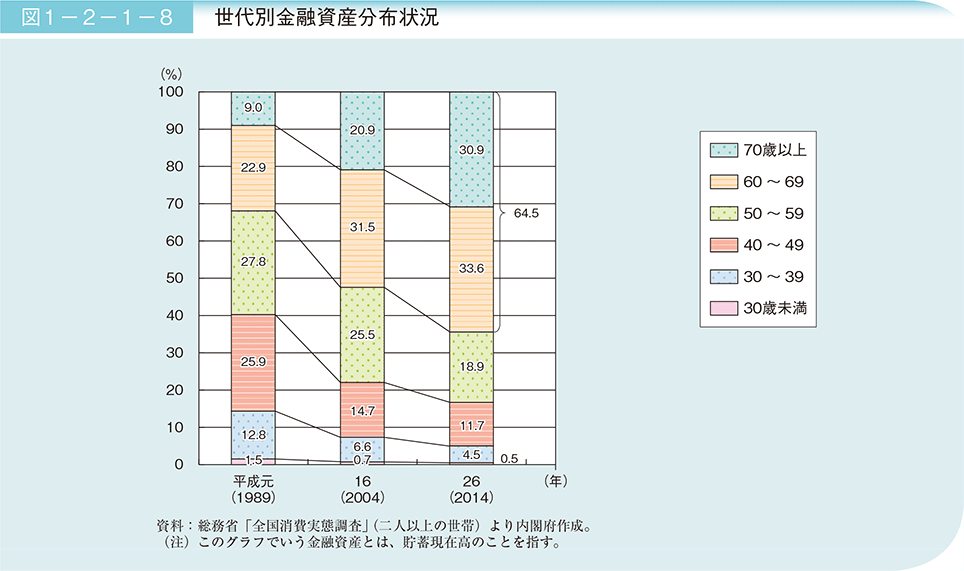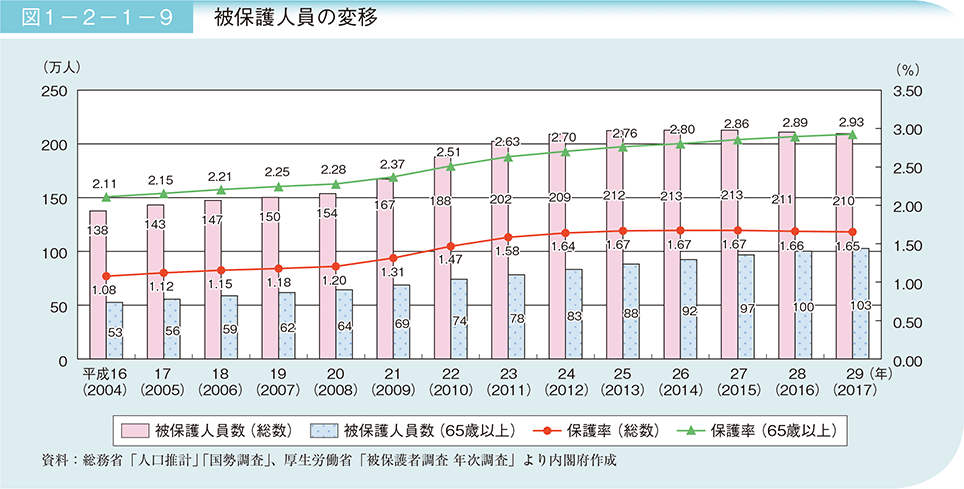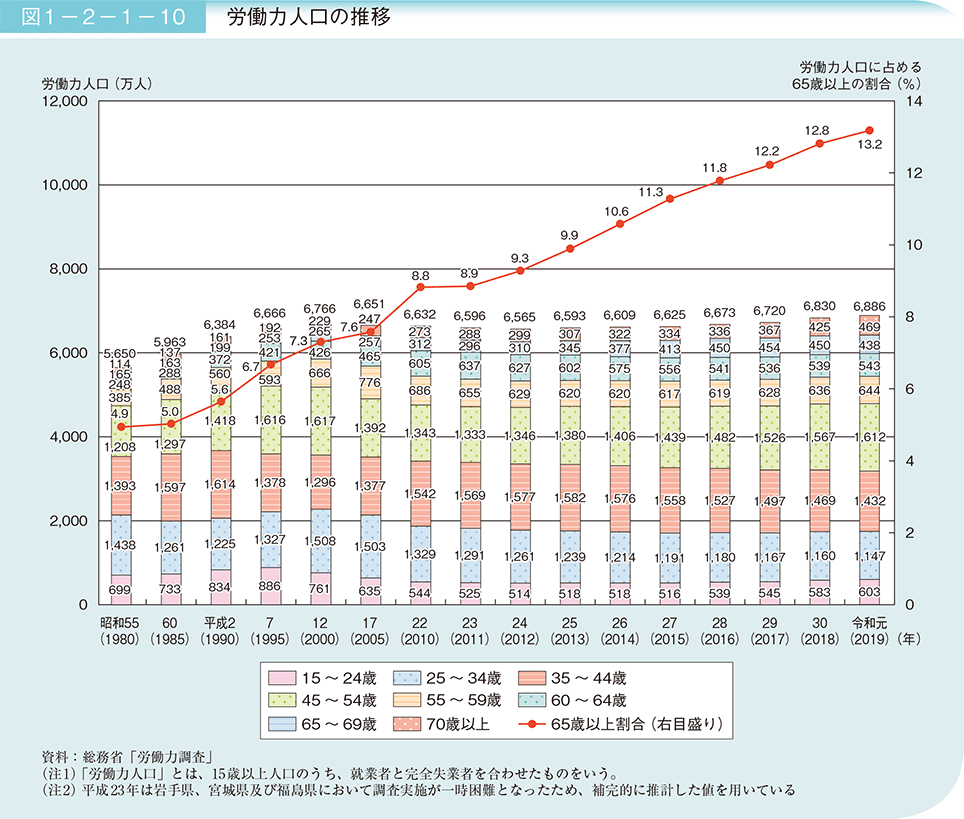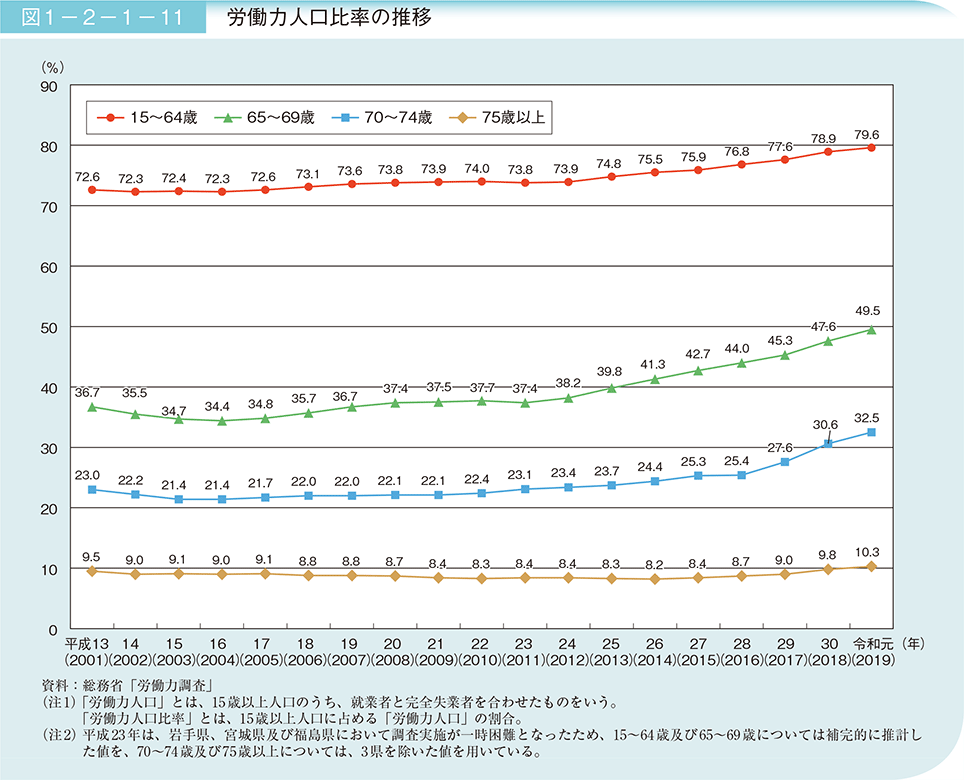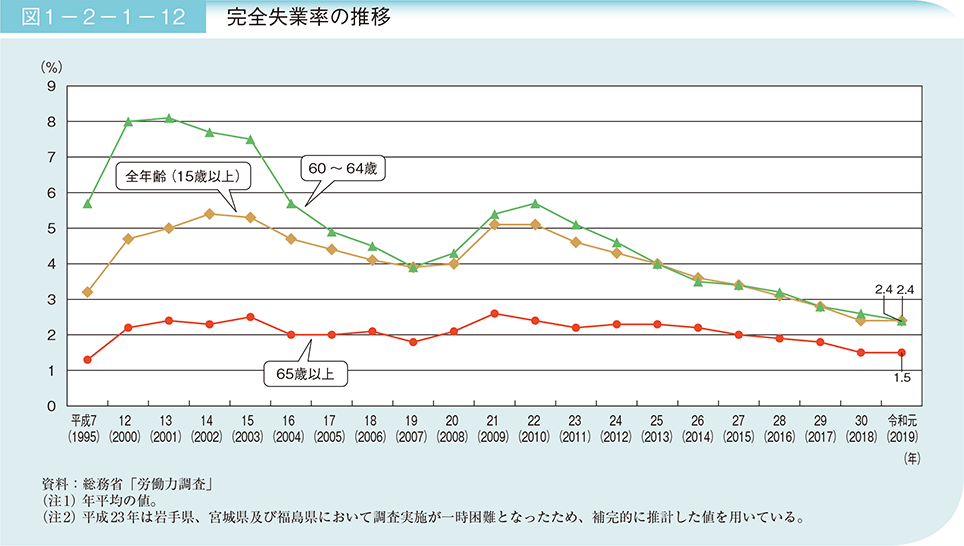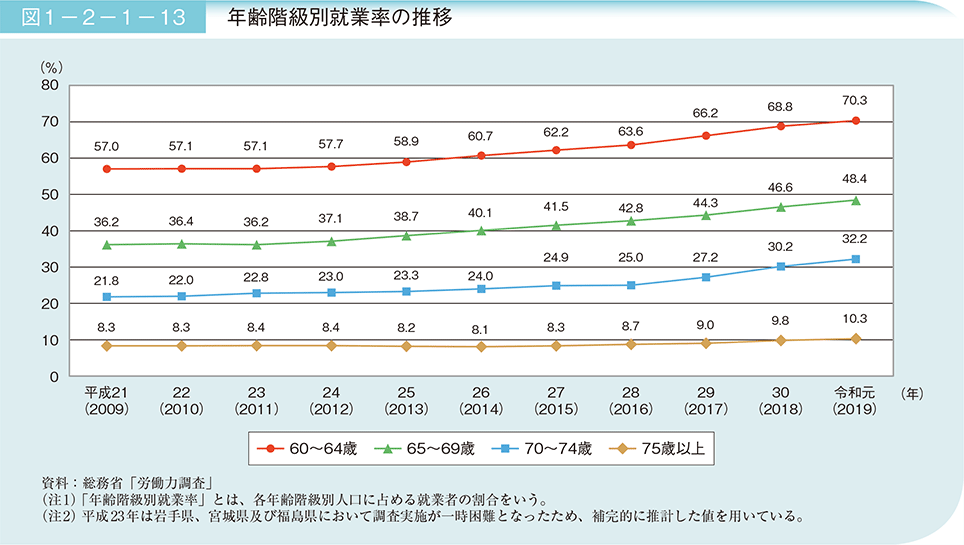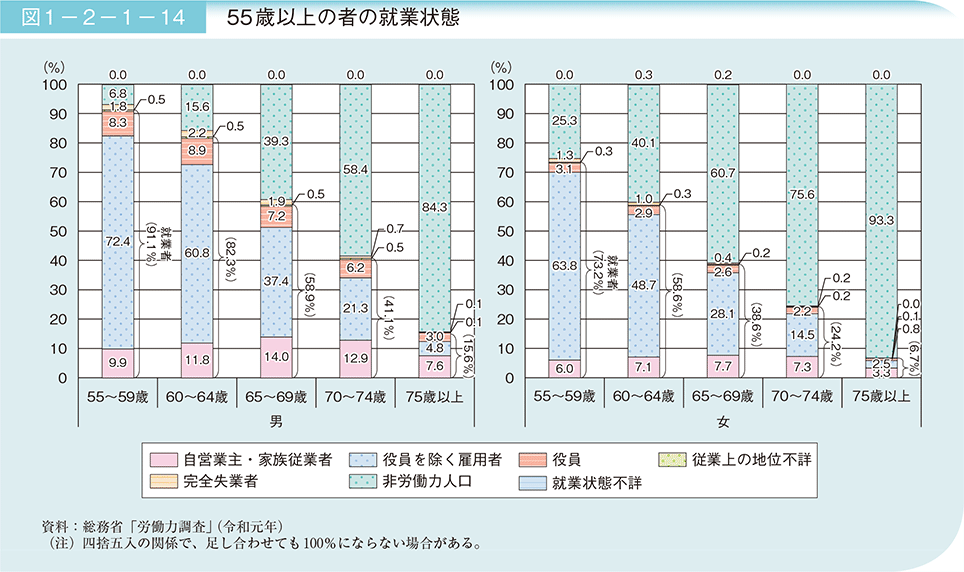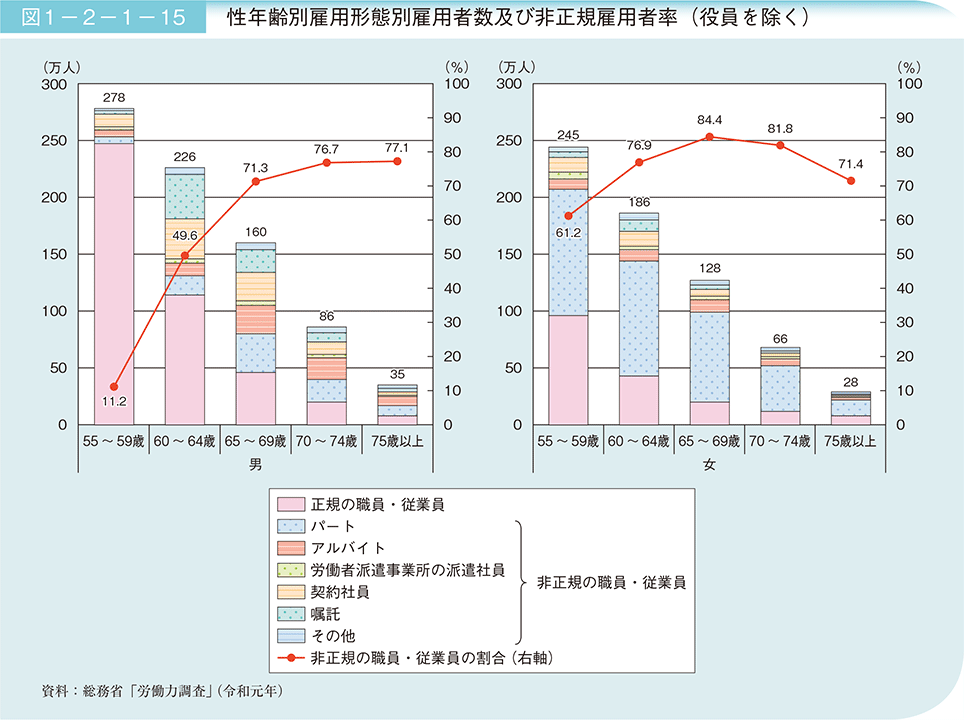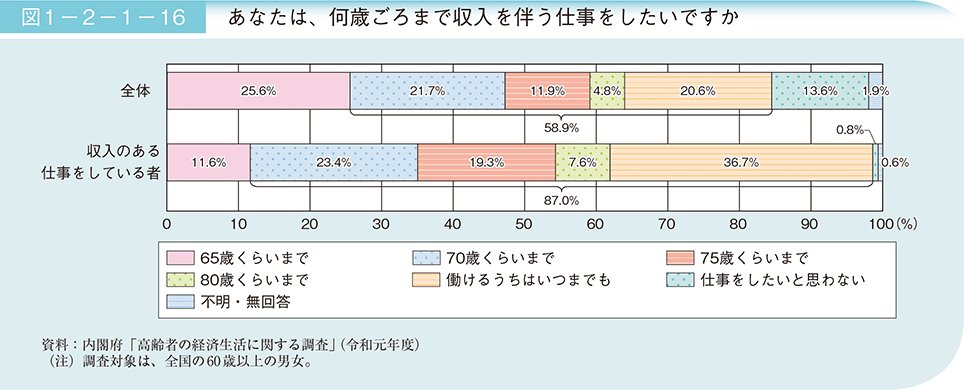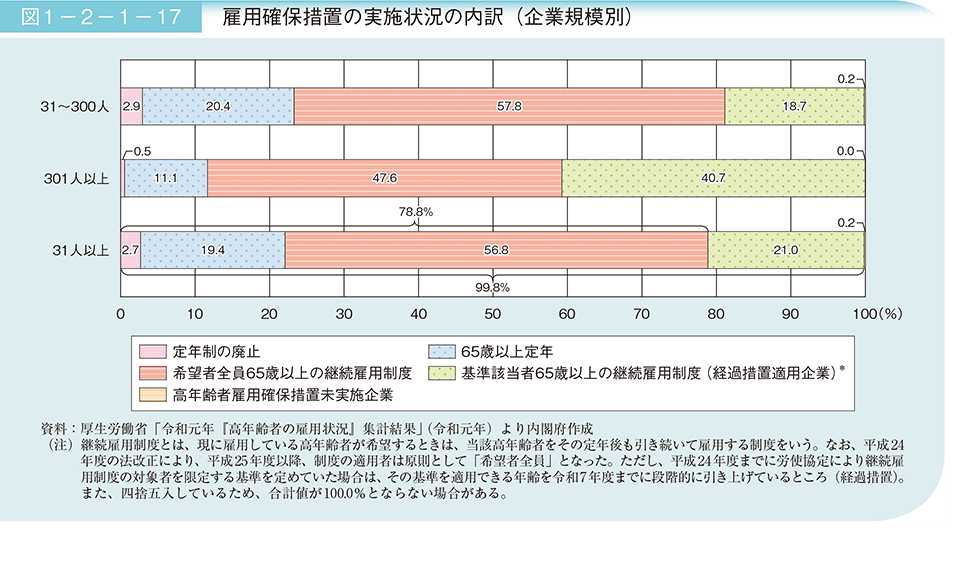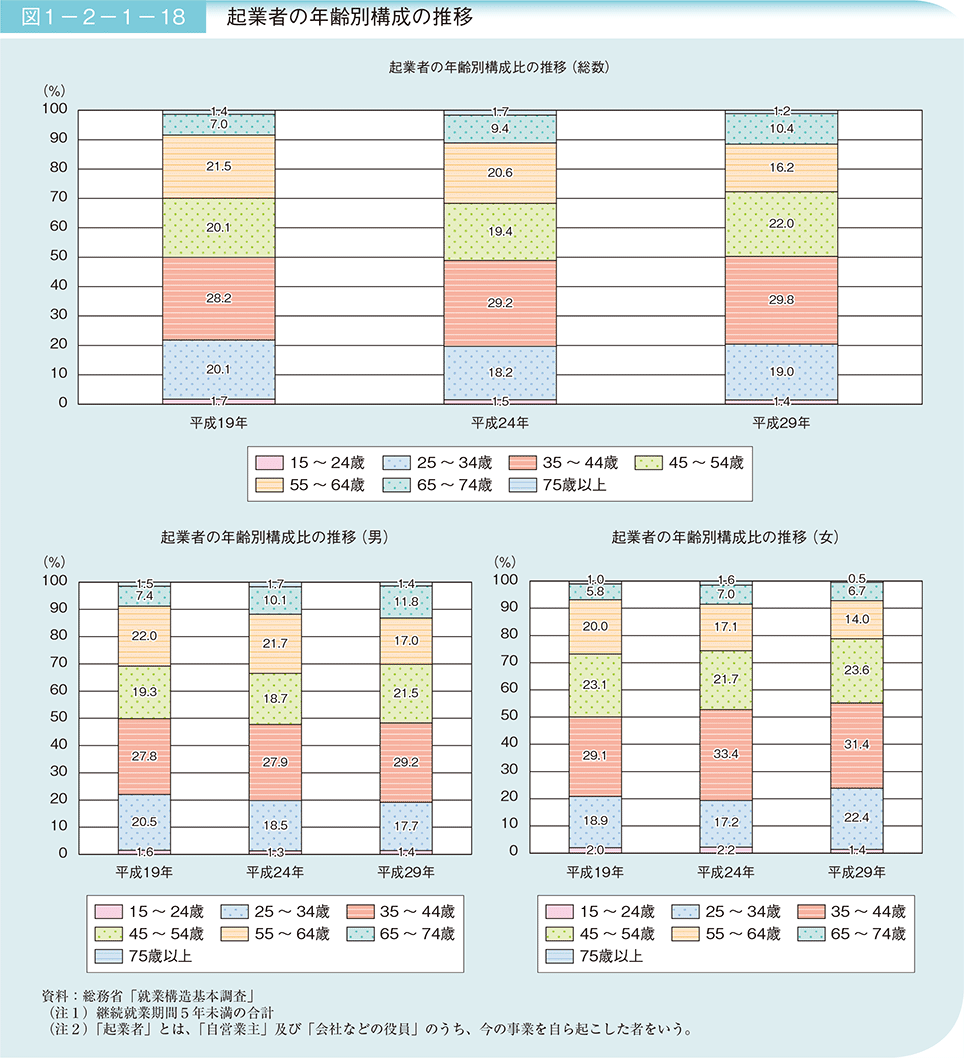第1章 高齢化の状況(第2節 1)
第2節 高齢期の暮らしの動向(1)
1 就業・所得
(1)経済的な暮らし向きに心配ないと感じる60歳以上の者は74.1%
内閣府が60歳以上の者を対象に行った調査では、経済的な暮らし向きについて「心配ない」(「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の計)と感じている人の割合は全体で74.1%となっている。また、年齢階級別に見ると、60~64歳と80歳以上において「心配ない」と回答した割合が高く、特に80歳以上では77.2%となっている(図1-2-1-1)。
(2)高齢者世帯の所得は、その他の世帯平均と比べて低い
高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯)の平均所得金額(平成29(2017)年の1年間の所得)は334.9万円で、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いたその他の世帯(661.0万円)の約5割となっている。
なお、平均所得金額で見るとその他の世帯と高齢者世帯の差は大きいが、世帯人員数が少ない方が生活コストが割高になるといった影響を調整し、世帯人員の平方根で割った平均等価可処分所得3金額で見ると、高齢者世帯は235.2万円となっており、その他の世帯(311.2万円)の約8割となっている(表1-2-1-2)。
| 区分 | 平均所得金額 (平均世帯人員) |
平均等価可処分 所得金額 |
|---|---|---|
| 高齢者世帯 | 334.9万円 (1.57) |
235.2万円 |
| その他の世帯 | 661.0万円 (2.92) |
311.2万円 |
| 全世帯 | 551.6万円 (2.48) |
290.9万円 |
| 資料:厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成30年)(同調査における平成29(2017)年1年間の所得) | ||
| (注1)高齢者世帯とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 | ||
| (注2)等価可処分所得とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整したものをいう。 | ||
| (注3)その他の世帯とは、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いた世帯をいう。 | ||
なお、世帯の可処分所得とは、世帯収入から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入である。
また、高齢者世帯の所得階層別分布を見てみると、150~200万円未満が最も多くなっている(図1-2-1-3)。
さらに、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯について、公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合を見ると、公的年金・恩給が家計収入の全てとなっている世帯が半数以上となっている(図1-2-1-4)。
(3)年齢階級別の所得再分配後の所得格差
世帯員の年齢階級別の等価再分配所得のジニ係数4(不平等度を測る指標)を見ると、平成29(2017)年における60~64歳、65~69歳、70~74歳及び75歳以上の層のジニ係数は、平成17(2005)年と比べてやや低下した。ジニ係数の値は、60~64歳で0.33、65~69歳で0.32、70~74歳で0.30、75歳以上では0.35である(図1-2-1-5)。
(4)世帯主が60歳以上の世帯の貯蓄現在高の中央値は全世帯の1.5倍
資産を二人以上の世帯について見ると、世帯主の年齢階級別の家計の貯蓄・負債の全般的状況は、世帯主の年齢階級が高くなるにつれて、1世帯当たりの純貯蓄はおおむね増加し、世帯主が60~69歳の世帯及び70歳以上の世帯では、他の年齢階級に比べて大きな純貯蓄を有していることが分かる。年齢階級が高くなるほど、貯蓄額と持家率がおおむね増加する一方、世帯主が30~39歳の世帯をピークに負債額は減少していく(図1-2-1-6)。
また、貯蓄現在高について、世帯主の年齢が60歳以上の世帯と全世帯(いずれも二人以上の世帯)の中央値を比較すると、前者は1,515万円と、後者の1,036万円の約1.5倍となっている。貯蓄現在高階級別の世帯分布を見ると、世帯主の年齢が60歳以上の世帯(二人以上の世帯)では、4,000万円以上の貯蓄を有する世帯が16.6%であり、全世帯(11.1%)と比べて高い水準となっている(図1-2-1-7)。
さらに、金融資産の分布状況を世帯主の世代別に見ると、平成元(1989)年では60歳以上が31.9%であったが、平成26(2014)年では64.5%と30ポイント以上上昇している(図1-2-1-8)。
(5)65歳以上の生活保護受給者(被保護人員)は増加傾向
生活保護受給者の推移を見ると、平成29(2017)年における被保護人員数の総数は前年から横ばいとなる中で、65歳以上の生活保護受給者は103万人で、前年(100万人)より増加している。また、65歳以上人口に占める生活保護受給者の割合は2.93%となり、前年(2.89%)より高くなった(図1-2-1-9)。
(6)労働力人口に占める65歳以上の者の比率は上昇
令和元(2019)年の労働力人口は、6,886万人であった。労働力人口のうち65~69歳の者は438万人、70歳以上の者は469万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.2%と上昇し続けている(図1-2-1-10)。
また、令和元(2019)年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)を見ると、65~69歳では49.5%、70~74歳では32.5%となっており、いずれも平成17(2005)年以降、上昇傾向である。75歳以上は10.3%となり、平成27(2015)年以降上昇傾向となっている(図1-2-1-11)。
雇用情勢を見ると、平成20(2008)年から平成22(2010)年は経済情勢の急速な悪化を受けて60~64歳の完全失業率は上昇していたが、平成22(2010)年をピークに低下し、令和元(2019)年の60~64歳の完全失業率は2.4%と、15歳以上の全年齢計(2.4%)と同水準となっている(図1-2-1-12)。
(7)就業状況
ア 年齢階級別の就業率の推移
年齢階級別に就業率の推移を見てみると、60~64歳、65~69歳、70~74歳では、10年前の平成21(2009)年の就業率と比較して、令和元(2019)年の就業率はそれぞれ13.3ポイント、12.2ポイント、10.4ポイント伸びている(図1-2-1-13)。
イ 男性は60代後半でも全体の半数以上が働いている
男女別、年齢階級別に就業状況を見ると、男性の場合、就業者の割合は、55~59歳で91.1%、60~64歳で82.3%、65~69歳で58.9%となっており、60歳を過ぎても、多くの人が就業している。また、女性の就業者の割合は、55~59歳で73.2%、60~64歳で58.6%、65~69歳で38.6%となっている。さらに、70~74歳の男性の就業者の割合は41.1%、女性の就業者の割合は24.2%となっている(図1-2-1-14)。
ウ 60歳を境に非正規の職員・従業員比率は上昇
役員を除く雇用者のうち非正規の職員・従業員の比率を男女別に見ると、男性の場合、非正規の職員・従業員の比率は55~59歳で11.2%であるが、60~64歳で49.6%、65~69歳で71.3%と、60歳を境に大幅に上昇している。一方、女性の場合、同比率は55~59歳で61.2%、60~64歳で76.9%、65~69歳で84.4%となっており、男性と比較して上昇幅は小さいものの、やはり60歳を境に非正規の職員・従業員比率は上昇している(図1-2-1-15)。
エ 「働けるうちはいつまでも」働きたい60歳以上の者が約4割
現在仕事をしている60歳以上の者の約4割が「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答している。70歳くらいまでもしくはそれ以上との回答と合計すれば、約9割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえる(図1-2-1-16)。
オ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業は7割以上
従業員31人以上の企業約16万社のうち、高年齢者雇用確保措置5を実施済みの企業の割合は99.8%(161,117社)となっている。また、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は78.8%(127,213社)となっている(図1-2-1-17)。
カ 65歳以上の起業者の割合は上昇
継続就業期間5年未満の起業者の年齢別構成の推移を見ると、65歳以上の起業者の割合は平成19(2007)年に8.4%であったが、平成29(2017)年は11.6%に上昇した。また、男女別に65歳以上の起業者の割合を見ると、男性は平成19(2007)年8.9%、平成24(2012)年11.8%、平成29(2017)年13.2%と上昇しているが、女性は平成19(2007)年6.8%、平成24(2012)年8.6%、平成29(2017)年7.2%となっている(図1-2-1-18)。