
 |
![]()
交通事故被害者の支援 第3章 交通事故が被害者に与える精神的影響
平成10年に行われた交通事故被害実態調査研究委員会の「交通事故被害実態調査研究報告書」の中から、重傷事故被害者の精神的負担について図-1に示した。
事故後1ヵ月以内で、最も多かったのは「突然に事故のときの光景がよみがえる(49%)」であり、次いで「事故のことについて考え込んでしまう(35%)」、「事故を思い出させるようなものや場所を避けてしまう(31%)」、「また同じ事故にあうのではないかと心配だ(31%)」が多くなっていた。
このことから、事故から1ヵ月以内では事故のことが頭に思い浮かんだり、事故のことが頭から離れなかったりする一方で、そのことを思い出させることを避けるという傾向がみられる。これは後述するASD(急性ストレス障害)やPTSD(心的外傷後ストレス障害)にみられる症状である。
|
図-1 重傷事故被害者の精神的ストレス (交通事故被害実態調査研究委員会編交通事故実態調査研究報告書 平成11年6月)より転載) |
また、このことは事故から間もない時期では、被害者は事故の事実に直面することが難しい状況にあることを示している。この調査では、事故から時間が経っても被害者に精神的影響があることが明らかにされた。
調査時点(事故から1ヵ月以上経過後)で、最も多かったのは「また同じ事故にあうのではないかと心配だ(46%)」、「事故に関わることは考えないようにしている(30%)」であった。事故から時間が経過しても事故への不安や事故のことを考えたくない気持ちがあることが分かる。
また、一般的な精神健康状態を示すGHQ20(一般健康調査票20項目版)において、調査時点における精神健康状態がよくないとされた人の割合は58.0%と高い割合を示していたことからも、事故の影響が継続していることがうかがわれた。このことは精神症状のみにとどまらず、社会活動や対人関係にも影響を与えていた。調査時点での事故後の生活の変化としては「外出する回数が減った(44%)」、「経済的に苦しくなった(24%)」、「趣味や遊びをしなくなった(23%)」、「仕事・学校を休みがちになった(19%)」など、さまざまな影響がみられた。
犯罪や災害、事故などで強い恐怖を体験すると、誰もがさまざまな精神的反応をきたす。そのような場合には精神的反応が一時的なものにとどまらず、後々まで残るようになり、トラウマ(心の傷、心的外傷)を形成する。
トラウマは身体的なケガにたとえると、手足を失ったり、複雑骨折をしたようなもので、日常的な擦り傷と違ってそう簡単に直らないし、後遺症を残すこともある。精神的な後遺症としては、PTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病などがあげられる。
もちろん、すべての交通事故がトラウマとなるわけではない。軽度の接触事故などでは精神的反応が小さく、後遺症なども見られないことが多い。
また、同じ事故でも人によって反応が異なることがある。平気で翌日から車に乗れる人もいれば、恐怖で運転ができなくなったり、交通量の多い道路を歩けなくなる人もいる。
交通事故がトラウマとなるのは、その事故の程度や負傷の程度、状況や被害者の恐怖感など、さまざまな要素が関係してくる。どのような場合に、そのような深い心の傷を残すのかということを以下に示した。
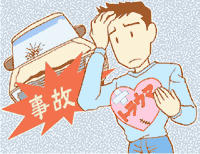
したがって、その交通事故によってひどい負傷をして、生命の危険を感じたような場合にはトラウマになりやすい。また、実際にケガをしなかったり、軽度であっても自分が死ぬのではないかという強い恐怖を味わった場合にも、トラウマになる可能性がある。
その他に、悲惨な事故現場を目撃した人も、その光景が頭に焼き付いて離れなかったり、自分の身に起こったかのように恐怖を感じる場合がある。この中には、救援にきた消防士や警察官も含まれる。家族や恋人など被害者に近い立場にいる人も、被害者が悲惨な目にあったということに直面することによって強い衝撃を受ける。もし、亡くなった場合には突然の死というショックや悲しみ、喪失感を激しく感じるようになる。
このように一つの事故であっても、多くの人々がトラウマになってしまうことが考えられる。ここでは、まず交通事故を直接体験した人の一般的な反応について、時間経過とともに記述する。
図-2に急性期と慢性期にわけて交通事故による精神的反応の全体像を示した。まず大切なことは、多かれ少かれどのようなレベルであれ、なんらかの反応はきたすということである。こういった反応の多くはこのような事故にあった場合の、人間の正常な反応ということができる。ただし、正常と病的の間には明確な線が引けるわけではない。トラウマの正常な反応と病的な反応はその種類が違うというより程度の違いとして表れるものが多い。その症状が強くて、苦痛がひどかったり、社会生活や日常生活に支障をきたすような場合に医療が必要なレベルと判断される。
|
図-2 交通事故による精神的反応の全体像 |
(1) 急性期にみられやすい反応
1) 麻痺、ショック、否認、解離
特に、事故の直後にこのような症状が見られる。被害者は、事故のときは平静だったとか、現実とは思えない、悪い夢を見ているようだ、信じられないというような発言をすることがある。
これはあまりにショックな出来事の際には物事を受け入れられなかったり、感覚や感情の麻痺が起こるためである。これは、耐え難い出来事に対する心の防衛反応の一つと考えられている。また、しばしば「解離」と呼ばれる精神症状が表れることがある。
解離とは、その人の意識や記憶、知覚、自分であるという同一性の感覚など、通常一つの人格として統合されている機能が破綻してしまい、一部が切り離されてしまうものである。例えば、事故についての記憶が失われたり(解離性健忘)、感情が麻痺した感じや現実ではない感じ、実際には事故はなかったように感じるなどの症状として表れる。
特に、事故直後の解離は「トラウマ期解離(peritraumatic dissociation)(Marmar.et al;1994)」と言われ、以下のような症状がみられる。
1) この部分は、「Hickling, E.J.& Blanchard, E.B. eds. 『Road Traffic Accidents & Psychologocal Trauma』 Elsvier Science Ltd, 1999」と、「厚生労働省 精神・神経疾患研究委託費外傷性ストレス関連障害の病態と治療ガイドラインに関する研究班 主任研究者 金吉晴 編集『心的トラウマの理解とケア』、じほう、2001」によっている。

このような症状は一過性であることが多いが、長期化する場合もある。解離が出現するのは、事故の程度がひどい場合が多い。また、急性期に解離がみられた人では、その後PTSDを発症する率が高いといわれている。
こういう時の被害者は、ボーっとして見えたり、表情がなく、話しかけられてもきちんとした応答ができないこともある。他方、一見非常に落ち着いて見え、テキパキと対応する被害者や遺族もいる。これは、実際にはショックで感情が麻痺しているためなのだが、しばしば周囲からは"冷たい"あるいは"しっかりしているから大丈夫"と誤解され、ケアされなかったり、非難されて二次被害となることもある。
感覚の麻痺が起こると、痛覚を感じにくいことがあり、ケガをしていてもあまり痛みを訴えないことがある。空腹や寒さなどに対する感覚も鈍くなり、ほとんど食事をとらなかったり、寒いのに薄着のままでいたりするので、周囲が気をつけてあげる必要がある。
2) 恐怖感
事故を実感した際に出現する。恐怖とともに動悸、呼吸が速くなる。手足の冷感、冷や汗などの交感神経系の興奮状態もしばしば体験される。
3) 抑うつ
抑うつは、何かを失った場合によくみられる反応である。事故にあうことによって、体の一部や健康、車、順調な社会生活など、さまざまなものが失われ、それに対して抑うつ反応が起こることが考えられる。
4) 高揚
そう多く見られる反応ではないが、まれに重大な事故から助かった安堵感や生理学的な反応の一環として表れることがある。非常に高揚した状態で動き回ったり、多弁になったりする。ときに驚異的なまでの痛みの耐性を示すことがある。
5) 怒り
被害者が怒りを感じるのはよくあることである。自分がなぜ事故にあったのかという説明のつけようのない事態に対して、発生してくるものである。事故の相手に対して向けられることもあるが、しばしば救援者や家族などに向けられることがある。周囲の対応が悪いという形で向けられることが多い。周囲の人がその怒りを理不尽だと感じる場合には、被害者の孤立を招くことにもなる。
6) 無力感
被害者は突然、自分ではどうしようもない状況――生きるか死ぬか、ケガをするかどうか――におかれることによって、自分のコントロール感を失い無力感を感じる。特に、入院して医療専門家にすべてをゆだねないといけないような状況があるとそれが強められる。
7) 罪悪感、自責感
事故に対して、自分に過失責任がある場合や、同乗者も含めケガ人や死者が発生すると、自分に責任があると強く思い、自分を責めることが多い。これは特に自分にはっきりした責任がない場合でも自分に何か問題があったのではとか、あるいは事故を回避できたのではと思い、自責感を持つこともある。
これは実際の過失や責任とは釣り合わない、過剰な自責感である。子どもの場合には、しばしば「自分が悪い子だったから事故が起こった」などの形で自分を責めることがある。
8) 焦燥感
事故によって神経が興奮することや、身体の回復や保障などが思うようにいかないことによって、イライラ感がつのることがある。家族や友人に当たってしまったりするため、人間関係に悪い影響を与えてしまう。また、相談の際には、攻撃的な人格と思われてしまい、相談者との関係に悪影響が出ることも懸念される。

9) 知覚・認知の変化
時間や出来事の内容、記憶などが誤って認識されることがある。特に突然の悲惨な事故の場合にみられる。時間の感覚が変わってしまうため、事故をゆっくりに感じたり、とても長い時間が経過していたと感じるなどである。また、トンネルビジョンといわれる、出来事のある部分だけを詳しく覚えていて、その他のことを覚えていないというような現象も発生する。
直後は事故のことを覚えていたのに、救急搬送後には覚えていなかったり、そのときには話を聞いて了解していたようなのに、あとで「聞いていない」というなど記憶が不明確なことがある。このように事故の直後の記憶や体験には、しばしば認知の歪みが生ずるといわれている。
10) 睡眠の障害
自律神経の過覚醒状態から生じるもので、寝つきにくかったり、途中で目が覚めてしまったり、深い睡眠がとれないという症状である。また、悪夢や事故のフラッシュバックによっても睡眠が障害されることもある。フラッシュバックが怖くて、寝ることを恐れる被害者もいる。
11) フラッシュバック
これは通常の記憶とは異なるもので、事故のときの情景やそれに関する強く印象づけられた光景がありありと思い出され、あたかも事故のときに戻ったような感じがするものである。
その情景が目に浮かんだり、そのときの音や臭いがするなどの幻覚を体験する場合もある。そのときの恐怖やさまざまな身体反応もよみがえり、被害者にとっては事故を再体験するようなものであるため、極めて苦痛な症状である。これは何のきっかけもなく生ずることもあるが、特に事故を思い出させるような状況に出会ったときに起こりやすい。
12) 過覚醒
事故のあと、自律神経(主に交感神経)が過剰に興奮している状態が続くことが多い。ときには数週間から数ヵ月続く場合もある。睡眠障害のほか、イライラ感や集中力のなさが出現する。
また、ちょっとした音に過剰に驚いたりすることもある。特に交通事故の被害者では、急ブレーキの音、クラクション、衝突音、対向車などに対して過剰に反応する場合が多い。
13) 回避行動
被害者は事故を思い出させるものを避けたり、話たがらなくなる。事故直後は割に話をするが、時間が経つにつれて話さなくなる。事故のニュースを見たくないので、新聞を読まない、テレビのニュースを見ないということも多い。
また、事故現場を通ることや車に乗ること、運転などをしなくなるため社会生活に支障をきたすこともある。損害賠償などの手続きも事故を思い出すのが嫌で取り掛かれなくなり、保険会社からの連絡を待つだけだったり、書類をなかなか書けないなどのために、きちんとした賠償を受けられないような問題が生ずる場合もある。
14) アルコールや薬物の依存
アルコールを飲むと不眠が改善されたり、思い出した時の苦痛が柔らぐため、飲酒量が増える場合がある。しかし、アルコールによる症状の改善は一時的なものに過ぎず、アルコール依存症という新たな問題を抱えることになってしまう。
また、医療機関で睡眠薬や抗不安薬を安易に処方されることによって、これらの薬物の依存が起こる場合もある。

(2) 慢性期にみられる反応
前述した反応が慢性化することのほかに、症状や問題が長期化することによって、以下のような反応が表面化してくる。
1) 世界、自分、他人についての見方(認知)の変化
バルマン(1989)は、「われわれは物事が悪くなるのではという考えに縛られずに生きていけるように、数多くの世界観を共有している」と言っている。例えば、「世界は(自分にとって)優しい(ひどいことはめったに起こらない)」、「世界には意味がある(大体のことは予測ができ、無差別に起こるものではない)」、「人は公正な寛大さを持っている(人は公正であり、ひどいことはしない)」などの世界観を持っているので、安心して毎日を生きていけるわけだが、交通事故のようなトラウマにあうとこれが一変してしまう。
もはや世界は安全な場所ではなく、いつ危険がふりかかるか分からない、車やドライバーは信用してはいけない、われわれは脆弱で危険を負っていると感じるようになる。被害者は安心して外出したり、車に乗ったり、自信を持ったり、人を信用することが困難になるだろう。
そのことによって、今までのような自由で、自信に満ちた社会生活がおくれなくなり、仕事や対人関係に多大な支障を生ずることになる。
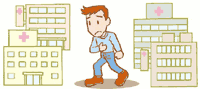
2) 身体的後遺症や身体的障害に対する不安
身体的障害を負った人では、その回復が大きな問題となる。回復しないのではないかとか、後遺症が残ることなどに強い不安を感じている。また、回復が思うようにいかなかったりすることで苛立ちや怒りが生じ、医療関係者の対応や治療についての不満という形で表れることもある。
さらに、はっきりとした診断はつかないものの頭痛やめまい、疲労感、胃腸障害、身体の痛みなどのさまざまな身体愁訴に悩まされることもある。このような状態があると自分の状態を理解してくれたり、治療を行ってくれる医療機関を探し回る、いわゆる"ドクター・ショッピング"を行うこともある。
自分の苦痛を訴えても周囲から理解されず、気のせいだとか、その人の人格に問題があるような扱われ方をされてしまうこともあり、不信感をつのらせることになる。あくまでも客観的診断のみで判断するのではなく、本人には苦痛であるという理解が必要であろう。また、後遺症が残っているといつまでも事故を思い出すきっかけとなり、精神的な回復に影響を与える。
(1) 心的外傷後ストレス障害(Posttraumatic Stress Disorder: PTSD)
PTSDは、トラウマ後の精神疾患として最も有名なものである。1980年にアメリカ精神医学会が出版した精神科診断マニュアルである「DSM-III」にはじめて取りあげられ、その後、改定を経て現在の「DSM-IV」の診断基準が広く用いられている。ここでも「DSM-IV」の診断基準を取りあげた。なお、精神医療ではWHOが示している診断基準「ICD-10」もよく用いられているが、PTSDに関しては両者に大きな差はない。DSM-IVの診断基準を、下記に示した。
A.その人は、以下の2つが共に認められる外傷的な出来事に暴露されたことがある。
| (1) | 実際にまたは危うく死ぬまたは重症を負うような出来事を、1度または数度、または自分または他人の身体の保全に迫る危険を、その人が体験し、目撃し、または直面した。 |
| (2) | その人の反応は強い恐怖、無力感または戦慄に関するものである。 注:子供の場合はむしろ、まとまりのないまたは興奮した行動によって表現されることがある。 |
B.外傷的な出来事が、以下の1つ(またはそれ以上)の形で再体験され続けている。
| (1) | 出来事の反復的で侵入的で苦痛な想起で、それは心像、思考、または知覚を含む。 注:小さい子供の場合、外傷の主題または側面を表現する遊びを繰り返すことがある。 |
| (2) | 出来事についての反復的で苦痛な夢。 注:子供の場合は、はっきりとした内容のない恐ろしい夢であることがある。 |
| (3) | 外傷的な出来事が再び起こっているかのように行動したり、感じたりする(その体験を再体験する感覚、錯覚、幻覚、および解離性フラッシュバックのエピソードを含む、また、覚醒時または中毒時に起こるものを含む)。 注:小さい子供の場合、外傷特異的な再演が行われることがある。 |
| (4) | 外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけに暴露された場合に生じる、強い心理的苦痛。 |
| (5) | 外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的きっかけに暴露された場合の生理学的反応性。 |
C.以下の3つ(またはそれ以上)によって示される(外傷以前には存在していなかった)外傷と関連した刺激の持続的回避と、全般的反応性の麻痺。
| (1) | 外傷と関連した思考、感情、または会話を回避しようとする努力。 |
| (2) | 外傷を想起させる活動、場所または人物を避けようとする努力。 |
| (3) | 外傷の重要な側面の想起不能。 |
| (4) | 重要な活動への関心または参加の著しい減退。 |
| (5) | 他の人から孤立している、または疎遠になっているという感覚。 |
| (6) | 感情の範囲の縮小(例:愛の感情を持つことができない)。 |
| (7) | 未来が短縮した感覚(例:仕事、結婚、子供、または正常な一生を期待しない)。 |
D.(外傷以前には存在していなかった)持続的な覚醒亢進状態で、以下の2つ(またはそれ以上)によって示される。
| (1) | 入眠、または睡眠維持の困難。 |
| (2) | 易刺激性または怒りの爆発。 |
| (3) | 集中困難 |
| (4) | 過度の警戒心 |
| (5) | 過剰な驚愕反応 |
E.障害(基準B、C、およびDの症状)の持続期間が1ヵ月以上。
F.障害は、臨床上著しい苦痛または、社会的、職業的または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。
■ 該当すれば特定せよ:
急性 症状の持続期間が3ヵ月未満の場合
慢性 症状の持続期間が3ヵ月以上の場合
■該当すれば特定せよ:
発症遅延 症状の始まりがストレス因子から少なくとも6ヵ月の場合
出典:高橋三郎、大野 裕、染谷俊幸 訳「DSM-IV 精神疾患の診断・統計マニュアル」医学書院、1996
1) 出来事の性質(A基準)
PTSDの診断で重要なのは、A基準にみられるように、体験した出来事がPTSDを引き起こすのに、十分な出来事であったかどうかということである。
一つは客観的にみてその出来事が生命の危機をもたらしたり、あるいはもたらすような出来事であったということである。さらにそのことに遭遇した際に、本人が強い恐怖や無力感を感じるという主観的要素が必要になる。つまり、いかに本人が恐怖を感じたとしても、あまりに軽微な出来事であったり、逆に他人から見てひどい事故であっても、本人が全く事故によって恐怖を感じないというようなことがあればPTSDの診断がつかないという可能性がある。
PTSDは、どんなひどい事故でも100%の人が同じように発症するということはまずありえないものであり、そこにはそのときの事故の状況や個人的要素(年齢、性別、成育歴、現在のストレス)などが関係する。事故が悲惨で深刻であるほど、あまり個体差なく発症し、事故の程度が弱くなるほど個体の要因が大きくなるといわれている。
A基準を満たすような出来事であった場合に、B、C、Dの3種類の症状がみられ、なおそれが1ヵ月を超えて続く場合に、PTSDの診断がつけられる。このように診断は操作的なものであり、PTSDの診断がつかないからといって、その人の症状がないということでも、問題がないということでもない。これはあくまでも精神科における線引きでしかないことを理解する必要がある。
また、損害賠償の請求などでも、近年PTSDが取りあげられることが多いが、PTSDの症状の持続期間は最低1ヵ月であることから、事故から1ヵ月経たないうちにPTSDの診断がつくということはないということは重要である。
2) PTSD 3つの症状
i.侵入・再体験(B基準)
通常、被害者にとって事故の記憶は最も思い出したくないものであるが、その記憶がかってによみがえってしまう症状である。しかも通常の記憶と異なり、大変生々しくそのときの光景が浮かんだり、音や臭いがするなど幻覚が起こることもある。
そのため、思い出すとそのときの恐怖も再現されてしまい、動悸がしたり、呼吸が速くなったり、冷や汗をかいたりする。特に、今いる現実の状況から離れてしまい、あたかもその事故のときの状態に戻ってしまったようになる場合には(解離性)フラッシュバックと呼ばれている。
この記憶の想起は、本人の意思と関係なく起こるために「侵入的」であるといわれる。また、これらの記憶は思い出しても言葉にすることが難しく、被害者はその場で固まってしまったり、気分が悪くなったり、そこにいられなくなったりという行動で示すことがある。
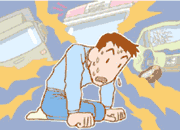
このようなトラウマによる記憶は、通常の記憶とは異なったメカニズムで処理されているため、日常生活の出来事のように思いだして話はできるが、別に生々しくはないという形には中々ならず、いつまでも鮮やかに残ってしまい、思いだすたびにそのときの苦痛が再現されることから「再体験」症状とされている。
この症状があると、被害者にとっていつまでも事件が過去のことにならず、現在の問題として体験され続けることになってしまう。
思い出すきっかけは特にない場合もあるが、事件に関連した出来事(事故現場を通る、車に乗る、救急車のサイレン、事故のニュース)などに接すると思い出す場合が多い。このきっかけは人によりさまざまで、その人が事故のときに強く記憶した出来事などに関係している。
人によっては、日中あまり思い出さないが、夜非常にリアルな悪夢として繰り返し見る人もいて、その場合には寝ることを苦痛と感じる。また、子どもの場合は、事故自体の意味がよく分かっていなかったり、言語表現が未熟なため、大人の症状とは異なっている。年少児や学童児では「ポスト・トラウマティックプレイ」と呼ばれる遊びの中で、事故を再現するようなことがみられる。例えば、ミニカーのおもちゃをぶつけるなどがそうである。プレイと呼ばれているが、遊びの楽しさはなく、子どもは取りつかれたような顔をして繰り返し行っていることが多く、言葉にできない記憶の再現を遊びの形にして表現しているといわれている。
[事例1]
車が大破する交通事故を経験した女性。本人のケガは軽度であったが、車が大きな音をたてて壊れ、やっと這い出てきた。それ以降、車に乗っていて対向車が向かってくると、「ボンッ」というそのときの音が聞こえて恐怖にすくんでしまう。怖いので車に乗ることができない。
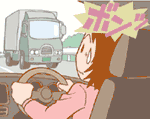
ii.回避・麻痺(C基準)
記憶が再現されることは、被害者にとって極めて苦痛なため、被害者は思いだすことを可能なかぎり避けようとする。その結果起こってくることが、回避反応や麻痺反応である。
例えば、被害者はできるだけ事故やそれに関係することを考えないようにしたり、話さないようにする。関連する出来事に直面することを避けたいと思うので、事故の処理を避けがちになる。警察で事情聴取を受けたり、現場検証をしなくてはならないのに、その連絡をしたがらなかったり、行くことを避けたりということがある。
損害賠償の手続きに関しても同様のことが起こる。賠償の請求をしたいと思っても、その書類を見ることや電話をすることさえも苦痛で、延ばし延ばしになってしまい手続きが遅れたり、十分な交渉ができないという問題が生ずる。あまりに連絡を取りたがらないと、熱心ではないと思われたり、相手側の意見ばかりで物事が決定されてしまう危険がある。保険業務に関わる人は、被害者がこのような症状から手続きが中々できないという問題を理解し、できるだけ分かりやすく負担のない形で交渉や手続きが行えるよう働きかける必要がある。
また、事件に関連する状況を避けると、社会的にさまざまな問題が起こってくることがある。事故現場を避けるということはよく見られるが、それが通勤途中であった場合には、通勤ルートを変えなくてはならず、費用や時間がかかったりする。車に乗ることや運転することの恐怖があると、通勤や子どもの送り迎え、日常生活などに多大な支障を生ずる。
さらに、道路や車を見ることが怖くなると外出困難をきたしてしまう。加害者への不信感から加害者に似ている人を避けるようになると、人のいるところへ行きたくないというところまで発展することがある。
このような意識レベルのものだけでなく、もっと心理的防衛機制として表れる症状もある。あまりにも辛い体験を思いださないですむように、事故のときの記憶が失われたり(健忘)、今まで興味を持っていた社会活動への関心が失われたり、他人から孤立しているように感じたり、感情の麻痺が起こる。感情の麻痺が起こると、苦痛な感情だけでなく、喜びや愛情といった感情もあまり感じなくなるために、何をしてもおもしろくない、生き生きとした現実感を感じないということが起こる。
事故によって、過去とのつながりが途切れたようになったり、将来に対して希望や計画を持てないことから、自分は早死にするという確信をもつ人もいる。
[事例2]
自分が車を運転していて対向車がぶつかり、重傷を負った男性。車には何とか乗れたものの、対向車が向かってくると事故を思い出してパニックになってしまう。交通量の多い通りを避けていくため、通勤に非常に時間がかかるようになってしまった。
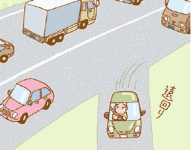
iii.過覚醒(基準D)
強い衝撃を受けると生理学的な変化が生ずる。動物や人間が襲われるような恐怖を体験すると「闘争か、逃走」反応が起こり、身体にアドレナリンというホルモンが多量に放出され、自律神経の一つである交感神経が過剰に興奮した状態が作られる。
この交感神経が興奮すると、動悸、発汗、過呼吸、手足の冷感、不安感などが生ずる。通常、これらの反応はその原因がなくなると消失するものであるが、トラウマ体験後では長期に持続することがあり、覚醒が亢進(こうしん)した状態(神経が敏感になっている状態)がみられる。
このような状態が続くと、不眠(寝つきが悪い、何度も目を覚ます)、イライラしてちょっとしたことで怒りが爆発する、仕事や本を読むことに集中できない、たえずあたりに気を配る、ちょっとした物音に飛びあがるように驚く、などの症状が続くことになる。イライラして家族にあたったりするため家族関係が悪くなったり、仕事や学業の機能が低下するなど、対人関係や社会生活への影響が表れる。また、たえずびくびくしている感じは自分が弱くなったように思われ、被害者の自信を失わせる要因になる。
PTSDの診断は上記の3つの症状を満たし、1ヵ月以上持続し、被害者が苦痛を感じ、社会的機能の障害などが発生している場合に行われる。
診断は、精神科医によってDSM-IVやICD-10に準拠した形でつけられるべきである。PTSDが疑れる症状、あるいはその一部の症状があるとしても、賠償請求などで正確な診断を必要とされる場合には、診断の根拠がはっきりと示される形で行われていることが求められるであろう。
PTSDの診断については、スクリーニングとしては項目数が少なく、簡易に評価できる「改訂 出来事インパクト尺度(IES-R:The Impact Event Scale-Revised 2))が便利であるが、正確に行うためにはPTSD臨床診断面接尺度(CAPS:Clinician- Administered PTSD Scale)と呼ばれる構造化面接などを用いることが勧められる。
2) IES-Rは、WeissとMarmarらによって作成されたものであるが、飛鳥井らによる日本語版がある。「厚生労働省 精神・神経疾患研究委託費外傷性ストレス関連障害の病態と治療ガイドラインに関する研究班 主任研究者 金吉晴 編集『心的トラウマの理解とケア』、じほう、2001」を参照されたい。

PTSDは、トラウマを受けたすべての人に発生するわけではない。交通事故でも同様である。
交通事故によるPTSDの有病率は、欧米の追跡研究(交通事故にあった人がPTSDを発症するかどうかの経過を追った研究)によると8%から50%であり、研究によってばらつきがみられるが、事故から1年以上経過した事例においては10〜20%前後という研究が多い。日本の研究では、重傷事故の被害者については横断調査において再体験症状が30%、回避症状が25%、覚醒亢進が9%、反応性の麻痺が15%という報告があり、やはり10〜30%くらいの発症が推測される。
どういう場合にPTSDになりやすいか(予測・危険因子)ということでは、
ことなどが有力な因子としてあげられている。
そのほかにも過去にトラウマ体験があること、うつや不安障害などの精神疾患の既往歴があることなどを取り上げる研究もあるが、一定していない。身体疾患の重症度とPTSDの発症率は一致しておらず、むしろ精神的な脅威の体験のほうの強く影響する、とする報告が多い。
このことは被害者の訴えを聞くうえで重要である。客観的には比較的軽症であったとしても、事故の状況によっては被害者が強い恐怖を感じることがあり、その場合にはPTSDをはじめとする精神的後遺症が発生しうることを示しており、ケガが軽度であるからといって、被害者の精神的苦痛の訴えを軽視するということがないようにすることが大切である。

(2) 急性ストレス障害:Acute Stress Disorder(ASD)
トラウマとなる出来事から1ヵ月以内に生じる特徴的な不安、解離などの症状が2日以上続く場合には急性ストレス障害と診断される。急性ストレス障害は4つの症状があり、そのうち3つはPTSDとほぼ同じ、侵入・再体験、回避、過覚醒の症状であるが、それに加えて解離性の症状があることが特徴である。ここでの解離性の症状は、自分で生き生きとした感情が感じられないという感覚や、以前楽しめていたことで喜びを感じることが困難になるという感情の麻痺や、ぼうっとしていて集中力がないという感じ、自分が自分の体から離れているような感覚、何か生きている世界が現実のものと感じにくい感覚、事故のことなどの詳細が思いだせないなどの症状である。
ASDがある場合に必ず、PTSDを発症するわけではないが、ASDを発症した患者ではPTSDの発症が高率であるという研究報告があるので、初期にこのような症状を呈する場合には、経過を注意深く追う必要がある。
1) うつ病
うつ病は、交通事故に限らず、トラウマを受けた人に発生しやすい精神疾患である。うつ病は、一般的には喪失体験や人生の変化をきっかけで発症するが、交通事故はどちらの条件も満たしている。事故によって今までの人生が大きく変化するとともに、健康や今までもっていた安心感、平穏な日常、金銭、車といったさまざまな喪失体験をすることになる。また、事故に対する不安などの心労からくる精神疲労の影響もあるであろう。
うつ病になると、以下のような症状が表れてくる
上記のような症状のために、仕事をしたり、人と交わることが困難になると、職場に行けなくなったり、外出せず引きこもりがちになる。人と疎遠な感じや感情の鈍磨、集中力の低下などはPTSDでも見られる症状のため、PTSDが合併している人では見過ごされてしまう場合がある。重症の場合には、自殺念慮や自殺企図という問題が起こるため、治療が必要である。
交通事故における抑うつ(調査時点でうつ状態をきたしている)の有病率は、研究報告からみると23%から67%であり、かなり多くの人に見られることが分かる。
2) 運転恐怖症
交通事故にあうと、また事故にあうのではないか、あるいは自分が事故を起こすのではないかという不安や、PTSDの症状として車に乗ることがきっかけで、事故を思い出したりすることから、運転や車に乗ることに対して恐怖感を抱き、避けるようになることがしばしばみられる。
症状の程度は、運転はできるが、事故現場を通れないなどの制限があったり、通勤や買い物など止むを得ない場合しか乗らなくなったり、ひどい場合には全く運転できない、あるいは車に乗ることさえもできないというレベルまで、様々である。
運転恐怖症については、どの程度のものまでを含むかという問題もあり、事故者の2%から47%というかなりばらつきのある結果となっている。このような運転恐怖があると、社会生活に支障をきたすというだけでなく、車の運転というスキルを失うことで、自信の喪失という問題も生ずる。
3) パニック障害
パニック障害は、強い不安や恐怖とともに突然、動悸、発汗、息苦しさなどの症状が発作的に出現し、患者は「自分は死ぬのではないか」あるいは「どうしていいか分からない」という状態を感じる。過呼吸発作を伴うこともある。
実際に身体的な異常はないのだが、精神的に苦痛な体験であり、またこの発作が起こるのではという恐怖から、きっかけになる状況を避けたり、外出できなくなったりするものである。PTSDではしばしばパニック障害の合併がみられ、苦痛な体験の想起に伴ってパニック発作が出現することがある。
![]()