特集 「交通安全対策の歩み~交通事故のない社会を目指して~」
第3章 終わりに
特集 「交通安全対策の歩み~交通事故のない社会を目指して~」
第3章 終わりに
第1章,第2章においては,平成の30年間を中心に,交通事故と道路交通安全の取組の流れを「人」「車両」「道路」及び「救急」について記述してきた。以上を踏まえ,将来に向けて,外国人の増加,及びさらなる高齢化についてとりあげる。
1 外国人の増加と交通安全
(1)一層の増加が見込まれる外国人
平成29年の訪日外国人旅行者数は,15年のビジット・ジャパン・キャンペーン開始以来増加を続け,2,869万人(対前年比19.3%増)と,元年の約284万人と比べると約10倍となった。平成30年は,3,119万人と(暫定値),初めて3千万人を超え,今後も,東京オリンピック・パラリンピック競技大会,大阪・関西万博などが控えており,更なる増加が見込まれる。
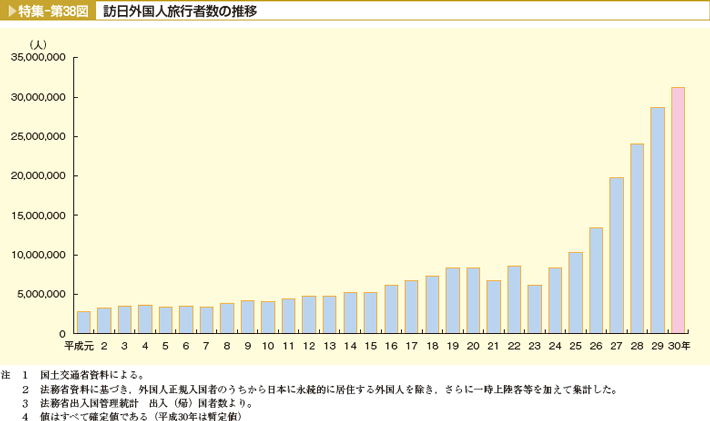
また,平成30年10月末現在,外国人労働者数は146万463人で,前年同期比で14.2%(18万1,793人)増加し,19年に届出が義務化されて以降,過去最高を更新し,平成後期の10年間(20年から30年)で97万人増加した。背景としては,政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れ,雇用情勢の改善による「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格のある者の就労,技能実習生の受入れが各々進展していることなどが考えられる。
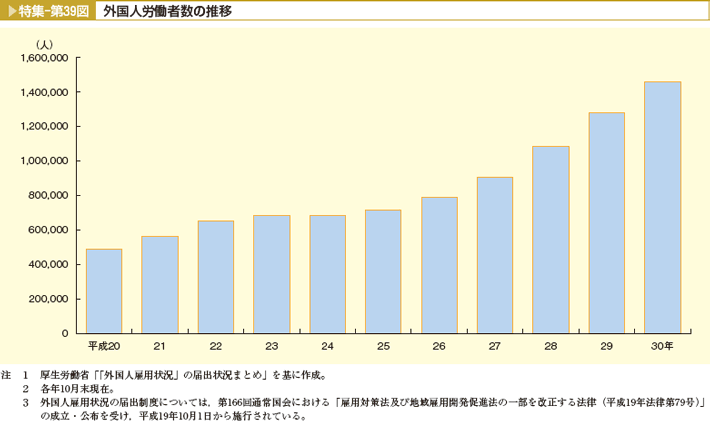
(2)外国人の運転と事故の現状
外国人による運転については,在留外国人等の外国籍運転免許保有者が運転する場合,訪日外国人観光客がレンタカーなどを運転する場合などがある。
外国籍運転者による交通事故は5年間で1.5倍に
外国籍運転免許保有者数は,平成21年から30年の間に25%増加し,30年に90万7,086人となっている(特集-第40図))。
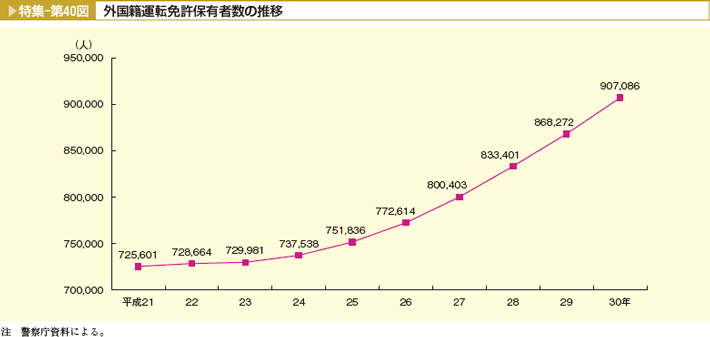
外国籍運転者(第1当事者)による交通事故件数は,平成26年6,672件に対し,30年6,710件とほぼ横ばいであるが,そのうち国際免許又は外国免許取得者による交通事故件数は,26年の180件に対し,30年280件と,5年間で約1.6倍となった(特集-第41図)。
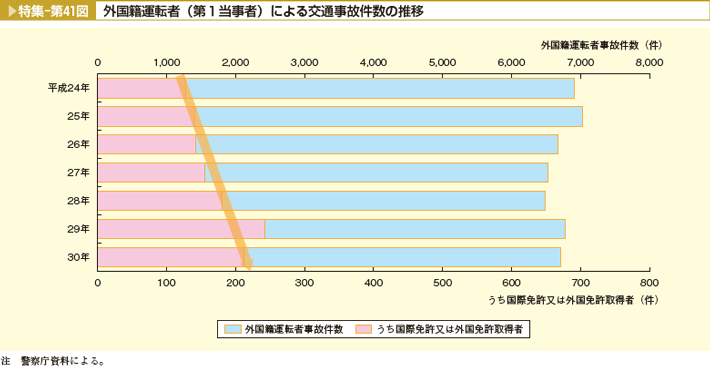
外国人レンタカー運転者による交通事故は2.3倍に
一方,訪日外国人の観光客の増加に伴い,レンタカーを利用する訪日外国人は,平成23年から29年までの7年間で約8倍増加し,約140万人となった(特集-第42図)。
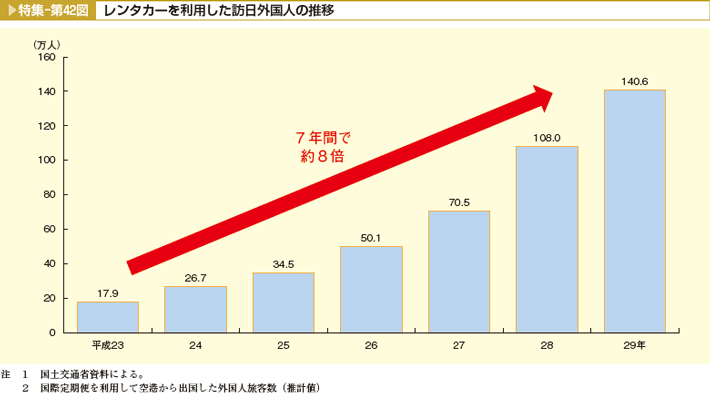
レンタカー運転者(第1当事者)による交通事故件数は,全体としては減少傾向にあるが(平成26年6,366件→29年5,913件,7.1%減),外国人(日本国籍以外で国際免許又は外国免許取得者)運転者による交通事故件数は,26年の68件に対し,30年158件と,5年間で2.3倍に増加した(特集-第43図)。
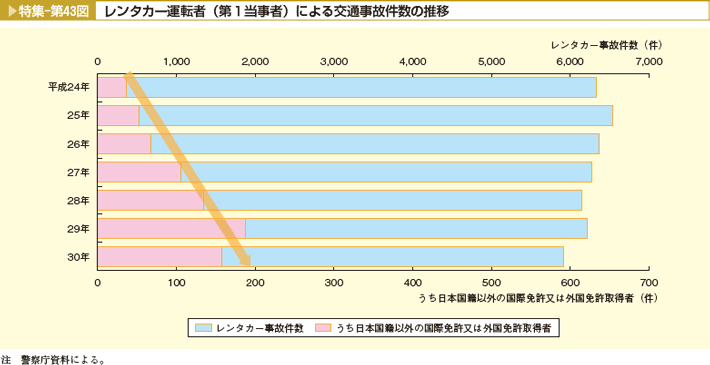
(3)多様化する運転者と交通安全に関わる対策
急増する訪日外国人観光客のレンタカー利用による事故を防止するため,各種対策を推進している。
外国人運転者にも分かりやすい道路標識の整備
訪日外国人が増加する中,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も控え,国民と訪日外国人の双方にとって分かりやすい道路標識を整備するため,平成29年4月,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭35総理府・建設省令3)の一部が改正され,同年7月に施行された。この改正により,規制標識「一時停止」について,「止まれ」という日本字の下に「STOP」という英字を併記した様式が,規制標識「徐行」及び「前方優先道路」について,「徐行」という日本字の下に「SLOW」という英字を併記した様式が,それぞれ追加された。
訪日外国人観光客レンタカー事故対策
日本を訪れる外国人が安全に我が国で自動車等を運転するためには,右側通行と左側通行の違いを始め,日本の交通ルール,交通事情等を周知することが重要である。警察庁では,一般社団法人全国レンタカー協会による外国語(英語,韓国語,中国語(簡字体・繁字体))のリーフレットの作成に協力するなどしている。また,同協会は,外国人が運転していることを周囲のドライバーに示す,専用ステッカー作成の取組を行っている。
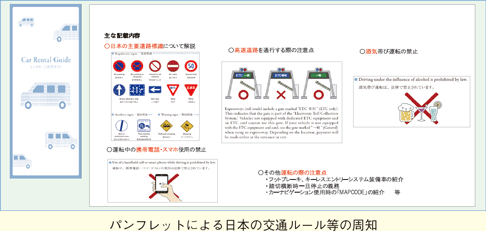

訪日外国人レンタカーピンポイント事故対策
国土交通省では,急増する訪日外国人観光客のレンタカー利用による事故を防止するため,レンタカー事業者や警察,観光部局と連携しながら,ETC2.0の急ブレーキデータ等を活用して,外国人特有の事故危険箇所を特定し,ピンポイント事故対策を講じている。
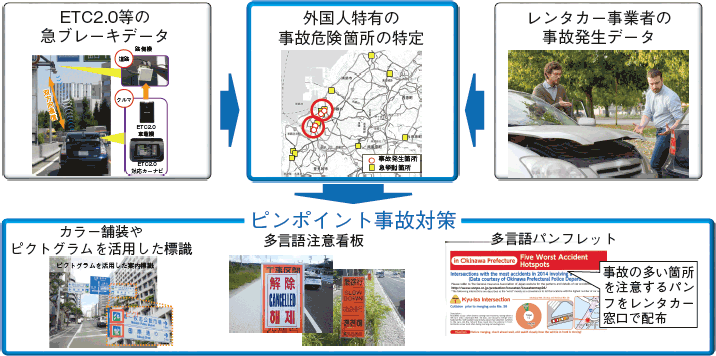
以上のとおり,訪日外国人のレンタカーの事故については,既に取組が進展しているように,今後は,増加が見込まれる外国人の運転者,歩行者に対し,我が国の交通ルールに関する知識を効果的に普及するための工夫が必要となる。
2 高齢化の一層の進展と交通安全
平成の30年間を通じて65歳以上人口は,2千万人以上増加し,総人口に占める割合(高齢化率)は,28.1%となるなど高齢化が一層進展した。この間,交通安全に関しては高齢歩行者,さらに高齢運転者の事故に着目し取組が進められてきた。今後も一層高齢化が進展するのに伴い,これからも,高齢者の交通安全は,歩行者としても運転者としても重要な課題である。
高齢歩行者の事故――歩行中死者数に占める高齢者の割合は71.5%
近年の交通事故による「状態別」死者数の推移をみると,平成20年に「歩行中」が「自動車乗車中」を上回り,以降最多となっており,海外と比較しても歩行者・自転車事故が多い。歩行中死者数に占める高齢者の割合は71.5%(平成30年)と,交通事故死者数全体に占める高齢者の割合(55.7%)よりも大きく,交通事故死者数の約4分の1を65歳以上の高齢歩行者が占めている。また,高齢者の中でもおおむね年齢層が高いほど,人口当たり歩行中死者数が多い傾向にある。
高齢歩行者の死亡事故について,法令違反別にみると,死亡した歩行者の約6割に違反があり,他の年代と比較して横断違反が多いといった特徴がある。このため,高齢歩行者の交通事故防止対策として,道路横断時等の交通ルールの遵守や加齢に伴う身体機能の変化に対応した安全な交通行動の実践,反射材用品等の着用促進等を重点に,安全教育・啓発に取り組んできた。
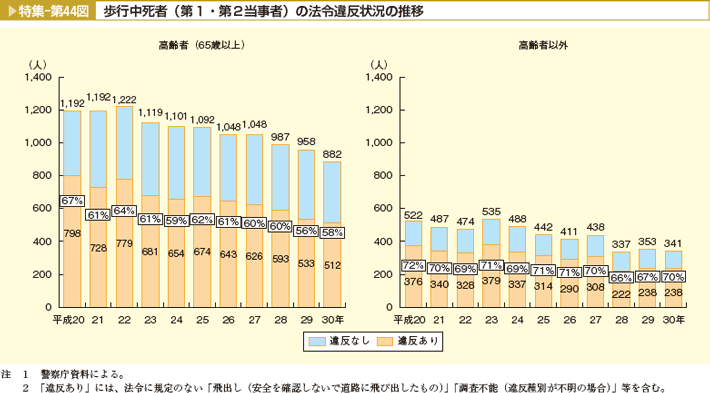
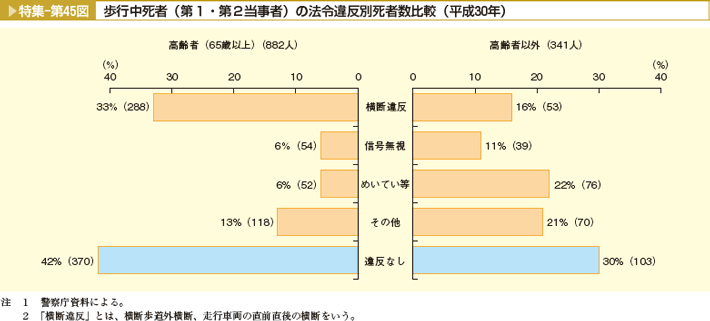
高齢者の交通事故を防ぐことへの意識
高齢者の交通安全については,昭和63年,交通対策本部は総合的な施策をとりまとめ,平成初期に取組が進展した。平成の前半に行われた「交通安全に関する世論調査」において,「高齢者の交通事故を防ぐためにはどうすればよいと思いますか。(複数回答)」という質問への回答をみると,「自治会,町内会,老人クラブなどで高齢者に対して行う交通安全講習」,「高齢者の運転免許取得の制限,検査の強化」,「高齢運転者に対して行う運転実技指導」などの順に回答が多い。平成2年と15年の調査結果を比べると,「高齢者の運転免許取得の制限,検査の強化」,及び「高齢者の特性などを理解してもらうための一般の人に対する交通安全教育」は回答した者の割合が大きく増えている。
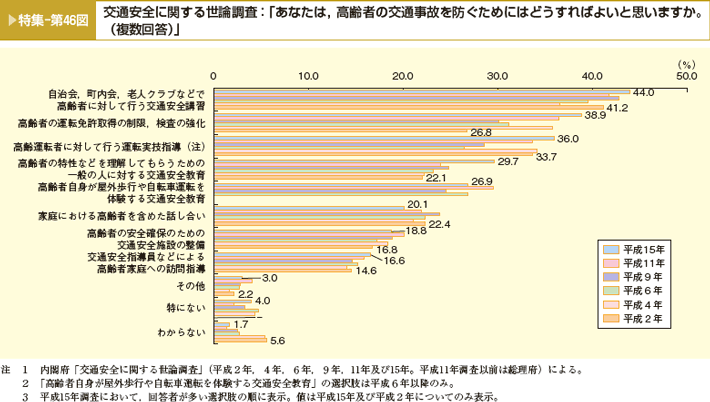
高齢運転者による事故への取組
第1節で見たとおり,高齢の運転免許保有者は,今後一層の増加が見込まれる。一方,平成30年中における免許人口10万人当たり死亡事故件数を年齢層別に見ると,75歳以上の高齢運転者については75歳未満の年齢層に比べて約2.4倍となっている。
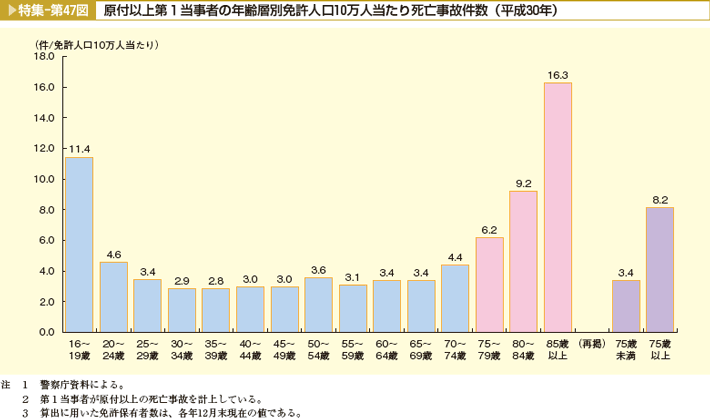
死亡事故を類型別にみると,車両単独による事故が多く,具体的には,工作物衝突や路外逸脱が多い。死亡事故について,人的要因をみると,操作不適による事故が最も多く,そのうち,ブレーキとアクセルの踏み間違い事故は,75歳未満の年齢層に比べて多い(75歳以上5.4%,75歳未満1.1%)。
平成20年代後半,平成28年10月通学中の小学生が高齢運転者による事故で死亡したこと等も背景に,関係省庁連携により,高齢運転者による交通事故防止のための,交通対策本部としての取組が始まり,対策が進められてきている15。
15 トピックス「高齢運転者の交通事故防止対策について」参照。
平均寿命の延びと高齢者の運転
平成4年の世論調査において,「あなたは,自分で運転できるのは何歳ぐらいまでだと思いますか」という質問に対し,「65歳ぐらいまで」と回答した者は46.4%,「75歳ぐらいまで」と回答した者は38.9%となっている。一方,平成の間に平均寿命は,概ね5年,男性は76年から81年へ,女性は82年から87年へと長寿化した16。諸外国に先駆けて高齢化が急速に進展する我が国においては,国民が生涯にわたり社会参加する機会を得て充実した生活を営む上で,加齢による身体変化を技術や社会により助け,高齢者や交通弱者も社会的に自立できる社会を目指していくことが不可欠であり,「人」「車両」「道路」等各々の面での取組はもとより,技術の進展が一層期待される。
16 平成29年簡易生命表 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/index.html
男性:平成元年75.91年,平成29年81.09年,女性:平成元年81.77年,平成29年87.26年
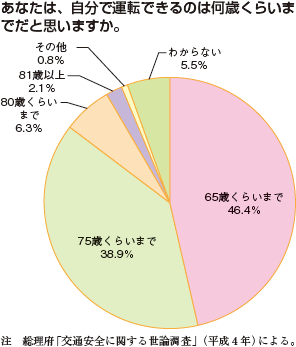
少子化の進展と子供の交通安全
また,高齢化の進展と同時に,安心して子を生み,育てることができる社会を実現するために,子供を交通事故から守る観点からの交通安全対策が一層求められる。平成の30年間を通じた家族やライフスタイルの変化も踏まえ,交通安全の観点からも,子供や子育て世代を社会全体で見守っていく必要がある。
3 終わりに
特集を通じてみてきたとおり,平成の30年間,特に後半を通じて,交通事故死者も負傷者も大きく減少した。30年間に,「人」の面では高齢化,女性運転者の増加,ライフスタイルの面で,居住の郊外化,夜間化などをはじめ大きな変化がみられた中でも,学校や地域における交通安全の取組は,都道府県や市町村,地域社会や企業など幅広い関係者により,着実に続けられてきた。交通へのニーズや社会の変化に対応し,車両,道路,救急の分野の取組も進展し,人口の増加や都市の拡大に伴いインフラを整備し,交通に関わる目まぐるしい技術の進展や,その実用化・普及に伴い,必要なルールが整備されてきた。安全・安心という価値は,より幅広い行政の取組の中に,明確に反映されるようになった。
30年の間に,交通安全にも大きく関わる技術の進展がみられた。本格的に普及し始めていたAT車は,平成3年に免許制度も改正され,今日では乗用車の大半を占め,平成20年代から普及し始めた衝突被害軽減ブレーキ搭載の新車は今日では8割近くに上る。平成中期からETCが普及し高速道路の渋滞解消に貢献し,さらに,これから得られるビッグデータは交通事故削減に活かされている。一方,交通以外の分野の技術の進展に伴う社会の変化により,交通安全のルールも変化を求められてきた。例えば,平成初期には一般には普及していなかった携帯電話は急速に広まり,平成25年頃には国民1人当たり1台以上普及した。このため,携帯電話の使用について,自動車や自転車を運転する際のルールも具体化し法定された。
新しい時代にも引き続き自動運転技術をはじめ科学技術のめざましい進展が期待され,日々進展する新たな技術を的確に交通安全に活かしていく必要がある。技術革新の過程にある製品や機能を過信せず,技術の限界も含めて,正しい理解を地域や学校,職場といった,交通安全の取組の様々な場面で,わかりやすく伝え普及していくリスクコミュニケーションが課題となる。日本人以外の運転者,歩行者,住民のほか旅行者などが増加し,交通参加者が多様化していく中で,技術の進展やこれに関わる交通ルールの変化についても,確実に伝えていくことも一層重要となろう。
世界一安全な道路交通を実現するために,このような取組を着実に続けていく上では,人,道路,車両,救急に関わる多数の関係者が連携して進めていくこととともに,交通事故がない社会は,交通弱者が社会的に自立できる社会であるという,平成の時代に培われた「人優先」の交通安全思想を,交通社会の参加者一人一人が,次世代に伝えていくことが基本となろう。
コラム3
昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策

高齢運転者による事故,子供が犠牲となる事故が相次いで発生したことを踏まえ,令和元年5月21日に,「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」が開催され,総理から
〇 高齢者の安全運転を支える対策の更なる推進
〇 高齢者の移動を伴う日常生活を支える施策の充実について,新たな技術の進展なども考慮しつつ,一層強力に推進するとともに,
〇 未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保
について対策を早急に講じるよう指示がなされた。同日,関係省庁の局長級のワーキングチームを設置し,関係省庁が連携して,対策を早急に取りまとめることとなった。

