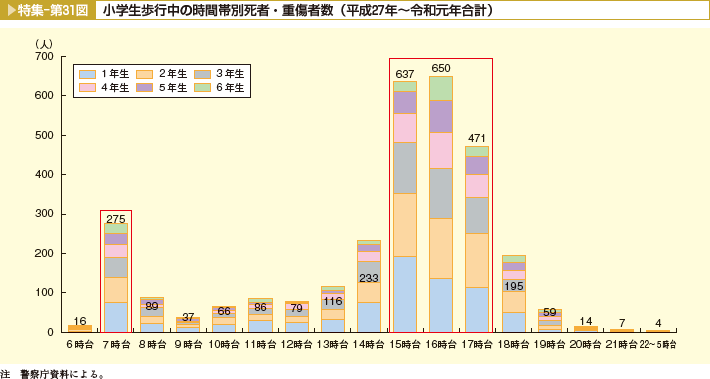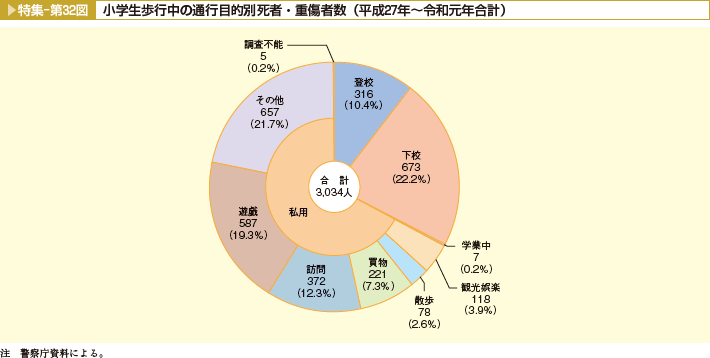特集 「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策について」
第1章 子供及び高齢運転者の交通事故の状況
第2節 子供の交通事故の状況
特集 「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策について」
第1章 子供及び高齢運転者の交通事故の状況
第2節 子供の交通事故の状況
1 年少人口の動向
(1)年少人口(15歳未満)の推移――少子化の進展
我が国の年間の出生数は,第1次ベビーブーム期には約270万人,第2次ベビーブーム期には約210万人であったが,昭和50年に200万人を下回り,それ以降,減少傾向が続いている。平成28年の出生数は97万7,242人と,明治32年の統計開始以来,初めて100万人を割り,令和元年の出生数は86万5,234人と,90万人を割り込んでいる。
年齢3区分別の人口規模及び構成の推移を見ると,年少人口(15歳未満)の割合は,昭和50年(24.3%)以降低下を続け,令和元年は,12.1%(1,521万人)と過去最低となっている。令和38年には1,000万人を割り,47年には898万人と,現在の6割程度になり,総人口に占める割合は10.2%となると推計されている(特集-第1図)。
年少人口(15歳未満)について,年齢層別に見ると,概ね未就学児に該当する0~5歳人口は,平成元年の822万人から令和元年には573万人に,小学生に該当する6~11歳人口は,947万人から627万人にそれぞれ減少した(特集-第5図)。
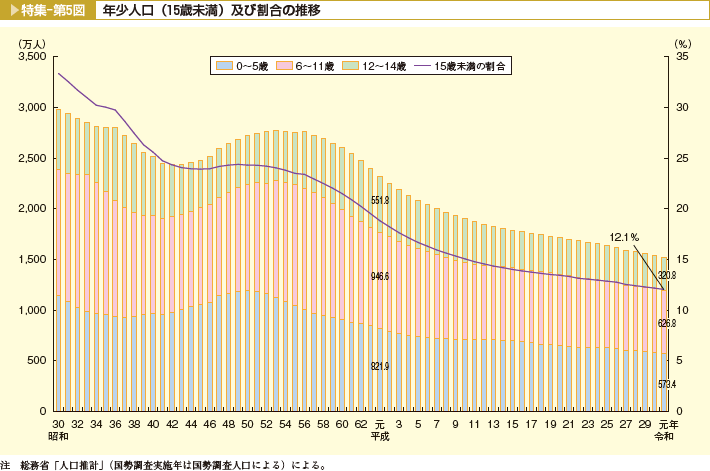
(2)未就学児と保育所等の動向
少子化が進み,年少人口が減少する一方で,近年の保育所等の施設数及び利用児童数は,ほぼ変動は見られないが,保育所等に子供を預けて働く世帯は,増加傾向にあると考えられる(特集-第6図,第7図)。
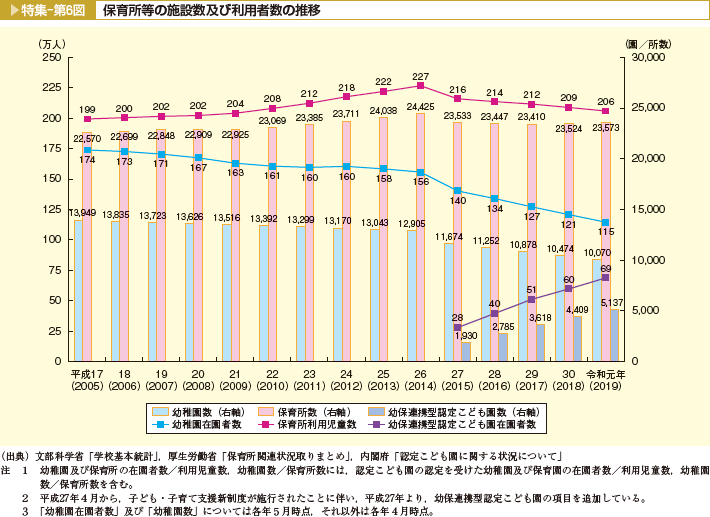
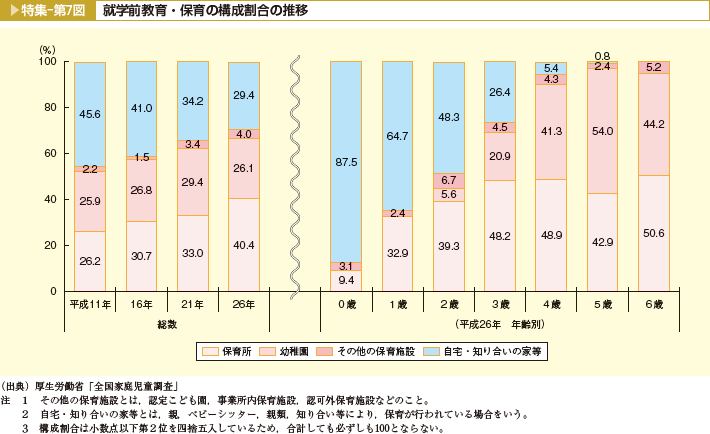
2 未就学児及び小学生の交通事故の状況
(1)年齢別に見た交通事故死者数等の推移
近年の12歳以下の交通事故死者数の推移を見ると,全体として減少傾向にある中で,5歳以下については平成20年の44人から令和元年は24人に,6~12歳については52人から21人に減少した(特集-第8図)。
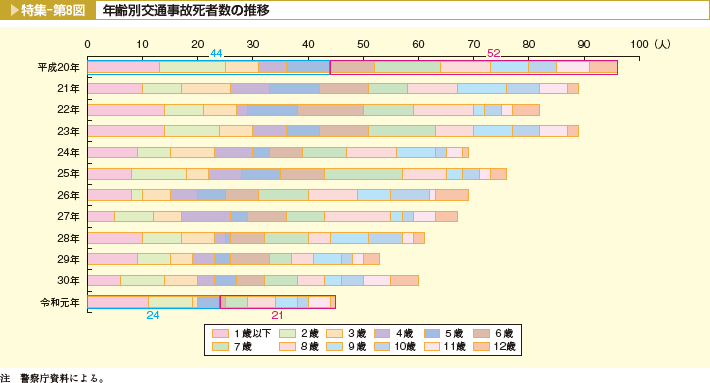
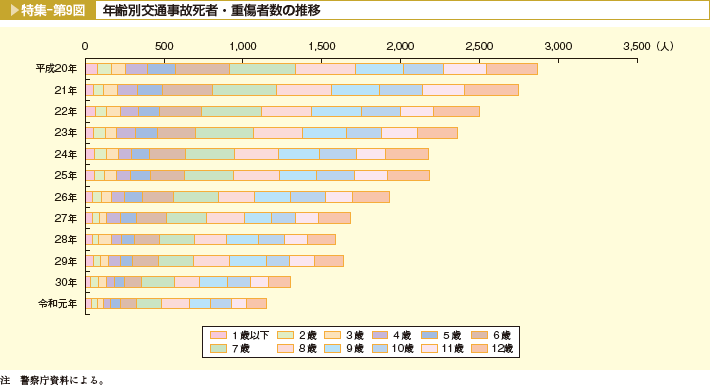
(2)状態別に見た交通事故死者数等の状況
○状態別に見た交通事故死者数等の特徴
状態別に平成27年から令和元年までの間の交通事故死者数を見ると,未就学児及び小学生共に,「歩行中」の死者が最も多く,未就学児については約6割,小学生については約5割を占める。
未就学児については,「自動車乗車中」の死者がこれに続き4割近くを占めている。未就学児は,屋外において親等と共に行動することが大半であることから,このような特徴が見られるものと考えられる。
小学生については,「歩行中」に続き「自転車乗用中」の死者が多く,3割近くを占めている。小学生になると,移動手段に自転車が新たに加わることから,このような特徴が見られるものと考えられる(特集-第10図)。
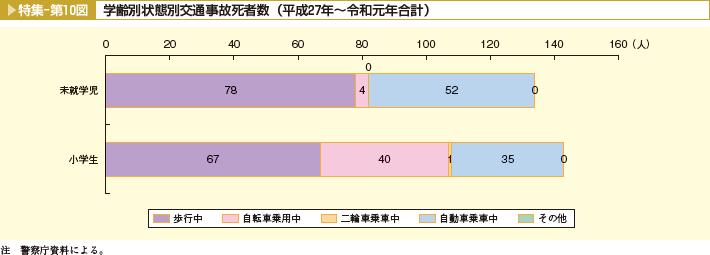
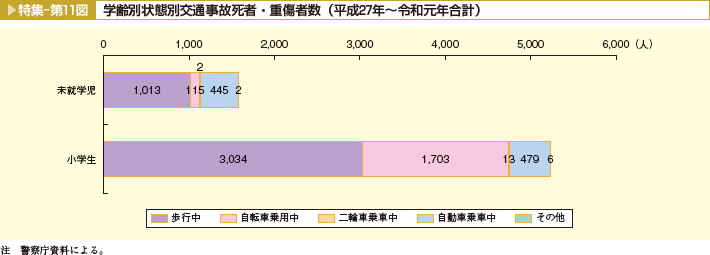
○状態別に見た未就学児の交通事故死者数等の推移
未就学児に着目して,状態別に交通事故死者数及び死者・重傷者数の推移を見ると,いずれも全体として減少傾向にある中で,死者・重傷者数については,「自動車乗車中」の割合が近年増加傾向にあることがわかる(平成2年:10.6%→令和元年:34.5%)(特集-第12図,第13図,第14図,第15図)。
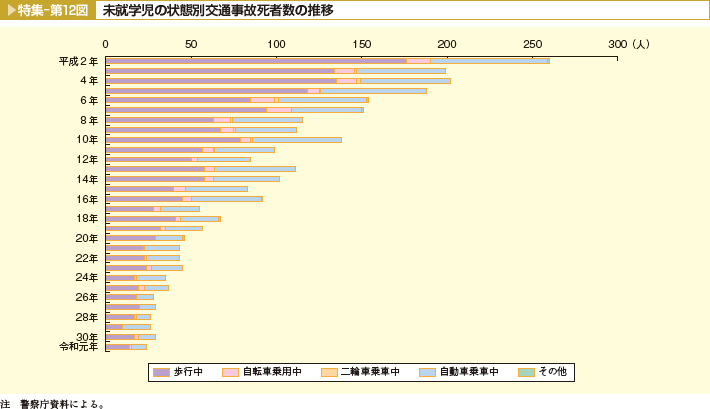
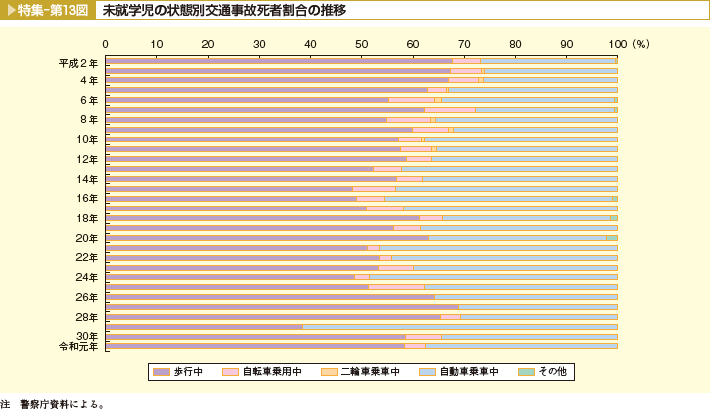
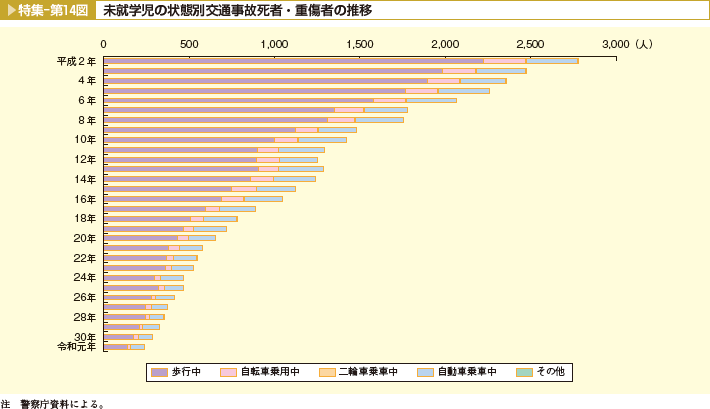
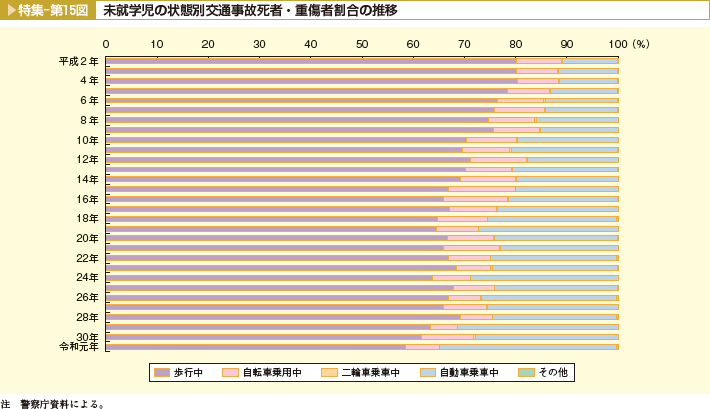
(3)歩行中の交通事故死者数等の状況
○通行目的別に見た歩行中死者数等の状況
状態別に見て最も交通事故死者数が多い「歩行中」の死者数について通行目的別に見ると,まず未就学児については,買物や遊戯等「私用」が最も多く(66人,84.6%),「通園中」の交通事故死者は限られている(8人,10.3%)。一方,小学校低学年については「通学中」の交通事故死者が目立つ(特集-第16図)。
また,死者・重傷者数を見ると,まず,全体として,未就園児よりも就園児の方が多く,小学生,中学生については,学年が上がるとともに少なくなっている。
通行目的別に見ると,未就学児については「私用」が大多数を占め,小学生については「私用」が半数以上を占めているが,学年が上がるとともに減少している。なお,中学生については,「通学等」と「私用」は,ほぼ同程度となっている(特集-第17図)。
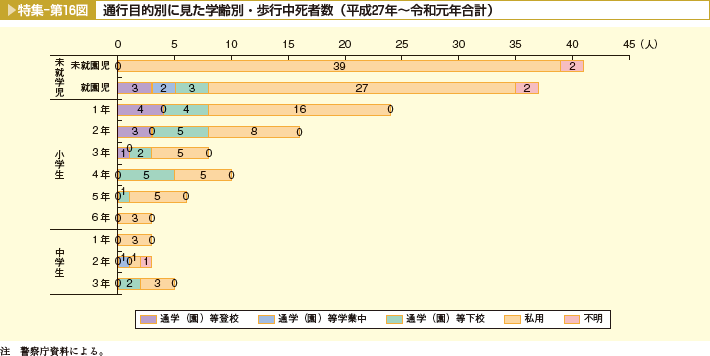
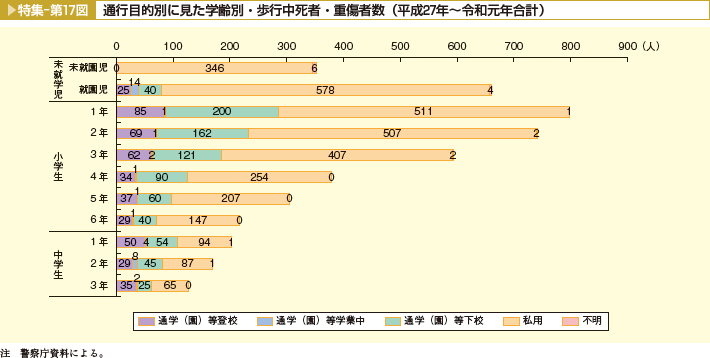
3 小学生の交通事故の状況
(1)小学校児童数等の推移
小学校児童数,学校数の推移を見ると,いずれも減少傾向にあり,令和元年には,636万8,550人,19,738校となっている(特集-第18図)。
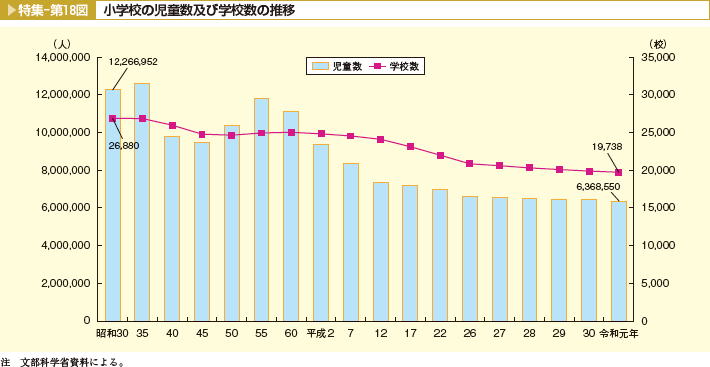
(2)小学生の交通事故の状況
○状態別に見た交通事故死者数等の推移
小学生の交通事故死者数及び死者・重傷者数の推移を見ると,いずれも全体として減少してきている。
また,状態別に見ると,全ての分類で大きく減少している(特集-第19図,第20図,第21図,第22図)。
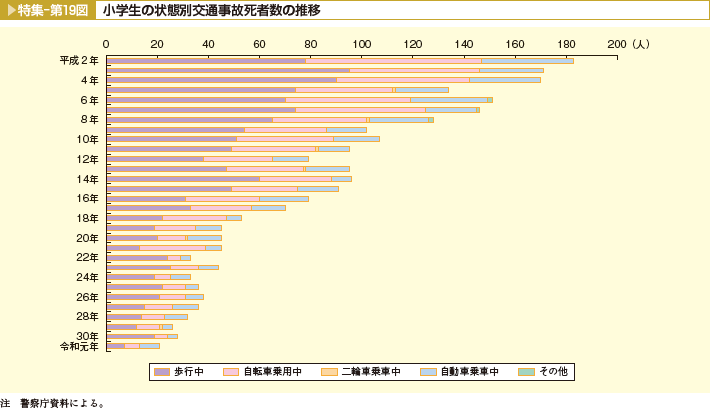
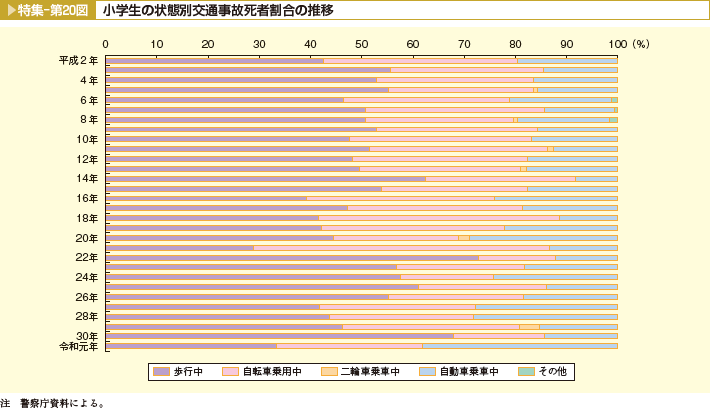
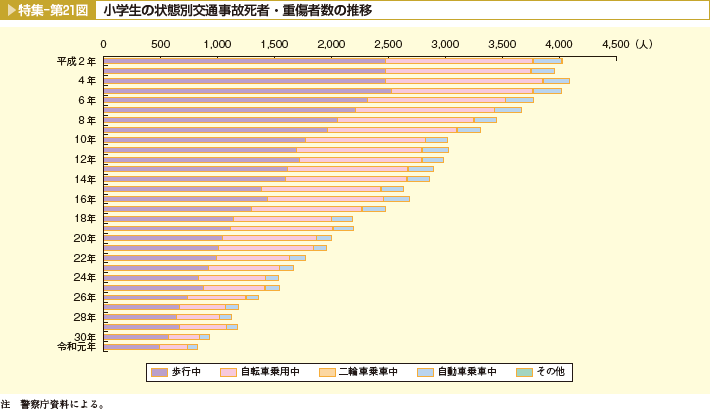
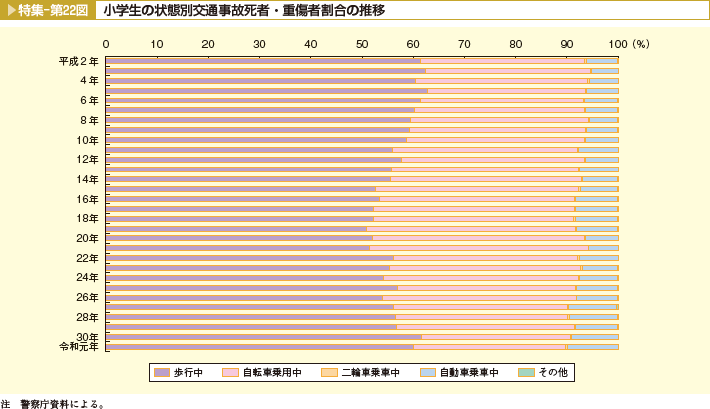
〈学年別〉
過去5年間(平成27年~令和元年)の小学生の状態別死者数を学年別に見ると,小学1年生の「歩行中」の死者数は,小学6年生の8.0倍と顕著な差がある。死者・重傷者数についても,3.7倍となっている。
また,死者数及び死者・重傷者数ともに,低学年ほど「歩行中」の割合が大きく,高学年になると「自転車乗用中」の割合が大きくなる傾向にある(特集-第23図,第24図)。
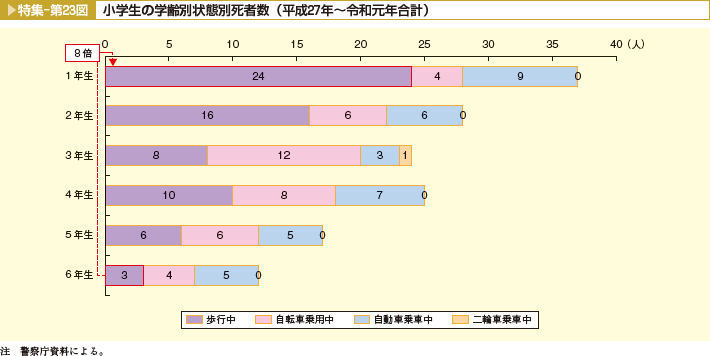
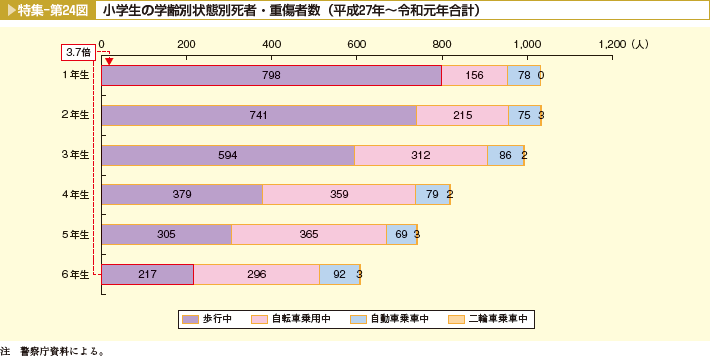
○歩行中死者数等の推移
〈学年別〉
状態別に見て最も交通事故死者数が多い「歩行中」の死者数について学年別に見ると,低学年(1・2 年生) が概ね全体の6 割(過去5 年平均59.7%)を占めている。また,死者・重傷者数についても,低学年(1・2年生)が概ね5割(過去5年平均50.7%)を占めている(特集-第25図,第26図)。
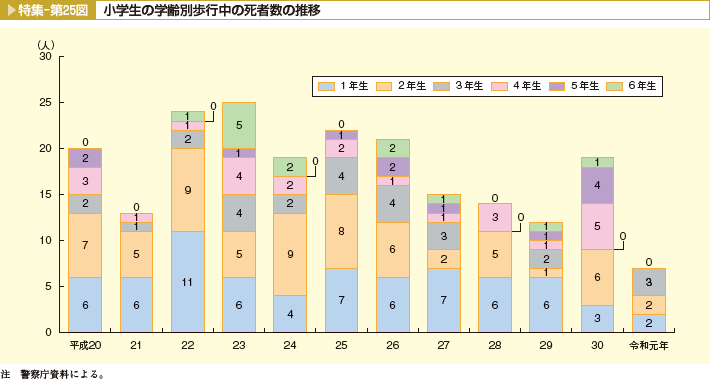
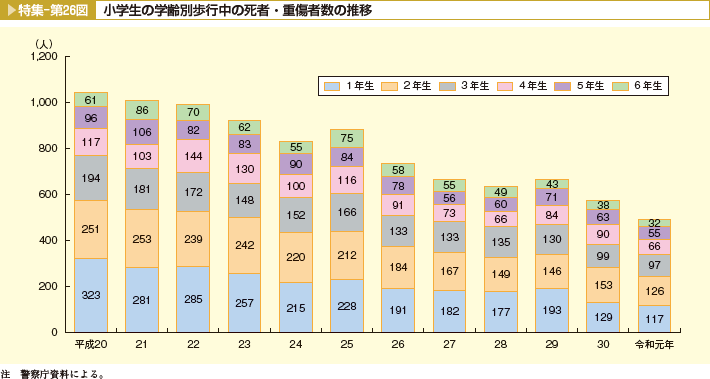
〈発生月別〉
「歩行中」について,発生月別に死者・重傷者数を見ると,3~6月及び10・11月が多い。学年別に見ると,特にこの時期には,小学1・2年生が多い。1年生については,入学間もない4月よりも5月中・下旬が第1のピークとなっている。
なお,全年齢層で見ると,年末に向けて死者・重傷者数は増加傾向にあるが,小学生については3~6月及び10・11月が多い(特集-第27図,第28図,第30図)。
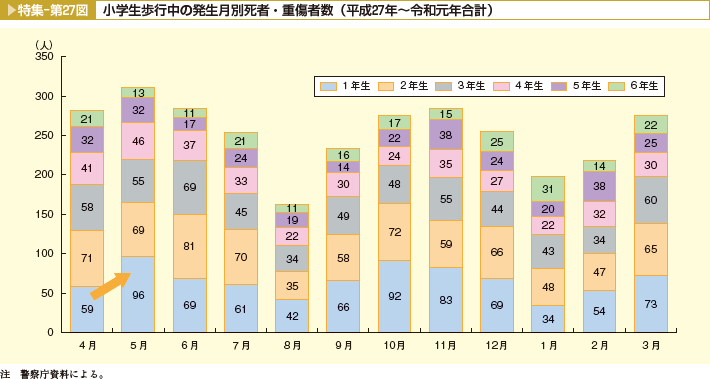
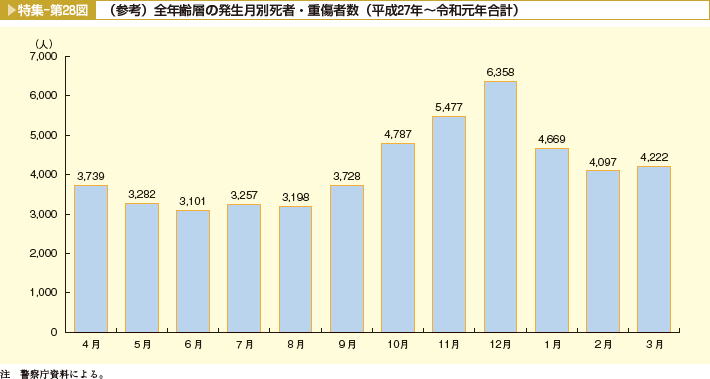
〈小学1年生の発生月別目的別〉
小学1年生に着目して,歩行中事故の発生月別・通行目的別に死者・重傷者数を見ると,事故の多い4~6月のうち,特に5月中・下旬に,私用及び下校中の死者・重傷者が多いことがわかる(特集-第29図,第30図)。
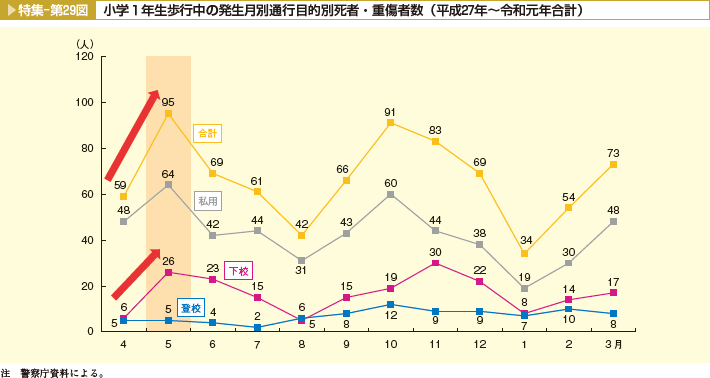
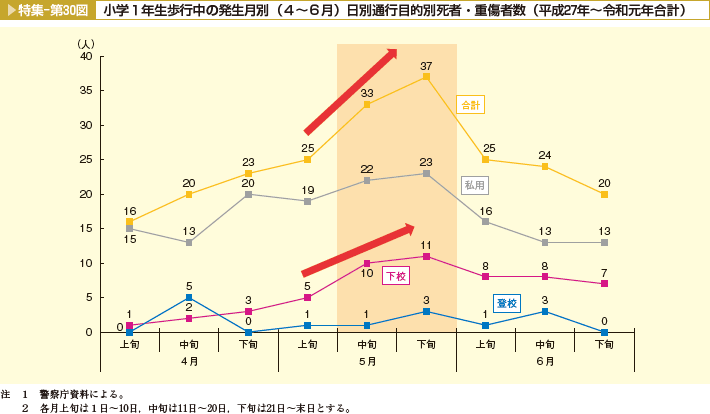
〈時間帯別〉
小学生の歩行中の時間帯別死者・重傷者数を見ると,7時台及び15~17時台に多く,特に,小学1・2年生が多い。通行目的別死者・重傷者数を見ても,登校中が10.4%,下校中が22.2%を占めている(特集-第31図,第32図)。