特集 自転車の安全利用の促進について
第2章 自転車の安全利用の促進について(自転車安全利用五則)
第1節 車道が原則,左側を通行 歩道は例外,歩行者を優先【第1則】
特集 自転車の安全利用の促進について
第2章 自転車の安全利用の促進について(自転車安全利用五則)
全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改正が行われた。これを機会に,自転車に関する交通秩序の更なる整序化を図り,自転車の安全利用を促進するため,令和4年11月1日付けで「自転車の安全利用の促進について」(中央交通安全対策会議交通対策本部決定)が決定された。
本章第1節から第5節では,「自転車安全利用五則※」について,それぞれのルールが,自転車を安全に利用するに当たって守るべきものであることを理解するため,そのルールの解説とともに,関係する交通事故統計を示すこととする。第6節では,国,地方公共団体,関係機関が取り組んでいる自転車安全利用に係る施策について紹介することとする。
※自転車安全利用五則
自転車の交通ルールの広報啓発に活用することとされている「自転車の安全利用の促進について」の別添に定められているもの。
第1節 車道が原則,左側を通行 歩道は例外,歩行者を優先【第1則】
1 第1則は自転車の走行場所を定めたもの
(1)自転車は軽車両と位置付けられ,車道通行が原則
道路交通法では,自転車は軽車両と位置付けられている。自転車は,歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり,車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
また,著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き,道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが,その場合は,歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
(2)歩道通行は例外
普通自転車が歩道を通行する場合は,道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は当該部分を,指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない。また,歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。ただし,普通自転車通行指定部分を通行し,又は通行しようとする歩行者がいないときは,歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。


2 交通事故統計から
交通事故統計は,自転車運転者が歩道において事故を起こしていることを示している。自転車関連死亡重傷事故件数(第1当事者,第2当事者の別。平成30年~令和4年の合計。)を,衝突地点が単路のケースで見たところ,衝突地点が歩道である割合は,第1当事者で約3割,第2当事者で約2割となっており,第1当事者の方が割合では高くなっている(特集-第12図)。

3 自転車通行空間の整備
(1)自転車道
全ての道路利用者が安全を確保するためには,歩行者,自転車,自動車等をそれぞれ分離した利用環境が整っていることが望ましい。自転車道は,専ら自転車の通行の用に供するために,縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいい(道路構造令(昭45令320)第2条第2号),その整備状況を延長距離の推移で見ると,緩やかではあるものの着実に増勢がみられ,令和3年度末(令和4年3月末)の延長距離は,平成29年度末(平成30年3月末)と比較して約1割伸長している(特集-第13図)。



(2)普通自転車専用通行帯
自転車と自動車が視覚的に分離された自転車通行空間として,普通自転車専用通行帯がある。普通自転車専用通行帯は,車両通行帯の設けられた道路において,普通自転車が通行しなければならない車両通行帯として指定された車両通行帯をいう。その設置状況を延長距離の推移で見ると,自転車道と同様,着実に増勢がみられ,令和3年度末(令和4年3月末)の延長距離は,平成29年度末(平成30年3月末)と比較して2割以上伸長している(特集-第14図)。
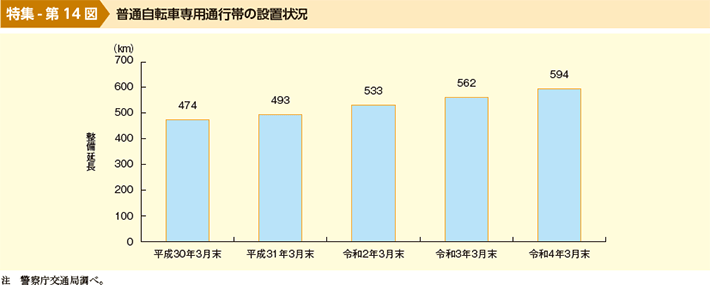


(3)車道混在(自転車と自動車を車道で混在)
車道混在とする場合,必要に応じて,自転車の通行位置を示し,自動車に自転車が車道内で混在することを注意喚起するための矢羽根型路面表示,自転車ピクトグラムを設置するものとされている。
※自転車は,車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。



