登壇者等一覧
主催者挨拶
ビデオメッセージ

俳優、ユニセフ親善大使、〈社福〉トット基金理事長
黒柳 徹子 氏
東京都生まれ。日本史上最初のテレビ女優。冠番組の『徹子の部屋』では同一司会者によるトーク番組の最多放送世界記録保持者としてギネス世界記録更新中。累計800万部を記録し、戦後最大のベストセラーとなった『窓ぎわのトットちゃん』など著書多数。『窓ぎわのトットちゃん』の印税を寄付して、社会福祉法人「トット基金」を設立、理事長に就任、ト ット文化館(就労継続支援B型)活動と日本ろう者劇団活動、手話教室を展開。日本ろう者劇団では、和泉流狂言師三宅右近師の指導の下、狂言のセリフや動きをそのままに手話で表現する手話狂言のほか、創作劇やムーブメントシアター、サインマイムなどを国内外で上演している。
基調講演 「手話施策推進法の意義」

弁護士、障害者権利条約締約国会合・障害者権利委員会委員
田門 浩 氏
1967年、福島県生まれ。父の仕事の関係で、福島、水戸、千葉、札幌など各地を転居し、現地のろう学校に通うも、10歳の時に父が死亡。妹とふたり、学校給食の調理場で働く母に育てられる。普通高校を経て、東京大学法学部卒業。5年間の千葉市役所勤務の後、司法試験合格。1998年、弁護士登録、人権擁護に取り組む。2024年、国連の障害者権利委員会の委員にトップで選出され、2025年より就任。わが国から選出された同委員会委員は、石川准氏(視覚障害)以来2人目。著書に「Q&A障害者差別解消法」(2016年:共著:生活書院)など。
ミニ講演

スターバックスジャパン株式会社 営業統括西日本リージョン
梅内 哲也 氏
1971年、東京都生まれ。2000年3月、スターバックスコーヒージャパン株式会社入社。
2016年営業統括中日本リージョン、2024年10月営業統括西日本リージョンに就任。営業統括として中日本リージョン担当時に、聴覚に障がいのあるパートナー(従業員)の「他の国のスターバックスではサイニングストアがあるんです。私たちもそんなお店で働いてみたい」という声を受け、国内初の手話が共通言語の「サイニングストア」nonowa国立店の立ち上げに尽力。全国2,000を超える店舗で年間約5,700件もの活動が行われている地域貢献をめざし、店舗が独自に企画・実施する“コミュニティコネクション”は、地域の歴史、伝統的な建築や工芸、文化、産業の紹介、認知症カフェ、手話カフェなど多彩。

俳優/手話パフォーマー
中嶋 元美 氏
1994年、東京都生まれ。中学生の時に「感音性難聴」とわかり、片耳だけ補聴器を付けていたが、高校1年生の時に聴力を失い、3歳から続けてきたバレエダンサーとなる夢を諦める。高校2年の春に母が探してくれた手話パフォーマンスの劇団に出会い、ミュージカルや手話ライブに取り組むうちにドラマや映画の手話指導に携わるようになる。2020年に劇団を卒業し、ソロ活動を開始。2021年の東京パラリンピック開会式にはダンサーとして参加。2022年、主人公と経験や年齢が近いことからドラマ「silent」の手話監修を手がける。幼い頃からのダンスに手話が加わり、表現力が増したと感じ、「手話という、見てわかる言葉でコミュニケーションできる今がすごく楽しい。聞こえなくなったこの人生に感謝している」 と話す。

『いくおーる』 編集者
小川 光彦 氏
1962年、栃木県生まれ。4歳の時に強い薬の影響で中等度難聴となり、現在、両耳とも聴力約95dB前後の重度難聴、語音明瞭度は50%以下(単音)で、どうしてもわからない音がある。28歳で手話に出会い、手話歴35年。聴器や無線マイク等の聴覚活用では不十分なため、視覚的な手話や読話、筆談、音声認識を併用してコミュニケーションを行う。2023年、 NHK総合のドラマ「デフ・ヴォイス法廷の手話通訳士」に中途失聴の弁護士役で出演。聴覚障害者向け総合情報誌編集、認定補聴器技能者職を経て現在、図書館関係企業の障害者サービス担当。(一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会前情報文化部長。ジョギングを趣味とし、今年初めてかすみがうらマラソンを完走。

兵庫教育大学特別支援教育専攻障害科学コース准教授
中島 武史 氏
1983年、大阪府生まれ。聞こえない父と聞こえる母のもとに生まれ、地域のろう者コミュニティにも親に連れられて参加していた。日本語を第一言語として生活しているが、手話は自分の周りに常にあり、自分も長く使用している言語。大学卒業後、ろう学校教諭として勤務しながら研究を続け、2024年より現職。社会の中での手話言語と音声言語のパワーバランスやろう教育、コーダの言語使用と言語意識、ろう者と他のマイノリティとの異同など、社会言語学的なテーマに関心を持ち、コーダに関する研究にも取り組んできた。著書に 『ろう教育と「ことば」の社会言語学:手話・英語・日本語リテラシー』(生活書院)など。
※CODA:聞こえない・聞こえにくい親をもつ聞こえる子ども(Children of Deaf Adults)
パネルディスカッション 「手話のすそ野を広げる」
コーディネーター

筑波技術大学教授、ICSD副会長、(社福)全国手話研修センター手話言語研究所所長
大杉 豊 氏
1962年、東京都生まれ。18歳の手話言語との出会いを「言語文化的に生まれ変わった」と表現する。劇団員、専門学校教員を経て米国ロチェスター大学大学院言語学専攻に留学、博士号を取得後、米国で大学教員として勤務。帰国後、全日本ろうあ連盟本部事務所長として 6年間勤務の後、2006年より筑波技術大学できこえない学生に手話言語学やろう者学を指導する傍ら、手話言語のフィールドワークを続ける。全日本ろうあ連盟が2010年に手話言語法制定推進事業を開始した時から現在まで委員を務め、全国手話研修センター手話言語研究所、現代人形劇センター、国際ろう者スポーツ委員会などで、手話言語とろう者文化・ スポーツの「居場所づくり」を求めてグローバルな活動を展開している。
パネラー

俳優/手話エンターテイナー
那須 映里 氏
1995年、東京都生まれ。日本大学法学部新聞学科を卒業後、2019年から1年間デンマークにあるFrontrunnersに留学し、ろう者のリーダーシップや組織活動、表現について学ぶ。 帰国後、「ビジュアル・ヴァナキュラー」パフォーマンスをはじめ、手話表現・翻訳・俳優として活動中。NHKEテレ『みんなの手話』、『手話で楽しむみんなのテレビ』に手話演者と して出演。舞台『うごく作品』や2022年のフジテレビ『silent』、2025年度A CジャパンのCM「決めつけ刑事」などでの演技が話題となる。手話普及活動、国際手話通訳など、活動は多岐にわたる。家族は、全員がろう者の「デフファミリー」。父・英彰さん、母・善子さんは俳優・キャスター、弟・元紀さんは映像制作会社勤務。
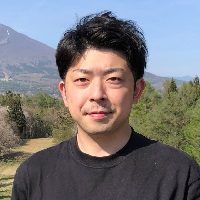
「めとてラボ」全体統括
根本 和徳 氏
1993年、福島県生まれ。2022年、手話による文化創造拠点づくりをめざす一般財団法人「めてラボ」を設立。全体統括、アーカイブプロジェクトを担当。手話による対話から生まれる表現や空間を日々追求している。「手話パフォーマンス甲子園」の手話指導、手話による哲学対話のファシリテーターも務める。SNS上でオススメの本を手話で発信、文章から心象風景を美しく再現する手話表現には定評がある。高校3年時に、東日本大震災で被災。「3.11手話語り」や手話劇の監修にも携わる。2025年、10年間勤めた特別支援学校教諭を退職、現在は福島県聴覚障害者協会教育文化・出版委員長として、手話指導や情報アクセシビリティに関する相談・支援などを中心に活動。

日本財団職員、東京2025デフリンピック応援アンバサダー
川俣 郁美 氏
1989年、栃木県生まれ。3歳の時に高熱でろうとなる。中学生の時に高村真理子氏(1958~2006、当時筑波技術短期大学英語非常勤講師)と出会い、アメリカへの夢を育む。日本財団聴覚障害者海外留学奨学金事業5期生として渡米、ギャロデット大学ソーシャルワーク学部、同大学院行政・国際開発専攻修士課程修了。日本財団でアジアのろう者支援事業コーディネート等を担当。栃木県聴覚障害者協会理事。2023年、東京2025デフリンピック応援アンバサダーに就任。東京2025デフリンピックでは、デフリンピックの素晴らしさのみならず、手話やろう者の文化の魅力、多様な人がともに支え合い、頼り合いながら自分らしく生きることができる共生社会の心地よさを多くの人に届けたいと願う。

アテネ、北京オリンピック柔道金メダリスト、医学博士
谷本 歩実 氏
1981年、愛知県生まれ。9歳の時に柔道を始め、2000年4月、筑波大学に進学。2004年のアテネオリンピック、2008年の北京オリンピックで金メダルを獲得、柔道史上初の五輪 2大会連続オール一本勝ちを成し遂げる。2010年に現役引退後、全日本ナショナルチームのコーチを務め、アスリートのコンディショニング管理の観点から、医学・栄養学・心理学を研究、フランスを拠点に諸外国のスポーツ事情を学ぶ。2018年、弘前大学大学院で医学博士号を取得、同年、国際柔道連盟(IJF)殿堂入りを果たす。現在、日本オリンピック委員会理事、パラリンピック強化本部長を務め、東京2025デフリンピックの気運醸成活動にも取り組む。
総合司会

「目で聴くテレビ」ディレクター・手話キャスター、
〈社福〉全国手話研修センター手話言語研究所事務局長
重田 千輝 氏
1990年、大阪府生まれ。デフファミリーで育つ。小学校から高校まで地域校に通い、筑波大学・同大学院でろう者・難聴者の心理を学ぶ。2018年に認定NPO法人障害者放送通信機構に入職、「目で聴くテレビ」のディレクター兼手話キャスターとして奮闘中。2024年、「手話言語アナウンサー・手話言語解説者・手話言語通訳者養成研修」(全日本ろうあ連盟主催)の講師を務め、2025年5月の第22回日本デフ陸上競技選手権大会では、丁寧で分かりやすい手話実況が高く評価された。国立民族学博物館や九州国立博物館の手話解説、『手話奉仕員養成テキスト』の作業委員及びモデル出演、デフリンピック普及啓発映画「みんなのデフリンピック」の監督を務めるなど、多岐にわたって活躍する。


