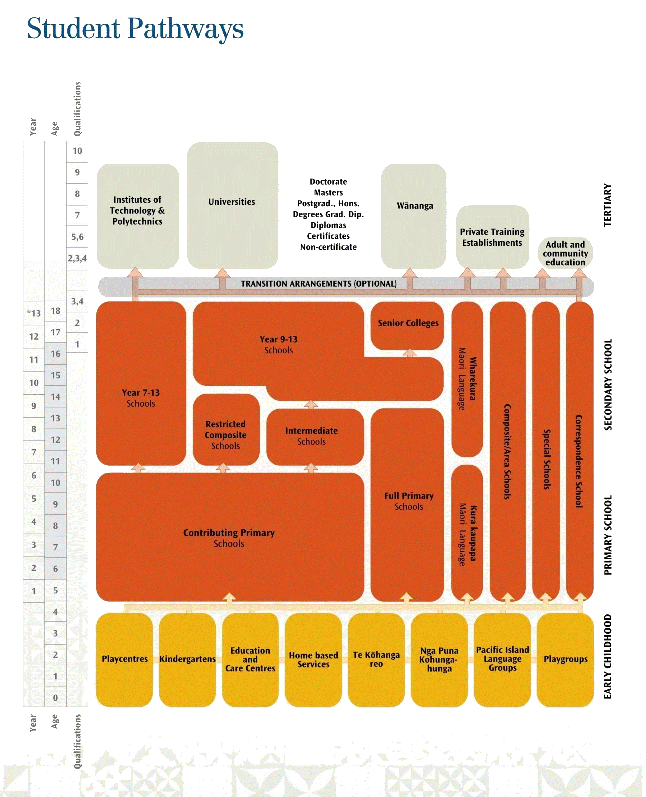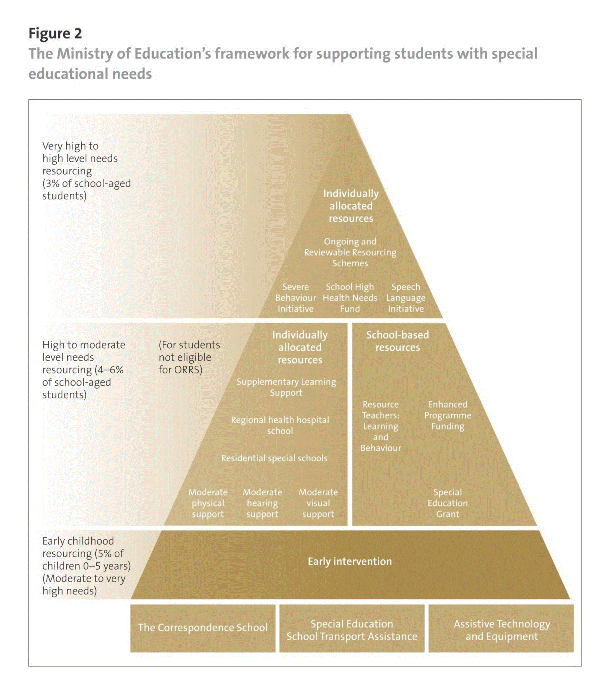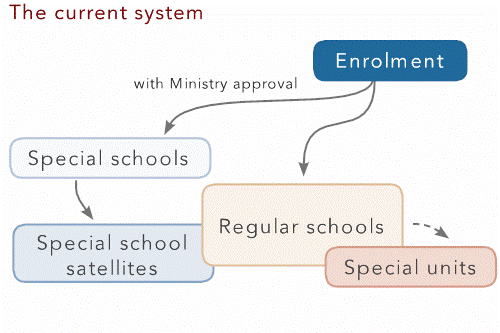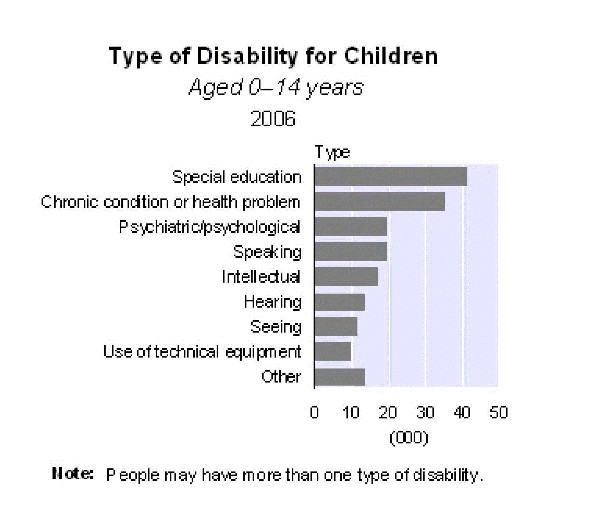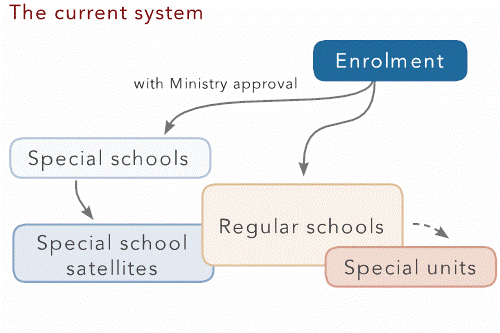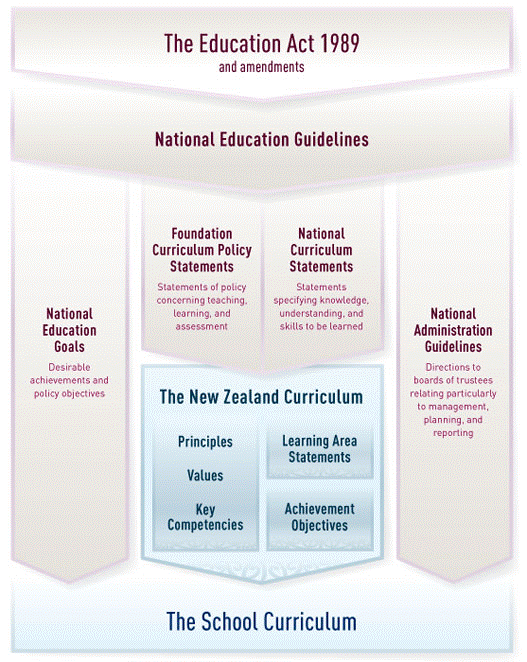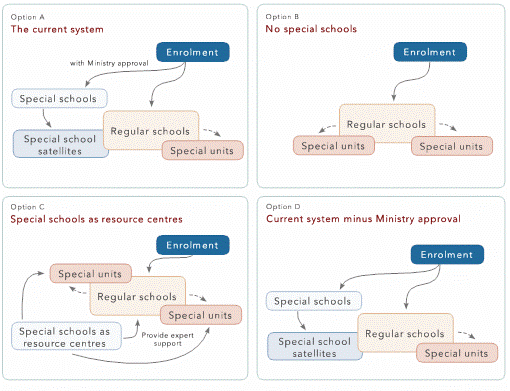第5章 ニュージーランド
マオリ語で「アオテアロア」(白く長い雲がたなびく国)というニュージーランドは、これまでイングランドよりも極端な規制改革を行なってきた国として日本では注目されてきた。規制改革の一環として教育面においても大きな変化がもたらされた。それは労働党政権のロンギ内閣時代に作成された「明日の学校(Tomorrow’s Schools)」に基づく政策により、教育省の権限縮小、教育委員会制度の廃止、教育評価機関の設置、人事・財政権のある学校理事会(Board of Trustees)の導入などである。これらを集約したものが、1989年教育法である。
同法は障害児教育の分野にも大きな変化をもたらし、特別な教育的ニーズのある子どもに対する特別教育を地域の通常学校・学級でも行い、保護者の選択対象とする制度を作り上げた。教育省の説明では、インクルーシブ教育の根拠はこの法律にあるとされている。
しかし、当事者団体、親・保護者団体、あるいは、人権委員会(Human Rights Commission)、子どもの権利コミッショナー(Children’s Commissioner)などの権利擁護・救済機関によると、インクルーシブ教育は確立されていないと批判されている。
これらの権利擁護の機関が多く作られているのは先住民族であるマオリ族の権利確立の長い戦いがあったことは改めて指摘するまでもないだろう。
ニュージーランドの面積は日本の約4分の3に相当するが、人口は約440万人。人口密度は小さい。マオリ系の住民は約66万人と言われている。
本報告では、現地調査(2011年3月)やネット検索による情報収集で得た資料・データをもとに作成したものである。現地調査の直前、多くの犠牲者を出したクライストチャーチの地震の影響で人権委員会へのインタビューが出来なかったことは残念である。
1.障害のある児童生徒の教育法制度と教育に関する基礎的なデータ
(1) 学校教育制度の概要
ニュージーランドの教育制度は図1のようになっている。
親が子どもを学校に通わせる意味での義務教育は6歳から16歳までであるが、子どもは5歳の誕生日から19歳の学年末まで学校に通うことができるようになっている。
5歳の誕生日を迎えれば就学できて0学年(year0)になる。入学した学年度の次に始まる学年からyear1となる。初等教育は初等学校(contributing primary:6年間)と中間学校(intermediate:2年間)とで構成され、両者が一体となった学校(full primary school)もある。
中等学校(year9-13 school)は5年間であるが、中間学校を付設する学校やそれと一体型の7年間の学校(year7-13 school)もある。義務教育終了の16歳を過ぎても学校を続けることは可能であり、多くがそうしている。12年間一貫のcomposite/Area 学校も存在している。中等学校3年終了で科目修了試験(school certificate)という国家共通試験を受けるようになっている。
設置主体別としては、国立学校(state school)、国立移管私立学校(integrated school)、私立学校(private school)となっているが、ホーム・スクーリングも認められている。特別学校(special school)やマオリ語学校は全て国立学校である。島の多い国なので通信教育もかなり行われている。
また国立学校でも中等学校になると男女別学の学校が存在している。
図1 ニュージーランドの学校教育制度
(http://www.minedu.govt.nz/NZEducation/EducationPolicies/
InternationalEducation/ForInternationalStudentsAndParents/NZEdOverview.aspx)
- *幼児期の教育・保育機関は、プレイ・センター、幼稚園など多様に存在している。
- *初等学校はContributing primary school という英語になっている。Contributingが何を意味するかは明確には分からないが、次の段階の学校に生徒を送り出す学校という意味のようである。
(2) 障害のある児童生徒の教育法制度
ニュージーランドの学校教育制度を規定している法律は1989年教育法(Education Act1989:最終改正2010年)であり、その中で無償の初等・中等教育への権利や初等・中等教育への平等な就学、特別教育(special education)が規定されている。具体的な条項は以下の通りである。
【1989年教育法第1部】
第2条:無償の初等・中等教育への権利
1975年の私立学校条件付き統合法(Private Schools Conditional Integration Act 1975)に規定される場合を除き、外国籍の生徒ではない全ての者は、その5歳の誕生日から19歳の誕生後の1月1日まで国立学校(state school)に無償で就学し、かつ、無償の教育への権利が与えられる(is entitled to)。
(注)
- *外国籍の生徒の権利は第3条で規定されている。
- *state school は公立学校と訳されることが多いが、中央政府がその財政負担をしているので、ここでは国立学校としておく。
- *私立学校から国立に移管した学校(state integrated school)も国立学校と同様に扱われる。
第8条:初等・中等教育への平等の権利
(1) 本法第2部で規定されるものを除き、(障害の有無に関わらず)特別な教育的ニーズを有する者は、国立学校への就学とそこでの教育への権利を有する。
(2) 第(1)項の規定は、就学要綱(enrolment scheme)並びに生徒の停学(suspension)、除籍(expulsion)、退学(exclusion)に関する第2部の効力を制約するものではない。
(注)
- *第2部の規定とは停学や退学に関わる規定
- *就学要綱(enrolment scheme)とは、ある学校への就学者が多すぎることがないようにするための方法を意味し、教育省が当該地域内に存在する学校の施設設備を有効に利用できるようにするためのもの。同要綱には明確に境界が定められている学区(home zone)を含んでおり、その学区に住む生徒はその学校に就学する絶対的権利(absolute rights)がある。なお、学区外から就学を希望する生徒については、法律で優先条件が定められ、学校が提供する特別プログラムへの登録が認められた生徒、兄弟姉妹が現在就学している生徒、兄弟姉妹が以前就学していた生徒、学校理事の子ども、その他となっている。
第9条:特別教育
(1) 21歳未満の者が特別な教育的ニーズを有すると認められれば、大臣(the Secretary)は、
(a) その者を特定の国立学校、特別学校、特別学級又は特別ユニットに就学させるべきかどうかにについて両親と合意する(agree with)か、又は、就学させるよう両親に指示し(direct)なければならない、又は、
(b) 特別サービスが提供する教育あるいは援助をその者が受けることを両親と合意するか、もしくは、両親に指示しなければならない。
(2) 就学要綱に関して本法あるいは学校の就学要綱に規定があるにも関わらず、本法第2部の停学、除籍及び退学に関する規定により、第(1)項による合意又は指示があれば、関連する特別サービスによる教育又は支援を考慮して、当該者は(状況に応じて)国立学校、特別学校、特別学級、あるいは、特別クリニックへの就学が認められなければならない。
(3) ある者に関して第(1)項に基づく指示が出された場合には、第10条第(4)項により、その指示がなされた1ケ月以上が経過した後に、その指示に従わず、又は、拒否する親は法律違反となり、また、略式裁判で(子どもの就学に関わる)第20条第(1)項の不遵守について規定されている罰が課せられる。
(4) いかなる者も、第(1)項に基づく同意または指示によらずに、特別学校、特別学級又は特別クリニックに就学させられるべきではなく、あるいは、就学継続が認められるべきではならず、また、特別サービスからの教育や援助を受け、あるいは、受け続けるべきではない。
(5) 第5条又は第6条の規定にも関わらず、
(a) 5歳未満の者は初等学校もしくは一貫学校(composite/area school)の第3フォーラム以下の学級に就学し、又は、継続して就学してもよい。
(b) 14歳以上21歳未満の者は初等学校又は一貫学校フォーラム3に就学しても、就学を継続してもよい。
(c) 21歳未満の者は、 (i) フォーラム3の学習を修了しなくても、 (ii) それに相当する学習を修了しなくても、大臣の意見により、中等学校又は一貫学校のフォーラム2より上のフォーラムに就学するか、又は、就学を継続してもよい。
(d) 第(1)項に基づく合意又は指示に従って、21歳未満の者は19歳の誕生日後の1月1日以降も中等学校又は一貫学校のフォーラム2より上のフォーラムに就学するか、就学継続をしてもよい。
(注)
- *法文中のSecretaryは「大臣」としておいたが、現在、ニュージーランドの内閣を構成する大臣はMinisterと表記されている。
- *特別クリニックは現在、存在しない。
- *クラスは同一年齢で、ユニットは異年齢で構成される学習集団
- *フォーラムとは初等学校と中等学校とが一体となった学校(一貫校)の内部区分けを示す言葉
第10条:再審の権利(Right of reconsideration)
(1) 本条の第(6)項の(p)及び(q)に従い、当該の子どもの親はこの第10条に基づき、
(a) 第9条第(1)項による当該の子どもに関する指示、又は
(b) もしも当該の子どもが外国籍でなければ、当該の子どもに関わる第(1)項の合意に対する大臣の拒否、の再審を提訴することができる。
(2) 第(1)項による提訴は文書により指示又は合意拒否がなされた時から1月以内に大臣に対して行わなければならない。
(以下、略)
このようにニュージーランドでは1989年教育法により、全ての子どもの教育への権利、特別な教育的ニーズのある子どもが他の子どもと同様に国立学校に通う権利、保護者が就学先を選択できる権利、教育省の指示や合意拒否を提訴する権利が保障されている。
(3) 障害と特別な教育的ニーズ
教育分野に固有の「障害」については定義されていない。定義されているのは、各種の障害にも起因する「特別な教育的ニーズ」である。
特別な教育的ニーズ(special education needs)のある子どもとは、「特別な、又は、通常の教育環境において支援するための追加補助(extra assistance)、改良された(adapted)プログラム又は学習環境、特別の設備又は道具を必要とする子ども」(1998年教育省発行「特別教育補助金の運用(Managing the Special Education Grant)」)である。
教育省のHPで特別な教育的ニーズが生じると思われる子どもの状態については、
[1]「身体的損傷がある」
[2]「学習障害がある」
[3]「視覚や聴覚に障害がある」
[4]「学習、コミュニケーション、他人との関わりにトラブルがある」
[5]「情緒あるいは行動に問題がある」
となっている。
なお、教育省が保健省との間で2010年に締結した「療法及び補助技術・装置:運用議定書(Therapy and Assistive Technology/Equipment Operational Protocols)」によれば、保健省のサービスを受ける基準上の障害について「障害者とは最低6ケ月以上継続し、継続的な支援を必要とするほどに自立的機能が低下している身体的、知的又は感覚的な障害(あるいはこれらの重複)があると認定された人」と定義している。
ニュージーランドでは、特別な教育的ニーズは、それに見合ったサービスに要する財政措置(funding)に関して段階区分が設けられている。以下の図は、ニュージーランドの障害児教育を大きく転換させることになった「特別教育2000(Special education 2000)」という政策文書で提示された、特別な教育的ニーズの分類とそれに見合ったサービスの種類を説明した枠組みである。
(http://www.oag.govt.nz/2009/special-education/docs/special-education.pdf![]()
![]() )
)
この三角形の上部は「最高度ニーズ(very high level needs)」と「高度ニーズ」までも含み、「継続的再審可能資源要綱(Ongoing Reviewable Resourcing Scheme:ORRS)」の対象となっており、生徒全体の約3%に該当する。
ここで提供されるサービスは、ORRSという仕組みのもとで行われる、行動支援(Behaviour Initiative)、コミュニケーション支援・言語療法(Communication Initiative/ Speech-language therapy)、学校保健基金(School High Health Needs Funds:SHNF)というサービスである。
ORRSは、学習に関する個人的な支援を必要とする生徒に対して行われる、主に専門家によるサービスであり、当該生徒が在籍する学校への支援への追加的サービスとなっている。ほとんどの生徒が在学中一貫して支援を受けることができるようになっている。再審可能資源要綱(Reviewable Resourcing Scheme:RRS)は、これに申し込んだ時点では生徒のニーズの程度が明確ではないために、一定期間のサービスを提供した後にニーズの再評価を行い、ニーズの程度を確定し、それに見合った資源の提供を行う、というシステムである。継続的とは、見直しを必要としないニーズへの資源提供の仕組みである。SHNFは、健康面での支えがなければ学校で安全に過ごすことが出来ない生徒に対して行われる介護員配置に要する資金である。
真ん中に位置するニーズは軽度(moderate level)から高度のニーズまでを含んでおり、上記のORRSの対象とはなっていない。そのニーズへのサービスは個々の生徒へのサービスと学校へのサービスとに大きく分かれている。前者のサービスには補充的な学習資源、地区保健学校(Regional Health School)への就学、寄宿制特別学校への就学、身体的支援(moderate physical support)、聴覚支援(moderate hearing support)、視覚支援(moderate visual Support)がある。後者には学習・行動支援リソース教員(Resource Teachers : Learning and Behaviour, RTLB)の配置、プログラム拡大基金(Enhanced Programme Funding)、特別教育補助金(Special Education Grant)が用意されている。
RTLBとは、学校の要請に応じて、学校での特別ニーズ支援の手助け(教員へのアドバイスや生徒個別指導など)を行う専門教員であり、数校で構成される学校群(cluster)に所属している。プログラム拡大基金とは、個別支援を受けないが、特別支援を集団として受けるニーズを有する子どもがかなり多くいる学校に割り当てられる基金である。
下の部分は幼児期に行われる早期介入プログラムによるサービスである。
(4) 各学校・学級への就学状況
ア 障害のある児童生徒の就学形態
1989年法及び制度図からわかるように、障害のある児童生徒の就学先は、国立の通常学校、その中にある特別学級・ユニットあるいは特別学校の分教室(satellite)、国立の特別学校(3種類)である。ニュージーランドでは、この他に、マオリ学校があり、また、ホーム・スクーリングが認められ、通信教育も行われており、そこでも学習をしている。
(ア) 通常学校の通常学級(4種類の形態)
- 支援はないが通常学級に就学
- 教員補助員(a teacher aide)による支援を受けて通常学級に就学(支援は多様)
- 学校への特別教育補助金による支援を受けて通常学級に就学
- 加配教員(additional teacher)による支援を受けて通常学級に就学
(イ) 通常学校の特別学級・ユニット及び分教室
- 通常学級にも毎日部分的に参加しながら、通常学校内の特別学級又は特別ユニットに就学
- 通常学校内の特別学級、特別ユニット又は分教室に就学
(ウ) 特別学校
| a | 昼間特別学校(day special schools) | 28校 | ||
| b | 寄宿特別学校(residential special schools) | 8校 | ||
| (a) | 重度行動障害児対象(for students with severe behavior difficulties) | 3校 | ||
| (b) | ろう児及び難聴児対象(for deaf and hearing impaired students) | 2校 | ||
| * | 2校の聾・聴覚障害学校の内、クライストチャーチに在った学校は先に大地震で現在閉鎖中である。その寄宿舎にいた子どもたちはオークランドのケルストン聾教育センターにある学校に移動している。同校には寄宿舎がある。同センターは北部地域の通常学校の学級や特別ユニット、さらには提携をしている学校で学んでいる生徒や学校の教員を支援する専門教員の拠点となっている。聾教育の専門家が42名いる。内、8名が聴覚障害のある教員(常勤の教員数は77名)。 | |||
| (c) | もう児及び弱視児対象(for blind and vision impaired students) | 1校 | ||
| (d) | 知的障害を伴う教育ニーズ、社会的ニーズ、情緒的ニーズを有する子ども対象(specializing in working with students with educational, social and emotional needs, together with underlying intellectual impairment) | 2校 | ||
| c | 地区保健学校(regional health schools) | 3校 | ||
| * | 北部、中部、南部の各地域に一校ずつある。「特別教育2000」政策で設置された学校であり、通常の学校に籍を残したまま、必要に応じて利用。 | |||
以上の就学先を図示したのが以下の図である。特別学校への就学については教育大臣の承認が必要となっている。
* 教育省の特別教育評価討議文書より
https://pdfs.semanticscholar.org/fa29/08726cbf9da78a30d214399150b6c4b0ffd6.pdf![]()
![]()
イ 就学先ごとの人数
就学先の個別の人数のデータは教育省の資料では見つからない。
そこで、ニュージーランド人権委員会が2010年に出した「ニュージーランドの人権2010(「Human Rights in New Zealand 2010」」の第17章「Rights of Disabled People」で用いている統計局(Statistics New Zealand)の2006年障害者調査(Disability survey 2006)でまず概要を捉えてみる。
<0歳から14歳までの子ども>
(ア) 子どもの総数865,100人:内障害のある子ども数 約95,300人(約11%)
(イ) 障害の種類別
- 特別な教育的ニーズのある子ども:全体の約5%にあたる41,000人(障害児の46%)特別教育支援を必要とする長期に病気(condition)や健康問題を抱える子ども、学習障害や発達障害がありIEPやIPを必要とする子ども、識字障害・注意欠陥症・注意欠陥多動症の子どもが含まれる。
(注)
* ここに入る障害児は、以下の伝統的な障害児以外のいわゆる発達障害児が中心となっている。
- 慢性的な病気や健康問題がある子ども:全体の約4%にあたる35,000人(障害児の39%)(ぜんそく、脳性まひ、糖尿病、その他の慢性的病気)
- 精神的障害(psychiatric or psychological disabilities)の子ども:全体の約2%にあたる19,300人(障害児の21%)
- 言語障害(speaking)
- 知的障害(intellectual)
- 聴覚障害(hearing)
- 視覚障害(seeing)
- 技術装置使用障害(use of technical equipment)
- その他
これらを表にしたものが、以下のグラフである。
この2006年調査を踏まえ、人権委員会は特別学校で学ぶ生徒を障害のある生徒の中で約3%としている。
2010年6月1日時点では、特別学校在学者数は2,878人となっているが、特別クラスやユニットの統計は見当たらない。特別学校在籍者で特徴的なことは15歳以上の年齢が多いことである。5歳から14歳までに限定すると在籍者数は1,732人となっている142。
(5)障害のある教員
教員採用は各学校の理事会(Board of trustees)が行っているが、教育省では、障害のある教員の調査を行っていない。
訪問したオークランドのケルストン聾教育センターには77名の常勤教員がいるが、内8名が聾教員である。
2.障害のある児童生徒の教育に関する法制上の原則
(1) 教育の機会均等
上記の1989年教育法第2条及び第8条が教育の機会均等に該当する。しかし、インクルーシブ教育については法律上の明示的規定はない。
ただし、教育省の政策文書や人権委員会のレポートにはニュージーランドにおいてインクルーシブ教育を原則とする方向性が示されている。
教育省は2010年10月「全ての学校と子どもが成功するように(Success for All—Every School, Every Child)」というプランを出した。これは「完全なインクルーシブ教育制度を達成するための政府4ケ年行動計画(the Government’s four year plan of action to achieve a fully inclusive education system)」のことである。
ニュージーランドは、前述したように1995年にインクルーシブ教育を目指すための「特別教育2000」を策定し、実施してきた。この政策文書では「全ての子ども・生徒に平等の教育機会を提供する世界標準のインクルーシブ教育制度(world class inclusive education system)」を目標としていた。
この政策は、ニュージーランドの教育制度を大きく転換させることとなった労働党のロンギ政権下(1984年〜1990年)で策定された1988年の「明日の学校(Tomorrow’s School)」(ピコット報告とも言われる。)と、その法制面での具体化である1989年教育法や1993年制定のナショナル・カリキュラムを下敷きにしつつも、当事者団体や保護者などの要求を踏まえ特別な教育的ニーズへの財政措置に関わる修正やインクルーシブ教育の理念を示したものである。しかし、そもそもインクルージョンを明確に定義づけてはいなかった。1995年というと、国民党政権(ロージャー首相)の時代(1990〜1999年)であるが、大幅な規制緩和政策は引き継がれたのである。
これ以降、ニュージーランドの特別教育は「特別教育2000」に沿って展開されてきた。
インクルーシブ教育の考え方は徐々に現場に浸透するようになってきた。今回、訪問した寄宿舎のあるろう学校を併設しているケルストンろう教育センターでは、「私たちはインクルーシブ社会の一部である。」との立場から、地域の学校で学ぶ生徒とその指導にあたる教員への支援の充実を力説していた。
これを裏付けるかのように、教育省のHPでは「インクルーシブ教育(inclusion in education)は生徒とスタッフ全員の価値を認めるものである。インクルーシブ教育は全ての子どもや青年が地域の学校(local school)の文化、カリキュラムさらに共同体に参加するのを支援する教育である。エスニシティ、文化、障害あるいはその他の要素に関係なく、全ての子どもの学習や参加にとっての障壁(barriers)は実際に縮小されている。そのため、子どもたちは自分たちが置かれている教育状況への所属意識や共同体の一員としての自覚を感じるようになってきている。」143とインクルーシブ教育を位置づけている。
しかし、世界標準のインクルーシブ教育が実現されてきたわけではない。最近出された三つの文書がその証拠である。
ア 2009年9月28日〜30日に開催された会議で配布された文書(全文翻訳は別添翻訳資料集を参照のこと)
この文書によると、子どもの権利コミッショナー事務所(Office of the Children’s Commissioner)には2つの相談窓口があり、障害のためにカリキュラムの全部又は一部から除外され、教育へのアクセスを否定されている子どものことを心配する親、専門家(professionals)、又は、校長や教員から寄せられる質問の多くを処理している。ここだけでなく、同様の苦情が人権委員会、家族問題委員会(Families Commission)、子ども・青年法律相談センター(Youth Law)、知的障害者支援の会(IHC)、オンブズ事務所などの機関にも寄せられている。
それはインクルーシブ教育がいまだにニュージーランドで確立していない証拠である、といってよい。
同文書で指摘されている以下の実例には、日本でもよく見られるものも含まれている。
- 障害のある生徒は「行儀が悪い」と帰宅させられる。
- 行動的障害のある生徒は学校行事のキャンプに行く許可が下りない。
- 教育評価機関の訪問期間中、親は問題のある子どもを家に居させるよう指示される。
- 多様な教育のニーズのある生徒が学校理事会による懲戒手続きでヒアリングされたり、あるいは、医学的症状が認められる行動や障害を理由として学校から排除される。
- 身体的及び知的ニーズが高い生徒は多くの資源を必要とするため、野外活動に参加できない。
- 多様なニーズのある子どもは頻繁に同級生のいじめの対象となる。
- また教育法(Education Act s8)に違反しているのに、多様なニーズのある生徒が、出席日数が少ないという理由で学校行事の全てに参加することができない。
- 昼休み時間に教室内に残ることが許可されない。
- 一週間のうち数日のみ通学が許可される。
- 教員補助員による支援への資金援助がされる時間帯のみ通学が許可される。
- 親が同伴できる時のみ子ども達の野外活動参加が許される。
- 子どもが継続的に通学できるかどうかは一週間当たりの学校での「親による支援(parent—helping)」次第であるとして、実際には教員補助員による指導時間を可能な限り長くするよう別の形で要求される。
- 教員補助員の報酬への上乗せを親が求められるなど、教職員への報酬に対しても親の協力を見込まれる。
- 別の学校であれば子どものニーズを満たしてくれる可能性があるという理由から、子どもを任意に退学させるよう圧力をかけられる。
- ORRSによる資金がないといわれ入学を拒否される。
- 資金の有無にかかわらず完全に入学を拒否される。
イ 2010年3月19日 人権委員会「特別教育2010評価に関する意見具申」(Submission on the Review of Special Education 2010)
人権委員会は「インクルーシブ教育への権利」について、次のように政策を批判する形で触れている(下線は引用者)。
ニュージーランドではインクルーシブ教育への権利はまだ確立されていない。1989年教育法第8条第(1)は「特別な教育的ニーズのある者は(障害又はその他の事由かどうかに関係なく)、特別な教育的ニーズのない他の者と同じく、国立学校に就学し、そこでの教育を受ける権利を有する。」と認めている。ダニエル対司法長官(Attorney General)裁判に関する控訴院の判決では、この権利は手続き的権利であるとして、教育制度についての実定法(statutory regulation)によってかなえられるものであると判じた。
<中略>
ニュージーランドにおける障害のある生徒に対する教育制度は他の多くの国と同様に非常に込み入っている。主にリソースセンターとして活動する特別学校、伝統的な特別学校、通常学校内の多くの専門的支援のある特別ユニット、さらに、インクルーシブ教育を行おうとしている多くの通常学校がニュージーランドには存在する。これを新たなインクルーシブ制度へと移行させるには総合的な移行計画が必要である。
<中略>
本委員会は障害児のこれからの教育については4つの選択肢、すなわち、現行制度、特別支援学校の廃止、リソースセンターとしての特別学校、特別学校への自由なアクセスを保障する改善を図る現行制度、を提示している。これまでの議論を踏まえ、本委員会はリソースセンターとしての特別学校の存続案を支持する。将来においては特別学校がなくなり、全ての学校が平等の機会を求めて就学する子どもを教育することができるようになるかも知れない。しかしながら、基盤と教員教育が適切に実施されるまでは、本委員会はリソースセンターとしての特別学校の存続という選択肢を支持する。
(注)下線部分にある「ダニエル対司法長官裁判」とは、ニュージーランドで1995年に新たな政策として「特別教育2000」が作成された時に、障害のある子どもをもつ親15人が政府を相手どって、この政策に基づく特別学級・ユニット・クリニックの廃止計画は法律に違反するとして提訴した裁判である。第一審の高等法院では原告側の勝訴になったが、第二審の控訴院では原告の主張の一部は認められたものの、教育省の対応は1989年教育法の第3、8、9条を侵すのもではないとされた(2003年)。なお、上述したように、特別クリニックは現在、存在しないが、特別学校だけでなく、特別学級やユニットは残っている。
ウ 教育評価機関(Education Review Office)「高度ニーズのある生徒のインクルージョンについて」(2010年6月30日発表)
今回の評価は学校がどの程度、高いニーズをもつ生徒を受け入れ、彼らが教科学習や、学校での課外活動や社会生活に参加できているかを検証したものである。ニュージーランドでは約3%の生徒が高いニーズを持つと見なされている。対象としたのは、インクルーシブ教育を積極的に行っていると報告している229校。
しかし、この内30%強の学校ではある程度インクルーシブ教育への取組を行っているが不十分であり、20%の学校はほとんどインクルーシブ教育の取組を実践していない、と評価されている。
またインクルーシブ教育を進める運動体である「知的障害児」(Intellectually Handicapped Children:IHC)や「インクルーシブ教育推進グループ」(the Inclusive Education Group:ILAG)は、ニュージーランドの教育について、インクルーシブ教育制度にはほど遠いとの評価をしている。
1949年に創立され、約60年間活動を行ってきたIHCは2009年に新しい内閣の各大臣に向けに説明文書(briefing)を出している。教育大臣に宛てた説明文書で「インクルージョンという言葉は教育関係者の間でよく話されていますが、インクルーシブ教育は依然としてとして実現をみていません。分離的な教育の場に就学する子どもや若者がニュージーランドでは増え続けています。何人かにとっては分離的な場への就学は選択(choice)であるでしょうが、多くは通常学校への就学という選択肢は障害のある子どもや若者を支援することが出来ないし、また、場合によっては支援しようとしない制度によって否定されてきたのです。IHCは親、生徒、障害者団体、校長、教員その他とともにこの問題を長年訴えてきましたが、甲斐がなく実現していません。そこで、IHCは2008年7月に人権委員会に対し、障害のある子どもが地域の学校に完全に参加することを阻んでいる政府の政策や措置に対する苦情(compliant)を訴えたのです。」として、分離教育が進んでいる状況を批判している144。
IEAGが2010年に出した声明「インクルージョンと学校改革に関するLEAG2010年声明(IEAG Position Statement on Inclusion and School Change 2010)は「我々は何年もの間、個々の学校ではわずかではあるが変化がみられたと考えている。しかし、全くそれでは不十分である。多くの通常学校が準備不足であり、また、障害のある生徒を教える上での支援を受けていないために、あまりにも多くの家族が依然としてインクルージョンを選択することができていない。<中略>ニュージーランドの通常学校は、物理的には資源の面でも教員の知識や実践の面でも全ての子どもを受け入れるように意図されてはこなかった。我々は、障害のある子どもを我々の学校から排除することを止めることは価値観、理解、教室の運営方針(classroom strategies)を大きく換えることになると信じている。」と述べ、ニュージーランドの教育の現状を批判している。なお、ILEAはIHCに比べ歴史は浅く2007年に創立されている。またIHCとは違い、障害問題担当大臣のイニシアティブによって設置されたという経緯がある145。
これらの文書から判断するに、ニュージーランドにおけるインクルーシブ教育の確立は道半ばということができよう。
(2) 教育に関する権利規定
前述したように、全ての子どもの教育への権利は1989年教育法第2条に規定されている。しかしながら、上位法である1990年の権利章典(New Zealand Bill of Rights Act 1990)には教育に関する明示的規定はないのである。
障害のある児童生徒についても同様であり、上述の1989年教育法第8条が相当する。
ただし、注目しておきたいのは、2006年に「ニュージーランド手話言語法」(New Zealand Sign Language Act 2006)が制定され、手話が、英語、マオリ語に続く第三言語として認められ、カリキュラムにも反映されるようになったことである。
(3) 教育における差別規定
教育における障害のある児童生徒への差別に関わる直接の規定はない。
しかし、教育における差別だけでなく、あらゆる差別禁止に関わる1993年の人権法(New Zealand Human Rights Act 1993)が適用されるようになっている。これは1990年権利章典の第19条(1)「全ての人は1993年人権法における差別自由に基づく差別から自由になる権利を有する。」で担保されている。
同法は2001年の改正で、公的部門における違法な差別問題にも適用されるようになっている(同法第1A部第20条第J号)。違法な差別(unlawful discrimination)の原因となる事由は、性、婚姻関係(marital status)、宗教的信念、倫理的信念、皮膚の色、人種、民族的出自(ethnic or national origin)に続いて障害(disability)、その後に年齢、政治的意見、雇用状況、家族状況、性的志向(sex orientation)と規定され、障害は以下の7種になっている(第21条第1項)。
- 身体障害又は身体損傷(physical disability or impairment)
- 身体疾患(physical illness)
- 精神疾患(psychiatric illness)
- 知的障害・損傷又は精神的障害・損傷(intellectual or psychological disability or impairment)
- その他の精神的、生理的、解剖学的構造もしくは機能の欠損又は異常(any other loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical structure or function)
- 盲導犬、車椅子又はその他の補助手段への依存(reliance on a guide dog, wheelchair, or other remedial means)
- 疾患の原因となりうるものが体内に存在している状態(the presence in the body of organisms capable of causing illness)
これらの事由に基づく違法な差別に関する規定は教育機関にも適用される(同法第57条)。第57条第(1)項の規定は以下の通りである。ただし、第58条に例外規定があり、例えば性別や人種別の学校などに関しては性や人種を事由として入学を認めないことは差別ではないとされている。
教育機関、教育施設の管理責任のある当局、もしくは、教育施設の運営又は教育施設での教育に責任を有する者は、差別禁止の事由により、以下の行為を行った場合は違法な差別となる。
(a) ある者の生徒又は学生としての入学を拒否し、又は、認めない。
(b) 他よりも不都合な条件(less favourable terms and conditions)をつけてある者を生徒又は学生としての入学を認める。
(c) 教育施設が提供する何らかの利益又はサービスを否定し、又は、制限する。
(d) 生徒又は学生としてのある者を排除し、又は、他の不利益を与える。
この中で、 (c) はいわゆる合理的配慮の否定に該当するものと考えられる。地域で青少年の権利擁護や法律相談をしているティノ・ランガティラガンナ・タイタマリキ地域青少年法律センター(YouthLaw Tino Rangatiratanga Taitamariki)146によると、これは差別に他ならないことは、特別な教育的ニーズをもつ青少年に対する差別についての次のような説明からも明らかであろう。
「差別」というのは正当な理由がないのに他の人とは違う扱いをされることを意味しています。例えば、もしもあなたが病気のせいや車椅子を使っているという理由で学校に通うことができないと言われたとすると、これは明らかに障害を事由にした差別となります。また、もしもあなたが他国出身だという理由で、学校に来るなと言われたとすると、これは人種を事由とした差別となります。これらの事由は、あなたが教育を受けることを妨げる正当な理由ではありません。法律により認められない差別の「事由(ground)」(理由)は数多くあるのです。
人権法と権利章典は性、宗教的又は倫理的信念、皮膚の色、人種、障害、出身国(national origin)、政治的意見、雇用状態、家族状況、性的指向、婚姻状態、年齢(16歳以上)を事由とする差別を禁止しています。
法律に反する差別は、労働や教育といった分野でのある対応についても妥当します。時として、学校は障害のある人を除いて全ての人を対象として何かを行おうとします。例えば、もしもあなたが難読症であり、読み書きが難しい場合には、あなたは他の人と同じ時間で試験問題を読んだり、答えを見直したりすることはなかなかできません。そんな時、学校は試験開始時間を早めるなど時間を増やすことで、その障害に配慮することが出来るはずです。それなのに、あなたの学校が試験の実施に際してあなたの障害を考慮しないようであれば、これは「間接的差別」になります。同じ時間の設定は全ての人にとって同じように適用されるという理由で、これは正当であると学校が主張するのであれば、この間接的差別をあなたはやめさせることができます。全ての人に適用される同じ規則は障害のある人々にとっては不公平であるからです。
しかしながら、差別や権利侵害があった場合の挙証責任(burden of proof)についての明示規定の存在については確認できていない。
3.障害のある児童生徒の学習保障
(1)就学先の決定手続き
ニュージーランドでは、1989年教育法第8条に基づき、特別な教育的ニーズを持つ子どもは国立の学校に通う権利を有しており、また、就学先として、通常学級、特別学級・ユニット、特別学校を選択する権利もある。具体的には親・保護者が選択することが多い。
ア 通常学校への就学の場合
障害のある子どもが通常学校の通常学級に就学しても資金を伴う支援を必要としなければ、学校理事会が親・保護者の選択をそのまま認める。しかし、何らかの資金を伴う支援が必要な場合にはアセスメントが行われ、その結果に基づく支援の方法・内容について、保護者と教育省との合意に基づき、子どもを通常学級、特別学級又は特別ユニットにさせることになる。学校理事会は基本的にはこの合意に基づく保護者の選択を拒否することはできない。就学することが決まれば、個別の教育計画が作成される。
以下は、就学前にあるいは就学後に、特別な教育的ニーズに応じた支援を得るための手続きを教育省が説明した内容である147。
特別な教育的ニーズをもつ何人かの子どもたちは、学校に就学する前に早期介入スタッフによってそのニーズが評価されているでしょうし、学校に就学すればそれに応じたサービスが提供されます。
そうでなければ、子どもの学習や発達について心配は就学後に起きる場合があります。
ご自分のお子さんの学習と発達を心配される親御さんは担任の先生や校長先生にお子さんに必要な支援やサービス、また、適切な支援の範囲について話したいと申し出てください。
もしも親御さんがお子さんの学校と話し合っても心配があるようでしたら、教育省の生徒支援マネージャー(National Operations student support manager)に話をしてください。そこが、次に何をしたらいいか教えてくれます。そこへの連絡の詳細は教育省の地区担当特別教育部(District Ministry of Education, Group Special Education:GSE)に聞いてください。
特別な教育的ニーズを持つほとんどの子どもや若者は学校やカレッジから支援やサービスを受けています。もしも必要なら、学校は、専門教員(specialist teachers)を手配したり、追加的なサービスや資源が必要かどうかの決定をするためにお子さんのニーズを評価(assess)できる教育省のGSEへ照会することができます。もっとも適切なプログラムと支援とが行えるようにお子さんの学習ニーズを評価することが非常に大切になっています。
評価
評価の責任はかなりの程度、他の機関の専門家の支援を受けつつも担当教員と学校スタッフにあります。評価で得られた情報は個別の教育計画(individual Education Programme)の基礎になります。特別な教育的ニーズを持つ子どもと一緒に活動する専門家は、専門教員、言語療法士(speech—language therapists)、特別教育アドバイザー(special education advisors)、作業療法士(occupational therapists)、心理療法士(psychologists)、心理士(psychologist)、ろう児アドバイザー(advisors on deaf children)などです。
子どもや若者の評価は、困難があるかどうか、その程度はどうか、子どものニーズは次のどれかを確かめるものです。
- 学習のための特別授業(special teaching)
- 彼らが見るのを手助けするための特別設備
- 彼らが聞き取るのを手助けするための特別施設
- 彼らが動き回るのを手助けするための特別設備
こうした評価は時間をかけて行われ、次のうちの一つあるいは二つ以上に基づいて行われることになります。
- 教室や遊び場など異なる状況での観察
- 正規の標準テスト
- カリキュラムを土台にした評価(a curriculum—based assessment)
- 学習環境評価
- 学習方法、例えば、もしも授業が口頭ではなく文字だけだった場合によって学習できるかどうかの評価
- 出席状況を含む生徒の活動記録の評価
- 生徒の学習(work)のポートフォリオ
- 自己評価
評価を効果的にするためには信念のシステム(belief system)や文化的期待(cultural Expectations)の多様性を考慮する必要があります。評価情報は評価の時点で、あるいは、終了後可能な限りすぐに生徒や家族にも共有されるようになっています。
評価はお子さんのニーズを見出すのに役立てるものであって、ご家族にストレスを与えるものではありません。関係者による特別の支援や理解があればこの過程はよりスムーズになります。
ニュージーランドの特別教育は特別な教育的ニーズのある子どもや若者を支援するため非範疇的アプローチ(non—categorical approach)を採用しています。つまり、医学的診断(diagnostic labels)によるのではなく必要な支援という観点によるアプローチなのです。
評価過程から得られた情報はIEPの基礎となります。
評価結果による情報に基づき、個別の教育計画が作成される。これは特別な教育的ニーズのある生徒のために作成される計画であり、生徒の目標とその目標が達成されるべき時期を概括するものである。それには、生徒が目標を達成できるのに必要な学習指導方針(teaching strategies)、リソース、モニタリング・支援さらに評価が盛り込まれる。
個別の教育計画は親・保護者、担任の教員、子ども(子ども自身が参加を希望する場合)、適切な専門家による話し合い(meeting)で作成される。その目的は、現状の能力(strengths)を把握し、短期・長期の目標を設定し、評価を記録することにある。
さらに、以下のことを明確にすることも目的としている。
- 子どもの学習を手助けする授業実践
- その子にカリキュラムを教える方法、リソース、教材・教具(materials)の改善
- 子どもが必要とする追加的で特別の設備
- 必要な場合に、個人的ケア(personal care)を行う最善の方法
- 親・保護者や家族が家庭での学習計画を支援する方法
- 目標達成に向けての子どもの成長を見守り、評価する時程
個別の教育計画は年に少なくとも2回親・保護者との話し合いで修正されるようになっており、最初に作成に関わったメンバーで次の計画を作成する。親・保護者は話し合いが終わった後、毎回修正計画のコピーを受け取るようになっている。
こうした就学に際しての評価や個別の教育計画作成に関する実例をここで紹介しておきたい。この例を紹介してくれた日本人の母親によると、特別な教育的ニーズに関わる評価に際しては医学的な評価は不可欠となっているということであった(この評価の位置づけが教育省の説明では十分に明確とはなっていない。)。
- 2001年1月19日生まれの息子さんは2006年2月に地元のTorbay初等学校(小1〜小6、全校400人程度)に就学。ニュージーランドでは、誕生とともに助産所(Plunket)という機関に登録され、そこで0歳から5歳までは成長具合の診断及び育児等について相談を受けるようになっているが、そこでは何も指摘されたことがなかった。2006年4月(0学年year 0)に、問題を担任の先生(担任は、5,6学年以外は毎年変わる。)から指摘された(Torbay小学校では、小1、小2の生徒全員が必須科目として、PMP=Perceptual motor skill programを受けることになっている。このPMPにより、何らかの問題のある子どもを見つけることができる。)。この時に、学校から要請をうけて、専門医のDr.Wattの診察を受け、Mild Dyspraxiaであるという診断書をもらい、Dr.Wattの推薦をうけたプロ・エドで作業療法を受けるようになった。その後、専門医からの診断書とプロ・エドでのアセスメントを学校に提出し、それを踏まえながら親、担任、学年主任、特別ニーズ教育専門の教員、さらに副校長と話し合ってIEPを作成した。内容としてはPMPをできるだけ多く参加させる、とか日々の学習では何を重点的に行うか、などが話し合われ、また、両親のすべきこととして、作業療法に行くこと、週一で作業療法士に学校に出張してもらう、などを薦められた。PMPへの参加は、Torbay小学校では低学年では必須科目になっているが、障害のある児童には、省ける授業があればPMPを優先させて受けさせている(PMPを受けることで恩恵が大きい場合)。
- 週一回の学校での作業療法士による支援では不十分と思ったのでGP(general practice: ホームドクター)に相談して、専門家を探し、私立病院の専門医(paedatrician)であるDr Wattを紹介された。彼によってdevelopmental dyspraxia(motor planning disorder)と診断された。費用は150ドルであった。
- 専門医により、私立のoccupational therapist(作業療法士)を紹介され、1時間半ほどのテストにより、作業療法士(Professional Education Centre: Pro—Ed Centreという主に発達障害の評価を行う民間機関に所属。この機関は2003年のThe Health Practioners Competence Assurance Actで設置されるようになった。)よりアセスメント・レポートを書いてもらうこととなった。経費は250ドル。しかし、2009年5月まで支援は認められなかった。そのため、土曜日に私費で作業療法を受けてきた。この時に漢方医(natural harbalist)を薦められ、そこにも通い、漢方薬を処方された。
- 2009年5月、4年生の時に、担任により学校生活中の行動に問題がある旨を指摘される。そこでGPに相談する(公立病院にしても私立病院にしてもGPを通す必要があるため。)。GPにより、地区の公立病院であるNorth Shore Hospital(ワイテマタ地区保健局(Waitemata Health Board) が管轄する4つの公立病院・医院の一つ)に予約を入れてもらう。その公立病院より予約を入れ、専門医による診察を受ける。地区保健局と教育省は障害児関係では一緒に活動するため、この診察のときには、RTLBのスタッフが同行した(ただし、スタッフの同行は、両親の意向及びスタッフの希望があった場合に行われると思われる。)。そこで軽度のADD(Mild ADD)との診断を受け、薬を試してみることを提案される。しかし、この時点では拒否。その後、投薬の検討を薦められたので、漢方医に相談し、量を増やす。しかし、担任の先生からは、際立った変化はない、との報告を受ける。2週間後に再度検診を受け、薬を試すだけ試してみよう、と結論を出し、投薬を開始。すると、すぐに担任の先生から、授業態度、集中力等が上がり、特に算数の学力が向上した旨の報告を受ける。そのため、2009年7月に、ABTによるフォローは不要となった。
- 2009年9月に学習支援の充実のために、私立の作業療法士のRick ChengさんにPsychological Educational Assessment Reportを2009年9月に書いてもらい、RTLBを通じて教育省に提出した。この時は時間がかかった(実際のテストはサイコロジストによって行われた。)。
- 2010年2月に、ラップトップが支給され、また、RTLBからの働きかけでMathletics(世界中で利用できる算数学習のサイト)の無料使用が実現した。
以上の流れを確認すると
誕生前後→plunketに登録→ 家庭・幼稚園→ 学校 (or 教育省)
↓ ↓ ↓
General practice(家庭医) ↓
↓ ↓
公立・私立病院の専門医の診断 ↓
↓ ↓
作業療法士によるアセスメント ↓
↓ ↓
早期介入スタッフや学校によるアセスメント
(アセスメントの時には外部の専門家が参加することが多い。)
↓
個別の教育計画
(資金がつかない支援もある。)
*****以下は追加情報***** - 個別教育計画は、両親、担任、RTLBのメンバー及び特別教育ニーズ・コーディネーターのミーティングで作成する。IEPで確認された週2時間の個別指導以外に、私的に経費を負担(1時間あたり16ドル)して毎日個別指導を受けている。
- 登下校での保護者の付き添いは4年生くらいまで。授業開始前(7:30〜8:30)と放課後に学童あり。1週間あたり100ドルかかるが、(低所得家庭には)補助がある。夏休みにはHoliday Programmeがあるが、保護者によるケアが中心。
- キャンプは4年で1泊、5・6年で2泊あり、いずれも平日であるが保護者がhelperとして参加する。学校の教育活動への保護者参加は多い。保護者の参加を可能とする環境は整っている。「家族のため」という理由で年休を取りやすい。子沢山の家庭には支援がある。
- 校区にある中学校7,8年生にはコンピュータークラスがあり、そこへは無条件では入れない。初等学校では音楽の時間がなくなった。体育は学校ごとに事情が違っているようだ。入学式はないが、卒業式はある。国歌は全校集会の時に歌うことが多い。制服はある。
- 医療面でいえば、GP(general practice)にかかる場合には費用(それぞれに違う。)がかかるが、その後公立病院で治療する場合には費用は不要(待ち時間が長い。)。私立病院の場合には経費がいるので、「私立医療保険」に入っている。公立病院は無料であるが、待ち時間が症状によって数週間から1年にわたる。公立の専門医、作業療法士を申し込むこともできるが、診察まで数カ月かかるため、教育省等に提出が必要なテスト結果(診断結果)を得るためには、私立に頼らざるを得ない(学習支援教材などは申し込んでからも、かなり実際に配布されるまで時間がかかるため。)。
- 教員も理解があり学校への注文はとりたててない。しかし、様々な経費の私負担があることや、社会的自立への不安はある。
イ 特別学校の場合
最初から特別学校への就学を選択する場合には、ORRSの受給の時と同じように、1989年教育法第9条の合意が必要となる。特別な教育的ニーズを持つ子どもが就学先を決める場合、基本的には子どもや親に権利があるとしながら、教育長官との間での合意が必要であると規定しているからである。ただし、第9条の規定では、特別な教育的ニーズをもつ子どもが就学先を決める場合には、通常学校であっても合意が必要であると読めるが、以下に整理する教育省HPではこれについては触れていない148。
(ア) 「第9条の合意」とは、子ども又は若者が特別教育サービスを受けるか、又は、特別学校へ就学することを認める、子ども・若者の親又は保護者と教育省との間の公的な合意(formal agreement)のこと。これは子ども・若者が、[1]ORRSなどの特別教育補助を受ける、[2]特別学校に就学する、[3]5歳前に就学する、[4]14歳以降も初等学校に在籍する、[5]19歳以降も中等学校に在籍する(ただし、21歳まで)ために必要である。
(イ) この合意による手続きの具体例
[1] ORRS:もし、ある生徒がORRS資金の資格があると証明されれば、確認レターが特別サービスを受けるための第9条合意とみなされる。
[2] —1 全日制特別学校(Day Special Schools)
もしも特別学校への就学を考えるとすると、あらかじめ地方の教育省特別教育部事務所(local GSE office)か特別学校とのコンタクトが必要となる。特別学校への就学のために第9条合意に申し込むかどうかを決定する時には助言を求めることができる。すでにORRS受給確認レターが届いている子どもでも、特別学校への就学には第9条合意が必要となる。まだ、受給資格の確認が取れてない子どもの場合には、特別学校の校長と教育省特別教育部の地区担当責任者(the Ministry of Education, Special Education (GSE) district manager)の勧告があれば、特別教育部地域責任者(the GSE regional manager)の承認が得られる。
—2 国立寄宿制特別学校と地域保健学校(National Residential Special Schools and Regional Health Schools)
これらの学校に入学する場合には、就学申し込みは当該校の入学許可委員会に提出する。しかし、第9条合意についてのプロセスは上述の特別学校とほぼ同じである。
* [3]、[4]、[5]は省略
(ウ) 第9条合意ができなかった場合には、親はその決定の再考を要請することができる。まず、教育省特別教育部地域責任者に合意不許可の再考要請を伝えなければならない。それを受けた地域責任者が、特別学校校長、教育省特別教育部地区責任者、教育省生徒支援チームのメンバー1名、親組織代表、通常学校の校長で構成される地域委員会(a regional panel)を招集する。同委員会は、第9条合意不許可の原決定を認めるか、あるいは、第9条合意を求める申請を承認するかを決定する特別教育担当副長官に必要なデータすべてと勧告を送付する。もしも、次官補(Deputy Secretary)が合意不許可の原決定を認めた場合には、1989年教育法第10条に基づき、親は公的な調停手続き(formal arbitration process)を取ることができる。その際には、事前に手続きについての情報を得るために地方のGSE事務所とコンタクトを取ることができる。
(注)
以下の図は、教育省が2010年に行った2010年特別教育評価に際して、関係者に示した討議資料に掲載された就学先の簡単な図式である。これを見ると、特別学校への就学だけ教育省の承認が必要となっている。しかし、ORRSを得て通常学校に就学する際における上述の第9条規定とは少し異なっている。
(2)カリキュラム
ナショナル・カリキュラムは次官が教育法第60条Aにしたがって国家教育指針(National Education Guidelines)を作成し広報紙に公表することになっている。指針はまず国家教育目標(National Education Goals)を定め、それを達成するためのカリキュラム基本政策ステイメント(授業の基本方針や評価)と国家カリキュラムステイメント(学習すべき知識や技能の明確化)、さらに、実際のニュージーランド・カリキュラム(原理、価値、キー・コンピテンシー、学習領域、達成目標)さらにカリキュラム実施に関する指針(学校カリキュラムの運営や実施報告などについての学校理事会への指示)で構成される。全体の構造は以下の通りになっている。
ニュージーランド・カリキュラムでは、高い期待、ワイタンギ条約の尊重、文化多様性、学び方の学習、地域関与、一体性、未来志向と並んで、インクルージョンが原則として提示されている。ここに示されたインクルージョンについて、「このカリキュラムは非性別主義、非人種主義、非差別的であり、生徒のアイデンティティ、言語、能力及び才能が確実に認識され肯定されるとともに、彼らの学習ニーズに対処することを保証する」ものとなっている。様々な事由による排除(exclusion)を否定したものであり、また、障害に特化したものでもない広い原則となっている。
なお、国家教育目標の7番目には、「特別ニーズを見つけ出し、適切な支援をすることで特別支援を持つ生徒の学習が成功すること。」が示されている149。
こうした指針や国家カリキュラムに沿って学校で具体的なカリキュラムが編成されるようになっている。なお、ニュージーランドの、特に初等学校では教科書はほとんど使用されていない。
ニュージーランド子ども委員会はニュージーランド・カリキュラムについて「インクルージョンはニュージーランドのカリキュラムの根幹である。このカリキュラムは社会的及び生物学上の性別、民族、信条又は能力や障害、社会的、文化的背景又は地理的位置に関わらず、公立移管私立学校も含めて英語による教育が行われている国立校の生徒全員に適用される(MoE, 2007, p. 6)。文書に記されているように、『カリキュラムは非性別主義、非人種主義、非差別的であり、生徒のアイデンティティ、言語、能力及び素質が確実に認識され肯定されるとともに、彼らが学ぶためのニーズに対処することを保証する。』」(OCC:万人の学校:ニュージーランドにおける、子どものインクルーシブ教育への権利 別添翻訳資料集の資料3を参照)
また、人権委員会の2009年報でも「1989年教育法の第60款A(1)により、教育長官相には国の教育目標、カリキュラム方針及び声明並びに教育行政指針を発表し、学校の規則の枠組みを決める権限が与えられている。全国教育目標の1及び7並びに全国行政指針1及び5は、ニュージーランドの教育課程における『高い期待』と『インクルージョン』の根本理念であると同時に、特に障害のある生徒の持つ潜在能力の実現に関わるものである。」と評価している。
ニュージーランド・カリキュラムにおいては、このようにインクルージョンが基本理念の一つとなっている。
(3)就学や学習保障上のトラブル・権利侵害への対応
上述のように、親や保護者は各種の機関との相談を経て、最終的には保護者自身がその子どもの就学先を決定するようになっている。しかし、1989年教育法でも教育省のHPでも特別な教育的ニーズを持つ子どもの就学先の決定には保護者と教育省との合意が必要とされている。
また、1989年教育法だけ読むと、場合によっては次官が就学先を指示(direction)するとも規定している(もちろん、それに対して見直しを求めることはできるようになっている。)。
それゆえに就学先をめぐるトラブルが生じてくるのであろう。就学に際してのトラブルや苦情に関しては、まずは教育省が窓口になるようであるが、さらには子どもへの関わり方における差別や人権侵害に関する苦情には、主に、人権委員会、オンブズマン、子どもの権利コミッショナーが対応しているようである。
ア 人権委員会報告
就学先の決定先をめぐるトラブルや学校での人権侵害が生じた場合、一番多く、訴えがなされるのは人権委員会である。
ニュージーランドの人権委員会は、1977年の人権委員会法(Human Rights Commission Act 1997)で設置された独立機関で、多様性に価値があり、人権が尊重され、誰もが偏見や不法な差別から自由になることができる公平で、安全でしかも正義のある社会のために活動している。その任務は大きくは以下の4点。
- ニュージーランドにおいて人権尊重を弁護し、促進する。
- ニュージーランドにおいて個々人間や多様な集団間の調和的な関係づくりを奨励する。
- 平等な雇用機会を先導し、監視し、助言する。
- 差別について情報を提供し、苦情や差別の解決を支援する。
人権委員会が扱う差別問題に障害を事由とする差別も含まれていることは前述したが、具体的に差別が起きる問題として、人権委員会があげているのは8領域である。
- 政府や公的部門の活動
- 雇用
- 教育へのアクセス
- 公共の場所、乗り物、施設
- 商品やサービスの提供
- 土地、住宅、宿泊設備(accommodation)の提供
- 産業・職業協会、資格付与団体、職業訓練機関
- パートナーシップ
人権委員会を通しての紛争解決の過程については、既に「平成20年度『障害者の社会参加推進に関する国際比較調査研究』委託報告書」で紹介されている(301頁)が、参考のため紹介しておく。
さて、障害のある子どもの教育にかかわる差別については、2009年の人権委員会報告『障害児の教育への権利』では、「学校がもしも障害を理由として生徒の入学を拒否した場合、あるいは、障害のある生徒に他の生徒と比べて良くない扱いをした場合、1993年人権法(HRA)に則り、違法な差別だと訴えることができる」との説明をしている。
この人権委員会が2002年以来関わってきたこの問題は261件であり、2002年に52件に上った後、2003年から2006年にかけ全体としては下降したが、最近2年間で反転し、2007年と2008年には苦情と問い合わせの件数は急増している。2009年3月18日時点で、委員会はすでに12件の苦情を受けており、5件の苦情と問い合わせのあった2008年の同時期と比べて2倍以上に上っている。
2002年から2005年までは、4分の3がインフォライン(問い合わせ受付電話窓口)サービスで扱われ、解決したが、2006年以降は、3分の2以上が更なる対処が必要なためにインフォラインから別のチームへ、大部分が紛争解決チームの調停人へ回されている。
過去7年間に受けた261件の苦情と問い合わせの内、インフォラインでの対応で解決しなかった126件には更なる対処が求められた。その内訳と結果は以下の通り。
| 結果 | 件数 | % |
|---|---|---|
| 未解決の苦情 | 14 | 11% |
| 調停実施 − 解決 | 11 | 9% |
| 調停実施 − 一部解決 | 3 | 2% |
| 調停実施 − 失敗 | 7 | 6% |
| 調停要請 − 学校や法的管轄に問題があり進展せず(資金問題) | 4 | 3% |
| 調停者のその他支援により解決 | 6 | 5% |
| その他の情報や調停者、人権委員会スタッフによる支援 | 25 | 20% |
| 苦情を出した者や人権委員会により調停プロセスが適切とみなされなかった − 支援進展無し | 8 | 6% |
| 人権委員会の役割が不適切であったため、その他の機関が関与 | 17 | 13% |
ところで、これらの苦情のなかで、73件(28%)は注意欠陥多動性障害(ADHD)関連、26件(10%)は自閉症の生徒、17件(6.5%)はアスペルガー症候群の診断を受けている生徒となっている。いわゆる発達障害に関連する問題が多くなっているようである。
また、60%の苦情と問い合わせが以下の4つの問題に関連している。
- 子どもの就学にかかわる問題(学校が子どもの就学を認めないか、認めたとしてもごく限られた時間の就学しか認めない(51件))。
- 障害、あるいは、障害が原因となる行動を理由として停学又は退学させられた(43件)。
- 障害のある生徒のための教員補助員など特別な支援のニーズと財源確保(44件)。
- キャンプや校外学習など、学校の様々な活動への障害児の完全な参加の可否(24件)。
人権委員会を通じた支援やその他の調停によって問題が解決しなかった場合、ニュージーランドでは人権審議裁判所(Human Rights Review Tribunal)での解決方法があるが、就学問題でこの裁判所で争われた事件はないようである。
イ 子どもの権利コミッショナー事務所(the Office of Children’s Commissioner)
ニュージーランドの子どもの権利コミッショナー事務所は、最初は1989年の「子ども、若者とその家族法(the Children, Young Persons and Their Families Act 1989)」で創立され、子どもの権利コミッショナー2003年法(the Children's Commissioner Act 2003)になって子どもの権利問題を扱う機関となった。
子どもの権利コミッショナー事務所で扱われる、障害のある子どもの教育問題に関わる苦情については、140・141頁で紹介しておいたが、人権委員会に次いで、特別支援教育についての苦情が寄せられる機関となっている。
子どもの権利コミッショナーは特別教育に関わって数多くの差別が存在するとして、教育省が行った「特別教育評価2010」に際して、かなり強烈な問題提起をしている。一部を要約して紹介しておこう。
2009年の博士論文でアリソン・カーニー(Alison Kearney)が障害のある生徒の排除について分類している。アリソンによると、それは、就学又は全時間出席の否定、カリキュラムへのアクセスや参加の否定、いじめ、基金に関しての教員や校長の不適切な考え方や扱い、学校スタッフによる介護・子どもの尊重・責任の欠如、教員の知識や理解の不足、家庭と学校スタッフとの貧しい関係、教員補助員に対する排除的な考え方や扱いである。
こうした事例で浮かび上がってくるのは、親を当該の子どもの専門家として、ともに子どもの幸福のために協力するパートナーとして学校が対応していないという現状。また、学校と家庭との間の葛藤を解決する法的な義務(legal requirement)が政府には課せられていない。1989年教育法では、例えば親擁護委員会(Parent Advocacy Boards)による親擁護(the provision of advocacy for parents)は意図されていないし、求められてもいない。同法にある「相談(consult)」は「擁護」や「問題解決(resolution of issues)」といった概念を含んでいる、また、含むように拡大できるという議論もありうる。しかし、「相談」といいながら、手続きを明確にしていないと、実際には学校は親や子どもを排除する権限をもった機関となってしまう。したがって、子どもの権利コミッショナーは、学校は透明で周知徹底されたシステムを作り、生徒や家族が学校に対して意見を述べ、懸念を表し、苦情を言えるようにすることを強く勧告する。
OCCによる調停はその一部である。教育省との前回の合意にもとづき、OCCは家庭と学校との間の問題解決を進める役割を果たしてきた。OCCによる調停は、代替的な苦情処理過程の一つなのである。
子どもの権利コミッショナーは、このように学校自体に苦情処理や紛争解決のシステムを作り上げるように提言しているが、逆にいえば、まだまだ第三者の介入を必要とするような差別問題が起きていることの証拠である。
ウ オンブズマン(Ombudsmen)
ニュージーランドでは1962年のオンブズマン法(Parliamentary Commissioner (Ombudsman)Act 1962)で、公的サービスを監視し評価する機関としてオンブズマンが設置されている。その後、1975年から1987年にかけて法改正でその権限が拡大されてきた。しかし、オンブズマンは拘束性のある決定をする権限を有するものでななく、調査をし、報告や勧告を行うだけである。
2009/2010オンブズマン報告によると、教育へのアクセスに関する苦情(complaints)は相当あるが、苦情の対象となるのは、学校理事会、第三段階教育機関(the Tertiary Institutions)、教育省、ニュージーランド資格当局(the New Zealand Qualifications Authority)、第三段階教育委員会(the Tertiary Education Commission)、教育評価機関、ニュージーランド教員審議会(the New Zealand Teachers Council)などである。
2009/2010オンブズ報告では特別教育に関わる苦情については触れていないが、2008/2009報告では触れている。しかしながら、詳細な内容や解決したのかどうかについての報告はなされていない。
なお、2009/2010報告では、2008年に障害者権利条約を批准したので、第33条の条約の実施に関する独立の監視機構としての役割を果たすため、人権委員会や障害者団体との協働活動を始めたいと述べている(この点について、2011年3月のオークランドの本部でのインタビューで聞いたところ、まだ具体的には動いていないということであった。)。
エ 保健・障害問題コミッショナー(Health and Disability Commissioner)
保健・障害問題コミッショナーは1994年の保健・障害問題コミッショナー法で設置され、同法で規定された権利規定(a Code of Rights)に基づき、保健・障害関係サービス利用者(consumer)の権利擁護を目的としている。
権利規定で掲げられている権利は、[1]尊敬をもって処遇される(be treated)権利、[2]差別なく公平に処遇される権利、[3]尊厳と独立への権利、[4]基準を満たしたサービスを受ける権利、[5]効果的なコミュニケーションへの権利、[6]情報を完全に受け取る権利(Rights to be fully informed)、[7]情報を得た上での選択や情報を得た上での同意の権利(Rights to Make an Informed Choice and Give Informed Consent)、[8]支援への権利、[9]教育や調査に参加する権利(Rights in Respect of Teaching and Research)、[10]苦情を訴える権利(Right to Complain)であるが、それぞれの権利より詳細に規定されている。サービスの提供者はこの権利を保障する義務がある。
この権利規定は全て特別教育にも適用されるが、特に第4、5、10の権利が重要とされている。障害のある子どもの就学問題で、同コミッショナーへの苦情処理申請がなされることが想定されるが、2010年の年報をみる限り、具体的な事案は紹介されていない150。
以上、差別や不当な扱いに対する苦情や不服を申し立てる第三者機関を4つ取り上げた。
先述した教育省が2010年度に行った「特別教育評価2010」で、「物事がうまくいかなくなった時に、問題解決にどんな手だて(arrangements)が取られるべきでしょうか。」という質問に対して、「問題を予防し、最小限に抑えるシステム」、「明確な不服申し立てのプロセス」、「早期の、内部的な解決」といった意見とともに、「第三者のアドバイス(Third party advice)」、「権利擁護(Advocacy)」、「調停(Mediation)」それに「独立した審査及び仲裁の手続き(review and arbitration process)」が挙がっていた。これまでのところ、ニュージーランドでは人権委員会とOCCの役割がかなり大きいといわなければならない。
4.今後の見通し
ニュージーランド教育省は2010年10月に「全てが成功するように:全ての学校、全ての子ども(Success for All: Every School, Every Child)」という政策を公表した。これは、ニュージーランドで完全なインクルーシブ教育制度を完成させるための政府4ケ年計画であり、その基本をなしているのは教育法、障害者権利条約そして2001年のニュージーランド障害者問題方略(the New Zealand Disabled Strategy)」である。
さらにこの計画策定には二つの評価作業が影響を与えている。
1) 教育評価機関の評価
前述したように、教育評価機関は2010年6月に「高度ニーズのある生徒のインクルージョン」という報告書を出している。
ここで高度ニーズのある生徒というのは、134頁の三角形の上位に該当する約3%の最高度ニーズのある生徒であり、この生徒たちが通常学校でどんな受け入れられ方をしているかを同機関が評価した結果での報告である。同機関は、高度ニーズのある生徒が主流のクラスで学ぶことは望ましいとの立場に立って、実践的な観点から評価を行った(とはいえ、同機関は主流から外れている特別学校や特別ユニット、さらに、自宅学校(homeschooled)で学ぶことも認めている。)。
評価は2009年度の3学期と4学期に、中等学校30校、初等学校199校に対して行われた。評価の観点は、[1]インクルーシブな学校という文化を打ち立てる倫理的基準とリーダーシップを備えていること、[2]高度ニーズのある生徒のインクルージョンを認識し、支援する組織の整ったシステム、効果的なチームワーク、建設的な関係ができていること、[3]高度ニーズのある生徒をインクルードするための複雑で独特の試みをマネージする革新的で柔軟な実践を行っていること、であった。
今回の評価では、30%強の学校がインクルーシブ教育の実践をある程度行ってはいたが、システム、授業、態度さらに方法など学校全体としてインクルーシブネスが弱かった。その結果、教科、課外活動、学校での社会生活への参加が十分ではなかった。
20%の学校ではほとんどインクルーシブ教育の実践がみられなかった。これらの学校では高度ニーズのある生徒のインクルージョンについての倫理的、職業的リーダーシップが欠如しており、その生徒たちは教科、課外活動などに全く参加できていなかった。
同報告書は、今回の評価をふまえて、学校スタッフに対しては、高度ニーズのある生徒が学校生活全体でどの程度インクルージョンされているかを評価するために、報告書に盛り込まれた評価データ、事例研究、自己評価のための質問、インクルーシブな授業の指標を利用し、また、これらの生徒がインクルードされていない点はどこかを確かめ、既に当該学校で実践されているインクルージョンを拡大する計画を実行するように求めるともに、教育省に次の3点を求めた。
- 効果的で、根拠に基づく(evidence—based)学校全体の職能成長プログラムを拡大して全ての生徒のための効果のある授業を支援する学校全体の力量を育てること。
- インクルーシブな学校を目指すリーダーシップを育むために校長の研修や支援の在り方を直すこと。
- 特別教育の評価の一環として、主流学校、特別学校、特別教育班(Group Special Education)そしてRTLBがニュージーランドの学校におけるインクルージョンのレベルを引き上げるための協働作業を効果的に進める方法を考えること。
2) 教育省自身の評価
教育省は2009年の秋から、特別教育の見直し作業を開始し、その一環として、2010年2月に討議文書を公表し、3月にかけて全国から意見を集めた。これに対しては2000件以上の意見が寄せられた。人権委員会や子ども権利コミッショナーはもちろんこの中に含まれている。
関係者の意見を求めるための質問は10である。
<学校教育について>
| [1] | a | 学校を成功に導くための必要な支援は何ですか。 |
| [1] | b | 学校が成功するために必要な学校間の協働の方法は何ですか。 |
<学校や社会への移行と協力機関について(Transitions and Agencies working together)
| [2] | スムーズな学校や社会への移行に必要なものは何ですか。 | |
| [3] | 生徒と家族のニーズに見合ったサービスをコーディネートする方法は何ですか。 | |
<基金と資源の利用(Funding and resource use)>
| [4] | 教育省は基金提供・意思決定・検証(verification)の手だて(arrangements)や基金受給(fundholding)をどうすべきでしょうか。 | |
| [5] | a | 個人を対象とするサービスや支援が効果的な方法は何ですか。 |
| [5] | b | プログラム、サービスそして支援が混在している現行システムは妥当で、それは経費に見合ったものになっているか。また、現行システムを変えるにはどうすればいいですか。 |
<質の高いサービスとアカウンタビリティについて>
| [6] | どうすれば質の高いサービスになりますか。 | |
| [7] | 家族や学校への適切な情報提供の方法は何ですか。 | |
| [8] | 成功した特別教育とはどのようなものですか、そして、それを評価するにはどうすればいいですか。 | |
| [9] | 問題が生じた時に、それを解決するにはどんな手だてが必要ですか。 | |
<最後に>
| [10] | 特別な教育的ニーズのある子どもや若者にとっての成果を改善するために最も重要な改革は何ですか。 | |
この質問に対して、2,000を超える回答があり、それを教育省が要約しているが、その中で、学校間のネットワーク作りを意図して設定した質問が [1]b の質問である。この質問をする際に、教育省はこれからのニュージーランドの学校システムを4つあげて、回答の際の参考として示している(現行システムについては 137、153頁ですでに紹介しておいたが、再掲する。)151。
(選択肢Dは、特別学校への就学に際して現行では必要となっている教育省の承認が不要となっているモデルである。)
教育省は以下のように要約している(下線は引用者)。
回答者の半数近くが学校間の協働関係に向けてのアイディアを出している。しかし、その多くについては実現が難しいので、関係作りに向けての支援が必要である。
学校間で知識やスタッフを共有する方法について幅広いアイディアが出された。幾人かの回答者は、特別教育だけでなく教育問題について成功を収めている学校群を参考にして特別教育の実践を支援する学校群を作り出すように提言している。
特別学校の将来についての4つの選択肢が討議文書では示されていた。多くの回答者は明確に考え方を表明していなかったが、しかし、何らかの形態で特別学校を存続させることについては19パーセントの支持があった。特別学校を閉鎖し、通常学校を改善すべきとした意見は1パーセントであった。
特別学校を資源センターとして残す選択肢のCは、資源センターの全体的利点についての議論を巻き起こした。特別学校の枠を超える資源センターの統治と運営については多様な選択肢が提起された。
これだけ読むと、インクルーシブ教育に対する意識が読み取れない。しかし、質問[10]に対する回答では、約3分の1の回答者が通常学校での基金とサービスの水準向上を求め、15パーセントの回答者が特別な教育的ニーズのある生徒に対する態度を変え、インクルージョンが促進されることを望んでいる。
なお、質問[9]の問題が生じたときの対応については、155頁でも触れておいたが、まずは問題が起きないこと、そして、問題が起きた時には第一段階(low—level)で解決できることを半分以上の回答者が望んでいた。その多くが明確な方針、手続き、有効なコミュニケーションだけでなく、適切な情報へのアクセスを求めている。討議文書では明確な苦情処理過程について触れておいたが、それが13%の回答者に支持された。
何らかの心配ごとが問題解決の手続きを踏んでも解決できない場合には、権利擁護や調停サービスが別の組織で行われることにかなりの支持が集まった。約22%の回答者がこうしたコメントをしている。
回答者たちは独立した、利用しやすいこれらのサービスを求めている。これについては家族のほとんどが適切であると回答したが、学校もまた必要としていることが分かった。
さらに15%が独立の審査(review)や仲裁(arbitration:これはmediationよりは法的強制力があるといわれている。*引用者注)の手続き、すなわち、最終的な結果や決定を下し、未解決の状態を解消する手続きを求めている。
ほぼ同じ時期に行われた教育評価機関と教育省自身の評価に基づき、上述したように教育省は「全ての学校と生徒が成功するように」を策定したのであった。4ケ年で完全なインクルーシブ教育制度を完成させるとしているが、しかし、特別学校やそのサテライトや特別ユニットをどうするかの具体的展望や苦情処理や調停・仲裁手続きの明確化は示されず、教職員養成・研修の充実、ORRSの枠拡大、特別学校の資源センターとしての役割拡大などを中心としている。
それゆえ、ニュージーランドの障害のある子どもの教育は極めて漸進的にインクルーシブ教育へと動いていくものと思われる。
しかし、2008年に障害者権利条約を批准したニュージーランドは、その国内での実施を監視する役割として人権委員会に障害者の権利問題を主に担当するコミッショナーを2011年に置くことになったし、また、人権委員会とオンブズマンとの連携も強化されるため、障害児差別問題の解決やインクルーシブ教育の推進に関わる動きが顕在化することが予想される。
インタビュー先
- Mr Kayne Goo; Special education: Office of Northern Region
- Azusa Barraclough(オークランド在住日本人で母親)
- Office of the Ombudsmen
- Margaret A. McLean & Rod Willis ; School of Critical Studies in Education
- Lisa Martin; Parent & Family Resource Center
- Tom Purvis; Kelstone Deaf Education Centre
- Paula Tornquist; Mangawhai Beach School
参考文献・資料・HP
- 八巻正治『アオテアロア/ニュージーランドの福祉』学宛社、2001年
- 矢部明宏「諸外国の憲法事情 3 ニュージーランド」国立国会図書館調査及び立法考査局、2003年12月
- 渡邉みさ子「ニュージーランド」『平成20年度内閣府「障害者の社会参加推進に関する国際比較調査研究」委託報告書、2010年3月
- 教育省HP(http://www.minedu.govt.nz/NZEducation.aspx
 )
) - 人権委員会HP(https://www.hrc.co.nz/
 )
) - 子どもの権利コミッショナー事務所HP(http://www.occ.org.nz/
 )
) - オンブズHP(http://www.ombudsmen.parliament.nz/
 )
) - 保健・障害コミッショナーHP(https://www.hdc.org.nz/)
- 障害者問題担当事務局HP(https://www.odi.govt.nz/
 )
) - 知的障害児(IHC)HP
(https://ihc.org.nz/ )
)