第1章 障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組 第1節 2
2.障害者差別解消法の概要
ここでは、「障害者差別解消法」の概要について、「改正障害者差別解消法」や「基本方針」において新たに記載された事項等も踏まえながら説明する。
(1)障害者差別解消法の趣旨
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要である。このため、「障害者差別解消法」では、行政機関等や事業者に対して、障害者への「障害を理由とする不当な差別的取扱い」を禁止するとともに「合理的配慮の提供」を求め、これらの措置等を通じて、障害者が社会で提供されている様々なサービスや機会にアクセスし、社会に参加できるようにすることで、共生社会の実現を目指すこととしている。
(2)対象となる障害者
「障害者差別解消法」において対象となる障害者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいい、いわゆる障害の「社会モデル」の考え方を踏まえている。したがって、「障害者差別解消法」が対象とする障害者の該当性は、当該者の状況等に応じて個別に判断されることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限られないものとされている。
共生社会を実現するために、障害者が直面する社会的障壁を取り除いていくという考え方は、「障害者権利条約」の理念である障害の「社会モデル」の考え方を踏まえたものである。障害の「社会モデル」とは、障害者が日常生活又は社会生活で受ける様々な制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生じるものという考え方である。
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく活動できる共生社会の実現のためには、このような考え方に基づき、障害者の活動や社会参加を制限している様々な社会的障壁を取り除くことが重要である。
※ 障害の「社会モデル」に対し、障害は個人の心身の機能の障害によるものであるという考えを「医学モデル」という。
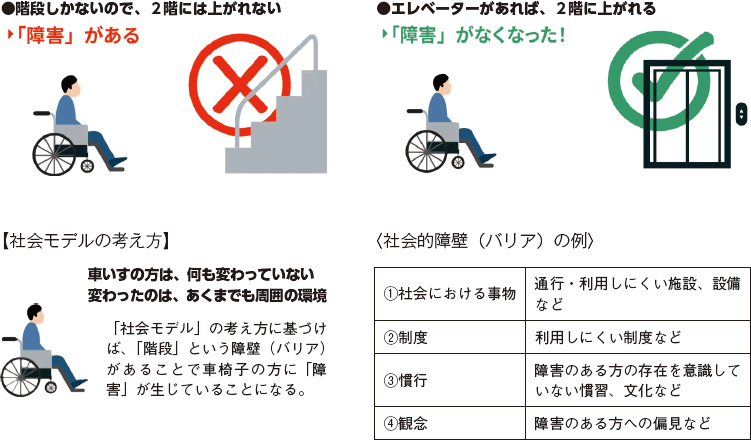
(3)対象となる事業者及び分野
「障害者差別解消法」では、行政機関等のほか、事業者も障害を理由とする差別を解消するための措置を行うこととされている。対象となる事業者は、商業その他の事業を行う者(地方公共団体が経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を含む。)であり、個人事業者やボランティアなどの対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人なども、同種の行為を反復継続する意思をもって行っている場合は事業者として扱われ、また対面やオンラインなどサービス等の提供形態の別も問わない。
分野としては、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となるが、雇用分野についての差別を解消するための具体的な措置(「障害者差別解消法」第7条から第12条までに該当する部分)に関しては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)の定めるところによるとされている。
(4)「不当な差別的取扱いの禁止」・「合理的配慮の提供」
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする差別について、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供の二つに分けて整理している。ここでは、それぞれの基本的な考え方について説明する。
① 不当な差別的取扱いの禁止
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は場所・時間帯などを制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害する行為である。このような行為は、行政機関等であるか事業者であるかの別を問わず禁止される。なお、「基本方針」においては、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当することが明記された。
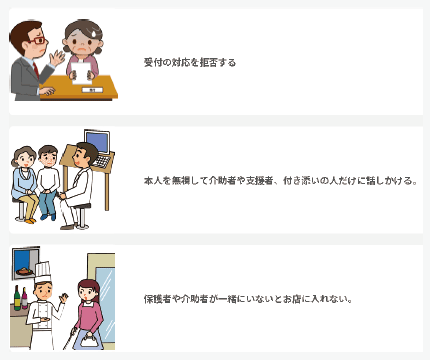
正当な理由に相当するのは、障害者に対して、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが、客観的にみて正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。その際、行政機関等及び事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。
「基本方針」においては、正当な理由がなく不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例として、以下の例が新たに記載された。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、正当な理由に相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断することが必要であること、正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しない場合であっても、合理的配慮の提供を求められる場合には別途の検討が必要であることに留意するものとされている。
(正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例)
・障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否すること。
・業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所での対応を行うこと。
・障害があることを理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げること。
・障害があることを理由として、具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、障害者に対し一律に保護者や支援者・介助者の同伴をサービスの利用条件とすること。
(正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例)
・実習を伴う講座において、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害特性のある障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定すること。(障害者本人の安全確保の観点)
・飲食店において、車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、敷物を敷く等、畳を保護するための対応を行うこと。(事業者の損害発生の防止の観点)
・銀行において口座開設等の手続を行うため、預金者となる障害者本人に同行した者が代筆をしようとした際に、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の取引意思等を確認すること。(障害者本人の財産の保全の観点)
・電動車椅子の利用者に対して、通常よりも搭乗手続や保安検査に時間を要することから、十分な研修を受けたスタッフの配置や関係者間の情報共有により所要時間の短縮を図った上で必要最小限の時間を説明するとともに、搭乗に間に合う時間に空港に来てもらうよう依頼すること。(事業の目的・内容・機能の維持の観点)
② 合理的配慮の提供
日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害者でない者には簡単に利用できても、障害者にとっては利用が難しく、結果として障害者の活動等が制限されてしまうことがある。このような場合には、障害者の活動等を制限しているバリアを取り除く必要がある。このため、「障害者差別解消法」では、行政機関等や事業者に対して、障害者に対する「合理的配慮」の提供を求めている。
障害者やその家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められる。こうした配慮を行わないことによって、障害者の権利利益が侵害される場合には、障害を理由とする差別に当たる。なお、「障害者差別解消法」においては、合理的配慮の提供について、行政機関等は義務、事業者は努力義務とされているが、前述のとおり、後者の努力義務を義務へと改めること等を内容とする「改正障害者差別解消法」が2021年6月に公布され、2024年4月1日から施行される。
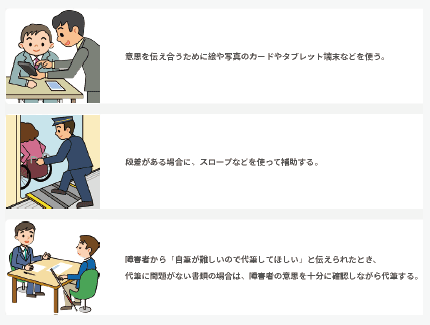
合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものである。また、合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、
① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと
に留意する必要がある。合理的配慮の提供に当たっては、これらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている現状を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、「過重な負担」の要素等も考慮し、代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされる必要がある。
「過重な負担」については、行政機関等及び事業者において、個別の事案ごとに、事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)、実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)、費用・負担の程度、事務・事業規模、財政・財務状況といった要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要である。行政機関等及び事業者は、過重な負担に当たると判断した場合は、障害者に丁寧にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。なお、合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応を求められることに留意する。
また、今般の「基本方針」では、合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例及び該当しないと考えられる例として、新たに以下の例を記載している。なお、記載されている内容はあくまでも例示であり、合理的配慮の提供義務違反に該当するか否かについては、個別の事案ごとに、前述の観点等を踏まえて判断することが必要であることに留意するものとされている。
(合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例)
・試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく一律に対応を断ること。
・イベント会場内の移動に際して支援を求める申出があった場合に、「何かあったら困る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断ること。
・電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断ること。
・自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害者からスクリーンや板書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確保などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること。
(合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例)
・飲食店において、食事介助等を求められた場合に、当該飲食店が当該業務を事業の一環として行っていないことから、その提供を断ること。(必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点)
・抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うことが困難であることを理由に、当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、当該対応を断ること。(障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであることの観点)
・オンライン講座の配信のみを行っている事業者が、オンラインでの集団受講では内容の理解が難しいことを理由に対面での個別指導を求められた場合に、当該対応はその事業の目的・内容とは異なるものであり、対面での個別指導を可能とする人的体制・設備も有していないため、当該対応を断ること。(事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことの観点)
・小売店において、混雑時に視覚障害者から店員に対し、店内を付き添って買物の補助を求められた場合に、混雑時のため付添いはできないが、店員が買物リストを書き留めて商品を準備することができる旨を提案すること。(過重な負担(人的・体制上の制約)の観点)
合理的配慮の提供に当たっては、社会的障壁を取り除くために必要な対応について、障害者と行政機関等・事業者双方が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要となる。このような双方のやり取りを「建設的対話」という。
「基本方針」では、「建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必要かつ実現可能な対応案を障害者と行政機関等・事業者が共に考えていくために、双方がお互いの状況の理解に努めることが重要であり、例えば、障害者本人が社会的障壁の除去のために普段講じている対策や、行政機関等や事業者が対応可能な取組等を対話の中で共有する等、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検討していくことが円滑な対応に資すると考えられる。」とし、建設的対話を行うに当たっての考え方を示している。
(5)環境の整備
「障害者差別解消法」は、個別の場面において、個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための不特定多数の障害者を主な対象として行われる事前的改善措置(施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上等)を、環境の整備として行政機関等及び事業者の努力義務としている。これには、ハード面のみならず、職員に対する研修や、規定の整備等の対応も含まれることが重要である。
環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものであるが、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置である。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なることとなる。
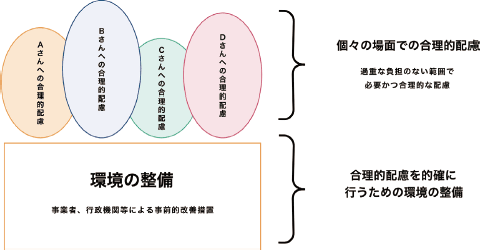
障害を理由とする差別の解消のための取組は、「障害者差別解消法」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年法律第91号)等不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する法令に基づく環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の整備と合理的配慮の提供を両輪として進めることが重要である。
なお、多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から、他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うことや、相談・紛争事案を事前に防止する観点からは合理的配慮の提供に関する相談対応等を契機に、行政機関等及び事業者の内部規則やマニュアル等の制度改正等の環境の整備を図ることは有効である。また環境の整備は、障害者との関係が長期にわたる場合においても、その都度の合理的配慮の提供が不要となるという点で、中・長期的なコストの削減・効率化にも資することとなる。
(6)基本方針並びに対応要領及び対応指針
「障害者差別解消法」第6条に基づき、政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を定めることとされている。
同基本方針に即して、行政機関等は、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関し、その職員が適切に対応するために必要な「対応要領」を定めることとされている。地方公共団体については努力義務であるが、全ての都道府県及び指定都市においては既に策定されている。
また、事業者の事業を所管する各主務大臣は、同基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な事項(相談体制の整備、研修・啓発等)や、各事業分野における合理的配慮の具体例等を盛り込んだ「対応指針」を定めることとされている。「改正障害者差別解消法」の施行に向けては、「基本方針」を受けて、各主務大臣において「対応指針」を見直すこととなる。
(7)主務大臣等による行政措置
事業者における障害を理由とする差別の解消に向けた取組は、主務大臣の定める対応指針を踏まえ、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。
しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されないような場合、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣又は地方公共団体の長等は、事業者に対し、「障害者差別解消法」第12条に基づき、報告を求め、又は助言、指導、勧告をすることができるとされている。こうした行政措置に至る事案を未然に防止するため、主務大臣は、事業者に対して、対応指針に係る十分な情報提供を行うとともに、事業者からの照会・相談に丁寧に対応するなどの取組を積極的に行うものとされている(2022年度、主務大臣等による助言、指導及び勧告の行政措置の実績はなし。)。
(8)相談及び紛争の防止等のための体制の整備
障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するためには、障害者や事業者等からの相談を受け止める体制整備が重要となる。「改正障害者差別解消法」では、国及び地方公共団体の連携協力の責務が定められており、適切な行政機関に事案が引き継がれる相談体制の整備や、障害者差別解消支援地域協議会(以下本章では「地域協議会」という。)の設置・運営の促進を推進することとしている。
「改正障害者差別解消法」により、事業者による合理的配慮の提供が義務化されたことに伴い、今後は事業者からの相談も含め、相談が増加することが見込まれる。このような中で障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するためには、相談対応等に当たり、国及び地方公共団体が役割分担・連携協力し、一体となって適切な対応を図ること、また、国や地方公共団体において相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図ることが重要となる。
「基本方針」では、
・障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するには、公正・中立な立場である相談窓口等の担当者が、障害者や事業者等からの相談に的確に応じることが必要であること
・相談対応等に際しては、地域における障害を理由とする差別の解消を促進し、共生社会の実現に資する観点から、まず相談者にとって一番身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たすこと、都道府県は、市区町村への助言や広域的・専門的な事案についての支援・連携を行うとともに、必要に応じて一次的な相談窓口等の役割を担うこと、国においては各府省庁が所掌する分野に応じて相談対応等を行うとともに、市区町村や都道府県のみでは対応が困難な事案について適切な支援等を行う役割を担うことが考えられること
・このような国及び地方公共団体の役割分担を基本としつつ、適切な関係機関との間で連携協力し、一体となって適切な対応を図ることができるような取組を、内閣府が中心となり、各府省庁や地方公共団体等と連携して推進すること
・内閣府においては、事業分野ごとの相談窓口の明確化を各府省庁に働きかけ、当該窓口一覧の作成・公表を行うほか、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進め、どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることがないよう取り組むとともに、各相談窓口等に従事する人材の確保・育成の支援及び事例の収集・整理・提供を通じた相談窓口等の対応力の強化等にも取り組むこと
・国及び地方公共団体においては、必要な研修の実施等を通じて、相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図ることが求められること
を明記している。
(9)啓発活動
障害を理由とする差別については、国民一人一人の障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りに起因する面が大きいと考えられる。このため、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現するためには、障害者に対する障害を理由とする差別は解消されなければならないこと、また障害を理由とする差別が、本人のみならずその家族等にも深い影響を及ぼすことを国民一人一人が認識するとともに、障害を理由とする差別の解消のための取組は、障害者のみならず、全ての国民にとっての共生社会の実現に資するものであることについて理解を深めることが不可欠であり、「障害者差別解消法」で求められる取組やその考え方が、幅広く社会に浸透することが重要である。このため「基本方針」においては、内閣府を中心に、関係行政機関等と連携して、いわゆる「社会モデル」の考え方も含めた各種啓発活動に積極的に取り組み、国民各層の障害に関する理解を促進することとされている。
(10)情報の収集、整理及び提供
事業者による合理的配慮の提供が義務化されることに伴い、今後、事業者や各相談機関が参考にできる事例の重要性が一層高まることが想定される。このため、「改正障害者差別解消法」では、国において事例等の収集等を行うものとする旨を定める「障害者差別解消法」第16条に、直接相談に対応することが多い地方公共団体についても同様の取組を行うよう努めるものとする旨が追加されている。
「基本方針」では、内閣府において、引き続き各府省庁や地方公共団体と連携・協力して事例を収集するとともに、参考となる事案の概要等をわかりやすく整理してデータベース化し、ホームページ等を通じて公表・提供することとされている。
(11)障害者差別解消支援地域協議会
「障害者差別解消法」において、国及び地方公共団体の機関は、「障害者差別解消支援地域協議会」を組織することができるとされている。地域協議会を設置することで、その地域の関係機関による相談事例等に係る情報の共有・協議を通じ、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築されるとともに、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となり、差別解消に関する地域の対応力の向上が図られる。
「基本方針」においては、地域協議会において情報やノウハウを共有し、関係者が一体となって事案に取り組むという観点から、地域の事業者や事業者団体も参画することが有効であるとしている。また、設置促進に向けた取組として、地域協議会の単独設置が困難な場合等に、必要に応じて圏域単位など複数の市区町村による地域協議会の共同設置・運営を検討することや、必要な構成員は確保しつつ、他の協議会等と一体的に運営するなど開催形式を柔軟に検討することが効果的と考えられることや、市区町村における地域協議会の設置等の促進に当たっては都道府県の役割が重要であることが明示されている。
内閣府は、障害及び障害者に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とすることを目的とした「障害者に関する世論調査」をおおむね5年ごとに実施しており、直近では2022年11月に実施した。我が国では、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」を定めている。また、2024年4月には「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化される。施行に当たっては合理的配慮などについての国民の正しい内容理解が重要であるが、この調査から共生社会の考え方の理解の高まりや、障害を理由とする差別の解消等について、広く国民が関心を持っていることがうかがえる。
(1)「共生社会」の考え方の支持
「障害のある人が身近で普通に生活しているのが当たり前だ」という「共生社会」の考え方について93.9%の人が当たり前だと思っており(※1)、国民の間に広く浸透してきていることがみて取れる。
※1 「当たり前だと思う」、「どちらかといえば当たり前だと思う」と答えた人の計
○「共生社会」の考え方について
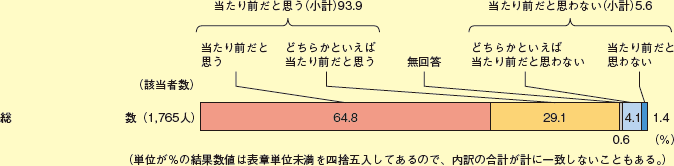
(2)障害を理由とする差別や偏見の有無
「世の中には障害のある人に対して、障害を理由とする差別や偏見があると思うか」について、あると思う人(※2)は88.5%となっており、多くの人が障害を理由とする差別や偏見を感じていることがみて取れる。このうち、今から5年前と比べて障害のある人に対する差別や偏見は改善されたと思う人(※3)は58.9%で、社会の変化が感じられていることがうかがえる。
※2 「あると思う」、「ある程度はあると思う」と答えた人の計
※3 「かなり改善されたと思う」、「ある程度改善されたと思う」と答えた人の計
○障害を理由とする差別や偏見の有無
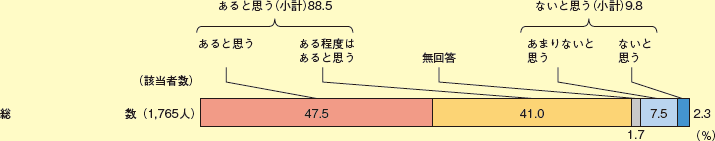
○今から5年前と比べた障害を理由とする差別や偏見の改善状況
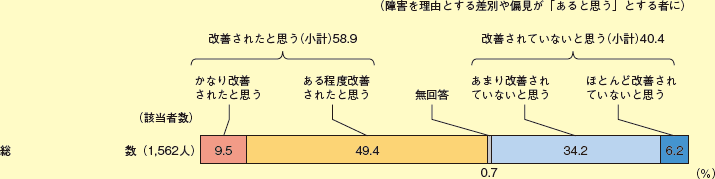
(3)合理的配慮と差別について
合理的配慮の提供が行われない場合、差別に当たる場合があると思う人(※4)は64.7%であった。事業者や行政機関等に対して合理的配慮の提供を行うこととしている障害者差別解消法の施行(2016年4月施行)前の2012年7月調査では46.1%であったが、施行翌年の2017年8月調査では53.5%に増えている。また、調査手法が異なることから単純比較はできないが、施行から6年が経過した2022年には64.7%となり、更に大きく増えている。障害者差別解消法の施行後、着実に合理的配慮の考え方が広がってきていることが確認できる。一方、(2)でみたように、依然として多くの人が障害を理由とする差別や偏見があると感じている。今後、事業者が合理的配慮の提供を円滑に行うためには、周囲の人々の理解等も重要であることから、「改正障害者差別解消法」の施行に向けて周知啓発を一層推進していく必要がある。
※4 「差別に当たる場合があると思う」、「どちらかといえば差別に当たる場合があると思う」と答えた人の計
○合理的配慮と差別について(※5)
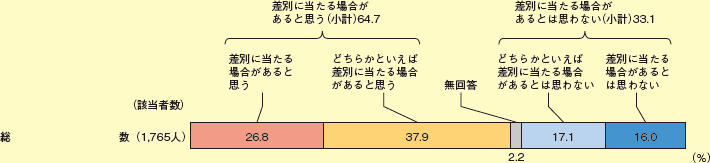
○合理的配慮と差別について(※5)の推移
※2022年11月調査と2017年8月以前の調査では調査手法が異なることから単純比較はできない。
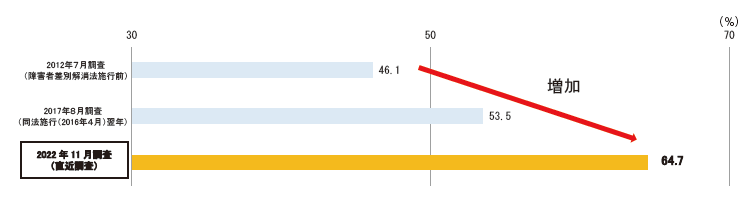
※5 次の設問に答えた人の割合:「障害のある人とない人が同じように生活するためには、例えば、受付窓口で耳の不自由な方に筆談で対応したり、商店で高い棚にある商品を店員が代わりに取ってあげたりするなど、さまざまな配慮や工夫が必要になることがあります。あなたは、もし、こうした配慮や工夫(合理的配慮の提供)が行われなかったとしたら、それが『障害を理由とする差別』に当たる場合があると思いますか」
「障害者に関する世論調査」(2022年11月)(https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-shougai/index.html)
・調査対象等 |
: |
全国18歳以上の日本国籍を有する者 3,000人 |
・調査期間 |
: |
2022年11月10日 ~ 12月18日 |
・調査方法 |
: |
郵送法(2017年8月調査までは調査員による個別面接聴取法) |
・調査項目 |
: |
①障害者と共生社会について ②障害者との交流について ③障害者関連施策について |
・調査実績 |
: |
おおむね5年ごとに実施、2017年8月(前回調査)以前に7回実施 |

