第1章 障害の有無により分け隔てられることのない共生社会の実現に向けた取組 第1節 3
3.障害者の差別解消に向けた取組等
(1)人材の育成等

内閣府においては、2022年度「障害を理由とする差別の解消に向けた事例の収集・分析に係る調査研究」として有識者等による検討会を開催し、検討会における議論の下、国や地方公共団体の相談窓口等担当者が相談対応業務を行うに当たり「障害者差別解消法」や「基本方針」に沿った事案の分析・対応の検討を行う際の参考資料となるような相談対応ケーススタディ集を作成した。同ケーススタディ集は内閣府ホームページにおいて公表している。
【障害を理由とする差別の解消の推進 相談対応ケーススタディ集(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html】
(2)周知・啓発
政府においては、各般の取組により国民各層の関心と理解を深めるとともに、建設的対話による相互理解を通じた合理的配慮の提供等の促進を始め、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うこととしている。
内閣府では以下のような周知・啓発活動に取り組んでおり、これらの活用を通じて、合理的配慮の提供を始めとする障害者差別の解消に向けた取組の裾野が更に広がるとともに、「障害者差別解消法」に対する国民の理解が一層深まることが期待される。
内閣府における周知・啓発の取組
・内閣府では、障害者差別解消法の周知・啓発のためにリーフレット「『合理的配慮』を知っていますか?」を作成し、内閣府ホームページへの掲載や毎年「障害者週間」(12月3日から9日)に開催する「『障害者週間』作品展」などで配布。
【障害者差別解消法リーフレット(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html】
・障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供や環境の整備に関する事例を関係省庁、地方公共団体、障害者団体などから収集し、障害種別や生活場面別に整理した上で、「合理的配慮の提供等事例集」として取りまとめ、内閣府ホームページで提供。
【合理的配慮の提供等事例集(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html】
・企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が障害者に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、「障害者差別解消法」により定められている事項について一層の広報啓発を推進することを目的として、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を2022年3月に公開。2023年には同サイト上で「障害者差別解消に関する事例データベース」も公開。
【内閣府ホームページ
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」:https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
「障害者差別解消に関する事例データベース」:https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ 】
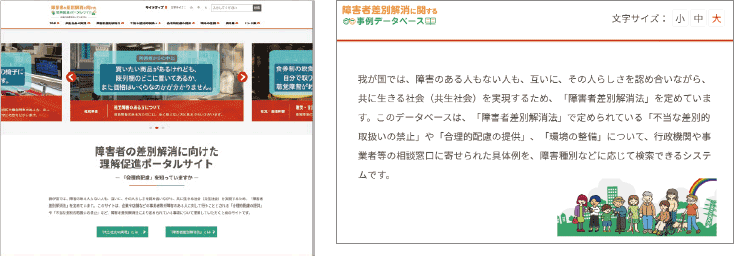
・2022年度に内閣府が実施した「障害を理由とする差別の解消に向けた事例の収集・分析に係る調査研究」では、同調査研究における有識者等による検討会での議論の下、今般の法改正で合理的配慮の提供が義務化される事業者を主な対象としつつ、国民一般の理解にも資するよう、「改正障害者差別解消法」の周知のためのリーフレットを作成し、内閣府ホームページで提供。
【リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html】
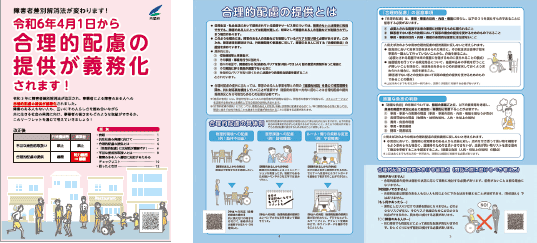
(3)障害者差別解消支援地域協議会の設置の促進
地域協議会は、都道府県及び指定都市においては全て設置されているが、一般市の設置率は約7割、町村の設置率は約5割であり、設置した市町村においても開催実績が少ないところもある。このため、「基本方針」においては、内閣府において、地方公共団体の担当者向けの研修の実施を通じ、地域における好事例が他の地域において共有されるための支援を行うなど、体制整備を促進することとしている。こうした状況を踏まえ、各都道府県等で地域協議会の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした「障害者差別解消支援地域協議会体制整備・強化ブロック研修会」を、2022年度は6ブロック(北海道・東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州・沖縄)で開催した。
| 選択肢 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 指定都市 | 中核市等 | 一般市 | 町村 | ||||||||
| 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 設置済み | 1,074 | 60% | 47 | 100% | 20 | 100% | 76 | 85% | 495 | 70% | 436 | 47% |
| 設置予定 | 66 | 4% | - | - | - | - | 1 | 1% | 25 | 4% | 40 | 4% |
| 設置しない | 61 | 3% | - | - | - | - | 1 | 1% | 26 | 4% | 34 | 4% |
| 未定(策定するかしないか決まっていない) | 587 | 33% | - | - | - | - | 11 | 12% | 160 | 23% | 416 | 45% |
| 計 | 1,788 | 100% | 47 | 100% | 20 | 100% | 89 | 100% | 706 | 100% | 926 | 100% |
国等は、事業者などに対して障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るために必要な啓発活動を行っている。
2021年6月に、事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けることなどを内容とする改正障害者差別解消法が公布された。その施行期日は、2024年4月1日とされている。この施行に向けて、内閣府は、企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が障害のある人に対して行うこととされる「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱いの禁止」など、「障害者差別解消法」により定められている事項について一層の広報啓発を推進することを目的として、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」(以下本章では「ポータルサイト」という。)を2022年3月に公開した。2023年には、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」の具体例を、障害の種別などに応じて検索できる「障害者差別解消に関する事例データベース」(以下本章では「データベース」という。)をポータルサイト内に公開した。
また、「障害者差別解消法」が改正されることの周知などを目的としたリーフレットを作成し、内閣府のホームページで公開するなど施行に向けた取組を進めている。
〇ポータルサイトの主な内容
(https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/)
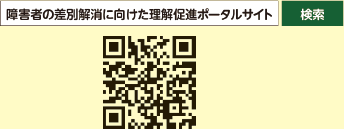
①「共生社会の実現」とは
②「障害者差別解消法」とは
③「不当な差別的取扱い」とは
④「合理的配慮の提供」とは
・障害種別ごとの概要説明や事例紹介、事例動画
⑤「環境の整備」とは
・障害種別ごとの概要説明と事例紹介
⑥事業者の障害者差別解消に関する取組事例
⑦障害者の差別解消に関する事例データベース

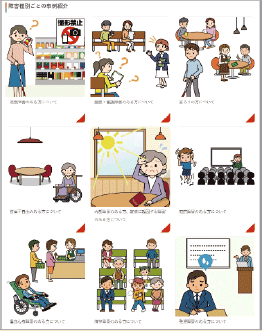
〇障害者の差別解消に関する事例データベース
ポータルサイトでは、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について国民の理解を深めるとともに、実際の対応時の一助となるよう、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例をデータベースとして公開している。このデータベースでは、利用者の要望に応じた事例を提供できるよう、キーワード検索のほか、障害の種別や事例が生じた場面ごとの検索ができる。加えて、検索によって抽出された各事例の内容・経緯・背景や事例を解決するための対応などについても確認できるシステムとなっている。
(データベースで確認できる各事例の主な項目)
「障害の種別」、「障害者の性別」、「障害者の年代」、「事例が生じた場面」、「事例の内容・経緯・背景」、「事例を解決するための対応」など
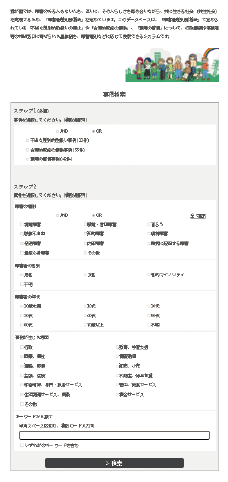
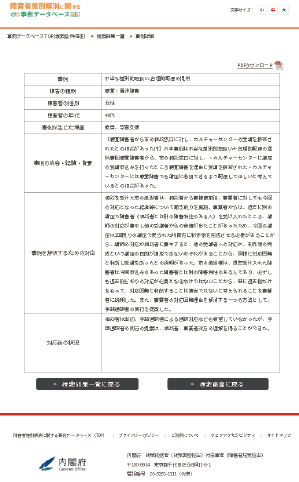
〇理解促進のためのチラシの配布等
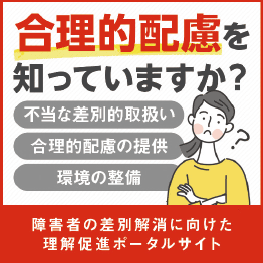
障害者の差別解消に向けた理解促進のためのチラシを作成し、障害者差別解消法改正法の施行により合理的配慮の提供が義務化される事業者などを中心としつつ、全ての人を対象にインターネットを介して配布している。
また、ポータルサイトや合理的配慮の広報啓発のために、ウェブ画面の広告枠に画像等を掲載するバナー広告を実施した。
2024年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮が義務化されることも踏まえ、事業者は、地域における共生社会の実現を図る重要な担い手となることが一層期待されている。ここでは、事業者の参画の下、障害を理由とする差別の解消に向けた様々な取組を行っている地方自治体として、北九州市(以下本章では「市」という。)における取組を紹介する。
1.相談体制の構築
市では、「障害者差別解消法」の成立を契機として、障害を理由とする差別に関する相談と解決のために、2016年4月より専用の窓口である「障害者差別解消相談コーナー」を設置した。同相談コーナーには専門相談員を配置し、障害のある人やその家族だけでなく、「障害のある人から配慮の申出があったが、適切な対応方法が分からない」等の悩みを抱える事業者からの相談を受け付け、事案の解決に至るまでの支援を行っている(専門相談員は、社会福祉士または精神保健福祉士及び社会福祉主事の任用資格を有するものと定めている。)
また、市では「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえ、市民、事業者及び市が協力して障害を理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組み、共生社会の実現を目指すことを目的に「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」を制定し、2018年4月1日に全面施行している(一部は2017年12月20日施行)。この条例に基づき、市では市の付属機関として「北九州市障害者差別解消委員会」を設置し、障害を理由とする差別に関する事案で市が相談対応を行っても解決が得られない場合には、相談者の申立てに基づき調査審議し、解決に向けた助言・あっせん等を行うことができることとされている。事案を調査審議し解決に向けた助言・あっせんを行うためには多様な視点からの事案の検討が必要との観点から、事案に対する事業者の対応の適否や可否、また求められている配慮が過重な負担となるかどうかなど、事業者の立場からの意見が得られるよう、同委員会の構成員には事業者も含まれている。
▽北九州市障害者差別解消委員会
| 構成員 | 学識経験者、法曹、障害当事者・家族、事業者、相談支援事業者(計7名) |
|---|
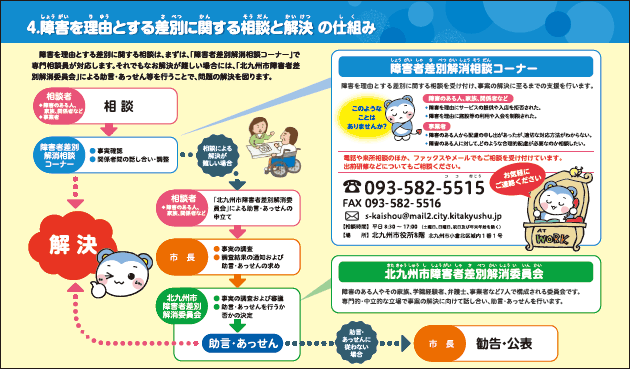
2.地域協議会における取組状況
市では、障害者差別に関する相談などについて情報共有し、障害を理由とする差別を解消する取組を効果的かつ円滑に行うため、2016年に「北九州市障害者差別解消支援地域協議会」(以下本章では「協議会」という。)を組織し、市内の障害者団体が加盟する「北九州市障害福祉団体連絡協議会」と共同で運営を開始した。
▽北九州市障害者差別解消支援地域協議会
| 構成員 | 学識経験者、法曹、医療・福祉等、教育、支援団体、障害当事者団体、民間事業者、行政(28名) |
|---|---|
| 開催頻度 | 年2~3回程度 |
構成員は、障害当事者・団体や福祉関係者だけではなく、中小企業団体連合会を構成員とし、地元の飲食業者や公共交通機関の事業者が参加していることが特徴であり、多種多様な業種の意見を共有できるというメリットがある。また、2021年度には、「改正障害者差別解消法」の施行を見据え、協議会における事業者委員の拡充に取り組むこととし、市職員が事業所を訪問し協議会への参画を依頼した結果、参画事業者数が増加した(2022年時点で7事業者が参画。)。
2021年度の協議会では、これまでに実施してきた障害者差別解消に向けた取組について総括し、今後の課題抽出を行った。
また、2022年度からは、「改正障害者差別解消法」の施行、条例改正に向けた議論を更に加速させるとともに、活発な議論を行うため、協議会の下に「事業者向け取組等検討部会」、「事例公開等検討部会」及び「啓発方法等検討部会」の3つの部会を立ち上げた。
特に「事業者向け取組等検討部会」においては、事業者委員の参画の下、本音で議論を重ねながらこれまでの啓発活動も踏まえつつ、事業者からの依頼を受けてから講演を行うといった、事業者に対して受け身であった市の啓発方法を見直し、「積極的な啓発」となることを意識しながら今後の取組について検討を行っており、2023年度以降は、市内の事業者へ周知啓発のための個別訪問、合理的配慮に関する動画作成、事業者向けパンフレットの改定などを実施する予定となっている。
3.周知啓発活動
市では、広報物や研修・イベントの開催などを通じて、より多くの市民や事業者に条例や障害理解に関する内容を伝えるよう努めている。ここでは主に事業者を対象とした周知啓発活動を紹介する。

(1)条例パンフレットの作成
市では、条例の施行に伴い、事業者向けに障害者差別解消条例リーフレットを作成し、事業者へ配布するとともに、中小企業向け情報誌に条例記事の掲載を行い、条例及び障害に応じた合理的配慮の提供について周知に努めている。
2016年度、2018年度は市内企業8,500社へ条例パンフレットを配布、2019年以降は、民間事業者への出前講演や障害福祉サービス事業者等集団指導、指定管理者研修会などの場で配布を行っている。
(2)出前講演の実施
市では、障害者差別解消条例や合理的配慮の提供について知りたい等の要望に応えるために、市民や事業者を対象に出前講演を実施しており、2020年には事業者団体等が主催する経営者研修会において講演を行った。また市では「合理的配慮の提供事例」等を内容とする啓発DVDを作成し、出前講演を実施する際に併せて上映している。現在は、コロナ禍の影響でオンラインや動画配信による研修が主流となり、研修方法が多様化している。
1に前述の専門相談員は、各種相談に対する対応に加え、これら出前講演や研修の企画運営等を行っている。
障害のある当事者の視点からユニバーサルデザインのインフラやソリューションを企業や自治体に提供している株式会社ミライロ(以下本章では「ミライロ」という。)では、障害者手帳をスマートフォン上でデジタル化するアプリケーション「ミライロID」や「民間事業者(※)による合理的配慮推進委員会」(以下本章では「合理的配慮推進委員会」という。)を運営している。
※委員会名の「民間事業者」とは、改正障害者差別解消法により合理的配慮の提供が義務化される事業者を指す。
1.デジタル障害者手帳(ミライロID)

(イメージ)
ミライロは、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を所有している人を対象としたスマートフォン向けアプリケーションであるデジタル障害者手帳「ミライロID」を運営している。
利用者は、障害者手帳、福祉機器の仕様、求めるサポートの内容等をミライロIDに登録した後、ミライロIDを本人確認書類として認めている自治体や事業者等(2023年3月31日現在の数3,769)の公共機関や商業施設において、障害者手帳の代わりに提示することで、割引や必要なサポートを受けることができる。
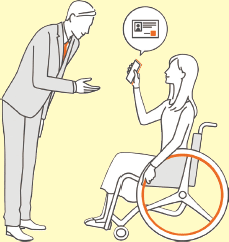
(イメージ)
ミライロIDを利用することで、紙の障害者手帳ではできなかったことができるようになる。例えば、オンラインによる事前決済や非対面決済において障害者割引が適用され、無人駐車場で障害者割引を受けたり、窓口等で改めて障害者手帳を提示することなくオンラインで障害者割引チケット等を購入したりすることが可能になる。また、障害者割引の適用を受ける際に障害者手帳の代わりにスマートフォンの提示で済むため、窓口等で障害者手帳を出すことで周囲に障害のあることを知られることがなくなり、障害者手帳を持つ人のプライバシーの強化につながる。さらに、必要なサポートや車椅子のサイズなどを登録しておくことで、窓口等での合理的配慮等に関する伝達を円滑に行いやすくなる。
ミライロでは、障害のある人の移動や生活をより便利に、より自由にしていくために、ミライロIDを利用できる公共機関や商業施設を拡大し、機能の一層の充実を図っていく予定である。
2.合理的配慮推進委員会
事業者による合理的配慮の提供を義務化する「改正障害者差別解消法」の施行を控え、ミライロは、国や地方公共団体と連携しながら、合理的配慮の事例、知見、ノウハウを蓄積し、事業者に対して啓発を行う組織が必要と考え、2021年10月に、弁護士、大学客員教授、ビジネスコンサルタントやWebアクセシビリティの専門家等の多様な有識者で構成される合理的配慮推進委員会を発足した。
2021年には「合理的配慮に関する実態調査」の結果を公開した。「障害者差別解消法の認知度」や「具体的に求める(あるいは実践している)合理的配慮の提供」等を設問としており、事業者に期待される合理的配慮の提供に係る障害のある人の声を確認することができる。合理的配慮推進委員会では、このような取組や、好事例の収集・発信を通じ、合理的配慮の提供が実践される社会づくりに寄与することとしている。

