第1章 障害者に対する偏見や差別をなくすための取組について 第1節 1
第1節 旧優生保護法に関する政府の対応
1948年の旧優生保護法の施行から1996年の母体保護法への改正までの48年間、多くの方々が、同法に基づき、あるいはその存在を背景として、特定の疾病や障害を有すること等を理由に生殖を不能にする手術や放射線の照射あるいは人工妊娠中絶を受けることを強いられ、子を生み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、耐え難い苦痛と苦難を受けてきた。
最高裁判所は、2024年7月3日、旧優生保護法の規定が憲法に違反するとした上で、当該規定に係る国会議員の立法行為が国家賠償法第1条第1項の適用上、違法であるとの判決を言い渡した。
政府としては、この判決を重く受け止め、同月17日、岸田文雄内閣総理大臣が旧優生保護法国家賠償請求訴訟原告団等と面会し謝罪を行った。その際、障害者に対する偏見差別の根絶に向けて、これまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めて取組を強化するため、全府省庁による新たな体制を構築することを表明した。
同月26日には、真摯な反省の下、障害のある人に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた取組を強化するため、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」(以下本章では「推進本部」という。)を設置した。9月30日には、旧優生保護法問題の全面的な解決を目指し、優生保護法被害全国原告団等との間で基本合意書を交わした。
1.障害者に対する偏見や差別のない共生社会に向けた行動計画
(1)行動計画策定の経緯
推進本部は、障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であり、社会全体が変わらなければならないという考えの下、内閣総理大臣を本部長とし、障害者・障害児行政を所掌する大臣のみならず、全大臣を構成員としている。
2024年7月29日、第1回推進本部において岸田文雄内閣総理大臣はこれまでの取組を点検し、教育・啓発等を含めて取組を強化するため、以下の4点を指示した。
① 障害のある人の結婚、出産、子育てを含めた希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進
② 障害者差別解消法に基づく各府省庁における職員の研修・啓発の点検・取組強化
③ ユニバーサルデザイン2020行動計画における「心のバリアフリー」の取組のフォローアップ・取組強化
④ 有識者の協力を得て、障害当事者の方から意見を伺った上で、成果を新たな行動計画として取りまとめること
総理の指示を受け、障害のない人を基準とし障害のある人を劣っているとみなす態度や行動と決別するという決意の下、障害のある人への偏見や差別をなくすために社会全体で取り組むよう行動計画を取りまとめるべく、推進本部を3回開催した。推進本部の下には「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部幹事会」(以下本章では「幹事会」という。)を設置し、旧優生保護法の被害者や障害当事者など多くの方々からヒアリングを行うなど検討を進めた。
同年12月27日、推進本部において、「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」(以下本章では「行動計画」という。)を決定した。
「行動計画」においては、「これまで障害のある人が受けてきた差別、虐待、隔離、暴力、特別視はあってはならないものである。」とし、障害の「社会モデル」の考え方を踏まえ、「我が国は、特定の疾病や障害を有する者に対する優生上の見地からの偏見や差別をはじめ、障害のない人を基準とし障害のある人を劣っているとみなす態度や行動と決別しなければならない。」としている。このような決意の下、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けて、政府一丸となって、教育・啓発等を含めて取組を強化することとしている。
(2)「行動計画」の概要
ア ヒアリングにおいて当事者の方々から示された主な問題意識
「行動計画」においては、まず、推進本部の幹事会でのヒアリングにおいて、障害当事者等から示された主な問題意識を記載している。
ここでは、ヒアリングにおいて、障害のある人に対する偏見や差別のない共生社会の実現のための方法として、「優生手術等に係る歴史的事実やその背景を後世に伝承し、記憶の風化を防ぐこと」や「人権侵害に迅速・確実に対応する体制を構築すること」等が示された。その他、障害のある人とない人が交流することによって障害に対する理解が深まっていくという観点から、「障害のある人とない人が共に学び共に育つ教育を推進すること」や「障害のある人とない人が共に働く環境を整備すること」といった指摘もあった。
イ 取り組むべき事項
次に、政府全体で重点的に取り組む事項について記載している。
我が国では、障害の「社会モデル」の考え方の下、障害者権利条約の署名以降、様々な取組を進めてきた。「ユニバーサルデザイン2020行動計画」(平成29年2月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)においては、障害の「社会モデル」の理解や障害のある人やその家族への差別を行わないことの徹底等を前提に、「様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと」を「心のバリアフリー」と定義し、その実現に向けて取り組んできた。
「行動計画」においては、その後の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下本章では「障害者差別解消法」という。)の改正法の施行や、人権擁護の観点から障害者の不利益を解消する観点も踏まえ、「心のバリアフリー」の取組をフォローアップし、時代に合わせて、その取組を強化することとしている。障害のある人への偏見や差別の解消に向け、障害のある人とない人が、対等な立場で、学校や職場などで関わりを持ち、障害に関する正しい知識を得られるよう、教育・普及啓発を進めることが重要であるとしている。また、障害のある人が社会で活動することを困難にする社会的なバリアの解消に向けて、障害のある人の生活を支える取組を、政府は、地方公共団体や民間団体などとも連携し、一丸となって、取組を進めていくこととしている。
その際には、障害のある人を自らの決定に基づき社会に参加する主体として捉え、政策決定過程への参画を促進し、併せて障害者施策の検討及び評価に当たってはジェンダーの視点も取り入れ、障害のある女性の参画拡大に取り組むこととしている。
障害のある人の社会的バリアの解消に向けて、政府が取り組むべき事項として、以下の4つの柱を立てている。
① 子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進
② 公務員の意識改革に向けた取組の強化
③ ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化
④ 障害当事者からの意見を踏まえた今後に向けた更なる検討
「行動計画」は、PDCA サイクルを適切に回すべく、継続的にフォローアップしていくこととされており、盛り込まれた施策については速やかに実行に移しつつ、障害者政策委員会における報告や意見聴取を経て、次期障害者基本計画などにも反映させていくなど、外部有識者や障害当事者の参画の下、実施状況を監視する体制を強化していくこととしている。
「行動計画」に記載した取組は、主に以下のとおりである。
① 子育て等の希望する生活の実現に向けた支援の取組の推進
妊娠、出産、子育てには、障害の有無にかかわらず周囲の人の支援が必要であるが、特に障害がある人は生きづらさを抱えている。「障害のある人は結婚、出産、子育てができない」とする偏見を払拭するとともに、結婚、出産、子育てを含め、障害のある人の意思決定の支援に配慮しつつ、希望する生活の実現に向けた支援のための取組を記載している。
具体的には、主に以下の取組を行うこととした。
・子育てをしている障害のある人の体験談を含む「障害者が希望する「結婚・出産・子育て」支援取組事例集」について、様々なイベント等の機会を通じて周知を行うとともに、新たに地方公共団体や支援者向け解説動画や障害当事者にもわかりやすいリーフレットを作成し、障害のある人の子育てが広がるようにする。
・こども家庭センターにおいて障害のある妊産婦・保護者等からの相談があった場合に、その把握・支援に係る障害保健福祉部局等の関係機関と連携の上で相談対応を行う。
・地域における相談の中核的な役割を担う機関である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)に基づく基幹相談支援センターの全国の市町村における設置を促進する。
・利用者の希望に沿った地域生活への移行を推進し、安心して地域生活を送れるよう、コーディネーターの配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制の構築も含めた、地域生活支援拠点等の全国の市町村における整備を促進する。
・令和7年10月開始予定の障害者本人の希望・適性等に合った選択を支援するためのサービス「就労選択支援」の円滑な施行に向けた準備を進める。
② 公務員の意識改革に向けた取組の強化
障害のある人に対する偏見や差別の根絶に向けた施策を推進するに当たり、行政機関においては、正しい知識をもって対処する必要がある。
「障害者差別解消法」では、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し職員が適切に対応するため、国の行政機関の長及び独立行政法人等は基本方針に即して「国等職員対応要領」(以下本章では「対応要領」という。)を定めることとされている。「行動計画」の策定にあたって、国の行政機関や独立行政法人等全655機関を対象に、「対応要領」に基づく職員への研修・啓発の実施状況等について調査を行った。この結果、分かったことは、主に以下のとおりである。
・「対応要領」の周知は、本府省では全府省庁が行っているが、周知の頻度は、策定・改定時のみとしているものが9割程度であり、定期的な周知を図る機関は少数である。
・本府省における新規採用職員向けの研修実施割合は約5割だが、既存職員への研修は2~3割程度にとどまっている。
・障害の定義、障害者差別の禁止の具体的内容、障害の特性については、多くの研修でその内容に含まれているが、障害者の実体験や具体的な事例検討等は含まれていない。また、旧優生保護法の歴史的経緯についての研修も極めて少数である。研修の理解度を確認するテスト等の実施割合は6割程度以下にとどまっている。
・当事者による講義の実施や教材の作成等、研修の内容への当事者の関与がない機関はおおむね7割以上となっている。
調査結果で明らかになった課題に対応するため、「行動計画」では、主に以下の取組を行うこととしている。
・各府省庁において、「対応要領」を毎年1回以上、全職員に周知する。
・2025年度に実施する国家公務員や地方公務員の人権研修において、旧優生保護法の歴史的経緯や被害当事者の声を取り入れ、同様の事態が生じないよう、公務員に対して人権啓発を行う。
・全ての幹部職員を対象とする障害当事者を講師とする障害者差別や障害の理解のための研修を2025年度中に実施する。
・障害当事者の参加の下、障害者の実体験、具体的事例の検討や旧優生保護法の措置を含む歴史的経緯なども含めた教材等を2025年度中に作成し、全府省庁等において研修を開始する。研修に当たっては、各府省庁等において、受講者の理解度を確認する。
・内閣府より、各府省庁及び地方支分部局の障害者差別の防止に係る研修の講師として、障害当事者や専門家を紹介する仕組みを2025年中に整備する。
また、このほか、「旧優生保護法に基づき、又はその存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を有すること等を理由に、優生手術等を受けることを強いられ、耐え難い苦痛と苦難を受けてきたことへの真摯な反省の下、全大臣から、各府省庁職員に向けて、障害のある人への偏見や差別を許さない旨のメッセージを自ら発信する」こととした。
③ ユニバーサルデザイン2020行動計画で提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化
「ユニバーサルデザイン2020行動計画」は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を機に策定された。同計画では障害の「社会モデル」を全ての人が理解し、意識と行動を変えることで社会全体の価値観を転換することを目指して、国民の意識啓発やコミュニケーションの変革を促す「心のバリアフリー」の取組が盛り込まれた。
ただし、同計画の策定から5年以上が経過し、その後の動きの中で、2022年の障害者権利委員会の総括所見において、日本の障害関連政策に恩恵的な性格が残っていることが指摘され、障害者の尊厳と権利を中心に据えた取組への転換が求められている。このことなどから、取組を改めて点検し、幹事会でのヒアリングの意見なども踏まえ、新たな課題への対応を全ての省庁に求め、必要な取組を行動計画に盛り込むこととした。
具体的には、主に以下の取組を進めることとしている。
【教育】
・旧優生保護法等の検証を踏まえた人権教育の教材を作成し、学校教育において活用を図るとともに、同教材を講演会等の人権啓発活動にも活用する。また、今後の教育課程における取扱いについて検討する。
・障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指し、特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的運営するインクルーシブな学校運営モデルの構築に取り組む。
【企業等での対応】
・「障害者差別解消法」に基づき、業種別に策定されている「対応指針」への民間企業等の対応状況(合理的配慮、相談体制、研修の実施等)について、2025年度中に調査を行い、好事例について横展開する。
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)に基づく雇用分野の障害者差別禁止指針・合理的配慮指針について事業主に対して周知を行うとともに、差別禁止や合理的配慮好事例集等の更新を行い、ホームページを通じて横展開する。
・重度障害者を含め、障害のある人が本人の希望や能力に沿った就労や修学を実現するために、障害者雇用納付金制度に基づく助成金による就労に係る支援や地方公共団体の補助事業等により、雇用・教育・福祉施策が連携しながら、重度障害者に対する就労・修学支援を推進する。
【理解促進】
・障害者週間において、体験作文やポスターの作品展を行うとともに、2025年度以降、企画段階から障害当事者の意見を聴きながら、障害の「社会モデル」などの理解に資する内容の体験型ワークショップの実施及び障害当事者団体等によるオンラインによるセミナーを実施する。
・障害のある人やその家族の協力を得つつ、障害の「社会モデル」を踏まえた正しい理解の促進を図る。
・医療・障害福祉の専門職の養成課程等における教育内容の充実等により、質の高い専門職の養成を図る。
ⅰ 医師・歯科医師の養成課程及び生涯教育において、障害のある人に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害の「社会モデル」の考え方を踏まえて障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努める。
ⅱ 精神保健指定医の研修過程において、精神障害のある人の人権に関する法令や精神医学等に関する研修を実施する。
ⅲ 障害福祉分野の専門職の養成課程において、障害者福祉の歴史、障害者の権利擁護、尊厳の尊重、障害の「社会モデル」の考え方に係る内容を盛り込んでおり、直近の社会の情勢等を踏まえつつ、引き続き、質の高い専門職の養成に向け取り組む。
・障害者団体等が行う障害特性の理解を図る啓発事業について一覧的に情報発信し参加を促進する。
・国民に向けた精神疾患やメンタルヘルスに係る正しい知識の普及啓発を実施する。また、心のサポーター養成等の地方公共団体が行う普及啓発を支援する。
・職場内で精神・発達障害のある同僚を見守る「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成講座を開催するなどにより精神・発達障害に関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神・発達障害のある人の特性に応じた支援の充実を通じて、精神・発達障害のある人の雇用拡大と定着促進を図る。
・精神障害のある当事者やその家族を含む様々な有識者による「精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会」を開催し、医療保護入院や身体的拘束を含む精神保健医療福祉の様々な課題を幅広く検討する。
・障害のある人とない人との相互理解の促進や障害のある人の社会参加のきっかけ作り、インクルーシブな社会の実現に向けた情報発信等を目的として、障害の有無にかかわらず楽しみ、交流することができる普及啓発イベントを新たに実施する。
【人権侵害への対応】
・2024年度中に、全国の法務局・地方法務局に対し、旧優性保護法に関する研修用DVDを配布し、人権相談や調査救済活動に従事する法務局・地方法務局職員及び人権擁護委員を対象とする研修を実施する。
・人権相談窓口の周知広報を図るとともに、全国の法務局・地方法務局において、インターネット上のものも含め、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じる。その際、人権侵犯性の有無にかかわらず、「障害者差別解消法」の趣旨を踏まえたより望ましい対応を提示するなど積極的に啓発を行う。
④ 障害当事者からの意見を踏まえた今後に向けた更なる検討
①~③の取組のほか、様々な意見がヒアリングにおいて示された。このため、ヒアリングでの障害当事者等の意見を受け止め、記憶を風化させないようにするための方策、人権侵害に迅速に対応する実効性のある体制の構築など、幹事会で示された問題意識について引き続き検討することとした。その際、今後予定されている国会による旧優生保護法に係る調査・検証の内容・結果も踏まえるとともに、障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向け、法制度の在り方を含め、教育・啓発等の諸施策を検討し、実施するものとしている。
(3)計画策定後の動き
2025年3月10日に開催した第82回障害者政策委員会では、行動計画に関する意見交換が行われた。委員からは、公務員への研修プログラムへの障害当事者の確実な参画、インクルーシブ教育の重要性、女性への複合差別の課題への対応などについての意見があった。「行動計画」に係る意見聴取を経て、今後、次期障害者基本計画などにも反映させていくこととしている。
なお、「行動計画」の策定後、各省庁において、全ての職員向けに、障害者への偏見や差別の根絶に向けたメッセージを、全ての大臣から発出している。内閣府では、2025年1月23日に、内閣官房長官訓示としてメッセージを全職員に発出した。
障害の「社会モデル」とは、障害者が日常生活又は社会生活で受ける様々な制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生じるものという考え方である。社会的障壁には、施設、設備のような物理的なものだけでなく、制度、慣行や偏見などの観念も含まれる。
この考え方は、「障害者権利条約」において採用されており、我が国でも、「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)や「障害者差別解消法」において、「障害者」の定義や、「合理的配慮」(社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮)に取り入れられている。
2024年12月の「行動計画」においても障害の「社会モデル」の普及が掲げられている。共生社会の実現に向け、障害のある人の社会参加を制限している様々な社会的障壁を社会全体で取り除くようにしていくことが重要である。
※ 障害の「社会モデル」に対し、障害は個人の心身の機能の障害によるものであるという考えを「医学モデル」という。
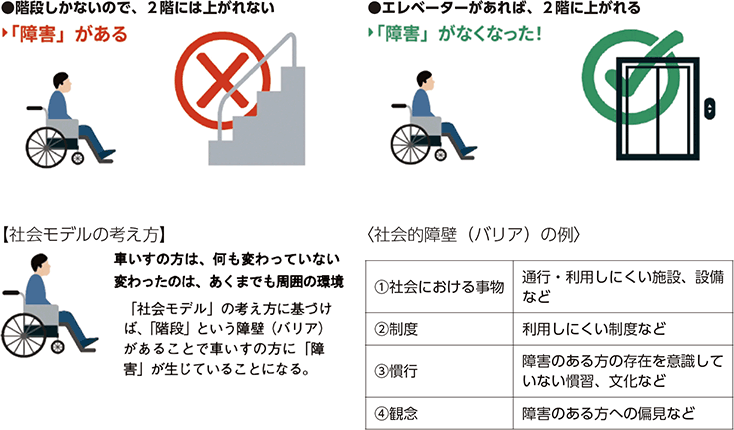
令和6年7月29日に開催された第1回推進本部において岸田文雄内閣総理大臣は、障害者に対する偏見や差別のない共生社会を実現すべく、必要な対応策を検討して新たな行動計画を取りまとめることとし、幹事会において、有識者の協力を得て、障害当事者から意見を聴取した上で、成果を取りまとめる体制を構築するよう指示した。総理の指示を踏まえ、政府は「幹事会」を開催し、旧優生保護法の被害者や障害当事者からのヒアリングの実施を含め検討を行った。
幹事会は、議長である内閣官房副長官補(内政担当)の下、構成員として、全ての省庁から官房長・局長級が出席した。また、障害当事者を含む有識者も構成員としており、石川准氏(静岡県立大学名誉教授・障害者政策委員会前委員長・視覚障害者)、坂元茂樹氏(公益財団法人世界人権問題研究センター理事長)、田門浩氏(弁護士・障害者権利委員会委員・聴覚障害者)が指名された。
幹事会でのヒアリングの問題意識は、「行動計画」に記載するとともに、意見の概要を資料として添付している。
同年12月27日の第3回においては、石破茂内閣総理大臣から、各大臣に対し、旧優生保護法に基づく施策が数多くの障害者の個人の尊厳を蹂躙し、数多くの苦痛を強いてきたという事実を重く受け止め、各所管分野を通じて、国民全体に障害についての正しい理解が行きわたるよう、地方公共団体や関係者とも連携した「行動計画」の着実な実施と継続的なフォローアップを求めた。また、これらの施策を進める公務員の意識改革に向け、各府省庁において障害当事者が参画した研修の実施など、これまで以上に取組を強化するとともに、各大臣自ら、職員に向けて、障害のある人への偏見や差別の根絶に向けたメッセージを発信するよう指示した。最後に、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府一丸となって取り組む決意を示し、各大臣への協力を要請した。
<開催実績>
第1回推進本部 7月29日 総理指示
第1回幹事会 7月29日 幹事会の進め方等について議論
第2回幹事会 8月30日 有識者構成員による講演
第2回推進本部 9月20日 基本合意書締結の報告、進捗状況の確認
第3回幹事会 10月21日 当事者ヒアリング①
・熊谷 晋一郎氏(障害者政策委員会委員長)
・佐藤 聡氏(DPI日本会議事務局長)
第4回幹事会 11月7日 当事者ヒアリング②
・旧優生保護法訴訟原告5名の方
第5回幹事会 11月13日 当事者ヒアリング③
・全国手をつなぐ育成会連合会
・南高愛隣会(子育てをする障害のある御家族)
第6回幹事会 11月20日 当事者ヒアリング④
・日本ALS協会
・日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構
第7回幹事会 12月26日 新たな行動計画(案)の決定
第3回推進本部 12月27日 新たな行動計画の決定
※別途、以下の団体に、内閣府において個別にヒアリングを実施
全国重症心身障害児(者)を守る会、全国精神保健福祉会連合会、全国脊髄損傷者連合会、日本発達障害ネットワーク、全国肢体不自由児者父母の会連合会、全日本ろうあ連盟、日本相談支援専門員協会、日本身体障害者団体連合会、日本視覚障害者団体連合、DPI女性障害者ネットワーク、全日本難聴者・中途失聴者団体連合会、全国盲ろう者協会

推進本部
<構成員>
本部長 内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官
内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画 共生・共助)
本部員 他の全ての国務大臣
推進本部幹事会
<構成員>
議長 内閣官房副長官補(内政担当)
副議長 内閣府政策統括官(共生・共助担当)
構成員 他の各省庁局長級職員等
<有識者構成員(五十音順、敬称略)>
石川 准 静岡県立大学名誉教授(視覚障害当事者)
坂元 茂樹 公益財団法人世界人権問題研究センター理事長
田門 浩 弁護士(聴覚障害当事者)

