第1章 障害者に対する偏見や差別をなくすための取組について 第1節 2
第1節 旧優生保護法に関する政府の対応
2.旧優生保護法の被害者への補償
(1)障害者差別解消法の趣旨
旧優生保護法は、終戦直後の人口過剰問題等を背景に、1948年に議員提案によって全会一致で制定された。優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的として、優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等について規定していた。同法が母体保護法に改正される1996年までの間、旧優生保護法に基づき、約2万5000件の優生手術が実施された。
2018年1月、国に対し、旧優生保護法の優生手術に関する規定は憲法に違反しており、国会議員の立法行為は違法であるなどとして、「国家賠償法」(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償などを請求した訴訟(以下本章では「旧優生保護法国家賠償請求訴訟」という。)が、仙台地方裁判所に初めて提訴され、以降全国各地で提訴が相次いだ。
こうした動きの中で、2019年4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年法律第14号。以下本章では「一時金支給法」という。)が議員立法により全会一致で可決・成立し、即日公布・施行され、被害者の方々に対する320万円の一時金の支給が開始された。2024年7月3日、最高裁判所において、旧優生保護法の優生手術に関する規定を憲法違反とし、当該規定に係る国会議員の立法行為は、「国家賠償法」第1条第1項の適用上違法であり、国の損害賠償責任を認める判決(以下本章では「最高裁判決」という。)が言い渡された。これを受け、同月17日に、岸田文雄内閣総理大臣が旧優生保護法国家賠償請求訴訟の原告団の方々と面会し、政府を代表して心からの謝罪を申し上げるとともに、訴訟についても早急な解決に向けた取組を進めることを表明した。同年9月13日には、加藤鮎子内閣府特命担当大臣と優生保護法被害全国原告団及び優生保護法被害全国弁護団との間で、「係属訴訟の和解等のための合意書」1が締結された。この合意書に基づき、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の原告の方々と和解協議を進め、同年11月15日、関連する訴訟の全件が和解により終局した。
加えて、同年9月30日、加藤鮎子内閣府特命担当大臣と優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会との間で、「基本合意書」が締結された。
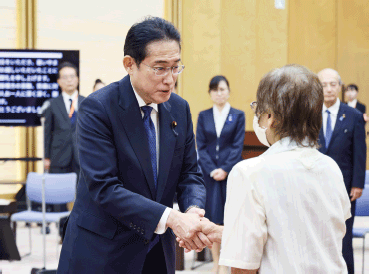

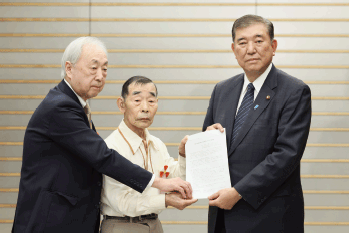
また、提訴していない方々も対象とする新たな補償についても、最高裁判決を受け、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(令和6年法律第70号。以下本章では「補償金等支給法」という。)が「一時金支給法」を全部改正する形で同年10月8日に議員提案により全会一致で可決・成立し、同月17日に公布された。
「補償金等支給法」の施行日である2025年1月17日には、石破内閣総理大臣が旧優生保護法国家賠償請求訴訟の原告団の方々と面会した。原告団の方々から、これまでの経験や思いなどを直接伺い、「補償金等支給法」に基づく新たな補償が被害者の方々に届くよう力を尽くしていくことを表明した。政府としては、引き続き都道府県等とも連携して、周知・広報に努めていくこととしている。
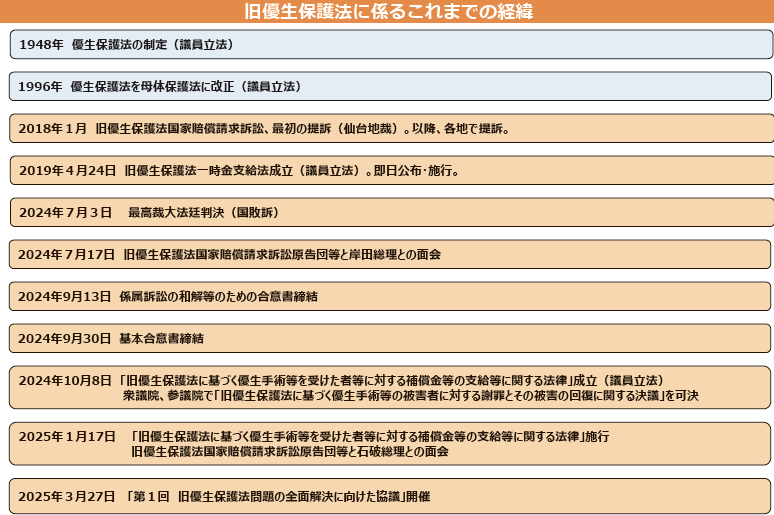
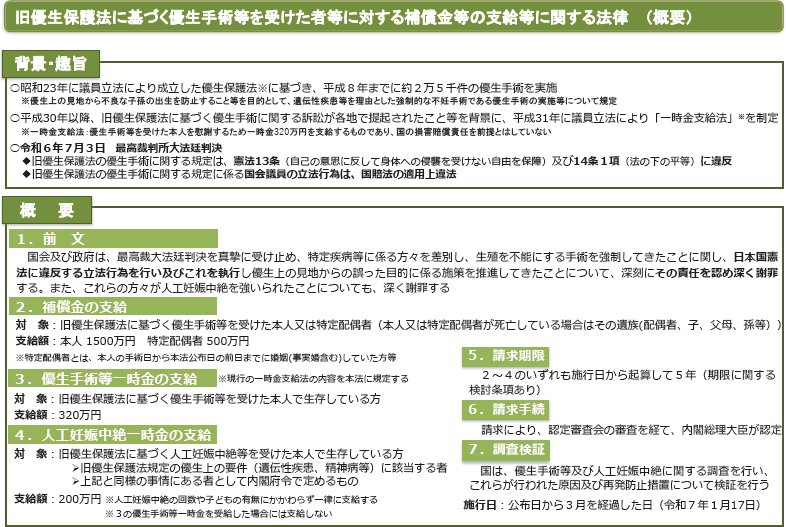
(2)恒久対策等について
ア 調査及び検証等
「補償金等支給法」第33条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとされた。この検証については、今後、国会が主体となって行うが、政府としても、適切に協力しその責任を果たしていくこととしている。
イ 継続的・定期的な協議について
2024年9月30日、加藤鮎子内閣府特命担当大臣と優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会との間で、「基本合意書」が締結された。この「基本合意書」に基づき、優生保護法問題の全面的な解決に向けた施策等の検討、実施に当たって、優生保護法被害全国原告団等と関係府省庁との協議の場を設置し、継続的・定期的な協議を行うこととしている。2025年3月27日に「第1回旧優生保護法問題の全面解決に向けた協議」が開催された。
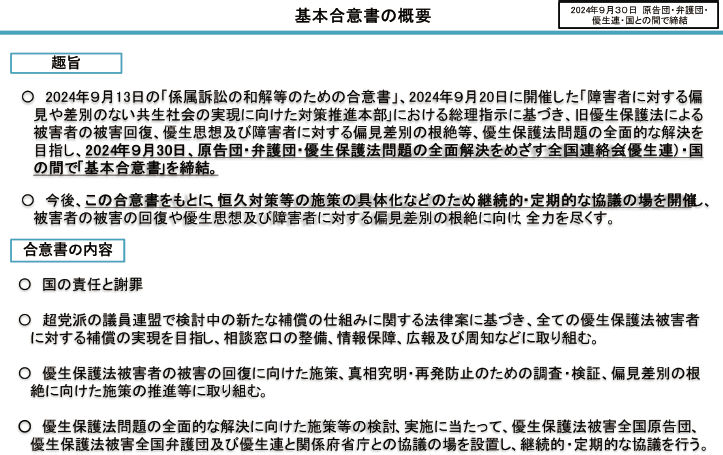
1 この合意書において、国は、原告が優生手術被害者本人のみの場合にはその優生手術被害者本人に1500万円を損害賠償金(慰謝料相当額)として支払うこととし、原告が優生手術被害者本人とその配偶者の場合には優生手術被害者本人に1300万円、その配偶者に200万円をそれぞれ損害賠償金(慰謝料相当額)として支払うこととした。

