第4章 障害のある人がその人らしく暮らせるための施策 第1節 5
第1節 生活安定のための施策
5.スポーツ・文化芸術活動の推進
(1)スポーツの振興
ア パラスポーツの普及促進
令和6年度「障害児・者のスポーツライフに関する調査研究」によると、障害のある人(20歳以上)の週1回以上の運動・スポーツ実施率は32.8%(障害のない人も含めた20歳以上全体の実施率は52.5%(令和6年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」))にとどまっており、障害の有無に関わらず、いつでも、どこでも、誰もがスポーツを気軽に楽しめるよう、身近なところでスポーツを実施できる環境を整備することが重要な課題となっている。
身近な地域の拠点である「障害者スポーツセンター」の設置が一部の都府県や政令市にとどまっていることから、障害者スポーツセンターの整備を検討する地方公共団体や、既存の障害者スポーツセンターの機能強化を検討する地方公共団体に対して、計画策定のための支援等を実施している。
また、広く日本の各地でパラスポーツ活動の機会が創出されるよう、都道府県・指定都市パラスポーツ協会、同パラスポーツ指導者協議会、パラスポーツ競技団体に対し、スポーツ活動の場づくりや体制の強化等の構築に必要な支援を実施している。
さらに、生涯にわたってスポーツ活動を定着させるためには、学齢期からスポーツに親しむことが重要である。特別支援学校等の児童生徒がスポーツ活動に継続して親しめるよう、総合型地域スポーツクラブや社会福祉施設等、多様な地域資源と連携した運動部活動の地域連携・地域移行に向けたモデルの創出や特別支援学校等の全国規模の競技会の開催支援に取り組んでいる。
「未来社会の実験場」をテーマとする2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)において、パラスポーツにおける先端技術を活用した取組の展示・体験を予定している。


(全国ボッチャ選抜甲子園)の様子
イ 障害者スポーツの競技力向上
スポーツ庁では、パラリンピックの競技特性や環境等に十分配慮しつつ、オリンピック競技とパラリンピック競技の支援内容に差を設けない一体的な競技力強化支援に取り組んでいる。
具体的には、「競技力向上事業」を通じて、障害者スポーツの競技団体を含む各競技団体が行う強化活動に必要な経費等の支援を実施しているほか、「ハイパフォーマンス・サポート事業」を通じて、国際総合競技大会期間中、アスリート、コーチ、スタッフが競技へ向けた最終準備を行うためのスポーツ医・科学、情報サポート等の支援を可能とする現地サポート拠点を設置している。
特に、パラリンピック競技大会において、メダル獲得が期待される競技を「重点支援競技」として選定し、競技力向上事業助成金の加算のほか、ハイパフォーマンス・サポート事業により、トレーニング、映像分析など各分野の専門スタッフの帯同活動等のアスリート支援を実施している。2024年度においては、パリ2024パラリンピック競技大会とミラノ・コルティナ2026パラリンピック競技大会の重点支援競技に対して、これらの支援を行った。
このほか、ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)を中心として、競技特性に対応した最適なコンディショニングの研究、先端技術を活用した多様な支援手法の研究、チェアスキーなどの競技用具等の研究等、継続的にパラアスリートの選手強化が行えるシステムの構築を目指す「先端技術を活用したHPSC基盤強化事業」を実施した。クラス分け6に関する最新の国際的な動向の把握や専門人材の育成等を行う中枢機関として2024年4月に日本パラリンピック委員会(JPC)に設置された「JPCクラス分け情報・研究拠点」に対する支援等も通じ、パラリンピック競技の国際競技力向上を図ることとしている。
(2)文化芸術活動の振興
我が国の障害のある人による文化芸術活動については、共生社会の実現に向けて、広く文化芸術活動の振興につながる取組が行われている。
2018年6月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」(平成30年法律第47号)が成立・施行されたことを受け、国は、同法に基づき、2019年3月に第1期、2023年3月に第2期の「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」を策定した。この計画に基づき、以下の取組を始め、障害のある人による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進しているところである。
厚生労働省では、2017年度から地域における障害のある人の自立と社会参加の促進を図るため、全国に芸術文化活動に関わる支援センター等の設置を行い、支援の枠組みを整備する「障害者芸術文化活動普及支援事業」を実施し、障害のある人の芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)の更なる振興を図っている。
また、障害のある人の生活を豊かにするとともに、国民の障害への理解と認識を深め、障害のある人の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として2024年に「清流の国ぎふ」文化祭2024(第39回国民文化祭、第24回全国障害者芸術・文化祭)を開催した。
文化庁では、美術・舞台芸術・音楽等の様々な文化芸術分野における鑑賞・創作活動・発表等に係る幅広い取組の推進や普及展開に向けた人材の育成、文化芸術へのアクセスの改善、助成採択した映画作品や劇場・音楽堂等において公演される実演芸術のバリアフリー字幕・音声ガイド制作への支援、特別支援学校の生徒による作品の展示や実演芸術の発表の場の提供等、障害者の文化芸術活動の充実に向けた支援に取り組んでいる。
国立美術館、国立博物館は、障害者手帳を持つ人について展覧会の入場料を無料としているほか、全国各地の劇場、コンサートホール、美術館、博物館などにおいて、車椅子使用者も利用ができるトイレやエレベーターの設置等障害のある人に対する環境改善も進められている。
文化庁では、2025年に開催される「大阪・関西万博」に向けて、「日本博2.0」事業において、引き続き文化芸術による共生社会の実現に向けた我が国の取組を国内外に発信していく。
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会では、施設整備、運営サービス、交通アクセスの各分野において、障害当事者や学識経験者等の意見を伺いながら、「ユニバーサルサービスガイドライン」等を策定し、これらにのっとって準備を進めている。日本政府館についても、こうしたガイドライン等に準拠し、ユニバーサルデザインの実現を図ることを目的として、2023年度に引き続き2024年度も「大阪・関西万博」日本館ユニバーサルデザインワークショップを実施し、検討結果について設計・運営等に反映した。また、障害の有無にかかわらず万博に来場しやすいようにするため、車椅子利用者や視覚に障害のある人のための移動のサポートや、視覚に障害のある人向けナビゲーションアプリの導入に向けた調整が行われた。さらに、万博会場への来場が困難な方も万博の様々なコンテンツを体験することができるよう、現地の開催期間にあわせて、インターネットを介して参加することのできるバーチャル万博を開催することとしている。
◯日本代表選手団の活躍
フランス・パリにおいて、パリ2024パラリンピック競技大会が2024年8月28日から9月8日まで開催された。本大会では、海外開催大会で過去最多となる11競技でメダルを獲得したほか、車いすラグビーや柔道(女子)等複数の競技種別において、競技初・種目初となる金メダルやメダルを獲得するなど、素晴らしい結果を収めた。さらに、18歳から61歳まで幅広い世代のメダリストが誕生し、国民全体に夢と希望を与えた。
2025年は「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025」が、2026年には「愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会」が開催される。スポーツ庁としては、パリ大会の成果等を踏まえながら、東京大会で育み、パリ大会で引き継がれたレガシーを継承しつつ、パラスポーツの国際競技力向上に向けた取組を実施していく。


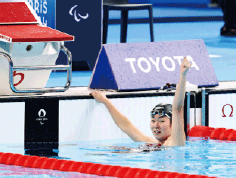

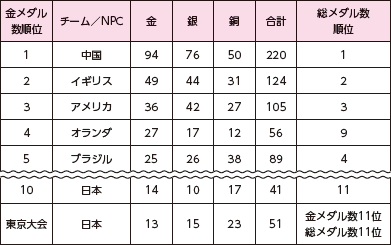
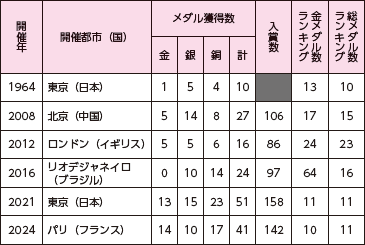
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会により、パラスポーツは国民の大きな関心を集め、スポーツを通じた共生社会の実現に向けた取組を進める契機となった。このオリパラレガシーを更に継承・発展する観点から、「第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025」、「愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会」等が控えている好機を生かすべく、取組を加速する必要がある。
この共生社会の実現に向けて、2025年度は、障害のある人とない人がともにスポーツを楽しむ機会を創出するため、競技団体と民間企業が連携し、障害のある児童とない児童が同一チームを編成した小学生ボッチャ大会といったインクルーシブなスポーツ大会や、公園や商業施設等のオープンスペースを活用したスポーツ体験、デジタル技術を活用したスポーツ体験など、パラスポーツ団体や民間企業が行っている先進的なモデルとなる取組について支援している。
また、スポーツ庁では、民間企業とパラスポーツ団体、地方自治体の連携を促進し、パラスポーツに関する新たな取組を創出するための連携基盤として「U-SPORT PROJECTコンソーシアム」を開設した。コンソーシアムでの活動を通じて、各加盟団体が自団体の強みを発見し、他団体との連携により継続性・持続性のある新たな取組の創出を図り、共生社会の実現に向けた機運醸成につなげることを目指している。
さらに、聴覚障害者の国際大会であるデフリンピックが日本で初めて開催されることを踏まえ、デフスポーツの振興のみならず聴覚障害者への理解促進を進めるため、全国各地で開催されるデフスポーツ体験等のイベントを支援している。

における車椅子ソフトボール体験会

【デフリンピックとは】
デフリンピックは国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)の主催で4年に1度世界的規模で行われる聴覚障害者のための総合スポーツ競技大会であり、夏季大会と冬季大会が開催されている。デフ(Deaf)とは英語で「耳がきこえない」という意味であり、「デフリンピック」の名称は2001年に国際オリンピック委員会が承認した。
競技は一般の競技ルールに準拠するが、競技会場に入った時点から補聴器等の使用は禁止されることや、競技運営に国際手話のほか、スタートランプや旗などを利用した視覚による情報保障がなされることが特徴である。実施競技は、夏季大会が21競技、冬季大会が6競技である。
夏季大会は1924年にフランスのパリで第1回大会が開催され、2022年にはブラジルのカシアス・ド・スルにおいて第24回大会が開催された。冬季大会は1949年にオーストリアのゼーフェクトで第1回大会が開催され、2024年にトルコのエルズルムにおいて第20回大会が開催された。
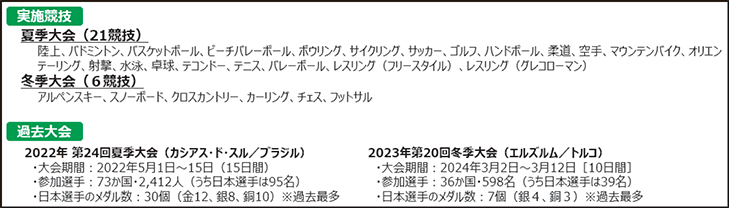
【第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025】
2025年11月15日(土)から26日(水)まで東京都、静岡県、福島県において「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025」が開催される。デフリンピック100周年の記念すべき大会であり、日本では初めての開催となる。
大会ビジョンとして、「デフスポーツの魅力や価値を伝え、人々や社会とつなぐ」、「世界に、そして未来につながる大会へ」、「“誰もが個性を活かし力を発揮できる” 共生社会の実現」を掲げており、東京都の会場を中心に21競技が実施される予定である。
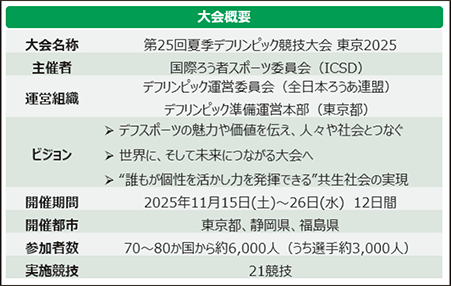
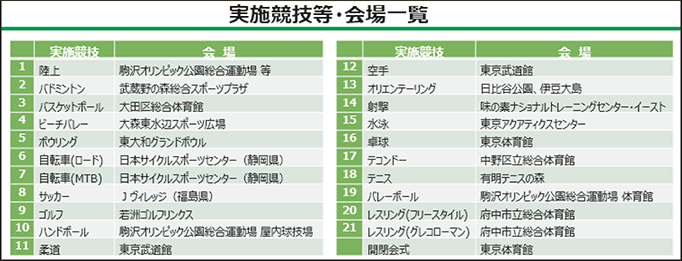
スポーツ庁では、全日本ろうあ連盟や東京都などの関係団体と連携し、大会の成功に向けて必要な支援・協力を行っている。具体的には、機運醸成活動への協力や、デフアスリートの強化支援、スタートランプを始めとする障害者スポーツ用具の整備の支援などに取り組んでいる。
特に、機運醸成活動については、大会開催1年前イベントとなる「東京2025デフリンピック1Year To Go!」を始めとしたイベントへ協力するほか、文部科学省エントランスでの広報物展示やこども霞が関見学デーでの大会PRコーナーを出展するなど、大会の成功及びデフスポーツの振興に向けて取り組んでいる。
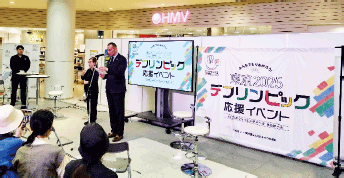
会場:ららぽーと富士見

会場:アーバンドック ららぽーと豊洲

会場:文部科学省

会場:文部科学省
文化庁では、2024年12月の「障害者週間」にあわせて、京都市岡崎公園に立地する美術館、劇場、図書館、動物園等の文化施設が連携し、共生や多様性について考えるプロジェクト「CONNECT⇄(コネクト)_~アートでのびのび ひろがるわたし~」を開催した。
京都での5回目の開催となる今回は、CONNECT ⇄_全体のインフォメーションセンターの役割を担うとともに、来場者が多様な表現や作品に触れられる展示、五感で遊べる仕掛けや、休憩もできる空間を備えた「のびのびストリート」をロームシアター京都等に設置した。
また、各プログラムをより深く楽しみ、共生について考えることを目的として、「なんでもOKなダンスパフォーマンス」を作り上げたプロセスや、視覚障害のある人の読書をめぐる現在をひもとき、参加者と出演者による双方向のディスカッションを行うトークイベント等を開催した。
さらに、参加施設が芸術家を特別支援学校に派遣し、生徒とダンスワークショップを行うなど、特別支援学校と連携したプログラムについても、2023年度に引き続き実施した。
各参加施設でも、CONNECT ⇄_の開催期間において、筆談による美術鑑賞会や、声に出して伝えることについて学ぶ朗読会、鑑賞マナーのないダンスと音楽のパフォーマンス、視覚に障害のある方との対話型美術鑑賞の映像展示、音の特徴を振動や光で体に伝達する機器Ontenna(オンテナ)を用いた動物園めぐりなど、障害当事者と共に考える多様なプログラムを展開した。

会場:ロームシアター京都

「読みたい!をかなえる方法―視覚障害者の読書から考える―」
会場:京都府立図書館

会場:ロームシアター京都

会場:京都市動物園
6 クラス分け:競技者の障害が、定められた規則の出場資格のある障害に該当するか決定し、競技や種目の基礎的な動作に影響する競技者の障害程度に基づいて、競技クラスに競技者をカテゴリー分けすること。競技者クラス分けともいう。

