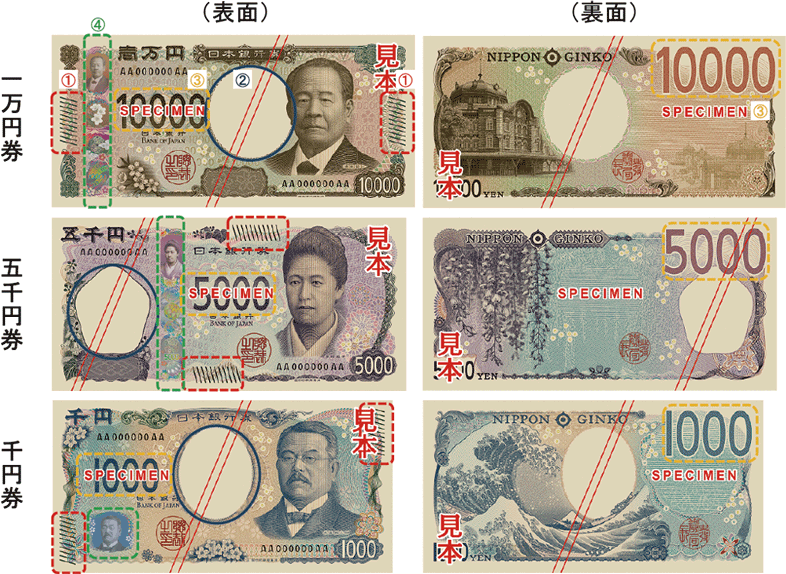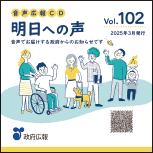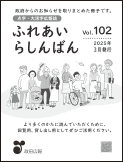第5章 住みよい環境の基盤づくり 第2節 3
第2節 障害のある人の情報アクセシビリティを向上するための施策
3.情報提供の充実
(1)情報提供に係る研究開発の推進
総務省では、障害のある人や高齢者向けの通信・放送サービスの充実に向けた、新たなICT機器・サービスの研究開発を行う者に対する支援のほか、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)を通じて、身体障害のある人のための通信・放送サービスの提供又は開発を行う者に対する助成、情報提供を実施している。
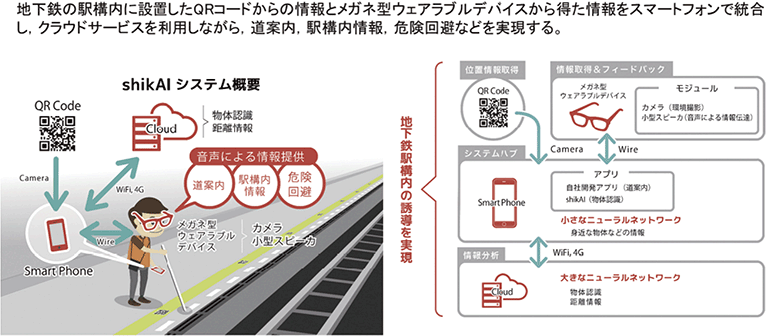
(2)情報提供体制の整備
ア 情報ネットワークの整備
厚生労働省において、在宅の身体に障害のある人もあまねく高度情報通信技術の恵沢を享受することを目的に、各団体が実施する以下の取組に対する支援を実施している。
① 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合においてネットワークを利用し、新聞情報等を即時に全国の点字図書館等で点字データにより受信でき、かつ、視覚障害のある人が自宅にいながらにしてウェブ上で情報を得られる「点字ニュース即時提供事業」
② 社会福祉法人日本点字図書館を中心として運営されている視覚障害者等用情報総合ネットワーク「サピエ」により、点字・録音図書情報等の提供
③ 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会が運営している「障害者情報ネットワーク(ノーマネット)」において、障害のある人の社会参加に役立つ各種情報の収集・提供と、情報交換の支援や、国内外の障害保健福祉研究情報を収集・蓄積し、インターネットで提供する「障害保健福祉研究情報システム」
イ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進
2019年6月に、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号。以下本章では「読書バリアフリー法」という。)が議員立法により成立・施行された。
その後、2020年7月、「読書バリアフリー法」第7条に基づき、文部科学省及び厚生労働省において、2020年度から2024年度の5年間を期間とする、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」(以下本章では「基本計画」という。)を策定した。
また、同法第8条により、地方公共団体は、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画の策定に努めることとされていることから、「基本計画」の策定に併せ、地方公共団体や関係機関等に向けて、「読書バリアフリー法」の趣旨を踏まえた取組の実施を促すための通知を発出した。
毎年、「基本計画」に記載の各施策の進捗状況の確認や関係者との協議等を行う場として、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会」を開催しており、2024年度においては、「基本計画」(第二期)の策定に向け、関係者からの意見聴取や、協議を行った。その後パブリックコメントを経て、図書館等におけるアクセシブルな書籍の充実や点字図書等の視覚障害者等が利用しやすい書籍の効率的な製作に向けた実証調査の実施等を新たに盛り込み、2025年3月に基本計画(第二期)を策定した。
ウ 政府広報における情報提供
内閣府では、視覚に障害がある人等が、円滑に必要な情報を取得し、利用することができるよう、政府の重要施策等の情報をわかりやすくまとめた音声広報CD「明日への声」及び点字・大活字広報誌「ふれあいらしんばん」を発行(年6回、各号約4,000部)している。「明日への声」及び「ふれあいらしんばん」はそれぞれ全国の視覚障害者情報提供施設、日本視覚障害者団体連合、特別支援学校、公立図書館(都道府県、政令市、中核市、特別区立等)、地方公共団体等に配布(約3,000か所)している。
エ 字幕付きビデオ及び点字版パンフレット等の作成
法務省では、犯罪被害者やその家族、さらに一般の人々に対し、検察庁における犯罪被害者の保護・支援のための制度についてわかりやすく説明したDVD「あなたの声を聴かせてください」を2021年度に新たに作成し、全国の検察庁に配布するとともに、YouTube法務省チャンネルで配信しており、説明のポイントにテロップを利用しているほか、全編に字幕を付けるなど、聴覚障害のある人も利用できるようになっている。
また、犯罪被害者等向けパンフレットの日本語版に音声コード(専用の機械又はアプリで読み取らせることにより、本文の音声読み上げが可能なもの)を導入したほか、点字版を作成し、全国の検察庁及び点字図書館等へ配布を行い、視覚障害のある人に情報提供している。
法務省では、2024年度に民間事業者を主な対象として、障害を理由とする偏見・差別の解消に向けた取組の重要性について理解を深めることを目的とした啓発動画を新たに作成し、全国の法務局・地方法務局において貸出しを行っている。
なお、各種人権課題に関する啓発動画を作成する際には、字幕付動画も併せて作成するとともに、啓発冊子等に、音声コードを導入し、聴覚や視覚に障害のある人も利用できるようにしている。
(3)字幕放送、解説放送、手話放送等の推進
視聴覚障害のある人等が、テレビジョン放送を通じて情報を取得し、社会参加していく上で、字幕放送、解説放送、手話放送等の普及は重要な課題であり、総務省においては、その普及を推進している。
1997年の「放送法」(昭和25年法律第132号)改正により、字幕番組及び解説番組をできる限り多く放送しなければならないとする努力義務規定が設けられた。これを受けて、同年、郵政省(当時)は字幕放送の普及目標を定めた「字幕放送普及行政の指針」を策定した。
その後、総務省は、2007年に字幕放送及び解説放送(2012年改定時に手話放送を追加)の普及目標を定めた「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」の策定を経て、2018年に2027年度までの字幕放送、解説放送及び手話放送の普及目標を定める指針について、障害者を含むすべての人が放送によるすべての情報にアクセスすることを目指す観点から、「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」として策定し、2023年10月に手話放送の更なる充実等のための改定を行った。現在はこの指針に基づき、各放送事業者において取組が進められている。
加えて、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)を通じて字幕番組、解説番組、手話番組や手話翻訳映像等の制作費や生放送番組への字幕付与設備の整備費の一部助成も行っている。特に、生放送番組への字幕付与については、多くの人手とコストがかかり、特殊な技能を有する人材等を要することから、特にローカル局等において普及が進んでいない。また、深夜・早朝に災害が発生した場合には、人員の参集に時間がかかるため、緊急速報等に対する迅速な字幕付与が困難であることも課題となっている。このような課題への対応として、最先端の技術を活用した、生放送番組への字幕付与システムについても上記助成事業の対象とし、設備の導入を促している。

手話入り映像の撮影
字幕付きCMの普及についても、字幕付きCM普及推進協議会(公益社団法人日本アドバタイザーズ協会、一般社団法人日本広告業協会、一般社団法人日本民間放送連盟の3団体で構成)が、2020年9月に策定した「字幕付きCM普及推進に向けたロードマップ」に基づき、字幕付きCMの放送枠を増やす取組が東名阪地区を中心に進められ、2021年10月からは全国的な取組に拡大されている。
厚生労働省では、聴覚障害のある人のために、字幕(手話)入り映像ライブラリーや手話普及のための教材の制作・貸出し、手話通訳者等の派遣、情報機器の貸出し等を行う聴覚障害者情報提供施設について、ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、その支援を促進している。
(4)国政選挙における配慮
国政選挙においては、2003年の「公職選挙法」(昭和25年法律第100号)改正により、郵便等投票の対象者が拡大されるとともに、代理記載制度が創設されている。また、障害のある人が投票を行うための必要な配慮として、点字による候補者名簿等の投票所等への備付け、投票用紙に点字で選挙の種類を示す取組、点字又は音声による「選挙のお知らせ版」や「国民審査のお知らせ版」の配布、選挙公報の音声読上げ対応データのホームページへの掲載、投票所における点字器の備付け等を行っている。加えて、各選挙管理委員会における代理投票の際の投票の秘密に配慮した意思確認の方法などの事例を取りまとめた「代理投票時における投票の秘密に配慮した取組事例等について」(平成30年12月14日付け総行管第358号)、各選挙管理委員会における投票所における取組事例を取りまとめた「障害のある方に配慮した選挙事務の事例について」(令和5年1月30日付け総行管第75号)を発出し、各選挙管理委員会に対し、本資料を参照しつつ、障害のある方に配慮した取組を実施するよう周知した。
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙においては、上記の取組について改めて各選挙管理委員会に周知したほか、視覚障害者向け選挙啓発物資として点字パンフレット及び音声CDを総務省において作成し、各都道府県選挙管理委員会に対して対象者の方への配布及び公共施設への備え付け等を依頼した。
また、政見放送における取組として、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙及び都道府県知事選挙にあっては手話通訳を、参議院比例代表選出議員選挙にあっては手話通訳及び字幕を、それぞれ付与することができることとしている。また、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙にあっては、政見放送として一定の要件の下政党又は候補者が作成したビデオを放送することができ(いわゆる「持込みビデオ方式」)、政党又は候補者の判断により手話通訳や字幕を付与することができることとしている。
(5)日本銀行券の券種の識別性向上に向けた取組
日本銀行券については、偽造抵抗力強化とユニバーサルデザインの観点から、2024年7月3日より新たな様式で発行を開始した。
新しい日本銀行券について、視覚に障害のある人が券種を識別しやすくなるよう、財務省では、日本銀行や国立印刷局等の関係者からの意見等を踏まえ、以下のような工夫を施している。
① 券種を識別できるマークを、券種ごとに異なる位置に配置し、触った時にわかりやすい形状に変更した。
② 肖像のすかしが入る部分の形状に違いを設け、券種ごとに異なる位置に配置。
③ 表・裏両面のアラビア数字を大型化。
④ 高額券と千円券のホログラムの形状に違いを設けて、券種ごとに異なる位置に配置。