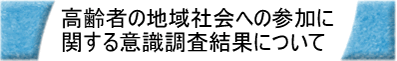
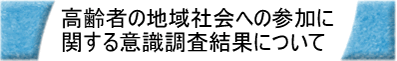
平成9年度高齢者対策総合調査として、60歳以上の一般男女ならびに60歳以上で社会的な活動を行っている男女に対して意識調査を実施しました。その調査結果の概要は次のとおりです。
21世紀初頭の本格的な高齢社会を目前に控え、心ゆたかな高齢社会を築くためには、国民一人一人がそれぞれの立場で地域社会に参加し、協力していくことが重要であり、特に高齢者には、これまで培ってきた、経験や能力を生かした積極的な参加が求められている。
このため、本調査は、昭和63年、平成5年に引き続き、高齢者一般及び現在社会参加活動を行っている高齢者の社会参加活動の実態及び意識等を調査し、今後の高齢関係施策の推進に資することを目的とする。
| 調査I | 全国の60歳以上の男女(以下「住民調査」という) |
| 調査II | (A)に掲げる団体に加入し、(B)に掲げる活動を行っている全国の60歳以上の男女(以下「活動者調査」という) |
| ア) | 老人クラブ | キ) | 市民運動団体 |
| イ) | 町内会・自治会 | ク) | 宗教団体(講などを含む) |
| ウ) | 婦人団体 | ケ) | 社会奉仕団体(ボランティア団体) |
| エ) | 趣味のサークル・団体 | コ) | 商工会・同業者団体 |
| オ) | 健康・スポーツのサークル・団体 | サ) | 退職者の団体(OB会など) |
| カ) | 学習・教養のサークル・団体 | シ) | シルバー人材センターなどの生産・就業組織 |
| ア) | 趣味(俳句、詩吟、陶芸等) |
| イ) | 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等) |
| ウ) | 生産・就業(生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) |
| エ) | 教育・文化(学習会、子供会の育成、郷土芸能の伝承等) |
| オ) | 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくり等) |
| カ) | 安全管理(交通安全、防犯・防災等) |
| キ) | 福祉・保健(在宅老人の介護・家事援助、施設訪問、食生活の改善等) |
| ク) | 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話役等) |
| 調査I | 調査員による面接聴取法により実施 |
| 調査II | 郵送法により実施 |
| ア) | 調査対象者の基本属性に関する事項 |
| イ) | 地域社会に参加するための環境に関する事項 |
| ウ) | 社会参加活動についての実態と意識に関する事項 |
| エ) | 地域奉仕活動についての考え方に関する事項 |
| オ) | 世代間交流についての実態と意識に関する事項 |
| 調査I | 平成10年1月29日〜2月8日 |
| 調査II | 平成10年2月6日〜2月27日 |
| 調査I(住民調査) | 調査II(活動者調査) | |
|---|---|---|
| 標本選定方法 | 層化二段無作為抽出法 | 市区町村社会福祉協議会による選定 (調査Iと同地区) |
| 標本数 | 3,000人 | 2,799人 |
| 有効回収数(率) | 2,303人(76.8%) | 2,302人(82.2%) |
| 総 数 | 性 別 | 年齢階級別 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 不明 | 60〜 64歳 | 65〜 69歳 | 70〜 74歳 | 75〜 79歳 | 80歳 以上 | 不明 | |||
| 住 民 調 査 | 平成10年 | 2,303人 100.0% | 1,069人 46.4% | 1,234人 53.6% | - - | 704人 30.6% | 646人 28.1% | 505人 21.9% | 267人 11.6% | 181人 7.9% | - - |
| 平成5年 | 2,385人 100.0% | 1,097人 46.0% | 1,288人 54.0% | - - | 774人 32.5% | 679人 28.5% | 494人 20.7% | 298人 12.5% | 140人 5.9% | - - | |
| 昭和63年 | 2,451人 100.0% | 1,109人 45.2% | 1,342人 54.8% | - - | 832人 33.9% | 613人 25.0% | 509人 20.8% | 319人 13.0% | 178人 7.3% | - - | |
| 活 動 者 調 査 | 平成10年 | 2,302人 100.0% | 1,414人 61.4% | 888人 38.6% | - - | 359人 15.6% | 572人 24.8% | 702人 30.5% | 449人 19.5% | 216人 9.4% | 4人 0.2% |
| 平成5年 | 2,539人 100.0% | 1,649人 64.9% | 883人 34.8% | 7人 0.3% | 403人 15.9% | 673人 26.5% | 633人 24.9% | 512人 20.2% | 305人 12.0% | 13人 0.5% | |
| 昭和63年 | 2,312人 100.0% | 1,611人 69.7% | 679人 29.4% | 22人 1.0% | 424人 18.3% | 534人 23.1% | 602人 26.0% | 507人 21.9% | 238人 10.3% | 7人 0.3% | |
| 総 数 | 単身世帯 | 夫婦二人 世帯 | 本人と子 の世帯 | 本人と子と 孫の世帯 | その他 | 住 民 調 査 | 平成10年 | 2,303人 100.0% | 211人 9.2% | 750人 32.6% |
512人 22.2% | 631人 27.4% |
199人 8.6% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成5年 | 2,385人 100.0% |
201人 8.4% | 653人 27.4% |
508人 21.3% | 787人 33.0% |
236人 9.9% |
|
| 昭和63年 | 2,451人 100.0% | 238人 9.7% |
640人 26.1% | 495人 20.2% |
780人 31.8% | 298人 12.2% |
|
| 活 動 者 調 査 |
平成10年 | 2,302人 100.0% | 172人 7.5% |
936人 40.7% | 361人 15.7% |
644人 28.0% | 189人 8.2% |
| 平成5年 | 2,539人 100.0% | 170人 6.7% |
854人 33.6% | 370人 14.6% |
895人 35.3% | 247人 9.8% |
|
| 昭和63年 | 2,312人 100.0% | 110人 4.8% |
792人 34.3% | 265人 11.5% |
724人 31.3% | 421人 18.2% |
| 総数 | 非常に健康 である | まあまあ健 康である | 病気がちで ある |
|
|---|---|---|---|---|
| 平成10年 | 2,303人 100.0% | 625人 27.1% | 1297人 56.3% | 381人 16.5% |
| 平成5年 | 2,385人 100.0% | 591人 24.8% |
1,400人 58.7% | 394人 16.5% |
| 昭和63年 | 2,451人 100.0% | 626人 25.5% |
1,362人 55.6% | 463人 18.9% |
| 総 数 | 有 職 | 無 職 | 不 明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林漁業 | 商工サービ ス・自由業 | 常勤の被 傭者 | パート アルバイト | 不明 | |||||
| 住 民 調 査 |
平成10年 | 2,303人 100.0% | 227人 9.9% |
303人 13.2% | 175人 7.6% |
165人 7.1% | - - |
1,433人 62.2% | - - |
| 平成5年 | 2,385人 100.0% | 302人 12.% |
293人 12.3% | 183人 7.7% |
174人 7.3% | - - |
1,433人 60.1% | - - |
|
| 昭和63年 | 2,451人 100.0% | 240人 9.8% |
268人 10.9% | 147人 6.0% |
179人 7.3% | - - |
1,617人 66.0% | - - |
|
| 活 動 者 調 査 |
平成10年 | 2,302人 100.0% | 245人 10.6% |
224人 9.7% | 127人 5.5% |
55人 2.4% | 9人 0.4% |
1,544人 67.1% | 98人 4.3% |
| 平成5年 | 2,539人 100.0% | 340人 13.4% |
369人 14.5% | 181人 7.1% |
58人 2.3% | 17人 0.7% |
1,470人 57.9% | 104人 4.1% |
|
| 昭和63年 | 2,312人 100.0% | 211人 9.1% |
333人 14.4% | 101人 4.4% |
95人 4.1% | 13人 0.6% |
1,432人 61.9% | 46人 2.0% |
| 総 数 | 家計にゆ とりがあ り、まっ たく心配 なく暮ら している |
家計にあ まりゆと りはない が、それ ほど心配 なく暮ら している |
家計にゆ とりがな く、多少 心配であ る |
家計が苦 しく、非 常に心配 である |
その他 | わからな い |
不 明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住民調査 | 人 2,303 | % 20.4 |
% 59.1 | % 17.2 |
% 3.0 | % - |
% 0.5 | % - |
| 活動者調査 | 人 2,302 | % 24.0 |
% 64.5 | % 8.3 |
% 1.0 | % 0.0 |
% 0.3 | % 1.8 |
| 総 数 | 大都市 | 中都市 | 小都市 | 町村 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住 民 調 査 |
平成10年 | 2,303人 100.0% | 429人 18.6% |
745人 32.3% | 469人 20.4% |
660人 28.7% |
| 平成5年 | 2,385人 100.0% | 394人 16.5% |
773人 32.4% | 503人 21.1% |
715人 30.0% |
|
| 昭和63年 | 2,451人 100.0% | 421人 17.2% |
763人 31.1% | 513人 20.9% |
754人 30.8% |
|
| 活 動 者 調 査 |
平成10年 | 2,302人 100.0% | 416人 18.1% |
810人 35.2% | 481人 20.9% |
595人 25.8% |
| 平成5年 | 2,539人 100.0% | 419人 16.5% |
840人 33.1% | 560人 22.1% |
720人 28.4% |
|
| 昭和63年 | 2,312人 100.0% | 418人 18.1% |
746人 32.3% | 476人 20.6% |
672人 29.1% |
| 注) | 「大都市」:東京都区部と政令指定都市 「中都市」:人口10万人以上の市(大都市を除く) 「小都市」:人口10万人未満の市 (調査時における規模による) |
| 1 | 近所づきあいの程度は、「親しくつきあっている」が半数以上、その割合は低下傾向 | |
| 2 | 親しい友人・仲間を「沢山もっている」が3分の1、その割合は低下傾向 | |
| 3 | 仕事や家事以外での主な過ごしかたは、「テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの見聞き」が約8割 | |
| 4 | 自由時間、趣味活動などを活発に行うためには、「一緒にする仲間」、「経済的なゆとり」が必要 |
| 5 | この1年間に社会参加活動に参加した者は43.7%、「健康スポーツ」、「趣味」の順 |
| 6 | 最も力を入れた活動は、「趣味」、「健康・スポーツ」の順 |
| 7 | 最も力を入れた活動の参加頻度は「週に2回以上」(活動者調査では「週に2,3回程度」)が最も高い |
| 8 | 最も力を入れた活動に初めて参加した時期は、「退職(隠居)してから」が最も高い |
| 9 | 最も力を入れた活動に参加したきっかけは、「友人、仲間のすすめ」が最も高い |
| 10 | 活動全体を通じて参加して良かったことは、「新しい友人を得ることができた」が約6割 |
| 11 | 活動に参加しなかった理由では、「健康・体力に自信がないから(年をとっているから)」「家庭の事情(病人、家事、仕事)があるから」がそれぞれ3割 |
| 12 | 地域活動への参加意向がある者は、半数近く |
| 13 | 今後参加したい活動・高齢者に今後参加してほしい活動は、「健康・スポーツ」が最も高く、「福祉・保健」が大きく上昇 |
| 14 | 活動に参加したい理由は、「生活に充実感をもちたいから」が最も高い |
| 15 | 退職者の地域とのかかわり方について、「退職すると地域生活の場となるのだから、積極的に地域活動に目を向けさせる手だてが必要だ」と答えた者の割合は、活動者調査の方が大幅に高い |
| 16 | 地域活動を進めていく上での環境について、「活動資金の確保」、「リーダー(指導者)の確保」、「活動者の研修・人材の養成」が不十分と答えた者は半数以上 |
| 17 | 地域活動への参加を推進する上で、「家庭の理解」、「町内会・老人クラブ等の活動団体自身の活発化」、「高齢者自身の参加意欲の高揚」の役割が「大きい」と答えた者はそれぞれ5割 |
| 18 | 実際に地域奉仕活動をするために最も必要な条件は、「一緒に活動する仲間がいること」が約4割 |
| 19 | 地域奉仕活動を盛んにするために必要な社会的整備は、「地域奉仕活動の必要性を多くの人に知らせること」が最も高い |
| 20 | 地域奉仕活動運営のための最も望ましい活動資金の確保は、「国、県、市区町村からの補助金」が最も高い |
| 21 | 地域奉仕活動の報酬に対する考え方「地域奉仕活動とはいえ、交通費などの実費ぐらいは受けてもよい」が最も高く、活動者調査の方が10.8ポイント高い |
| 22 | 高齢者による地域奉仕活動への国や地方公共団体のかかわり方は、直接、協力・援助を望んでいる者は、住民調査では約7割、活動者調査では8割以上 |
| 23 | 高齢者が地域奉仕活動に参加する上での国や地方公共団体に対する要望は、住民調査では「施設を利用しやすくする」、活動者調査では「指導者の養成、活動者の確保の機会を充実する」が最も高い |
| 24 | ボランテイア時間貯蓄制度注)を知っている者の割合は約5割(活動者調査では8割) |
| 25 | ボランティア時間貯蓄制度を推進すべきであると答えた者が約7割 |
| 26 | 地域のための奉仕活動を含めたボランティア活動者への社会的評価について、行ってもよいまたは行うことが望ましいと答えた者は、住民調査では約6割、活動者調査では約7割27社会的評価を行う形としては、「感謝状の授与など、社会的に賞賛する」が住民調査では約7割、活動者調査では約8割 |
| 28 | 社会的評価を行うべきではないと思う理由は、「ボランテイア活動は、自分自身が充実感や満足感を得られればそれでよく、他人や社会からの評価を求めるものではないから」が最も高い |
| 29 | 若い世代との交流の機会のある者は約5割(活動者調査は約8割)、その割合は低下傾向 |
| 30 | 交流の相手は、「壮年の世代」が約7割 |
| 31 | 若い世代との交流への参加意向がある者は、約5割(活動者調査では約9割) |
| 32 | 参加したい若い世代との交流の内容は、「若い世代と一緒に楽しめる活動」が約7割 |
| 33 | 若い世代との交流に参加したくない理由としては、「若い世代とは話が合わないと思うから」が約4割 |
| 34 | 世代間交流促進のための必要条件としては、「交流機会の設定」(活動者では「世代間交流の世話役的リーダーの存在」)が最も高い |
| 35 | 生きがい(喜びや楽しみ)を感じている者は8割(活動者は9割)以上 |
| 36 | 生きがい(喜びや楽しみ)を感じる時としては、「孫など家族との団らんの時」(活動者調査は「社会奉仕や地域活動をしている時」)が最も高い |