本調査は、高齢者の基本的な生活の状況、経済生活に関する状況を把握し、今後の高齢社会対策の施策の推進に資する基礎資料とすることを目的とする。
第1章 調査の目的及び方法等
1.調査の目的
2.調査の仕様
(1)調査地域
全国
(2)調査対象者
60歳以上(令和6年10月1日現在)の男女
(3)標本数
男女合わせて4,000人
(4)調査事項
- ア 調査客体の基本属性に関する事項(F1~F7)
- イ 生きがい、健康状態、社会的活動に関する事項(問1~問6)
- ウ 仕事に関する事項(問7~問16)
- エ 経済的な暮らし向きに関する事項(問17~問28)
- オ 貯蓄、老後の備え等に関する事項(問29~問37)
(5)調査方法
郵送調査法(オンライン回答併用)
(6)調査期間
令和6年10月1日~11月8日
(7)サンプリング方法
層化二段無作為抽出法を用いた。具体的には以下の手順。
①層化
第1次抽出単位となる調査地点として、令和2年度国勢調査時に設定された調査区を使用した。 なお、都市規模における市区町村は令和6年1月1日現在の住民基本台帳データによる。
〔地域区分〕
| 北海道(1道) | 北海道 |
|---|---|
| 東北(6県) | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東(1都6県) | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
| 北陸(4県) | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |
| 東山(3県) | 山梨県、長野県、岐阜県 |
| 東海(3県) | 静岡県、愛知県、三重県 |
| 近畿(2府4県) | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国(5県) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国(4県) | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州(8県) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
〔都市規模区分〕
- 大都市(東京都23区・政令指定都市)
- 中都市(人口10万人以上の市)
- 小都市(人口10万人未満の市)
- 町村
※人口による都市規模の分類は、令和5年1月1日現在の住民基本台帳データに基づく人口による。
②抽出
各層(地域10区分×都市規模4区分)について、それぞれの層における母集団(令和5年1月1日現在の住民基本台帳データの60歳以上人口に基づく)の大きさにより200 地点を比例配分し、1地点につき20サンプルずつとすることにより、設定標本数4,000を配分する。
抽出された地点(大字・町丁目)ごとに、満60歳以上の男女個人を、対象年齢に該当する人だけを数えて、一定の抽出間隔で20サンプルを抽出する。
(8)有効回収数
ア. 標本数、有効回収数、有効回収率
| 標本数 | 4,000人 | |
|---|---|---|
| 有効回収数 | 2,188人 | ※郵送:1,897、Web:291 |
| 有効回収率 | 54.7% | ※郵送:47.4%、Web:7.3% |
(注):回答期限の11月8日までの回収数:2,224サンプル
うち、36サンプルは下記理由により無効票とした。
- 無回答が5割以上:10サンプル
- 抽出名簿との性別不一致:18サンプル
- 抽出名簿との年齢差±3歳以上:16サンプル* *9サンプルは性別不一致の票と重複
- 郵送とオンライン回答の重複:1サンプル(郵送回答を無効票とした)
イ. 性・年齢階級別の標本数、有効回収数、有効回収率(CSV形式:1KB)
| 標本数 | 有効回収数 | 有効回収率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 60~64歳 | 384人 | 208人 | 54.2% |
| 65~69歳 | 374人 | 220人 | 58.8% | |
| 70~74歳 | 379人 | 226人 | 59.6% | |
| 75~79歳 | 345人 | 211人 | 61.2% | |
| 80~84歳 | 217人 | 134人 | 61.8% | |
| 85~89歳 | 109人 | 65人 | 59.6% | |
| 90~94歳 | 44人 | 25人 | 56.8% | |
| 95歳以上 | 9人 | 3人 | 33.3% | |
| 計 | 1,861人 | 1,092人 | 58.7% | |
| 女性 | 60~64歳 | 319人 | 178人 | 55.8% |
| 65~69歳 | 367人 | 212人 | 57.8% | |
| 70~74歳 | 422人 | 223人 | 52.8% | |
| 75~79歳 | 419人 | 216人 | 51.6% | |
| 80~84歳 | 301人 | 140人 | 46.5% | |
| 85~89歳 | 162人 | 72人 | 44.4% | |
| 90~94歳 | 120人 | 46人 | 38.3% | |
| 95歳以上 | 29人 | 8人 | 27.6% | |
| 計 | 2,139人 | 1,095人 | 51.2% | |
| その他 | 計 | - | 1人 | - |
| 全体 | 4,000人 | 2,188人 | 54.7% | |
(9)調査委託機関
一般社団法人新情報センター
(10)企画分析委員会
「高齢者の経済生活に関する調査企画分析委員会」を設置し、下記の検討項目について3回の会議を開催。
| 開催回 | 開催日時 | 主な議題 |
|---|---|---|
| 第1回 | 令和6年6月17日(月) 10:00~12:00 |
・調査票の検討 |
| 第2回 | 令和6年12月9日(月) 10:00~12:00 |
・集計結果の報告 ・報告書作成方針の検討 ・分析委員の執筆方針の検討 |
| 第3回 | 令和7年2月12日(水) 10:00~12:00 |
・報告書案の報告・検討 |
本調査は、内閣府政策統括官(共生・共助担当)の委託により一般社団法人新情報センターが 学識経験者の協力を得て実施した。
企画分析委員は以下のとおりである。
| 今城 志保 | 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 組織行動研究所 主幹研究員 |
| 駒村 康平 | 慶応義塾大学 経済学部 教授 |
| 藤森 克彦 | 日本福祉大学 福祉経営学部長 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 社会保障・藤森クラスター 主席研究員 |
| 丸山 桂 | 上智大学 総合人間学部社会福祉学科 教授 |
(50音順、敬称略)
(11)本報告書を読む際の留意点
- 本文及び図表において調査票の質問文や選択肢を引用する場合、これらを簡略化して表記することがある。
- 回答率(各回答の百分比)は、小数点以下第2位を四捨五入したため、回答率の合計が100.0%にならないことがある。また、同様に、個別の選択肢を合計して小計を出している場合も、各選択肢の回答率の合計が小計と一致しないことがある。
- 本文、図表、集計結果表で用いた記号等の意味は、次のとおりである。
・n:その質問に対する回答者数であり、回答率の合計100.0%が何人に相当するかを示す比率算出の基数である。
・複数回答:1回答者が2つ以上の回答をすることができる質問。複数回答質問における比率は、回答数の合計を回答者数(n)で割った比率であり、通常その値の合計は100.0%を超える。
・択一回答:1回答者が1つのみ回答することができる質問。択一回答質問における比率は、原則100.0%である。
・0.0 :回答者はいるが、その比率が表章単位に満たない値である。
・- :回答者がいないことを示す。
・クロス集計(表)で、分析軸(表側軸)の該当者が50人未満の場合は*(アスタリスク)で示し、原則、本文の分析の対象にしていない。 - 標本誤差は回答者数(n)と得られた結果の比率によって異なるが、単純任意抽出法(無作為抽出)を仮定した場合の誤差(95%は信頼できる誤差の範囲)は下表の通りである。
(CSV形式:1KB)
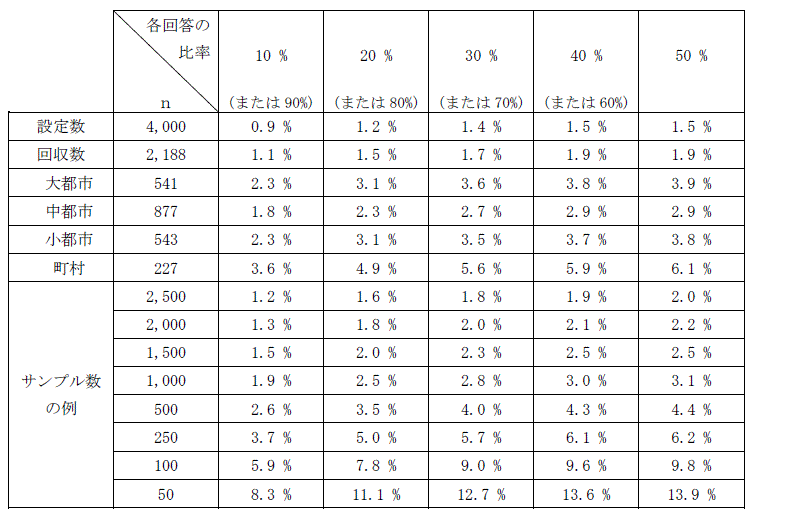
※表の見方
全体(母集団)の中から一部を抽出して行う標本調査では、全体を対象に行った調査(全数調査)と比べ、標本抽出にともなう誤差が発生し、その誤差のことを「標本誤差」という。
「標本誤差」は、調査結果を見る際に、どの程度確かな数字であるかを判断するための情報である。
前掲の表で言えば、回答者数が 1,000 人で、ある質問中の選択肢の回答比率が 50.0%だった場合、標本誤差は最大でも±3.1%なので、「95%の確率で、46.9%~53.1%の範囲である」とみることができる。なお、層化二段抽出法による場合は標本誤差が若干増減することもある。また、誤差には回答者の誤解などによる計算不能な非標本誤差も存在する。
3.調査対象者の基本属性
(1)性別(F1)
F1 性別をお答えください。(○は1つだけ)
図表1-3-1 性別(F1)(択一回答)(CSV形式:1KB)
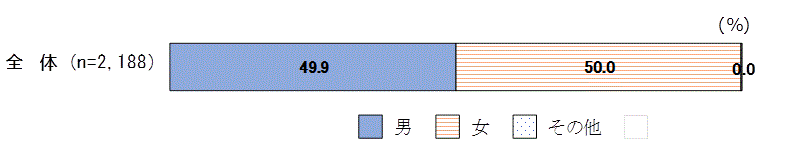
(2)年齢(F2)
F2 満年齢でおいくつですか。
図表1-3-2 年齢(F2)(択一回答)(CSV形式:1KB)
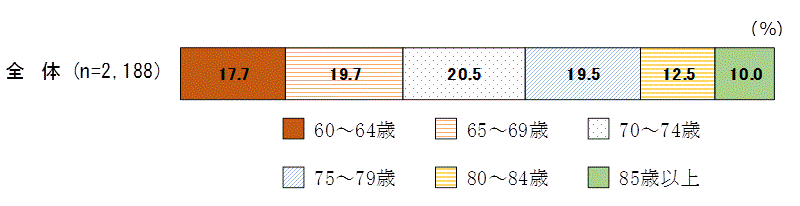
(3)現在の結婚状況(F3)
F3 現在、結婚していますか。事実婚も含めて次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つだけ)
事実婚を含む現在の結婚の状況をみると、全体で「現在、配偶者あるいはパートナーがいる」(66.1%)が最も高い。次いで、「配偶者あるいはパートナーとは死別している」(17.0%)、「配偶者あるいはパートナーがいたことがない」「配偶者あるいはパートナーとは離別している」(ともに6.9%)が続く。
図表1-3-3 現在の結婚の状況(事実婚含む)(F3)(択一回答)(CSV形式:1KB)
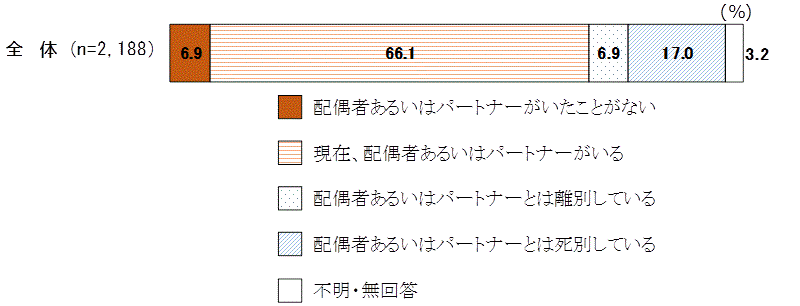
(4)同居者(F4)
F4 現在、どなたと一緒に暮らしていますか。養子の方も含めて次の中からあてはまるものを全てお答えください。また、同居者がいる方は、あなたを除く同居者の人数もあわせて、お答えください。(○はいくつでも)
同居者をみると、全体で「配偶者あるいはパートナー」(55.4%)が最も高い。次いで、「子(子の配偶者あるいはパートナーを含む)」(30.8%)、「同居者はいない(ひとり暮らし)」(16.7%)、「親(配偶者あるいはパートナーの親を含む)」(5.1%)、「その他(親族以外も含む)」(3.4%)が続く。
図表1-3-4-1 同居者(F4)(択一回答)(CSV形式:1KB)
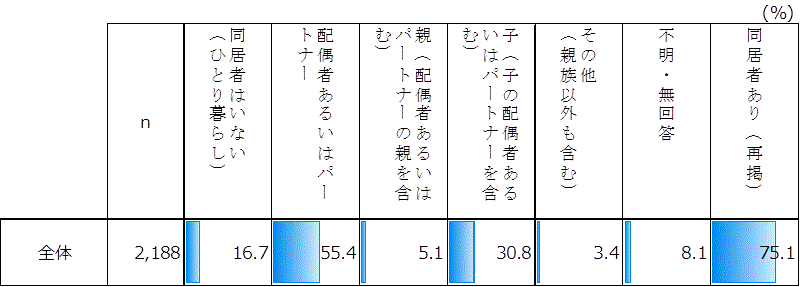
同居している人数をみると、全体で「1人」(43.6%)が最も高い。次いで、「0人(ひとり暮らし)」(16.7%)、「2人」(15.8%)、「3人」(6.4%)が続く。
図表1-3-4-2 同居者している人の人数(F4)(CSV形式:1KB)
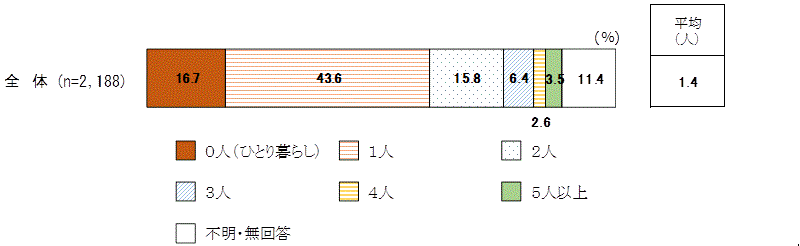
(5)現在のお住まい(F5)
F5 あなたのお住まいは、次の中ではどれにあたりますか。また、持家にお住まいの方は、住宅ローンの返済額(※)について、賃貸住宅にお住まいの方は家賃について、それぞれ1カ月あたりの金額も合わせてお答えください。(○は1つだけ)
※住宅ローンの返済がない方は0万円と記入してください。
現在のお住まいをみると、全体で「持家(一戸建て)」(78.2%)が最も高い。「持家(一戸建て)」(78.2%)と「持家(分譲マンション等の集合住宅)」(3.5%)を合わせると、81.7%が持家と回答している。
図表1-3-5-1 現在のお住まい(F5)(択一回答)(CSV形式:1KB)
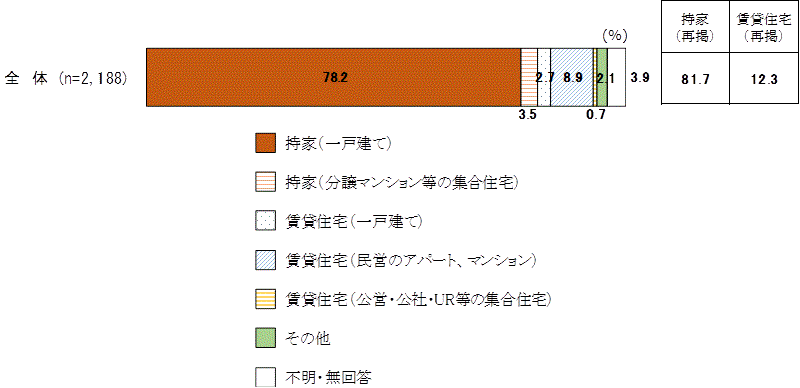
※ 「持家(再掲)」は「持家(一戸建て」と「持家(分譲マンション等の集合住宅)」の合計、
「賃貸住宅(再掲)」は「賃貸住宅(一戸建て)」と「賃貸住宅(民営のアパート、マンション)」と「賃貸住宅(公営・公社・UR等の集合住宅)」の合計。
図表1-3-5-2 1ヵ月のローン返済額(F5)(CSV形式:1KB)
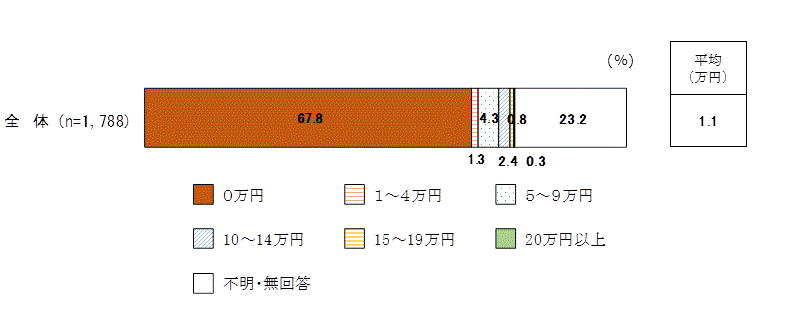
図表1-3-5-3 1ヵ月の家賃(F5)(CSV形式:1KB)
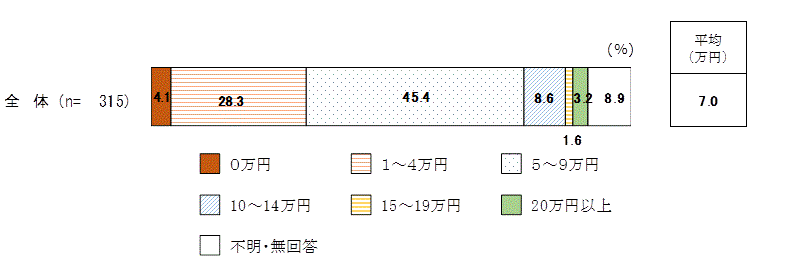
(6)ネットショッピングの利用について(F6)
F6 ネットショッピング等(※)をどの程度利用していますか。次の中から1つだけお答えください。(〇は1つだけ)
※WEBサイト上でのお買い物やネットオークションなど、インターネット上で行われる物やサービスの取引のこと。
ネットショッピングの利用をみると、全体で「全く利用していない」(43.5%)が最も高い。「週に1回以上」(4.1%)、「月に1回以上」(14.0%)、「年に数回」(17.9%)を合わせると、36.1%が利用していると回答している。
図表1-3-6 ネットショッピングの利用(F6)(択一回答)(CSV形式:1KB)
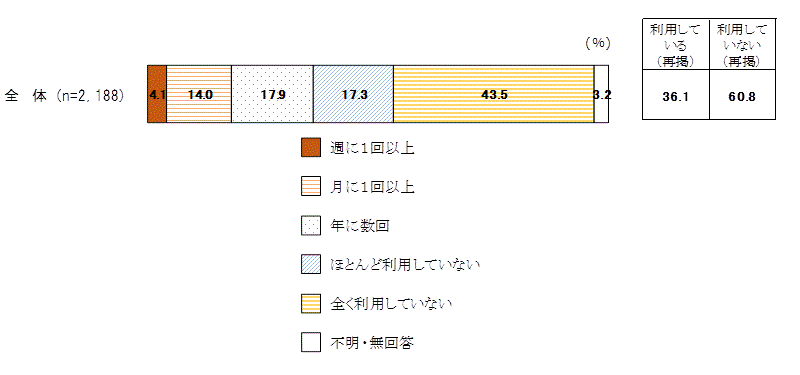
※ 「利用している(再掲)」は「週に1回以上」と「月に1回以上」と「年に数回」の合計、
「利用していない(再掲)」は「ほとんど利用していない」と「全く利用していない」の合計。
(7)キャッシュレス決済の利用について(F7)
F7 次のようなキャッシュレス決済の手段について、どの程度利用していますか。次の(イ)~(ニ)について、あてはまるものをそれぞれお答えください。(○は1つずつ)
キャッシュレス決済の利用を、“クレジットカード”“バーコード、QRコード決済”“電子マネー”“その他”の4項目について聞いた。
「よく使う」と「たまに使う」を合わせた「使う(再掲)」は、“クレジットカード”(49.2%)が最も高く、“電子マネー”(30.0%)、“バーコード、QRコード決済”(22.9%)と続く。
「ほとんど使わない」と「使わない」を合わせた「使わない(再掲)」は、“バーコード、QRコード決済”(60.6%)が最も高い。
図表1-3-7 キャッシュレス決済の利用(F7)(それぞれ択一回答)(CSV形式:1KB)
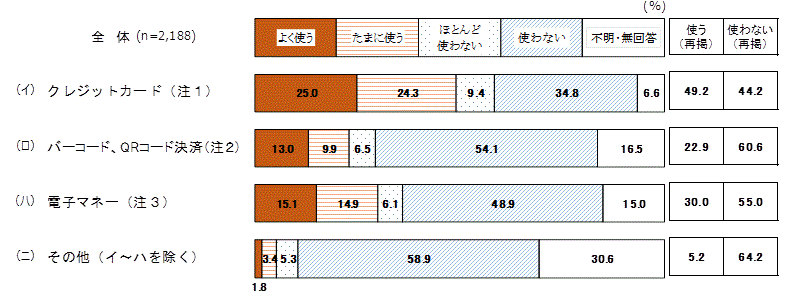
(注1)デビットカードを含む
(注2)PayPay、LINE Pay等
(注3)Suica、ICOCA、WAON、nanaco、楽天Edy等
※ 「使う(再掲)」は「よく使う」と「たまに使う」の合計、
「使わない(再掲)」は「ほとんど使わない」と「使わない」の合計。

