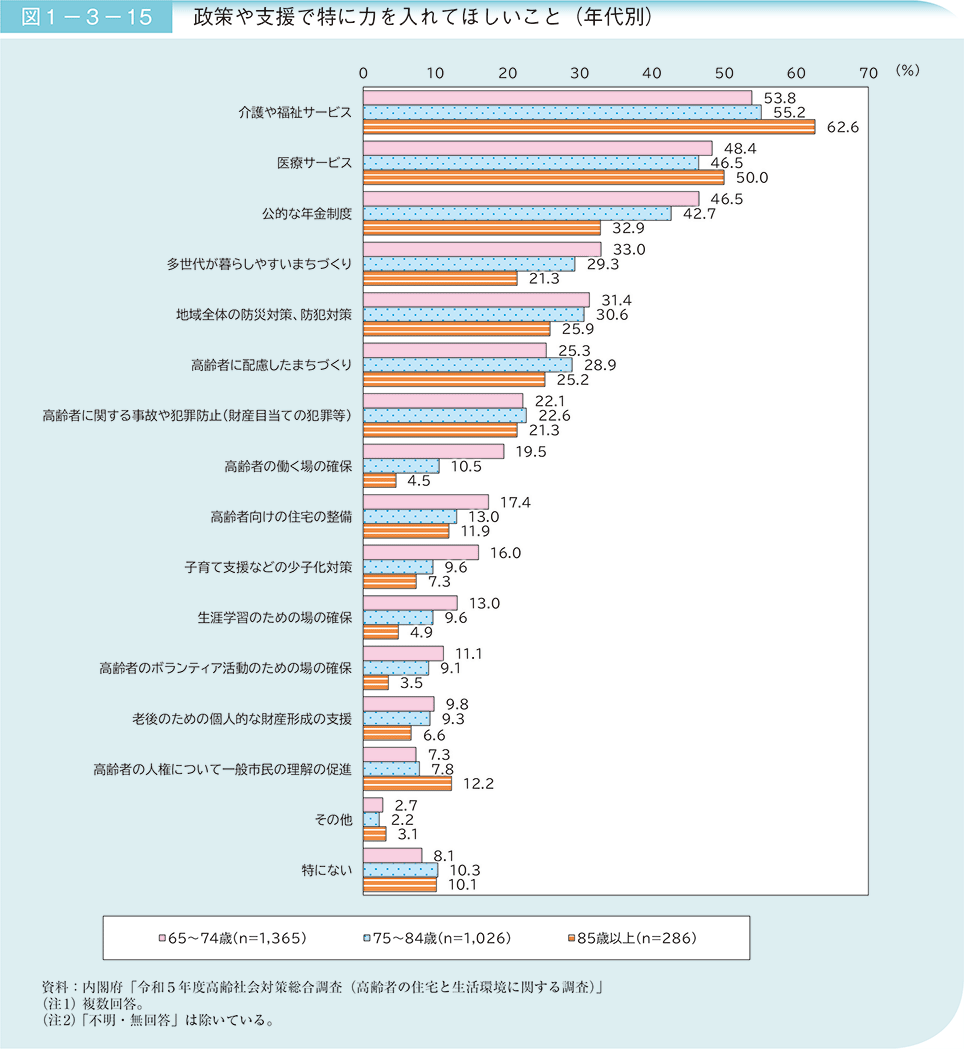第1章 高齢化の状況(第3節 1)
第3節 〈特集〉高齢者の住宅と生活環境をめぐる動向について(1)
我が国の高齢化率は29.1%(令和5年10月1日現在)となっており、今後更に上昇する見込みとなっている中で、安心して高齢期の生活を送るためには、生活の基盤となる住まいの確保や、良好な生活環境の整備が重要である。
一方で、今後、単身高齢者の増加が見込まれるなど、住まいの確保に困難を抱える高齢者の増加も懸念されている。また、コロナ禍も踏まえたライフスタイルの変化や、地方における過疎化の進行、自然災害の激甚化・頻発化等、高齢期の暮らしを取り巻く環境は大きく変化している。
そこで、本節においては、内閣府が令和5年度に実施した以下2調査を基に、高齢者の住宅と生活環境に関する状況や意識、高齢期における住み替えに関する意識について分析を行い、今後求められる施策の方向性を含め、必要な対応について考察を行った。
「令和5年度高齢社会対策総合調査(高齢者の住宅と生活環境に関する調査)」(以下本節において「総合調査」という。)
- 調査地域:全国
- 調査対象者:65歳以上の男女
- 調査方法:郵送調査法(オンライン調査併用)
- 調査時期:令和5年10月26日~11月30日
- サンプリング方法:層化二段無作為抽出法
- 有効回答数:2,677人(うちオンライン:198人)(標本数:男女合わせて4,000人)
- 有効回収率:66.9%
<今回調査> 平均値:75.2歳 中央値:74.0歳
<前回調査1> 平均値:74.2歳 中央値:73.0歳
「高齢社会に関する意識調査」(以下本節において「意識調査」という。)
- 調査地域:全国
- 調査対象者:60~99歳の男女
- 調査方法:オンライン調査
- 調査時期:令和6年2月27日~令和6年3月5日
- サンプリング方法:居住地・性・年代の構成を人口構成比に合わせた形で抽出
- 回収数2:3,329人(目標回収数:男女合わせて3,000人)
1 高齢期の住宅・生活環境をめぐる状況や意識について
(1) 住宅・地域の満足度と幸福感の程度について
現在居住している住宅と地域のいずれについても満足度が高くなるほど、幸福感を「十分感じている」、「多少感じている」と回答した割合が高くなっており、住宅又は地域について「十分満足している」と回答した人では9割を超えている(図1-3-1)。
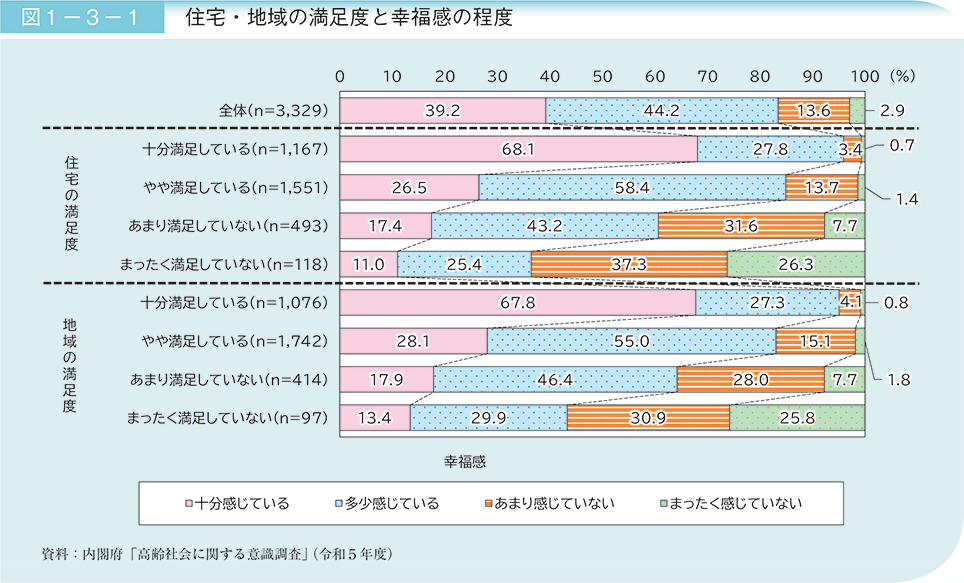
(2) 高齢期の住宅に関する状況や意識について
ア 現在の住宅の問題点
全体でみると、「住まいが古くなり、いたんでいる」、「地震、風水害、火災などの防災面や防犯面で不安がある」等と回答した割合が高い(図1-3-2)。
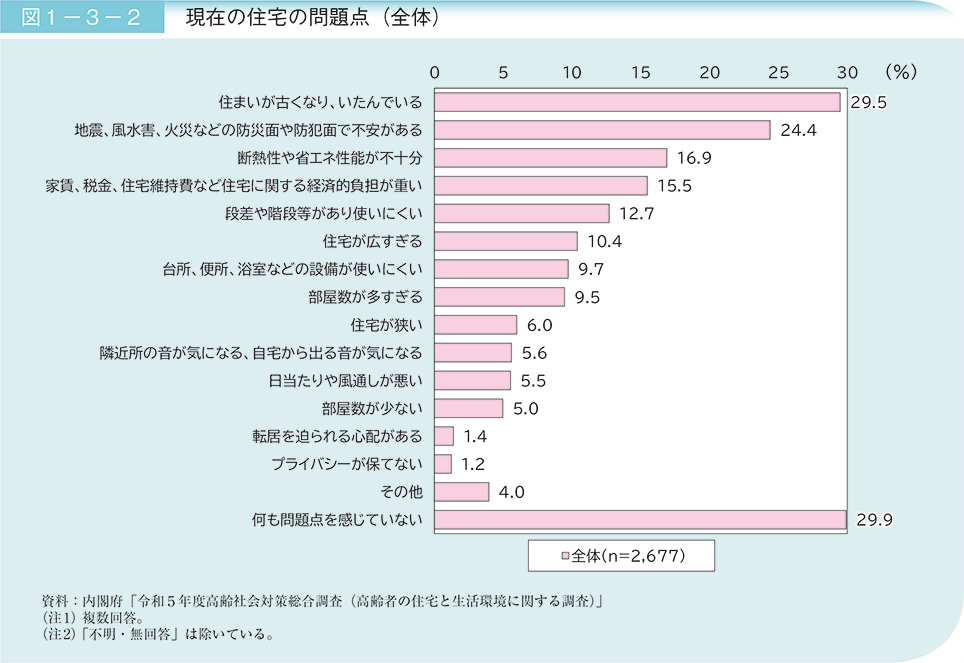
持家/賃貸住宅の別でみると、持家に居住している人は「住宅が広すぎる」、「部屋数が多すぎる」等と回答した割合が、賃貸住宅に居住している人を大きく上回っている。また、賃貸住宅に居住している人は、「家賃、税金、住宅維持費など住宅に関する経済的負担が重い」のほか、「台所、便所、浴室などの設備が使いにくい」、「住宅が狭い」等と回答した割合が、持家に居住している人を大きく上回っている。
なお、持家に居住している人は、「何も問題点を感じていない」と回答した割合が、賃貸住宅に居住している人に比べて9ポイント程度高くなっている(図1-3-3)。
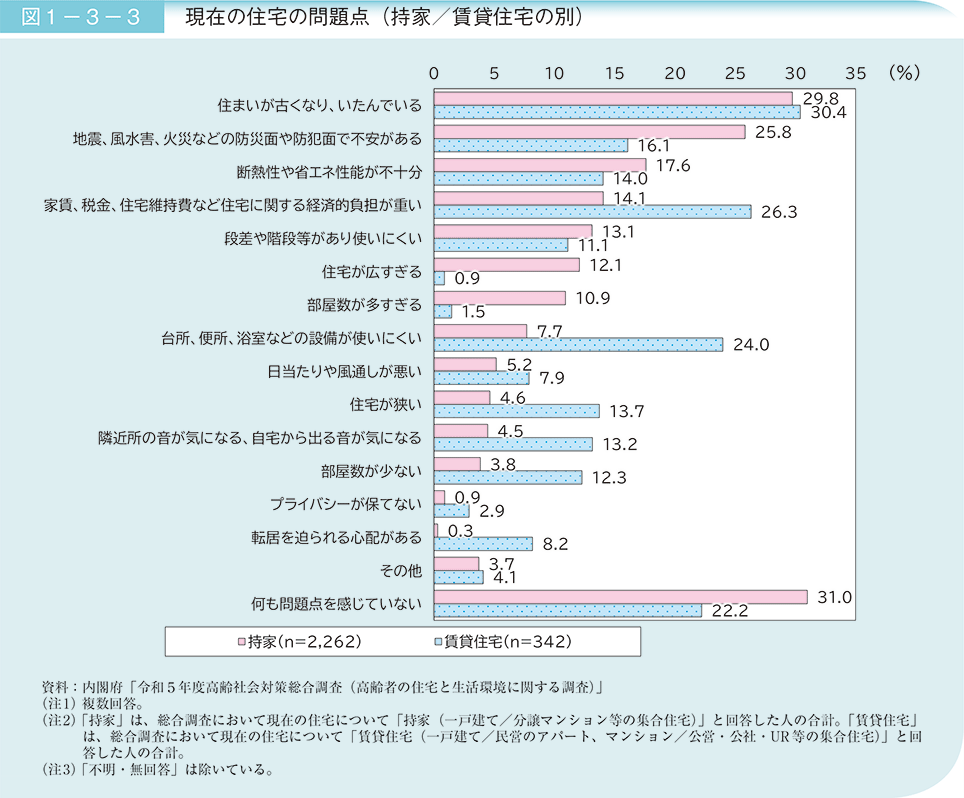
イ 災害への備え
前回調査と比較すると、「特に何もしていない」と回答した割合が低下している一方、「近くの学校や公園など、避難する場所を決めている」、「自分が住む地域に関する地震や火災、風水害などに対する危険性についての情報を入手している」と回答した割合が上昇し、上位となっている(図1-3-4)。
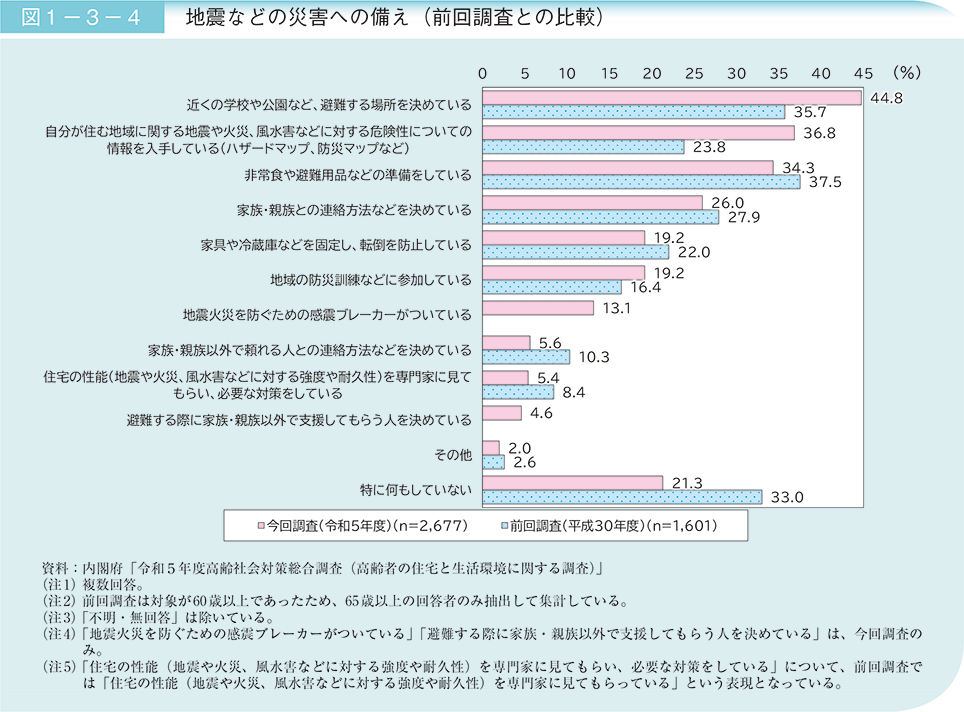
また、家族形態別にみると、ひとり暮らしの人はそれ以外の人と比べて、ほとんどの項目で対策をとっている割合が低く、「特に何もしていない」と回答した割合が高い(図1-3-5)。
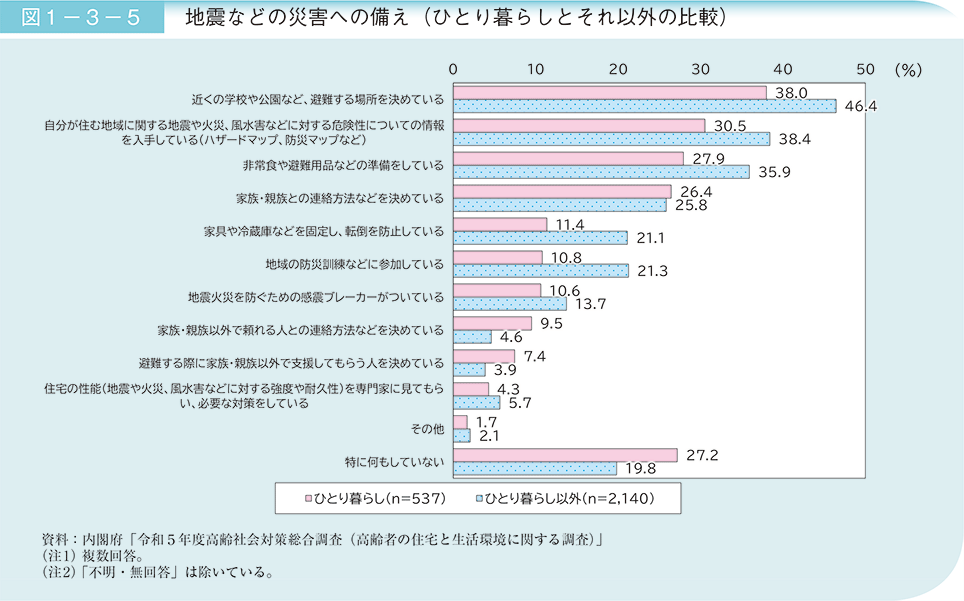
(3) 高齢期の生活環境に関する状況や意識
ア 現在居住している地域における不便や気になること
現在居住している地域における不便や気になることを感じている人についてみると、「日常の買い物に不便」、「医院や病院への通院に不便」、「交通機関が高齢者には使いにくい、または整備されていない」と回答した割合が高い(図1-3-6)。
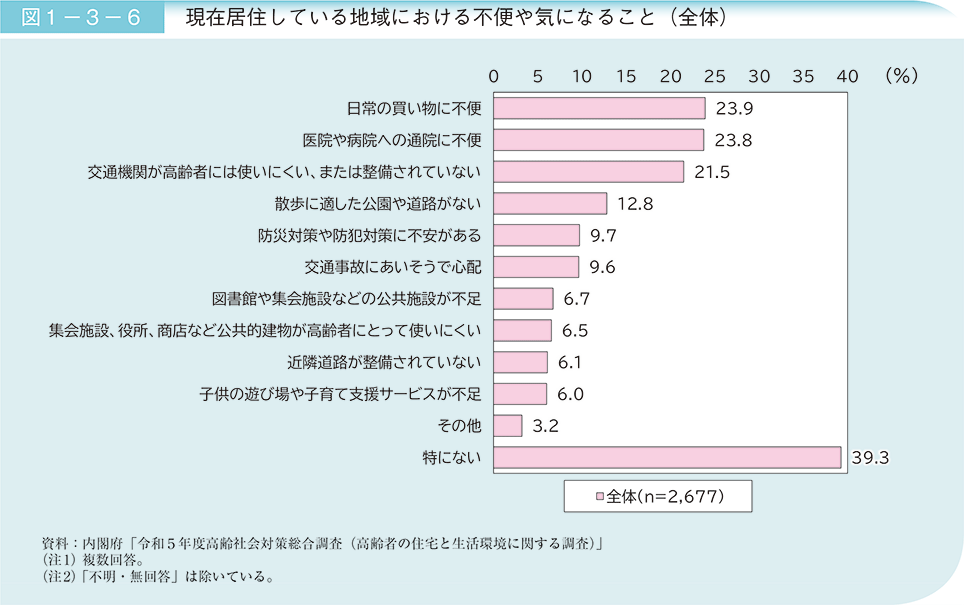
イ 子との同居・近居に関する意向
前回調査と比較すると、同居の意向を持つ割合が低下している一方、近居の意向を持つ割合が上昇している(図1-3-7)。
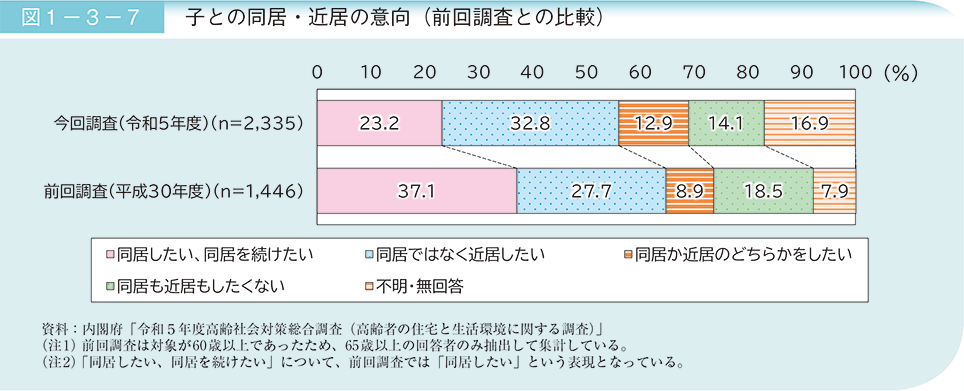
年代別にみると、年代が高くなるほど同居の意向を持つ割合が高く、近居の意向を持つ割合が低い(図1-3-8)。
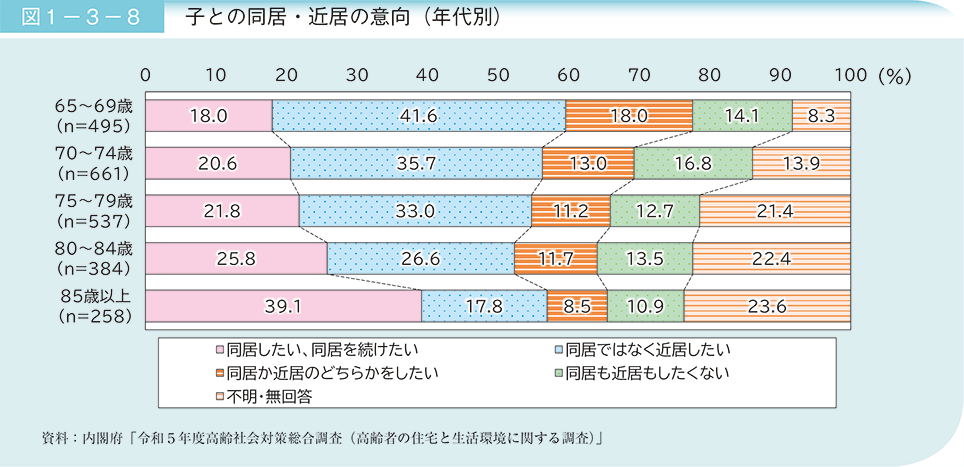
ウ 親しくしている友人・仲間がいるか、人と話をする頻度
親しくしている友人・仲間がいるかについて、前回調査と比較すると、「たくさんいる」又は「普通にいる」と回答した割合が大きく低下している(図1-3-9)。
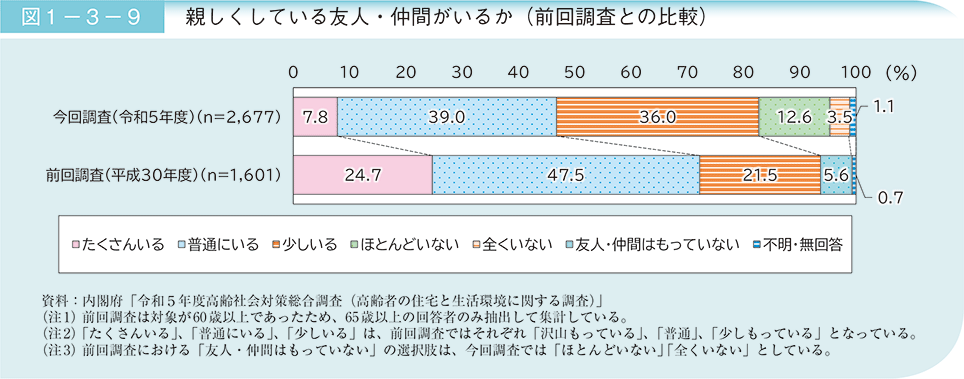
人と話をする頻度についても、前回調査と比較すると、「毎日」と回答した割合が大きく低下している(図1-3-10)。また、ひとり暮らしの人についてみると、「毎日」と回答した割合が、ひとり暮らし以外の人の半分以下となっている。(図1-3-11)。
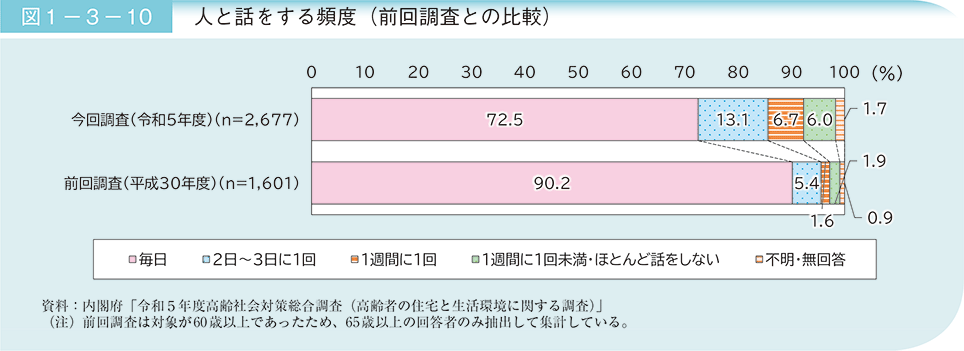
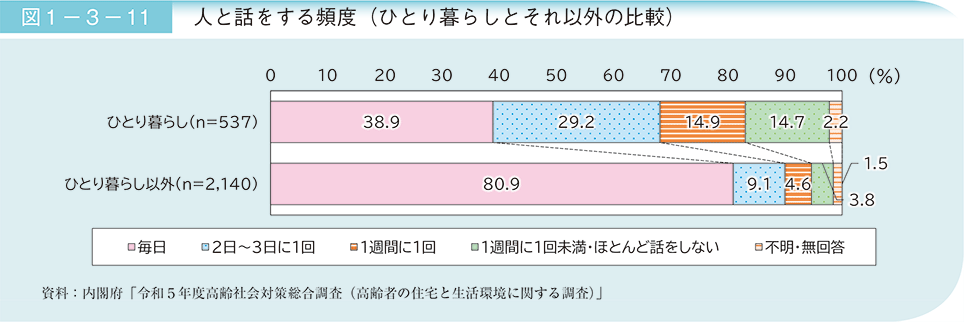
エ 地域に住み続けるために必要なこと・近所の人との付き合い方
前回調査と比較すると、「近所の人との支え合い」や「家族や親族の援助」と回答した割合は低下しているが、「近所の人との支え合い」については依然として半数以上の人が必要と考えている(図1-3-12)。
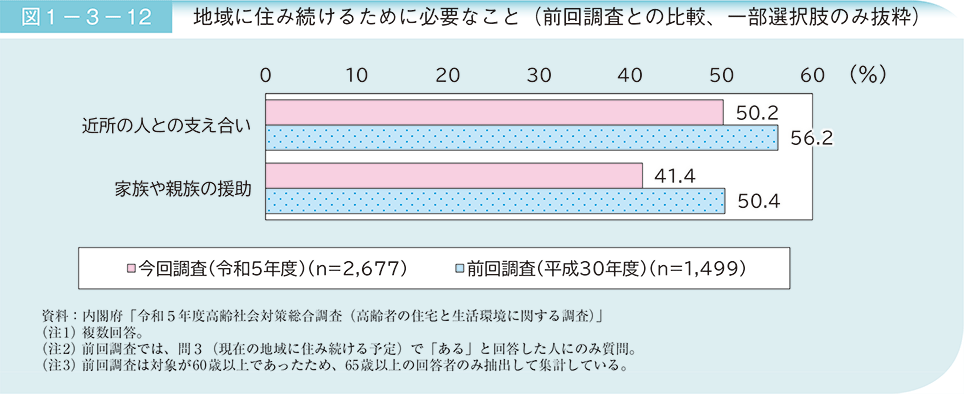
一方、「近所の人との支え合い」と回答した人について、どのような近所付き合いをしているかをみると、「会えば挨拶をする」、「外でちょっと立ち話をする」、「物をあげたりもらったりする」といった、比較的表面的な付き合いが多く、「病気の時に助け合う」、「家事やちょっとした用事をしたり、してもらったりする」といった、より深い付き合いは1割前後にとどまっている(図1-3-13)。
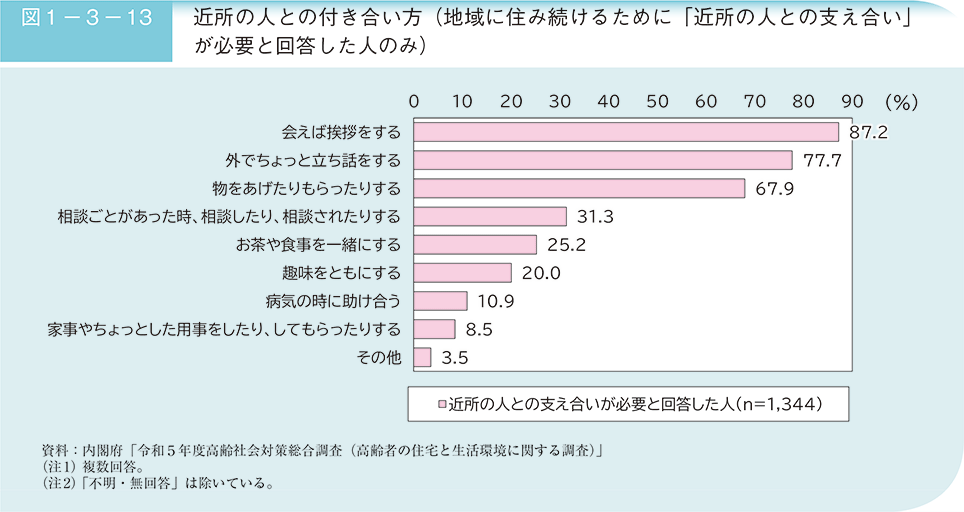
(4) 住まいや地域の環境について重視すること
全体でみると、「医療や介護サービスなどが受けやすいこと」と回答した割合が最も高く、次いで、「駅や商店街が近く、移動や買い物が便利にできること」が高い。
また、性別でみると、女性は「医療や介護サービスなどが受けやすいこと」や「手すりが取り付けてある、床の段差が取り除かれているなど、高齢者向けに設計されていること」、「親しい友人や知人が近くに住んでいること」等と回答した割合が男性を上回っている(図1-3-14)。
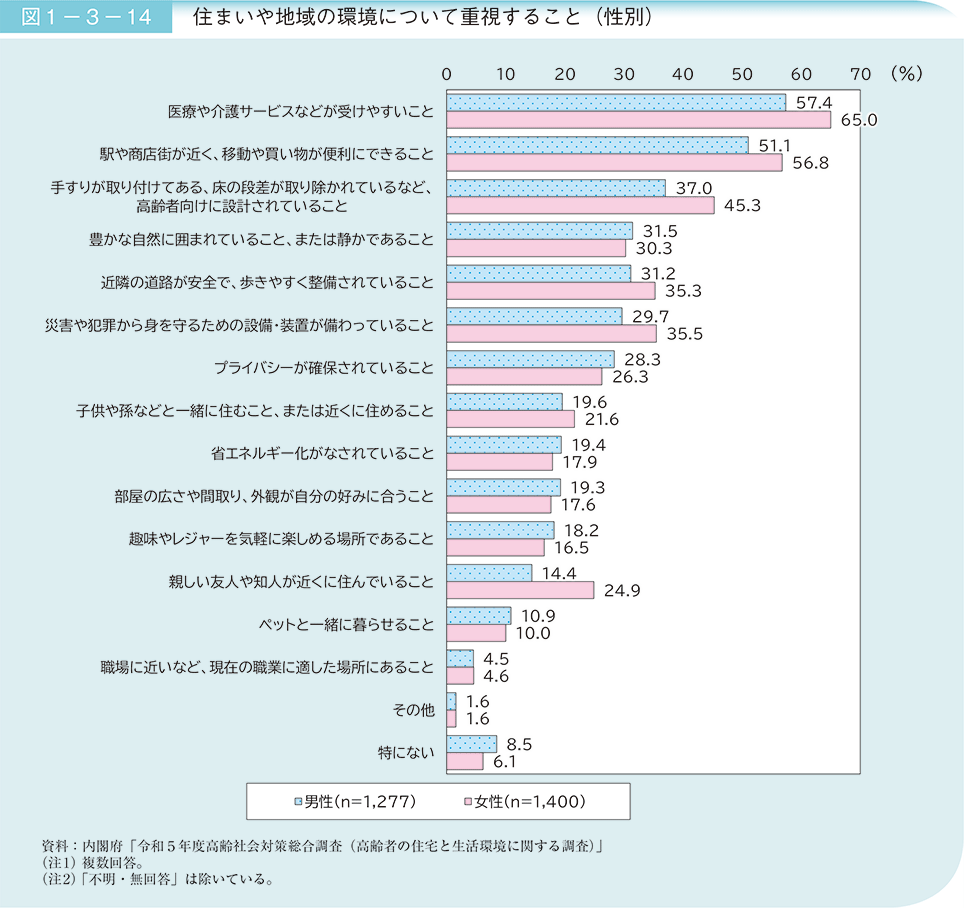
(5) 政策や支援で特に力を入れてほしいこと
全体でみると、「介護や福祉サービス」、「医療サービス」、「公的な年金制度」、「多世代が暮らしやすいまちづくり」、「地域全体の防災対策、防犯対策」と回答した割合が高い。
年代別でみると、年代が高くなるほど、「介護や福祉サービス」と回答した割合が高く、年代が低くなるほど、「公的な年金制度」、「多世代が暮らしやすいまちづくり」、「高齢者の働く場の確保」と回答した割合が高い(図1-3-15)。