第1章 高齢化の状況(第3節)
第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について
我が国の平均寿命は世界で最も高い水準にあり、長い人生をより豊かに過ごすことができる社会を実現していくことが重要である。高齢期に差し掛かると、多くの人が仕事や収入、心身の機能、人間関係等、様々な面で変化を経験する。また、我が国全体をみても、近年の経済・社会情勢は大きな変動の渦中にある。そのような中、特に経済的な観点から、高齢期も安定して豊かに暮らすことができる社会の実現に資するため、内閣府が令和6年度に実施した「高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)」を基に、高齢者の経済生活に関する状況や意識について分析を行った。
【令和6年度高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)調査概要】
○調査地域:全国
○調査対象者:60歳以上(令和6年10月1日現在)の男女
○調査時期:令和6年10月1日~11月8日
○有効回答数:2,188人
○収入を伴う仕事をしている割合は増加
全体で見ると、「現在、定期的に収入を伴う仕事をしている」又は「現在、不定期ではあるが、収入を伴う仕事をしている」と回答した割合(仕事をしている割合)は4割を超えており、前回調査(令和元年)時と比較して上昇している。なお、65 歳以上について見ると、定期・不定期合わせて「仕事をしている」と回答した割合は35.6%となっている。
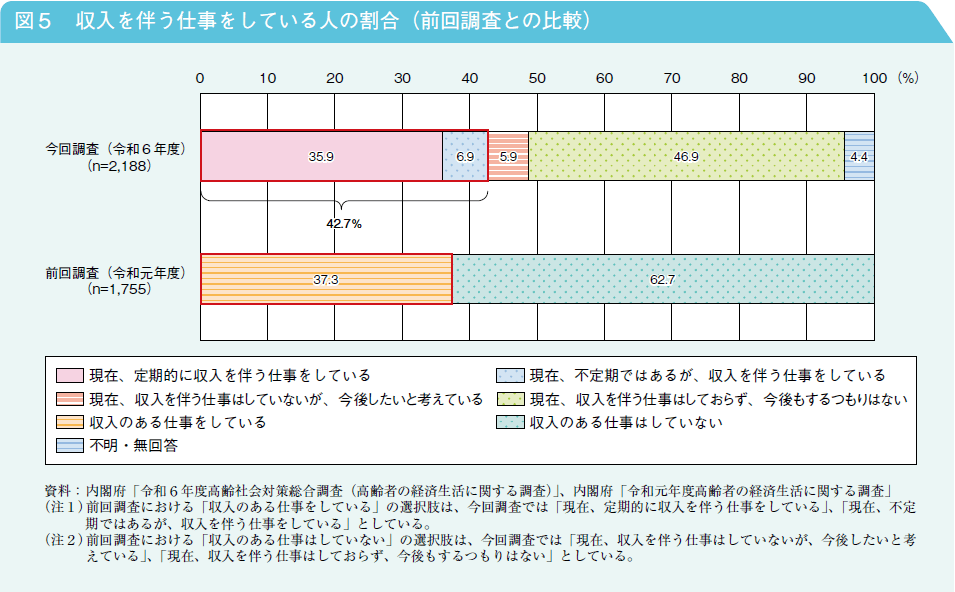
○仕事をする理由は「収入のため」が最も多い
全体で見ると、「収入のため」と回答した割合が5割以上で最も高く、次いで、「働くのは体によいから、老化を防ぐから」、「自分の知識・能力を生かせるから」と回答した割合が高い。なお、65歳以上について見ると、「収入のため」と回答した割合が最も高いものの、「働くのは体によいから、老化を防ぐから」と回答した割合が3割弱となり、全体と比較して、高くなっている。
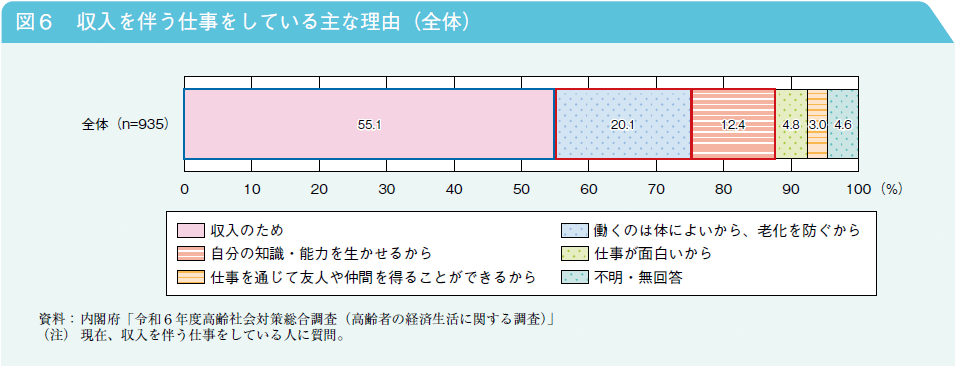
○高齢期における就業意欲は高まっている
全体で見ると、「65歳くらいまで」と回答した割合が約2割で最も高い一方、「働けるうちはいつまでも」と回答した割合も2割を超えており、「75歳くらいまで」、「80歳くらいまで」又は「働けるうちはいつまでも」と回答した割合を合計すると4割を超える。
前回調査時と比較すると、「75歳くらいまで」、「80歳くらいまで」又は「働けるうちはいつまでも」と回答した割合は上昇しており、高齢期における就業意欲の高まりがみられる。
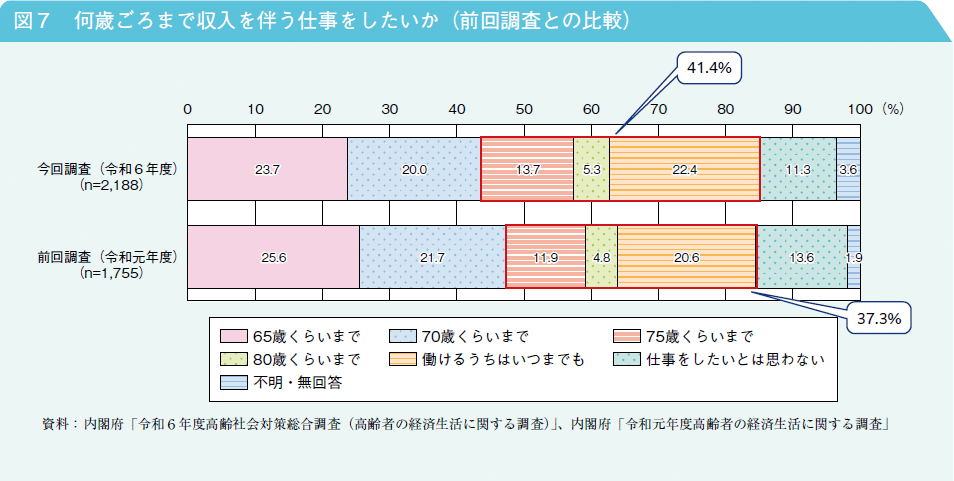
○就業に対するニーズは個々人の属性に応じて多様
仕事をする理由としては、前述のとおり収入を挙げる人が最も多い一方で、実際に仕事を選ぶ際には、給与等が希望に適っていることよりも、自分の経験やスキルを生かせること、自宅から通いやすいこと、仕事のやりがいがあることを重視する傾向がみられた。
また、おおむね年代が低い層ほど経験やスキルが生かせることを重視し、年代が高い層ほど仕事内容について体力的な負担が少ないことを重視するなど、個々人の属性に応じて、就業に対するニーズは多様である。
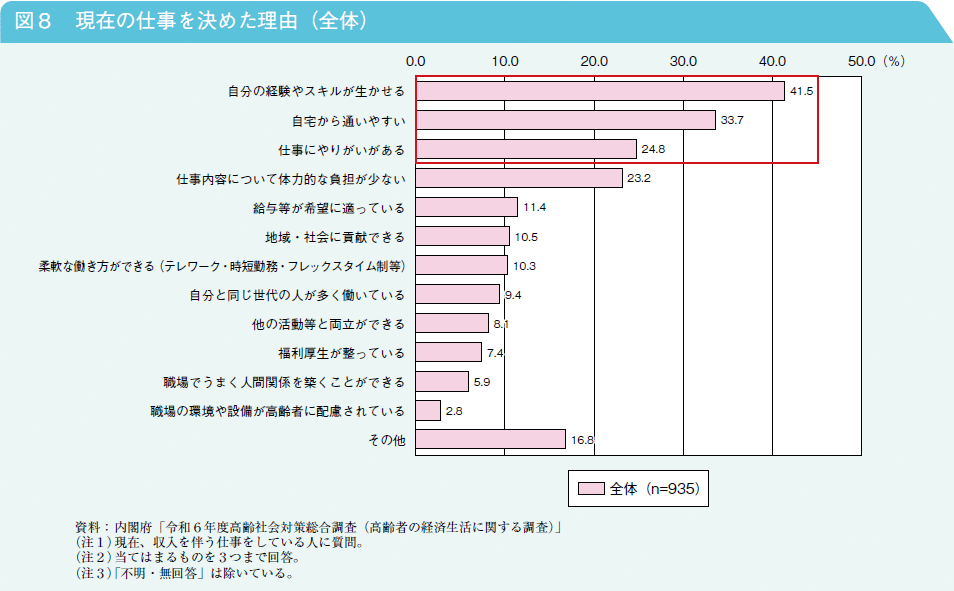
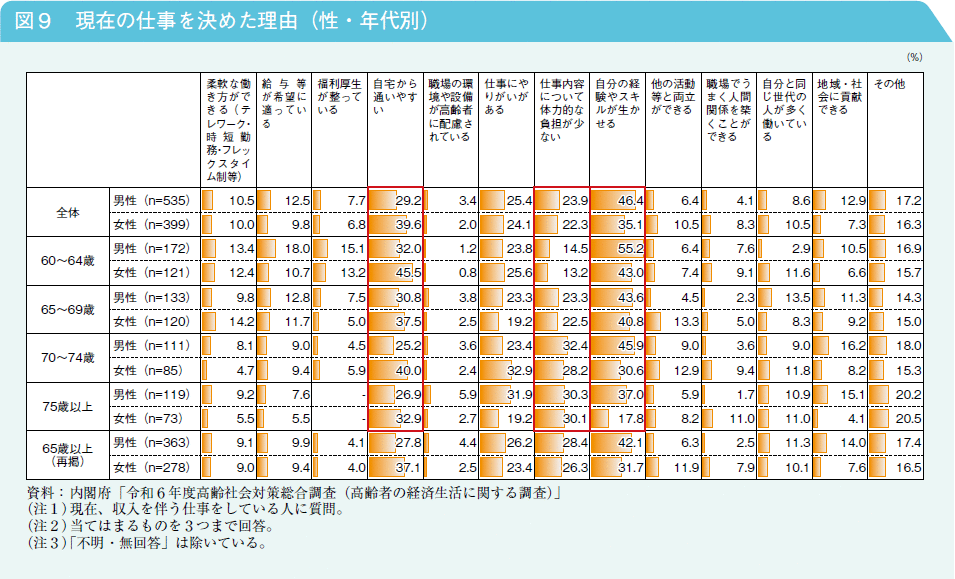
○仕事をしたいと考えているが就業に至っていない人の理由は様々
現在、収入を伴う仕事をしていない人のうち、今後仕事をしたいと考えている人について、仕事をしていない理由を見ると、「健康上の理由」に次いで、「年齢制限で働くところが見つからないから」、「仕事の種類(職種)で合うところが見つからないから」、「勤務場所・時間など条件が合うところが見つからないから」と回答した割合が高くなっている。
こうした傾向を踏まえると、高齢期においても希望に応じて働き続けられる環境の整備や、高齢期の就業ニーズを踏まえたきめ細かなマッチングの推進を図っていくことが重要である。
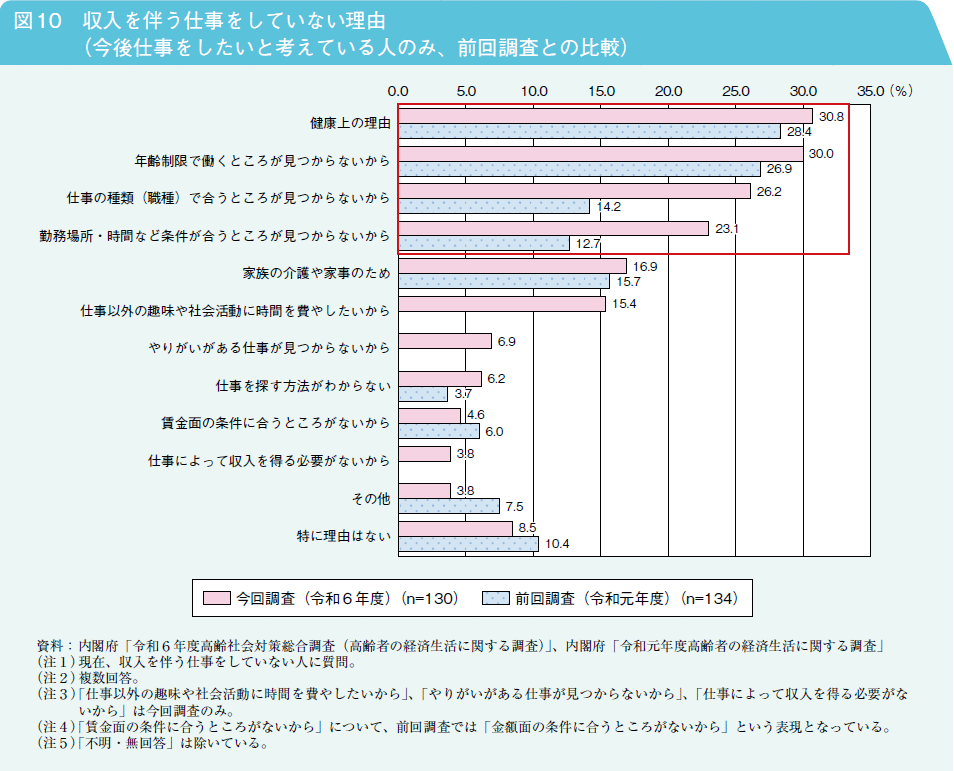
○家計に対する不安は高齢女性(75歳以上)において高い
全体で見ると、「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」又は「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」と回答した割合(心配なく暮らしていると回答した割合)は前回調査時と比較してやや低下しているものの、7割弱となっている。
一方、75歳以上の女性は、同年代の男性と比べ、心配であると回答した割合が高く、高齢女性が抱える経済的不安への対応も求められる。
また、家族形態別で見ると、ひとり暮らしの人は、心配であると回答した割合がひとり暮らし以外の人を大きく上回っている。
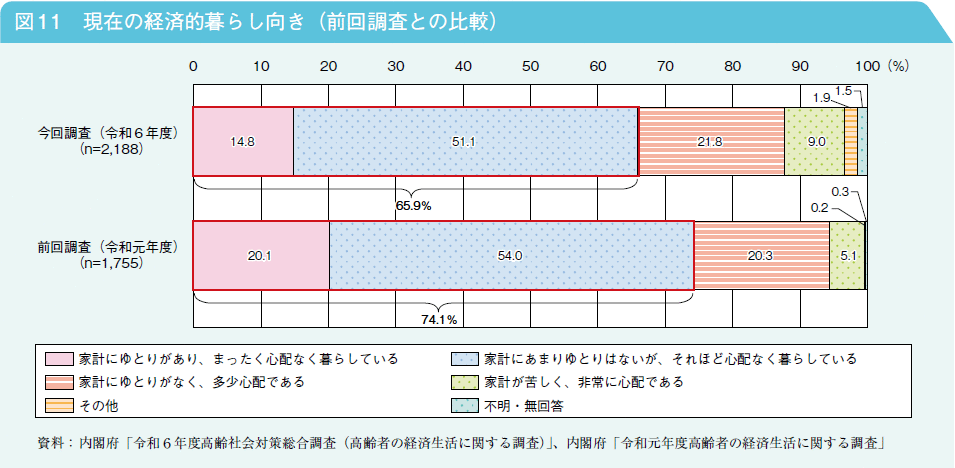
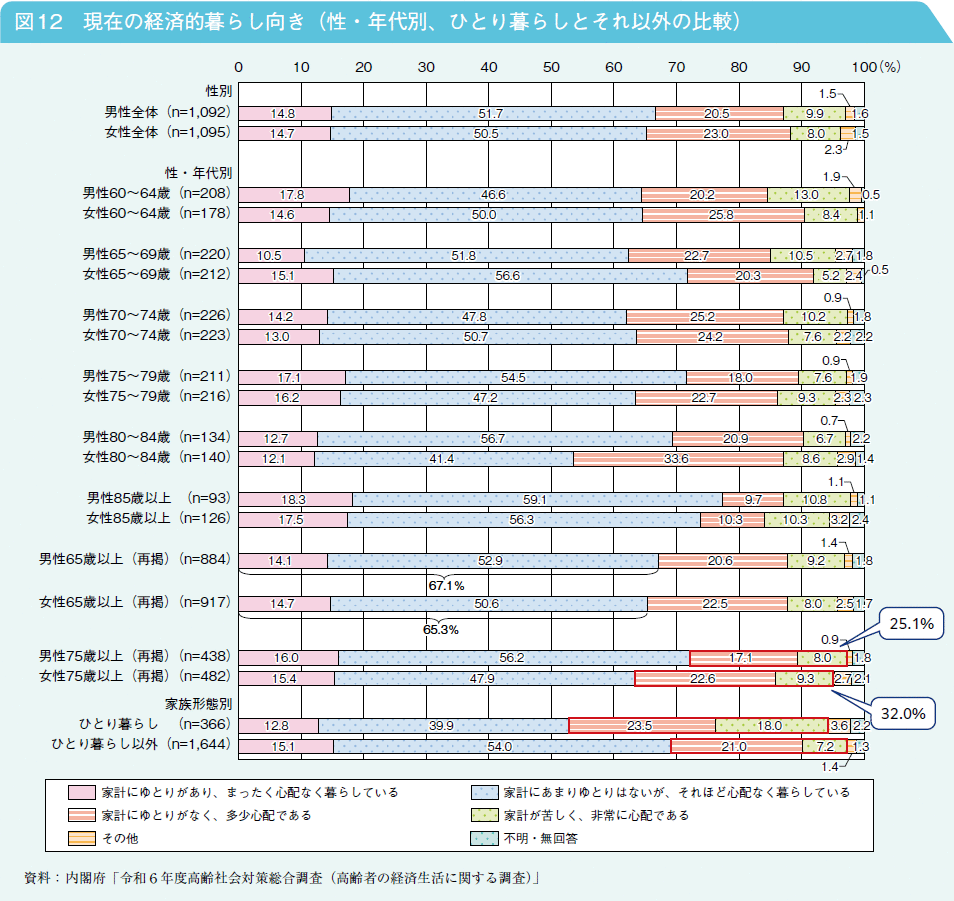
○具体的な不安として特に物価上昇を挙げる人が多い
経済的な面の不安について見ると、「物価が上昇すること」と回答した割合が7割以上で最も高く、次いで、「収入や貯蓄が少ないこと」、「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」、「災害により被害を受けること」、「自分や家族の医療・介護の費用がかかりすぎること」が高い。
こうした傾向を踏まえると、高齢期における就業促進による安定的な収入確保のほか、若年期からの資産形成の促進や介護予防の推進を図っていくことが重要である。
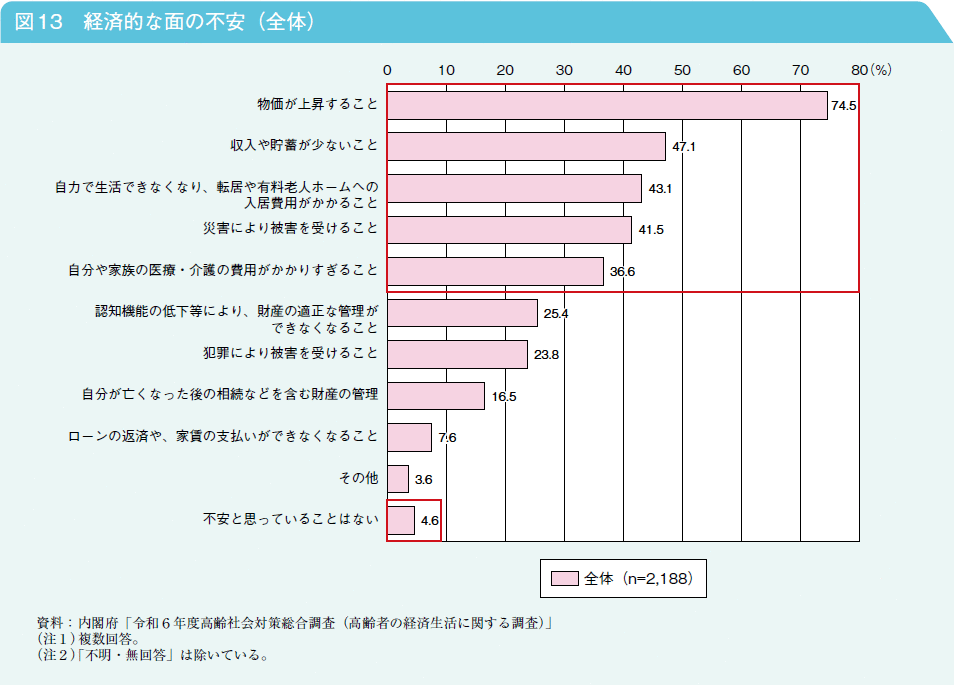
○高齢期のリスクに応じた備えは全体的に進展
全体で見ると、「生命保険」と回答した割合が最も高く、次いで、「病気やけがのための保険」が高い。また、前回調査時と比較すると、「生命保険」、「病気やけがのための保険」、「個人年金」、「介護のための保険」、「企業年金」と回答した割合はいずれも上昇し、「いずれも加入していない」と回答した割合は大きく低下しており、収入面や健康面等、高齢期のリスクに応じた備えは全体的に進展している。
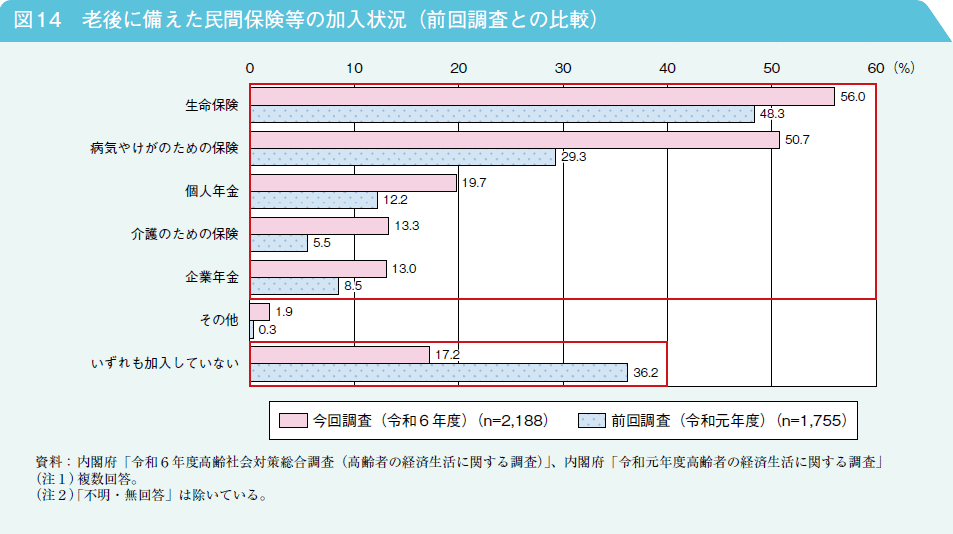
○ほとんどの人は認知機能の低下等に備えた財産管理の必要性の認識が薄い
老後のために必要だと思う備えについて、全体で見ると、「健康に関する備え(健康の維持・増進、介護予防、保険、病気やけがの治療等)」と回答した割合が最も高い。次いで、約4割の人が「終活関係の準備(自身の葬儀やお墓の準備、財産等の整理・相続の準備)」を挙げている一方、そのうち約3割が実際に準備を行っておらず、こうした準備の必要性を感じつつも、実際には取り組むことができていない層が一定程度存在していることが明らかになった。
また、「財産管理に関する備え(認知機能の低下等に伴う、財産管理の相談(金銭管理サービスの利用等))」が必要と回答した割合は1割以下となっている。加齢に伴う認知機能が低下すると、自身がそういった状態にあること自体を認識できなくなる可能性もあり、特に、頼れる家族や親族等がいない場合には、日常的な金融経済活動や意思決定等の場面で支障が生じるおそれがあることから、認知機能の低下等に伴う財産管理の備えの必要性についての認識を高めていくことや、地域において必要に応じて金銭管理や意思決定支援等の日常生活支援を受けられる体制を構築していくことが重要である。
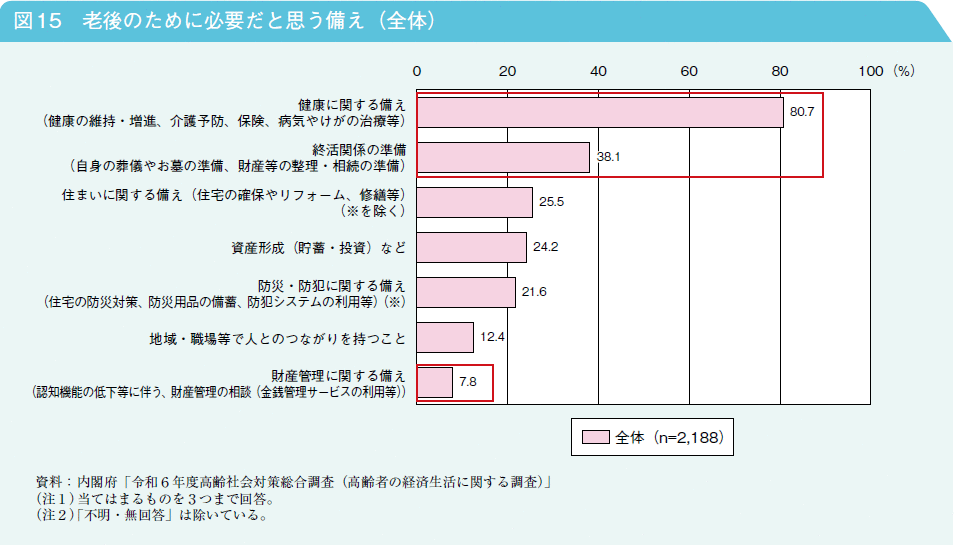
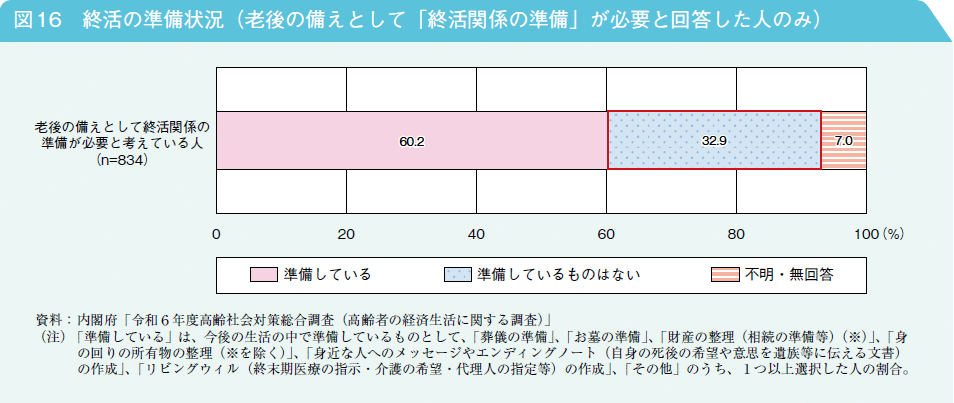
<トピックス>
(事例1)〈岡山県勝田郡奈義町〉しごとコンビニ~「ちょっとだけ働きたい」を叶える「しごと」と人材のマッチング~
岡山県勝田郡奈義町では、「しごと」の依頼主と働き手双方の希望をヒアリングしたうえで「しごと」を作業内容や時間で分解し、チーム制も導入することで、「ちょっとだけ働きたい」という高齢者や子育て中の若い世代等の働き手にマッチングさせる「しごとコンビニ」事業を行っている。当初は町から委託を受けた事業者が事業を運営していたが、令和元年度からは地域主導に切り替え、一般社団法人奈義しごとえんが運営している。この取組により、「しごと」を通して高齢者や子育て世代の方に繋がりができ、多世代交流が生まれているほか、働き手の生きがいにもなっており、生涯活躍できるまちづくりにも寄与している。
(事例2)〈福岡県大川市〉大川市おひとりさま支援事業~簡易な金銭管理・意思決定支援~
少子高齢化により一人暮らしの高齢者や親族が遠方で生活しているため支援が困難な市民が増加し、日常生活のちょっとした困りごとへの対応や入院・入所手続き及び支払いができない高齢者が顕在化している中、福岡県大川市では、市、市社会福祉協議会、市成年後見センター、地元の金融機関等が連携し、「大川市おひとりさま支援事業」を行っている。支援事業では、①予算管理機能付きカード等を使った日常的金銭管理サービス、②意思決定サポーターによる意思決定支援、③入院・入所費用支払いのための支援を行っており、事業の利用によって、意思決定サポーターの支援を受けながら、お金の使い方を利用者自身で決めることができるようになり、やってみたいことが広がり、利用者の生活の充実に繋がっている。
(事例3)〈東京都墨田区〉地域力を活かした公民学連携のスマートフォン(スマホ)講座~仲間とスマホ操作を楽しく習得~
東京都墨田区では、高齢者がスマホ操作を習得するためのスマホ利活用の習慣化を目的として、スマホ習慣化アプリ「みんチャレ」(以下、「みんチャレ」という。)を活用したスマホ講座を行っている。スマホ講座では、みんチャレによって基本操作の反復練習を行っており、その内容は、最大5人1組のチームを組み、チーム内で毎日歩いた歩数とその日にスマホで撮影した写真にコメントを付けて投稿するというもので、グループ内の仲間と交流しながら文字入力やカメラ機能を楽しく習得できるように工夫されている。その結果、受講者の外出時のスマホ携帯率の向上は85%、スマホを使った交流の機会は75%増加している等、スマホの利活用の習慣化を実現している。
(事例4)軟骨伝導イヤホン~誰もが利用しやすい窓口へ~
奈良県立医科大学の細井裕司氏により発見された耳の軟骨を振動させて音声を伝える「軟骨伝導」の仕組みをもとに開発された軟骨伝導イヤホンは、軽度から中程度の難聴のある方には音声がクリアに聴こえ、音漏れがないほか、耳穴に挿入せず装着でき、イヤホンに穴や凹凸もないことから完全に清拭でき衛生的であるなどの利点を有している。そのため、窓口での対話で個人の情報を扱う自治体や金融機関等では、高齢者等難聴のある方に対応する際に大きな声を出す必要がなくなり、プライバシーに配慮して対応できることから導入する団体が増えている。こうした難聴の方も生活しやすい環境の整備を進めていくことで、フレイルや認知症等のリスクを抑制する効果も期待される。

