第1章 高齢化の状況(第3節 トピックス)
第3節 〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について(トピックス)
事例4 軟骨伝導イヤホン ~誰もが利用しやすい窓口へ~
事業の目的・概要
自治体や金融機関等の窓口に、老眼鏡は設置されているが難聴者のためのものは何もないという問題意識から「窓口用軟骨伝導イヤホン」は生まれた。耳の軟骨を振動させて音声を伝える「軟骨伝導」という、これまでの「気導」、「骨伝導」に次ぐ第3の経路の発見により開発されたもので、軽度から中程度の難聴のある方には音声がクリアに聴こえ、手入れもしやすいため、プライバシーへの配慮が必要な窓口で対応がしやすいということで全国に広がっている。また、その導入には、信用金庫の全国的なネットワークも活用されている。
具体的な取組内容
軟骨伝導の仕組みは、平成16年に奈良県立医科大学の細井裕司氏により発見された。その仕組みを基に令和5年に開発された軟骨伝導イヤホンは、耳穴に挿入せず耳甲介腔・耳珠・耳介裏に装着するもので、イヤホンに穴や凹凸もないことから完全に清拭でき衛生的であり、また装着時に骨を圧迫しないので痛みもないなどの利点を有している。さらに、音声がクリアであるとともにイヤホンを装着している本人にしか聞こえないため、聴こえに支障のある高齢者等に大きな声で対応する必要もないことから、窓口での対話で個人の情報を扱う自治体や金融機関等で導入する団体が増えており、令和6年末時点で、全国449機関(団体)1,879か所の窓口で設置されている。
導入に当たっては、奈良県立医科大学と包括連携協定を結ぶ「よい仕事おこしフェア実行委員会」(以下、「実行委員会」という。)とのつながりがきっかけというケースも多い。この実行委員会は全国の信用金庫で構成されており、そのネットワークを通じて軟骨伝導イヤホンが信用金庫に設置され始め、同じ地域の自治体窓口に設置されたところもある。信用金庫から銀行といった金融機関における設置の広がりだけでなく、自治体における設置の広がりも増えている。
軟骨伝導の仕組みを発見した奈良県立医科大学のある奈良県では、令和5年5月に奈良中央信用金庫が、同年6月には奈良中央信用金庫開催のデモンストレーションに参加した田原本町役場が軟骨伝導イヤホンを設置した。
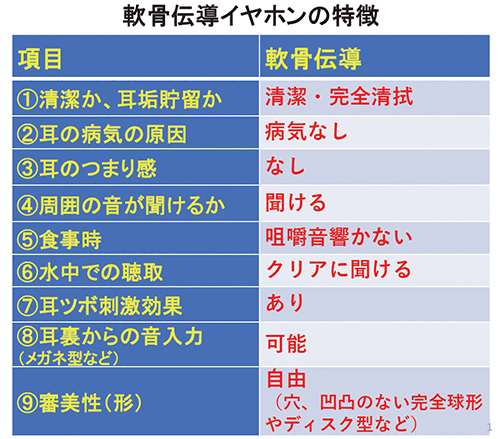
事業効果
窓口に軟骨伝導イヤホンを設置している田原本町では、障害者手帳を持つまでに至らない中程度までの方からは音声がクリアに聴こえる、補聴器よりも扱いやすいといった声も寄せられている。以前は聴こえに支障のある高齢者等に対応する際には普段より大きな声で対応したり、筆談したりする必要のあった窓口業務も、導入後は聴こえに支障のない方と同程度の声で対応できるようになった。また、窓口に設置するだけでなく、高齢者宅を訪問する際に職員が持参し使用することもある。

今後の展開
難聴は、生活や社会参加の範囲を狭め、フレイルや認知症等のリスクを高める要因にもなり得るなど、高齢期の生活に及ぼす影響も大きいため、本事例のように難聴の方も生活しやすい環境を整備していくことが、ますます求められている。今後は、医療機関等の窓口への設置促進や、韓国世宗特別自治市の窓口に設置された事例もあるように日本だけでなく世界へも導入を広げ、「難聴者が窓口で困らない社会」を目指していくこととしている。

