第2章 令和6年度高齢社会対策の実施の状況(第2節 1)
第2節 分野別の施策の実施の状況(1)
1 就業・所得
(1) 年齢に関わりなく希望に応じて働くことができる環境の整備
① 高齢期を見据えたスキルアップやリ・スキリングの推進
DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)の加速化や職業人生の長期化、働き方の多様化など、企業・労働者を取り巻く環境が急速かつ広範に変化する中で、労働者の学び・学び直しの必要性が高まっている。労働者がこうした変化に対応して、自らのスキルを向上させるためには、企業主導型の職業訓練の強化を図るとともに、労働者がその意義を認識しつつ、自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しを行うことが必要であり、こうした取組に対する広く継続的な支援のため、職業訓練の実施や職業能力の「見える化」のみならず、個々人に合った職業人生を通じたキャリア形成支援を推進した。また、高齢期を見据えたキャリア形成支援を推進するため、労働者のキャリアプラン再設計や企業内の取組を支援するキャリア形成・リスキリング推進事業において、労働者等及び企業に対しキャリアコンサルティングを中心とした総合的な支援を実施した。加えて、中高年齢者の中長期的なキャリア形成を支援するため、キャリアコンサルタント向けに必要な知識・技能等を付与する研修教材をオンラインで提供した。
さらに、労働者個人の主体的な能力開発・キャリア形成を促進するため、教育訓練給付金の給付率の上限の引上げや教育訓練休暇給付金の創設等を内容とする「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号。以下「改正雇用保険法」という。)が令和6年5月に成立した。
令和4年10月から施行された「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号。以下「改正職業能力開発促進法」という。)により法定化された都道府県単位の協議会において、前年度に実施した公的職業訓練の分析結果を踏まえ、今後の課題を協議したほか、協議会の下に設置されたワーキンググループを活用し、訓練修了生や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果の把握・検証を行い、訓練内容の改善に取り組んでいる。
このほか、生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人選抜の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施等を引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを促進した(図2-2-1)。
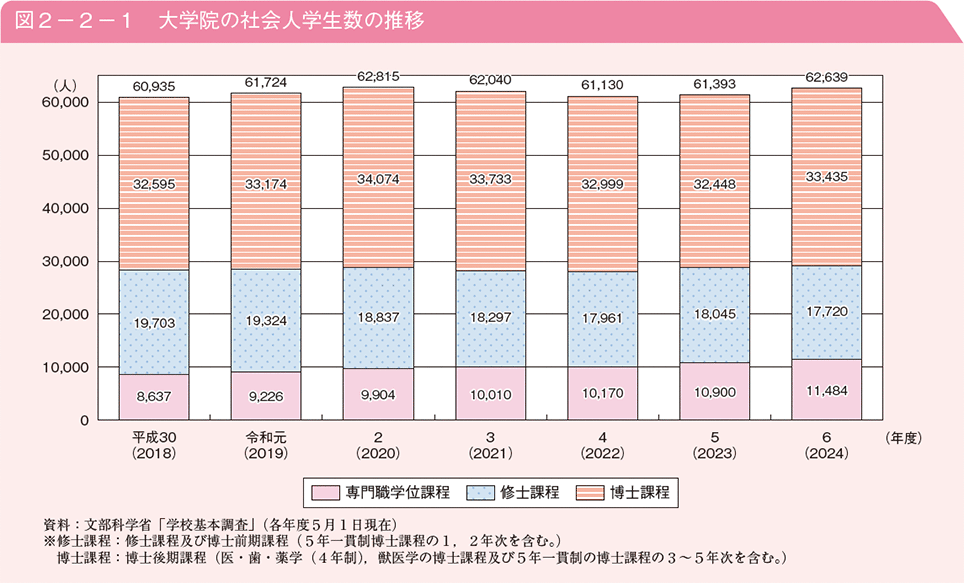
また、大学等が、その学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、履修証明プログラムや公開講座を実施する等高度な学習機会を提供することを促進した。さらに、高等教育段階の学習機会の多様な発展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者、専門学校等修了者で、大学における科目等履修生制度等を利用し一定の学習を修めた者については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において審査の上、「学士」の学位授与を行っている。
放送大学においては、テレビ・ラジオ放送やインターネット等の身近なメディアを効果的に活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供した(図2-2-2)。
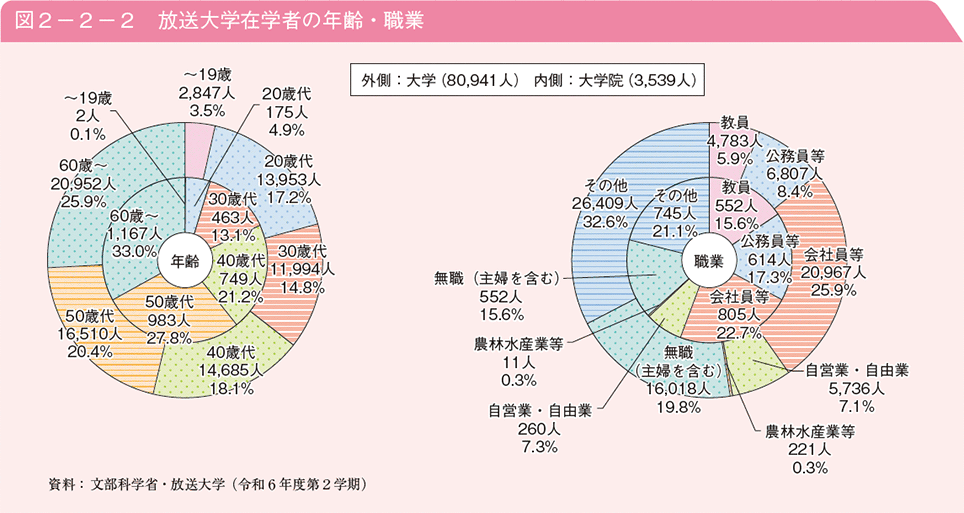
② 企業等における高齢期の就業の促進
ア 知識、経験を活用した高齢期の雇用の確保
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)では、希望者全員について65歳までの雇用が確保されるよう、事業主に対して、65歳までの定年引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入のいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じるよう義務付けており、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対しては、公共職業安定所による指導等を実施した。さらに、令和3年4月に施行された「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号。以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)において、事業主に対する70歳までの就業機会確保が努力義務とされたことを踏まえ、適切な措置の実施に向けた事業主への周知啓発を行うとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の70歳雇用推進プランナー等により、①70歳までの定年引上げ、②70歳までの継続雇用制度の導入(他社との契約に基づく継続雇用も含む。)、③定年の定めの廃止、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に社会貢献事業(a.事業主が自ら実施する社会貢献事業、b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)に従事できる制度の導入の措置(高年齢者就業確保措置)に関する技術的事項についての相談・助言を行った。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和41年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第9条に基づき、労働者の一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等を行った。
また、企業における高年齢者の雇用を推進するため、65歳以上の年齢への定年延長や66歳以上の年齢への継続雇用制度の導入又は他社による継続雇用制度の導入を行う事業主、高年齢者の雇用管理制度の見直し又は導入等や高年齢の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換する事業主に対する支援を実施した。さらに、継続雇用延長・定年引上げに係る具体的な制度改善提案を実施し、企業への働きかけを行った。加えて、日本政策金融公庫(中小企業事業)の融資制度(地域活性化・雇用促進資金)において、エイジフリーな勤労環境の整備を促進するため、高齢者(60歳以上)等の雇用等を行う事業者に対しては当該制度の利用に必要な雇用創出効果の要件を緩和(2名以上の雇用創出から1名以上の雇用創出に緩和)する措置を継続した。
地域における高齢者の就業促進に当たり、地方公共団体の意向を踏まえつつ、都道府県労働局と地方公共団体が一体となって地域の雇用対策に取り組むための雇用対策協定の活用を図った。
高年齢労働者が安心して安全に働ける職場づくりや労働災害の防止のため、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)の周知を行った。また、高年齢労働者の安全・健康確保の取組を行う中小企業等に対し、エイジフレンドリー補助金による支援を行うとともに、労働災害防止団体による個別事業場支援の利用勧奨を行い、高年齢労働者の安全衛生対策を推進した。
公務部門における高齢者雇用において、国家公務員については、定年を段階的に引き上げて65歳とすることとされたところであり、シニア職員の具体的な職務付与や若年層等の職員との職務分担、貢献意欲の向上策等について、「国家公務員の定年引上げに向けた取組指針」(令和4年3月25日人事管理運営協議会決定)を踏まえた取組を進めた。また、引き続き、定年の段階的な引上げ期間中の経過措置として、暫定再任用制度を活用し、定年退職者等のうち希望者を、公的年金の支給開始年齢まで原則再任用する等の措置を講じた。
地方公務員についても、国家公務員と同様に定年を段階的に引き上げることとされたところであり、高齢期職員の具体的な職務付与、モチベーション維持のための取組、周囲の職員も含めた職場環境の整備等に取り組むとともに、定年の段階的な引上げ期間中の経過措置として、引き続き、定年退職等する職員が再任用を希望する場合、公的年金の支給開始年齢まで原則再任用するなど、定年引上げの適切かつ円滑な運用に向けて、必要な助言等を行った。
イ ゆとりある職業生活の実現等
我が国の労働時間の現状を見ると、週労働時間60時間以上の雇用者の割合が1割弱となっており、また、年次有給休暇の取得率は6割前後の水準となっている。この状況を踏まえ、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」(平成4年法律第90号)及び「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働省告示第108号)に基づき、時間外・休日労働の削減及び年次有給休暇の取得促進を始めとして労使の自主的な取組を促進する施策を推進した。具体的には、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るため、10月の「年次有給休暇取得促進期間」に加え、連続休暇を取得しやすい時季(夏季、年末年始及びゴールデンウィーク)における集中的な広報などによる年次有給休暇の取得促進や、勤務間インターバル制度を導入する際に参考となる業種別マニュアルの作成・周知やシンポジウムの開催などを通じた制度の導入促進等を行った。
③ 高齢期のニーズに応じた多様な就業等の機会の提供
ア 多様な形態による就業機会・勤務形態の確保
(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備
地域における高年齢者の多様な雇用・就業機会の創出を図るため、地方公共団体を中心とした協議会が行う高年齢者の就労支援の取組と地域福祉・地方創生等の取組を一体的に実施する生涯現役地域づくり環境整備事業等を実施し、先駆的なモデル地域の取組の普及を図った。
定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズに応じ、就業機会を確保提供し、高年齢者の生きがいの充実、社会参加の促進等を図るシルバー人材センター事業について、各シルバー人材センターにおける就業機会及び会員拡大等の取組への支援を行うとともに、少子高齢化が急速に進展する中で、人手不足の悩みを抱える企業を一層強力に支えるため、サービス業等の人手不足分野や介護、育児等の現役世代を支える分野での高年齢者の就業を促進する高齢者活用・現役世代雇用サポート事業を実施した。また、多様化する高年齢者のニーズに対応するため、令和7年1月末までに759地域において都道府県知事が業種・職種及び地域を指定し、派遣及び職業紹介の働き方において就業時間の要件緩和がなされた。
また、従来の就業形態に加え、高齢者がこれまでの豊富な経験を生かし地域のニーズに応じた働く場を自ら創出することなどを促進する制度として、令和4年10月1日に「労働者協同組合法」(令和2年法律第78号)が施行され、働く人が出資し、意見の反映を通じ自ら事業の内容・進め方などの運営にも関わる新しい法人形態である労働者協同組合が設立可能となっており、セミナー等による制度の周知やモデル事業の実施による制度の活用促進を図った。
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に向け、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するための規定等が整備された「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号。以下「パートタイム・有期雇用労働法」という。)が令和3年4月1日に全面施行され、同法違反が認められる企業に対しては是正指導を行い、法違反に当たらないものの、改善に向けた取組が望まれる企業に対しては具体的な助言を行いつつ、支援ツール等を活用し、企業の制度等の見直しを検討するように促し、同法の着実な履行確保を図った。令和4年10月に策定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)及び令和5年11月に策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、労働基準監督署と都道府県労働局が連携し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を行った。加えて、企業における非正規雇用労働者の待遇改善等を支援するため、平成30年度より47都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」において、労務管理等の専門家による無料の個別相談支援やセミナー等を引き続き実施した。
さらに、職務、勤務地、労働時間を限定した「多様な正社員」制度の導入・定着を図るため、「多様な正社員」制度導入支援セミナーや「多様な働き方の実現応援サイト」での好事例の周知、「多様な正社員」制度を導入・整備しようとする企業への社会保険労務士等による導入支援等を行った。
高齢者を含め多様な人材の能力を最大限発揮させるダイバーシティ経営について、自社の目指す姿や取組の振り返りを目的とした「ダイバーシティ・コンパス」を用いたワークショップの開催や、中小企業向けリーフレットの普及、その他「ダイバーシティ経営診断ツール」等の各種支援ツールの活用促進や企業事例の調査・普及等を通じ、企業における取組を促進した。加えて、副業・兼業については、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」等の周知を引き続き実施するとともに、公益財団法人産業雇用安定センターにおいて、副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情報及びその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に対して企業情報を提供する「副業・兼業に関する情報提供モデル事業」を実施し、副業・兼業への取組の拡大を図った。
(イ)情報通信を活用した遠隔型勤務形態の普及
テレワークは、高齢者の就業機会の拡大及び高齢者の積極的な社会への参画を促進する有効な働き方と期待されている。「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和5年6月9日閣議決定)においては、「働く時間や場所を柔軟に活用できる働き方であるテレワークは、働き方を変えるだけでなく、人々の日常生活における時間の使い方に大きな変化をもたらすものであり、その更なる導入・定着は不可欠である」とされている。そのため、関係府省庁では、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を連携して推進している。具体的には、適正な労務管理下におけるテレワークの導入・定着支援を図るため、テレワークに関する労務管理とICT(情報通信技術)の双方についてワンストップで相談できる窓口での相談対応や、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(令和3年3月改定)の周知、中小企業事業主に対するテレワーク導入経費の助成等を行った。また、事業主を対象としたセミナー等の開催、中小企業を支援する団体と連携した全国的なテレワーク導入支援体制の構築、テレワークに先進的に取り組む企業等に対する表彰の実施、「テレワーク月間」等の広報、中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)の周知等により、テレワークの定着・促進を図った。さらに、テレワークによる働き方の実態やテレワーク人口の定量的な把握を行った。
イ 高齢者等の再就職の支援・促進
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する高年齢離職予定者の希望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した求職活動支援書を作成・交付することが事業主に義務付けられており、求職活動支援書の交付を希望する高年齢離職予定者に対して必ず事業主が交付するよう公共職業安定所において指導・助言を行った。求職活動支援書の作成に当たってジョブ・カードを活用することが可能となっていることから、その積極的な活用を促した。
主要な公共職業安定所において高年齢求職者を対象に職業生活の再設計に係る支援や、特に就職が困難な者に対する就労支援チームによる支援及び職場見学、職場体験等を行った。
また、常用雇用への移行を目的として、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を公共職業安定所等の紹介により、一定期間試行雇用した事業主に対する助成措置(トライアル雇用助成金)や、高年齢者等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)を実施した(表2-2-3)。
| トライアル雇用助成金 |
|---|
|
| 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |
|
| 65歳超雇用推進助成金 |
|
| 資料:厚生労働省 |
さらに、再就職が困難である高年齢者等の円滑な労働移動を強化するため、早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)により、離職を余儀なくされる高年齢者等の再就職を民間の職業紹介事業者に委託した事業主に対して助成措置を実施したほか、早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)により、高年齢者等を早期に雇い入れるとともに、前職よりも賃金を5%以上上昇させた事業主に対して助成措置を実施し、能力開発支援を含めた賃金上昇を伴う労働移動の支援を行った。あわせて、早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)により中途採用者の能力評価、賃金、処遇の制度を整備した上で、45歳以上の中高年齢者の中途採用率等を拡大させるとともに、当該45歳以上の中高年齢者の賃金を前職よりも5%以上上昇させた事業主に対して、助成額を増額し、中高年齢者の賃金上昇を伴う労働移動の促進を行った。また、高年齢退職予定者のキャリア情報等を登録し、その能力の活用を希望する事業者に対してこれを紹介する「高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業」を公益財団法人産業雇用安定センターにおいて実施し、高年齢者の就業促進を図った。
ウ 高齢期の起業の支援
日本政策金融公庫において、高齢者等を対象に優遇金利を適用する融資制度により開業・創業の支援を行った。
(2) 公的年金制度の安定的運営
ア 働き方の多様化や高齢期の長期化・就労拡大に対応した年金制度の構築
今後、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる。こうした社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号。以下「令和2年年金改正法」という。)が順次施行されており、その円滑な施行に向けた取組を行った。
また、社会保障審議会年金部会では、令和2年年金改正法に規定された検討課題や、令和6年財政検証の結果、一定の制度改正を仮定したオプション試算の結果等を踏まえ、平均寿命・健康寿命の延伸や家族構成・ライフスタイルの多様化、女性・高齢者の就業拡大、今後見込まれる最低賃金の上昇・持続的な賃上げという社会経済の変化に対応する観点から取り組むべき課題、年金制度が有する所得保障機能の強化の観点から取り組むべき課題への対応を大きな2つの柱として、次期年金制度改革に向けた具体的な見直しの方向性について検討を行い、令和6年12月25日に「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を取りまとめた。
イ 年金制度等の分かりやすい情報提供
短時間労働者等への被用者保険の適用拡大の円滑な施行に向けて、制度改正の内容や適用拡大による被保険者のメリット等について、周知・広報に努めた。また、若い人たちに年金について考えるきっかけとしてもらうため「学生との年金対話集会」や、若い世代向けの年金学習教材の作成等を行った。さらに、利用者の働き方等に対応した将来受け取る年金額の見通しを「見える化」する公的年金シミュレーターについて、令和6年4月に更改した社会保険適用拡大特設サイトや令和6年5月に公表した中高生向けの年金教材などで紹介するなど活用促進を図った。「ねんきん定期便」については、老後の生活設計を支援するため、令和2年年金改正法による年金の繰下げ受給の上限年齢の引上げを踏まえた年金額増額のイメージ等について、分かりやすい情報提供を推進した。
(3) 高齢期に向けた資産形成等の支援
ア 資産形成等の促進のための環境整備
勤労者財産形成貯蓄制度の普及等を図ることにより、高齢期に備えた勤労者の自助努力による計画的な財産形成を促進した。
企業年金・個人年金に関して、「令和3年度税制改正の大綱」(令和2年12月21日閣議決定)において決定された確定拠出年金(以下「DC」という。)の拠出限度額の引上げ等(令和6年12月施行。)を行った。また、個人型DC(以下「iDeCo」という。)の加入可能年齢の上限の70歳未満への引上げ、iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、社会保障審議会企業年金・個人年金部会において議論をとりまとめた。さらにiDeCoについて、更なる普及を図るため、各種広報媒体を活用した周知・広報を行った(加入者数は、令和7年3月末時点で363.1万人)。退職金制度については、中小企業における退職金制度の導入を支援するため、中小企業退職金共済制度の普及促進のための周知等を実施した。
また、令和6年1月から新しい少額投資非課税制度(以下「NISA」という。)が開始されたところ、NISAの更なる利便性向上等に向け、「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)において、金融機関変更時の即日買付を可能とすることや、つみたて投資枠で投資可能なETF(上場投資信託)に係る要件の見直しなどの措置が講じられることとされ、関係法令の整備等を行った。また、NISAの普及の観点から、分かりやすさを追求したガイドブック等の活用や、新しいNISAを含む安定的な資産形成を目的としたイベント・セミナーの開催等により、適切な周知・広報を行い、NISA口座数及び買付額を増加させ、NISAの利用の促進を図った。
イ 資産の有効活用のための環境整備
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)において、高齢者が住み替え等のための住生活関連資金を確保するために、リバースモーゲージ型住宅ローンの普及を促進した。また、低所得の高齢者世帯が安定した生活を送れるようにするため、各都道府県社会福祉協議会において、一定の居住用不動産を担保として、世帯の自立に向けた相談支援に併せて必要な資金の貸付けを行う不動産担保型生活資金の貸与制度を実施した。

