防衛省 戦後資料 [B03-5] 381-390件
- 「※」印の付いた資料は日本図書センターの協力によるものです。
- 「請求番号」は原本所蔵機関における請求番号になります。
- 「詳細」欄に公文書の冒頭300字程度をテキストで表示しています。
原本の保存状態などにより読み取りが困難な文字は「〓」で表示しています。
整理番号:B03-5-343
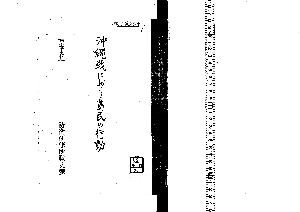
収蔵文書名
簿冊名
沖縄戦における島民の行動 大本営参謀(船舶)馬淵新治(1) (PDF形式:4088KB)
沖縄戦における島民の行動 大本営参謀(船舶)馬淵新治(2) (PDF形式:4059KB)
沖縄戦における島民の行動 大本営参謀(船舶)馬淵新治(3) (PDF形式:3639KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
沖台 沖縄303
詳細
沖縄戦における島民の行動 沖縄事情の一班と沖縄戦における島民の行動について 目次 其一、沖縄の一般的な観察 1頁 其二、沖縄の現代史について 5頁 其三、終戦後の沖縄の立場とその政治組織 15頁 其四、沖縄戦における沖縄出身者の戦没者について 19頁 其五、対住民対策について 23頁 一、島外集団疎開と島内疎開 24頁 二、防諜対策 28頁 三、人的資源の活用について 30頁 1.防衛召集 30頁 2.学徒について 31頁 3.戦闘協力について 33頁 其六、 住民感情について 43頁 其七 後記 47頁 其八 附録 48頁 其一、沖縄の一般的な観察 沖縄は今次大戦に於ける唯一の国内戦の戦場となった県であり、物量を誇る米軍に対して約三ヶ月の長期に亘って悪戦苦闘した結果、
頁数
67
備考
整理番号:B03-5-344
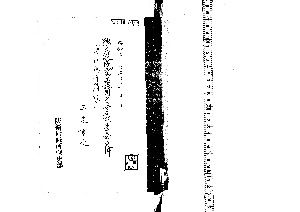
収蔵文書名
簿冊名
独立混成第44旅団第2歩兵隊第1大隊史料(伊江島守備隊)昭和19.9.5~20(PDF形式:3637KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
沖台 沖縄317
詳細
昭和一九、九、五~二〇年 独立混成第四十四旅団第二歩兵隊第一大隊史料 (伊江島守備隊) 三宅重之 伊江島守備隊 此の小篇を南海の孤島伊江島に華々しく散つた幾多英霊の遺族に捧ぐ 伊江島守備隊 井川部隊、詳しくは独立混成第四十四旅団第二歩兵隊第一大隊 昭和十九年九月五日沖縄県国頭郡名護に於て編成さる。部隊長陸軍少佐井川正は大分県の人年令三十九才。部隊の根幹をなすは大分・熊本・宮崎・鹿児島四県出身の将兵約三百五十名にして、之れに加わるに現地召集の兵約三百名を以てす。編成と共に名護地区以北の防衛を任ぜらる。九月十九日より十月三日の間。伊江島飛行場設定工事に従事す。十月四日名護帰隊。十月七日本部半島・真部山・崎本部地区防衛の新任務を受けて進駐す。
頁数
17
備考
整理番号:B03-5-345
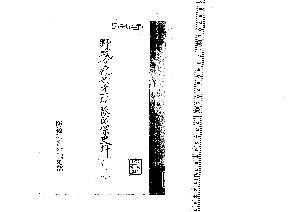
収蔵文書名
簿冊名
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
沖台 沖縄320
詳細
野戦重砲兵第一連隊関係史料 野戦重砲兵第一連隊(通称号球四四〇一部隊) 沖縄県糸満市摩文仁原野の連隊指揮班 (山根忠連隊長以下戦闘指揮班と通信班第一、第二、中間点要員真壁本部から六月十九日早朝井澗満大尉と来た数名の兵隊達)と糸満市真壁の連隊本部(経理部、兵器班、自動車班)(観測班、通信班、無線班の一部兵隊達を含む)病院壕の最後の状況 野重一連隊二大隊本部恩田上少尉摩文仁原野から 山根連隊長の最後の命令を軍司令部へ屈ける 恩田上少尉 三重県出身生存者(昭和五十二年に沖縄戦跡訪門) 現住所〒630奈良県西紀寺本町四五TEL0742(24)2705番 恩田少尉(通信掛将校)は沖縄戦も終り頃与座岳と八重瀬岳で居り米軍の進撃で摩文仁原野へ後退した。
頁数
11
備考
整理番号:B03-5-346
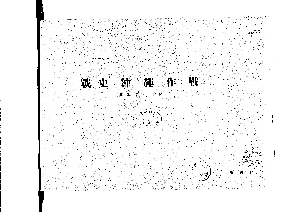
収蔵文書名
簿冊名
戦史 沖縄作戦 附図第一部 陸上自衛隊幹部学校(1) (PDF形式:4040KB)
戦史 沖縄作戦 附図第一部 陸上自衛隊幹部学校(2) (PDF形式:4091KB)
戦史 沖縄作戦 附図第一部 陸上自衛隊幹部学校(3) (PDF形式:429KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
沖台 沖縄394
詳細
戦史沖縄作戦 附図第一部 STRATEGIC SITUATION IN THE PACIFIC RYUKYU ISLANDS ISLAND OF OKINAWA THE PLAN OF ATTACK KERAMA ISLANDS TENTH ARMY ADVANCE JAPANESE DEFENSIVE POSITIONS THROUGH THE OUTPOSTS THE PINNACLE KAKAZU RIDGE
頁数
43
備考
米軍作成地図41葉
整理番号:B03-5-347
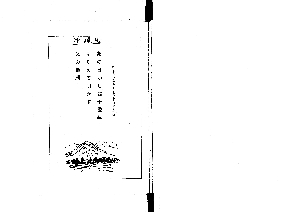
収蔵文書名
簿冊名
我が家の戦争記録(沖縄戦)平成元年9月 瀬良垣克夫(PDF形式:1054KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
沖台 沖縄398
詳細
平成元年九月 我が家の戦争記録(沖縄戦) 瀬良垣克夫 沖縄戦 《我が家の戦争記録》 あの日から四十数年はじめて明かす父の最期 終戦直後の一時期、本島の住民の殆んどが、石川、久志と田井等の周辺に集められ、羽地村は田井等市と呼ばれていた。その頃の僕は、炎天下を、羽地大川の上流にあった田井等カンパンの揚水場の前を通って、田井等の部落へ行き、知っている人はいないかと、テントの中をのぞいたり、道端に立って、ほこりをまき上げて通るトラックやジープを眺めたりするのが日課であった。たまには源河の人達が収容されていたサガヤ(伊差川の奥)まで足をのばす事もあった。その様な或る日、その日も暑い日であった。兵隊達はふだんとは様子が違い、昼間から、走っている車の上でもビール等を飲んでさわいでいた。
頁数
9
備考
整理番号:B03-5-348
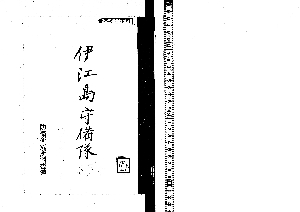
収蔵文書名
簿冊名
伊江島守備隊 児玉軍医手記(1) (PDF形式:4215KB)
伊江島守備隊 児玉軍医手記(2) (PDF形式:1328KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
沖台 沖縄401
詳細
伊江島守備隊 伊江島守備隊 序 この文書は三五頁の通り無電機が敵弾のため破壊されたことを知り、井川大隊長は軍司令部に最後の電文を準備していたがそれもできない、井川大隊長は部隊の悲壮なる奮闘を誰にも伝えられなくなった。部隊長として莞爾として死んで行く部下の心境を思いやり砲声韻々たる壕の入り口で児玉軍医に向かい最後の突撃後若しできれば本部半島に渡り連隊長に戦闘経過の報告するよう話した。 昭和二十年四月二十三日午前三時井川大隊長と諸江大尉は二隊に分れて学校前の敵陣に突入した井川大隊長は左上膊、左胸部に敵弾を受け今はこれまでと武人の最期を従容として自決した。児玉軍医は戦後別府市に復員し「伊江島守備隊」を草稿し井川義子夫人に渡したものであり、
頁数
33
備考
同B03-5-328
整理番号:B03-5-349
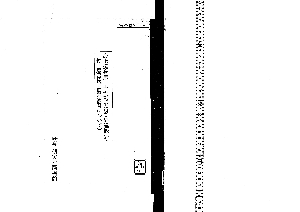
収蔵文書名
簿冊名
海上挺進第29戦隊 行動経過概要(昭和19.10~20.11)付 爆雷投下展示演習について(PDF形式:3947KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
沖台 沖縄425
詳細
海上挺身第二十九戦隊行動経過概要 (付 爆雷投下展示演習について) 海上挺進第29戦隊 (暁第19768部隊) 行動経過概要 平9,10,10 元海上挺進第29戦隊長 山本久徳 海上挺進第29戦隊 (暁第19768部隊) 行動経過概要 1編成 昭19.10.26 江田島幸ノ浦 戦隊長 人員 1 ○レ 大尉 山本久徳(54) 直轄 3 3見士×1先進隊 7 7 長 少尉 堀俊彦(慶大) 第1中隊 31 30 長 中尉 中川康敏(56) 内訳 中隊長 1 直轄 3 3 戦闘群×3 9×3 9×3 長 見士 第2中隊 第1中隊に同じ 長 少尉 重富正(57) 第3中隊 同上 長 少尉 相馬光夫 (57) 計 人員 104名 (将校 5 見習士官 10 下士官 89) ○レ 100艇
頁数
31
備考
整理番号:B03-5-350
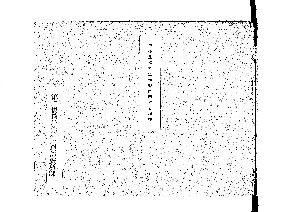
収蔵文書名
簿冊名
沖縄並に本土作戦に関する調査(1) (PDF形式:4103KB)
沖縄並に本土作戦に関する調査(2) (PDF形式:3839KB)
沖縄並に本土作戦に関する調査(3) (PDF形式:759KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
3 大東亜戦争-本土-14
詳細
沖縄並に本土作戦に関する調査 第二復員局 沖縄並に本土作戦に関する調査 第二復員局残務処理部資料課 沖縄並本土作戦に関する調査 一九四五、四、二二 藤原 被調査者及当該職責在任期間 (T)元海軍軍令部作戦部長(一九四四、一二、一以降) 海軍少将 富岡定俊 (O)〃企画班長 一九四五、一以降 作戦課長 一九四五、六 以降 海軍大佐 大前敏一 (TE)〃 航空作戦主任(一九四五、一、二五以降) 海軍中佐 寺井義守 (F)元連合艦隊航空作戦主任(一九四四、四、二一終戦迄) 海軍大佐 淵田美津雄 区分 回答者 内容 Q 捷号戦略ハ何時崩壊ヲ認識サレタカ A T 十二月十五日(一九四四年)米軍ガ「ミンドロ」ニ上陸スルニ至ツタ時ニ個人トシテハ実質的ニハ崩壊シタモノト認識シタ
頁数
25
備考
被調査者:元海軍軍令部員
整理番号:B03-5-351
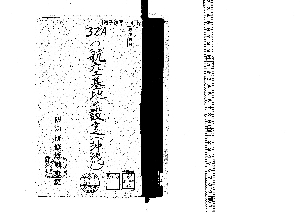
収蔵文書名
簿冊名
第32軍の航空基地の設定(沖縄)(PDF形式:3761KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
陸空 本土周辺42
詳細
32Aの航空基地の設定(沖縄) 昭和二十七年三月二十六日沖縄戦の最期 牛島 長 元大将の遺骨発堀の記事を読んで 沖縄戦の真相に就いては先に第三十二軍高級参謀の著書(沖縄戦の最期死生の門)に詳細に記述してあって両将軍の最期も手に取る如く記録されて居る亦今般両将軍の遺骨が発堀された事は悲しい中にも嬉しい知らせである 沖縄戦が第二次世界大戦の終末等を告ぐべき悲惨淒烈な戦であって亦戦略的重大使命を持つて居つた其の重任を負はされたのが牛島元大将であり其の幕僚長として七面八臂の手腕を振つたのが長元大将であつた其の作戦主任参謀として知謀を絞つたのが八原参謀である而して八原参謀の自叙伝にと比すべき「死生の門」には其の苦心の跡霊無と記述されて余す所はない
頁数
24
備考
第32軍航空主任参謀回想記録
整理番号:B03-5-352
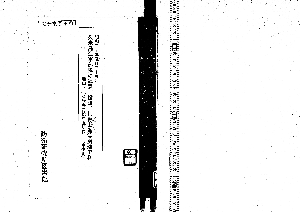
収蔵文書名
簿冊名
久米島海軍部隊の戦闘・投降・指揮官上申等関連資料(久米島特設見張所長鹿山少尉)(PDF形式:2079KB)
原本所蔵機関
防衛研究所
請求番号
4 艦船・陸上部隊-陸上部隊-47
詳細
昭和二十年及び二十五年 久米島海軍部隊の戦闘、投降、指揮官上進等関連史料 鹿山正(久米島特設見張所長 海軍少尉) 久米島陸戦隊の戦闘 二十年六月二十六日、米南西諸島攻撃団(指揮官I.N.キランド海軍少将)上陸隊第七十七師団(指揮官A.O.ブルース陸軍少将)が久米島に上陸して来た。 久米島守備兵力は電探見張所員(所長鹿山兵曹長)二十七名のみであったが、その後海軍航空隊不時着塔乗員三名、徴用員輸送任務を以て来島中の山根部隊(海軍設営隊員七名、同軍属二名)九名に加え、沖縄本島並びに慶良間列島脱出の陸軍軍人軍属(下士官兵二十名、軍属九名)二十九名を合わせ、敵上陸時の守備兵力は合計六十八名であつた。尚同島には本来陸軍部隊の配備はなかったのである。
頁数
13
備考
部分複写

