第1章 障害者に対する偏見や差別をなくすための取組について 第2節
第2節 改正障害者差別解消法の施行
2024年4月、事業者による障害者への合理的配慮の提供の義務化等を内容とする「改正障害者差別解消法」が施行された。政府では、改正法の施行を機に、相談体制の充実、事例の収集・共有の強化、周知啓発の強化等に取り組んでいる。
(1)相談体制の整備
ア 基本的な考え方
障害を理由とする差別の相談対応は、国及び地方公共団体が役割分担・連携協力し、一体となって適切な対応を図ることが重要である。また、相談対応の質の向上を図るため、相談対応等を行う人材の専門性向上が重要となる。「障害者差別解消法」に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定。以下本章では「基本方針」という。)には、相談体制について、主に以下の点を国と地方公共団体に求めている。
・相談者にとって一番身近な市区町村が基本的な窓口の役割を果たすこと
・都道府県は、市区町村への助言や広域的・専門的な事案についての支援・連携を行うとともに、必要に応じて一次的な相談窓口等の役割を担うこと
・国においては以下の対応を行うこと
① 各府省庁が所掌する分野に応じて相談対応等を行うこと
② 市区町村や都道府県のみでは対応が困難な事案について、適切な支援等を行う役割を担うこと
・内閣府においては以下の対応を行うこと
① 事業分野ごとの相談窓口の明確化を各府省庁に働きかけ、当該窓口一覧の作成・公表を行うこと
② 障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進め、どの相談窓口等においても対応されないという事案が生じることがないよう取り組むこと
③ 各相談窓口等に従事する人材の確保・育成の支援及び事例の収集・整理・提供を通じた相談窓口等の対応力の強化等にも取り組むこと
・国及び地方公共団体においては、必要な研修の実施等を通じて、相談対応を行う人材の専門性向上、相談対応業務の質向上を図ること
イ 相談窓口の設置
市町村や都道府県においては、住民や事業者等のため、相談窓口を設置している。約10年の間で増加傾向にあるが、2024年4月現在、全体で約5割の設置2となっている。地方公共団体別にみると、都道府県では約8割の自治体で設置されている一方、市町村においては約5割の設置と、市町村での相談窓口の設置が課題となっている。国においては、後述のマニュアルの作成やブロック研修会などを通じて、相談窓口の設置に向けた支援を行っている。
また、国においては、各事業分野における国の相談窓口について、整理・一覧化し、「事業分野相談窓口(対応指針関係)」として、内閣府ホームページに公表している。
ウ 相談窓口試行事業「つなぐ窓口」
障害を理由とする差別の相談がどの相談窓口においても対応されないことのないよう、内閣府では国の相談窓口として「つなぐ窓口」を試行的に設置した。この窓口は、2023年10月から2025年3月まで、障害のある人や事業者、都道府県・市区町村等からの障害者差別に関する相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担ってきた。
試行期間(2023年10月から2025年3月)中に4,602件3の相談が寄せられ、そのうち半数近くが「障害者差別解消法」に係るものであった。このうち、相談者の意向も踏まえて自治体等へ取り次いだ件数は551件である。
相談件数を、障害種別に見ると、精神障害が最多で3割近くを占めている。次いで肢体不自由、発達障害となっている。また、相談事案の相手方の業種は、行政が最多で約2割、次いで医療・福祉、教育・学習支援となった。
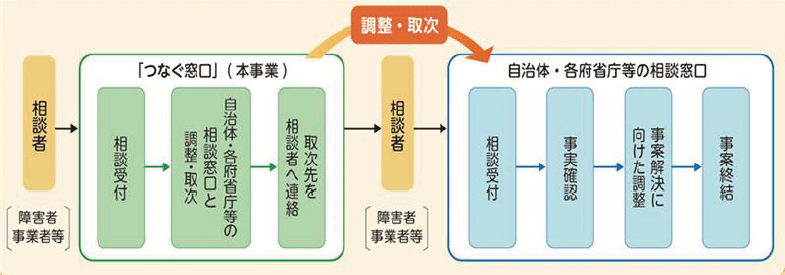
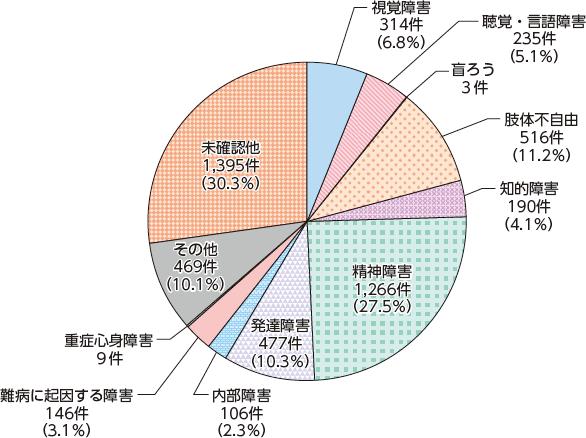
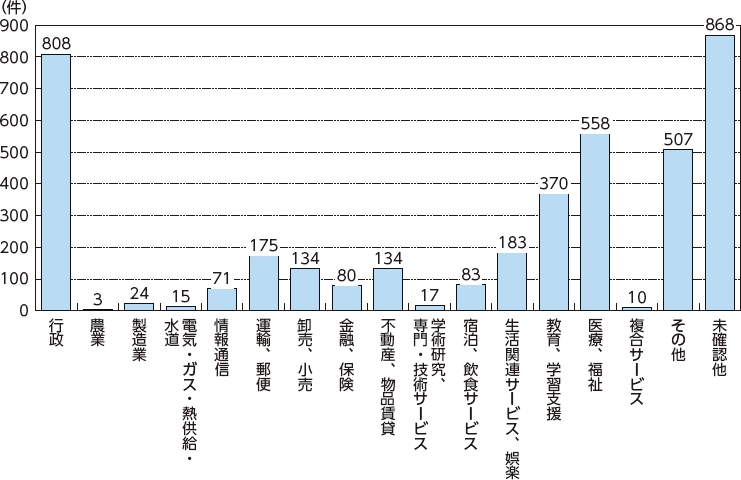
また、月別にみると、2024年4月の「改正障害者差別解消法」の施行前後で件数が大きく上昇しており、特に施行直前の3月から、施行直後の5月において大幅に増加している。相談者については、おおむねいずれの月も、障害のある人からが約8割、事業者が約1割、地方公共団体その他が約1割となっている。
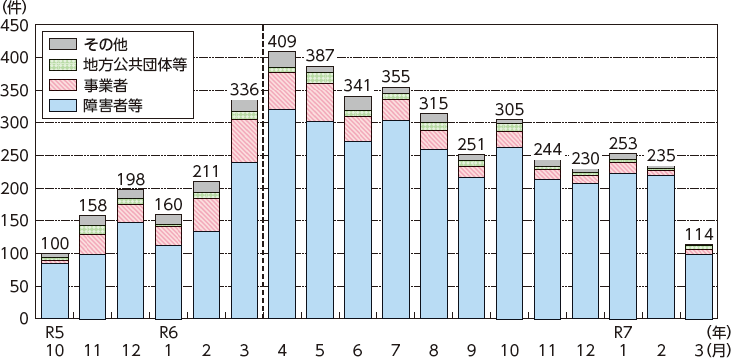
「つなぐ窓口」については試行段階を経て、2025年度においても継続して実施することとしている。障害のある人の差別の相談に適切に対応できるよう、更なる充実を図ることとしている。
エ 人材の確保・育成
地方公共団体等の人材育成に向け、内閣府においては、「障害を理由とする差別の解消の推進 国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル」を2023年度に作成している。同マニュアルは、実践編と法令編の二部構成であり、実践編には、関係機関の役割、相談対応の一連の流れや留意事項等の適切な相談対応に資する情報が記載されている。2024年度は、地方公共団体へのヒアリングを実施し内容の充実を図った。具体的には、相談窓口に初めて配属された職員にも活用できるよう、概要版や動画版を作成するとともに、相談に当たっての心構えや複数の自治体が関係する場合の基本的対応を記載するなど充実させた。
内閣府においては、この相談対応マニュアル(概要版・動画版)について、各省庁や地方公共団体に通知するとともに、内閣府ホームページに掲載するなど周知を図ることとしている。
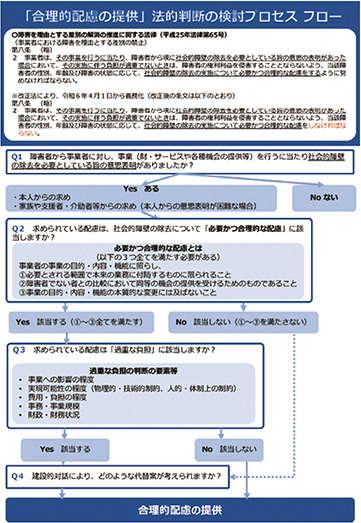
資料:内閣府
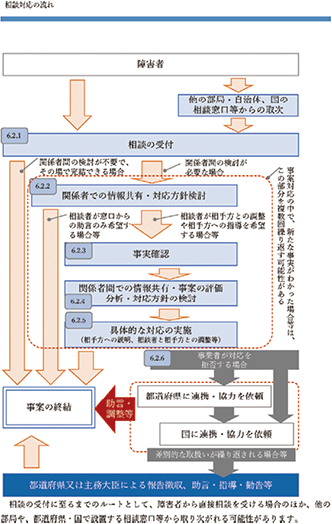
資料:内閣府
オ 障害者差別解消支援地域協議会の設置の促進
障害のある人や事業者からの相談等には、当事者や行政の相談窓口だけではなく、関係機関で連携して対応することが必要なケースもある。このため、「障害者差別解消法」では、国及び地方公共団体の機関は、「障害者差別解消支援地域協議会」(以下本章では「地域協議会」という。)を組織することができるとしている。「地域協議会」においては、地域の関係機関による相談事例等に係る情報の共有・協議を通じ、各自の役割に応じた事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークを構築することとしている。「地域協議会」の構成機関が連携し、効果的な対応や紛争解決の後押しが可能となり、地域の対応力の向上が期待される。
「地域協議会」においては、情報やノウハウを共有し、関係者が一体となって事案に取り組む観点から、鉄道会社や経営者協会などの地域の事業者や事業者団体も参画している例もある。また、「地域協議会」の単独設置が困難な場合等には、必要に応じて圏域単位など複数の市区町村による「地域協議会」の共同設置・運営や、他の協議会等との一体的な運営などが行われている市町村等もある4。
地方公共団体の「地域協議会」の設置率は増加傾向にあり、2024年4月1日現在、都道府県及び指定都市においては全て、中核市等(中核市、特別区及び県庁所在地の市(指定都市を除く。))においては約9割が設置済みである。一方、一般市(指定都市及び中核市等以外の市)では7割程度、町村においては5割程度と、一般市や町村における設置率が低い傾向にある。この背景には、人員や知識及びスキルの不足などがあげられている。このため、各地域で「地域協議会」の設置や活性化に向けた的確な助言等ができる人材育成等を図ることを目的とした研修会を開催しており、2024年度は4ブロック(北海道・東北、関東甲信越、東海北陸・近畿、中国四国・九州・沖縄)で開催し、200名近い職員等が参加した。
| 選択肢 | 合計 | 類型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 指定都市 | 中核市等 | 一般市 | 町村 | ||
| 設置済み | 1,190 | 47 | 20 | 78 | 529 | 516 |
| 設置予定 | 81 | - | - | 1 | 18 | 62 |
| 設置しない | 517 | - | - | 10 | 159 | 348 |
| 計 | 1,788 | 47 | 20 | 89 | 706 | 926 |
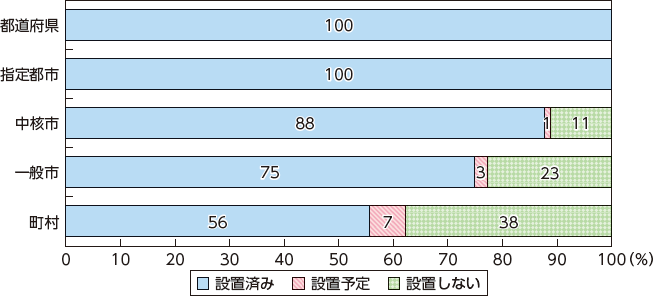
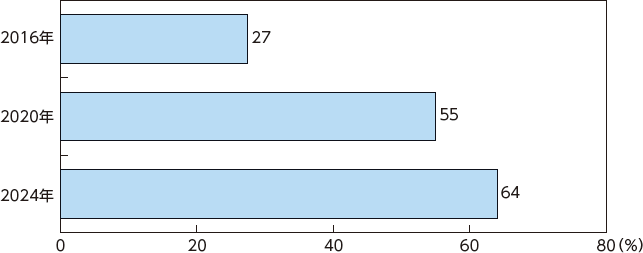
(2)障害者の差別解消に向けたその他の取組等
ア 周知・啓発
「障害者差別解消法」について、内閣府では、以下のような周知・啓発活動に取り組んでおり、これらの活用を通じて、合理的配慮の提供を始めとする障害者差別の解消に向けた取組の裾野が更に広がるとともに、同法に対する国民の理解が一層深まることが期待される。
① 事業者等への普及・啓発

・「改正障害者差別解消法」の施行を受けて、事業者を対象に、同法の説明や有識者による講演を内容とするオンライン説明会を2024年6月に合計6回実施した。
・事業者団体、障害者団体等が主催する講演会等において、「改正障害者差別解消法」の説明・周知を実施した。2024年度は合計10回以上対応した。
② 地方公共団体職員への啓発
「障害者差別解消支援地域協議会に係る体制整備・強化ブロック研修会」において、地方公共団体職員等を対象に、「改正障害者差別解消法」の説明、有識者による講演、グループディスカッションを実施した。
③ 国民全体への普及啓発
・企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市区町村などの行政機関等における「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、「障害者差別解消法」により定められている事項について一層の広報啓発を推進することを目的として、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を2022年3月に公開した。同サイト上では、検索機能を持つ「障害者差別解消に関する事例データベース」も公開し、随時事例を掲載した。また、政府広報とも連携し、合理的配慮の提供に関する周知・広報を実施した。
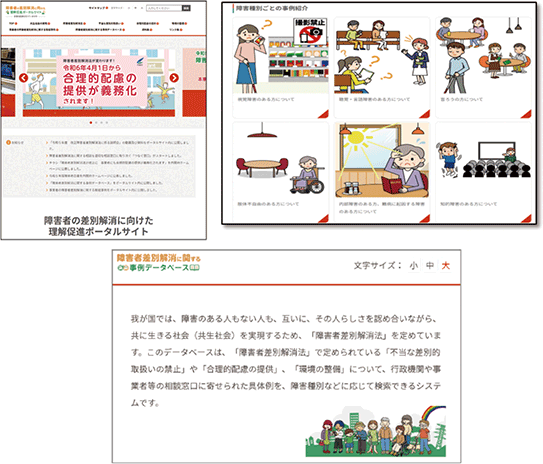
・「改正障害者差別解消法」や「つなぐ窓口」に関するリーフレットやチラシを制作し、内閣府ホームページに掲載。音声コードの付与、大活字版の制作、テキストデータの提供など、多様な利用者に配慮した情報保障を実施した。
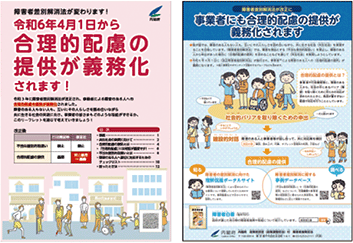
イ 主務大臣等による行政措置
事業者における障害者差別解消に向けた取組は、主務大臣の定める対応指針を参考にして、各事業者により自主的に取組が行われることが期待される。
しかしながら、事業者による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難である場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣又は地方公共団体の長等は、事業者に対し、行政措置を講ずることができるとされている。
G7包摂と障害に関する担当大臣会合(G7 Ministerial meeting on Inclusion and Disability)は、G7サミットに合わせて、G7・EUの障害者施策を担当する閣僚が一堂に会して開催される「関係閣僚会合」の一つである。
初開催となる2024年は、10月14日~17日の日程で、イタリア・ウンブリア州のアッシジ及びソルファニャーノ城等にて、歓迎式典、パネルディスカッション、閣僚会合、署名式等が実施されるとともに、最終日にはローマ教皇庁においてローマ教皇への特別謁見が行われた。
我が国からは三原じゅん子内閣府特命担当大臣(共生・共助担当)が出席し、パネルディスカッションや閣僚会合等において、過去、旧優生保護法に基づき不妊手術、人工妊娠中絶等が強制されていた事実を真摯に反省し、障害のある方に対する偏見や差別の根絶に向け強い覚悟で取り組むことを強調した。また、G7各国の閣僚等に、東京2025デフリンピックのバッジを配布しつつ、デフリンピックを国内外で広めていただくよう呼びかけた。さらに、障害当事者の方々の意見を伺いながら、共生社会を目指して施策を推進することを強調した。
パネルディスカッションにおいては、各国の専門家が登壇し、「普遍的なアクセシビリティと緊急事態の予防・管理」「自立した生活と労働の包摂」「人工知能」「すべての人のためのスポーツとサービス」のテーマで議論が行われた。我が国からは、障害当事者の有識者として、障害者政策委員会前委員長の石川准氏、日本障害フォーラム(JDF)政策委員長の田中伸明氏、同政策委員の南由美子氏が出席し、議論に参画した。
10月16日には、本担当大臣会合の成果文書として「ソルファニャーノ憲章」(Solfagnano Charter)を採択した。本憲章は、「アクセシビリティ」「自立した生活」「労働の包摂」「新技術の推進」など8章で構成されている。障害のある方の権利をあらゆる政治的アジェンダに取り込むとともに、障害のある方の意見を政策決定に積極的に反映する重要性を強調している(詳細は参考3参照)。
(参考1)主要日程
10月14日(月)歓迎式典 (アッシジ・聖フランチェスコ聖堂前広場)
10月15日(火)閣僚・有識者によるパネルディスカッション (ソルファニャーノ城)
10月16日(水)閣僚会合、署名式、共同記者会見 (ソルファニャーノ城)
10月17日(木)ローマ教皇謁見 (バチカン・ローマ教皇庁)
(参考2)参加閣僚等
(イタリア)アレッサンドラ・ロカテッリ 障害者担当大臣
(カナダ)カマル・ケラ 多様性・包摂・障害者担当大臣
(フランス)シャルロット・パルマンティエ=ルコク 障害者担当大臣
(米国)サラ・ミンカラ 国務省国際障害者権利担当特別補佐官
(英国)スティーブン・ティムズ 社会保障・障害者担当閣外大臣
(ドイツ)ケルシュタイン・グリーゼ 労働・社会問題省政務次官
(日本)三原 じゅん子 内閣府特命担当大臣(共生・共助担当)
(EU)ヘレナ・ダッリ 欧州委員(機会均等担当)
(ケニア)アルフレッド・ムトゥア 労働・社会保護大臣
(南アフリカ)シンディシウェ・チクンガ 女性・若者・障害者大臣
(チュニジア)イッサーム・ラフマル 社会問題大臣
(ベトナム)グェン・ヴァン・ホイ 労働・傷病兵・社会省次官
(参考3)「ソルファニャーノ憲章」概要
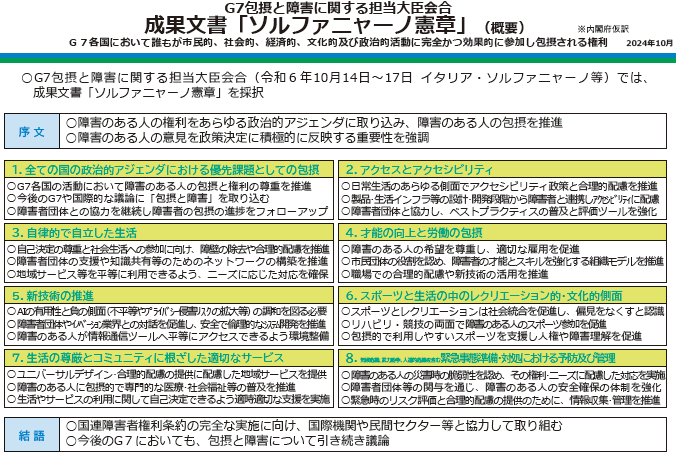
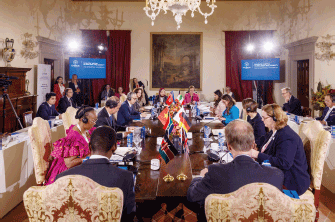



2 障害者差別に関する相談を一元的に受け付ける窓口(ワンストップ相談窓口)を設置又は定めている自治体の割合。
3 実績の集計値は、速報値。
4 埼玉県蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町及び杉戸町においては、「地域協議会」を共同で設置し、輪番で運営している。なお、同協議会は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく「(自立支援)協議会」の部会を兼ねており、これらの事務局は、幹事市町と基幹相談支援センターが担っている。

