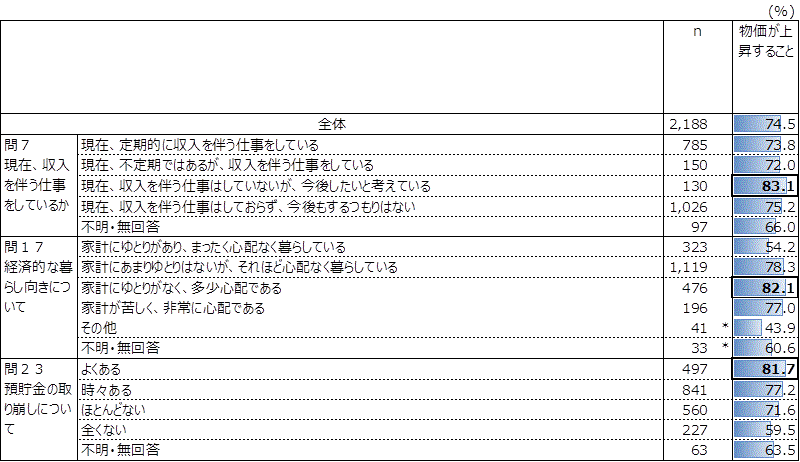現在の経済的な暮らし向きをみると、全体で「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」を合わせた「心配なく暮らしている(再掲)」が65.9%となっている。全体で「家計にゆとりがなく、多少心配である」と「家計が苦しく、非常に心配である」を合わせた「心配である(再掲)」が30.7%となっている。
第2章 調査結果の概要 -3
3.経済的な暮らし向きについて
(1)現在の経済的な暮らし向きについて(問17)
問17 あなたは、ご自分の現在の経済的な暮らし向きについてどのようにお考えですか。次の中から1つ選んでお答えください。配偶者あるいはパートナーと一緒に暮らしている方は、お二人の状況についてお答えください。(○は1つだけ)
図表2-3-1-1 現在の経済的な暮らし向きについて(問17)(択一回答)(CSV形式:1KB)
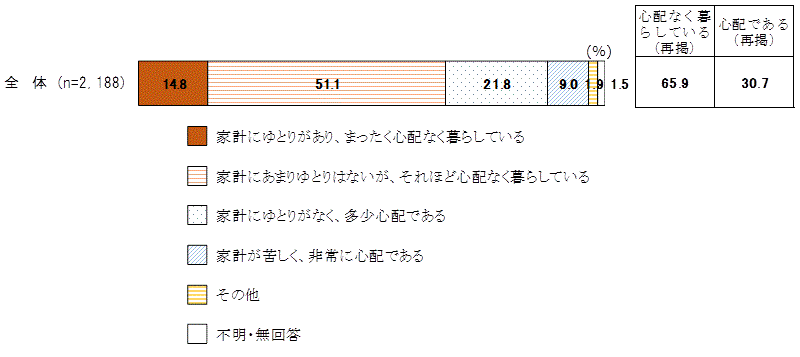
※ 「心配なく暮らしている(再掲)」は「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の合計、「心配である(再掲)」は「家計にゆとりがなく、多少心配である」と「家計が苦しく、非常に心配である」の合計。
性・年齢でみると、女性の80~84歳は「心配である(再掲)」(42.1%)が高い。
現在の結婚状況でみると、「心配なく暮らしている(再掲)」は現在、配偶者あるいはパートナーがいる者で7割と高いが、配偶者あるいはパートナーとは離別している者では4割程度で低い。
同居者でみると、同居者はいない者は「心配である(再掲)」(41.5%)が高い。一方、配偶者あるいはパートナーと同居している者と親と同居している者は「心配なく暮らしている(再掲)」(それぞれ71.9%、74.1%)が高い。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、ネットショッピング等の利用頻度が高いほど「心配なく暮らしている(再掲)」が高くなっている。
地域(6区分)でみると、北海道・東北は「心配である(再掲)」(41.2%)が高く、中国・四国は「心配なく暮らしている(再掲)」(71.9%)が高い。
図表2-3-1-2 現在の経済的な暮らし向きについて(問17)(択一回答)(CSV形式:5KB)
※ 「心配なく暮らしている(再掲)」は家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」の合計、「心配である(再掲)」は「家計にゆとりがなく、多少心配である」と「家計が苦しく、非常に心配である」の合計。
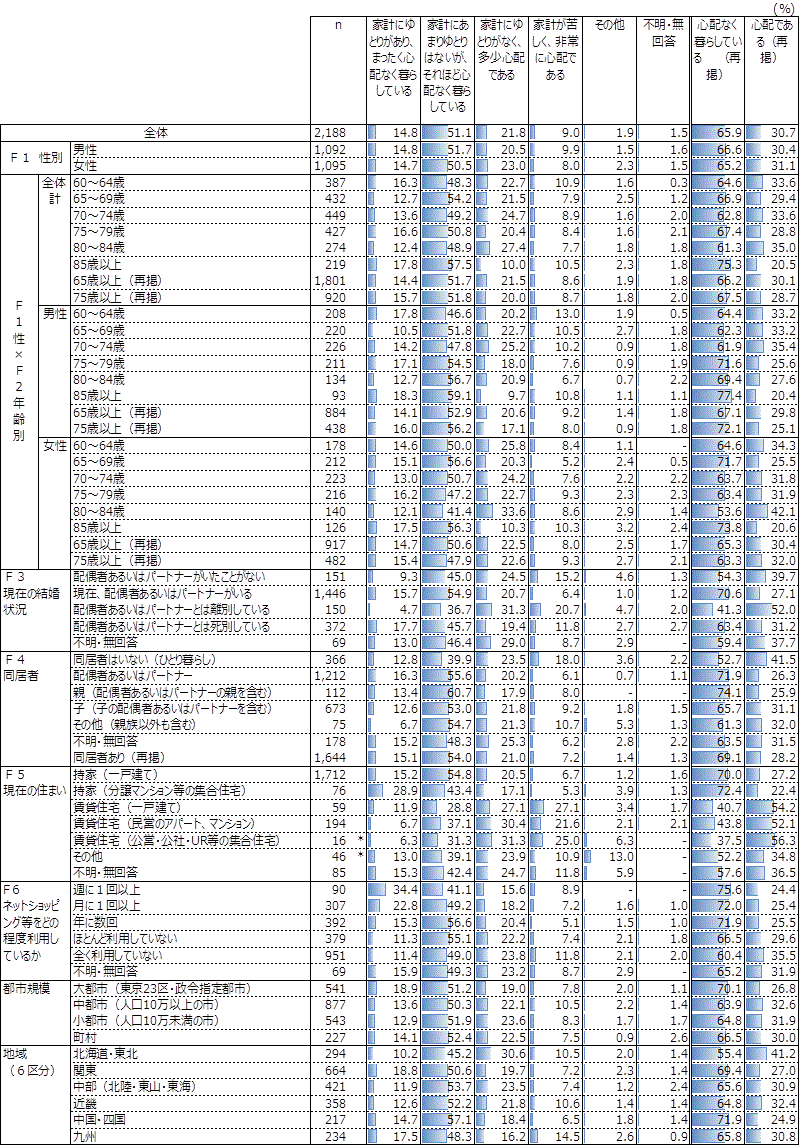
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「心配なく暮らしている(再掲)」は、『生きがいを感じるか(問1)で「十分感じている」と答えた者』、『現在の健康状態(問2)で「良い」と答えた者』、『現在の収入を伴う仕事に満足しているか(問11)で「満足している」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「自分の知識・能力を生かせるから」と答えた者』、『預貯金の取り崩しについて(問23)で「ほとんどない」、「全くない」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-1-3 現在の経済的な暮らし向きについて(問17)(択一回答)(CSV形式:2KB)
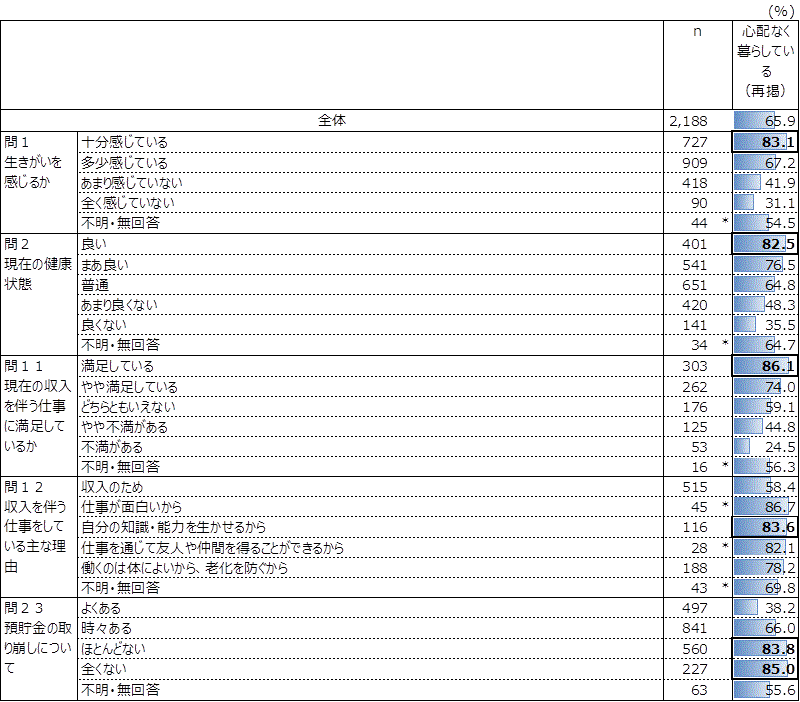
(2)現在の収入源について(問18)
問18 あなたの現在の収入について、次の中からあてはまるものを全てお答えください。配偶者あるいはパートナーと一緒に暮らしている方は、お二人の状況についてお答えください。(〇はいくつでも)
現在の収入源をみると、全体で「公的年金」が最も高く75.7%となっている。次いで、「仕事による収入」(44.6%)、「企業年金、個人年金等」(23.3%)が続く。
図表2-3-2-1 現在の収入源について(問18)(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「その他」「収入はない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
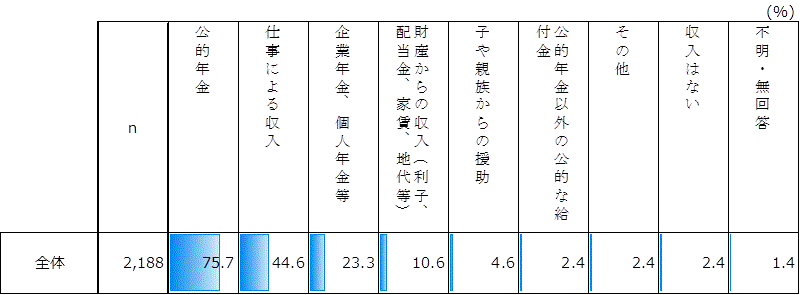
性・年齢でみると、「仕事による収入」は男性の64歳までは86.1%で高い。
現在の結婚状況でみると、配偶者あるいはパートナーとは死別している者は「公的年金」(84.7%)が高く、「仕事による収入」(20.2%)が低い。
同居者でみると、親と同居している者は「公的年金」(48.2%)が低く、「仕事による収入」(75.9%)が高い。
現在の住まいでみると、持家(一戸建て)は「公的年金」(79.0%)が高く、賃貸住宅(民営のアパート、マンション)は「公的年金」(57.2%)が低い。
都市規模でみると、都市規模が小さくなるほど「公的年金」は高くなる。
図表2-3-2-2 現在の収入源について(問18)(複数回答)(CSV形式:5KB)
※「その他」「収入はない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
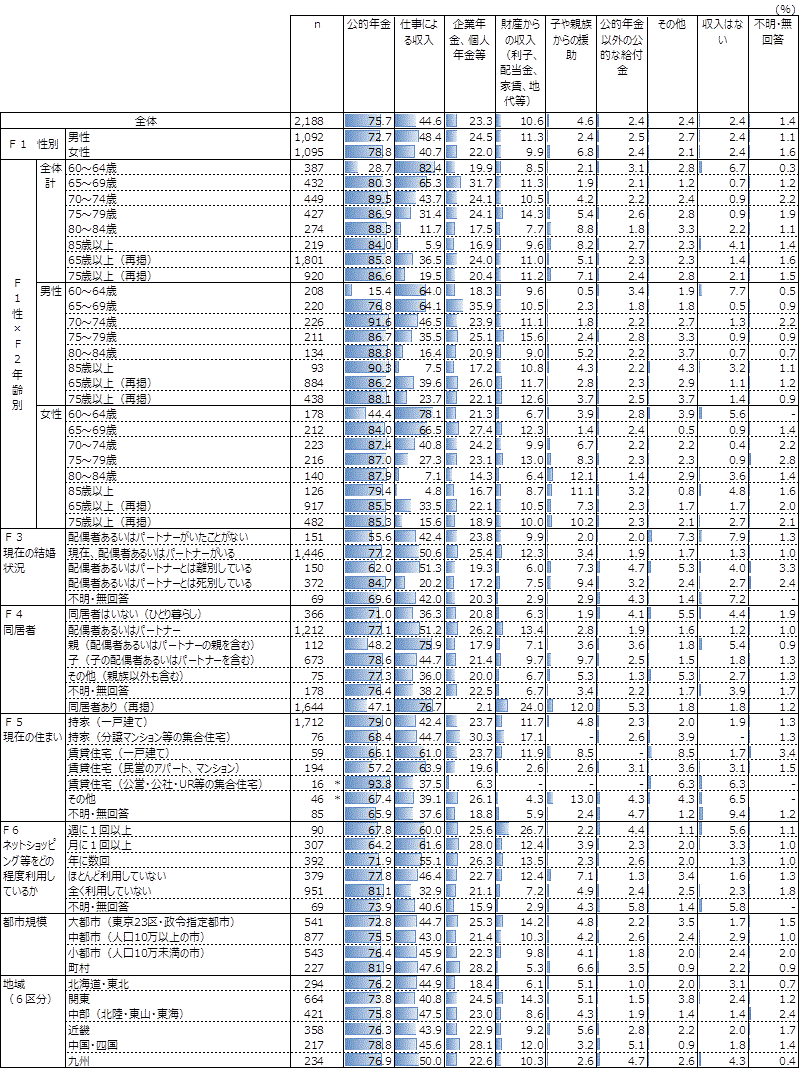
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「公的年金」は、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「働くのは体によいから、老化を防ぐから」と答えた者』、『何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか(問16)で「80歳くらいまで」、「仕事をしたいとは思わない」と答えた者』、『認知機能の低下に伴う財産管理について(問35)で「子や他の親族に財産管理を委ねる」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-2-3 現在の収入源について(問18)(複数回答)(CSV形式:2KB)
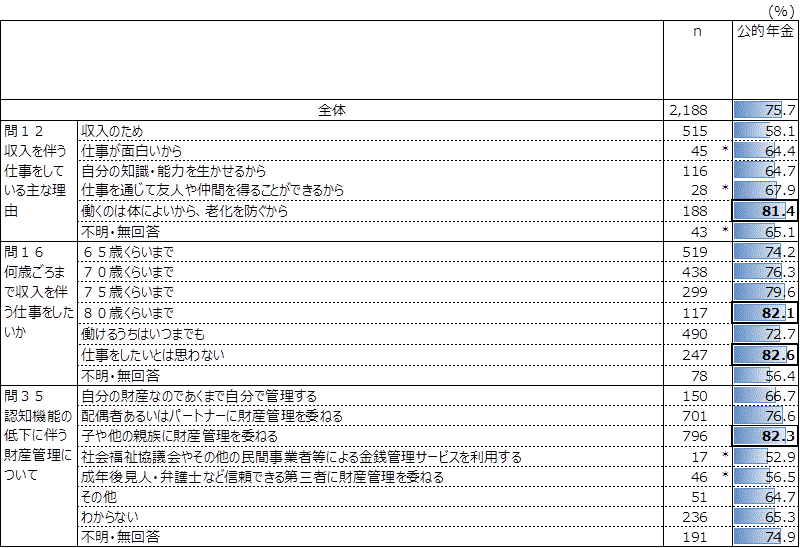
(3)1か月あたりの平均収入額(1年間の収入額)(問19)
問19 あなたの現在の仕事・年金による収入を全て合計すると、税込みで1か月当たりおよそいくらくらいになりますか(ボーナスも含みます)。1か月当たりの収入額又は1年間の収入額でお答えください。配偶者あるいはパートナーと一緒に暮らしている方は、お二人の状況についてお答えください。
1か月当たりの収入額はおよそ______万円
又は
1年間の収入額はおよそ______万円
1か月あたりの平均収入額(1年間の収入額)をみると、「30万円~40万円未満(年額では360万円~480万円未満)」(15.0%)が最も高く、平均年収は340万円となっている。
図表2-3-3-1 1か月あたりの平均収入額(1年間の収入額)(問19)(CSV形式:1KB)
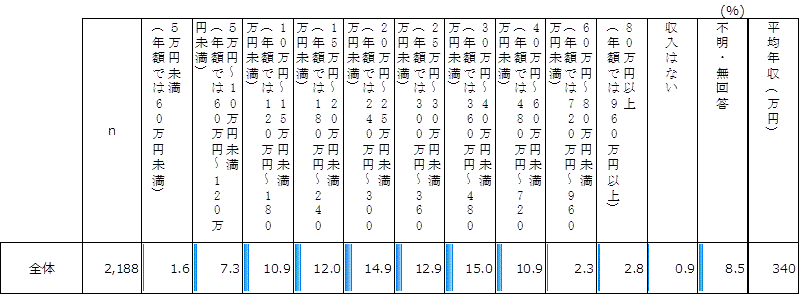
※月収と年収の両方に回答があるもの場合、年収の回答を優先とした。
性別にみると、平均年収は男性が383万円、女性が297万円となっている。
年齢でみると、年齢が高くなるほど平均年収は低くなる傾向にある。
同居者でみると、平均年収は同居者はいない者は232万円、同居者がいる者は366万円となっている。
都市規模でみると、町村(313万円)、小都市(319万円)、中都市(335万円)、大都市(382万円)と都市規模が大きいほど平均年収は高くなる。
図表2-3-3-2 1か月あたりの平均収入額(1年間の収入額)(問19)(CSV形式:6KB)
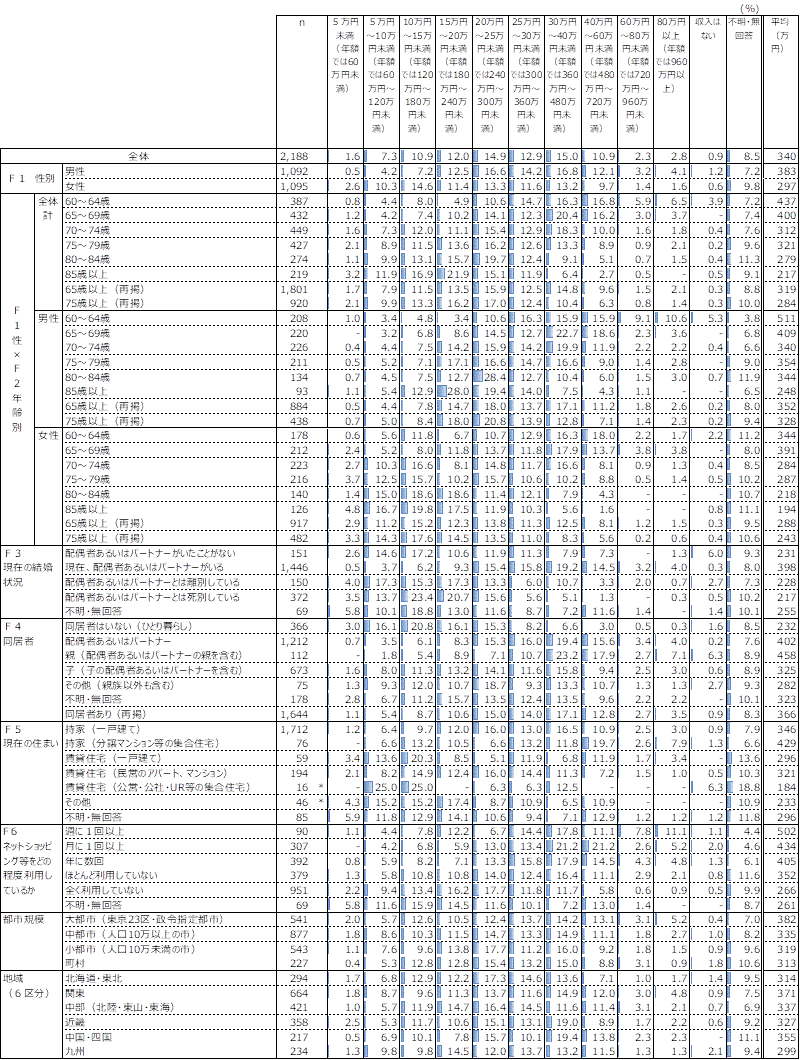
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、平均年収は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)」と答えた者』、『現在の収入を伴う仕事に満足しているか(問11)で「満足している」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「自分の知識・能力を生かせるから」と答えた者』、『金融資産の総額について(問30)で3,000万円以上と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-3-3 1か月あたりの平均収入額(1年間の収入額)(問19)(CSV形式:2KB)
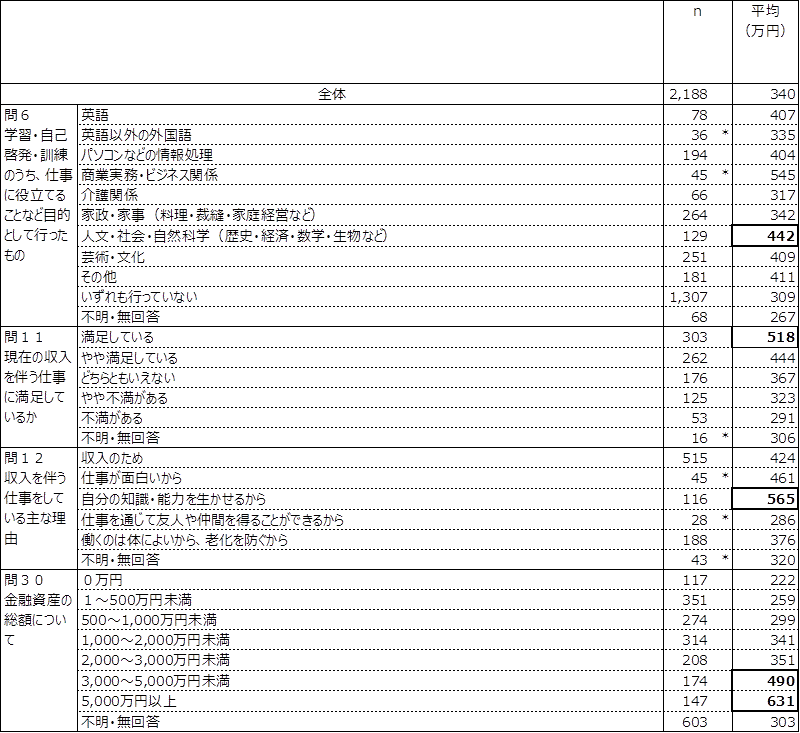
(4)1か月あたりの生活費(問20)
問20 現在の生活費(※)を全て合計すると、1か月当たりおよそいくらくらいになりますか。配偶者あるいはパートナーと一緒に暮らしている方は、お二人の状況についてお答えください。
※食費、住宅の設備修繕・維持費、光熱・水道費、家具・家事用品費、被服及び履物費、保健医療費、交通・通信費、教育費、教養娯楽費など。家賃や住宅ローンは含めないでください。
※子や親などその他家族と一緒に暮らしている場合は、世帯全体の生活費をお住まいの人数で割って、1人分又は配偶者あるいはパートナーを含めた2人分を記入してください。
1か月あたりの生活費をみると、平均で20.6万円となっている。最も高いのは「20~25万円未満」(19.4%)。次いで、「30万円以上」(19.1%)、「15~20万円未満」(14.9%)が続く。
図表2-3-4-1 1か月あたりの生活費(問20)(CSV形式:1KB)
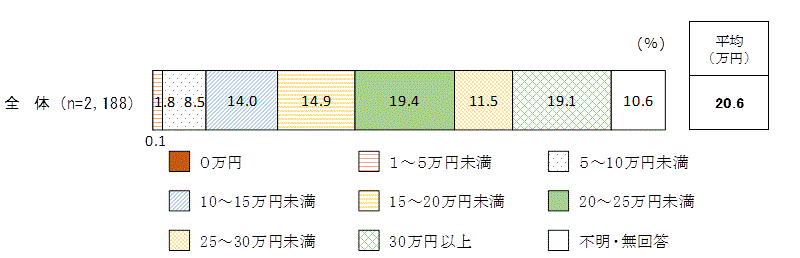
性別でみると、平均は男性(22.4万円)が女性(18.9万円)よりも高い。
性・年齢でみると、平均は男性の64歳までが24.0万円で最も高く、女性の85歳以上が14.0万円で最も低くなっている。
同居者でみると、平均は同居者はいない者が13.9万円、同居者がいる者が22.1万円となっている。
都市規模でみると、平均は町村(19.6万円)、小都市(19.7万円)、中都市(20.3万円)、大都市(22.5万円)と、都市規模が大きいほど1か月あたりの生活費は高くなる。
図表2-3-4-2 1か月あたりの生活費(問20)(CSV形式:5KB)
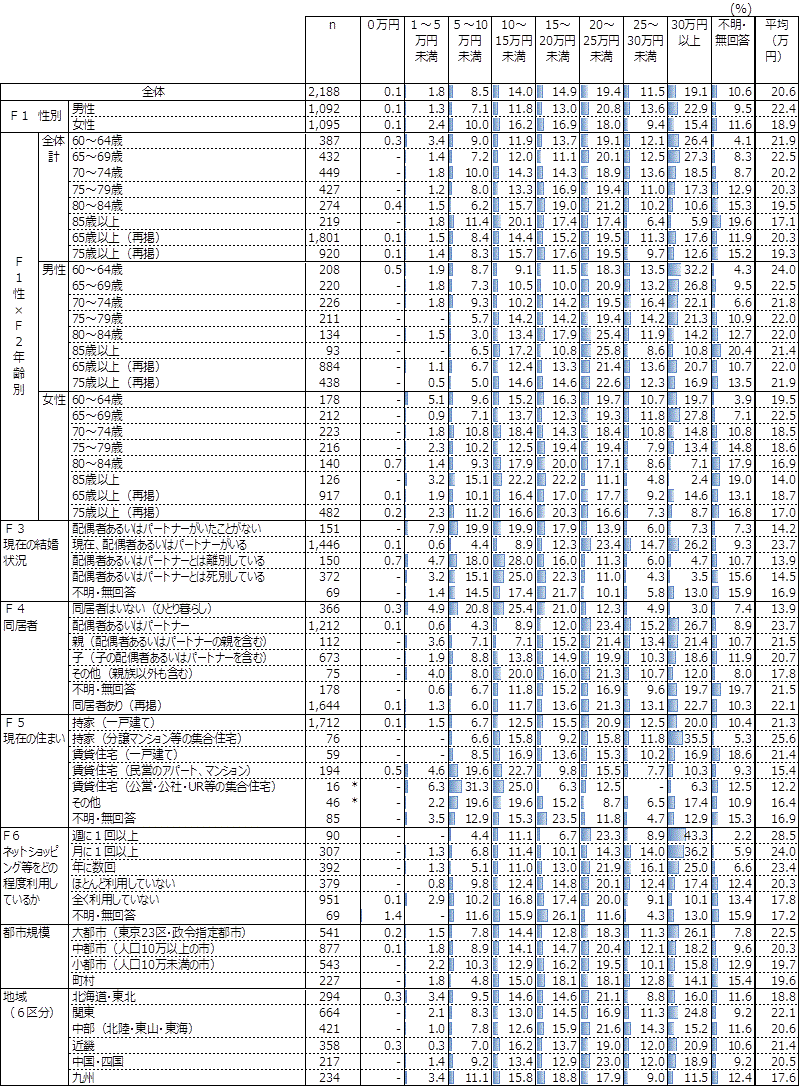
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「30万円以上」は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「自分の知識・能力を生かせるから」と答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-4-3 1か月あたりの生活費(問20)(CSV形式:2KB)
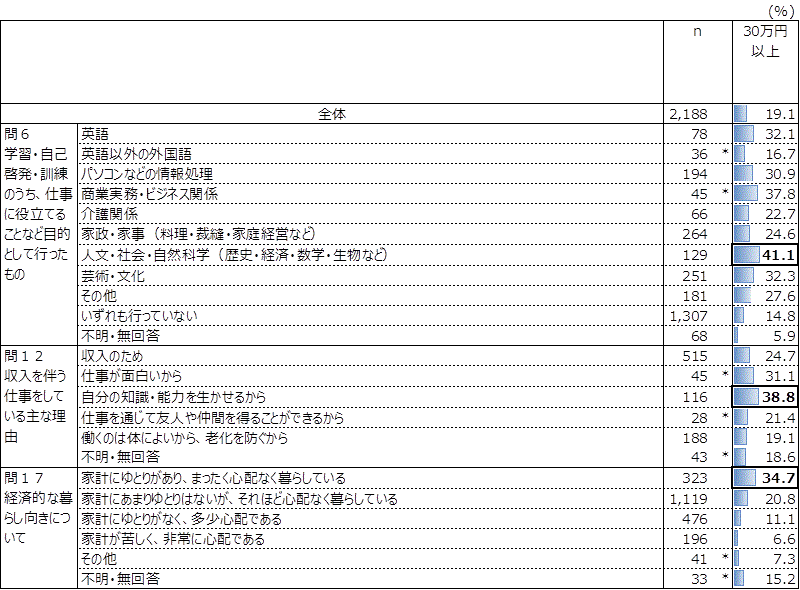
(5)無理なく生活するために必要な生活費(問21)
問21 無理なく生活するために必要な1か月あたりの生活費(※)はいくらくらいだと考えていますか。配偶者あるいはパートナーと一緒に暮らしている方は、お二人分の金額をお答えください。
※食費、住宅の設備修繕・維持費、光熱・水道費、家具・家事用品費、被服及び履物費、保健医療費、交通・通信費、教育費、教養娯楽費など。家賃や住宅ローンは含めないでください。
※子や親などその他家族と一緒に暮らしている場合は、必要と考える世帯全体の生活費をお住まいの人数で割って、1人分又は配偶者あるいはパートナーを含めた2人分を記入してください。
無理なく生活するために必要な生活費をみると、平均で24.8万円となっている。最も高いのは「30万円以上」(32.0%)。次いで、「20~25万円未満」(17.4%)、「25~30万円未満」(14.9%)が続く。
図表2-3-5-1 無理なく生活するために必要な生活費(問21)(CSV形式:1KB)
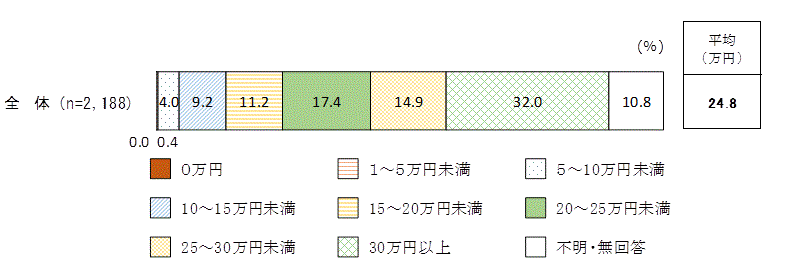
性・年齢でみると、女性では年齢が高くなるほど平均が低くなる傾向にある。
同居者でみると、平均は同居者はいない者が17.5万円、同居者がいる者が26.4万円となっている。
都市規模でみると、平均は町村(23.4万円)、小都市(23.9万円)、中都市(24.7万円)、大都市(26.3万円)と、都市規模が大きいほど1か月あたりの生活費は高くなる。
図表2-3-5-2 無理なく生活するために必要な生活費(問21)(CSV形式:5KB)
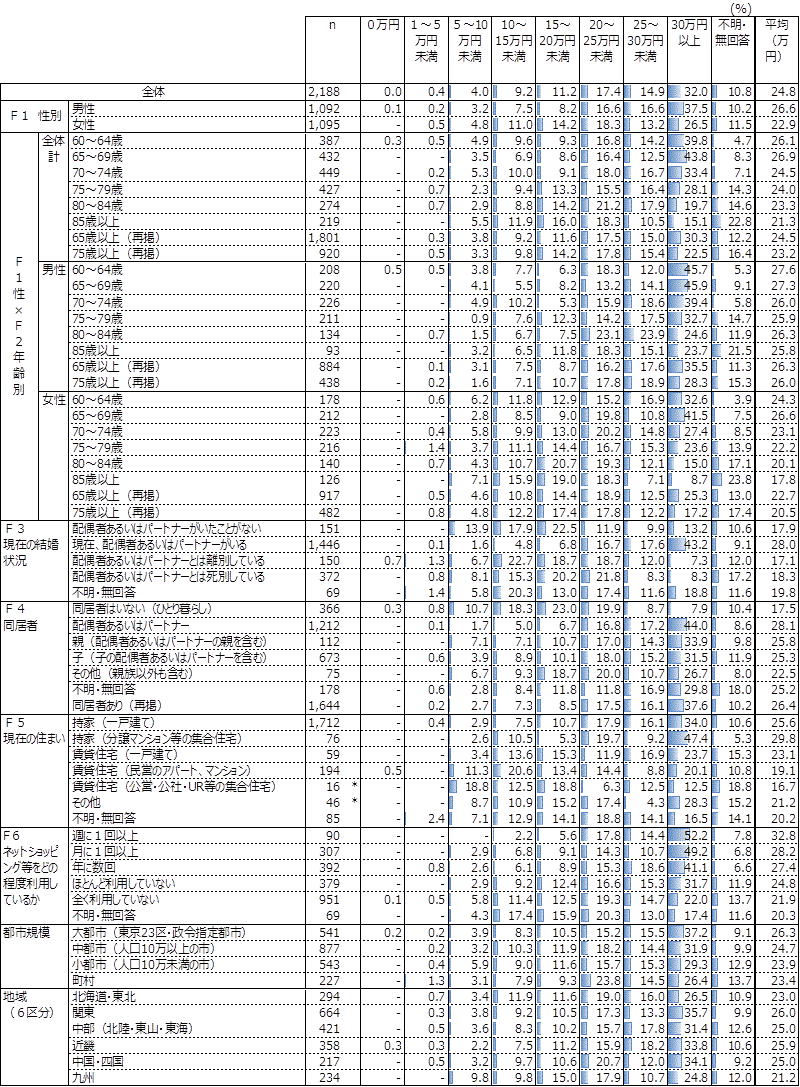
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「30万円以上」は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「自分の知識・能力を生かせるから」と答えた者』、『金融資産の総額について(問30)で「5,000万円以上」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-5-3 無理なく生活するために必要な生活費(問21)(CSV形式:2KB)
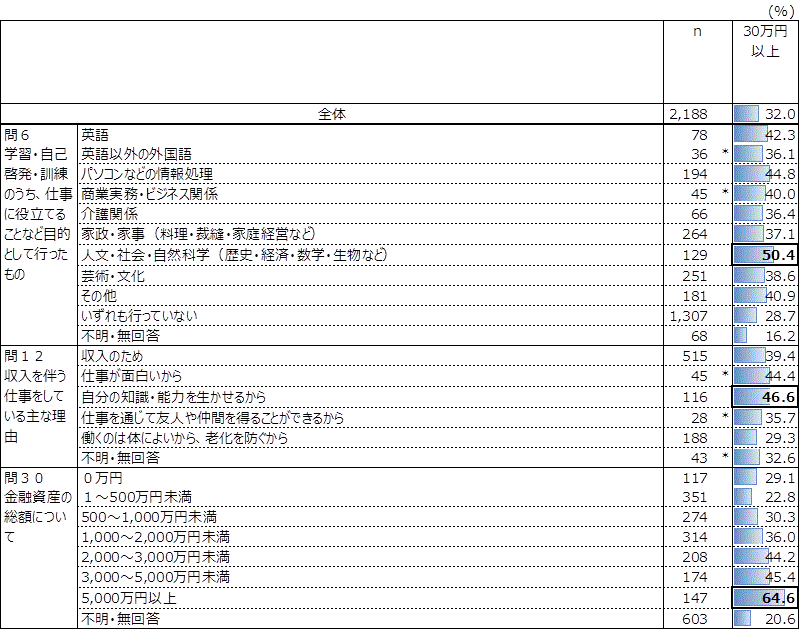
(6)子や孫の生活費負担について(問22)
問22 あなたは、同居、別居にかかわらず、お子さんやお孫さん(それぞれの配偶者あるいはパートナーを含む)の生活費を負担していますか。次の中から1つ選んでお答えください。配偶者あるいはパートナーと暮らしている場合には、配偶者またはパートナーが負担している場合も含みます。(○は1つだけ)
子や孫の生活費負担をみると、全体で「子や孫の生活費をほとんど負担している」と「子や孫の生活費の一部を負担している」を合わせた「負担している(再掲)」が25.2%となっている。
図表2-3-6-1 子や孫の生活費負担について(問22)(択一回答)(CSV形式:1KB)
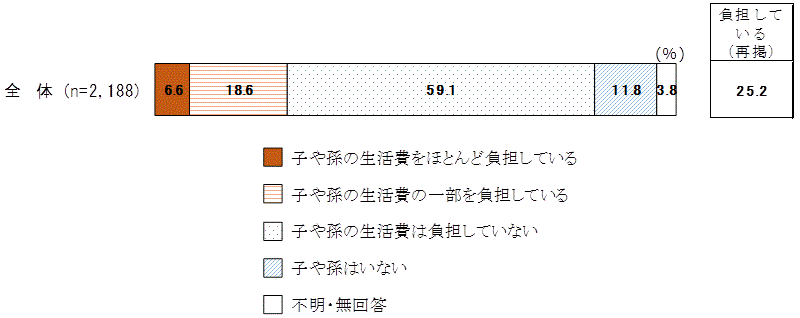
※ 「負担している(再掲)」は「子や孫の生活費をほとんど負担している」と「子や孫の生活費の一部を負担している」の合計。
性・年齢でみると、「負担している(再掲)」は男性の69歳までと女性の64歳までで3割台となっている。年齢が高くなるほど「子や孫の生活費は負担していない」は高くなる傾向となっている。
同居者でみると、配偶者あるいはパートナーと暮らしている者は「子や孫の生活費は負担していない」(64.8%)が高く、子と同居している者は「負担している(再掲)」(49.8%)が高い。
現在の住まいでみると、持家(一戸建て)と持家(分譲マンション等の集合住宅)は「子や孫の生活費は負担していない」が6割となっている。
地域(6区分)でみると、中部(北陸・東山・東海)は「負担している(再掲)」(33.3%)が高い。
図表2-3-6-2 子や孫の生活費負担について(問22)(択一回答)(CSV形式:4KB)
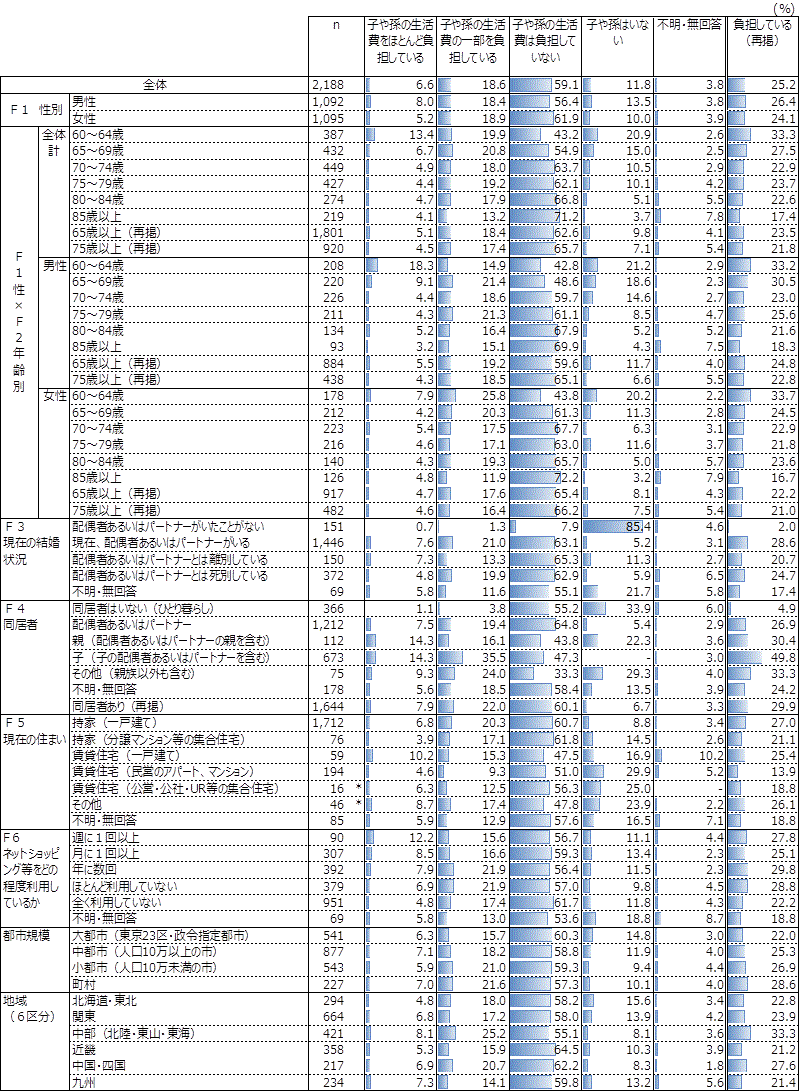
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「子や孫の生活費は負担していない」は、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と答えた者』、『預貯金の取り崩しについて(問23)で「全くない」と答えた者』、『認知機能の低下に伴う財産管理について(問35)で「配偶者あるいはパートナーに財産管理を委ねる」、「子や他の親族に財産管理を委ねる」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-6-3 子や孫の生活費負担について(問22)(択一回答)(CSV形式:1KB)
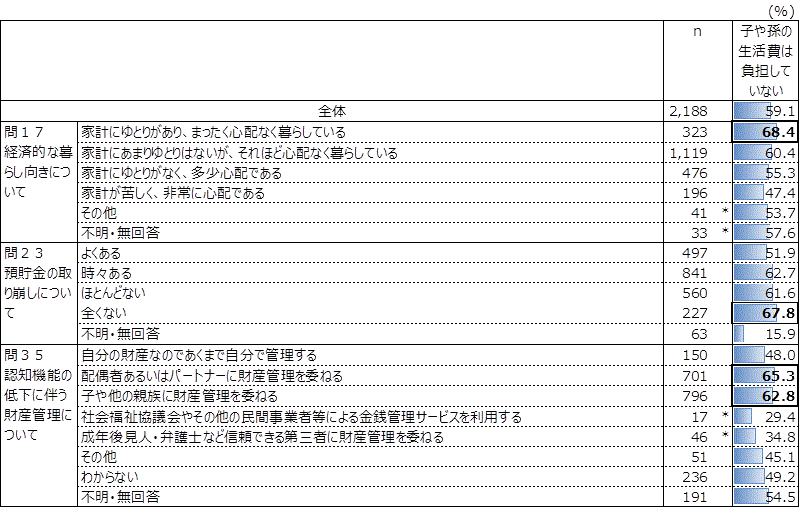
(7)預貯金の取り崩しについて(問23)
問23 日常生活の支出の中で、収入より支出が多くなり、これまでの預貯金を取り崩してまかなうことがありますか。次の中から1つ選んでお答えください。(○は1つだけ)
預貯金の取り崩しをみると、全体で「よくある」と「時々ある」を合わせた「ある(再掲)」が61.2%となっている。
図表2-3-7-1 預貯金の取り崩しについて(問23)(択一回答)(CSV形式:1KB)
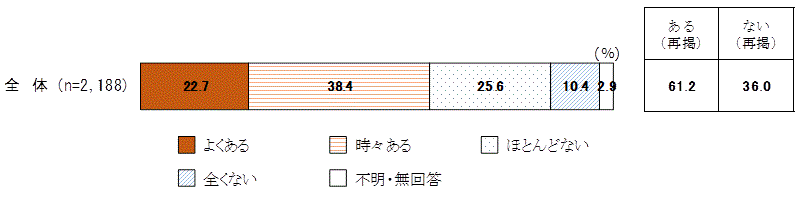
※ 「ある(再掲)」は「よくある」と「時々ある」の合計、「ない(再掲)」は「ほとんどない」と「全くない」の合計。
性・年齢でみると、男性の80~84歳は「ある(再掲)」(70.9%)が高い。
現在の結婚状況でみると、「ある(再掲)」は配偶者あるいはパートナーとは離別している者で高い(66.7%)。
同居者でみると、親と同居している者は「ない(再掲)」(46.4%)が高い。
地域(6区分)でみると、中国・四国は「ない(再掲)」(44.2%)が高い。
図表2-3-7-2 預貯金の取り崩しについて(問23)(択一回答)(CSV形式:4KB)
※ 「ある(再掲)」は「よくある」と「時々ある」の合計、「ない(再掲)」は「ほとんどない」と「全くない」の合計。
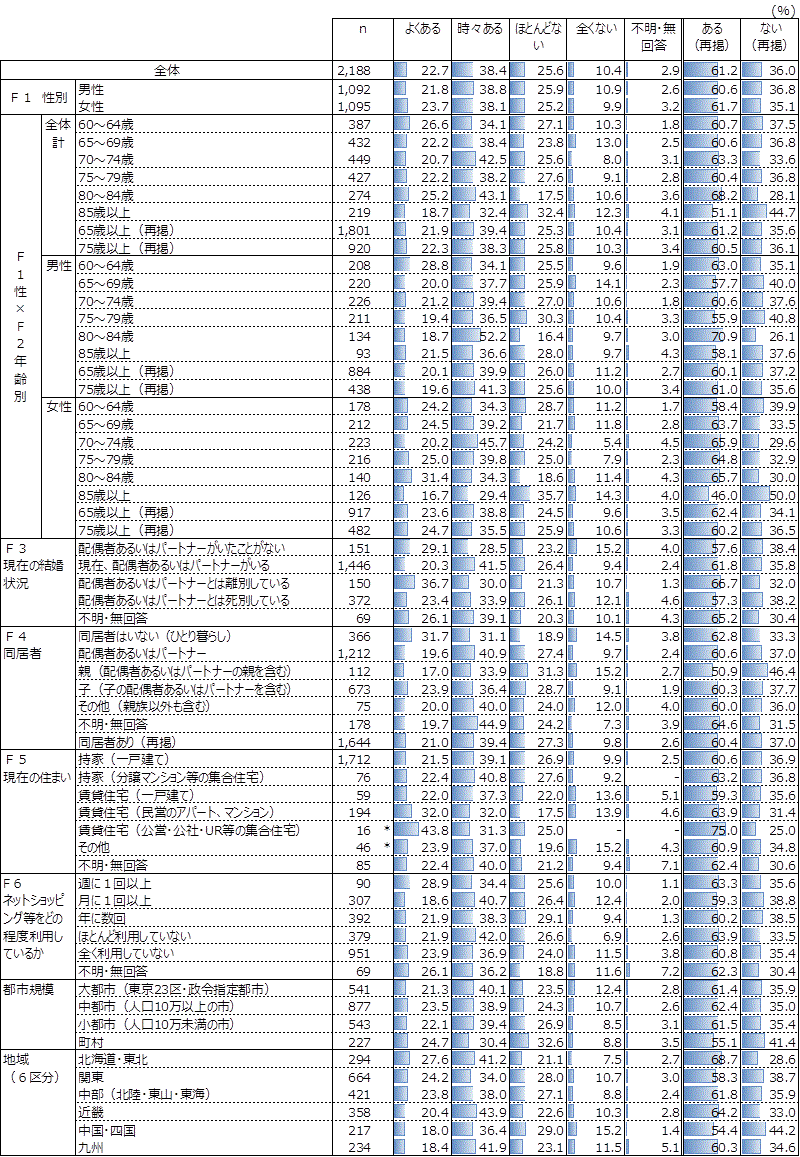
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「ある(再掲)」は、『現在の収入を伴う仕事に満足しているか(問11)で「不満がある」と答えた者』、『お金に困った際に相談できる相手はいるか(問26)で「相談できる相手はいない」と答えた者』、『金融資産の総額について(問30)で「1~500万円」と答えた者』、『認知機能の低下に伴う財産管理について(問35)で「自分の財産なのであくまで自分で管理する」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-7-3 預貯金の取り崩しについて(問23)(択一回答)(CSV形式:2KB)
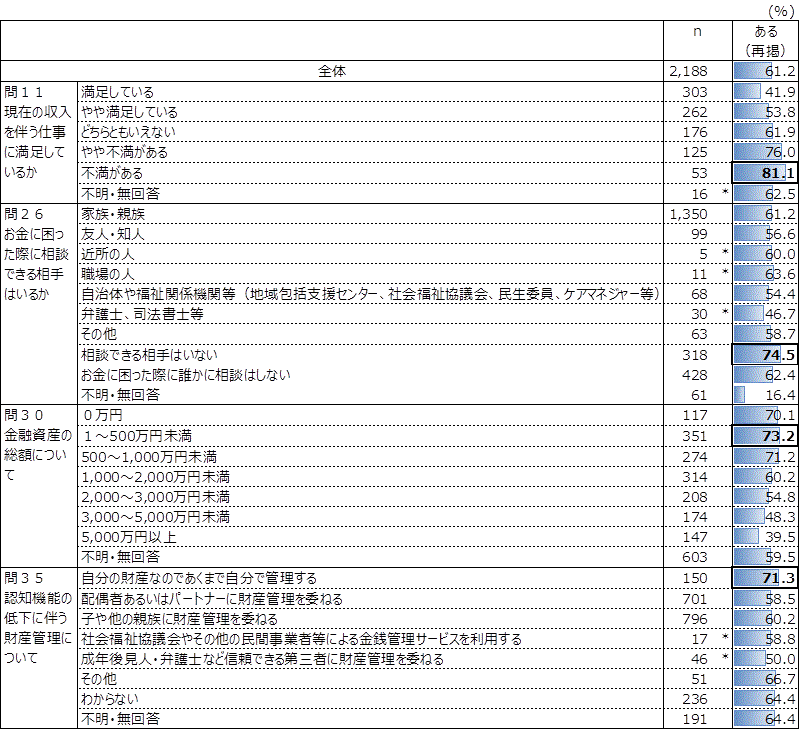
(8)1年間の取り崩し平均額について(問24)
【問23で「1または2(ある)」と答えた方にお伺いします。】
問24 この1年間の取り崩しは、平均して1か月にどのくらいでしょうか。
1年間の取り崩し平均額をみると、平均して1か月で6万8千円程度となっている。最も高いのは「2~5万円未満」(36.4%)。次いで、「5~10万円未満」(23.2%)、「10万円以上」(17.1%)が続く。
図表2-3-8-1 1年間の取り崩し平均額について(問24)(CSV形式:1KB)
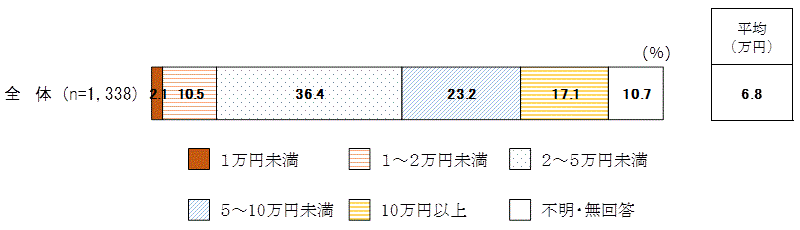
性・年齢でみると、男性の69歳までと女性の65~69歳は、8万円を超えている。
同居者でみると、同居者はいない者は5.9万円、同居者がいる者は6.7万円となっている。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、週に1回以上利用している者は10.3万円と高い。
地域(6区分)でみると、関東は7.9万円と高く、北海道・東北は5.9万円と低くなっている。
図表2-3-8-2 1年間の取り崩し平均額について(問24)(CSV形式:4KB)
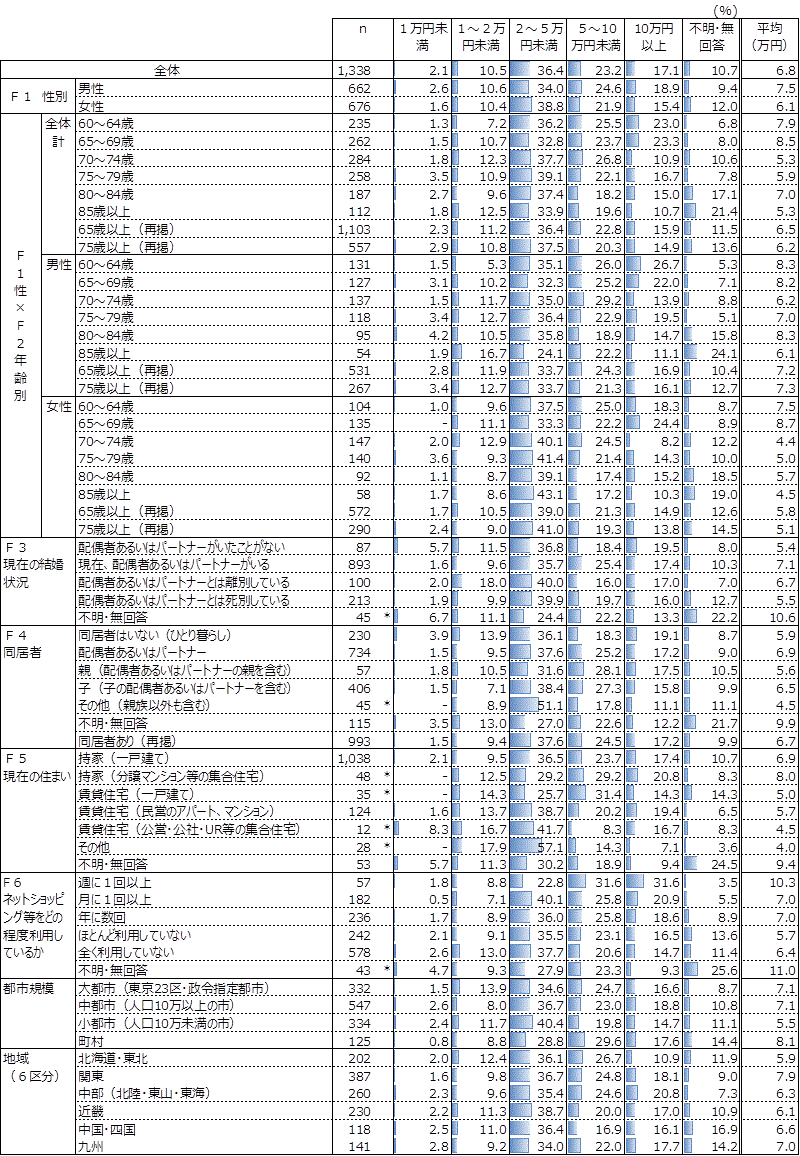
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、1年間の取り崩し平均額は、『生きがいを感じるか(問1)で「全く感じていない」と答えた者』、『現在の健康状態(問2)で「良くない」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-8-3 1年間の取り崩し平均額について(問24)(CSV形式:1KB)
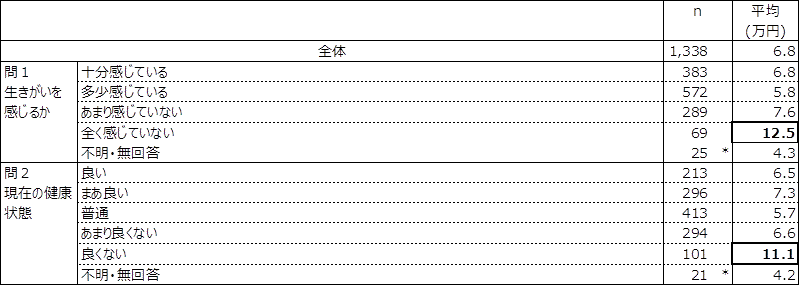
(9)収入を増やす方法(問25)
問25 現在より収入を増やす必要がある場合、これからどのような方法をとりますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(○はいくつでも)
収入を増やす方法をみると、全体で「節約等により支出を減らす」(54.3%)が最も高い。次いで、「貯蓄を取り崩している」(40.2%)、「自分が仕事をして収入を得る」(29.4%)、「資産の運用・売却により必要な収入を得る」(12.8%)が続く。
図表2-3-9-1 収入を増やす方法(問25)(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「その他」「特に何もしない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
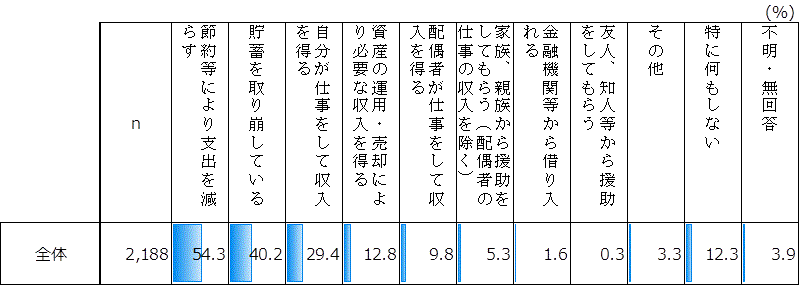
性別でみると、「自分が仕事をして収入を得る」は男性が35.8%と、女性(22.9%)よりも高い。
性・年齢でみると、男性の64歳までは「自分が仕事をして収入を得る」(63.0%)が高い。女性の85歳以上は「特に何もしない」(35.7%)が高くなっている。
現在の結婚状況でみると、配偶者あるいはパートナーがいたことがない者と配偶者あるいはパートナーとは離別している者は「自分が仕事をして収入を得る」(それぞれ45.0%、45.3%)が高い。
同居者でみると、親と同居している者は「自分が仕事をして収入を得る」(58.9%)が高い。
現在の住まいでみると、賃貸住宅(一戸建て)と賃貸住宅(民営のアパート、マンション)は「自分が仕事をして収入を得る」(それぞれ47.5%、49.5%)が高い。
図表2-3-9-2 収入を増やす方法(問25)(複数回答)(CSV形式:6KB)
※「その他」「特に何もしない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
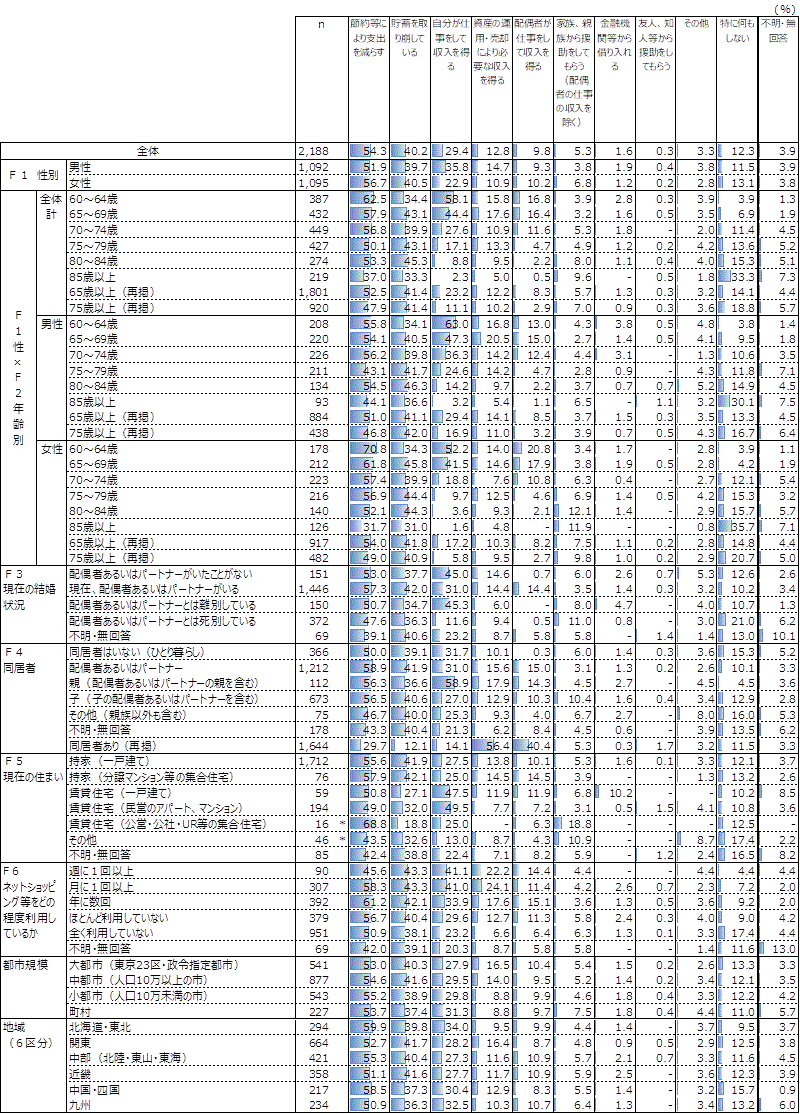
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「節約等により支出を減らす」は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など)」と答えた者』、『現在の収入を伴う仕事に満足しているか(問11)で「やや不満がある」と答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがなく、多少心配である」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-9-3 収入を増やす方法(問25)(複数回答)(CSV形式:2KB)
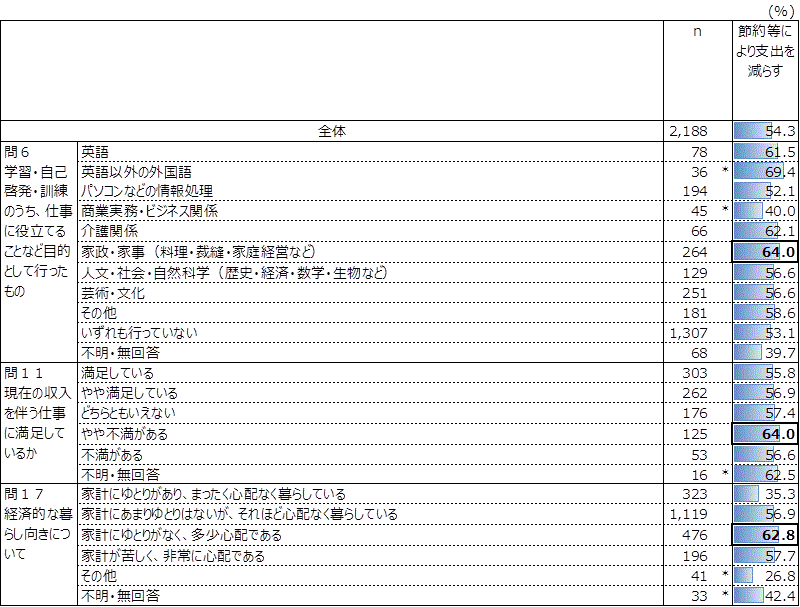
(10)お金に困った際に相談できる相手(問26)(複数回答)
問26 あなたは、お金に困った際に相談できる相手はいますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
お金に困った際に相談できる相手をみると、全体で「家族・親族」(61.7%)が最も高い。次いで、「友人・知人」(4.5%)、「自治体や福祉関係機関等(地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、ケアマネジャー等)」(3.1%)が続く。
「相談できる相手はいない」は14.5%、「お金に困った際に誰かに相談はしない」は19.6%となっている。
図表2-3-10-1 お金に困った際に相談できる相手(問26)(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「その他」「相談できる相手はいない」「お金に困った際に誰かに相談はしない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
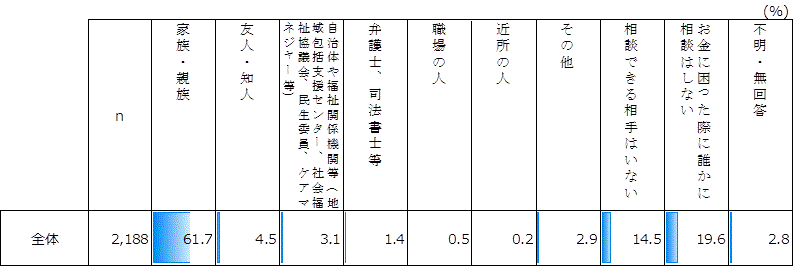
性・年齢でみると、男性の64歳までは「相談できる相手はいない」(21.2%)が高い。
現在の結婚状況でみると、配偶者あるいはパートナーがいたことがない者と配偶者あるいはパートナーとは離別している者は「相談できる相手はいない」(それぞれ27.2%、32.0%)が高い。
同居者でみると、同居者はいない者は「家族・親族」(51.1%)が低い。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、週に1回以上利用する者は「お金に困った際に誰かに相談はしない」(26.7%)が高い。
都市規模でみると、町村(67.8%)、小都市(64.3%)、中都市(60.1%)、大都市(59.1%)と都市規模が小さいほど「家族・親族」が高くなる。
図表2-3-10-2 お金に困った際に相談できる相手(問26)(複数回答)(CSV形式:5KB)
※「その他」「相談できる相手はいない」「お金に困った際に誰かに相談はしない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
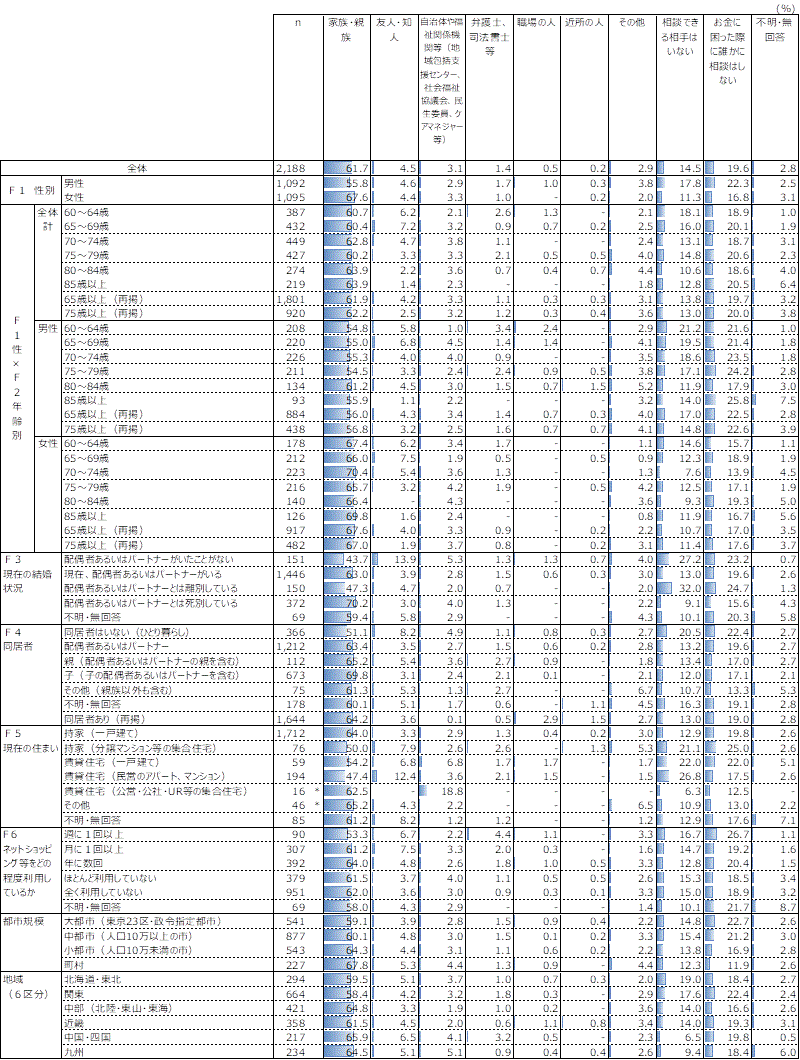
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「家族・親族」は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など)」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「働くのは体によいから、老化を防ぐから」と答えた者』、『認知機能の低下に伴う財産管理について(問35)で「子や他の親族に財産管理を委ねる」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-10-3 お金に困った際に相談できる相手(問26)(複数回答)(CSV形式:2KB)
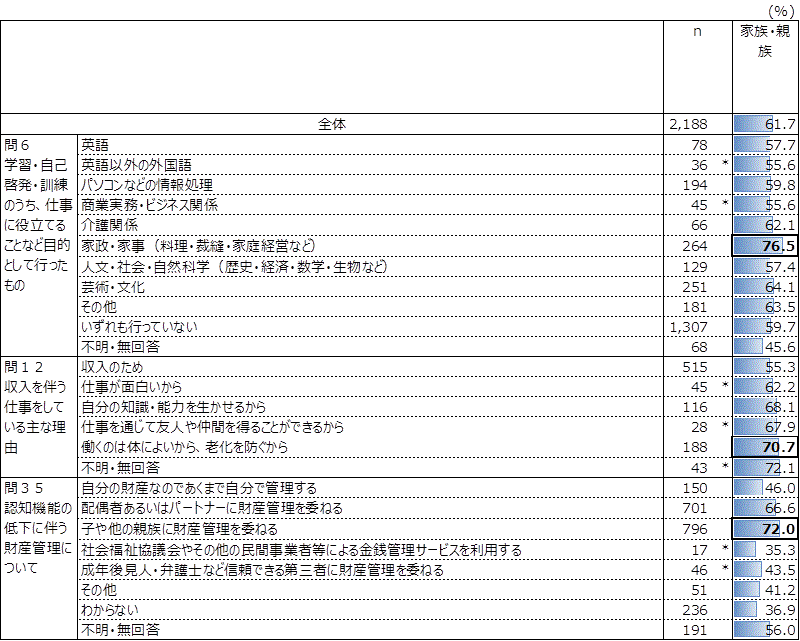
(11)優先的にお金を使いたいもの(問27(1))(複数回答)
問27 今後のお金の使い方についてお伺いします。(1)(2)について、それぞれあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
(1) 今後、優先的にお金を使いたいと考えているもの
(2) 今後、節約したいと考えているもの
優先的にお金を使いたいものをみると、全体で「自分や配偶者あるいはパートナーの医療・介護の費用」(47.5%)が最も高い。次いで、「食費」(43.2%)、「趣味やレジャー(旅行等)の費用」(32.4%)、「子や孫のための支出(学費、こづかい等)」(25.8%)が続く。
図表2-3-11-1 優先的にお金を使いたいもの(問27(1))(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「その他」「特にない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
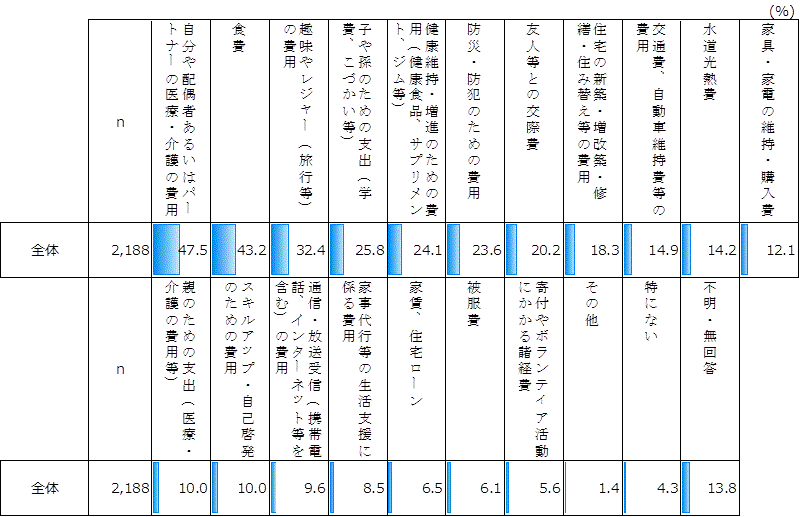
性・年齢でみると、男女ともに「趣味やレジャー(旅行等)の費用」は年齢が高くなるほど低くなる傾向となっている。女性の85歳以上は「水道光熱費」(26.2%)が高い。
現在の結婚状況でみると、現在、配偶者あるいはパートナーがいる者は「子や孫のための支出(学費、こづかい等)」(30.1%)が高い。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、週に1回以上利用している者は「食費」(65.6%)が高い。
図表2-3-11-2① 優先的にお金を使いたいもの(問27(1))(複数回答)(CSV形式:6KB)
※「その他」「特にない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
※表頭の項目数が多いため図表を①②に分割して掲載。
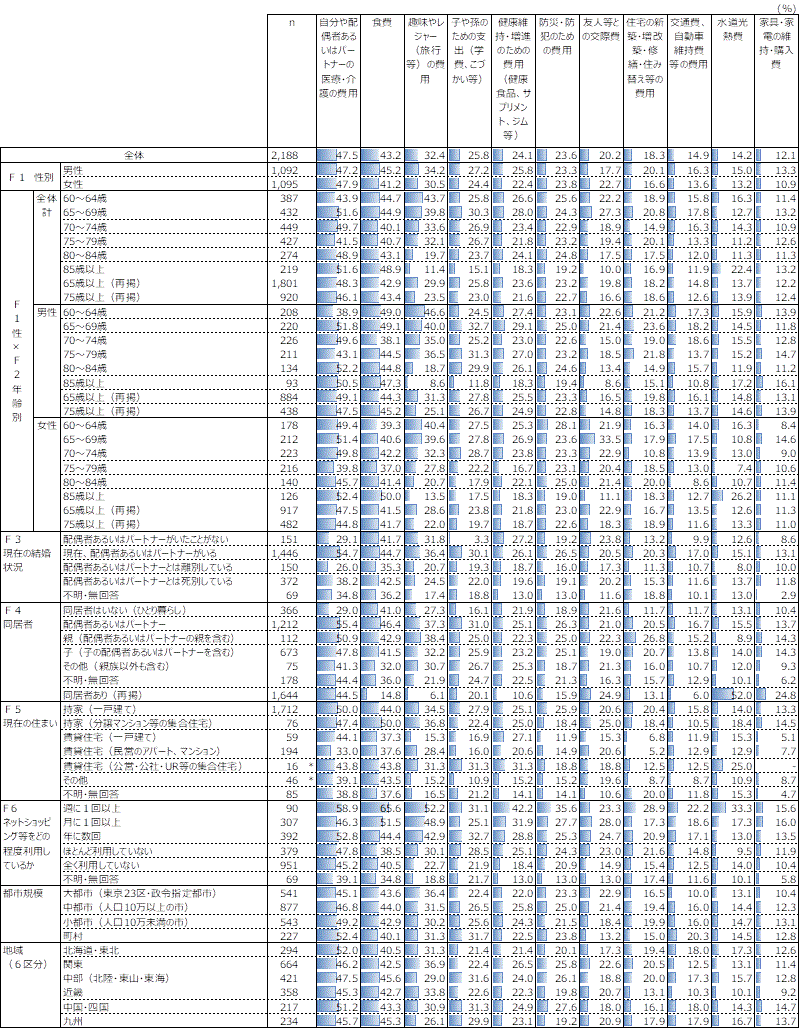
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
図表2-3-11-2② 優先的にお金を使いたいもの(問27(1))(複数回答)(CSV形式:5KB)
※「その他」「特にない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
※表頭の項目数が多いため図表を①②に分割して掲載。
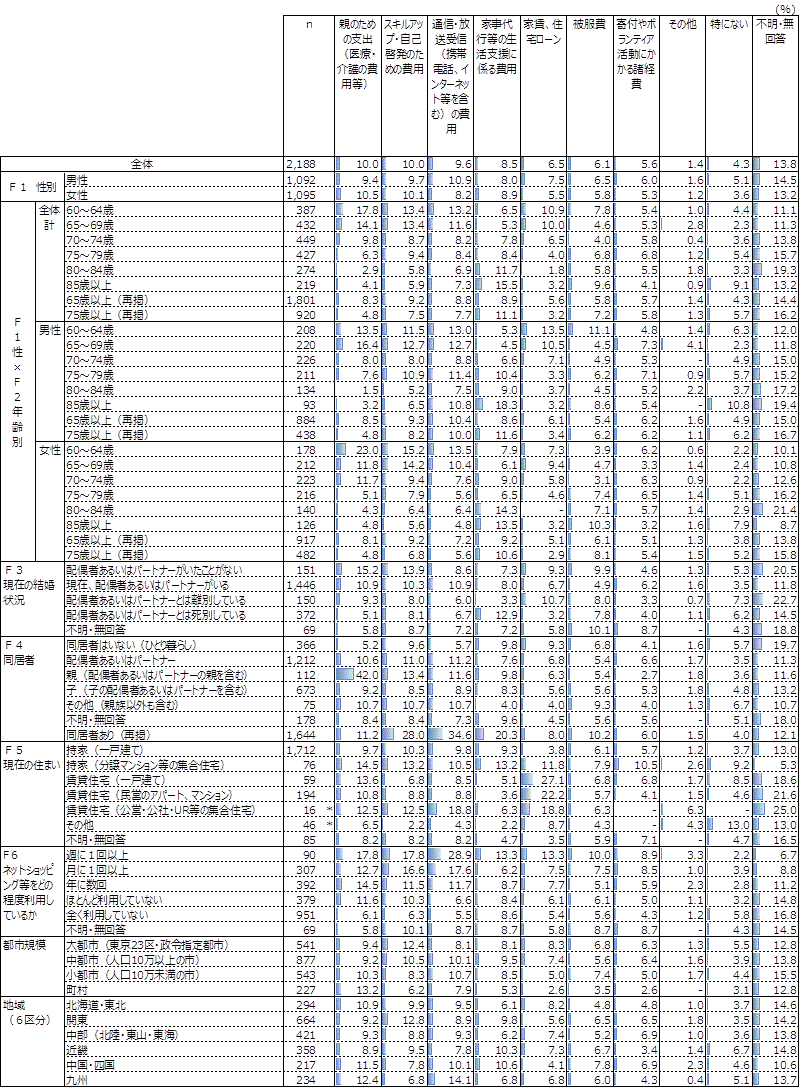
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「食費」は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「パソコンなどの情報処理」、「人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「自分の知識・能力を生かせるから」と答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-11-3 優先的にお金を使いたいもの(問27(1))(複数回答)(CSV形式:2KB)
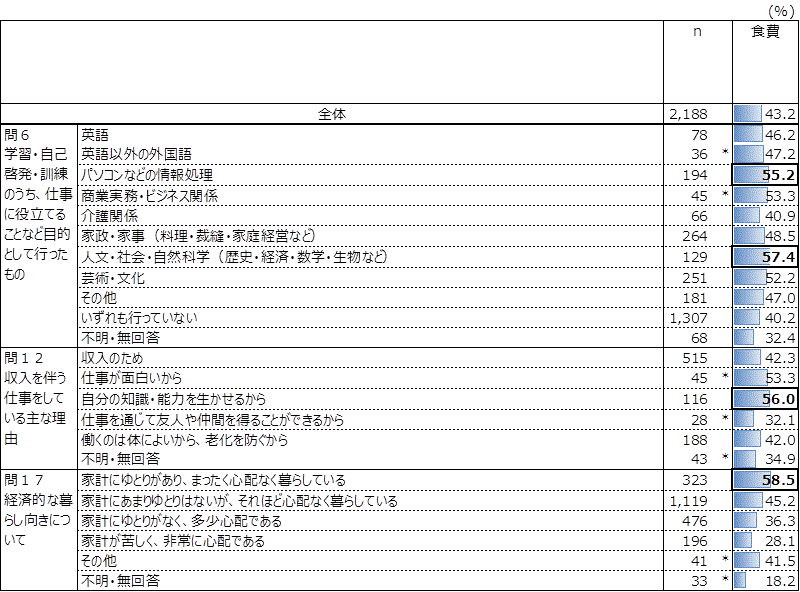
(12)今後節約したいもの(問27(2))(複数回答)
問27 今後のお金の使い方についてお伺いします。(1)(2)について、それぞれあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
(1)今後、優先的にお金を使いたいと考えているもの
(2)今後、節約したいと考えているもの
今後、節約したいものをみると、全体で「水道光熱費」(60.5%)が最も高い。次いで、「被服費」(52.8%)、「通信・放送受信(携帯電話、インターネット等を含む)の費用」(45.0%)、「交通費、自動車維持費等の費用」(40.9%)、「家具・家電の維持・購入費」(40.6%)が続く。
図表2-3-12-1 今後節約したいもの(問27(2))(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「その他」「特にない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
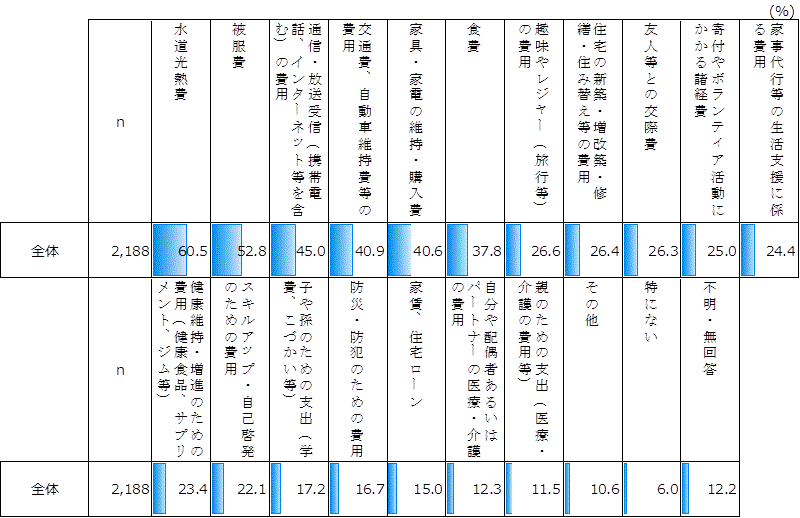
性・年齢でみると、「水道光熱費」は男女ともに84歳までは半数を超えているが、85歳以上(男性46.2%、女性37.3%)は低くなる。女性の64歳までは「被服費」(70.8%)が高い。
同居者でみると、親と同居している者は「通信・放送受信(携帯電話、インターネット等を含む)の費用」(61.6%)、「趣味やレジャー(旅行等)の費用」(35.7%)、「寄付やボランティア活動にかかる諸経費」(39.3%)が高い。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、週に1回以上利用している者は「家具・家電の維持・購入費」(52.2%)が高い。
地域(6区分)でみると、北海道・東北は「食費」(46.6%)が高い。
図表2-3-12-2① 今後節約したいもの(問27(2))(複数回答)(CSV形式:6KB)
※「その他」「特にない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
※表頭の項目数が多いため図表を①②に分割して掲載。
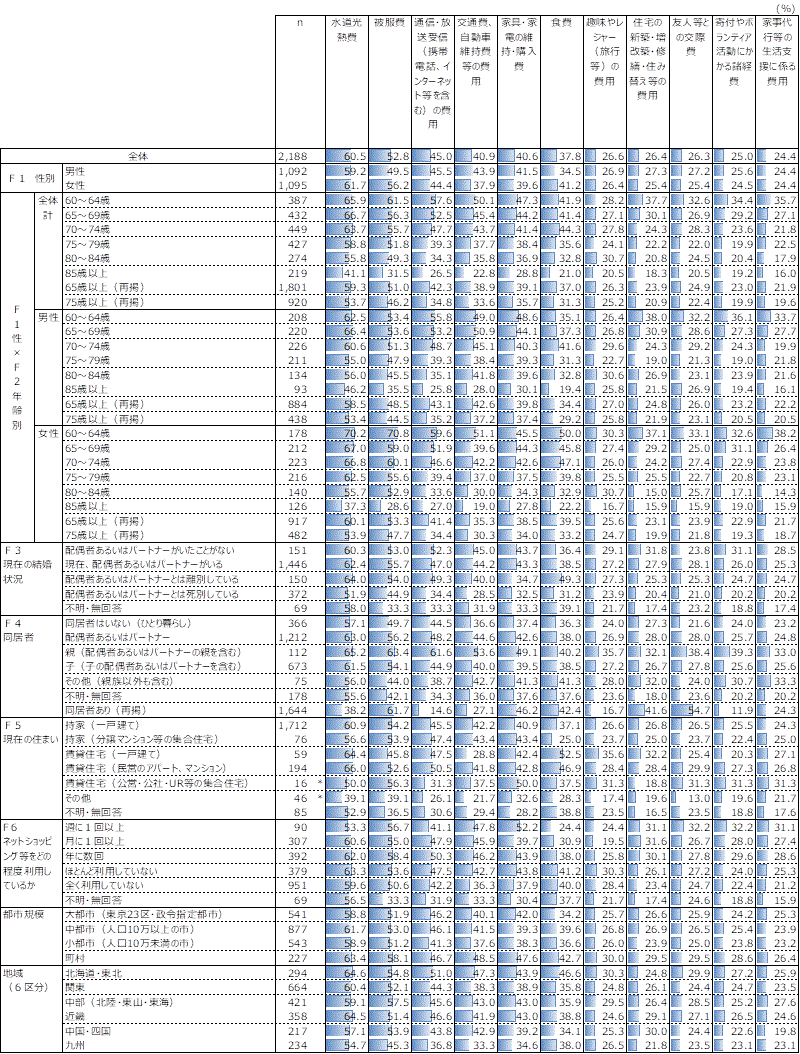
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
図表2-3-12-2② 今後節約したいもの(問27(2))(複数回答)(CSV形式:6KB)
※「その他」「特にない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
※表頭の項目数が多いため図表を①②に分割して掲載。
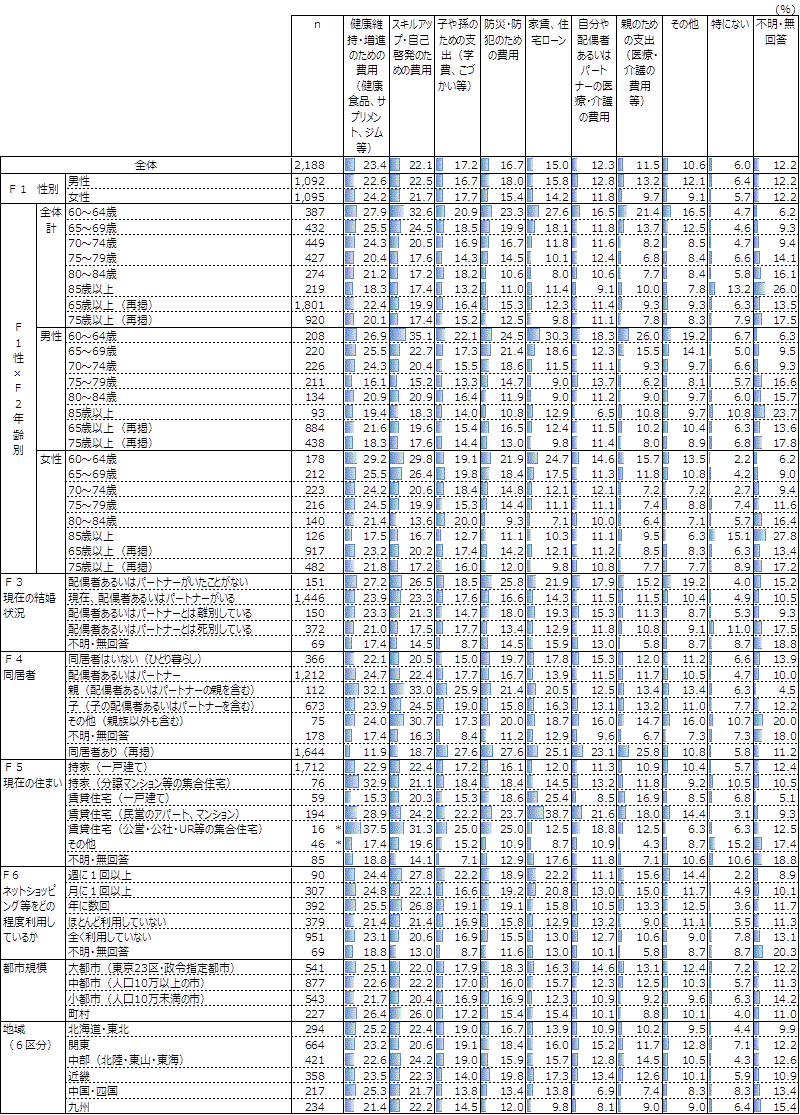
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「水道光熱費」は、『現在、収入を伴う仕事をしているか(問7)で「現在、収入を伴う仕事はしていないが、今後したいと考えている」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「収入のため」と答えた者』、『何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか(問16)で「70歳くらいまで」と答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがなく、多少心配である」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-12-3 今後節約したいもの(問27(2))(複数回答)(CSV形式:2KB)
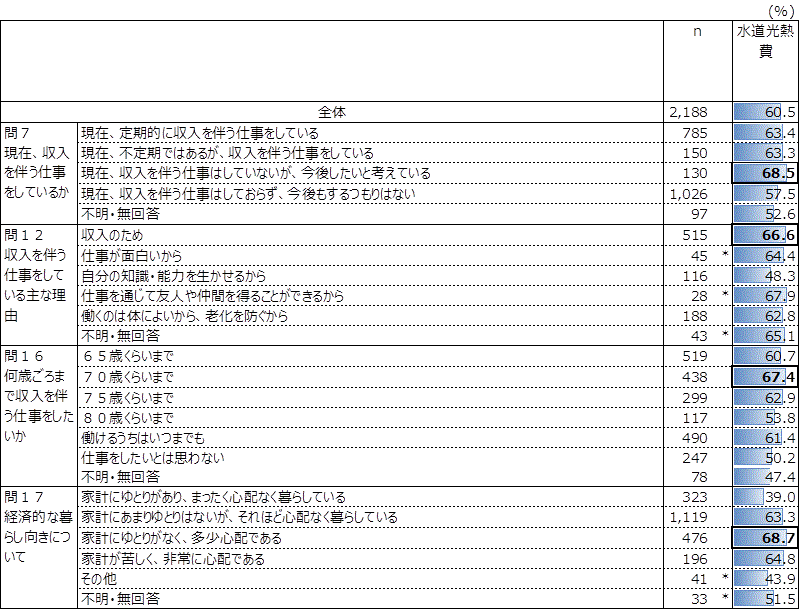
(13)経済的に不安に思うこと(問28)(複数回答)
問28 今後の生活において、経済的な面で不安に思うことはありますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
経済的に不安に思うことをみると、全体で「物価が上昇すること」(74.5%)が最も高い。次いで、「収入や貯蓄が少ないこと」(47.1%)、「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」(43.1%)、「災害により被害を受けること」(41.5%)が続く。「不安と思っていることはない」は4.6%、「不安に思う(再掲)」は92.6%。
図表2-3-13-1 経済的に不安に思うこと(問28)(複数回答)(CSV形式:2KB)
※「その他」「不安と思っていることはない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
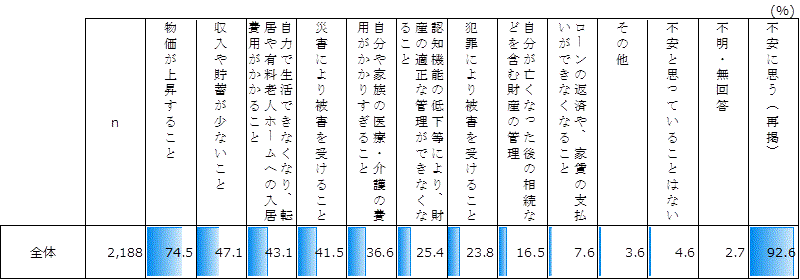
※ 「不安に思う(再掲)」は「物価が上昇すること」と「収入や貯蓄が少ないこと」と「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」と「災害により被害を受けること」と「自分や家族の医療・介護の費用がかかりすぎること」と「認知機能の低下等により、財産の適正な管理ができなくなること」と「犯罪により被害を受けること」と「自分が亡くなった後の相続などを含む財産の管理」と「ローンの返済や、家賃の支払いができなくなること」と「その他」のうち1つでも選択している割合。
性別でみると、「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」は女性が46.8%と、男性(39.5%)よりも高い。
性・年齢でみると、男性の80~84歳は「自分や家族の医療・介護の費用がかかりすぎること」(47.0%)が高く、女性の60~64歳は「物価が上昇すること」(83.7%)が高い。
現在の結婚状況でみると、配偶者あるいはパートナーとは離別している者は「収入や貯蓄が少ないこと」(68.0%)が高い。
同居者でみると、同居者はいない者は「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」(50.3%)が高い。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、週に1回以上利用している者は「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」(51.1%)が高い。
図表2-3-13-2 経済的に不安に思うこと(問28)(複数回答)(CSV形式:6KB)
※「その他」「不安と思っていることはない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
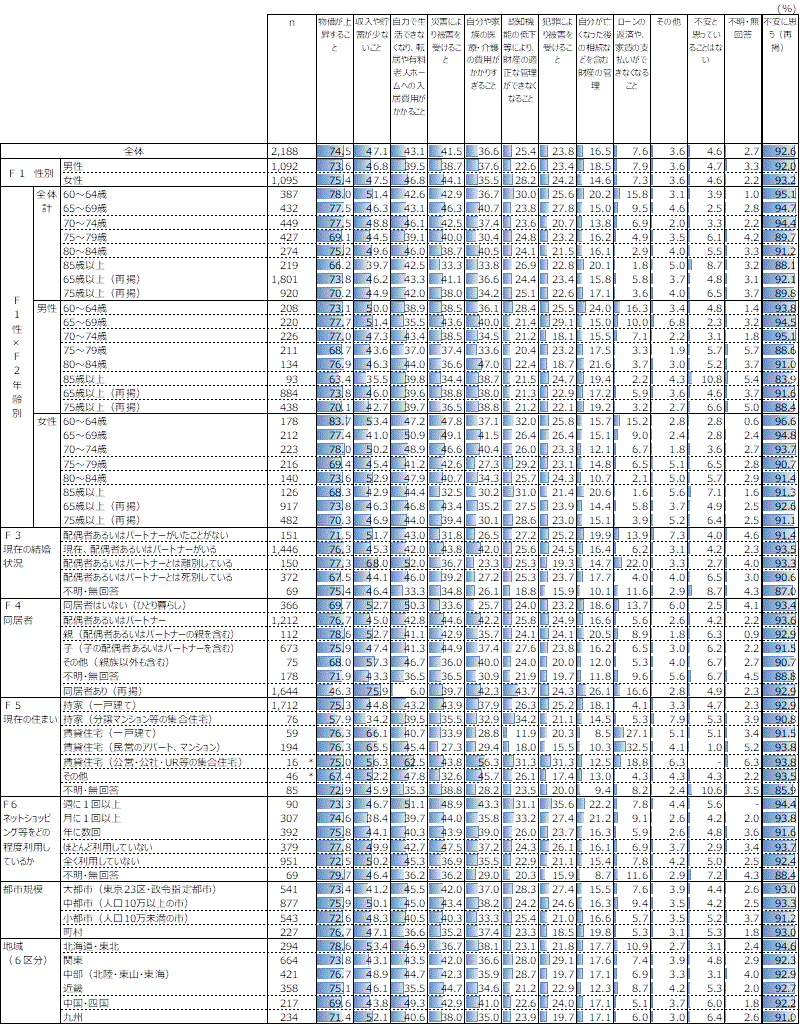
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「物価が上昇すること」は、『現在、収入を伴う仕事をしているか(問7)で「現在、収入を伴う仕事はしていないが、今後したいと考えている」と答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがなく、多少心配である」と答えた者』、『預貯金の取り崩しについて(問23)で「よくある」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-3-13-3 経済的に不安に思うこと(問28)(複数回答)(CSV形式:2KB)