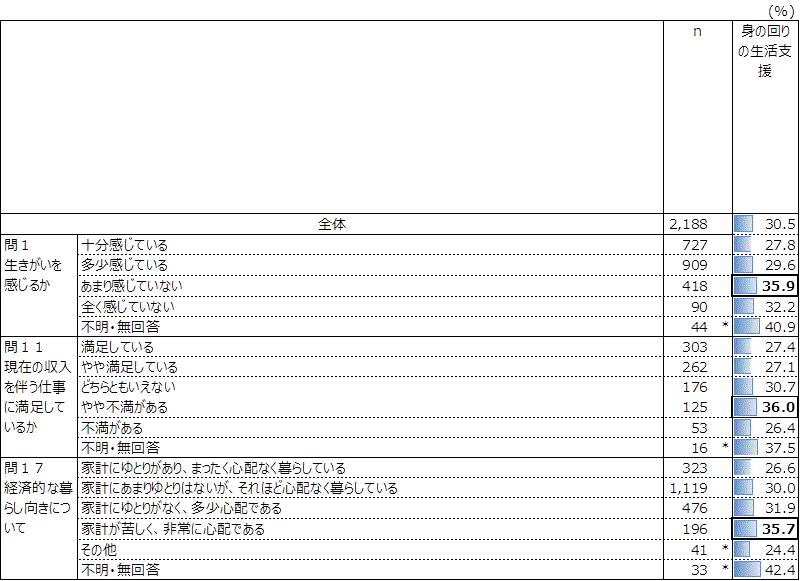老後の備えをみると、全体で「健康に関する備え(健康の維持・増進、介護予防、保険、病気やけがの治療等)」(80.7%)が最も高い。次いで、「終活関係の準備(自身の葬儀やお墓の準備、財産等の整理・相続の準備)」(38.1%)、「住まいに関する備え(住宅の確保やリフォーム、修繕等)(防災・防犯に関する備えを除く)」(25.5%)、「資産形成(貯蓄・投資)など」(24.2%)が続く。
第2章 調査結果の概要 -4
4.貯蓄、老後の備え等について
(1)老後の備えについて(問29)(複数回答・3つまで)
問29 老後の備えとして、今後どのようなことに取り組む必要があるか、次の中からあてはまるものを3つまでお答えください。(〇は3つまで)
図表2-4-1-1 老後の備えについて(問29)(複数回答・3つまで)(CSV形式:1KB)
※「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
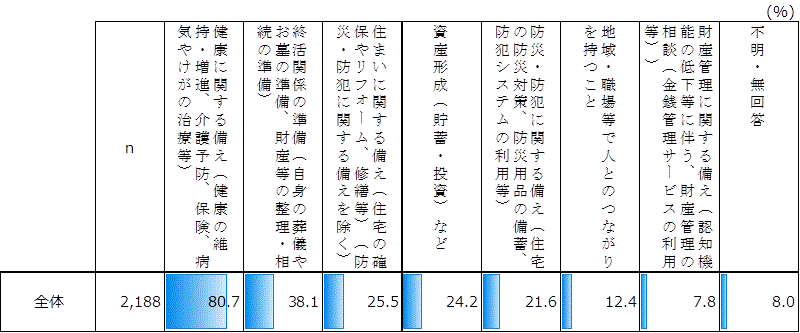
性・年齢でみると、「資産形成(貯蓄・投資)など」は男女ともに64歳までが4割以上と高く、年齢が高くなるほど低くなっている。
同居者でみると、親と同居している者は「住まいに関する備え(住宅の確保やリフォーム、修繕等)(防災・防犯に関する備えを除く)」と「資産形成(貯蓄・投資)など」(それぞれ33.0%、45.5%)が高い。
地域(6区分)でみると、中国・四国は「健康に関する備え(健康の維持・増進、介護予防、保険、病気やけがの治療等)」(74.7%)が低い。
図表2-4-1-2 老後の備えについて(問29)(複数回答・3つまで)(CSV形式:5KB)
※「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
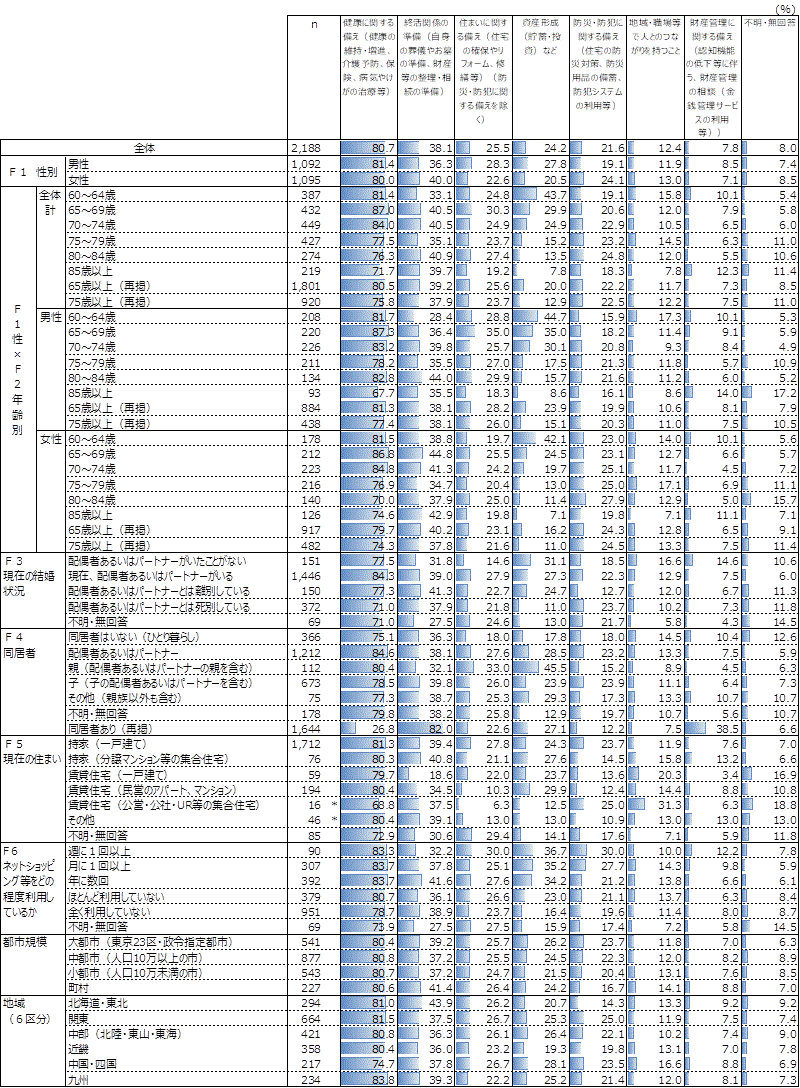
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「終活関係の準備(自身の葬儀やお墓の準備、財産等の整理・相続の準備)」は、『生きがいを感じるか(問1)で「あまり感じていない」と答えた者』、『現在、何らかの社会的な活動を継続的に行っていますか(問4)で「ボランティア活動」と答えた者』、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「介護関係」と答えた者』、『現在の収入を伴う仕事に満足しているか(問11)で「やや不満がある」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-1-3 老後の備えについて(問29)(複数回答・3つまで)(CSV形式:2KB)
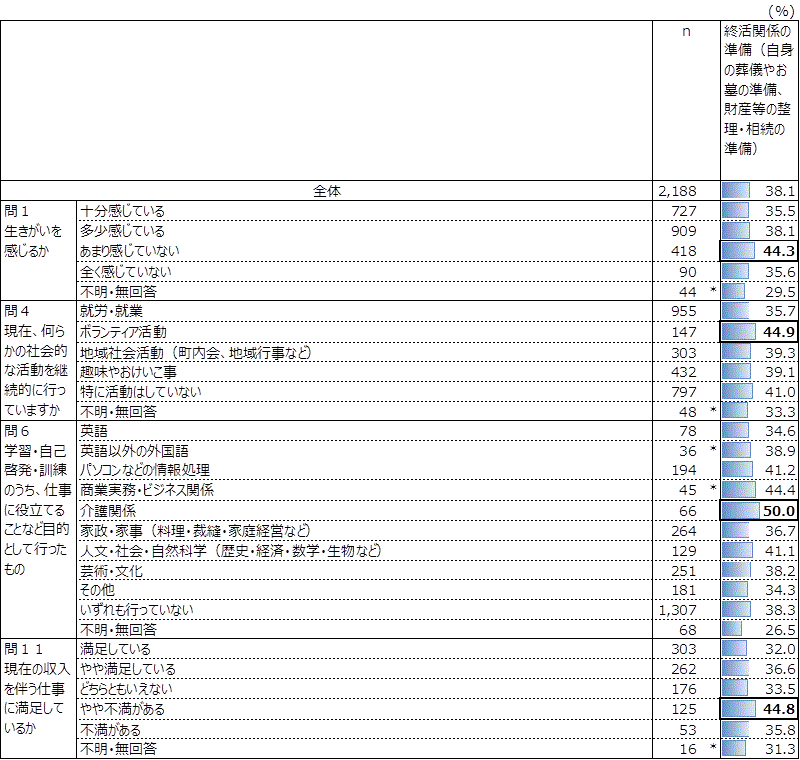
(2)金融資産の総額について(問30)
問30 金融資産(※)の総額は、およそどれくらいになりますか。配偶者あるいはパートナーと一緒に暮らしている方は、お二人の状況についてお答えください。
※株式や投資信託、預貯金なども含みます
金融資産の総額をみると、平均で1,769万円となっている。最も高いのは「1~500万円未満」(16.0%)。次いで、「1,000~2,000万円未満」(14.4%)、「500~1,000万円未満」(12.5%)が続く。
図表2-4-2-1 金融資産の総額について(問30)(CSV形式:1KB)
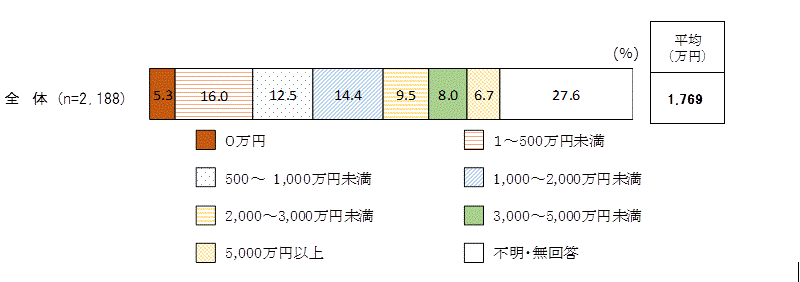
性別でみると、平均で男性は1,900万円、女性は1,628万円となっている。
性・年齢でみると、男性の64歳までは平均で2,332万円と高い。
同居者でみると、平均で同居者はいない者は1,293万円、同居者がいる者は1,882万円となっている。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、ネットショッピング等の利用頻度が高いほど平均が高くなる。
都市規模でみると、大都市は平均で2,456万円と高い。
地域(6区分)でみると、平均は関東が2,384万円と高い。
図表2-4-2-2 金融資産の総額について(問30)(CSV形式:5KB)
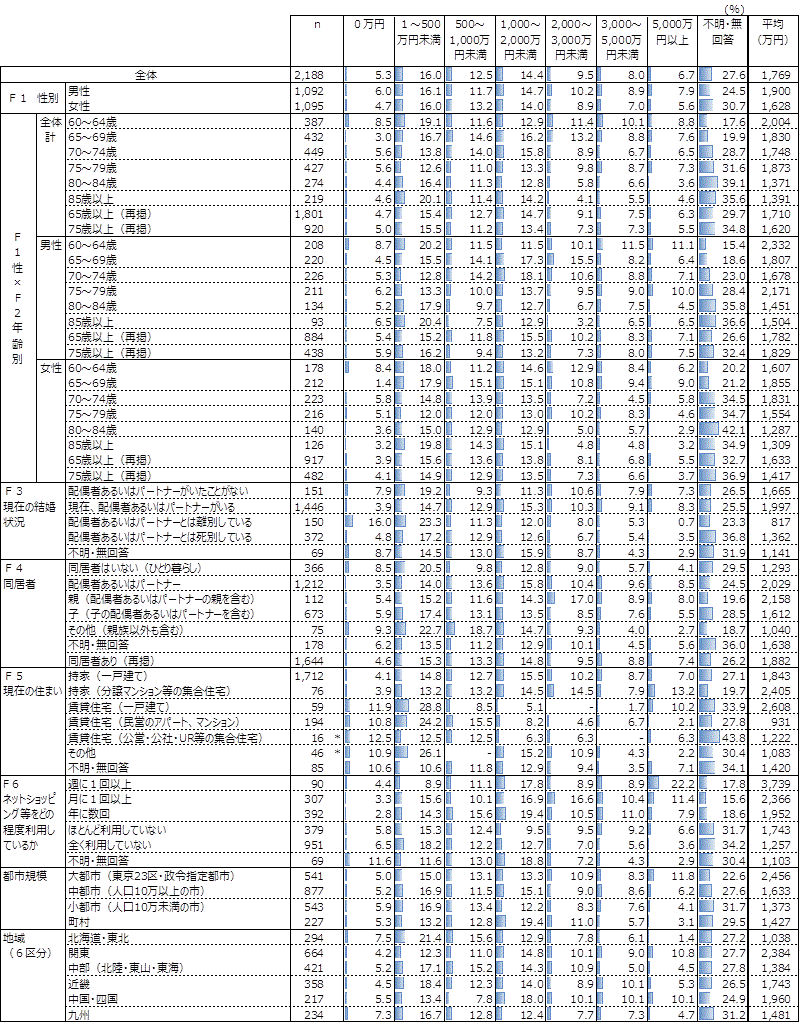
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、金融資産の総額の平均額は、『生きがいを感じるか(問1)で「十分感じている」と答えた者』、『現在の健康状態(問2)で「良い」と答えた者』、『現在、何らかの社会的な活動を継続的に行っていますか(問4)で「ボランティア活動」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「自分の知識・能力を生かせるから」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-2-3 金融資産の総額について(問30)(CSV形式:1KB)
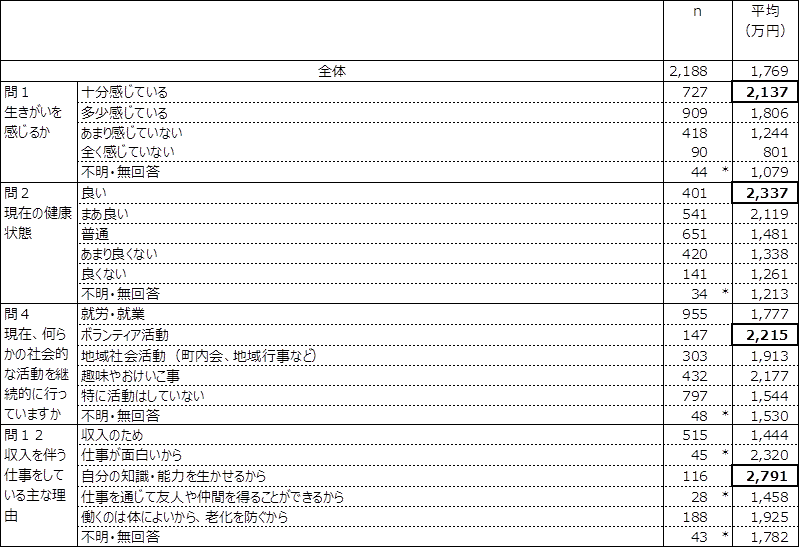
(3)必要な金融資産額について(問31)
問31 今後の生活のために、金融資産(※)はどのくらい必要だと思いますか。配偶者あるいはパートナーと一緒に暮らしている方は、お二人の状況についてお答えください。
※株式や投資信託、預貯金なども含みます
必要な金融資産額をみると、平均で2,648万円となっている。最も高いのは「2,000~3,000万円未満」(17.1%)。次いで、「1,000~2,000万円未満」(16.0%)、「3,000~5,000万円未満」(14.6%)が続く。
図表2-4-3-1 必要な金融資産額について(問31)(CSV形式:1KB)
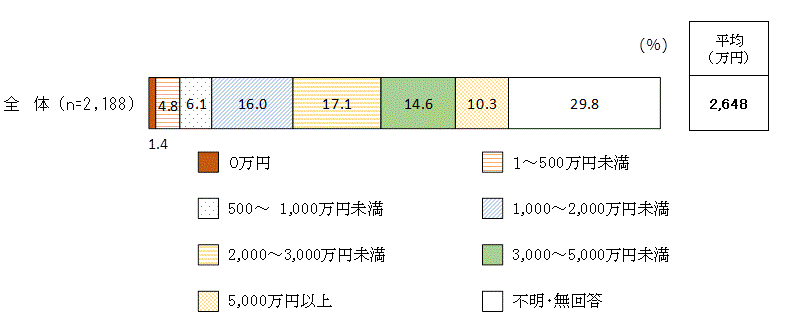
性別でみると、平均で男性は2,706万円、女性は2,587万円となっている。
性・年齢でみると、男性の64歳までは平均で3,265万円と高い。
同居者でみると、平均で同居者はいない者は2,013万円、同居者がいる者は2,787万円となっている。
ネットショッピング等をどの程度利用しているかでみると、週に1回以上利用している者は平均で4,777万円と高い。
地域(6区分)でみると、北海道・東北は平均で1,904万円と低い。
図表2-4-3-2 必要な金融資産額について(問31)(CSV形式:5KB)
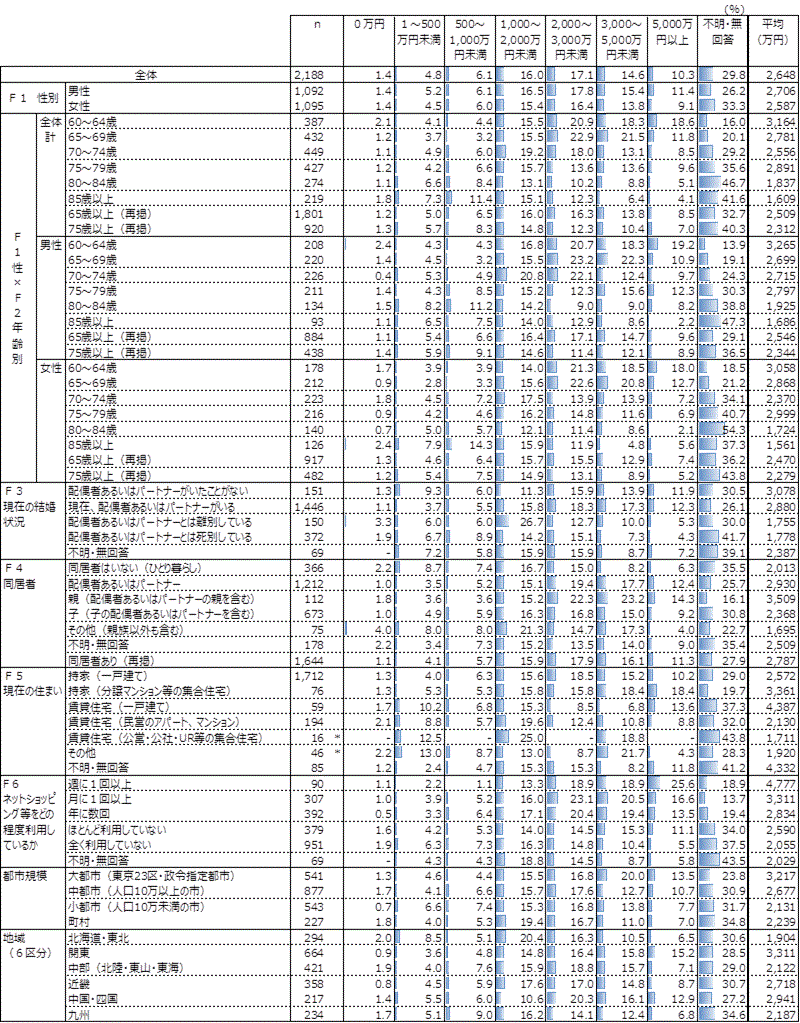
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、必要な金融資産額の平均額は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「英語」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「自分の知識・能力を生かせるから」と答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-3-3 必要な金融資産額について(問31)(CSV形式:2KB)
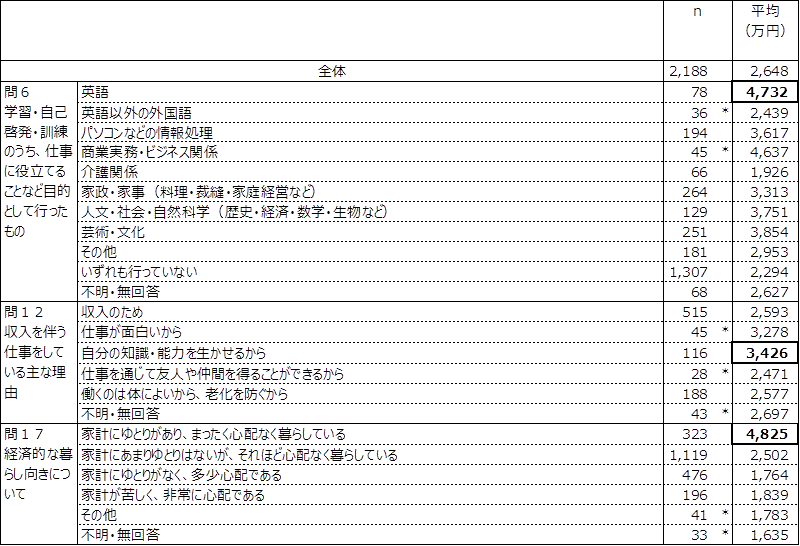
(4)公的年金・保険以外の保険について(問32)(複数回答)
問32 あなたは、公的年金・保険のほかに、老後の備えとして私的な年金・保険に加入していますか。掛け捨てのものも含めて、次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
公的年金・保険以外の保険をみると、全体で「生命保険」(56.0%)が最も高い。次いで、「病気やけがのための保険」(50.7%)、「個人年金」(19.7%)、「介護のための保険」(13.3%)、「企業年金」(13.0%)が続く。「いずれも加入していない」は17.2%。
図表2-4-4-1 公的年金・保険以外の保険について(問32)(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「その他」「いずれも加入していない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
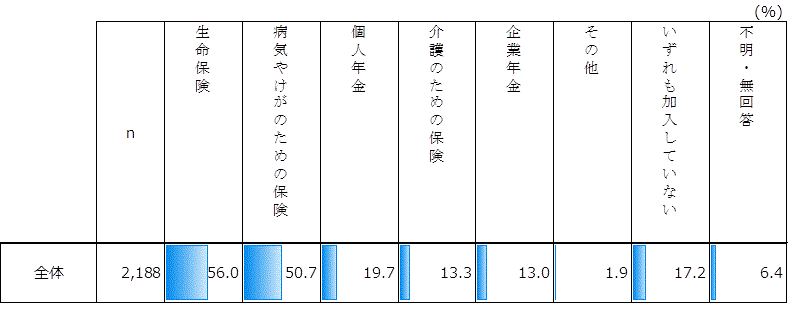
性・年齢でみると、男女ともに60歳代は「生命保険」が6割台と高い。また、女性の65~69歳は「病気やけがのための保険」(67.5%)が高くなっている。
現在の結婚状況でみると、現在、配偶者あるいはパートナーがいる者は「生命保険」と「病気やけがのための保険」(それぞれ61.6%、56.3%)が高い。
同居者でみると、同居者はいない者は「生命保険」と「病気やけがのための保険」(それぞれ39.6%、41.5%)が低い。
図表2-4-4-2 公的年金・保険以外の保険について(問32)(複数回答)(CSV形式:5KB)
※「その他」「いずれも加入していない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
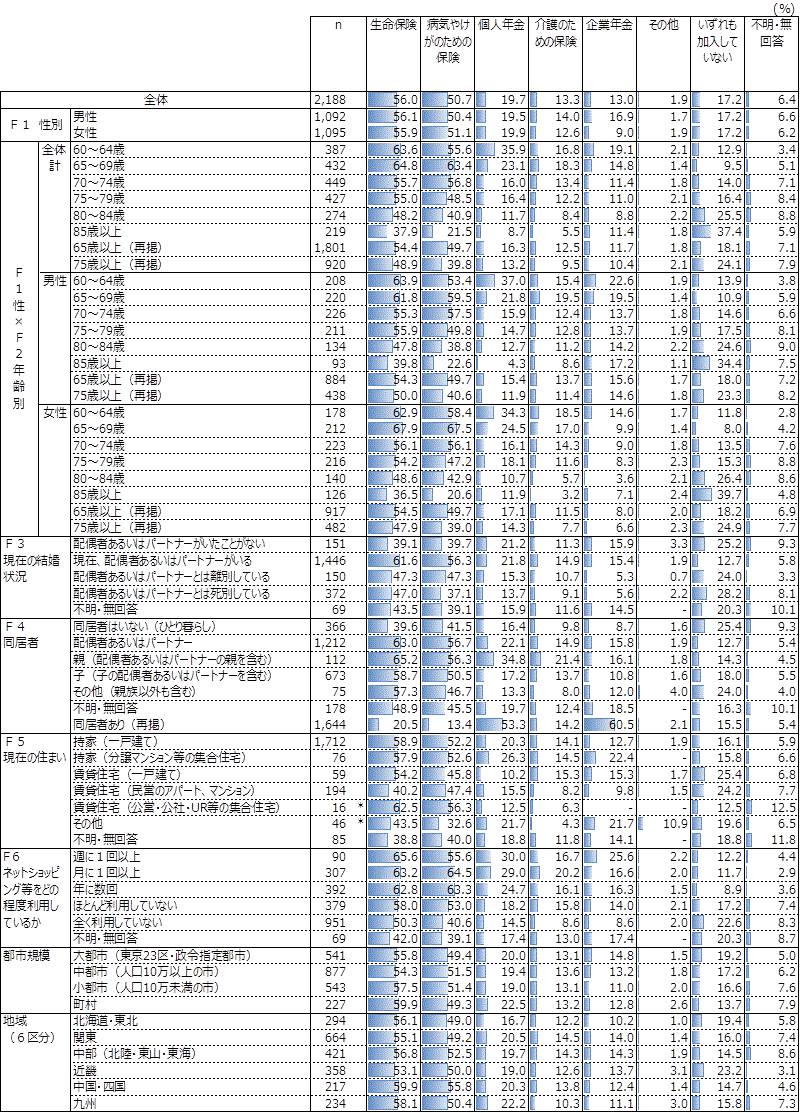
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「生命保険」は、『現在、何らかの社会的な活動を継続的に行っていますか(問4)で「地域社会活動(町内会、地域行事など)」と答えた者』、『金融資産の総額について(問30)で「5,000万円以上」と答えた者』、『認知機能の低下に伴う財産管理について(問35)で「配偶者あるいはパートナーに財産管理を委ねる」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-4-3 公的年金・保険以外の保険について(問32)(複数回答)(CSV形式:2KB)
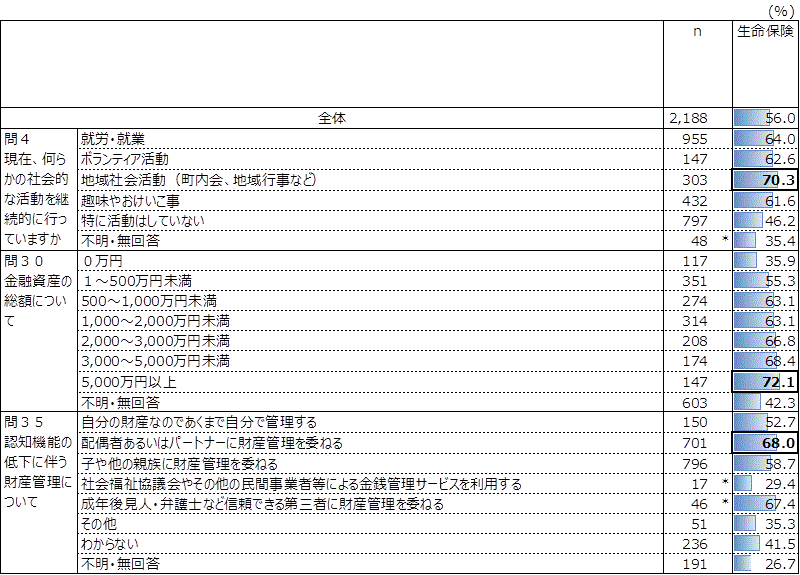
(5)貯蓄は十分か(問33)
問33 現在の貯蓄の額は、あなたがこれから生活をしていく備えとして十分だとお考えですか。次の中から1つ選んでお答えください。(○は1つだけ)
貯蓄は十分かをみると、全体で「十分だと思う」と「最低限はあると思う」を合わせた「ある(再掲)」が36.7%となっている。
図表2-4-5-1 貯蓄は十分か(問33)(択一回答)(CSV形式:1KB)
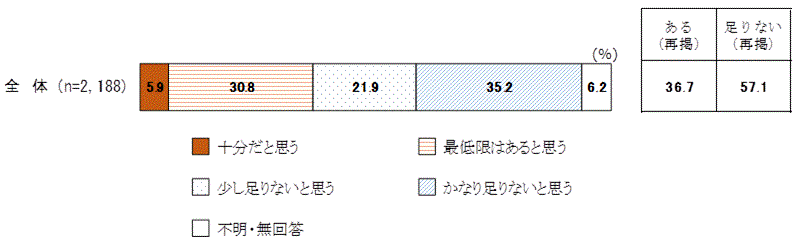
※ 「ある(再掲)」は「十分だと思う」と「最低限はあると思う」の合計、
「足りない(再掲)」は「少し足りないと思う」と「かなり足りないと思う」の合計。
性・年齢でみると、「ある(再掲)」は、男女ともに85歳以上で5割程度となる。
現在の結婚状況でみると、配偶者あるいはパートナーとは離別している者は「足りない(再掲)」(76.0%)が高い。
現在の住まいでみると、賃貸住宅(一戸建て)と賃貸住宅(民営のアパート、マンション)は「足りない(再掲)」(それぞれ72.9%、74.2%)が高い。
地域(6区分)でみると、北海道・東北は「足りない(再掲)」(66.7%)が高い。
図表2-4-5-2 貯蓄は十分か(問33)(択一回答)(CSV形式:4KB)
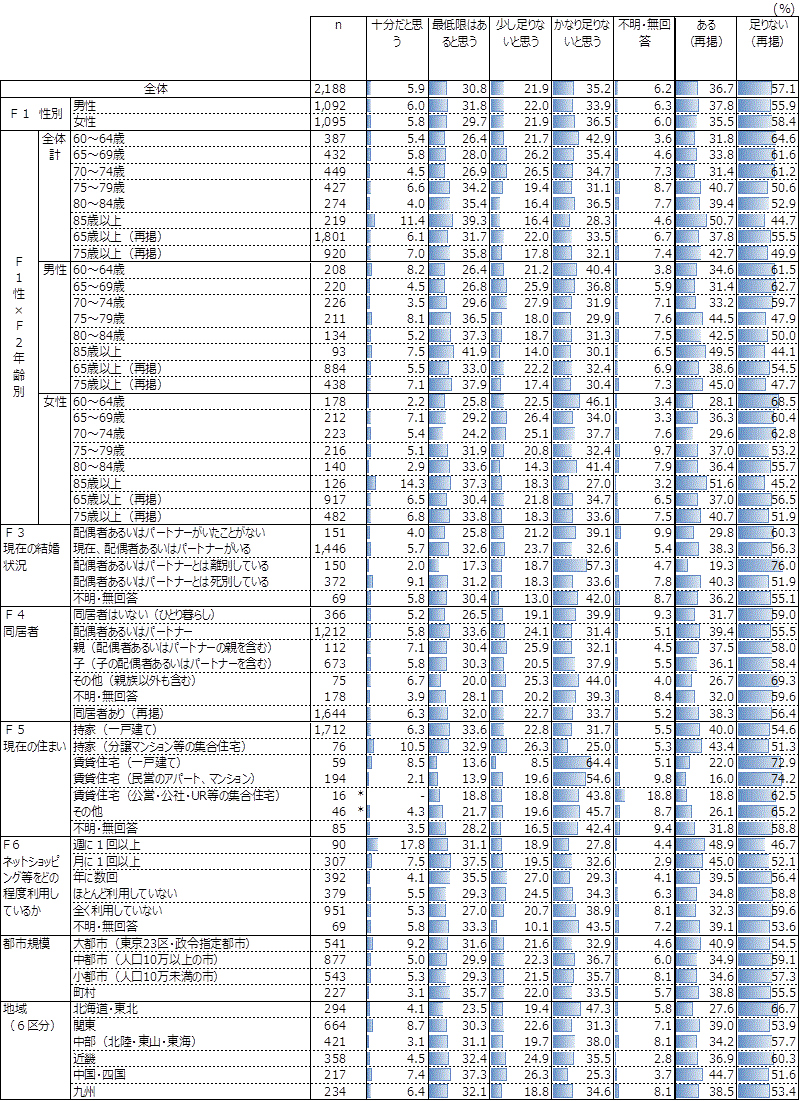
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「足りない(再掲)」は、『現在の収入を伴う仕事に満足しているか(問11)で「やや不満がある」「不満がある」と答えた者』、『預貯金の取り崩しについて(問23)で「よくある」と答えた者』、『お金に困った際に相談できる相手はいるか(問26)で「相談できる相手はいない」と答えた者』、『金融資産の総額について(問30)で500万円未満と答えた者』、『認知機能の低下に伴う財産管理について(問35)で「わからない」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-5-3 貯蓄は十分か(問33)(択一回答)(CSV形式:2KB)
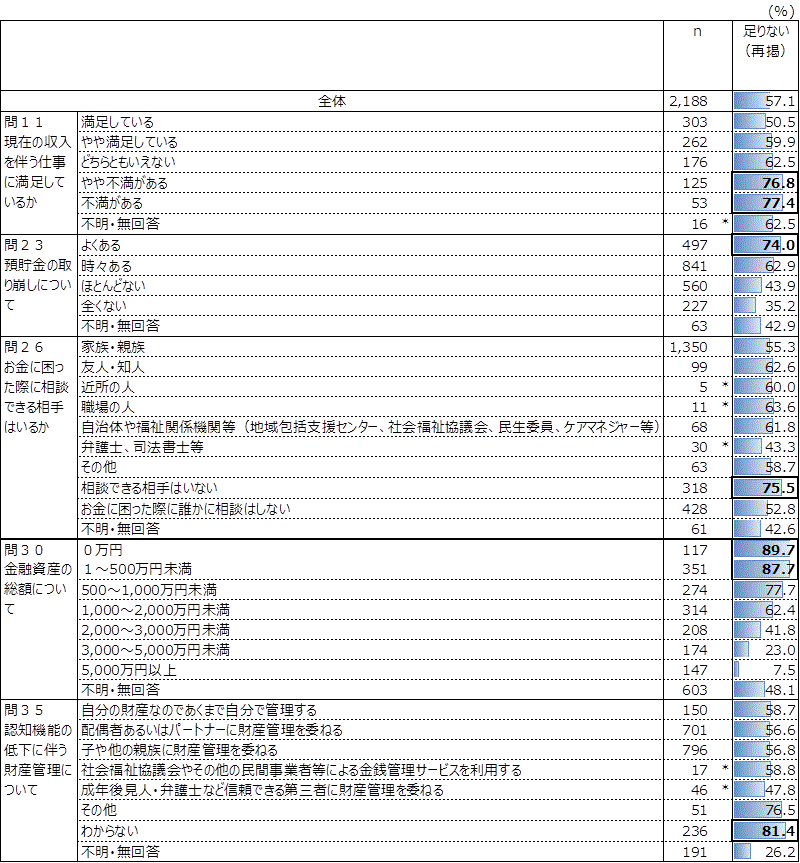
(6)将来的な財産の使い道(問34)(複数回答)
問34 将来的な財産の使い道について、どのようにお考えですか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
将来的な財産の使い道をみると、全体で「遺族等へ財産を残したい」(35.9%)が最も高い。次いで、「財産は自分のために使いたい」(33.0%)、「困っている人や社会・公共の役に立つように寄付等をしたい」(3.0%)の順となる。「残す財産がない」は24.5%、「財産の使い道については考えていない」は14.4%。
図表2-4-6-1 将来的な財産の使い道(問34)(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「残す財産がない」「財産の使い道については考えていない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
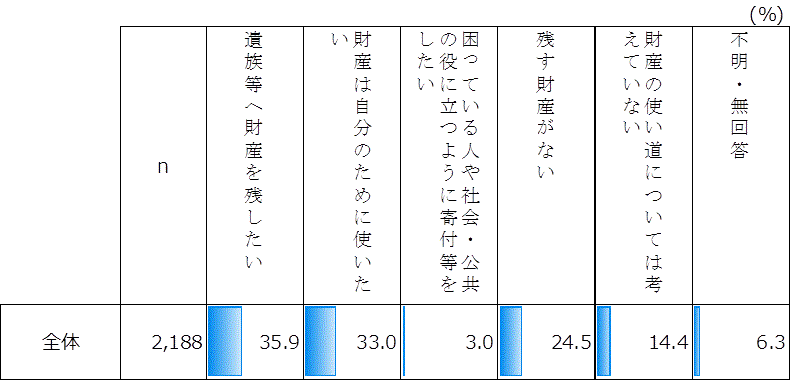
性・年齢でみると、男女ともに年代が高いほど「財産は自分のために使いたい」が低くなる傾向にある。
現在の結婚状況でみると、配偶者あるいはパートナーとは離別している者は「残す財産がない」(42.0%)が高い。
同居者でみると、親と同居している者は「財産は自分のために使いたい」(46.4%)が高い。
現在の住まいでみると、賃貸住宅(一戸建て)と賃貸住宅(民営のアパート、マンション)と賃貸住宅(公営・公社・UR等の集合住宅)は「残す財産がない」(それぞれ55.9%、46.4%、43.8%)が高い。
地域(6区分)でみると、中国・四国は「遺族等へ財産を残したい」(43.3%)が高い。
図表2-4-6-2 将来的な財産の使い道(問34)(複数回答)(CSV形式:4KB)
※「残す財産がない」「財産の使い道については考えていない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
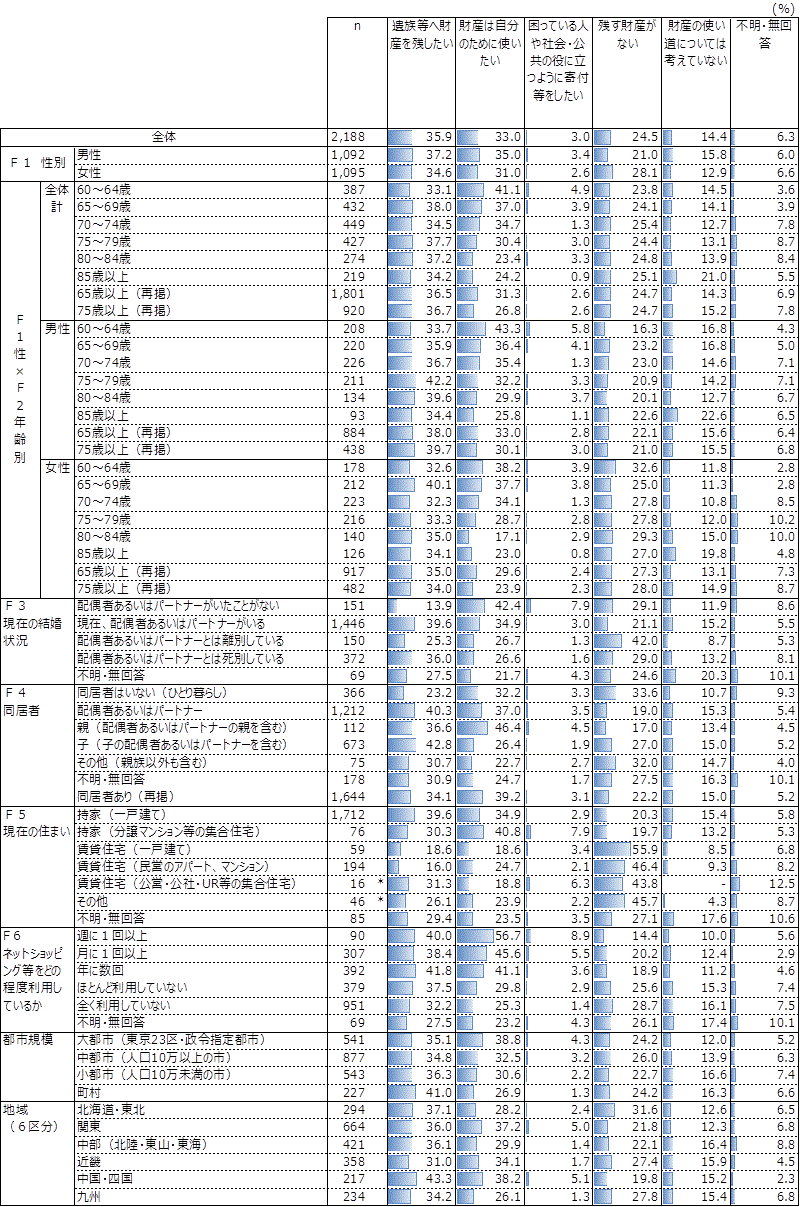
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「遺族等へ財産を残したい」は、『生きがいを感じるか(問1)で「十分感じている」と答えた者』、『現在、何らかの社会的な活動を継続的に行っていますか(問4)で就労・就業以外の何らかの活動を行っている者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と答えた者』、『金融資産の総額について(問30)で2,000万円以上と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-6-3 将来的な財産の使い道(問34)(複数回答)(CSV形式:2KB)
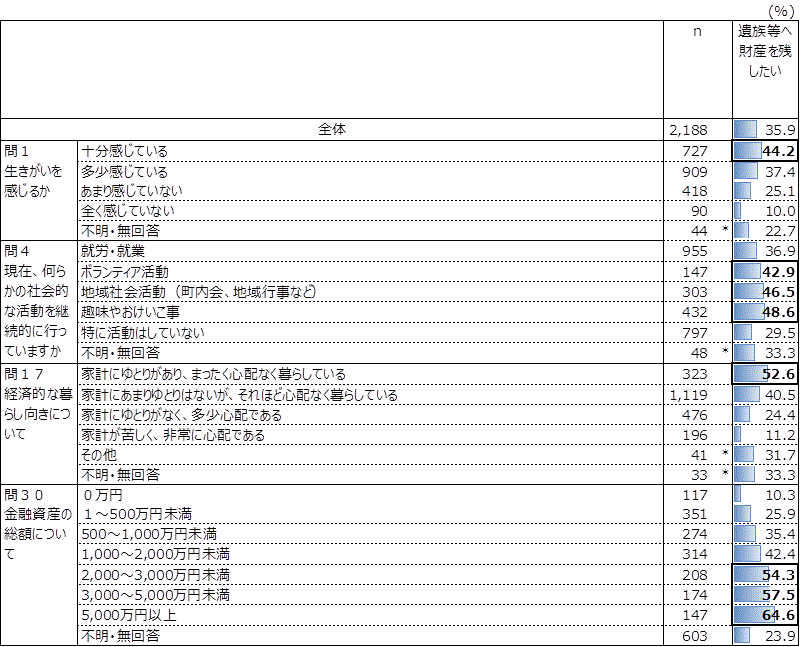
(7)認知機能の低下に伴う財産管理(問35)
問35 万一、認知機能の低下など、高齢化に伴って財産(日常生活に要する費用を含む)の適正な管理や活用に不安が生じた場合、あなたはどのようにされますか。次の中からあてはまるものを1つ選んでお答えください。(〇は1つだけ)
認知機能の低下に伴う財産管理をみると、全体で「子や他の親族に財産管理を委ねる」(36.4%)が最も高い。次いで、「配偶者あるいはパートナーに財産管理を委ねる」(32.0%)、「自分の財産なのであくまで自分で管理する」(6.9%)が続く。「わからない」は10.8%。
図表2-4-7-1 認知機能の低下に伴う財産管理(問35)(択一回答)(CSV形式:1KB)
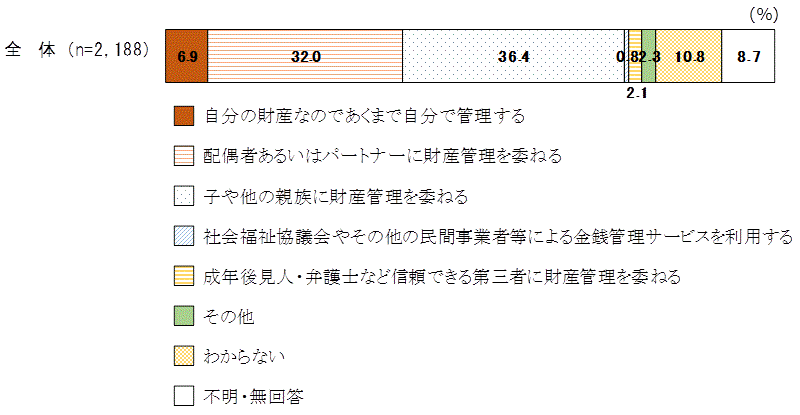
性別でみると、「配偶者あるいはパートナーに財産管理を委ねる」は男性が42.2%と、女性(21.8%)よりも高く、「子や他の親族に財産管理を委ねる」は女性が46.9%と、男性(25.8%)よりも高い。
同居者でみると、同居者はいない者と子と同居している者は「子や他の親族に財産管理を委ねる」(それぞれ41.0%、47.0%)が高い。
地域(6区分)でみると、中国・四国は「配偶者あるいはパートナーに財産管理を委ねる」(39.2%)が高い。
図表2-4-7-2 認知機能の低下に伴う財産管理(問35)(択一回答)(CSV形式:5KB)
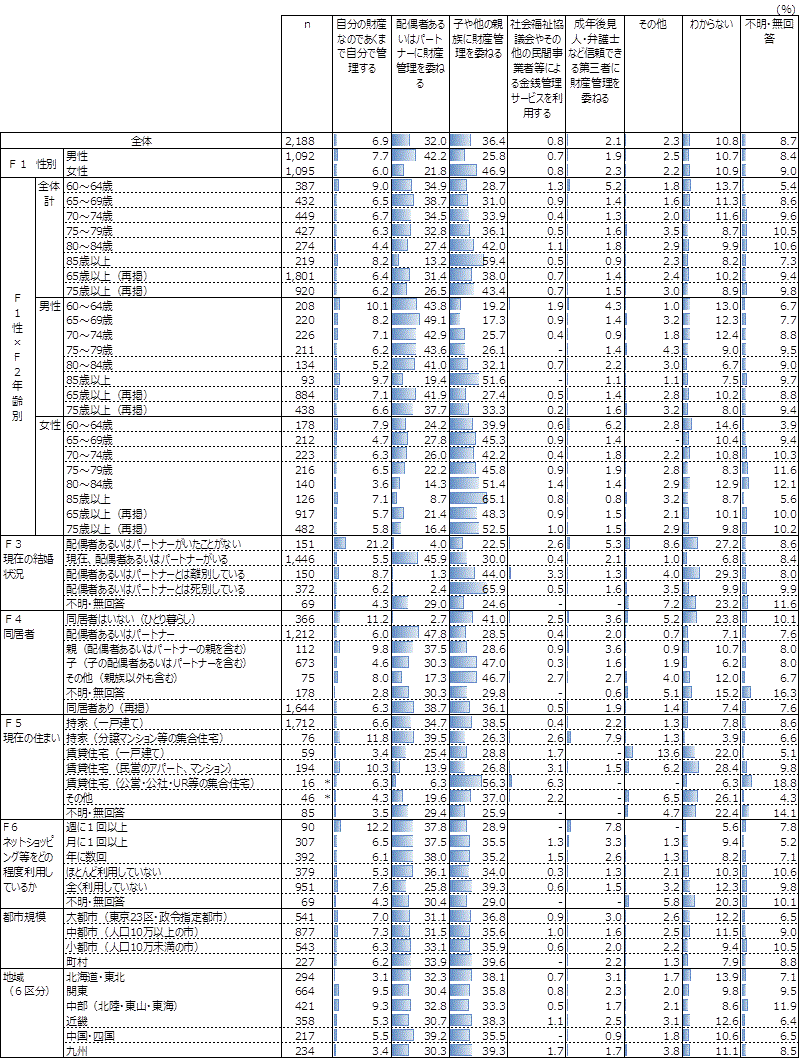
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「子や他の親族に財産管理を委ねる」は、『現在の認知機能(問3)で(イ)周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われると答えた者』、『現在の認知機能(問3)で(ハ)今日が何月何日かわからない時があると答えた者』、『現在、何らかの社会的な活動を継続的に行っていますか(問4)で「特に活動はしていない」と答えた者』、『現在、収入を伴う仕事をしているか(問7)で「現在、収入を伴う仕事はしておらず、今後もするつもりはない」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-7-3 認知機能の低下に伴う財産管理(問35)(択一回答)(CSV形式:1KB)
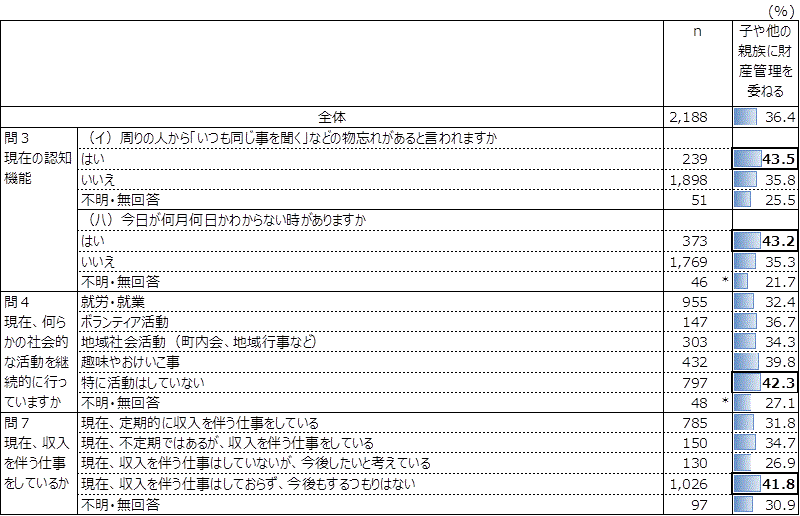
(8)今後の生活の中で準備しているもの(問36)(複数回答)
問36 今後の生活の中で準備をしているものはありますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
今後の生活の中で準備しているものをみると、全体で「身の回りの所有物の整理(財産の整理を除く)」(27.9%)が最も高い。次いで、「お墓の準備」「葬儀の準備」(ともに20.4%)が続く。「準備しているものはない」は37.4%。
図表2-4-8-1 今後の生活の中で準備しているもの(問36)(複数回答)(CSV形式:1KB)
※「その他」「準備しているものはない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
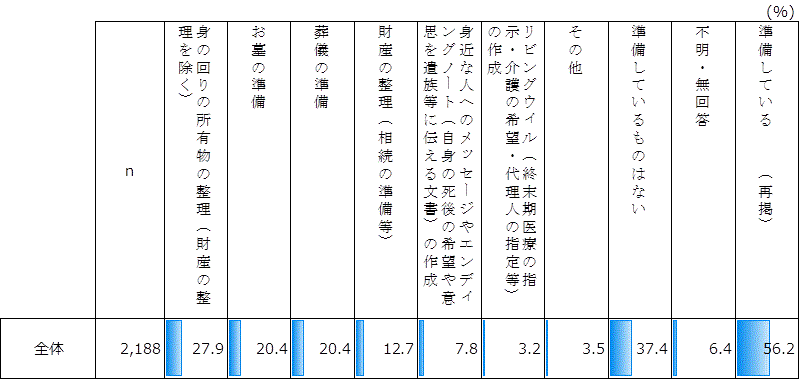
※ 「準備している(再掲)」は「身の回りの所有物の整理(財産の整理を除く)」と「お墓の準備」と「葬儀の準備」と「財産の整理(相続の準備等)」と「身近な人へのメッセージやエンディングノート(自身の死後の希望や意思を遺族等に伝える文書)の作成」と「リビングウィル(終末期医療の指示・介護の希望・代理人の指定等)の作成」と「その他」のうち1つでも選択している割合。
性・年齢でみると、「準備している(再掲)」は男性の80歳以上、女性の75歳以上で6割を超えている。
現在の結婚状況でみると、配偶者あるいはパートナーとは死別している者は「葬儀の準備」(27.2%)が高い。
現在の住まいでみると、持家(一戸建て)と持家(分譲マンション等の集合住宅)は「準備している(再掲)」(それぞれ58.7%、64.5%)が高い。
地域(6区分)でみると、中国・四国は「お墓の準備」(26.3%)が高く、「準備している(再掲)」も65.0%と高くなっている。
図表2-4-8-2 今後の生活の中で準備しているもの(問36)(複数回答)(CSV形式:5KB)
※「その他」「準備しているものはない」「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
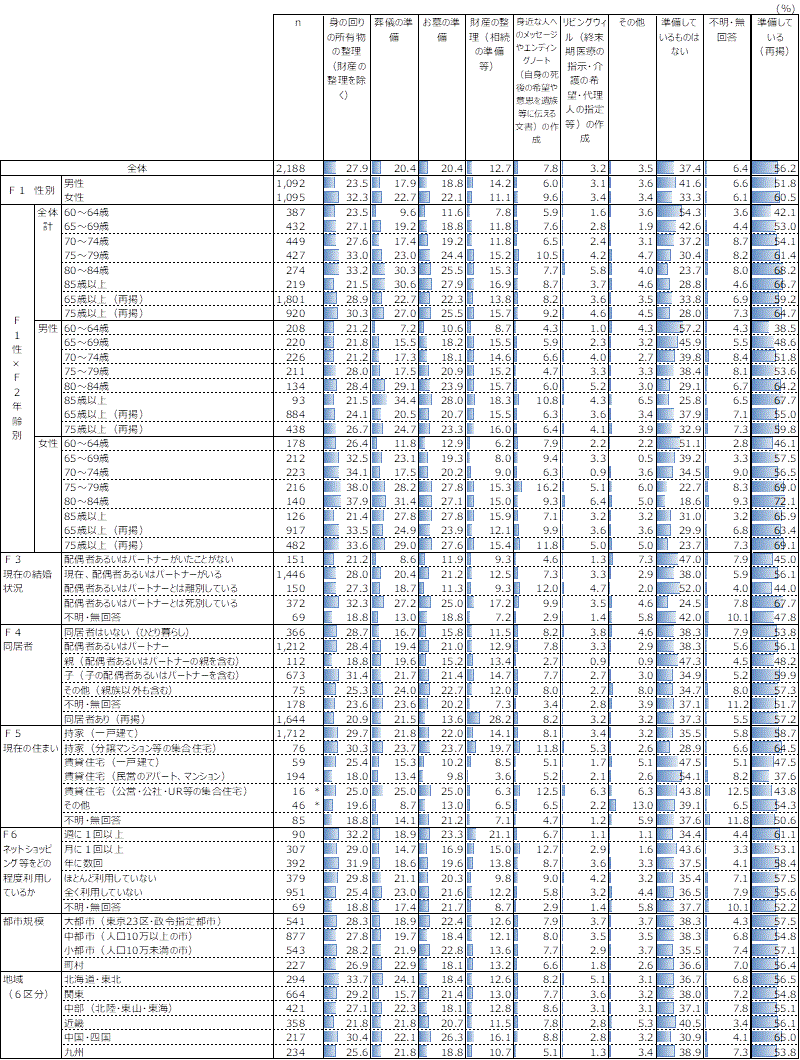
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、「準備している(再掲)」は、『現在、何らかの社会的な活動を継続的に行っていますか(問4)で「ボランティア活動」と答えた者』、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など)」と答えた者』、『現在、収入を伴う仕事をしているか(問7)で「現在、収入を伴う仕事はしておらず、今後もするつもりはない」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-8-3 今後の生活の中で準備しているもの(問36)(複数回答)(CSV形式:2KB)
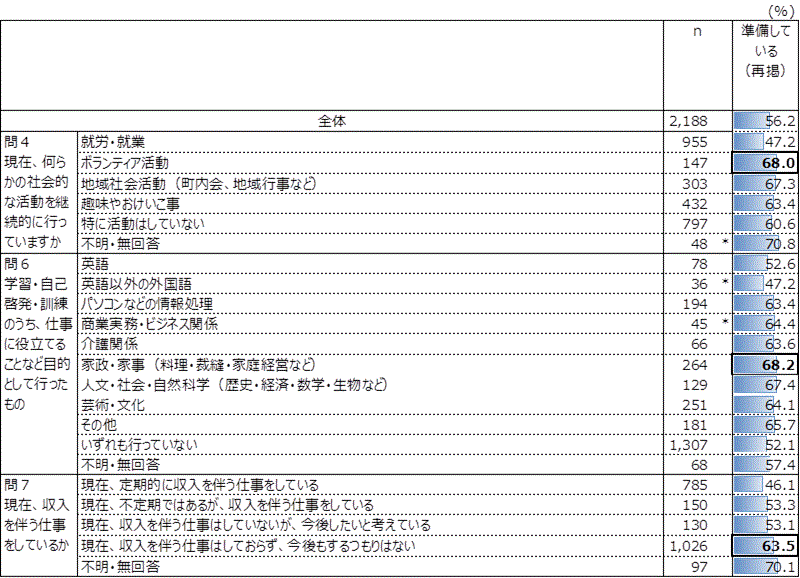
(9)経済生活に必要なサポートについて(問37)(複数回答・3つまで)
問37 今後の経済生活に当たって必要だと考えるサポートについて、次の中からあてはまるものを優先順位の高いものから順番に3つまでお答えください。(○は3つまで)
経済生活に当たって必要だと考えるサポートをみると、1~3番目の合計では「医療費・健康関連の支援(医療費の補助、健康診断や検診の無料化など)」(87.5%)が最も高い。次いで、「身の回りの生活支援」(52.8%)、「公共交通・移動の支援(公共交通機関の割引、シニア向け移動サービスなど)」(51.3%)が続く。
1番目に必要なサポートは「医療費・健康関連の支援(医療費の補助、健康診断や検診の無料化など)」(71.5%)、2番目は「公共交通・移動の支援(公共交通機関の割引、シニア向け移動サービスなど)」(30.3%)、3番目は「身の回りの生活支援」(30.5%)が、それぞれ最も高くなっている。
図表2-4-9-1 経済生活に必要なサポートについて(問37)(複数回答・3つまで)(CSV形式:2KB)
※1~3番目の合計でみて、「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
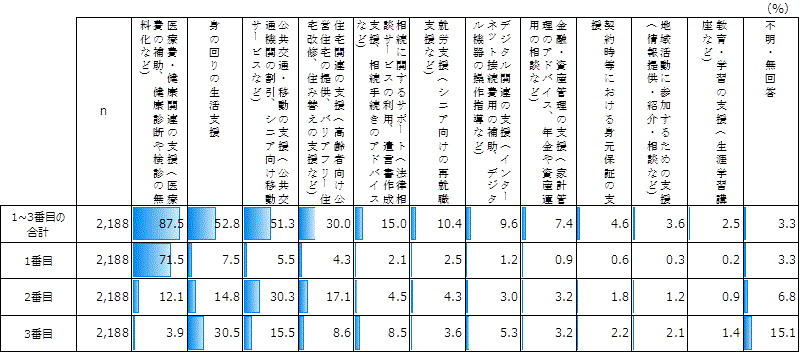
1~3番目の合計について、属性別にみる。
性・年齢でみると、「身の回りの生活支援」は男性の80歳以上、女性の75~79歳、85歳以上で6割を超えている。
現在の結婚状況でみると、現在、配偶者あるいはパートナーがいる者は「医療費・健康関連の支援(医療費の補助、健康診断や検診の無料化など)」(89.8%)が高い。
同居者でみると、同居者はいない者は「医療費・健康関連の支援(医療費の補助、健康診断や検診の無料化など)」(78.7%)が低い。
現在の住まいでみると、賃貸住宅(民営のアパート、マンション)は「住宅関連の支援(高齢者向け公営住宅の提供、バリアフリー住宅改修、住み替えの支援など)」(50.5%)が高い。
都市規模でみると、小都市と町村は「公共交通・移動の支援(公共交通機関の割引、シニア向け移動サービスなど)」(それぞれ60.2%、60.8%)が高い。
図表2-4-9-2 経済生活に必要なサポートについて(問37)(複数回答・3つまで)(CSV形式:6KB)
※1~3番目の合計でみて、「不明・無回答」以外の選択肢(%)の高い順に並べ替え。
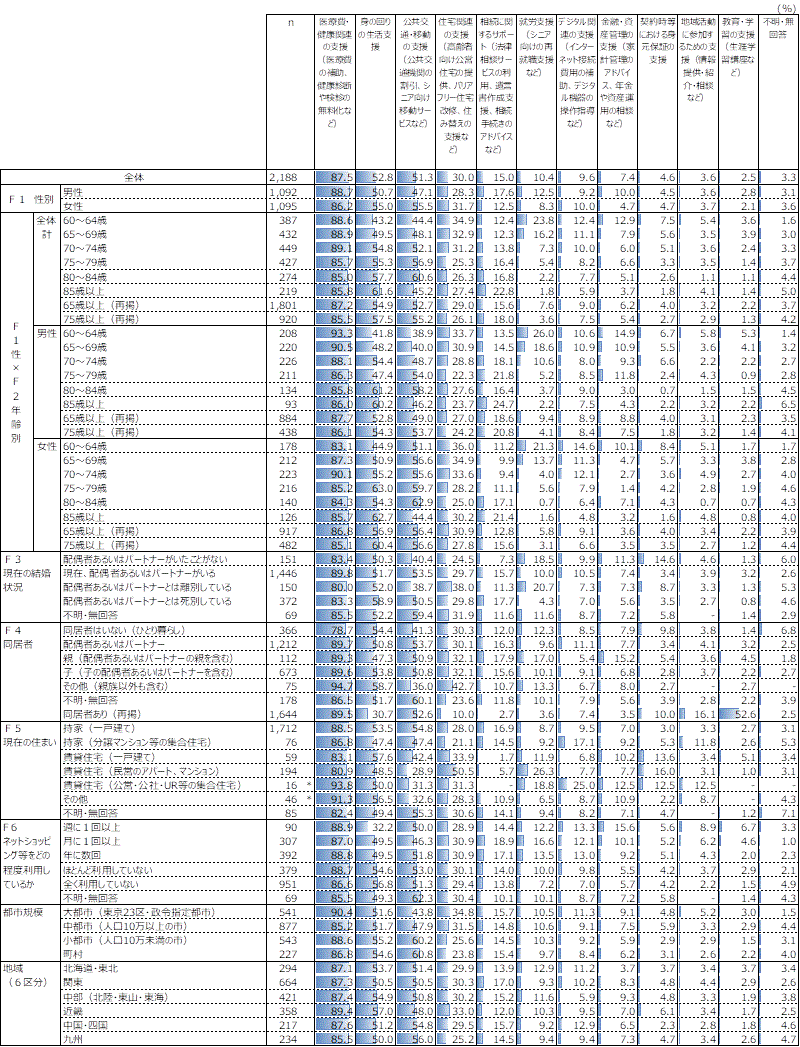
※表側項目のF1性別「その他」についてはn=1のため掲載を省略。
質問間でみると、1番目に必要なサポートで「医療費・健康関連の支援(医療費の補助、健康診断や検診の無料化など)」は、『現在の認知機能(問3)で(イ)周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われると答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」と答えた者』、『預貯金の取り崩しについて(問23)で「時々ある」と答えた者』、『金融資産の総額について(問30)で「2,000~3,000万円未満」と答えた者』、『認知機能の低下に伴う財産管理について(問35)で「配偶者あるいはパートナーに財産管理を委ねる」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-9-3 経済生活に必要なサポートについて(問37)(複数回答・3つまで)(CSV形式:2KB)
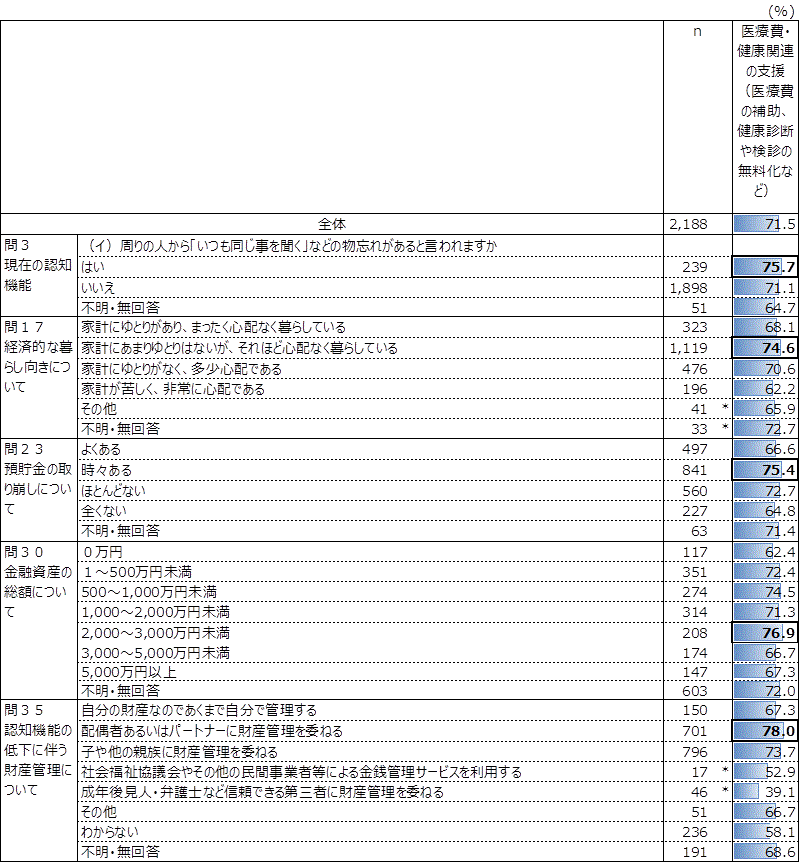
質問間でみると、2番目に必要なサポートで「公共交通・移動の支援(公共交通機関の割引、シニア向け移動サービスなど)」は、『学習・自己啓発・訓練のうち、仕事に役立てることなど目的として行ったもの(問6)で「介護関係」と答えた者』、『収入を伴う仕事をしている主な理由(問12)で「働くのは体によいから、老化を防ぐから」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-9-4 経済生活に必要なサポートについて(問37)(複数回答・3つまで)(CSV形式:1KB)
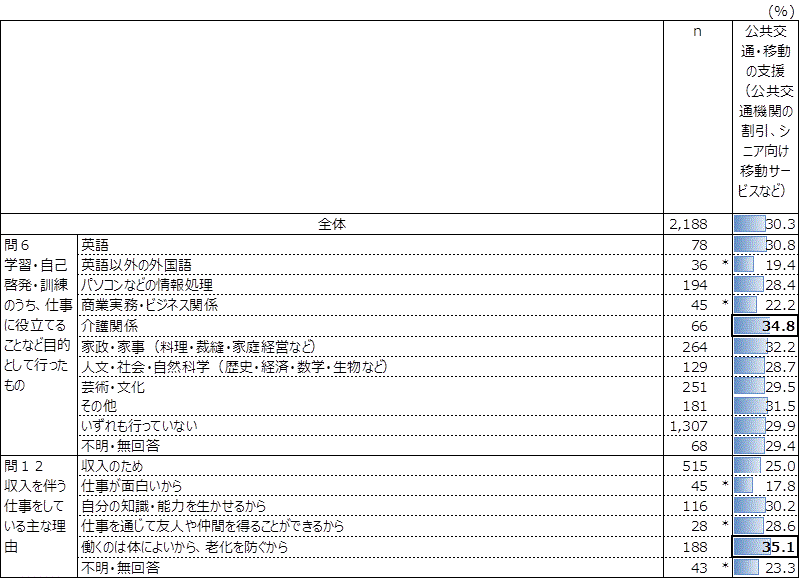
質問間でみると、3番目に必要なサポートで「身の回りの生活支援」は、『生きがいを感じるか(問1)で「あまり感じていない」と答えた者』、『現在の収入を伴う仕事に満足しているか(問11)で「やや不満がある」と答えた者』、『経済的な暮らし向きについて(問17)で「家計が苦しく、非常に心配である」と答えた者』で、それぞれ高くなっている。
図表2-4-9-5 経済生活に必要なサポートについて(問37)(複数回答・3つまで)(CSV形式:1KB)