多くの日本人は、シニアになっても働き続けたいと考えているようだ。本調査でも、8割を超える人がシニアになっても働き続けたい、働き続けたかった、と回答している。ところが、働く人一般を対象にした国際比較調査では、日本人の仕事の中心性(仕事の生活における中心をなしている程度)は近年低下しており、仕事満足度も低いことが指摘されている(米田, 2021)。このギャップはどのように説明されるだろうか。現在のシニアは、現役時代に仕事の中心性が高かったため、現在でも継続して仕事をすることに積極的に意味を見出しているが、若手はそうではないのだろうか。あるいは、シニアの仕事の中心性も現役時代の仕事を離れたことで失われており、収入を得る手段として仕方なく働いているのだろうか。
第3章 調査結果の分析・解説 -1
(本章の内容は、すべて執筆者の見解であり、内閣府の見解を示すものではありません。)
シニアにとっての就労の意味を考える
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 今城 志保
個人の視点からは、就労は幸福感を高める効果が期待される。サクセスフル・エイジングという考え方では、心身が健康であることに加えて、生産的であることと、人とのつながりを持つことがシニアにとって重要であると説かれている(Rowe & Kahn, 1997)。就労を含む趣味やボランティアなどの社会活動には,生産的である機会も、人とのつながりの機会もある。定年退職後のシニアの幸福感に、就労や社会活動がどのように影響しているかを検討した結果、人間関係が保たれること、また自分が社会や周囲の人の役立つ能力があるとの認識が、幸福感を高めた(今城他, 2023)。特に、自分が役立つ感覚は、就労によってより高まりやすいと考えられる。
今日の日本では、シニアが働くことは個人の側からだけでなく、社会的に求められている。高齢者雇用を企業に義務づける法的な後押しもあって、高齢者の就業率は徐々に上昇をしている(令和3年版高齢社会白書)。日本では高齢者の就労は順調に進んでいるように見える。ところが、同白書の高齢就労者の就労理由を見ると、日本は「収入が欲しいから」が51%と最も多く、アメリカ、ドイツ、スウェーデンと比べると、「仕事が面白い、自分の活力になる」の回答が15.8%と少ない。上記に紹介した、働く人一般に行われた調査結果と同様の状況が見て取れる。シニアは仕事にやりがいを感じていないのだろうか。
実際のところ、シニア就労では収入の低下は一般的であるため、収入以外の動機づけがあることは、就労促進を考えるうえで重要である。また、経済的に働く必要のないシニアの就労促進においても、有用な知見となる。そこで、本稿では働くシニアにとって、収入と仕事のやりがいなどの収入以外の理由が、どのように仕事満足に影響しているかについてデータを用いて検討する。
本稿で検討したいもう一つの視点は、仕事の継続性である。これは、企業がシニア社員の雇用継続を行う現状を考えると、検討すべき観点である。そして、働きがいにも関連する。現役時代の活躍を前提とすれば、同じ仕事を続けることができれば、シニアの仕事のやりがいは高まるだろう。実際、再雇用や勤務延長等の雇用継続を行う企業では、これを前提とすることが多いように思われる。一方で、定年前に仕事に収入以外の意味を見出せなかった人や、それ以外の理由で定年を心待ちにしていた人は、現役時代の仕事は継続せず、仕事を変える方がやりがいは高まるかもしれない。
日本企業で社員として働く多くの人たちは、60歳以降に定年を迎える。そして、定年後のキャリアの在り方はさまざまである。①定年前に勤務していた会社・組織に継続雇用(再雇用、勤務延長など)される、②転職する、③独立する(起業・個人事業主など)、④仕事から完全にリタイアするなどに分かれる。①継続雇用、②転職、③独立する人たちの中には、現役時代と同じ仕事をする人もいれば、異なる職場や仕事、役割へと異動する人もいる。私たちの長いキャリアの中にはいくつか転換点がある。新卒時の就職活動や、転職活動がその典型的なものだが、近年、定年もその後のキャリアの意志決定を行う重要な機会となっている。そこで本稿では、「現役時代からの仕事の継続性」の観点から、シニアが就労する際の動機について考える。
本稿で検討するリサーチクエスチョンをまとめると、以下の2つになる。
Ⅰ.シニアにとって、収入以外の働く理由(仕事の意義や就労条件)は、仕事満足度にどのように影響するだろうか
Ⅱ.シニアの働く理由が仕事満足度に及ぼす影響は、現役時代からの仕事の継続性によってどのように影響を受けるだろうか
Ⅰ.収入以外の働く動機(仕事の意義や就労条件)の仕事満足度への影響
最初に、シニアが現在の仕事を選択した理由を3つまで選んだ結果を見る(表1の2列目)。この質問とは別に、仕事をしている主な理由を1つだけ選択するように指示されると、「収入」が最も多く選ばれる(55.1%)。一方で、表1にあるように具体的に現在の仕事を選んだ理由を尋ねると、「給与等が希望に適っている」を選んだのは11.4%にとどまる。つまり、働くことは一義的に収入を得るためではあるが、それは仕事選択の際に必ずしも重視されるわけではないということだろう。そこで、仕事選択理由を用いて分析を行う。
仕事選択の理由は、その他を除き12項目ある。これらを項目の内容をもとに、いくつかのまとまりに分け、該当する項目の選択数を1点から3点の3段階、あるいは1点~2点の2段階として数値化を行った。その結果、仕事選択理由は「給与(1項目・選択有無)」「条件(6項目・3段階)」「意義(3項目・3段階)」「人間関係(2項目・2段階)」の4カテゴリについて、重視する程度を表す指標とした。なお、「給与」については1項目のみ対象としたため、選択の有無(0,1)を用いる。各カテゴリの平均と、年齢コード(60歳から5刻みで85歳以上までの6段階)、健康状態、経済的な暮らし向き、仕事満足度との関係を表1の3~7列目に示す。年齢が若く、経済的な暮らし向きが良い人ほど「給与」を理由に選択する有意な傾向が、弱いもののみられる。また、「意義」を理由に仕事を選択する人は、健康状態が良く、経済的な暮らし向きが良い傾向があった。仕事満足度とは、「給与」と「意義」が有意な正の相関があった。
表1 現在の仕事を決めた理由(複数回答3つまで/n=935)
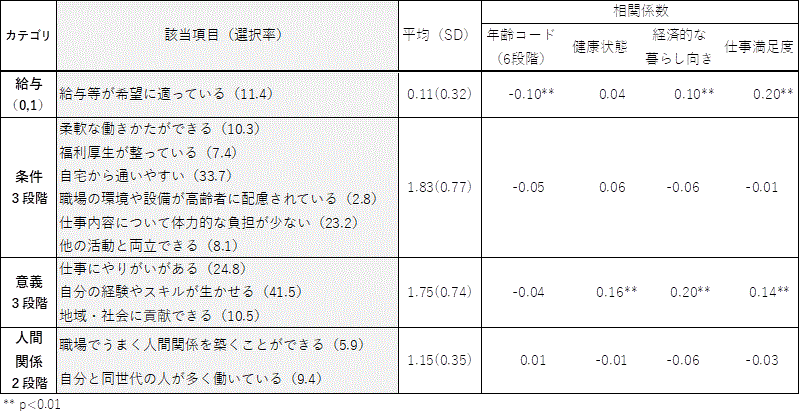
仕事選択理由を説明変数、仕事満足度を目的変数とする一般化線形モデルでの分析を行った。分析にあたっては、性別、年齢、未既婚、健康状態、経済的な暮らし向きといった個人要因、都市の規模や雇用形態、仕事開始時期といった、就労や仕事満足度に影響しそうな変数を統制した。その結果、「給与」と「意義」が仕事満足度を予測する結果となったが、「条件」と「人間関係」は有意な関係が見られなかった(表2)。やはりシニア就労者にとって、収入は仕事満足度に強く影響していたが、加えて仕事に意義を感じることも、満足度を高めたことが示された。
表2 仕事満足度を目的変数とする一般化線形モデル(n=815)
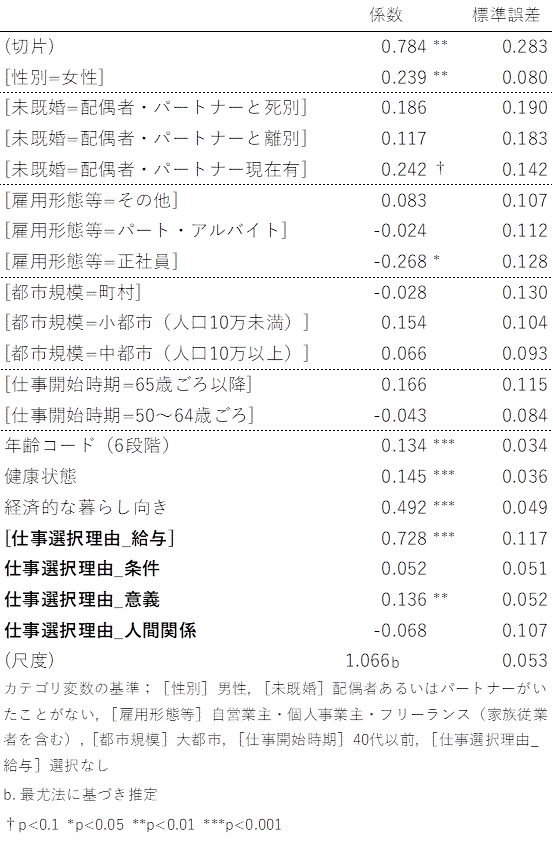
Ⅱ.仕事の継続性が働く動機に与える影響
上述したように、日本のシニア就労を考える際に、現役時代からの仕事の継続性は重要な視点である。著者は2013年ごろから数年間、ホワイトカラーのキャリアチェンジの研究を行った。その際の問題意識は、社会やビジネス環境の変化に対応するために、中高年になってからのキャリアチェンジを余儀なくされる人がいるが、どうすればキャリアチェンジをスムーズに行うことができるのか、というものであった。一般社団法人人材サービス産業協議会(JHR)でのポータブルスキル(業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキル)の開発等を通じて見えてきたこととして、中高年になってキャリアチェンジを経験した結果、自分の強みであるポータブルスキルの活用が難しい環境に置かれた場合でも、仕事の裁量があれば、適応が促進されていたことである(今城・藤村, 2016)。つまり、個人は環境に合わせるだけでなく、近年のジョブクラフティングの議論にあるように、環境に働きかけて変えていくことができるということだろう。
定年を迎えたシニアの多くは、キャリアチェンジを余儀なくされていると言っても過言でないだろう。チェンジの性質は、定年前との「働く集団・組織の変化」と「仕事内容の変化」の2つの側面から見ることができる。たとえば、現役時代からの組織を離れて、同じ仕事で転職する場合は前者のみ、同じ組織内で現役時代と異なる仕事を行う場合は後者のみが変化している。
本稿で扱うデータにはキャリアチェンジに直接関係する項目はないが、シニアが現在行っている仕事を何歳ごろから始めたかを問うた質問(仕事開始時期)がある。これを用いて、40歳代以前から始めた場合を継続性高群(n=389, 43.8%)、50~64歳ごろから始めた場合を継続性中群(n=342, 38.5%)、65歳ごろ以降に始めた場合を継続性低群(n=157, 17.7%)とするカテゴリ変数を作って、分析に用いることとする。40歳代以前からの仕事を継続している場合は、明らかに現役時代に所属した組織や自営で経験してきた仕事を継続していると言ってよいだろう。50~64歳ごろに始めた群には、現役時代に所属した組織で、役職定年や定年後に異なる仕事に就いた人が、一定数含まれていると考える。65歳ごろ以降に始めた場合は、現役時代にいた会社・組織を離れた後の人が多く、仕事も大きく変わった可能性が高い。
表3は、仕事の継続性と関連する変数との関係を見たものである。継続性高群では、自営業主・個人事業主・フリーランスと正社員の比率が高く、パート・アルバイトの比率が低い。継続性低群ではパート・アルバイトの比率が高いことに加えて、65歳ごろ以降に今の仕事を始めた人たちなので、年齢が高い傾向がある。継続性低群は、主観的な健康状態はやや高く、仕事満足度が高かった。高齢者の仕事満足度が相対的に高いことは、他の調査・研究でも報告があることから(例えばNg & Feldman, 2010)、継続性低群の仕事満足度の高さは、対象者の年齢が高いことによる影響が考えられる。ちなみに、少なくとも海外の研究では、高齢者ほど報酬や待遇といった外的なものではなく、仕事の意味づけのような内的なものに動機付けられるとの指摘がある(Kooji, 2011)。継続性低群において、仕事の意義が仕事満足度に及ぼす影響は、他の群と比べて高いのだろうか。
仕事の継続性は、表2の分析において統制変数として仕事満足度との関係を検証した際には、満足度との有意な関係性は確認されなかった。ただし、これは継続性高群を基準とした結果になっているため、改めてデータを3群に分けて分析を行った。結果は表4に示す。
継続性高群では、4つの仕事選択理由のうち、「給与」のみが有意な正の関連を示した。継続性中群では、「給与」が有意な正の関連を示し、「条件」と「意義」も有意傾向ではあったが正の関連を示した。継続性低群では、「人間関係」とのみ、有意傾向で負の関係が見られた。
現役時代からの仕事を続ける人たちほど、「給与」が仕事満足度に及ぼす影響が大きいのはなぜだろうか。シニアになると、一般に収入が減少することが指摘されている。仕事が変わらない場合、同じ給与を得ることを期待する。仕事の変化がない分、給与の変化に目が行きやすくなるため、減少が少ないことが満足度に影響したとも言える。一方で、65歳ごろ以降に新しい仕事を始めた人にとっては、サービス業や清掃の仕事など、給与水準がある程度定まったものが多く、しかも給与が上がることへの期待も小さいと考えられる。従って、経済的暮らし向きが等しいとの前提での解釈にはなるが、「給与」は満足度に影響しなかったと考えられる。つまり、「給与」が満足度に及ぼす影響は、給与への期待水準によって左右される可能性が考えられる。
「意義」については、表2の結果と異なり、継続性高群、継続性低群では仕事満足度との関連がなかった。表2の結果で「意義」の係数は相対的に小さかったことから、継続性別にデータを分割して、サンプル数が少なくなったことで有意な結果が得られなくなった可能性が考えられる。ちなみに、仕事の意義の持つ重要性は、継続性低群と比べて継続性高群で高くなっていた(表3)。継続性の違いによって、仕事に求める意義が質的に異なる可能性もあり、この点は今後の検討課題である。
「条件」については、50~64歳ごろから現在の仕事を始めた継続性中群でのみ、有意傾向ではあったが、満足度にプラスの影響があった。「条件」には、自宅からの近さや、時間の融通の利きやすさ、体力的負担の少なさなど、高齢者にとって望ましいとされる特徴が含まれている。50~64歳ごろから現在の仕事を始めた人は、上記のような条件をベースに新たな仕事を選択して、その結果仕事に満足していると考えられる。ところが、65歳ごろ以降に仕事を始めた継続性低群では、「条件」は仕事満足度には影響しなかった。「意義」の場合と同様、継続性低群の「条件」の平均値は継続性中群と変わらず、一方で仕事の満足度は高くなっていた(表3)。やはり継続性低群の仕事満足度は、仕事の選択理由と別の要因によって高まった可能性が高い。
表3 仕事の継続性と他の変数との関連性(n=888)
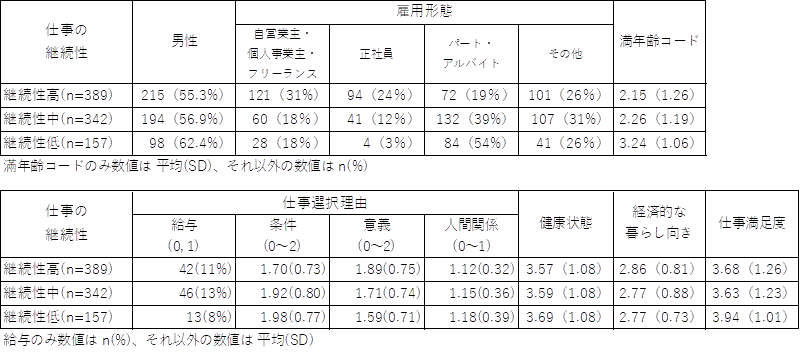
表4 仕事継続性別の仕事満足度を目的変数とする一般化線形モデル
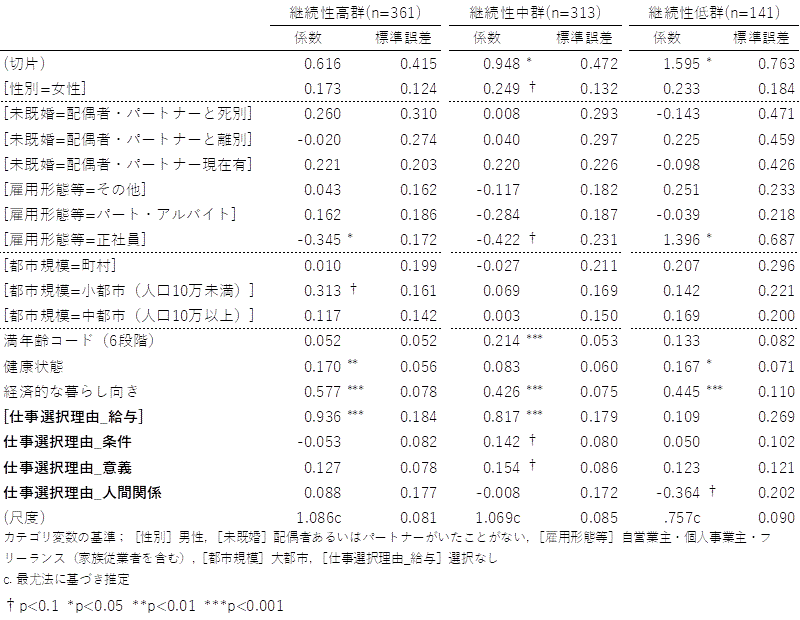
最後に、改めてリサーチクエスチョンに沿って、本分析の結果をまとめる。シニア就労者にとって、給与は仕事満足度に影響していた。影響の程度は、現役時代からの仕事を継続している人の方が強い傾向があった。給与によって仕事に満足する程度は、個人が期待する給与水準に応じて変化する可能性を指摘した。現役時代からの仕事を継続している人ほど、その時の水準で給与を期待するため、満足度に及ぼす影響が強いと考えられる。給与の影響に加えて、シニア就労者が自分にとって意味のある仕事を行っているとの認識も、仕事満足度にポジティブな影響が見られた。現役時代からの仕事を継続している人の方が意義で仕事を選ぶ傾向が強かったものの、満足度に及ぼす影響について継続性による違いは十分確認できなかった。特に、65歳以降に今の仕事を始めた人は、仕事の満足度は高いものの、給与や仕事の意味づけの影響は見られなかった。この人たちにとって、仕事の選択理由には入っていないが、例えば働くこと自体が身体によい、老化を防ぐといったことが満足度に影響している可能性もあり、今後の検討が必要である。

