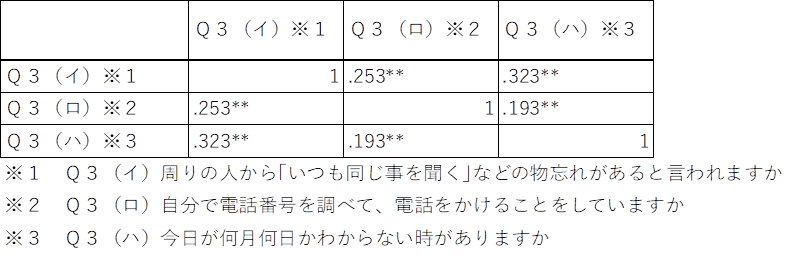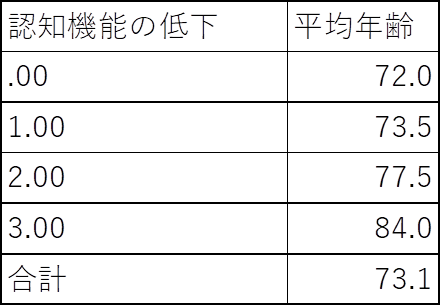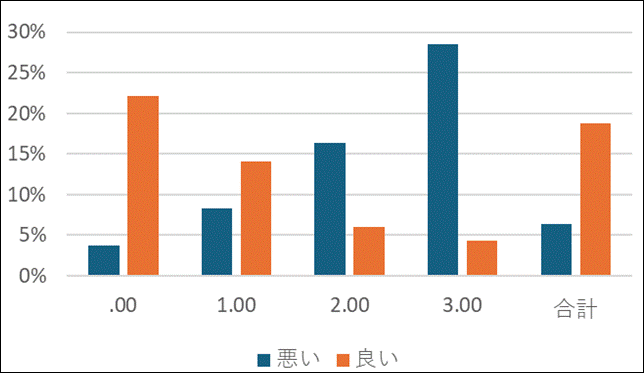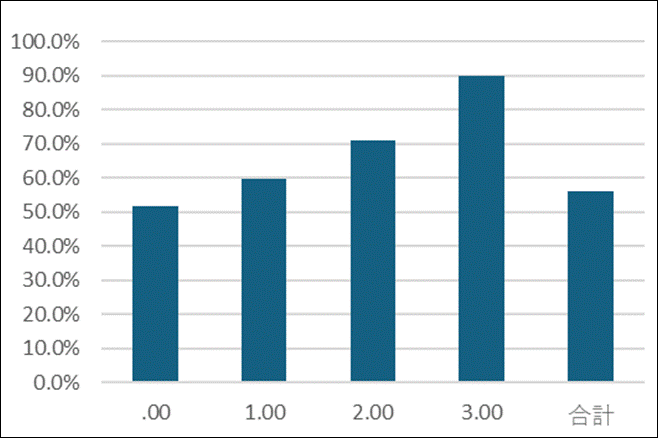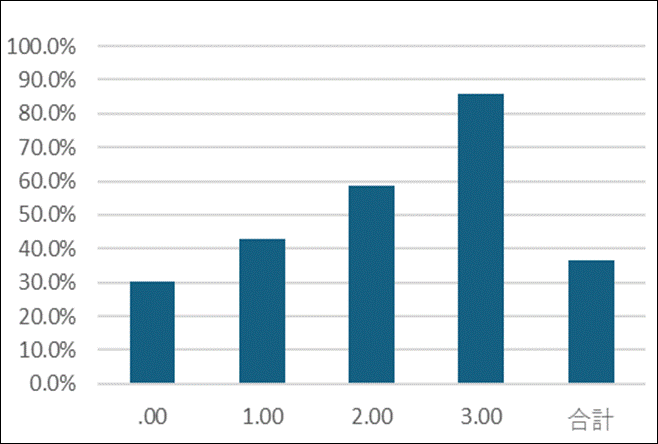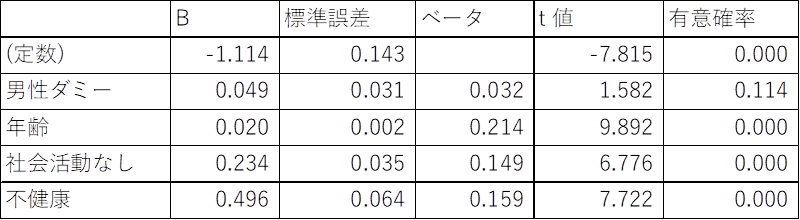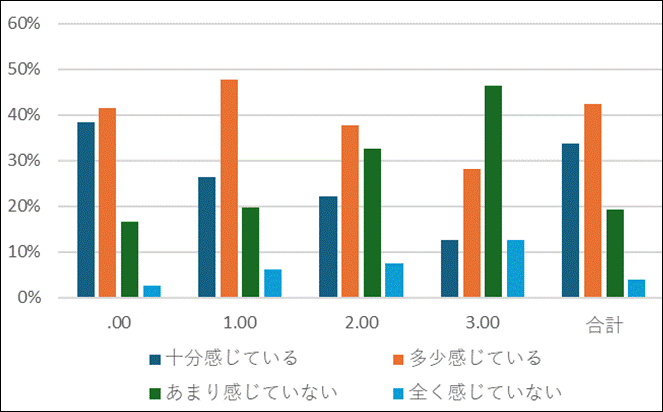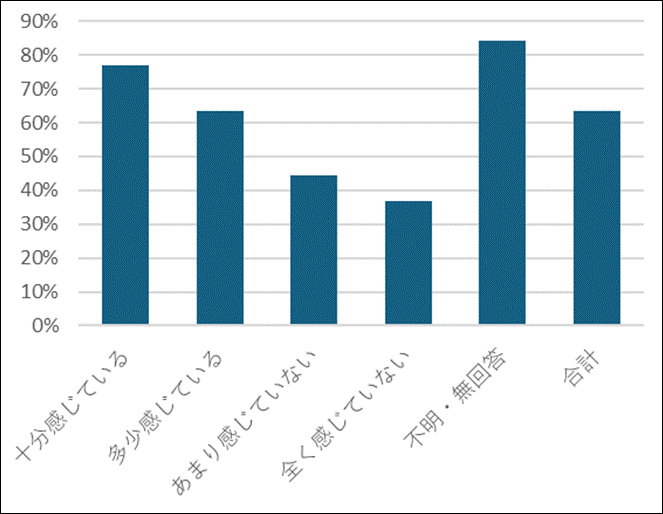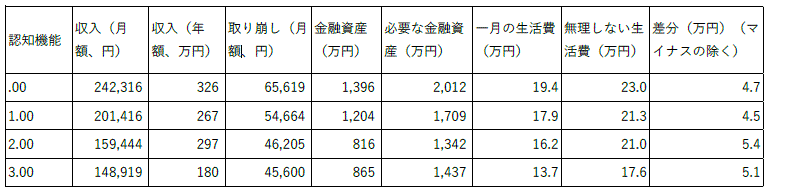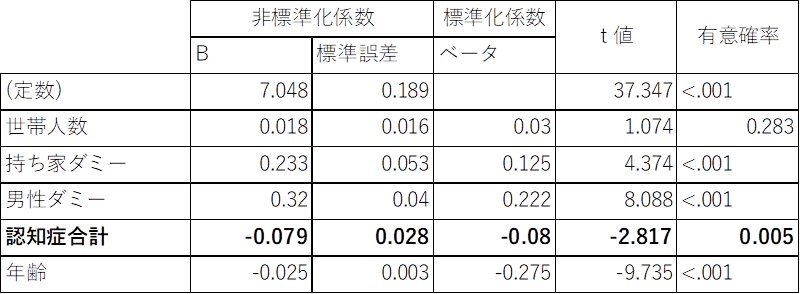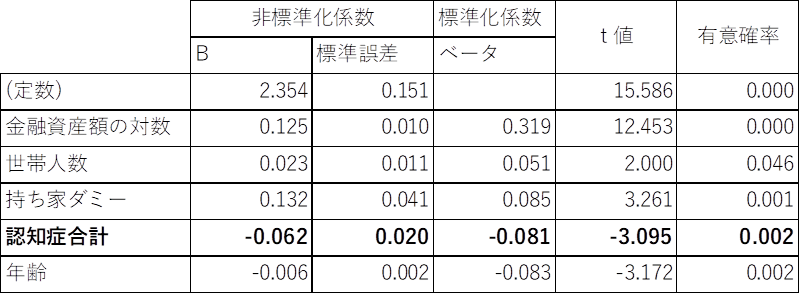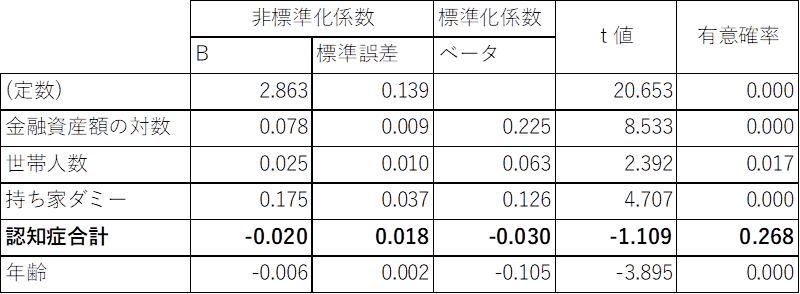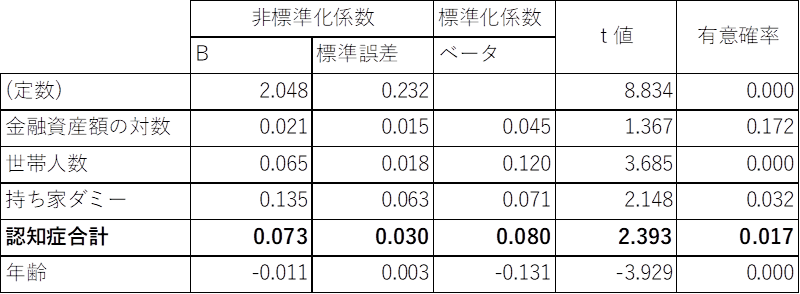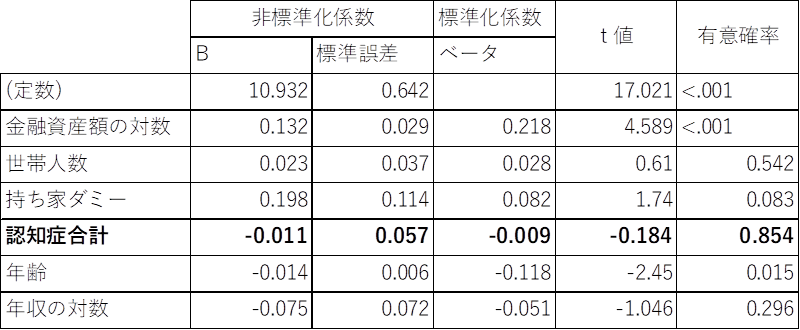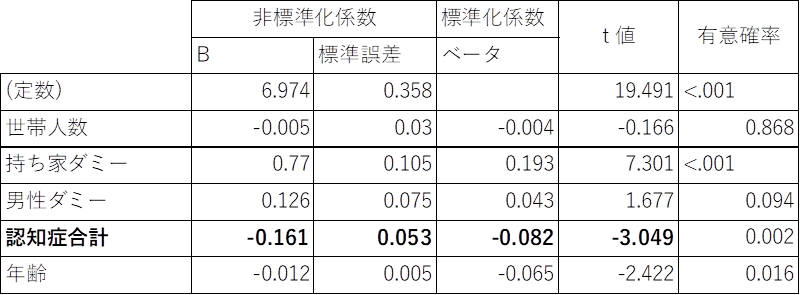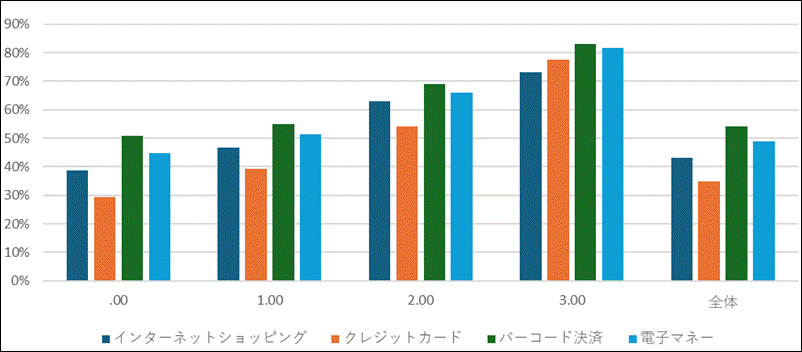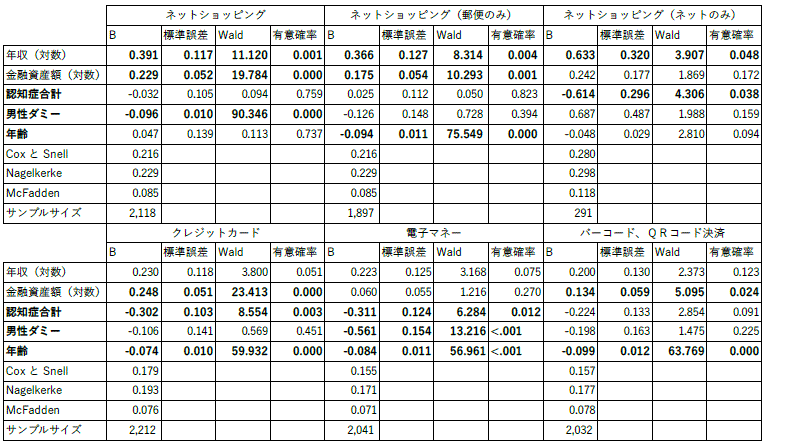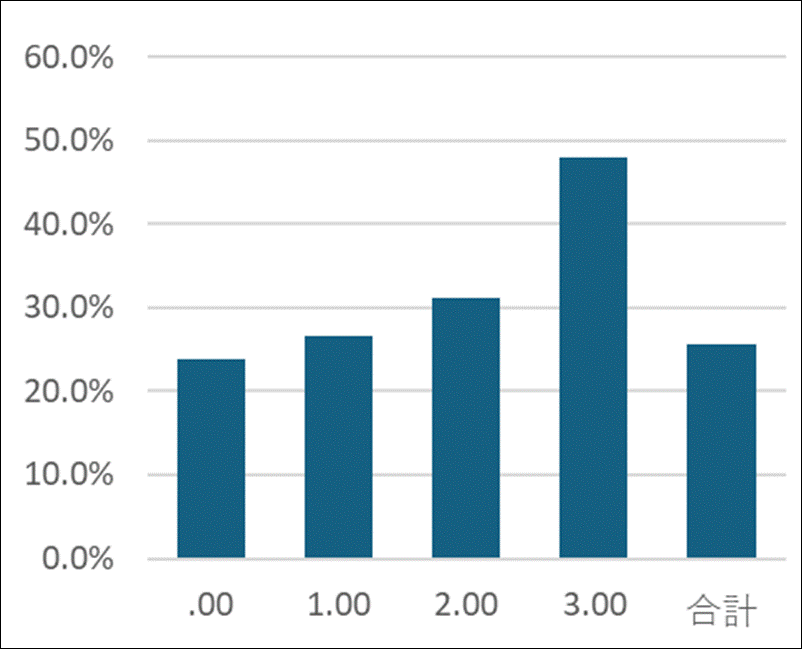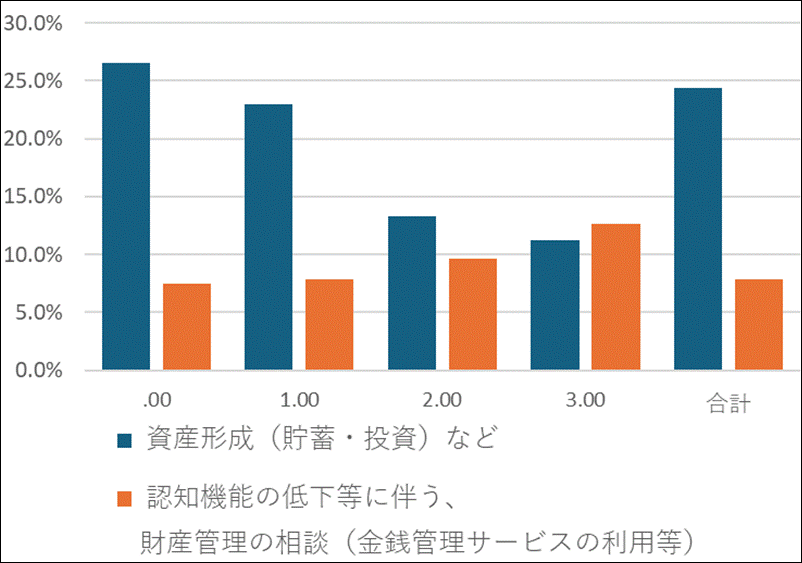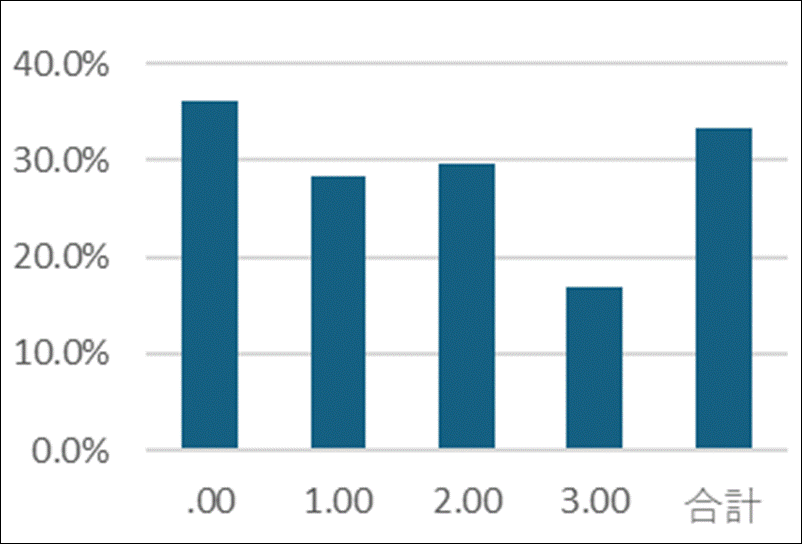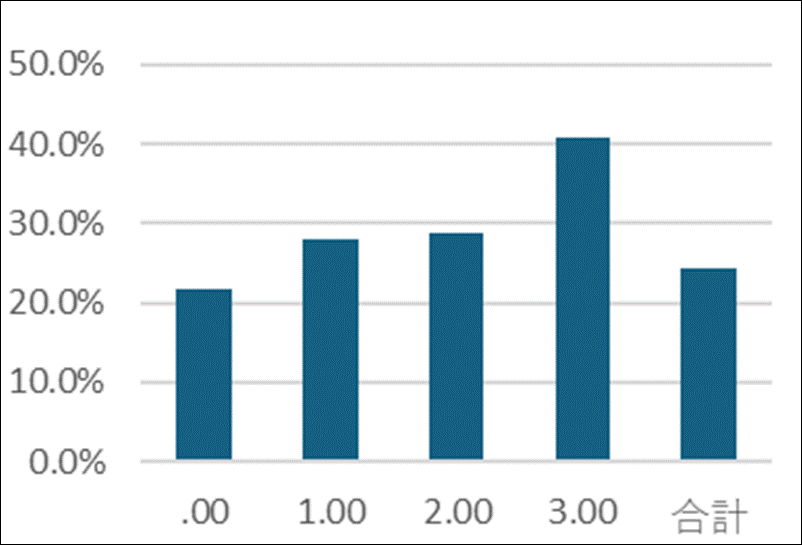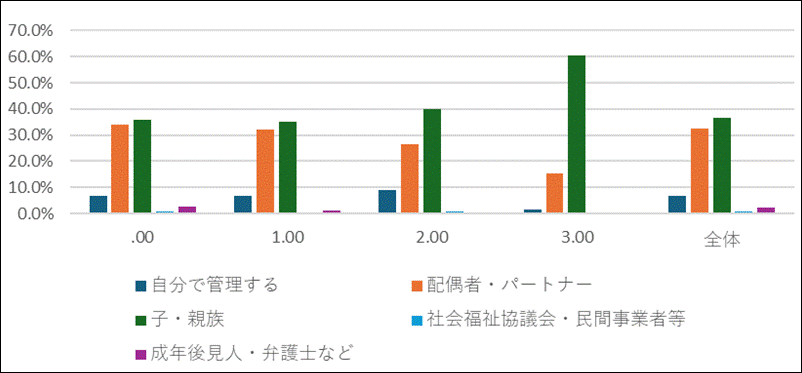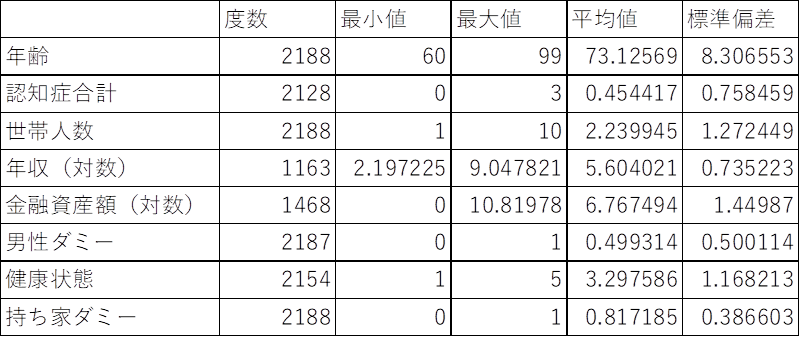(本章の内容は、すべて執筆者の見解であり、内閣府の見解を示すものではありません。)
認知機能の低下とその経済活動への影響
慶應義塾大学経済学部教授 駒村康平
1.問題意識-認知機能の低下とその社会経済活動への影響について
人は誰でも加齢とともに認知機能1の低下は避けがたい。認知機能の低下は、要介護の発生率を高めるとともに、社会経済活動にも様々な影響を与える。厚生労働省の推計によると軽度認知障害と認知症患者の合計は、1000万人を超え、今後も増加を続けると見込まれる。2024年9月に閣議決定された高齢社会対策大綱では、こうした認知機能の低下のために社会的な取り組みの必要性が指摘されている。
本調査では問3で認知機能の状況に関する簡易な調査を行っている2。本論では、この問3の回答について、該当する数が多いほど、認知機能低下を示している変数として扱い、認知機能の低下の要因、低下のもたらす影響、その対策について検討する。
2.分析に使用した変数
(1)認知機能の状況
問3(イ)「いつも同じ事を聞く」(はい、10.9%)、(ロ)「電話をかけることをしている」(いいえ、16.7%)、(ハ)「日にちがわからない」(はい、17.0%)は、認知機能の低下の傾向を示している。イロハの該当数から認知機能の低下尺度(0から3の4段階)を計算した。3
表1(認知機能の相関性)はイロハの状態の相関係数を見たものであり、「イとハ」、「イとロ」、「ハとロ」の順番で正の相関が強いことが確認できる。
つぎに該当数別に見たのは表2であり三つとも該当する人(できない人)は回答者の3.3%存在している。
表1 認知機能の相関性
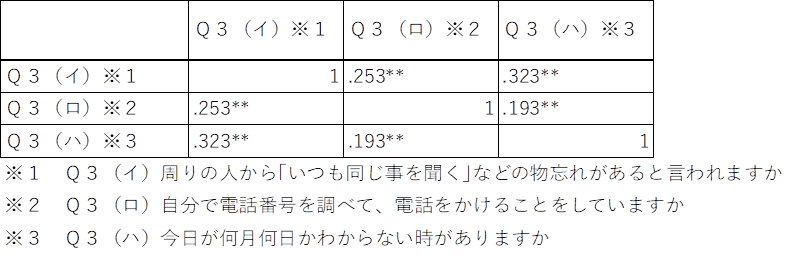
(2)認知機能の低下と関係がある変数
1)年齢・健康状態との関係
年齢、健康状態(主観的)と認知機能については、認知機能低下のスコアが高いほど平均年齢が高い(表2認知機能と平均年齢)。
そこで認知機能の低下と年齢の相関係数は0.279(1%水準で有意)となった。これは高齢者ほど軽度認知障害、認知症の有病率が高くなる先行研究と整合的である。次に健康状態(問2)との関係であるが、認知機能が低下するほど、健康状態が「良い」という回答は減少し、「悪い」という回答が増加することが確認できる(図1認知機能と健康)。
表2 認知機能と平均年齢
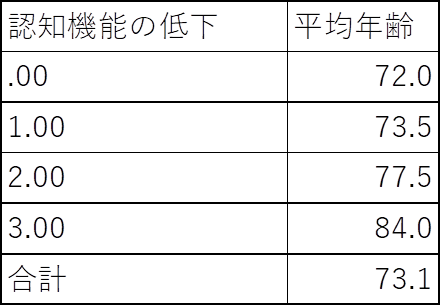
図1 認知機能と健康
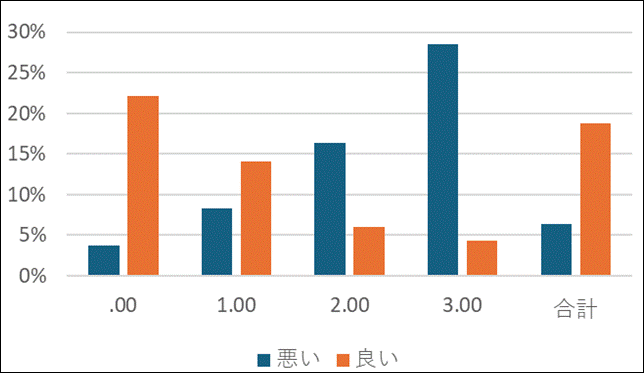
2)社会活動と認知機能の関係
問4で、就労・就業ほか様々な社会活動の状況について質問している。認知機能は社会活動と密接に関係があることが確認されているが、図2で見ると、認知機能が低下すると就業率が下がっていることが確認できる。ただし、これは、①社会活動への参加が少ないと認知機能が低下する、②認知機能が低下すると社会活動ができなくなる、という点で双方向の可能性もある点は留意する必要がある。また就業も含めて社会活動をしていないという回答は認知機能の低下とともに増加することも確認できる(図3認知機能と社会活動なし)。
図2 認知機能と非就業
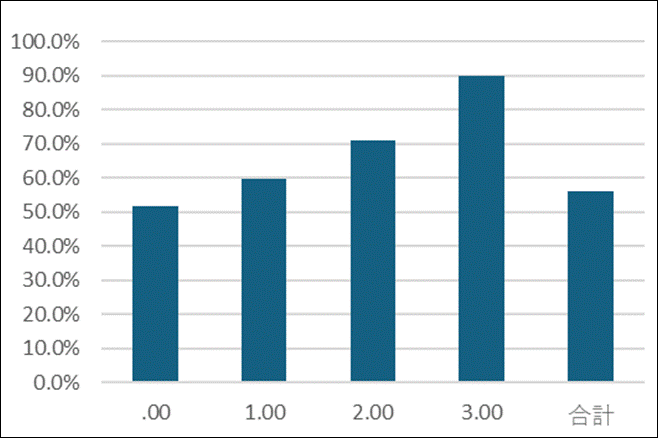
図3 認知機能と社会活動なし
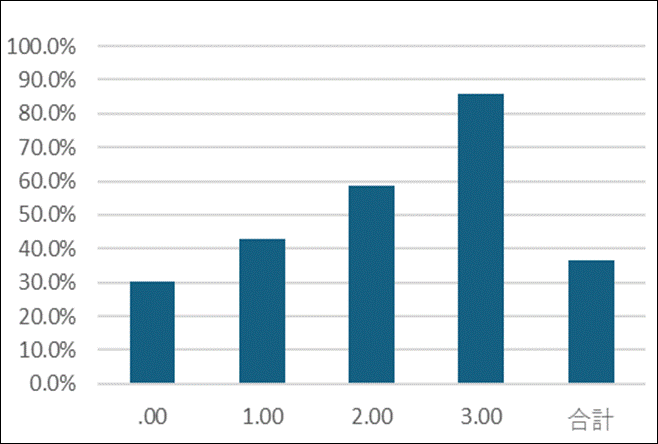
3.認知機能の低下に関する分析
(1)認知機能の低下に関する重回帰分析の結果
認知機能の低下に年齢、性別、健康状態、社会との関係が与える影響について重回帰分析を行った(表3認知機能重回帰)。
表3 認知機能重回帰
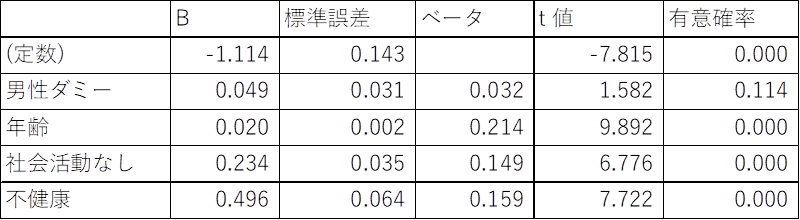
その結果、年齢、健康状態(良くない)、社会活動(参加していない)はいずれも有意に認知機能の低下と関係していることが確認できた。他方、性別(男性ダミー)については、有意な影響は確認できなかった。一般的には女性のほうが認知症のリスクは高いとされているが、前述したように本調査では、軽度の認知機能低下を把握したものとされ、この段階では、男女の差は見られないという先行研究の結果と整合的である。
(2)認知機能、社会活動と幸福度との関係
問1で、「どの程度生きがいを感じているか」という問いがある。これを幸福度とみなし、認知機能の低下、社会活動をしていないという回答との関係を分析した(図4認知機能と幸福度)。認知機能の低下ともに幸福度が低下していくことが確認できる。また社会活動と幸福度の関係(図5幸福度と社会活動)を見ると幸福度の高い人ほど社会活動をしている割合が高い。他方、幸福度が低い人は、社会活動をしていないことが確認できる。この結果、社会活動の有無を社会との関係すなわち「孤独・孤立」を示したものと解釈すると、孤独・孤立は認知機能の低下と関係性があり、同時に幸福度も下げているという可能性が示唆される。
図4 認知機能と幸福度
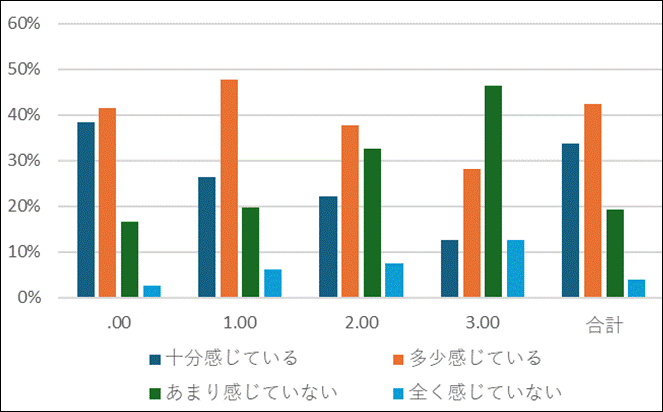
図5 幸福度と社会活動
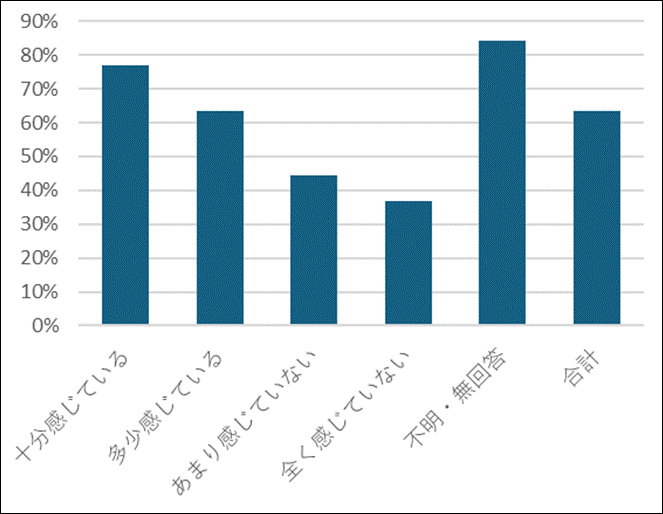
(3)認知機能と経済状況の関係
1)認知機能の状況と金融資産、所得の関係
表4(認知機能と経済状況)は、認知機能低下と収入(月、年収、問19)、現在の生活費(問20)、無理なく生活するために必要な生活費(問21)、両者の差分(問21-問20)4、取り崩し額(問24)、金融資産(問30)、必要な金融資産額(問31)の平均値を比較したものであり、認知機能の低下とともに一部を除き減少する傾向にある。そこで、1)収入(表4-1)、2)生活費(表4-2)、3)無理ない生活費(表4-3)、4)1)と2)の差分(以下、差分)(表4-4)、5)取り崩し額(表4-5)、6)金融資産(表4-6)5を被説明変数にして、主要説明変数を男性ダミー、持ち家、世帯人数、年齢、認知機能等で重回帰分析を行った結果、1)生活費、3)差分、5)金融資産、6)収入(対数)について、認知機能の低下が有意にマイナスの影響を与えていることが確認できた(表4-1から6、経済状況の重回帰分析)6。
表4 認知機能と経済状況
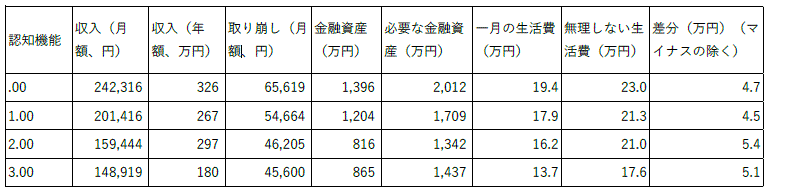
表4-1 収入
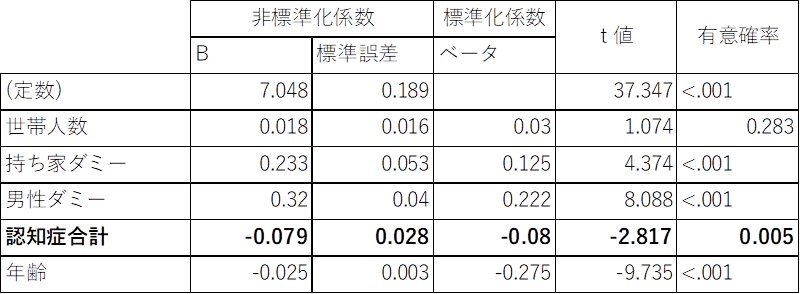
表4-2 生活費
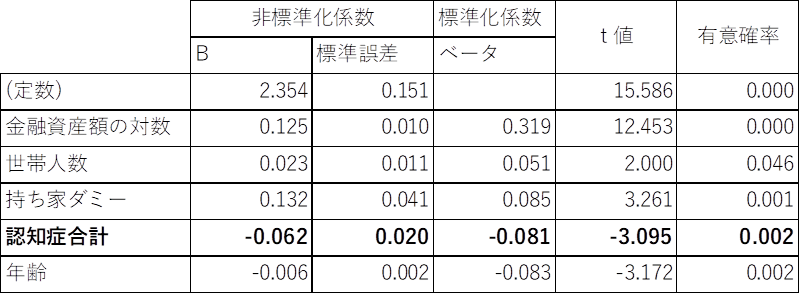
表4-3 無理ない生活費
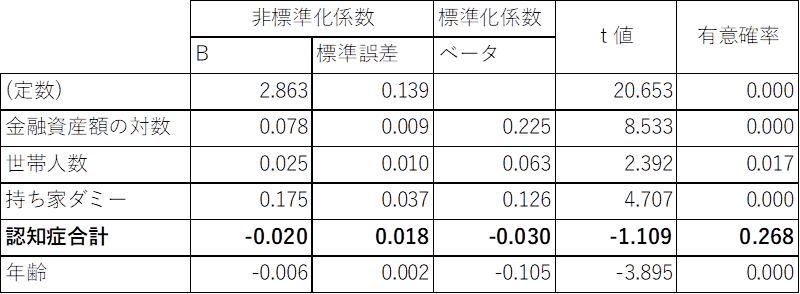
表4-4 収入と生活費の差分
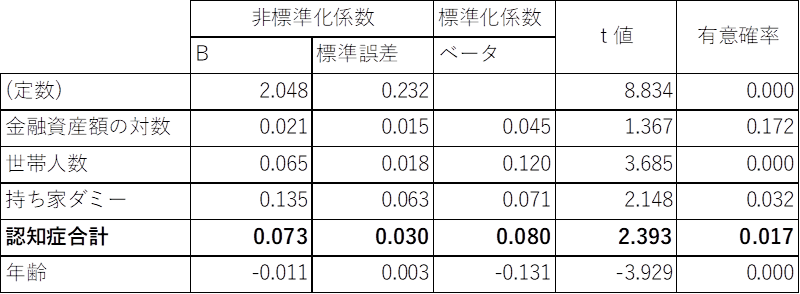
表4-5 取り崩し額
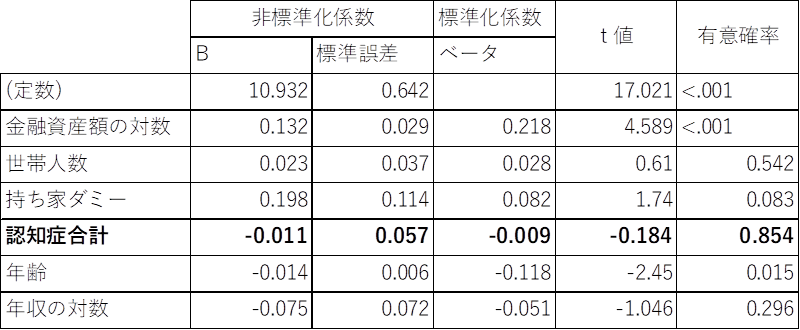
表4-6 金融資産
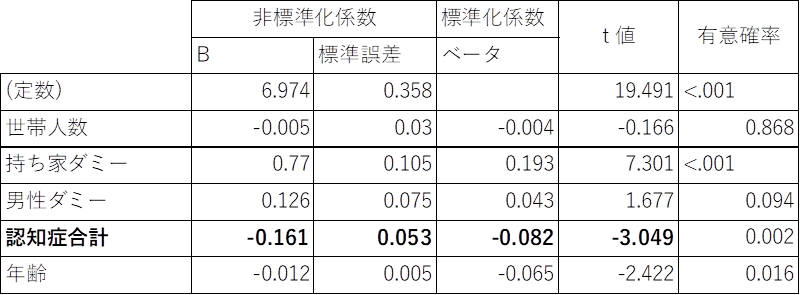
2)認知機能の低下と決済手段との関係
認知機能の低下は、日々の経済活動の決済手段にどのような影響を与えるのか、認知機能の低下とネットショッピング(F6)、決済手段(F7)関係を見たのが(図6認知機能と使わない決済手段)である。ネットショッピングは「全く利用しない」、クレジットカード、バーコード決済、電子マネーは「使用しない」という回答の割合は、認知機能の低下とともに増加する傾向がある。
図6 認知機能と使わない決済手段
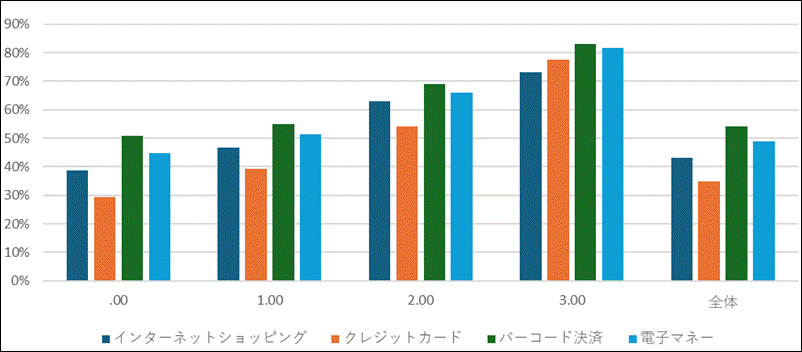
この選択について、順序ロジット分析を行った(表5順序ロジット)7。説明変数は、年収(対数)、金融資産(対数)、認知機能の低下、男性ダミー、年齢とした。
分析結果は、ネットショッピングについては、年収、金融資産がプラスで有意であるが、認知機能の低下と年齢は有意な影響が確認できなかった。クレジットカード(以下、クレカ)については、金融資産がプラスに、認知機能の低下、年齢がマイナスに有意の影響を与えていた。電子マネーは認知機能の低下、男性、年齢がマイナスに影響を与えていた。バーコード決済については、金融資産がプラスに、年齢がマイナスに影響を与えていた。バーコード決済はスマートフォンがないとできないが、スマートフォンの保有率は年齢別に大きな差があるため、年齢の影響大きく出ていると考える8。
クレカ、電子マネーにおいては、認知機能の低下は有意に利用率を下げているが、ネットショッピングでは認知機能の低下は有意な影響を与えていない。ただし、調査設計上、郵便回答者とネット回答者が混在しているため、両者を分けて分析した。この結果、郵便回答者では、年齢がマイナスの影響を与えているが、認知機能は有意な影響を与えていなかった。一方、ネットでの回答者では年齢は有意でなくなる一方で、認知機能は有意にマイナスの影響があった。ネットショッピングは、本人確認が複雑な場合もあり、認知機能の低下している人にとっては、対応できない可能性が推測される。他方、クレカについても、使用時に暗証番号を求められこともあるため、認知機能の低下の影響を受けやすいと考えられる。
表5 決済手段順序ロジット
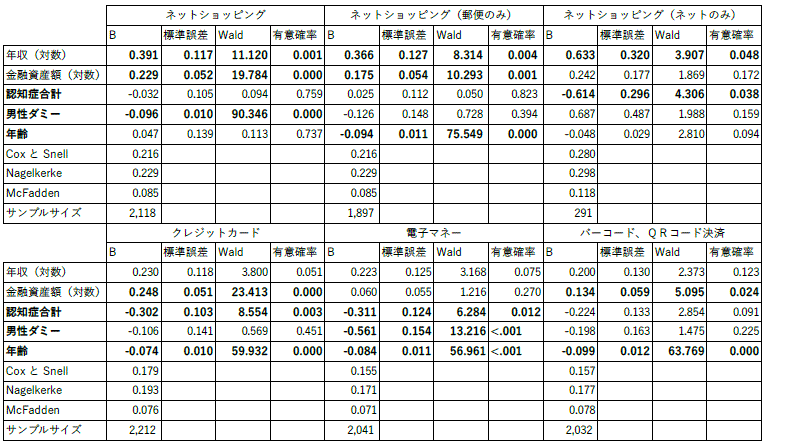
(4)認知機能の低下に対する対応状況について
認知機能の低下に対する不安は問28、その対応については問29が調査している。
1)認知機能の低下に対する不安なことについて
問28では、今後の生活における経済的な不安について質問している。「認知機能の低下等によって財産の適正な管理ができなくなること」の不安については、認知機能の低下している人ほど、この不安を強く感じている(図7財産の管理ができなくなること)。
2)認知機能の対策
問29では、老後の備えを聞いているが、認知機能の低下している人ほど、資産形成(貯蓄・投資)などを選択する割合は減少する。この一方で、「財産管理に関する備え」を回答する割合は、認知機能の低下とともに増加することが確認できる(図8老後の備え)。
図7 財産の管理ができなくなること
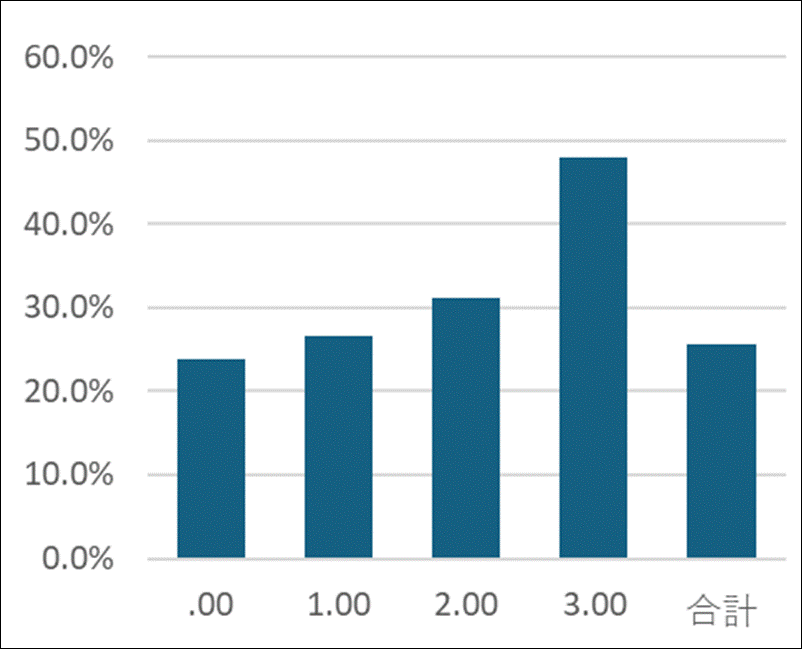
図8 老後の備え
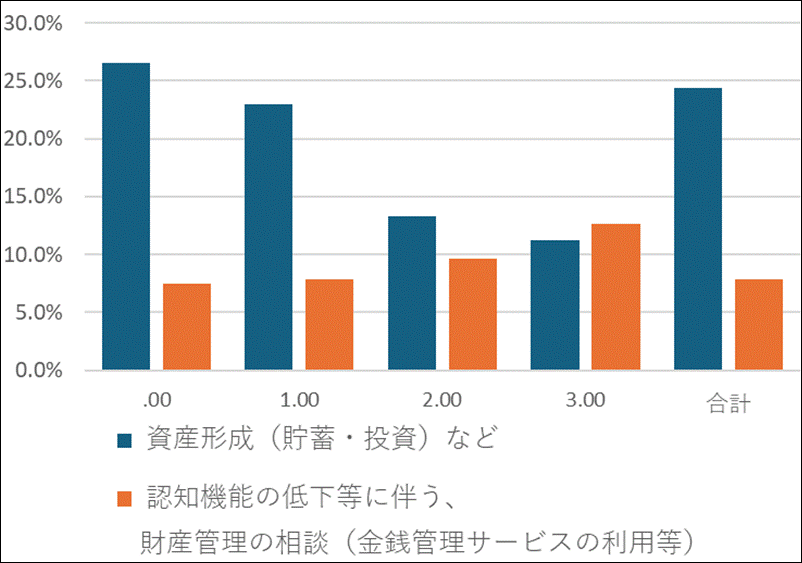
3)将来の資産の使い方
問34の将来の財産の使い方であるが、認知機能の低下とともに財産を「自分のために使う」という回答は減少する(図9自分のために使う)。他方で、認知機能の低下とともに「残す財産はない」という回答も増える(図10残す財産はない)。
図9 自分のために使う
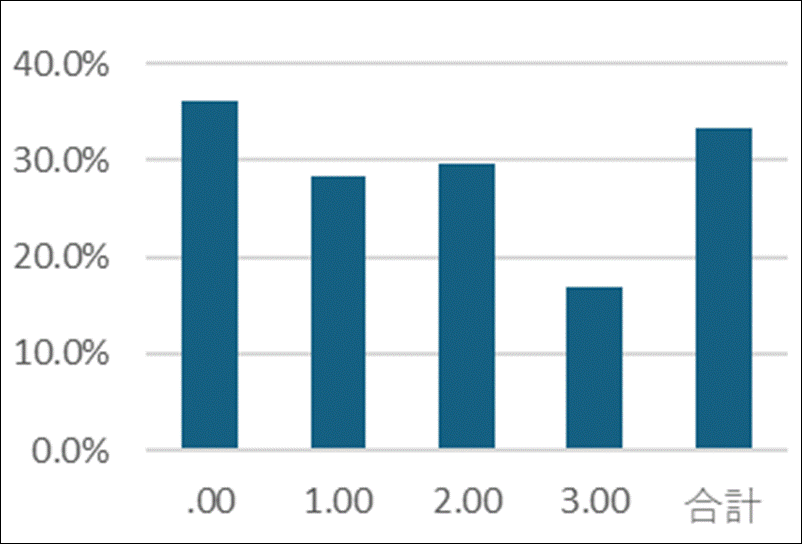
図10 残す財産はない
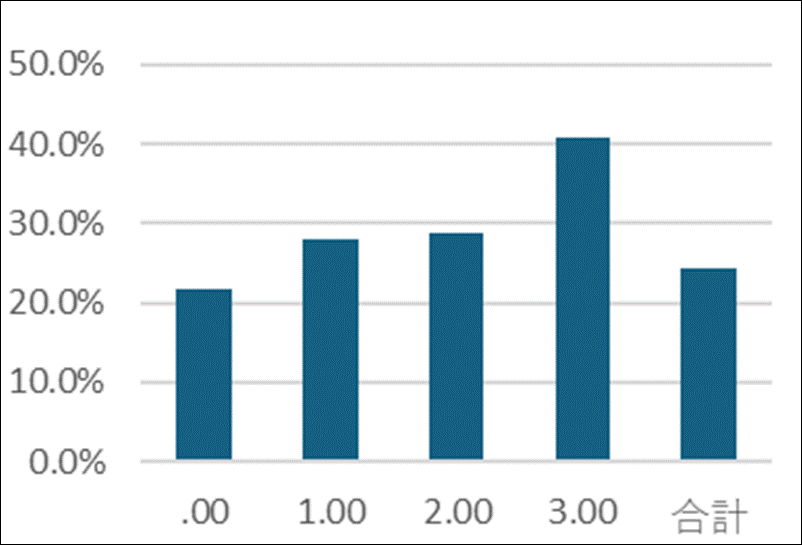
4)資産の管理
問35では「認知機能の低下などで財産の管理に不安が生じた場合」への対応を聞いているが、認知機能が低下するほど「子・親族」などに委ねる割合が上昇する。他方で、認知機能が低い人のなかでも、成年後見や社会福祉協議会という回答はほとんどない(図11認知機能の低下により誰に財産を委ねるか)。
図11 認知機能の低下により誰に財産を委ねるか
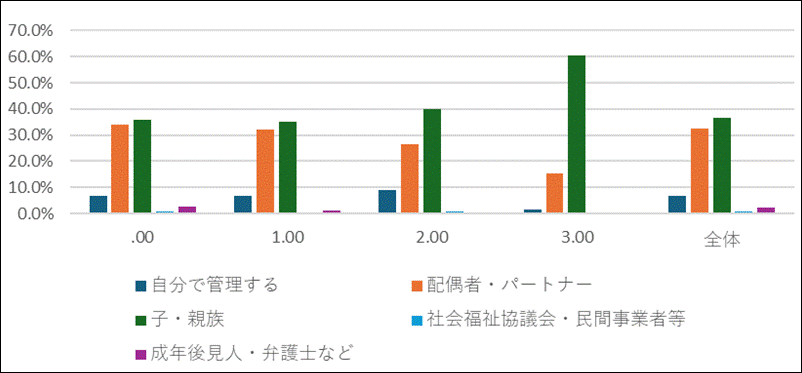
4.まとめと考察
以上、認知機能の低下の原因、その低下が経済活動に与える影響及びそれに対する対応について分析を行った。高齢者が経済行動を行う場合、予算制約(収入、資産)だけではなく、認知機能の影響を受けることになると想定したが、分析の結果、認知機能は社会経済活動に一定の影響が発生していることが確認できた。1)貯蓄や資産運用などライフサイクル的な性格のある経済活動は、年齢の影響がでること、同時に2)認知機能の低下には、年齢の影響が大きいこと9、3)認知機能と社会活動の因果関係が逆の可能性もあるため、より掘り下げた分析が必要であるため、認知機能の低下と社会経済活動に関する縦断調査が必要になる。
今後、認知機能の低下が進む75歳以上人口が増加することが予測される。認知機能の低下が経済活動に与える影響が大きくなるため、その対応が急がれる。例えば、決済手段のデジタル化が急速に普及しており、今後、デジタル技術に慣れた高齢世代が増えるため、対応が可能な高齢者も増加すると想定される。一方で、認知機能の低下にともないデジタル技術への対応力が低下する高齢者、つまり次第に加齢にともない認知機能の低下が進むためデジタルツールの操作能力が低下する高齢者も増える点に留意が必要である。認知機能の低下した高齢者が社会経済活動から取り残されないように、デジタル技術のユーザーインターフェースについては、認知機能が低下した高齢者でも使えように改善する必要がある10。
またネットショッピングにおいては、ダークパターンなどによる消費者問題も増加傾向にあり、認知機能の低下といった脆弱性の問題に対応できるように消費者保護政策の見直しも重要になる11。
(参考文献)
駒村康平(2024)「認知機能の低下が経済行動に与える影響とその政策的対応-金融老年学を手がかりに」Dementia Japan,日本認知症学会誌 38(2) 220-227 2024年4月.
東京都福祉保健局(2014)『認知機能や生活機能の低下が見られる地域在宅高齢者の実態調査報告書』
Johnson Jeff・Finn Kate(2019)『高齢者のためのユーザインタフェースデザイン ユニバーサルデザインを目指して』榊原 直樹(訳)、近代科学社.
(参考資料)記述統計量
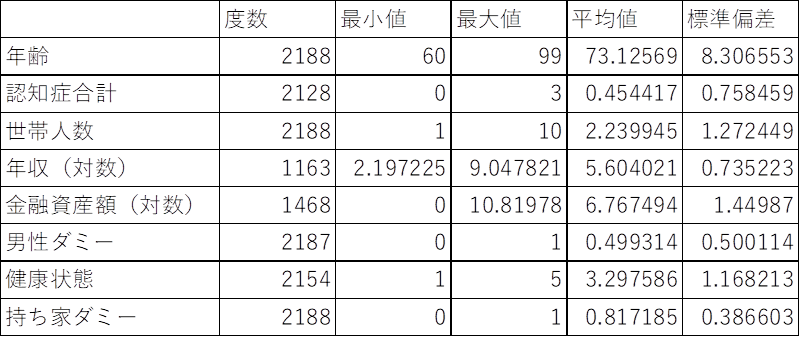
1認知機能は、情報を認識・理解して、行動を遂行するための脳であり、記憶力や注意力、判断力、遂行力を意味している。
2チェック項目は、平成27年 厚生労働省基本チェックリスト、認知症項目18~20を使用した。厚生労働省基本チェックリストは25項目となっており、得点が高いほど認識機能や社会生活に支障がでる可能性があるとしている。イ)、ハ)は認知機能の低下を、ロ)は生活機能低下を反映しているとされる。東京都福祉保健局(2014)参照
3ただし、回答者は本アンケートに対して、郵便もしくはネットで回答できていることから、回答者の認知機能の低下の程度は、自身の認知機能の低下を把握できなくなるレベルの中度、重度の認知症を示しているわけではなく、主観的認知機能低下、軽度認知障害から初期の認知症あたりに相当し、自身の認知機能の低下を把握できるレベル認知機能低下を示しているものと解釈し、それぞれの回答に大きな影響を与えているものではないとした。他方で、認知機能が低下した人からの回答が行われていないという回収時のバイアスの存在は否定できない。
4差分がマイナスの回答は対象から外した。
5いずれも対数。
6東京都福祉保健局(2014)においても、認知機能の低下が見られる高齢者に低所得者が多いことが確認されている。
7クレジットカードについては、「全く利用しない」から「週1回以上」、クレジットカード、バーコード決済、電子マネーについては、「使わない」から「よく使う」というように選択肢について、頻度が低い順からに変換している。
8総務省令和3年情報通信白書によると、スマートフォンやタブレットの利用状況については、年齢が上がるにつれて利用率は低下し、60~69歳では73.4%、70歳以上はわずか40.8%にとどまるとしている。
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd111430.html
9重回帰分析で、年齢と認知機能が多重共線性の問題が発生する可能性もある。VIFで見る限り、許容度を超える共線性は確認できなかった。
10Johnson Jeff・Finn Kate(2019)参照。
11関連研究は、駒村康平(2024)参照。