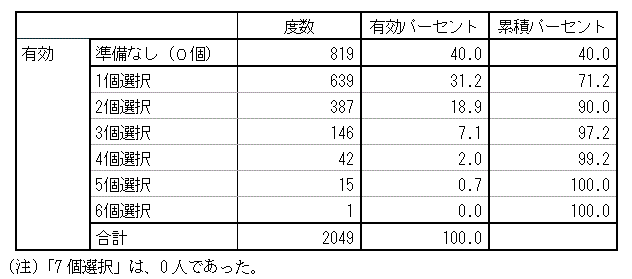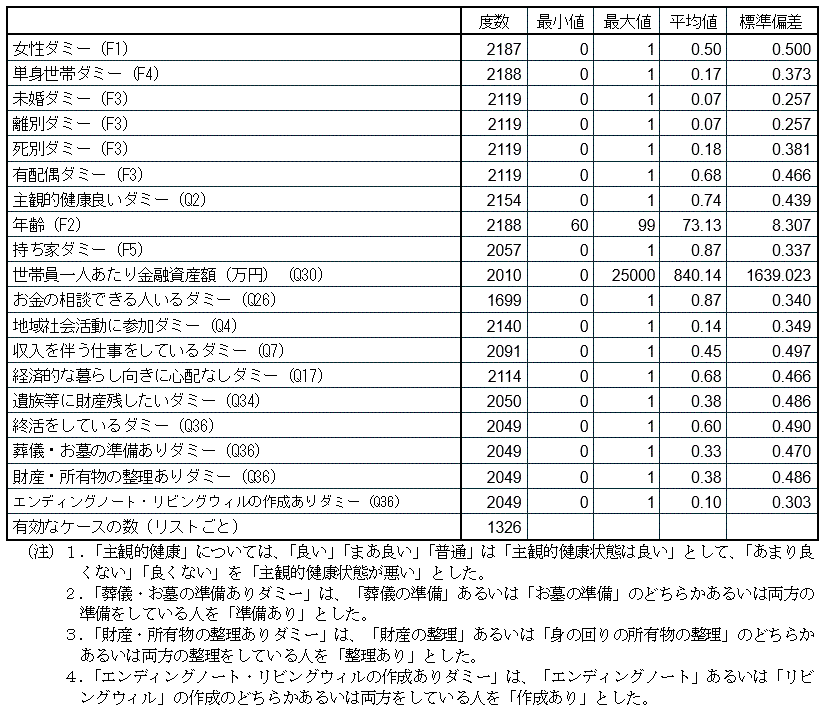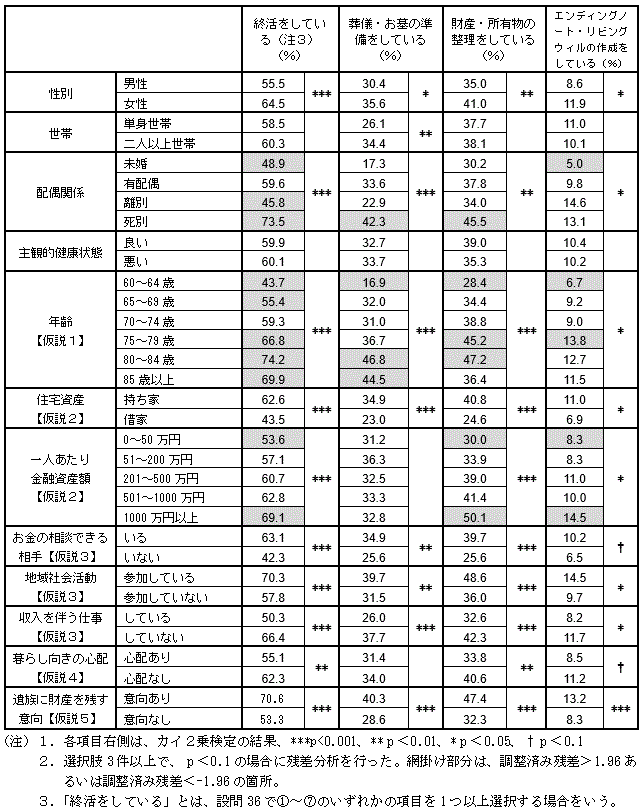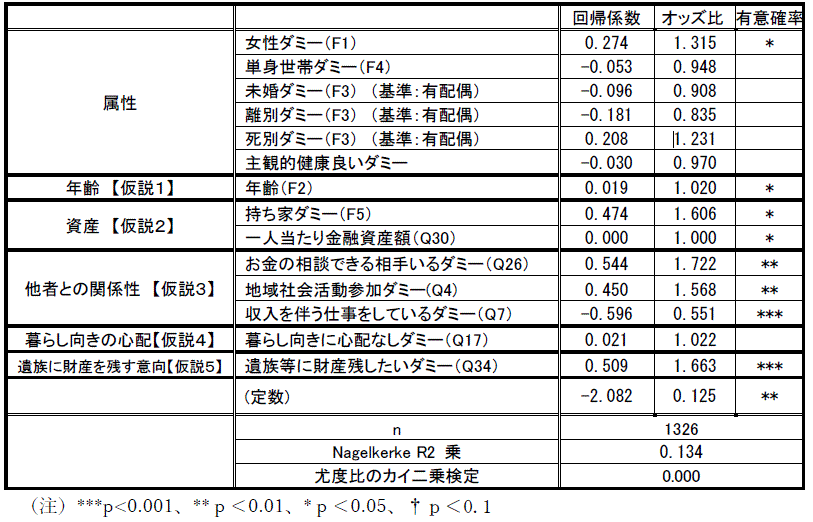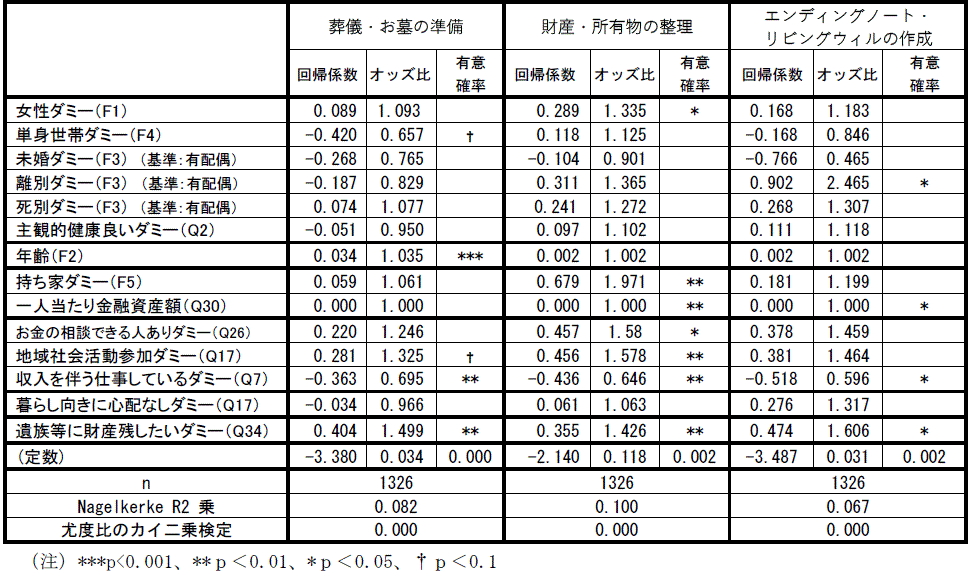(本章の内容は、すべて執筆者の見解であり、内閣府の見解を示すものではありません。)
「終活」をしている高齢者の特徴について
日本福祉大学/みずほリサーチ&テクノロジーズ 藤森克彦
1. はじめに
今後、「身寄りのない高齢者」が増えていくとみられている。身寄りのない高齢者とは、「家族・親族がいない高齢者」だけでなく、「家族・親族がいても、連絡が取れない高齢者」や「家族・親族がいても頼れない高齢者」も含まれる1。高齢期に「身寄りのない」状況になることは、現在家族と同居している人も含めて、誰にでも起こりうる。
ところで、身寄りのない高齢者が増える中で、課題になっている一つの点は、葬儀やお墓の準備、財産や家財などの所有物の整理、死亡後の希望や終末期医療の指示などの人生の最終段階や死後に向けた準備―いわゆる「終活」―である。こうした点は、これまで本人が行わなければ、主に家族が対応してきた。しかし、身寄りのない高齢者には、こうした点を対応する家族がいない。
死後対応に向けた準備は、基本的には私的領域の事柄といえる。しかし、身寄りのない高齢者が死後対応に向けた準備をしない(あるいはできない)場合、社会問題になりうる。例えば、借家に住む身寄りのない高齢者が残置物を残して死亡した場合、処分コストは大家の負担となる。大家は処分コストを避けるために、空き家や空室があっても単身高齢者には貸さないという問題が起こっている。
また、持ち家に住む身寄りのない高齢者が亡くなった後、空き家が長期に放置されて朽ちていけば、公金を使って処分することが考えられる。さらに、身寄りのない高齢者が死亡した場合、親族探しや遺留金等の調査が自治体の負担となっている。
誰もが「身寄りのない」状況になりうることを考えれば、現在、家族と暮らしているか否かに拘わらず、生前から死後対応に向けた準備をすることが重要と考えられる。そこで本稿では、死後対応に備えることを「終活」と呼び、「終活」をしている高齢者はどのような特徴をもつのか、また、高齢期の終活の規定要因は何かを明らかにする。
1山縣然太郎(2019)「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究班」、p.6)。
2. 使用するデータと変数の設定
本稿では、内閣府『高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)』(2024年10月実施)のデータを用いる。この調査では、終活に関連して「今後の生活の中で準備をしているものはあるか」(Q36)を尋ねている。その回答項目には、①葬儀の準備、②お墓の準備、③財産の整理(相続の準備等)、④身の回りの所有物の整理(③を除く)、⑤身近な人へのメッセージやエンディングノート(自身の死後の希望や意思を遺族等に伝える文書)の作成、⑥リビングウィル(終末期医療の指示・介護の希望・代理人の指定等)の作成、⑦その他、⑧準備しているものはない、が設定されている(複数回答)。
本稿では、設問36で設定された①~⑦の項目を「終活」とみなして、終活を行う高齢者の特徴を明らかにする。
(1)従属変数
従属変数としては、設問36で「準備しているものはない(⑧)」を選んだ人を「終活をしていない」とする。一方、同項目を選ばなかった人で設問36の①~⑦を選択した人を「終活をしている」とする。回答者計(n=2049)では「終活をしている」は60.0%、「終活をしていない」は40.0%となる(図表1) 。
なお、終活をしている人のうち、①~⑦の7項目のうち1個行っている者が52.0%、2個行っている者が31.5%、3個以上行っている者は16.5%である。また、各項目について実施している人の比率をみると、①葬儀の準備(21.8%)、②お墓の準備(21.8%)、③財産の整理(相続の準備等)(13.6%)、④身の回りの所有物の整理(③を除く)(29.8%)、⑤身近な人へのメッセージやエンディングノート(自身の死後の希望や意思を遺族等に伝える文書)の作成(8.3%)、⑥リビングウィル(終末期医療の指示・介護の希望・代理人の指定等)の作成(3.5%)、⑦その他(3.8%)、⑧準備しているものはない(40.0%)、である。
(図表1)終活に関連して今後の生活の中で準備をしている項目の個数(Q36)
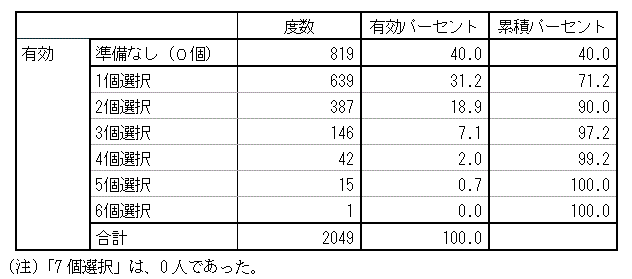
一方、終活の有無だけでは、どのような内容の終活をしているのかが不明である。そこで、設問36の回答項目から3つの合成変数を作成して、各々を従属変数とする。具体的には、「葬儀の準備」と「お墓の準備」のどちらかあるいは両方の準備をしている人を、「葬儀・お墓の準備ありダミー」とする。「葬儀・お墓の準備ありダミー」に該当する人は、全体(n=2049)の33.0%である。
また、「財産の整理(相続の準備等)」と「身の回りの所有物の整理(相続の準備等を除く)」のどちらかあるいは両方を整理している人を、「財産・所有物の整理ありダミー」とする。「財産・所有物の整理ありダミー」に該当する人は、全体(n=2049)の38.0%である。
さらに、「エンディングノート」と「リビングウィル」のどちらかあるいは両方を作成している人を、「エンディングノート・リビングウィルの作成ありダミー」とする。「エンディングノート・リビングウィルの作成ありダミー」は、全体(n=2049)の10.2%である。
以上から従属変数は、「終活をしているか」「葬儀・お墓の準備をしているか」「財産・所有物を整理しているか」「エンディングノート・リビングウィルを作成しているか」の4つになる。
(2)独立変数
独立変数としては、まず高齢者の属性として、「性別」(F1)、「配偶関係」(F3)、「単身世帯か否か」(F4)、「主観的健康状態」(Q2)を統制変数とする。なお、主観的健康状態については、「良い」「まあ良い」「普通」を「主観的健康状態は良い」として、「あまり良くない」「良くない」を「主観的健康状態が悪い」とした。
次に、終活をしている高齢者の特徴として、以下の5つの仮説を考えた。
【仮説1】高年齢の高齢者ほど、終活をしている。
【仮説2】資産(住宅資産、金融資産)をもつ高齢者が、終活をしている。
【仮説3】終活には情報が必要なので、他者との関係性をもつ高齢者が、終活をしている。
【仮説4】現在の経済的な暮らし向きに心配のない高齢者が、終活をしている。
【仮説5】「遺族に財産を残したい」という意向をもつ高齢者が、終活をしている。
その上で、上記の5つの仮説について、本調査の設問から以下の通り独立変数を設定した。
【仮説1】の「高年齢の高齢者ほど、終活をしている」について、年齢(F2)を独立変数とする。
【仮説2】の「資産(住宅資産、金融資産)をもつ高齢者が、終活をしている」については、下記の2つの変数から分析する。まず、住宅資産として、「持ち家か否か」(F5)を独立変数とする。また、「金融資産の総額はどのくらいになるか」(Q30)について、世帯員一人当たりの金融資産額を独立変数とする。
【仮説3】の「終活には情報が必要なので、他者との関係性をもつ高齢者が、終活をしている」という点については、以下の3つの独立変数から分析する。まず、「お金に困った際に相談できる相手」の有無(Q26-8)を独立変数とする。「お金に困った際に相談できる相手」は、本人にとって深い関係性を持つ人と考えられる。財産管理など死後対応についても相談できる相手になりうると推察される。
また、継続的に行う社会的な活動として、「地域社会活動(町内会、地域行事など)」の参加の有無」(Q4-3)を独立変数とする。継続的に地域社会活動を行う人は、地域の人と関係性をもち、終活に関する情報を得やすいと考えられる。
さらに、「現在、収入を伴う仕事をしているか否か」(Q7)を独立変数とする。職場においても、同僚から終活に関する情報を得ることができるのではないかと考える。
【仮説4】は、「現在の経済的な暮らし向きに心配のない高齢者が、終活をしている」というものである。本調査では「現在の経済的な暮らし向きについてどのように考えているか」(Q17)を尋ねており、「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」という回答を「暮らし向きに心配なし」とする。一方、「家計にゆとりがなく、多少心配である」と「家計が苦しく、非常に心配である」は「暮らし向きに心配あり」とする。そして、暮らし向きについて心配の有無を独立変数とする。
【仮説5】は、「『遺族に財産を残したい』という意向をもつ高齢者が、終活をしている」という点である。この点は、将来的な財産の使い道について「遺族等へ財産を残したい」(Q34-2)という意向の有無を独立変数とする。
(3)分析方法
分析方法としては、「終活」をしている高齢者の特徴を明らかにするために、上記の独立変数を用いて、クロス表から分析した。クロス分析においては、カイ二乗検定の結果、5%未満の水準で有意差が認められた場合、どのセルが有意差をもたらしたのかを明らかにするために残差分析を行う。残差分析によって出力される調整済み残差は、その絶対値が 1.96以上であれば5%水準で有意な差であると解釈できる。選択肢が複数ある場合には、該当セルに注目する。
また、終活の内容ごとに高齢者の特徴を明らかにするため、「葬儀・お墓の準備ありダミー」「財産・所有物の整理ありダミー」「エンディングノート・リビングウィルの作成ありダミー」を従属変数として、各従属変数についてクロス分析を行って独立変数との関連性をみる。
次に、高齢者の終活の規定要因を明らかにするため、「終活をしている」を1、「終活をしていない」を0とした二値変数を従属変数とするロジスティック回帰分析を行った。独立変数は、上記と同様である。
さらに、終活の内容を具体的に把握して規定要因を分析するため、「葬儀・お墓の準備ありダミー」「財産・所有物の整理ありダミー」「エンディングノート・リビングウィルの作成ありダミー」を各々従属変数として、先の独立変数を使ってロジスティック回帰分析を行なった。その上で、各従属変数の規定要因を比較した。
上記変数の記述統計量は、以下の通りである(図表2)。
(図表2)使用する変数の記述統計量
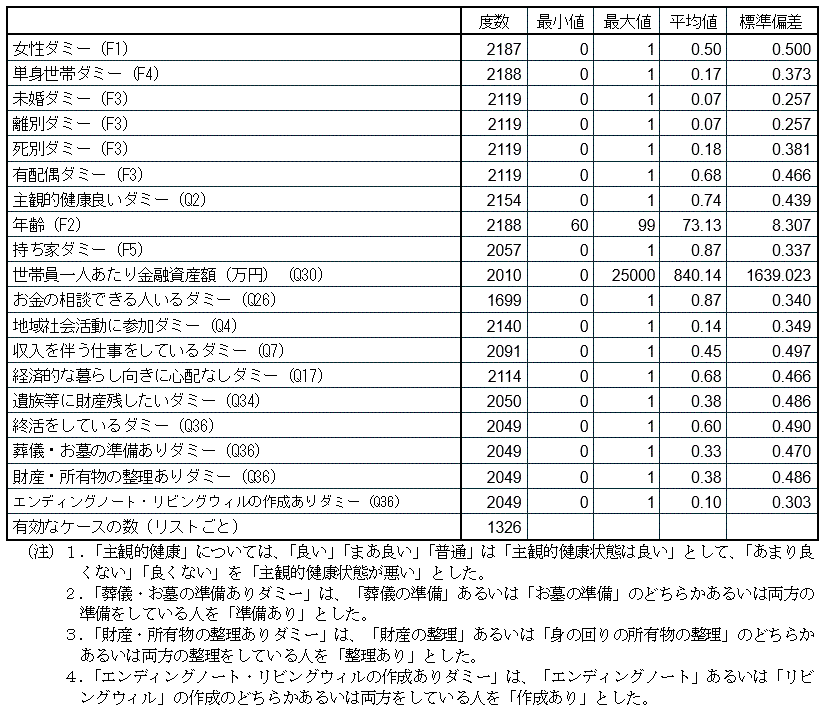
3.調査結果
以下では、クロス分析と、ロジスティック回帰分析の結果について示していく。
(1)クロス分析の結果
クロス分析は、「終活をしている高齢者」「葬儀・お墓の準備をしている高齢者」「財産・所有物の整理をしている高齢者」「エンディングノート・リビングウィルを作成している高齢者」の4つの従属変数について、先述した独立変数と関連性を分析する。
A.終活をしている高齢者の特徴
「終活をしている高齢者」と「終活をしていない高齢者」について、各独立変数からクロス分析を行った(図表3)。まず、属性をみると、女性は男性よりも終活をしている人の比率が有意に高い。また配偶関係別にみると、死別者は、未婚者や離別者に比べて、終活をする高齢者の比率が有意に高い。一方、「単身世帯か否か」「主観的健康状態が良いかどうか」は、統計的に有意な差は示されなかった。
次に、【仮説1】の「高年齢の高齢者ほど、終活をしている」について、年齢階層別に終活の有無をみると、クロス表はp<0.001となっていて、統計的に有意である。調整済み残差をみると、70~74歳のセルを除いて、有意になっている。したがって、「75~79歳」「80~84歳」「85歳以上」の高齢者は、「60~64歳」「65~69歳」の高齢者に比べて、終活をしている高齢者の比率が有意に高い。
【仮説2】の「資産(住宅資産、金融資産)をもつ高齢者が、終活をしている」について、まず「持ち家か借家か」と終活との関連性をみると、クロス表はp<0.001 となっていて統計的に有意である。持ち家を保有する高齢者は、借家に住む高齢者に比べて、終活をしている高齢者の比率が有意に高い。
また、一人当たりの金融資産額と終活との関連性をみると、クロス表はp<0.001 となっていて統計的に有意である。残差分析を見ると、有意になっているセルは「0~50万円」と「1000万以上」である。したがって、一人当たり金融資産額が「1000万円」以上の高齢者は、同資産額「0~50万円」の高齢者に比べて、終活をする人の比率が有意に高い。
【仮説3】の「終活には情報が必要なので、他者との関係性をもつ高齢者が、終活をしている。」という点について、まず「お金に困った際に相談できる相手」の有無と、終活との関連性をみる。その結果、p<0.001となっていて、お金について相談できる相手がいる高齢者は、相談相手がいない高齢者に比べて、終活をしている人の比率が有意に高い。また、「継続的な地域社会活動(町内会、地域行事など)の実施の有無」と終活との関連性をみると、p<0.001となっていて、地域社会活動を実施している高齢者は、実施していない高齢者に比べて、終活をしている人の比率が有意に高い。
一方、「高齢期に収入を伴う仕事をしているかどうか」と終活との関連性をみると、収入を伴う仕事をしている高齢者は、仕事をしていない高齢者に比べて、終活をしている人の比率が有意に低い。この結果は、想定した仮説とは異なる。
【仮説4】は、「現在の経済的な暮らし向きに心配のない高齢者が、終活をしている」という点である。その結果、p<0.01となっていて、経済的な暮らし向きについて心配がない高齢者は、心配がある高齢者に比べて終活をしている人の比率が有意に高い。
【仮説5】は、「『遺族に財産を残したい』という意向をもつ高齢者は、終活をしている」という点である。遺族に財産等を残す意向と終活との関連性をみると、クロス表はp<0.001 となっていて統計的に有意である。「遺族等へ財産を残したい」という意向をもつ高齢者は、意向をもたない高齢者に比べて、終活をしている人の比率が有意に高い。
(図表3)属性と仮説別の項目でみた死後対応の準備状況―クロス表分析
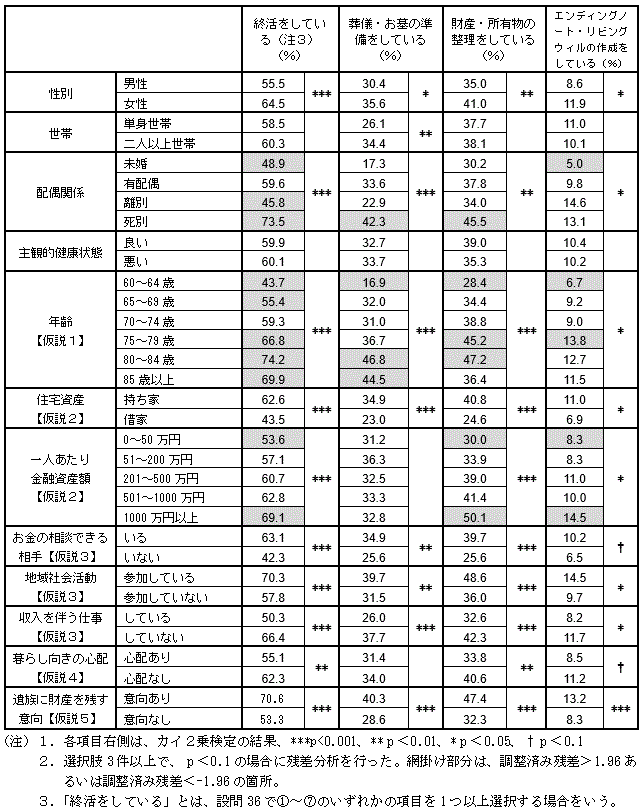
B.「葬儀・お墓」「財産・所有物」「エンディングノート・リビングウィル」のクロス分析結果
次に、「葬儀・お墓の準備をしている高齢者」「財産・所有物の整理をしている高齢者」「エンディングノート・リビングウィルを作成している高齢者」の特徴をクロス分析の結果から比較していく(前掲、図表3)。
まず、属性についてみると、3つの従属変数とも、女性は男性に比べて準備している人の比率が有意に高い。一方、単身世帯か否かについては、「葬儀・お墓の準備」についてのみ有意になっており、二人以上世帯は単身世帯に比べて葬儀やお墓の準備をする人の比率が高い。配偶関係をみると、「葬儀・お墓の準備」と「財産・所有物の整理」では、死別者において準備をしている人の比率が有意に高い。一方、「エンディングノート・リビングウィルを作成」は、未婚者において作成する人の比率が有意に低い。なお、主観的健康状態については、どの従属変数も有意な差はみられなかった。
次に、【仮説1】について、年齢階層別にみると、3つの従属変数全てにおいて、「60~64歳」は、準備する人の比率が有意に低くなっている。一方、「葬儀・お墓の準備」では、「80~84歳」「85歳以上」で準備をする人の比率が有意に高い。また、「財産・所有物の整理」では、「75~79歳」「80~84歳」で整理をする人の比率が有意に高い。さらに、「エンディングノート・リビングウィルの作成」では、「75~79歳」で作成する人の比率が有意に高い。終活の内容によって、準備する人の年齢階層は異なっている。
【仮説2】の住宅資産をみると、3つの従属変数全てにおいて、持ち家に住む高齢者は、借家に住む高齢者に比べて、準備をしている人の比率が有意に高い。また、「一人当たり金融資産額」については、「財産・所有物の整理」と「エンディングノート・リビングウィルの作成」において、一人当たり金融資産額が「1000万円以上」の高齢者は「0~50万円」の高齢者に比べて、準備をする人の比率が有意に高い。一方、「葬儀・お墓の準備」については、一人当たり金融資産額と有意な差がみられなかった。
【仮説3】の「他者との関係性」については、「お金の相談相手」がいる高齢者は3つの従属変数全てにおいて準備をしている人の比率が有意に高い。また、「地域社会活動への参加」についても、全ての従属変数において、地域社会活動に参加している人は、準備をしている人の比率が有意に高い。
一方で、「収入を伴う仕事」については、全ての従属変数において、収入を伴う仕事をしている人は、仕事をしていない人に比べて、準備をしていない人の比率が有意に高い。これは、当初の想定とは異なる結果である。
【仮説4】の「現在の経済的な暮らし向きの心配」については、「財産・所有物の整理」と「エンディングノート・リビングウィルの作成」について、心配のない人は、心配のある人に比べて有意に整理や作成をする人の比率が高い。一方、「葬儀・お墓の準備」は必ずしも、暮らし向きの心配の有無とは有意な関連性がみられなかった。
【仮説5】については、「遺族等に財産を残したい」という意向をもつ高齢者は、全ての従属変数において、準備をしている人の比率が有意に高い、という結果になった。
(2)ロジスティック回帰分析
それでは、終活をしている高齢者の規定要因は何か。ここでは「終活をしている」を1、「終活をしていない」を0とする二値変数を従属変数として、ロジスティック回帰分析を行った。なお、独立変数についてVIFを調べたところ、全ての独立変数においてVIFの値は2.0未満であり、独立変数の多重共線性の問題はない。
次に、終活として実施している内容ごとに規定要因を明らかにしていくため、「葬儀・お墓の準備」「財産・所有物の整理」「エンディングノート・リビングウィルの作成」を従属変数として、規定要因を比較した。
A.終活をしている高齢者の規定要因
終活の有無を従属変数としてロジスティック回帰分析を行うと、まず、カイ二乗検定は p<0.001 で有意となっている(図表4)。分析に投入した変数の有意確率をみると、属性では、「女性ダミー」が5%水準で有意となっており、回帰係数の符号もプラスである。女性であることは、終活の規定要因となっている。一方、「単身世帯ダミー」「未婚ダミー」「離別ダミー」「死別ダミー」「主観的健康良いダミー」は統計的に有意ではなく、必ずしも終活の規定要因とはいえない。
(図表4)終活をしている高齢者の規定要因―ロジスティック回帰分析
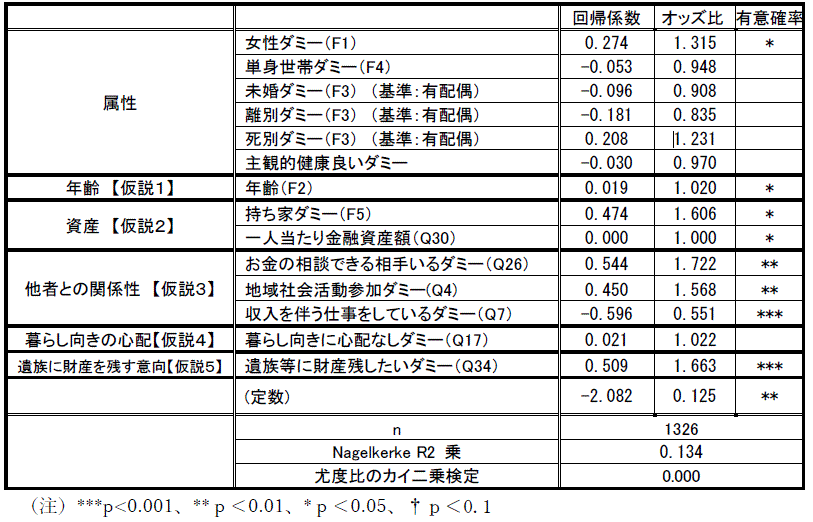
次に、仮説ごとにみていくと、【仮説1】については、「年齢」は5%水準で有意となっており、回帰係数の符号もプラスである。年齢が高いことは終活をすることの規定要因と考えられる。
【仮説2】については、「持ち家ダミー」と「一人当たり金融資産額」はともに、5%水準で有意になっており、回帰係数の符号もプラスである。住宅資産や金融資産をもつことは、終活をすることの規定要因と考えられる。
【仮説3】については、「お金の相談できる人いるダミー」と「地域社会活動参加ダミー」はともに、1%水準で有意となっており、回帰係数の符号もプラスである。お金の相談できる人がいることや、地域の社会活動に継続的に参加することは、終活の規定要因と考えられる。
一方、「収入を伴う仕事をしているダミー」は0.1%水準で有意であるが、回帰係数の符号がマイナスとなっている。つまり、収入を伴う仕事をすることは、終活に負の影響を与える規定要因となっている。これは、当初の想定とは異なる結果である。
【仮説4】について、「暮らし向きに心配なしダミー」は統計的に有意ではなく、暮らし向きについての心配の有無は必ずしも終活の規定要因とはいえない。
【仮説5】について、「遺族等に財産を残したいダミー」は、0.1%水準で有意であり、回帰係数の符号もプラスである。遺族等に財産を残したいという意向をもつことは、終活に正の影響を与える規定要因である。
B.「葬儀・お墓の準備」「財産・所有物の整理」「エンディングノート等の作成」の規定要因
次に、「葬儀・お墓の準備」「財産・所有物の整理」「エンディングノート・リビングウィルの作成」をそれぞれ従属変数として、ロジスティック回帰分析を行った(図表5)。各従属変数の規定要因を比較すると、属性では、「財産・所有物の整理」において、女性ダミーが5%水準で正の影響を与える規定要因になっている。また、「葬儀・お墓の準備」では、単身世帯ダミーが10%水準で負の影響を与える規定要因になっている。さらに、配偶関係では、「エンディングノート・リビングウィルの作成」において離別者が有配偶者と比べて正の影響を与える規定要因になっている。
(図表5)「葬儀・お墓準備」「財産・所有物整理」「エンディングノート・リビングウィル作成」の規定要因―ロジスティック回帰分析
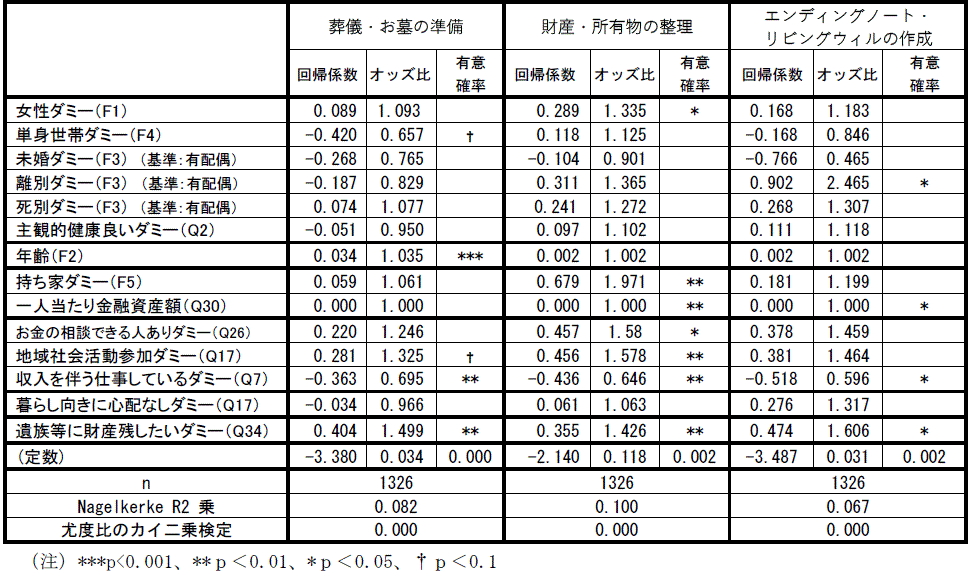
次に、仮説ごとに規定要因を比べていく。【仮説1】の「年齢」については、「葬儀・お墓の準備」についてのみ正の影響を与える規定要因になっている。
【仮説2】について、「持ち家ダミー」と「一人当たり金融資産額」は、ともに「財産・所有物の整理」に1%水準で正の影響を与える規定要因になっている。また、「一人当たり金融資産額」は、「エンディングノート・リビングウィルの作成」に、5%水準で正の影響を与える規定要因になっている。
【仮説3】について、「お金の相談できる人がいるダミー」は、「財産・所有物の整理」において5%水準で正の影響を与える規定要因となっている。また、「地域社会活動参加ダミー」は、「葬儀・お墓の準備」と「財産・所有物の整理」において正の影響を与える規定要因となっている。
一方、「収入を伴う仕事をしているダミー」は、いずれの従属変数についても、負の影響を与える規定要因となっている。
【仮説4】について、「暮らし向きに心配なしダミー」は、いずれの従属変数においても、統計的に有意ではなく、必ずしも規定要因とはいえない。
【仮説5】について、「遺族等に財産残したいダミー」は、いずれの従属変数において正の影響を与える規定要因となっている。
4.まとめ
以上のように、本稿では、高齢者の終活の規定要因は何かについて5つの仮説をあげて分析した。その結果、下記の通りまとめられる。
(1)5つの仮説についての分析結果
終活全体についてみると、【仮説1】の「高年齢の高齢者ほど、終活をしている」、【仮説2】の「資産(住宅資産、金融資産)をもつ高齢者が、終活をしている」、【仮説5】の「『遺族に財産を残したい』という意向をもつ高齢者が、終活をしている」という点は、ロジスティック回帰分析の結果、これらは仮説通り、終活に正の影響を与える規定要因である。
一方、【仮説4】の「現在の経済的な暮らし向きに心配のない高齢者が、終活をしている」という点については、必ずしも終活の規定要因とはいえない。つまり、暮らし向きに関する心配の有無は、必ずしも終活に影響を与えるとはいえないことが示された。
また、【仮説3】の「終活には情報が必要なので、他者との関係性をもつ高齢者が、終活をしている」という点については、「お金の相談をできる相手がいること」と「地域社会活動に参加していること」は、終活に正の影響を与える規定要因となっていた。
一方、「収入を伴う仕事をしているダミー」は、終活に負の影響を与える規定要因である。つまり、収入を伴う仕事は、終活をさせない方向での規定要因になっており、仮説とは真逆の結果となった。この理由については、収入のある仕事をしている高齢者は、「現役である」という意識が強いことがあり、これが終活を妨げる要因になっているのではないかと推察される。また、職場の同僚といっても、高齢世代ばかりではないので、終活の情報を得られる場という見方が妥当ではなかったと考える。
(2)終活の内容によって異なる規定要因
次に、終活の内容を「葬儀・お墓の準備」「財産・所有物の整理」「エンディングノート・リビングウィルの作成」に分けて、各々を従属変数として規定要因を探った。その結果、従属変数によって規定要因が異なることが明らかになった。
具体的には、【仮説1】について「年齢」が正の影響を与える規定要因となるのは、「葬儀・お墓の準備」のみであった。「葬儀・お墓の準備」は、年齢が高まることとの関連性が大きい。
【仮説2】について、住宅資産や金融資産を保有していることは、「財産・所有物の整理」に正の影響を与える規定要因となっている。資産をもつことが「財産・所有物の整理」のインセンティブになっていると考えられる。なお、金融資産額は、「エンディングノート・リビングウィルの作成」の規定要因にもなっている。
【仮説3】について、他者との関係性として、「お金の相談できる人がいること」は、「財産・所有物の整理」に正の影響を与える規定要因になっている。また、「地域社会活動に参加すること」は、「葬儀・お墓準備」と「財産・所有物整理」に正の影響を与える規定要因になっている。
一方、「収入を伴う仕事をしていること」は、全ての従属変数について、負の影響を与える規定要因となっている。先述の通り、収入のある仕事は自らを「現役である」という意識を強め、終活を阻害する面があると推察される。
【仮説4】について、「経済的な暮らし向きの心配の有無」は、全ての従属変数において必ずしも規定要因とはいえない。
【仮説5】について、「遺族等に財産を残したいという意向」は、全ての従属変数において、正の影響を与える規定要因となっている。
(3)今後の対策への示唆
冒頭で示した通り、高齢期に身寄りのない状況になることは誰にでも起こりうることであり、生前から死後対応の準備をしておくことが重要になる。今後の対策として考えられるのは、仮説3でとりあげた「他者との関係性」を用いて終活の重要性を伝えていくことであろう。
町内会や地域行事などの「地域社会活動」は、「葬儀・お墓の準備」や「財産・所有物の整理」に正の影響を与える規定要因であった。一方、「エンディングノートやリビングウィルの作成」については、必ずしも規定要因とはいえない。この点、愛知県のある地域では、地域の支援団体が高齢期の一人暮らしについて啓発セミナーを開いて、その中で集まった人々と対話をしながらエンディングノートを作成する取り組みが行われている。こうした取り組みによって、人々は終活の重要性を認識するとともに、エンディングノートの内容を深めていくことにもなるだろう。
また、「収入を伴う仕事をしていること」は、「葬儀・お墓の準備」「財産・所有物の整理」「エンディングノート・リビングウィルの作成」の全てに負の影響を与える規定要因であった。今後、高齢期に働く人は増えていくので、死後対応への備えをする人が減少していく可能性がある。
この点については、高齢者が働く企業の中で、終活の重要性を伝えていくセミナーを開催していくことが考えられる。例えば、現在、50歳前後の中高年を対象に、役職定年や退職後の生活についてセミナーを行う企業が少なくない。今後は、60歳以上の従業員を対象に終活セミナーを企業で開催して、生前に終活をしていくことの重要性を伝える機会としていけないか。高齢期に身寄りのない人が増える中で、終活の重要性を知る機会をもつことは、個人にとっても、社会にとっても有益であろう。