内閣府(2024)「令和6年度 年次経済財政報告」では、高齢者の貯蓄取り崩し行動は非常に限定的で、純粋なライフサイクル仮説とは異なり、高齢者が金融資産を保有し続けているという。その背景には、生活への不安感、遺産動機の可能性があると指摘されている。本稿は、前回調査と比較しながら、高齢者の経済不安と節約志向、貯蓄の取り崩しに着目して、高齢者の生活状況について分析することを目的としている。
第3章 調査結果の分析・解説 -4
(本章の内容は、すべて執筆者の見解であり、内閣府の見解を示すものではありません。)
高齢者の経済不安の高まりと節約志向
上智大学総合人間科学部 丸山 桂
1. はじめに
2.2019年調査との比較
高齢者の経済的な暮らし向き感を前回調査(2019年)と比較すると、「心配なく暮らしている」1は前回調査の74.1%から65.9%に低下し、「日常生活の支出の中で、収入より支出が多くなり、これまでの預貯金を取り崩してまかなうこと」が「よくある」、「時々ある」と回答する者の割合は61.2%となり、前回調査より13ポイント程度増加した。
「今後の生活において、経済的な面で不安に思う項目(複数回答可)」(以下、経済不安)について比較すると、なんらかの不安に思う項目がある者の割合は、前回調査の64.0%から92.6%へと大幅に上昇した(表1参照)。特に、「物価が上昇すること」に対する不安は74.5%ときわめて高く、「収入や貯蓄が少ないこと」、「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」「災害により被害を受けること」など世相を反映した項目に対する不安感が高い傾向がある。
表1 今後の生活における経済的な面での不安(複数回答)
(単位:%)
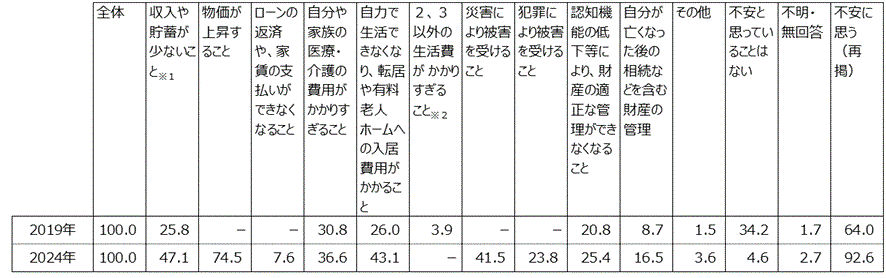
※1 2019年調査は、「収入や貯蓄が少ないため、生活費がまかなえなくなること」である。
※2 2は「自分や家族の医療・介護の費用がかかりすぎること」、3は「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」である。
1「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」(14.8%)と「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」(51.1%)の合計である。
3.経済的な暮らし向き感と貯蓄の取り崩しの状況
次に、高齢者の生活状況を分析するため、経済的な暮らし向き感と貯蓄の取り崩しに関するマトリックスを作成し、分析を行うこととする。まず、経済的な暮らし向き感については、「心配である」と「心配なく暮らしている」2の2類型に分類した。また、日常生活費のための貯蓄の取り崩し状況については、「ない」と「あり」の2類型に分類した3。
表2 経済的な暮らし向き感と貯蓄の取り崩しの状況
(単位:%)
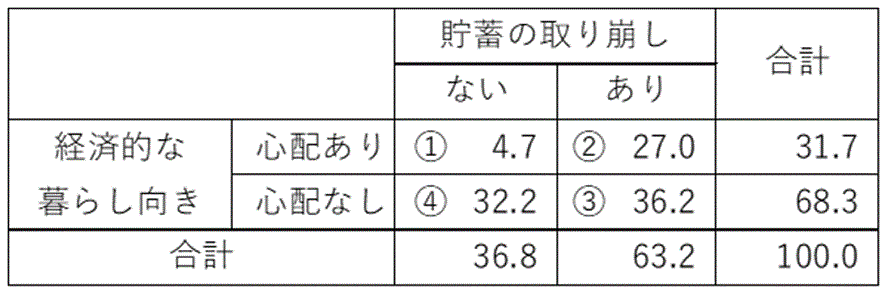
注:「不詳・無回答」は分析対象から除外している。
注:回答率(各回答の百分比)は、小数点以下第2位を四捨五入したため、回答率の合計が100.0%にならないことがある。
4類型の分布は、表2より時計回りに、①経済的な心配があり、貯蓄の取り崩しがない(4.7%)、②経済的な心配があり、貯蓄の取り崩しをしている(27.0%)、③経済的な心配がなく、貯蓄の取り崩しをしている(36.2%)、④経済的な心配がなく、貯蓄の取り崩しをしていない(32.2%)とした。それぞれの解釈については、①は貯蓄残高が少なく、取り崩しができずに経済的に不安を抱える層、②は、貯蓄を取り崩しながら将来に対する不安を抱えている層、③は、経済的な心配はないが、貯蓄を取り崩しながら暮らしている層、④は経済的な心配もなく、貯蓄を取り崩さずとも暮らしている、相対的に豊かな老後生活を送っている層と考えられる。
表3は、経済的なゆとり感と貯蓄の取り崩しの状況について、4つの類型を作成し、それぞれの平均スコアを比較し、分散分析を行った結果である。
表3 高齢者の経済的な暮らし向き感と貯蓄取り崩し状況別にみた比較
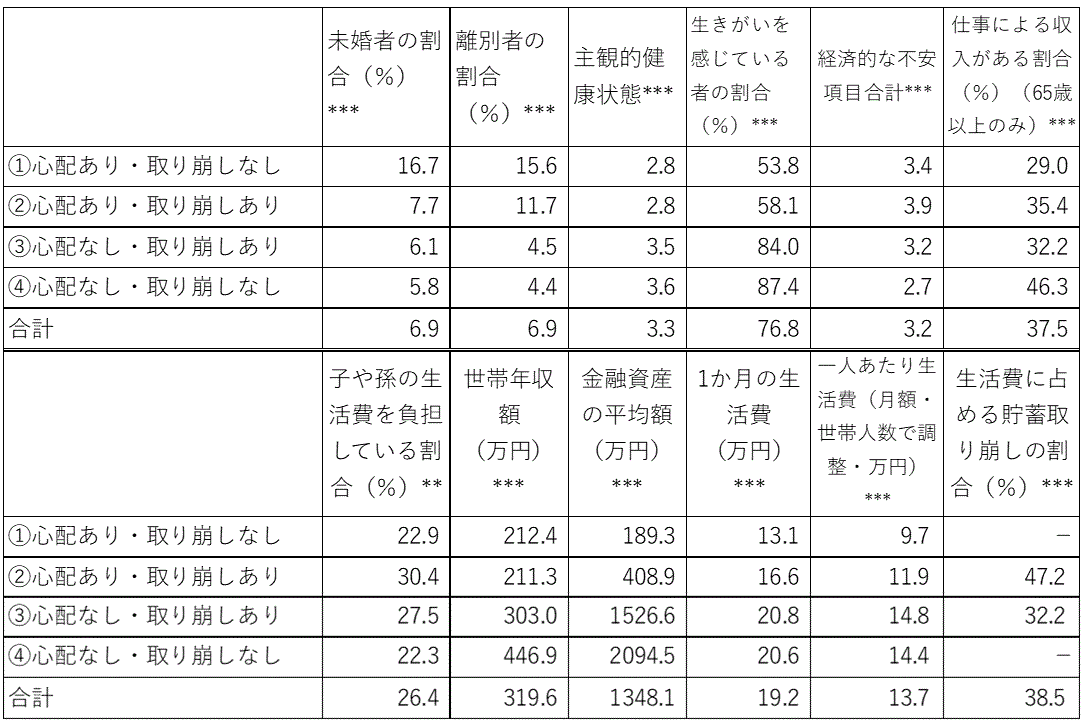
注:「不詳・無回答」は分析対象から除外している。
表中の*は、分散分析の結果、**:p<0.05、***p<0.01であることをあらわす。
表3の結果をみていこう。配偶関係については、未婚者、離別者が特に①の「心配あり・取り崩しなし」のカテゴリーに該当する者の割合が高い。主観的健康状態(1~5の5段階。数字が高いほど、主観的健康状態が良い)は、①と②の「心配がある」者の平均スコアが低く、③と④の「心配がない」者のスコアが高い。生きがい については、①と②、③と④で生きがいを感じている者の割合に大きな格差があり、経済的な状況と生きがいとの関連性が非常に高いことが分かる。
次に、経済的な項目との関連性を見ていこう。経済的な不安項目については、②が一番高く、④が一番低かった。仕事による収入がある割合は、高年齢者雇用安定法による65歳までの雇用機会の確保や老齢基礎年金の支給開始年齢が65歳であるため、65歳以上の者のみに限定した結果、その割合は①から④の順番に高くなっている。とりわけもっとも豊かな④では他のカテゴリーより10%ポイント以上高い割合 で、仕事による収入が経済的なゆとりに大きな貢献をしていることが示唆される。
子や孫の生活費を負担している者の割合は、②と③の貯蓄を取り崩している者にやや高い傾向が見られた。世帯収入、金融資産額の平均額は①から④の順番で金額が多くなるが、①と②、③と④という2つの層に大別でき、経済的な心配の有無との関係性が強いことがわかる。とくに注目すべきは、①のカテゴリーに属する者の金融資産の平均額は189.3万円と突出して低く、貯蓄を取り崩そうともそれができない厳しい状況がうかがえる。
1か月の生活費と世帯人数で調整した生活費6も同様の傾向がみられた。経済的に厳しい①のカテゴリーの者の一人あたり生活費の平均額は9.7万円で、生活を切り詰めている様子がうかがえる。最後に、生活費に占める貯蓄の取り崩しの割合をみると、将来を心配する②の割合は47.4%、つまり生活費の約半分を貯蓄の取り崩しで賄っており、②の平均金融資産残高408.9万円も考慮すると、いずれ貯蓄が底をつき、生活困窮に陥るリスクが非常に高い可能性が示唆された。
2「家計が苦しく、非常に心配である」、「家計にゆとりがなく、多少心配である」を「心配である」、「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている。」と「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている。」を「心配なく暮らしている」の2類型に分類した。
3「全くない」と「ほとんどない」を「ない」、「よくある」と「時々ある」を「ある」とした。
4生きがいについて「十分感じている」「多少感じている」の合計を、生きがいを「感じている」とした。
5表中には記載していないが、現在、仕事をしている理由に「収入のため」という経済的理由をあげた者の割合が88%、④は46%であった。
6世帯規模の経済性を鑑み、世帯人数の平方根を等価尺度として使用した。
4.4類型に関する多項ロジスティック分析
ここで、4類型を被説明変数とした多項ロジスティック分析を行う。参照カテゴリーは、④心配なし・取り崩しなしの世帯である。説明変数は、男性ダミー(男性=1,女性=0)、年齢、配偶関係として、有配偶ダミー(有配偶者を1、それ以外を0)、主観的健康状態(1~5の5段階:5がもっとも良い)、仕事による収入ありダミー7(ある=1、なし=0)年収の対数、金融資産額の対数、生きがい(1~4の4段階。4がもっとも生きがいがある)、高齢者の貯蓄取り崩し行動の背景にある不安感と遺産動機を見るため、将来不安の代理変数として「経済的な不安の項目合計」、遺産財産を把握するため「財産は自分のために使いたい」、「遺族等へ財産を残したい」の設問について該当者を1、非該当者を0としたダミー変数を作成した。最後に、収入増の手段として考えている項目として、「自分が仕事をする」、「家族・親族からの援助」についてそれぞれ該当者を1、非該当者を0としたダミー変数を作成した。そして、「節約」志向を尋ねるため、今後節約したい費目数を連続変数として使用した8。いずれも、不詳や無回答の回答は除外している。
表4は基本統計量、表5は分析結果である。なお、紙幅の都合上、表5の分析結果のカテゴリーは、横に並べて掲載している。
表4 基本統計量
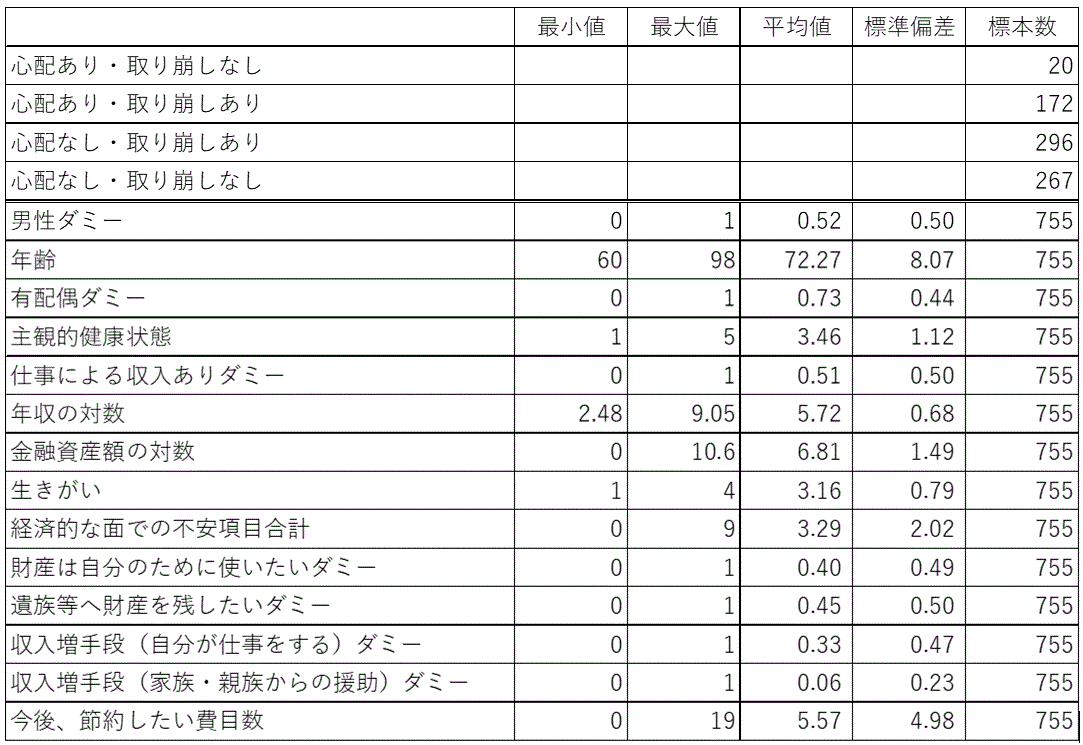
表5 経済的な暮らし向き感と貯蓄取り崩しに関する多項ロジット分析結果
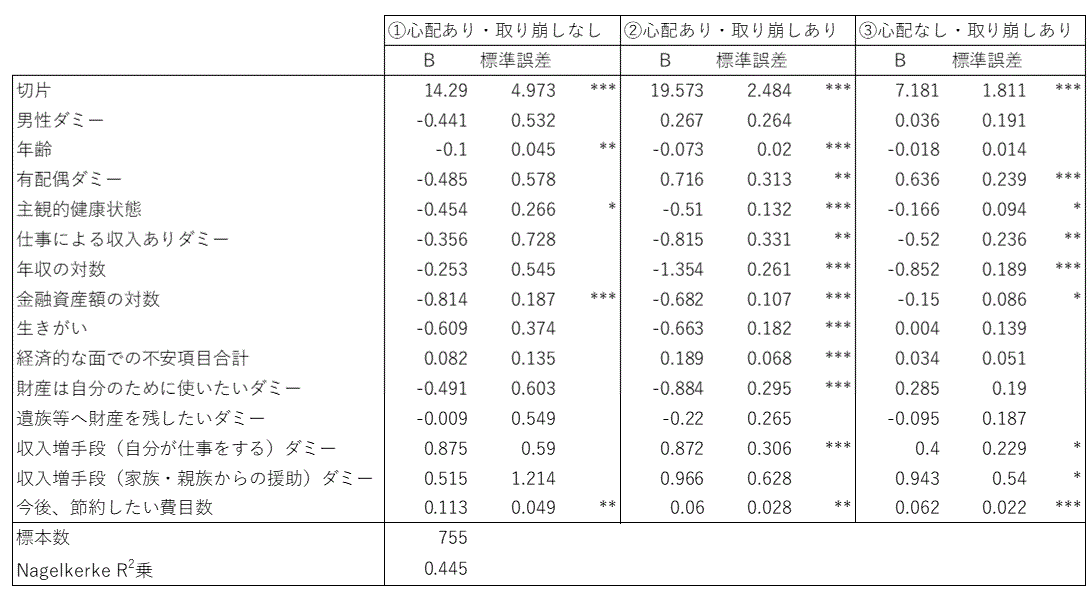
注:*:p<0.1、**:p<0.05、***:p<0.01をあらわす。
表5より結果をみていこう。男性ダミーは、統計的に有意差は認められなかった。年齢は①と②のカテゴリーで、マイナスの係数で統計的に有意な結果となり、暮らし向きを「心配あり」と答える者は、相対的に年齢が若い高齢者が多い傾向にあることが分かった。有配偶ダミーについては、②と③のカテゴリーでプラスの係数で統計的に有意な結果となり、貯蓄の取り崩しをしているのは、年長者の方が多い傾向にあることが分かった。
主観的健康状態については、いずれのカテゴリーもマイナスの係数で統計的に有意な結果となった。そして、仕事による収入があるダミーは、いずれもマイナスの係数で、②と③のカテゴリーのみ統計的に有意となった。つまり、②や③のカテゴリーに入る貯蓄を取り崩して生活している者は、④の経済的に心配がなく、貯蓄を取り崩さない者に比べ、仕事による世帯収入がない者の割合が高いことが分かった9。
経済的な指標である世帯年収の対数は②と③のカテゴリーでマイナスの係数で統計的に有意となり、金融資産額の対数はすべてのカテゴリーで、マイナスの係数で統計的に有意となった。高齢者の経済的な不安や貯蓄の取り崩し行動には、世帯収入よりも金融資産額の方がより大きな影響を与えていることが分かる。生きがいについては、②のカテゴリーのみがマイナスの符号で統計的に有意となった。
経済的な面での不安項目合計は、②のカテゴリーにおいてプラスの係数かつ1%水準で有意となった。表2でみたように、最も家計が苦しいと思われる①よりも、②のカテゴリーに属する者の方が将来への経済的な不安感が強いことは、貯蓄の取り崩しにも限度があることを悲観しての結果と考えられる。また、財産を自分のために使いたいダミーは、②のカテゴリーのみマイナスの係数かつ1%水準で統計的に有意な結果となった。一方で、遺産動機についてはどのカテゴリーでも統計的に有意差が認められなかった。つまり、今回の分析結果からは、参照カテゴリー④と明確な違いが認められたのは、その正反対のカテゴリーとなる②心配あり・取り崩しありのカテゴリーのみであった。つまり、この貯蓄を取り崩しながら将来を心配しながら生活している層は、それとは正反対の④のカテゴリーに属する者に比べ、将来への経済不安項目が多く、財産を自分のために使いたい者が相対的に少ないと思っていることが確認できた。
収入増の手段としてみた結果については、自分が仕事をするについては、すべてでプラスの係数となったが、②と③のみが統計的に有意となる結果となった。家族・親族からの援助ダミーは、③の心配は少ないが貯蓄を取り崩しながら暮らしている者のみプラスの係数で有意となり、やや家族や親族からの援助を期待していることがわかった。
最後に、今後、節約したい費目数については、すべてのカテゴリーでプラスの係数で統計的に有意となった。特に、経済的にもっとも厳しい状況にある①のカテゴリーの係数がもっとも大きく、他の変数を調整してもなお、節約志向が強いことがわかる。①は表3でみたように、仕事による収入がある割合は、もっとも低いが、それでもなお収入増の手段を、仕事をすることよりも節約と優先的に考えていることがわかった10。
7世帯収入源として、仕事の収入がある場合を1とした。
8収入増の手段として「節約」という設問もあり、そちらを使用して分析した結果は割愛している。物価上昇もあり節約志向は広がっているが、より分布が大きい費目数を使用した分析結果を掲載した。
9「仕事による収入がある」は、世帯収入の指標のため、それが本人の仕事かそれ以外の世帯員の収入であるかは分からない。また、仕事による収入の金額も把握することはできない。ただし、仕事をしている者に限って、その仕事への満足の割合(満足しているとやや満足しているの合計)は、①40.5%、②33.5%、③65.1%、④77.3%で、①と④ではその労働条件が大きく異なる可能性が示唆される。
10表中には記載していないが、①や②のカテゴリーに共通して節約志向が強いのは「食費」、「趣味やレジャー(旅行等)の費用」、「友人等との交際費」が目立ち、物価高騰が続く食費の節約には限界があることや、必需品ではないものの暮らしを豊かにする費目で節約傾向が高かった。
5.まとめ
本稿では、高齢者の経済的な暮らし向き感と貯蓄の取り崩しの状況について分析を行った。本調査では、過半数の高齢者は経済的に大きな心配がない状況で暮らしているが、その生活状況には格差が大きいこともまた明らかとなった。
経済的な暮らし向き感と貯蓄の取り崩しに関して、4類型を作成して比較すると、家計が苦しいにもかかわらず、貯蓄の取り崩しもしない者は、取り崩す貯蓄額自体が少額で、主観的健康状態や生きがいが低いなど、厳しい生活を送っている姿が示唆された。
また、本分析では、経済状況によって遺産動機が異なるということは確認できなかった。物価上昇の影響で、高齢者全体に節約志向が広がっているが、経済的に厳しい環境にある高齢者は、収入増手段を自身の就労よりも節約を優先していることがわかった。健康状態が優れないために、就労が厳しい可能性も考えられるが、長寿化する社会においてはできるだけ就労期間を延ばし、働きながら資産形成の期間を後ろ倒しすることで資産寿命を延ばすことが求められている。この実現には、高齢者の就労環境の整備やiDeCo等の期間延長も必要であるが、若いうちからの資産形成を促すことも必要で、学校教育等も含めた金融リテラシーの形成や生活設計の準備が必要である。
参考文献
内閣府(2024)『令和6年度 年次経済財政報告』

