第2章 令和6年度高齢社会対策の実施の状況(第3節 2)
第3節 〈特集②〉新たな高齢社会対策大綱の策定について(2)
2 新たな大綱策定に向けた検討
こうした状況変化に伴う社会課題に適切に対処し、持続可能な経済社会を構築していく観点から、令和6年2月13日の高齢社会対策会議において、同年夏頃を目途に新たな大綱の案の作成を行うことを決定した。
これを踏まえ、新たな大綱の案の作成に資するため、内閣府特命担当大臣決定により、有識者を構成員とする「高齢社会対策大綱の策定のための検討会」(座長:柳川範之東京大学大学院経済学研究科教授)(以下本節において「検討会」という。)を開催することとした(図2-3-1)。
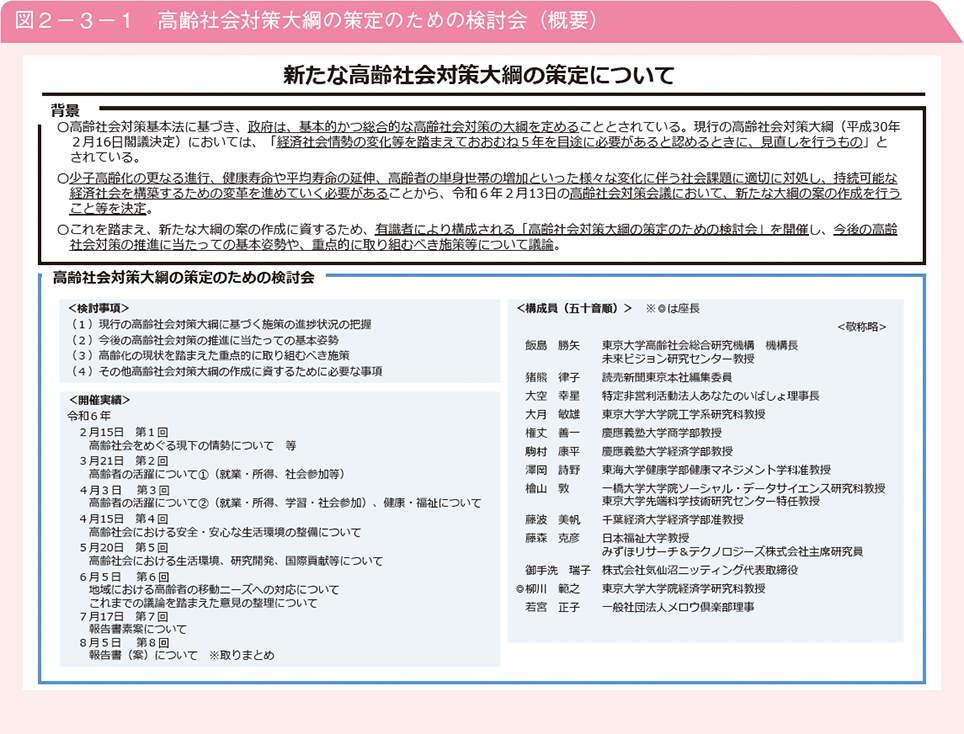
検討会においては、
- 加齢とともに、同じ年齢層の中でも身体機能や認知機能の程度にはグラデーションがあることから、個々人の実態を踏まえてきめ細かな施策を行うことが必要であること
- 年を重ねて心身に余裕がなくなってきても、モザイク就労(注3)などで活躍し続けられることが重要であること
- 加齢に伴い認知機能が低下しても、高齢者が自立して金融・経済活動を続けられるとともに、地域包括ケア等必要な支援につなげられるよう、金融・福祉等が連携し、社会で支援する体制の検討が必要であること
- 地域における居住支援の体制について、住宅だけでなく、医療や福祉、相続等の別の分野の相談にも必要に応じてつなげるようにしておくことが重要であること
- 加齢に伴い、誰もが難聴となり得る中、難聴が離職のきっかけや認知症のリスク要因となっていることを踏まえ、地域や職場における理解の促進等の対策を進めていくことが重要であること
等、様々な意見が挙げられた。こうした観点も踏まえ、令和6年8月に取りまとめられた「高齢社会対策大綱の策定のための検討会報告書」(以下本節において「報告書」という。)においては、政府が高齢社会対策を推進するにあたっての基本的考え方として、①年齢に関わりなく、希望に応じて活躍し続けられる経済社会の構築、②高齢期の一人暮らしの人の増加等の環境変化に適切に対応し、多世代が共に安心して暮らせる社会の構築、③加齢に伴う身体機能・認知機能の変化に対応したきめ細かな施策展開・社会システムの構築、の3点が掲げられた。
(注3)地域の様々な活動について、1人分の業務や作業等を分解し、個々人の知識・経験、関心、都合(時間・場所等)等に応じて、複数の人で柔軟に分担すること。

