第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり 1
広報・啓発等の推進
障害者施策の円滑な推進を実効性あるものにしていくには、幅広い国民の理解を得ながら進めていくことが重要であり、「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)及び「障害者基本計画」の掲げる共生社会の実現を目指すためには、行政、民間企業・団体、マスメディア等、多様な主体が連携して、幅広い広報・啓発活動を計画的かつ効果的に推進することが必要である。
2018年3月に閣議決定された「障害者基本計画(第4次)」では、「Ⅱ 基本的な考え方」として「理解促進・広報啓発に係る取組等の推進」を掲げている。この中では、「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」という当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害のある人と障害のない人が、お互いに、障害の有無にとらわれることなく、支え合いながら社会で共に暮らしていくことが日常となるように、国民の理解促進に努めること、また、本基本計画の実施を通じて実現を目指す「共生社会」の理念や、いわゆる「社会モデル」の考え方について、必要な広報啓発を推進することとされている。
また、2023年3月に閣議決定された「障害者基本計画(第5次)」(2023年度からの5年間)でも同様に、「Ⅱ 基本的な考え方」として「理解促進・広報啓発に係る取組等の推進」を掲げており、障害者への偏見や差別意識を社会から払拭し、一人一人の命の重さは障害の有無によって少しも変わることはないという当たり前の価値観を社会全体で共有し、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会が実現するよう、国民の理解促進に努めること、また、本基本計画の実施を通じて実現を目指す「共生社会」の理念や、いわゆる「社会モデル」の考え方について、必要な広報啓発を推進することとされている。
1.障害者週間
「障害者基本法」第9条では、毎年12月3日から9日までの1週間を「障害者週間」と規定している。この「障害者週間」は、同法の基本原則である、全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障害及び障害者に対する国民の関心と理解を一層深めることを目的として、我が国全体で実施するものである。
また、「障害者基本計画(第4次)」では、障害者施策における「理解促進・広報啓発に係る取組等の推進」として、「障害者週間における各種行事を中心に、一般市民、ボランティア団体、障害者団体など幅広い層の参加による啓発活動を推進する」としており、「障害者基本計画(第5次)」でも同様に掲載している。障害者週間の実施に当たっては、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを促進するため、毎年、全国各地で様々な障害者週間の趣旨にふさわしい障害者の自立及び社会参加等に関する多様な取組が行われている。
【障害者週間(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html】
障害者基本法(昭和45年法律第84号)(抄)
(障害者週間)
第9条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(1)障害者週間における具体的な取組の推進
内閣府では、「障害者基本法」の基本理念である、障害の有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現を目指し、同法に規定される「障害者週間」の趣旨を踏まえ、障害及び障害のある人に対する理解促進のための各種広報啓発事業等を行っている。
2022年度においては、新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、次の取組を実施した。
○「障害者週間」関係表彰の実施
○「障害者週間」作品展の開催
○「障害者週間」ワークショップの実施
○「障害者週間」オンラインセミナーの実施
【令和4年度「障害者週間」行事実施状況(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/r04shukan/jyokyo.html】
ア 「障害者週間」関係表彰の実施
内閣府では、2022年12月5日に「障害者週間」関係表彰式を実施した。
本表彰式は、天皇皇后両陛下の御臨席の下執り行われ、天皇陛下よりおことばを賜るとともに、岸田内閣総理大臣から3つの表彰制度における受賞者に対して表彰状が授与された。
〈2022年度の実施状況〉
○日程 |
2022年12月5日(月) |
○場所 |
有明セントラルタワーホール&カンファレンス(東京都江東区) |
○次第 |
・主催者挨拶(岸田文雄 内閣総理大臣) ・天皇陛下おことば ・内閣総理大臣表彰(岸田文雄 内閣総理大臣) 〈心の輪を広げる体験作文〉 最優秀賞受賞者4名 [小学生区分/中学生区分/高校生区分/一般区分] 〈障害者週間のポスター〉 最優秀賞受賞者2名 [小学生区分/中学生区分] 〈障害者関係功労者表彰〉 受賞者20名 [個人/団体] ・受賞者代表(作文)朗読 |


(写真:内閣府)

(小学生区分)最優秀賞受賞者の浅沼稟佳さん(写真:内閣府)
◇ 「障害者週間」関係表彰 各表彰制度の概要
Ⅰ 「心の輪を広げる体験作文」・「障害者週間のポスター」表彰
本表彰は、内閣府と都道府県・指定都市との共催事業として、全国から障害のある人とない人との心の触れ合い体験をつづった「作文」、及び障害のある人に対する国民の理解の促進等に資する「ポスター」を募集し、「障害者週間」に合わせて入賞者に対する表彰を行うものである。
① 対象・表彰種別等
○ |
「心の輪を広げる体験作文」表彰 |
|||
対象(4区分): |
[小学生区分/中学生区分/高校生区分/一般区分] |
|||
表彰種別: |
最優秀賞(内閣総理大臣表彰) |
各区分1名 |
||
優秀賞(内閣府特命担当大臣表彰) |
各区分3名 |
|||
佳作 |
各区分5名 |
|||
○ |
「障害者週間のポスター」表彰 |
|||
対象(2区分): |
[小学生区分/中学生区分] |
|||
表彰種別: |
最優秀賞(内閣総理大臣表彰) |
各区分1名 |
||
優秀賞(内閣府特命担当大臣表彰) |
各区分1名 |
|||
佳作 |
各区分5名 |
|||
② 募集・応募等の状況
○ |
募集期間 |
2022年7月1日(金)~9月下旬(※都道府県・指定都市が定める日) |
|
○ |
応募・推薦状況 |
| 区分 | 都道府県・指定都市における応募総数 | 都道府県・指定都市からの内閣府への推薦数 |
|---|---|---|
| 小学生 | 251 | 36 |
| 中学生 | 817 | 46 |
| 高校生 | 452 | 25 |
| 一般 | 113 | 24 |
| 合計 | 1,633 | 131 |
〈※内閣府へ推薦を行った都道府県・指定都市〉
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、熊本市
| 区分 | 都道府県・指定都市における応募総数 | 都道府県・指定都市からの内閣府への推薦数 |
|---|---|---|
| 小学生 | 589 | 39 |
| 中学生 | 434 | 40 |
| 合計 | 1,023 | 79 |
〈※内閣府へ推薦を行った都道府県・指定都市〉
岩手県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市、熊本市
○ |
受賞者/入賞作品 |
| 最優秀賞 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 県・市 | 氏名 | 作品名 |
| 小学生 | 茨城県 | 浅沼 稟佳 | 一緒に歩いていきたい |
| 中学生 | 秋田県 | 榎 奏子 | ショウコさんと私と |
| 高校生 | 東京都 | 小林 咲葵 | 彼女の「すべて」 |
| 一般 | 沖縄県 | 銘苅 幸也 | 苦しくても、苦しくても |
| 優秀賞 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 県・市 | 氏名 | 作品名 |
| 小学生 | 富山県 | 濱﨑 釉色 | 今、ぼくががんばっていること |
| 名古屋市 | 藤本 千尋 | かかのしょうがい体けんをしてわかったこと | |
| 愛媛県 | 村上 立騎 | ヘルプマークを知ってほしい! | |
| 中学生 | 徳島県 | 大野 里桜 | 一人一人が笑顔になれる社会を目指して |
| 富山県 | 東 朔太郎 | 「普通」とは何か | |
| 三重県 | 前田 咲幸 | 「人の役に立てたこと」 | |
| 高校生 | 神戸市 | 菅原 ルン | 私の広げたい心の輪。 |
| 千葉県 | 田苗 優希 | 歩み寄る姿勢 | |
| 熊本県 | 廣田 琉人 | 配慮とは | |
| 一般 | 熊本県 | 坂本 高広 | 「失ってこそ見えるもの」 |
| 埼玉県 | 土屋 美貴 | 障害者ってなんだろう | |
| 神戸市 | 濱口 聡 | わかってもらう努力 | |
| 佳作 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 県・市 | 氏名 | 作品名 |
| 小学生 | 広島県 | 礒辺 彩月 | 私の大切な妹 |
| 埼玉県 | 笹川 稜央 | 心で通じるやさしい社会をつくりたい | |
| 鹿児島県 | 初田 一心 | めざせ!世界福祉遺産 | |
| 横浜市 | 原國 海音 | きつ音のぼくと障害の妹 | |
| 京都市 | 福田 琉斐 | 「みんな幸せに」 | |
| 中学生 | 岩手県 | 齋藤 香音 | 目に見えないものを支えるということ |
| 兵庫県 | 隅田 莉桜 | 人権が守られている世の中とは | |
| 宮崎県 | 谷山 心絵 | 「普通」のない平和な世の中に | |
| 宮城県 | 永井 瑚子 | 「音楽」はすべての人に | |
| 鳥取県 | 村谷 琉聖 | 僕の歩みとこれからの人生 | |
| 高校生 | 和歌山県 | 岡野 明音 | 幸せになる権利 |
| 北海道 | 加藤 紗耶音 | 障がいって何だろう | |
| 徳島県 | 木川 真綾 | 幸せの伝播 | |
| 愛媛県 | 酒井 賢太郎 | 弟と向き合って | |
| 鳥取県 | 菱川 玲 | サイクリングとの出会いから | |
| 一般 | さいたま市 | 勝又 みゆき | 「つけ麺男子の両立支援」 |
| 札幌市 | 関谷 由美子 | 香りポスター 広がる未来 | |
| 岡山市 | 千田 浩一 | お世話になった人々へ | |
| 新潟県 | 野沢 香苗 | 「クリエイター」 | |
| 広島市 | 大和 なゆた | 私の挑戦 | |
| 最優秀賞 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 県・市 | 氏名 | 作品名 |
| 小学生 | 沖縄県 | 喜納 雅 | その笑顔をいつまでも |
| 中学生 | 群馬県 | 水出 向日葵 | 自由に動ける社会へ |
| 優秀賞 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 県・市 | 氏名 | 作品名 |
| 小学生 | 熊本市 | 圓山 実咲 | みんな大じな1ピース |
| 中学生 | 長崎県 | 赤木 心祐子 | 僕とずっと一緒だよ |
| 佳作 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 県・市 | 氏名 | 作品名 |
| 小学生 | 神奈川県 | 大坂 怜央 | いろいろなおかおのしんかけい |
| 長崎県 | 酒井 優和 | みんなで心の手をつなごう | |
| 茨城県 | 成田 葉乃歌 | みんなで幸せになる | |
| 名古屋市 | 宮波 朱里 | 協力のかたまり | |
| 愛知県 | 森田 彪斗 | 障害があっても ぼくたちともだち | |
| 中学生 | 岐阜県 | 川口 萌花 | 覚えよう!優しさマーク |
| 福井県 | 酒井 歩 | みんながんばれ | |
| 福岡市 | 佐々木 俊輔 | 友情 | |
| 仙台市 | 半澤 美海 | 一緒 | |
| さいたま市 | 森田 夏花 | 笑顔を共に | |
【令和4年度「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の入賞作品の決定について(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/nyushou/r04nyushou.html】
○ |
受賞者/入賞作品に対する表彰等 |
|
最優秀賞受賞者[作文:4名/ポスター:2名]に対し、2022年12月5日に開催した「障害者週間」関係表彰式で表彰状及び記念品を授与 |
||
優秀賞受賞者に対しては表彰状及び記念品を、佳作入賞者に対しては記念品を推薦自治体経由で贈呈 |
||

○入賞作品の広報活用
内閣府では、「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の入賞作品を、「障害者週間」等における全国的な広報に活用することとしており、障害及び障害のある人に対する国民への理解促進につなげている。
「作文」「ポスター」の全入賞作品は、「入賞作品集」として冊子に収め、全国に配布 |
||
「ポスター」最優秀賞受賞作品の中から1点を、「障害者週間」の広報用ポスターに採用し全国に配布するとともに、翌年度の「障害者白書」の表紙としても活用 |
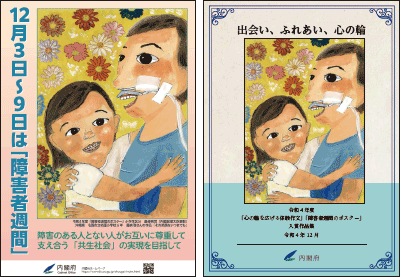
さん)を採用した広報用のポスター(左)と入賞作品集(右)
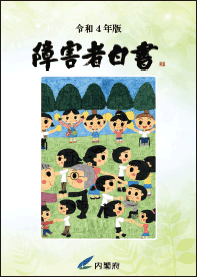
のポスター最優秀賞受賞作品を採用)
Ⅱ 障害者関係功労者表彰
本表彰は、自立して社会活動に参加し、広く他に範を示している障害者又は障害者の福祉の向上に関し顕著な功績のあった個人若しくは団体に対し、各省庁の推薦に基づき、障害者週間の時期に合わせ受賞者に対する表彰(内閣総理大臣表彰)を行うものである。
① 対象・表彰種別等
![]() 対象(2部門):個人部門/団体部門
対象(2部門):個人部門/団体部門
② 2022年度の実施状況
○受賞者
![]() 個人部門:18名/団体部門:2団体
個人部門:18名/団体部門:2団体
| 氏名 | 功績概要 | |
|---|---|---|
| 1 | 朝貝 芳美 | 医師。全国肢体不自由児施設運営協議会会長、障害児に係る学会等の役員を歴任した。肢体不自由児のリハビリテーションの在り方の確立に貢献するとともに、先天性股関節脱臼の早期診断の開発と普及に尽力する等、障害児の医療、福祉の向上に寄与している。 |
| 2 | 荒木 雅信 | パラスポーツに医・科学・情報サポートを導入し、組織的、継続的なサポート活動を行う体制を構築した。その結果、日本選手が海外でも活躍できるようになった。2014年のソチ冬季パラリンピックでは日本代表選手団団長として日本のメダル獲得に貢献した。 |
| 3 | 市川 宏伸 | 児童精神科医。日本発達障害ネットワーク理事長。長年にわたり発達障害者支援の臨床に携わり、数多くの関連団体・学会の代表も務め、当事者やご家族、支援者に対する尽力は多大である。また、国の検討会委員も多数務められ、発達障害者施策の推進に寄与した。 |
| 4 | 井上 博 | 日本知的障害者福祉協会会長。同団体の要職を歴任した。障害者の望む暮らしの実現に向けて施設入所者の地域移行を推進するとともに、知的障害者の意思決定支援の支援現場での浸透に尽力するなど、長きにわたり障害福祉の向上に寄与した。 |
| 5 | 及川 清隆 | 東日本大震災の復興活動において、被災した視覚障害者の声を集め、国等に対する働きかけや国の検討会への参画など、復興支援に尽力した。また、日本盲人会連合(現日本視覚障害者団体連合)の理事等を歴任し、視覚障害者の支援に尽力した。 |
| 6 | 河村 久 | 全国特別支援学級設置学校長協会会長として文部科学省諸会議委員を歴任し、特別支援学級・通級指導教室の指導の充実をはじめとした特別支援教育の発展に寄与した。また、大学教員として特別支援教育に関する教員養成、現職教員の研修に努め成果を上げた。 |
| 7 | 北村 昭子 | 永年に亘りパラスポーツの普及に尽力し、特に重度障害者が楽しめるスポーツとして、車いすツインバスケットボールを考案し、全国大会を開催するまでになり、今年で33回目を迎える。また国際大会のコーチとしても活躍し、日本選手団のメダル獲得に貢献した。 |
| 8 | 栗原 敏郎 | 自身が会長を務める株式会社大協製作所において知的障害者を中心とした障害者雇用に積極的に取り組んだ。平成20年から現在まで公益社団法人全国障害者雇用事業所協会の会長を、平成23年から29年まで障害者雇用分科会委員を務めるなど、障害者雇用の促進に貢献している。 |
| 9 | 小中 栄一 | 富山県ろうあ福祉協会の理事に就任後、聴覚障害者センターの建設に尽力した。聞こえない・聞こえにくい子ども達への人工内耳等の環境整備や支援のあり方に関する提言のとりまとめなどに尽力した。 |
| 10 | 齋藤 幸枝 | 一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会会長として心臓病児の就学及び福祉制度の改善・充実を推進した。足立区役所において福祉・教育の充実に努めた。この間、文部科学省、厚生労働省の諸会議等の委員を歴任し福祉・教育の施策の充実に努めた。 |
| 11 | 坂井 美惠子 | 全国聾学校長会会長として、聴覚障害教育の振興、教員養成、研究に努めた。定年退職後も大学院で研究を継続し、大学の非常勤講師として聴覚障害教育に関する科目を担当し、学生の障害理解を深めた。また、国立特別支援教育総合研究所運営委員等を歴任した。 |
| 12 | 島﨑 洋二 | 北海道聾学校長会会長、特別支援学校長会副会長を歴任、聴覚障害者の冬季スポーツの振興、職業教育の充実、手話の指導方法の整備に尽力した。また、日本体育大学附属高等支援学校の開設を担当し、軽度知的障害の高等部教育の充実を図り、経営を行っている。 |
| 13 | 鈴木 清覺 | 全国社会就労センター協議会顧問。同団体の要職を歴任。障害福祉制度の充実に貢献した。また、アジア地域の障害者福祉の発展に貢献した。現在は名古屋市を中心に地域の障害者支援を行うとともに、障害者の就労を支援する全国団体の事業推進に貢献している。 |
| 14 | 竹下 義樹 | 平成24年から現在まで、障害者雇用分科会の委員を務めてきた。障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供の事業主への義務付け、精神障害者の雇用義務化、障害者法定雇用率の引上げ等に尽力し、障害者雇用施策の進展に大きく貢献した。 |
| 15 | 益子 慶一郎 | 警察官拝命後に聴覚障害となったが、県警交通総務課において29年余の間、交通事故分析業務にあたり、システムの構築をはじめ業務の高度化に貢献した。また、豊富な経験と知識を生かし、後継者の育成にも積極的に取り組んでいる。 |
| 16 | 松山 雅則 | がんで失声した自らの障害を克服し、失声した喉摘者の代用音声獲得支援に尽力した。また、日本喉摘者団体連合会の理事等を歴任し、現在、会長として喉摘者の支援に尽力している。 |
| 17 | 三室 秀雄 | 全国特別支援学校肢体不自由教育校長会会長として肢体不自由児教育の充実と発展に努めた。特にコンピュータ等の活用、医療的ケアに関しては検討会委員として施策の充実に寄与した。また、大学において教員養成に携わると共に、ハンドサッカーの普及に努めた。 |
| 18 | 三宅 初穂 | 要約筆記者として長年活動を行うとともに、要約筆記指導者として、人材育成などに尽力した。また、要約筆記者養成カリキュラムや要約筆記者指導者養成研修プログラムの策定等に尽力した。 |
| 氏名 | 功績概要 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般社団法人 日本自閉症協会 |
結成以来55年間にわたり自閉症児・者の支援活動を行ってきた。自閉症に関わる、理解啓発、相談・支援、調査・研究、施策提言、これらを支える人材の育成を実施し、自閉症児・者に対する教育・福祉・労働の在り方の充実を推進し、成果を上げた。 |
| 2 | 社会福祉法人 鉄道身障者福祉協会 |
身体障害者福祉法の施行に向け、審議会委員として参画するなど、障害者福祉向上に尽力した。また、身体障害者の更生相談事業や生計困難者への低利融資事業の実施などに尽力した。 |
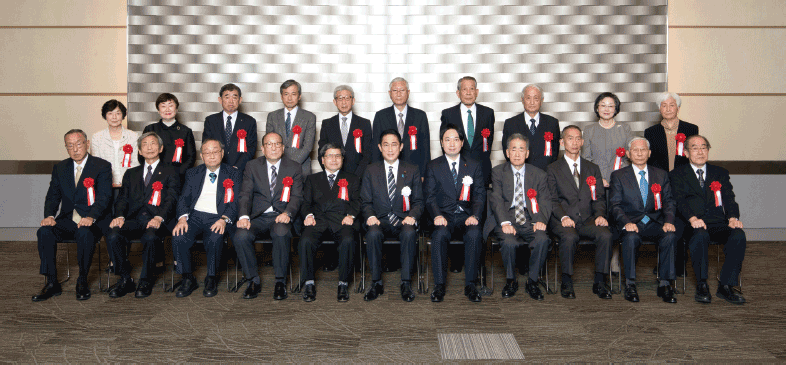
イ 「障害者週間」作品展の開催(都道府県・指定都市からの推薦作品の広報活用)
都道府県・指定都市から内閣府に推薦のあった「障害者週間のポスター」の全作品の原画(入賞作品を含む)及び「心の輪を広げる体験作文」の最優秀賞作品については、国民に対する障害及び障害のある人に対する理解促進の取組の一環として、「障害者週間」の期間中、「作品展」を開催して展示・公開している。
〈2022年度の実施状況〉
○日時 |
2022年12月3日(土)~9日(金) 各日10:00~20:00 |
○場所 |
スクエア ゼロ(JR東京駅改札内地下1階) |
【「障害者週間」作品展(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/r04shukan/main.html#poster1】
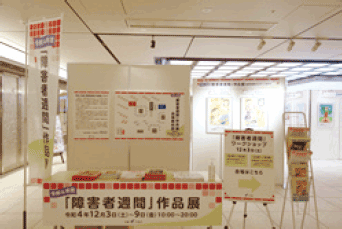

ウ 「障害者週間」ワークショップの実施
内閣府では「障害者週間」の実施に合わせ、体験をテーマに、障害の特性を知っていただくための疑似体験、障害者スポーツや障害者のための器具やバリアフリーに配慮された製品の実演や使用体験などのワークショップを各団体等と連携し開催している。
〈2022年度の実施状況〉
○日時 2022年12月3日(土)10:00~16:00、4日(日)11:00~17:00
○場所 スクエア ゼロ(JR東京駅改札内地下1階)0
○主催 障害者関係団体等(4団体)
【「障害者週間」ワークショップ(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/r04shukan/main.html#workshop】
| 2022年12月3日(土) | ||
| 主催団体等 | テーマ | |
|---|---|---|
| 実施概要 | ||
| 1 | 特定非営利活動法人 ホープ |
手話・アイマスク体験に挑戦しよう! |
| 手話を通して聴覚障害者に、そしてアイマスク体験で視覚障害者に対して理解を深めよう。 | ||
| 2 | 公益財団法人 日本盲導犬協会 |
人と盲導犬が笑顔で歩く社会へ ~盲導犬のこと、もっと知って~ |
| 目の見えない人・見えにくい人が歩く時の大切なパートナーである盲導犬。 盲導犬・視覚障害クイズや音声式計量器を使っての計量体験を通じて、盲導犬や視覚障害について理解を深めてみませんか。盲導犬ユーザーが参加するデモンストレーションでは、体験談を交えながら盲導犬との生活についても紹介します。 |
||
| 2022年12月4日(日) | ||
| 主催団体等 | テーマ | |
| 実施概要 | ||
| 3 | 市川手をつなぐ親の会 キャラバン隊『空』 |
不自由さを体験してみよう! |
| 軍手の手袋をはめて折り紙を折るとどんなことに気づくでしょうか?早くできなくてイライラしてしまう、綺麗にできなくてがっかりしてしまう。そんな時に待ってくれるとあせらずにできた!と嬉しくなります。ほめてくれると自信が持てます。障がいのある人の不自由さを体験し理解を深めましょう。偏見のない社会を目指して。 | ||
| 4 | 東京大学先端科学技術研究センター 当事者研究分野熊谷研究室 | 自閉スペクトラム症の視覚世界を疑似体験しませんか? |
| 自閉スペクトラム症の特徴の一つとして、知覚過敏や知覚鈍麻といった非定型な知覚があることが分かっています。本企画では、自閉スペクトラム症の人々が見ている視覚世界を疑似体験できる「VR体験」、「ミニレクチャー」、「当事者が語るフィルム上映」を行います。発達障害やD&Iにご関心のある方、ぜひご参加ください。 | ||
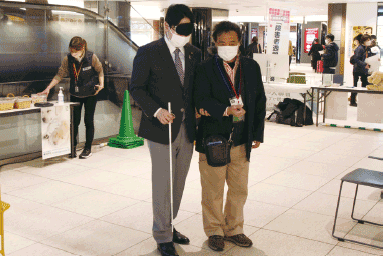


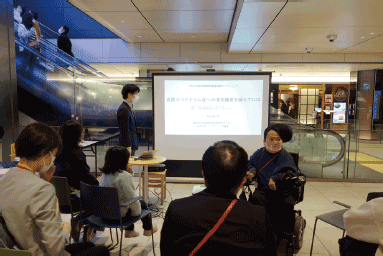
エ 「障害者週間」オンラインセミナーの実施
内閣府では「障害者週間」の実施に合わせ、障害及び障害のある人に関する理解を促進するため、オンライン配信により、障害者週間の趣旨にふさわしいセミナーを各団体と連携して開催している。
〈2022年度の実施状況〉
○配信期間 2022年12月3日(土)~28日(水)17:00
○配信場所 内閣府ホームページ
○主催 障害者関係団体等(5団体)
【「障害者週間」オンラインセミナー(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/r04shukan/main.html#seminar】
| 主催団体等 | テーマ | |
|---|---|---|
| 実施概要 | ||
| 1 | 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 |
発達障害児の読みを支援するデジタル図書「マルチメディアデイジー図書」 |
| 読みの困難がある児童生徒(約15,000人)向けにデジタル教科書(デイジー教科書)を製作・提供している。文部科学省の進めるGIGAスクール構想によるパソコンでも再生できる新配信システムの運用を開始した。教科書で推薦されている副読本についても、デイジー版の読み物を製作・提供している。デモを含めその報告を行う。 | ||
| 2 | 公益社団法人 日本発達障害連盟 |
こどもをめぐって考える~障害とこども家庭庁~ |
| 令和5年4月1日に「こども家庭庁」が創設されます。また、こどもの権利を定めた「こども基本法」も同じく令和5年4月1日から施行されます。日本発達障害連盟の構成団体4団体より、公式に発表されている情報を基に「こども家庭庁」に関連する障害のある子どもたちに関する内容を、発達障害連盟の構成団体として、共生社会の視点を盛り込みながらそれぞれの視点での発表を行います。 | ||
| 3 | 特定非営利活動法人 全国言友会連絡協議会 |
吃音の理解と支援 |
| 吃音(きつおん)の基本概念と特徴について触れた上で、どのような支援が必要なのかを概説する。また、演者自身の吃音に対する体験を語ることで、より深い啓発の機会としたい。 | ||
| 4 | 特定非営利活動法人 全国視覚障害者情報提供施設協会 |
読書が困難な方のためのインターネット図書館「サピエ図書館」のご紹介 |
| 視覚障害や読字障害、肢体不自由などの理由から活字の本をそのままでは読めない方々が、全国の図書館が所蔵している約80万タイトルの点字図書や録音図書などを利用することのできるサービス「サピエ図書館」。その概要と利用方法について、機器操作の実演も交えてご紹介いたします。 | ||
| 5 | 特定非営利活動法人 日本トゥレット協会 |
チック・トゥレット症を知っていますか? ~正しい理解と支援のために~ |
| トゥレット症は、運動チックと音声チックの両方がある慢性チック症で、発達障害に含まれる。チックは脳神経系の不調を基盤に生じるが、不安や疲労などで悪化する。思春期にピークを迎えて成人期に軽快することが多いが、時に強い症状が続く。学校や職場で理解が得られずに活動への参加が困難なことがあり、社会啓発が強く求められている。 |
(2)障害者週間における具体的な取組の推進(国(各省庁等)・都道府県・指定都市における取組)
内閣府では、「障害者週間」の全国的な展開を図るため、国(各省庁等)及び都道府県・指定都市と連携・協力を図り、「障害者週間」の実施に合わせた取組を推進している。
全国で「障害者週間」に合わせて行われる行事や取組については、国民が多くの行事等に参加し、障害及び障害のある人に対する理解を深めることができるよう、内閣府のホームページで公開している。
○国主催行事:63件
○関係機関・団体主催行事:35件
○都道府県・指定都市主催行事:1,688件
※上記件数は、2022年12月時点で内閣府に登録のあったもの
【障害者週間(内閣府):https://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html】

